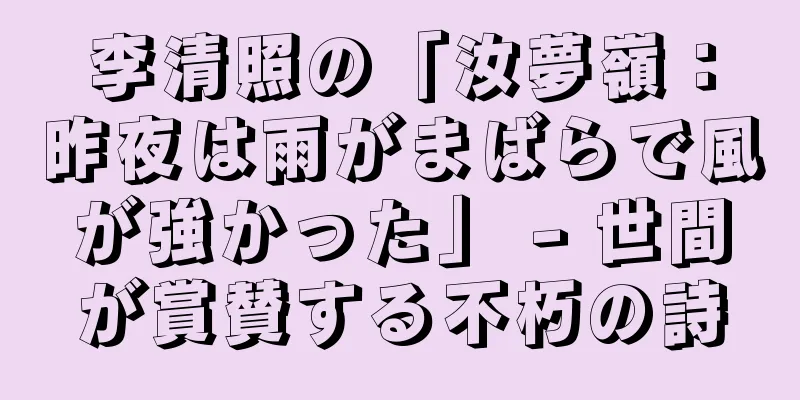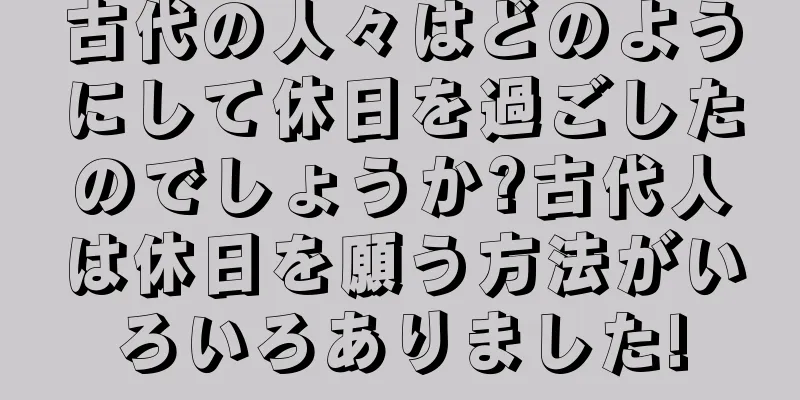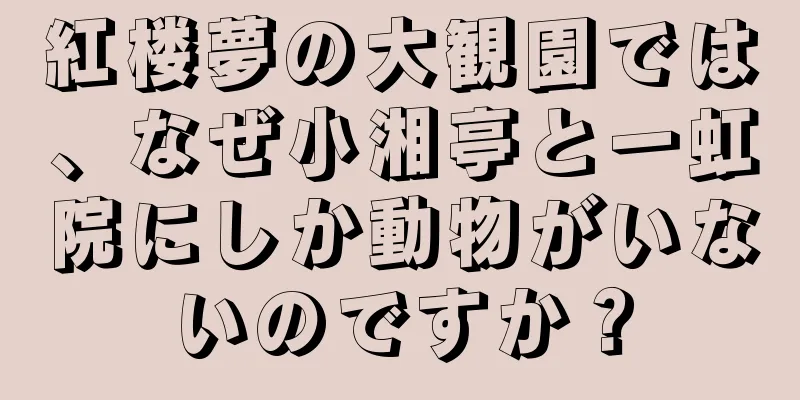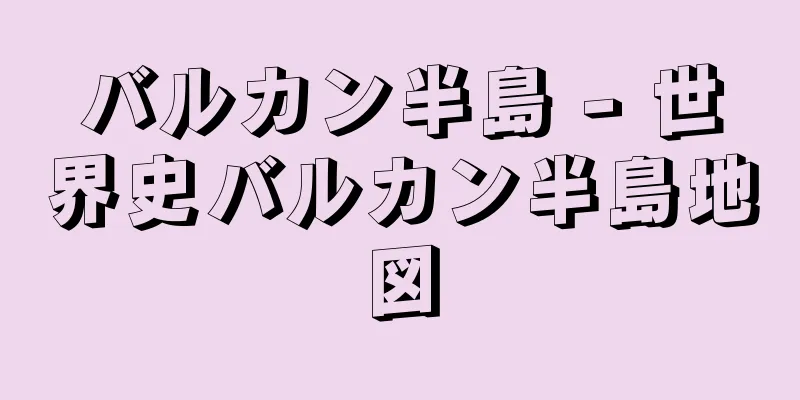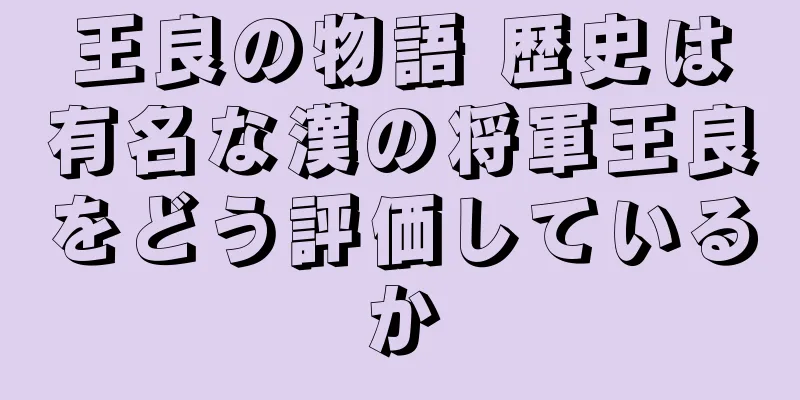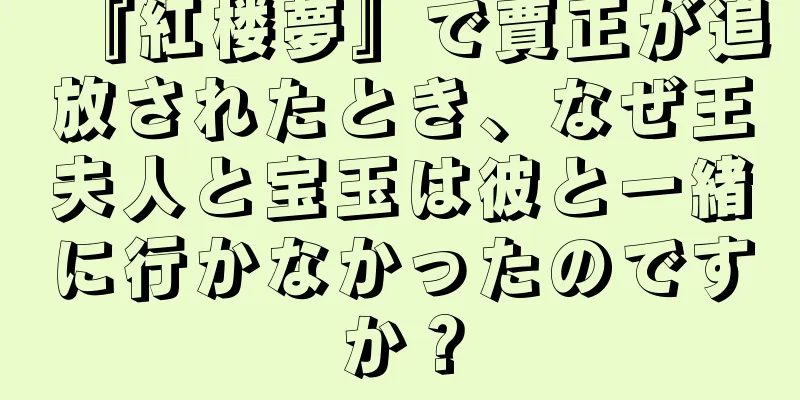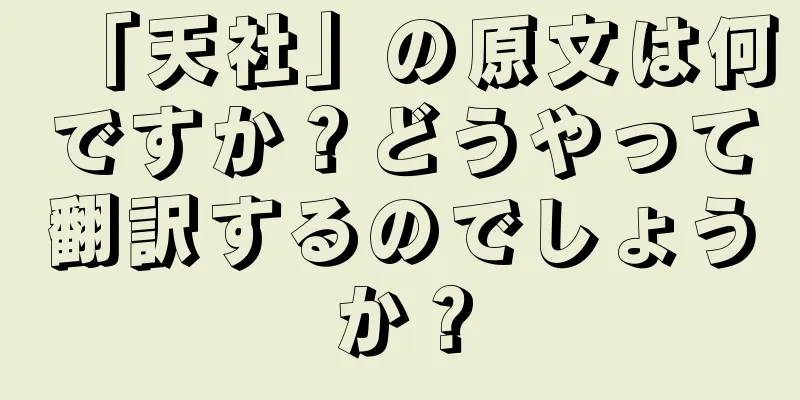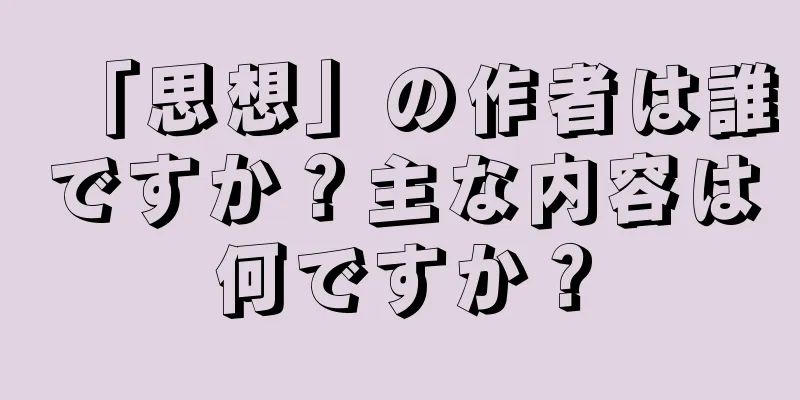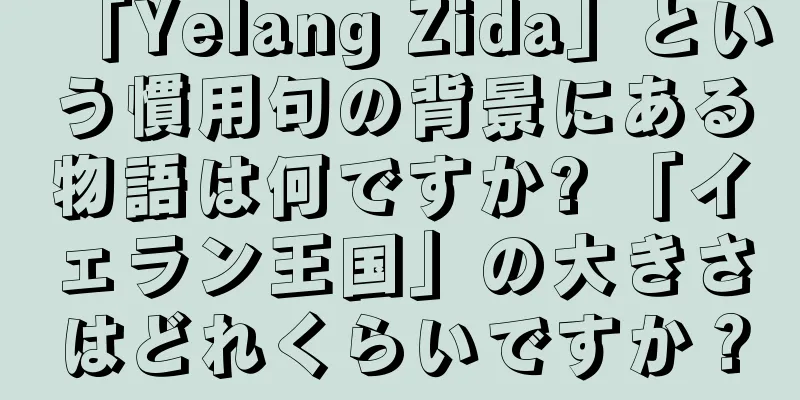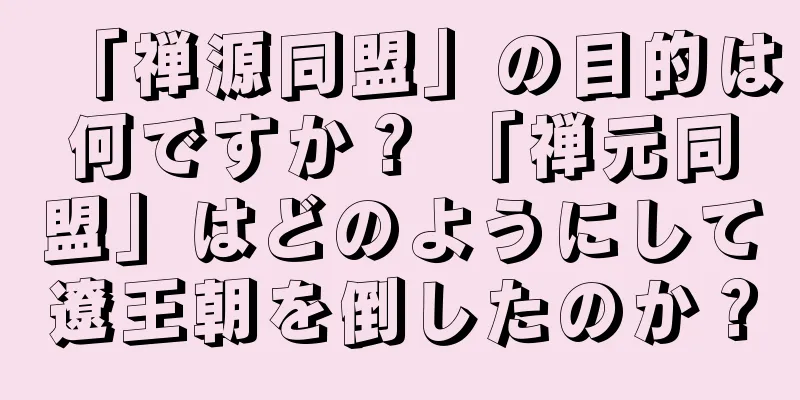なぜこの4つの姓は日本の名前のように聞こえるのでしょうか?これら4つの姓の由来は何でしょうか?
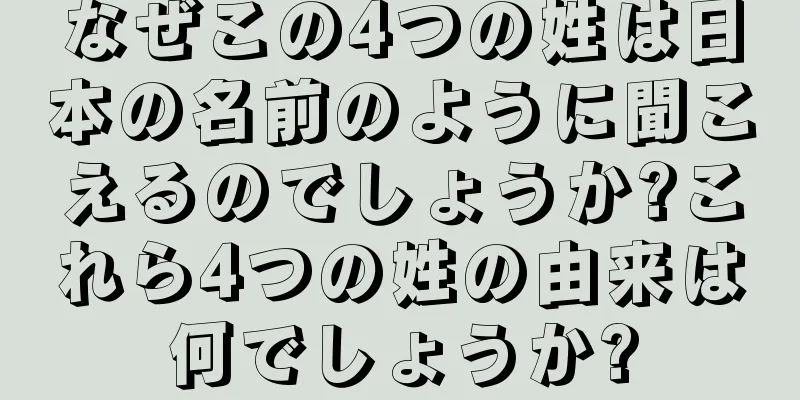
|
これら 4 つの苗字が何であるかご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。Interesting History の編集者がお教えします。 中国の姓の起源は非常に古く、最初は「天の道」による祖先とトーテムの崇拝に基づいていましたが、時代の進化とともに、家族の血縁関係のシンボルに発展しました。中国の歴史上、2万以上の姓が存在し、現在でも5,000以上の姓が受け継がれています。しかし、一部の名字は日本の名字に似ているため、不必要な誤解を招く可能性があります。実際、それらはすべて中国本土から伝わった名字です。 東野 この姓の由来は、古代五帝の初代皇帝である黄帝の姓である「冀」に由来します。皇帝の本来の姓は公孫、名は玄元であった。彼は冀江で育ち、姓を冀に改めた。日本の苗字のように聞こえますが、東野という苗字の由来は非常に深い歴史的背景があり、純粋な中国の苗字です。 東業は姓を名乗った後、魯に住んだ。楚の高烈王が魯を征服するために北征を開始したのは紀元前269年のことでした。魯の王族500人以上が殺害され、東業之とその子孫だけが呉に逃れ、大惨事を逃れた。彼らが故郷に戻ったのは紀元前212年になってからであり、彼らの子孫が今日まで故郷を継承しています。 荒木 この姓は中国では比較的珍しいが、歴史上、辛元という姓を持つ有名人は多い。『史記 巻83 呂仲廉・鄒陽伝』には、戦国時代、魏の将軍に辛元燕がいた。彼は魏の安熙王の命を受け、趙の孝成王を説得して秦の昭襄王を皇帝として擁立させた。しかし斉国の義人である陸忠の説得により、魏王から与えられた任務を放棄した。 漢の武帝が権力を握っていた時代もありました。辛元平という錬金術師がいましたが、漢の武帝が望んでいたような不老不死の薬を作ることができなかったため、漢の武帝に殺されました。これらの多くの歴史資料から、荒垣氏もまた非常に古い中国の姓であることがわかります。日本の苗字とは何の関係もありません。 ドゥアンム 段木姓は漢民族の複合姓の一つです。この姓の起源はかなり古く、西周初期に周の文王の師であった玉雄の子孫である段木典に由来しています。 『端牧家系図』には、黄帝の次男は昌義であると記されている。昌義は荘胥を産み、荘胥は程を産み、程は崔璋を産み、崔璋は長男崇礼と次男五慧の二人の息子を産んだ。呉慧は陸忠を産み、陸忠には6人の息子がおり、その末っ子が季廉であった。季蓮は傅菊を産み、傅菊は薛雄を産んだ。その後、彼の系譜は玉雄のいる20代目まで失われました。 玉雄は周に仕え、周の文王季昌と周の武王季法の師であった。玉雄には二人の息子がいた。長男は熊礼、次男は段木段である。舒は滇を産み、滇は父の名を姓として、端木滇と名付けられた。 尚観 尚官は歴史上比較的有名な姓であり、宋代の『百姓録』では411位にランクされています。この姓の起源は、戦国時代に楚の淮王が末子の子蘭を上官位の官吏に任命したことに遡ります。そのため、子蘭の子孫は皆この官名を姓として使い、上官という名前が生まれました。 『唐書丞相系譜』には、漢の時代に関中の人口を豊かにするために朝廷が多くの大家族を関中に移住させたと記録されています。そのうち、上官一族は隴西の上桂に移住しました。これは、楚の国の王族に由来する上官一族が天水の名家となった理由でもあります。 歴史上、上官姓を持つ著名人は多く、例えば唐代の名高い才女上官婉児、宋代の龍吐閣侍従上官鈞、礼部大臣上官丁などが挙げられる。いずれも比較的有名な歴史上の人物です。尚官が日本の苗字だと思わないでください。 |
<<: 明朝は「土姑事件」の危機をいかに乗り越えたのか?イェセンはなぜ明の英宗皇帝を捕らえたのに首都を占領できなかったのか?
>>: 「楼蘭を征服するまで帰らない」というのは誰の願いでしょうか? 「楼蘭」はなぜそんなに嫌われているのか?
推薦する
李清昭の有名な詩の一節を鑑賞する:冷たい香りが消え、新しい夢が目覚め、悲しい人々は立ち上がることを許されない
李清昭(1084年3月13日 - 1155年)は、易安居士とも呼ばれ、宋代の斉州章丘(現在の山東省章...
秋の雨を題材にした七つの詩を振り返ると、詩人たちはどんな情景を描いたのでしょうか。
どの王朝にも秋の雨を詠んだ詩は数多くあります。次の『Interesting History』編集者が...
『北への旅』第2章における王と大臣たちの狩猟旅行の原文の鑑賞
国王と大臣たちの狩猟旅行ある日、葛歌国の成安王が勅令を出し、文官の張明と李涛、武官の劉飛虎と鄭政らと...
史公の事件 第314章: 徳の高い女性が正義を訴え、いじめっ子がショックを受け、英雄が誇りに思う
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
扶余はどこにありましたか?扶余王国に関する伝説は何ですか?
今日は、おもしろ歴史編集長が扶余王国がどこにあったか教えます。興味のある読者は編集長をフォローして見...
『紅楼夢』の賈雲とは誰ですか?紅楼夢における賈雲の紹介
『紅楼夢』の登場人物、賈雲。彼は顔が長くて背が高く、とても優しくてハンサムです。賈宝玉は父親が若くし...
胡三娘は林冲に生け捕りにされた後、なぜ王英との結婚に不満を抱かなかったのでしょうか?
みなさんこんにちは。Interesting Historyの編集者です。今日は胡三娘の物語をお話しし...
唐の睿宗皇帝の生涯は伝説的と言える。その主な理由は何でしょうか?
睿宗は生涯に二度王位に就いた。一度目は、宋勝元年(684年)2月7日、高宗皇帝の死後2年目に当たる。...
賈牧とはどんな人でしょうか?彼女は見た目は華やかで、誰からも尊敬されていますが、裏では孤独な人でもあります。
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting Historyの編集者が『紅楼夢』の...
咸豊帝の治世中に清朝の基盤はどのように揺らいだのでしょうか?
咸豊帝の治世3年正月8日、咸豊帝は自らを責める旨の勅を発した。その内容は簡潔で、私は天下を治める者で...
金塊はどんな形をしているのでしょうか?金塊を見つけるにはどうすればいいですか?
金塊はどのように見えるのでしょうか? 金塊はどうやって見つけるのでしょうか? 興味のある読者は編集者...
安禄山と同じくらい有名だった葛樹韓は、なぜ敗北後に安禄山に慈悲を乞うたのでしょうか?
今日は、History.comの編集者がゲシュハンについての記事をお届けします。ぜひお読みください~...
シルクにはどんな種類がありますか?人間はシルクをどのように利用しているのでしょうか?
シルクは、成熟したカイコが繭を作るときに分泌する絹液によって形成される連続した長い繊維です。天然シル...
第89章(パート2):陳立清が鉄背狼を殺し、朱永清が知恵で愛夜宝を倒す
『水滸伝』は清代の作家于完春が口語で書いた長編英雄小説である。道光帝の治世6年(1826年)に起草さ...
『世界物語の新記録:賞賛と報酬』の第 2 章には誰の行為が記録されていますか?
まだ分からないこと:『新説世界物語・賞賛と評判』の第二条に記録されているのは誰の行為ですか?それ...