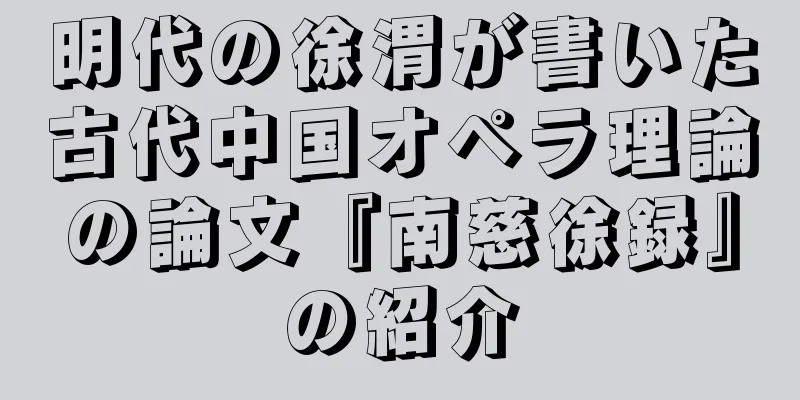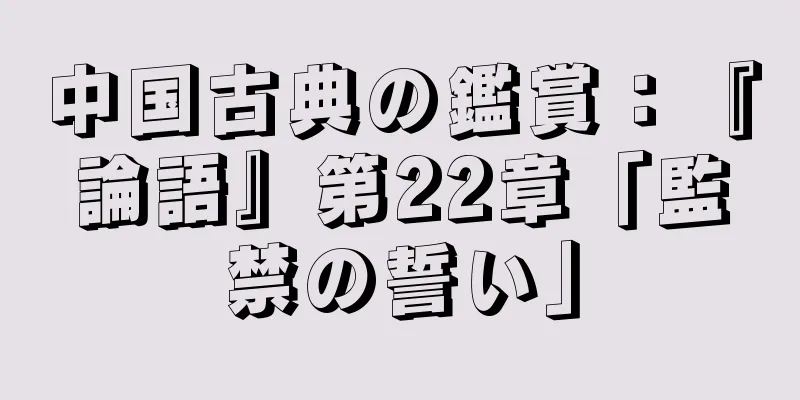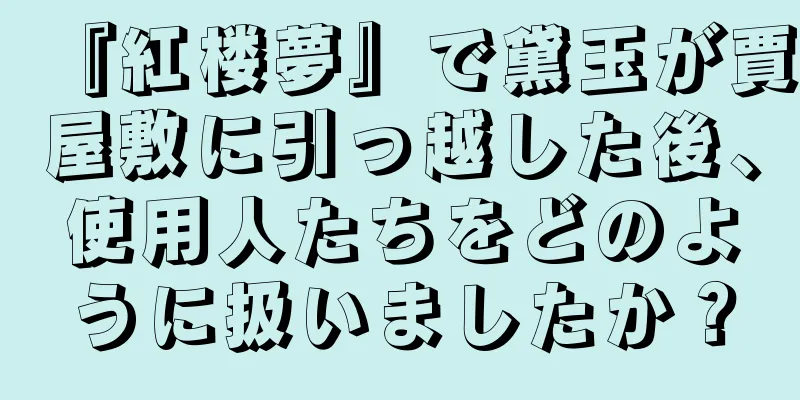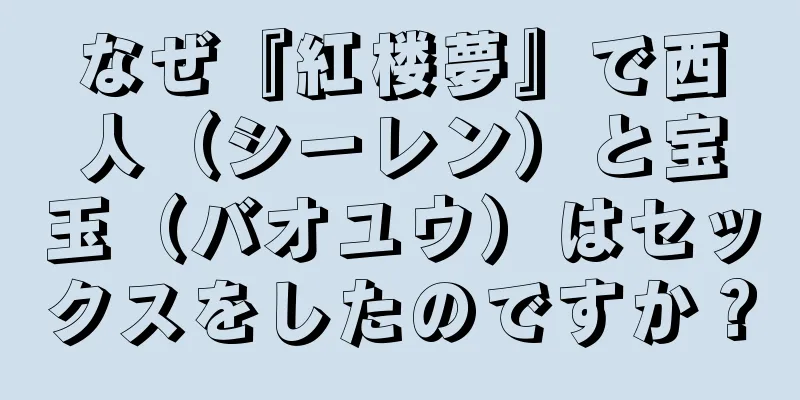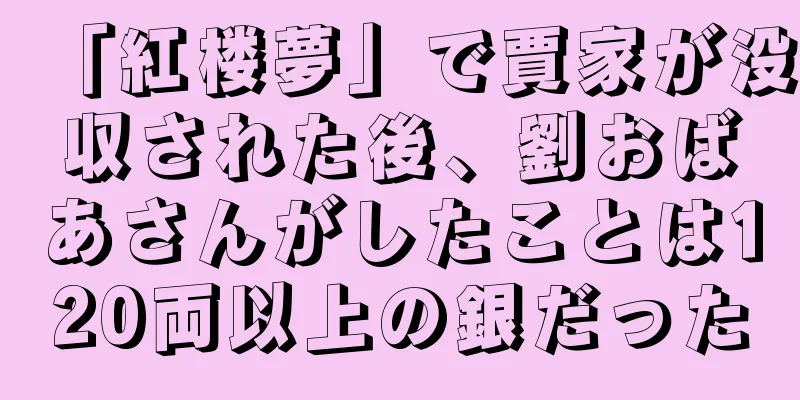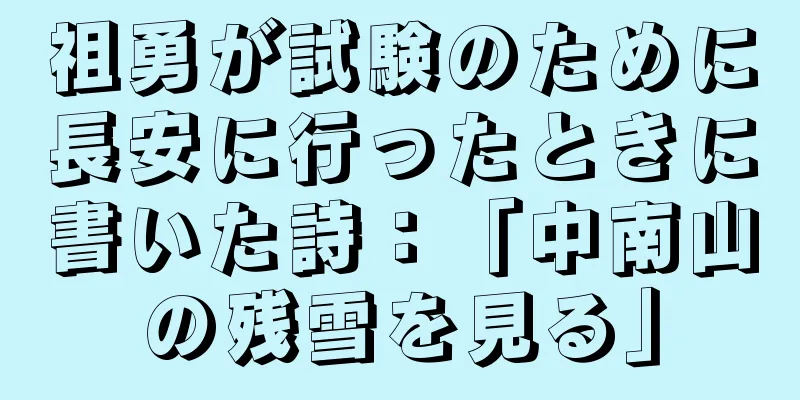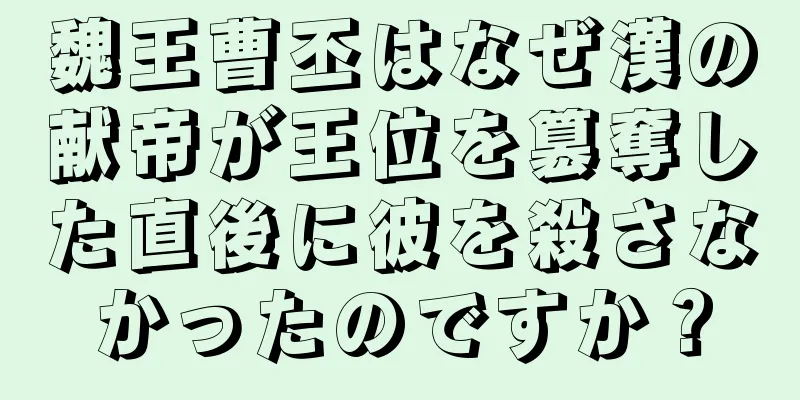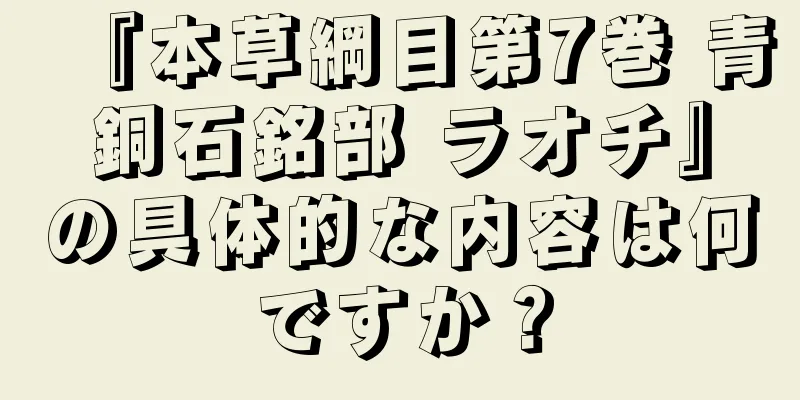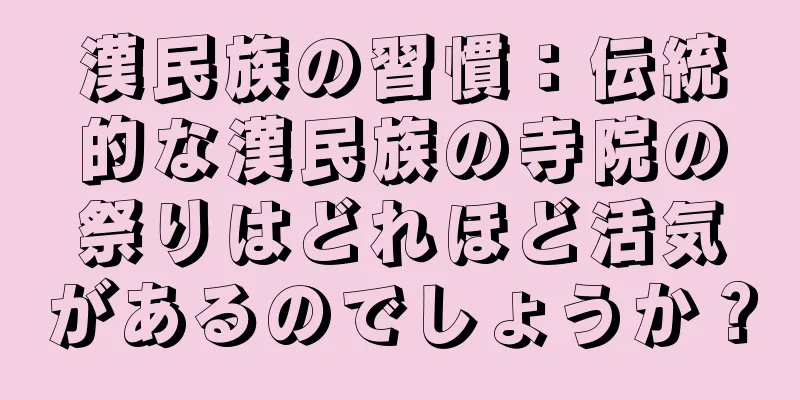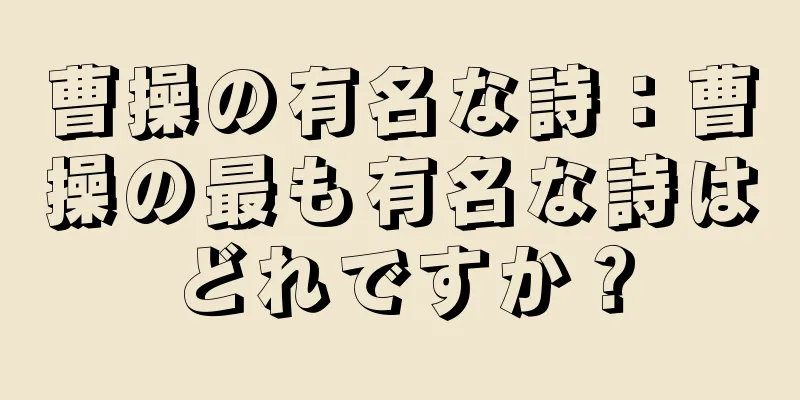建安時代の七賢の文学的業績:詩、散文、散文への貢献
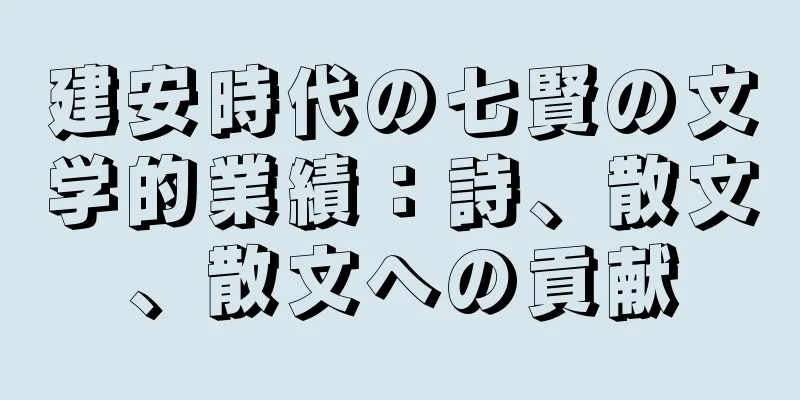
|
『七人の息子』は中国文学史上非常に重要な位置を占めています。彼らは「三曹」とともに建安の作家たちの主力を構成している。彼らは皆、詩や賦、散文の発展に貢献してきました。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 『七人の息子』の創作スタイルにも共通の特徴があり、それは建安文学の時代スタイルでもある。この時代のスタイルの具体的な内容とその形成理由は、劉謝が『文人の心と龍の彫刻:時間の順序』で述べたとおりである。「当時の文学を見ると、優雅で寛大であるが、それは世の中の混乱と分離が蓄積されたためである。」 詩 「七子」は主に五字詩を著した。五字詩は後漢末期に盛んになった新しい詩風で、桓帝と霊帝の治世に「古詩」が出現し、五字詩が成熟した。「七子」の優れた五字詩は、感情が飛び交い、変化に富んだ文章で書かれており、五字詩の芸術性をさらに高めている。 例えば、徐干の『室内思索』は、同じ主題の『河畔の青草』や『竹の一本』よりも繊細で奥深い。しかし、陳林の『長城洞の酒馬』と阮渝の『北果門追い出し』は、どちらも漢末の戦乱前に書かれたもので、その執筆時期は必ずしも「古詩」より後というわけではない。五音節詩の発展史におけるその重要性は、さらに注目に値する。 チフ 「七匠」は数多くの短賦を著し、張衡、蔡勇らの業績を基にして、短賦のさらなる隆盛に貢献した。 「Seven Sons」短編小説には注目すべき点が 3 つあります。 ①題材の範囲が拡大し、日常的で平凡な題材が過去の大譜の貴族的性格をさらに薄めた。 ②社会現実を反映する機能が強化され、政治的な出来事を直接描写する作品が増加した。 ③叙情的な色合いがますます強くなります。 曹丕は『経文随筆』の中で「七子」の賦を非常に高く評価した。劉謝も『文心彫龍』の「賦の解釈」で同様の意見を表明した。彼はまた、王燦と徐干が曹魏の世代の「最初の賦作者」であると信じ、宋濤、司馬相如、左汪、潘越らと並んでランク付けできると述べた。 散文 孔容の追悼文、陳林と阮季の覚書、徐干と王燦の論説文はいずれも当時としては独特なものであった。彼らの共通の利点は、曹丕が「文学は精神によって支配される」(『経文随筆』)と呼んだものであり、そこには作者の独特の気質が染み込んでいる。 『七子』の有名な散文作品としては、孔容の『倪亨推挙記』『盛小章曹公宛書状』、陳林の『豫州移封の勅』『曹洪を代表して魏王に送る書状』、阮愈の『曹公を代表して孫権に送る書状』、王燦の『要諦について』『荊州文学作品官録』などがある。 『七人の息子』の散文は、特に孔容と陳林の場合、形式において徐々に平行法に向かう傾向を示しました。彼らの作品の中には、対句の構成が優れ、多くの暗示を用いているものもあり、漢末から西晋にかけての散文の対句化の過程において重要なつながりとなっている。 仕事 「七大師」の著作の原本はすべて失われ、徐干の政治倫理論文『中論』だけが残っている。明代には張普が『孔紹福全集』『王世忠全集』『陳其詩全集』『阮元宇全集』『劉公全集』『英徳連秀連全集』を編纂し、『漢魏六代百三人文集』に収録された。清代の楊鳳塵は『建安七賢集』を編纂した。 「七人の息子たち」の作品はそれぞれ独自の個性と独特のスタイルを持っています。 孔容は詩文や散文を書くのが得意で、その作品は高尚な文体と精緻な精神を備えていた。王燦は詩、散文、賦の達人として知られ、その作品は非常に叙情的です。劉震は詩作に優れ、その作品は荘厳かつ荒涼とした作風であった。陳林と阮涛は当時、詩人や秘書として有名であり、詩においても一定の業績を残していた。彼らのスタイルの違いは、陳林のスタイルがより活発で力強いのに対し、阮宇のスタイルはより自然で流暢であるということです。徐干は詩や賦を書くのが得意で、文体は繊細で落ち着いた雰囲気を持っています。嬴厳は詩や散文を書くのも得意で、その作品は調和がとれていて優雅であった。 「七人の息子」の作品は、一般的に2つの段階に分けられます。彼の初期の作品は主に社会不安の現実を反映し、国と国民に対する懸念を表現していた。後期の作品の多くは曹操政権への支持と自らの業績を確立しようとする野望を反映しており、内容も宴会や贈答、贈り物の交換などに関するものがほとんどであるが、曹操父子への賛辞の一部には廷臣の口調が見られ、下品な態度が表れている。 しかし、初期、後期を問わず、「七人の息子」の作品は肯定的で健全な内容が主流です。 |
<<: 建安七賢の一人である阮玉と、竹林七賢の二人である阮季と阮仙との関係は何ですか?
>>: 魏晋時代の有名な学者7人が竹林の七賢と呼ばれています。竹林の七賢という称号はどのようにして生まれたのでしょうか?
推薦する
呉俊の『同流五行鶴山』:詩全体が別れについてだが、別れの悲しみを直接書いているわけではない。
呉俊(469-520)、号は叔祥、南朝梁の作家、歴史家。呉興市古章(現在の浙江省安吉市)の出身。彼は...
『紅楼夢』の親友としてふさわしいのは誰でしょうか?賈宝玉の親友は誰ですか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
「彭公事件」第43章:玉面虎が聖手仙人張耀宗と単独で戦い、李其厚を追い払う
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
武夷山大紅袍の起源と伝説
大紅袍の起源については、とても興味深い伝説があります。昔、貧しい学者が科挙を受けるために北京へ行き、...
宋代の詩「潤州青年旅記」を鑑賞します。この詩はどのような場面を描写していますか?
宋代の蘇軾著『青年の潤州への旅』。以下はInteresting History編集者による詳しい紹介...
お金をうまく管理するにはどうすればいいでしょうか?張碩の名作『千本草』を読んでみよう
張碩は唐代の作家で、四つの王朝に仕え、三度政府の要職に就き、三十年間文芸を担当し、多くの作品を著した...
『後漢書』巻59にある張衡の伝記の原文は何ですか?
張衡は、名を平子といい、南陽市西鄂の出身であった。それは何世代にもわたって有名な姓でした。彼の祖父の...
写実的な風景画家レヴィタンの芸術スタイルは何ですか?
ロシアの画家レヴィタンは、19 世紀の偉大な写実主義の風景画家でした。彼は高い称号と名誉を持っていた...
『偽証の術』:唐代武周時代の残虐な官僚、頼俊塵が書いた本ですが、どのような本ですか?
『虚実書』は唐代武周年間の残酷官僚頼俊塵が著した書物で、主に当時の宮廷内の複雑かつ残酷な政治闘争を描...
『紅楼夢』の妻と妾の間の隠された争いは、賈正の寝室での秘密の情事を明らかにする
古代から、妻と妾の間の争いは避けられないものでした。例えば、『紅楼夢』の賈正はその争いの中心にいます...
グリーンピオニー全話第12話:華振芳が友人を救出し、頂興へ向かう
『青牡丹全話』は清代に書かれた長編の侠道小説で、『紅壁元』、『四王亭全話』、『龍潭宝羅奇書』、『青牡...
唐の睿宗皇帝の娘、安興公主の簡単な紹介
安興昭淮公主(687?-692)は唐の睿宗皇帝李旦の次女であり、母親は不明である。彼女は当初、安興県...
人民元の「元」はなぜ私たちが普段使っている「人民元」と同じではないのでしょうか?
銀貨は 15 世紀後半にヨーロッパで鋳造され始め、16 世紀にはスペインの入植者によってアメリカで大...
賈夫人が食べ物が足りないのかと尋ねたとき、元陽はその場で王夫人にどのように異議を唱えたのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
太平広記・巻14・仙人・万宝帖の具体的な内容は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...