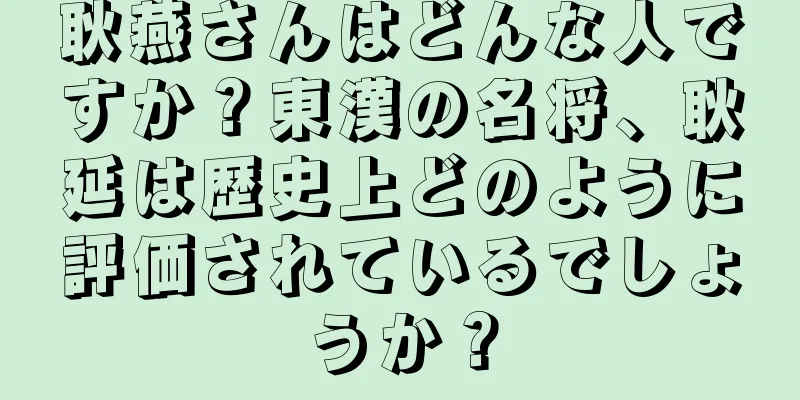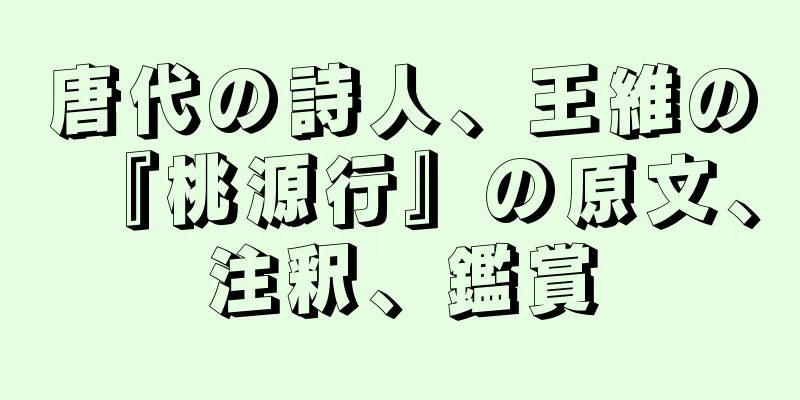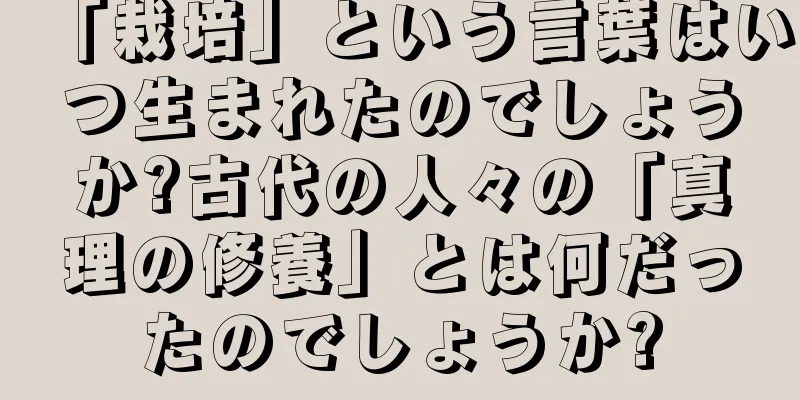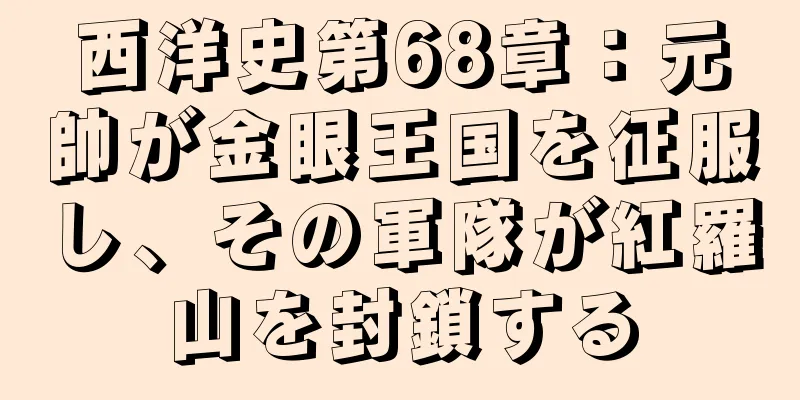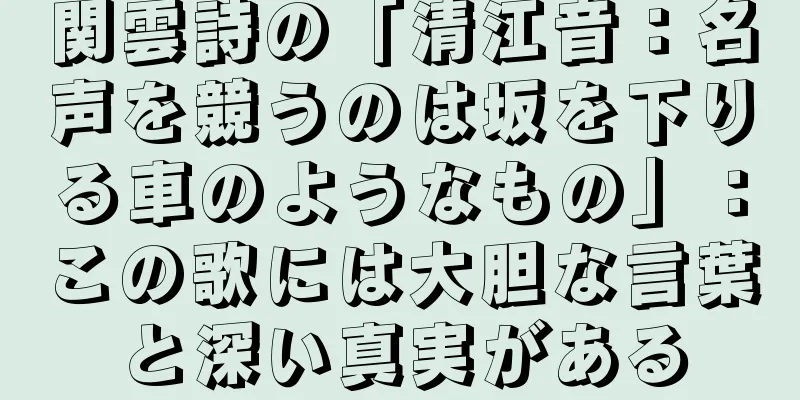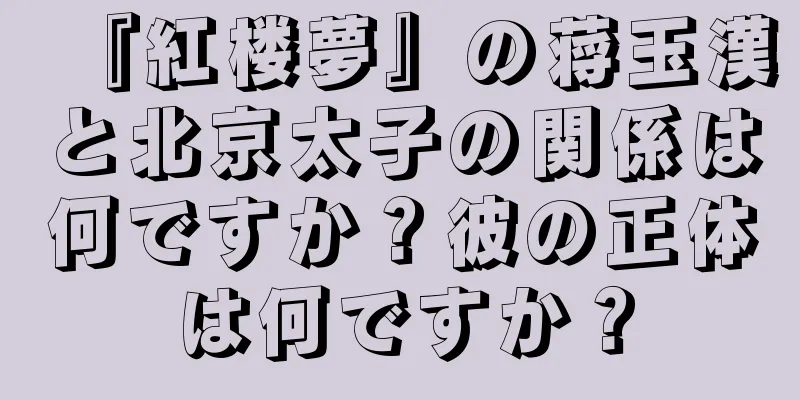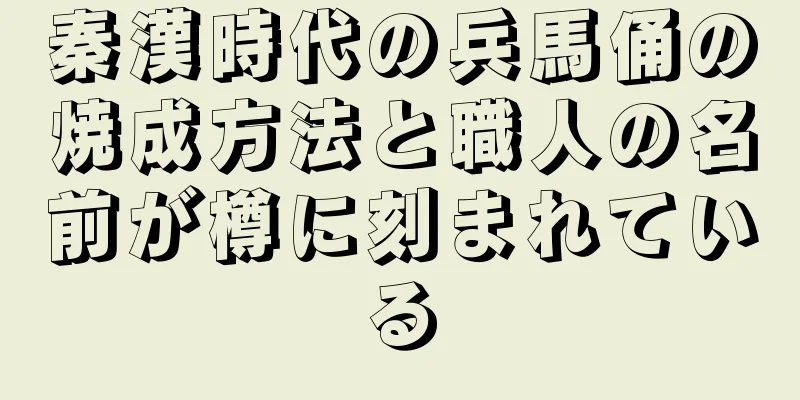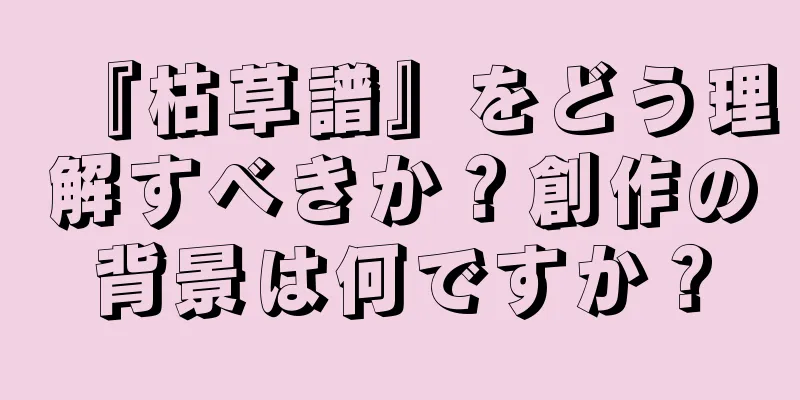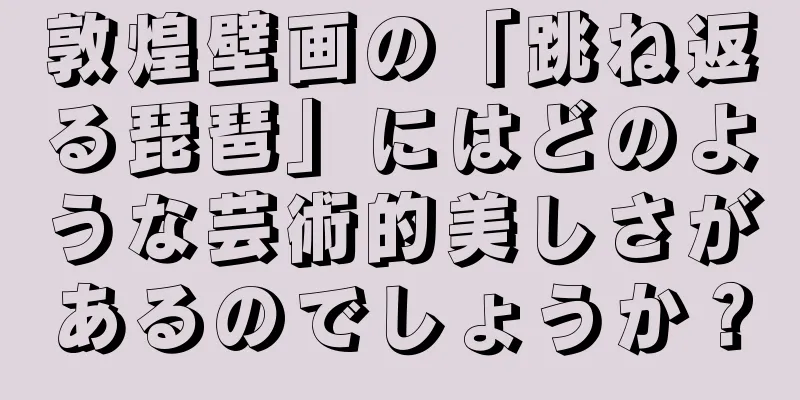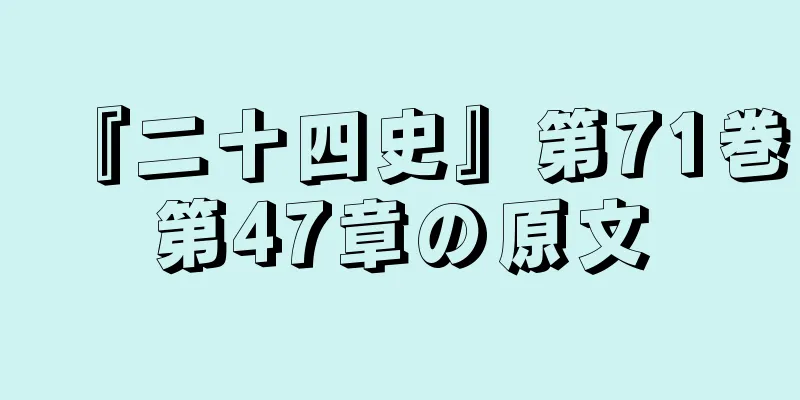古代の皇帝は宮廷でどれほどの権力を持っていたのでしょうか?あなたはすべての最終決定権を持っていますか?
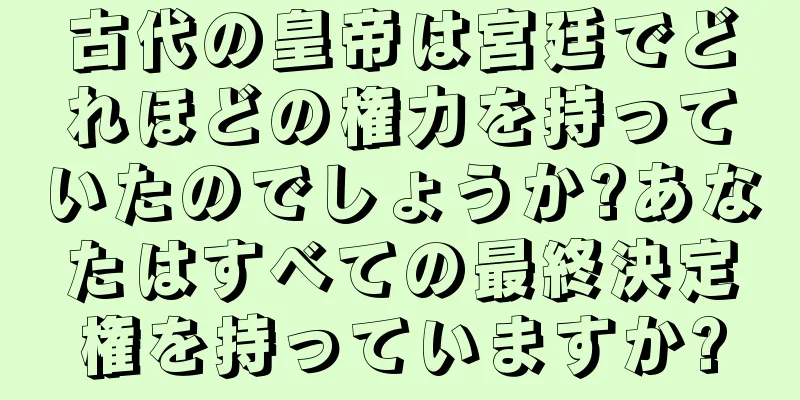
|
時代劇や映画を見ていると、古代の皇帝の言葉は金言だと感じることがよくあります。皇帝は、突然ひらめいたり、何かをしたいと思ったりすると、「勅書を起草せよ!」と叫んで、勅書を口述しました。勅令が書かれると、それはただちに最高法規となり、これに異議を唱える者は「勅令不服従」という重罪に問われることとなった。皇帝は強大な権力を持ち、何でも好きなことができるようです! もしこれが真実だと信じているなら、あなたはこのメロドラマ的なテレビシリーズによってどん底に導かれていることになります。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! では古代の皇帝はどれほどの権力を持っていたのでしょうか? まずは勅令から見ていきましょう! 勅令と三省制度 隋は二つの大きな改革を行なった。一つは秦漢時代の三官九大臣の官制を三州六省に改め、もう一つは科挙(今の大学入試に相当)を実施して人材を募ることだ!この二つの大改革は中国の歴史に数千年にわたって影響を与えてきた!その中でも三州は権力の中核であり、すなわち書記局、商書、孟下省である!機能分担は、書記局が勅令の起草を担当し、孟下省が勅令の内容の審査を担当し、不合理なところがあれば拒否する権利を持つ!審査で問題がないものについては、執行のために商書局に引き渡される! 唐と宋の時代を例に挙げてみましょう。勅令を発布する通常の手順は次の通りでした。まず首相府が案を書き、次に大臣たちが午前中に会議を開いて議論し、全員一致で承認を得て、その後、勅令の草案が皇帝に提出され、承認を得るというものでした。そして、官房長官(武則天の時代には馮閣と改名)は、それぞれが自分の考えに基づいて勅旨(草案)を書き、官房長官に送りました。官房長官は、その中から最良と思われるものを選び、修正・磨きをかけて本物の勅旨(草案)とし、皇帝に送って印章をもらい(皇帝は意見が異なる場合は、勅旨の余白に赤ペンでコメントを書き込むこともできますが、理論上は勅旨を直接拒否する権限はありませんでした)、人事部(武則天が皇帝になったときに桓台と改名)に送って審査・印章してもらいました。最終的に、執行のために事務局(現在の国務院に相当)に引き渡されました。 天皇は勅令の起草を直接指示する権限も持っていたが、官房が何かを書き、天皇が承認の印を押すだけのケースが多かった。つまり、勅令の実質的な決定権は官房にあり、天皇の役割はそれに署名し、印を押すことだった。人事省が勅令に納得できないと感じた場合、たとえ天皇がすでに同意の印を押していたとしても、人事省はそれを直接拒否する権利を持っていた。以上の手続きを経て、官房、内務省、皇帝の印を受けた勅書のみが有効な勅書となり、そうでない場合は違法となる。 天皇が勅令の内容に同意しない場合、大臣たちは国と国民を第一に考え、早く押印するよう天皇にせがみ続け、罷免や世論、さらには命まで脅迫する。つまり、必ず署名しなければならないのだ! 一方、皇帝が勅令を発布したいが、大臣らが反対した場合、どうすればよいのだろうか。これは非常に興味深い。歴史上、三省を迂回して密かに勅令を発布した皇帝もいた。例えば、則天武后はかつて自分の印章のみを押印し、奉格鑾台を迂回して「偽の勅令」を発布し、大臣らから非難を浴びた。唐の皇帝中宗は側近を任命したかったが、宰相たちが同意しないのではないかと恐れた。官房の二つの関門を越えられないだろうと、官房を迂回して「偽の勅令」を発布し始めた。しかし、やはり臆病だったため、署名には墨ペンを使用し(規定では赤ペンが必要)、勅令の捺印には斜印を使用し、官房が柔軟に執行すべきであることを暗示した。意外にも、突破不可能な壁はなく、このことは後に他の人にも知られることとなった。人々は中宗が個人的に任命した側近を「斜印官吏」と呼び、任命された側近たちでさえ恥ずかしがった。 宋代の皇帝は、中書社人による勅令の起草や介石中による審査といった法的手続きを経ずに勅令を発布することができ、宰相の連署も必要とせず、直接勅令を発布することができた。これを「直筆勅令」「内勅」「内批」などと呼んだ。今日の言葉で言えば、それは指導者が覚書を承認することを意味しますが、これは歴史上珍しいことではありません。しかし、このような私令には正当性がなく、「奉格鑾台から発せられなければ勅令とは呼べない」ということわざがあるように、政府が執行を拒否することもできる。つまり、三省機関の審査を受けていない勅令は単なる紙くずであり、役に立たないということだ。宋代の仁宗皇帝の時代、宰相の杜延は皇帝が個人的に発布した「直筆の勅書」を一切公開せず、十数部を集めてそのまま皇帝に返した。皇帝は何もできず、「大いに助けてくれた」と称賛することしかできなかった。一度そのような勅令が出れば、それは必ず永遠の不名誉をもたらすことになるだろう。 結論:ここから、古代では、天皇は好き勝手なことはできず、勅令も軽々に発せられることはなかったことがわかります。天皇の権力を牽制するこれらの機関(別の見方をすれば、天皇を補佐する機関でもありました)があったからこそ、天皇は勤勉に働き、少しも怠慢になることができませんでした。万暦帝が30年近くも国政を無視していたにもかかわらず、国が秩序正しく統治されていたのは、まさにこのような完全で成熟した権力機構があったからこそです。皇帝の権力が統制された制度のもとで、文官の地位は徐々に向上していきました。 宋代には文官の地位が最高潮に達しました。そのため、唐の太宗皇帝は魏徴を見て恐怖し、宋の仁宗皇帝は怒りのあまり泣きながらも大臣たちを褒め、鮑正は皇帝と口論して皇帝の顔に唾を吐きました!皇帝の権力が集中していた明代でも、文官は皇帝と対峙することによってのみ権力を恐れない誠実さを示すことができました!一方、対峙されることに耐えられる皇帝は怒らず、不快で正直なアドバイスにも耳を傾け、心が広い良い皇帝であることを証明しています! |
<<: 近代的な娯楽施設がなかった古代において、なぜ人々は夜更かしすることが多かったのでしょうか。
>>: 古代の地形は本当に存在したのでしょうか、それとも古代人によって発明されたものなのでしょうか?
推薦する
有名なドイツの発明家グーテンベルクは印刷術にどのような貢献をしましたか?
グーテンベルクの伝記によると、彼はヨハネス・グーテンベルクという名の有名なドイツの発明家でした。彼は...
『緑氏春秋・リスオラン』の難問の内容は何ですか?どのような考えが表現されていますか?
まだ分からないこと:『緑氏春秋・里素蘭』の内容は何ですか?それはどんな思想を表現していますか?次...
林黛玉には無限の発展の可能性があると言われるのはなぜでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
張虎の『何曼子』:詩全体では「落ちる」という動詞だけが使われている。
張虎(785年頃 - 849年)、号は程基、唐代の清河(現在の邢台市清河県)出身の詩人。彼は名家の出...
前秦の景明帝、苻堅の物語。苻堅に関する興味深い話にはどんなものがありますか?
苻堅(317年 - 355年)は、本名は苻丙、号は建業(石堅とも呼ばれる)で、ディ族の人で、甘粛秦安...
ランタンフェスティバルの起源を探ります。ランタンフェスティバルの起源に関する伝説は何ですか?
おもしろ歴史編集部がランタンフェスティバルの起源についてご紹介します。ご興味のある方はぜひお読みくだ...
目録: 古代中国の歴史の中で最も野心的な詩はどれですか?
河は赤い - 岳飛彼は怒りで髪を逆立て、雨が止むと手すりに寄りかかった。彼は目を上げて空を見上げ、高...
『謝書』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
ありがとう李尚閔(唐代)私には何の意図もありません。ただあなたの要望に応えるためにペンとインクを持っ...
山鞭と老君山に関する神話と老子に関するいくつかの神話
甘山鞭と老君山の神話的物語:鹿邑城の東門内には、高さ 39 フィートを超える老君台地があり、台地の頂...
趙の武霊王は趙国で最も影響力のある君主でした。なぜ彼は奥宮で餓死したのでしょうか?
戦国時代、または単に戦国時代とも呼ばれる。それは中国の歴史において春秋時代後の大きな変化の時代でした...
『老老衡彦』第4巻の主な内容は何ですか?
マットにはさまざまな種類があります。古代では、座るときに必ずマットを敷いていましたが、現在では寝具と...
『紅楼夢』で青文が朱爾に勝ったのはなぜですか?理由は何ですか?
朱允は、賈宝玉の怡宏院の小侍女です。普段は雑用や雑用を担当しています。次の『興味深い歴史』編集者が、...
「紅楼夢」で最悪の結末を迎える賈家の一員は誰ですか?
ご存知のとおり、『紅楼夢』の賈一族は必ず衰退します。では、賈一族の中で最悪の結末を迎えるのは誰でしょ...
南唐最後の君主李毓:「江南を観て、どれほど悔やむ」の文学的特徴を評価する
今日は、Interesting Historyの編集者が、李游の『王江南・どれだけ憎い』の文学的特徴...
『紅楼夢』では、なぜ林黛玉は薛宝柴よりも友達が多いのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...