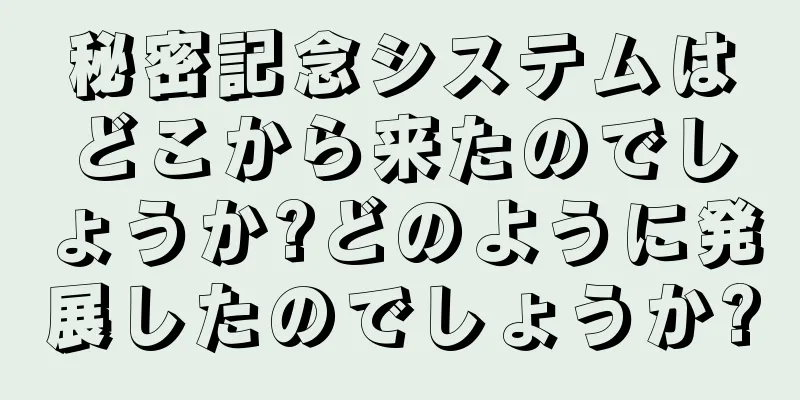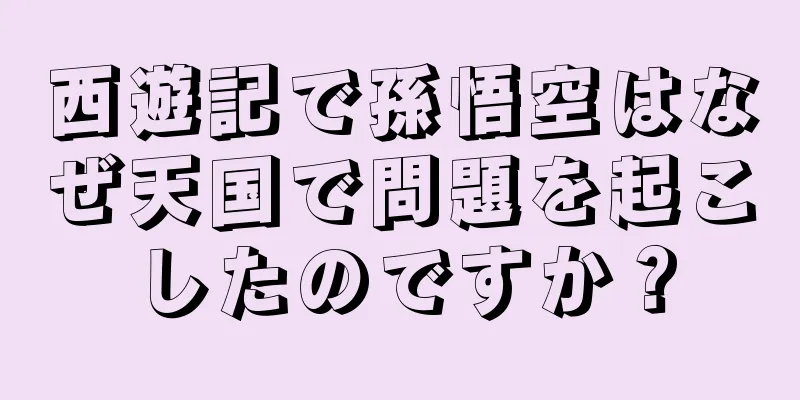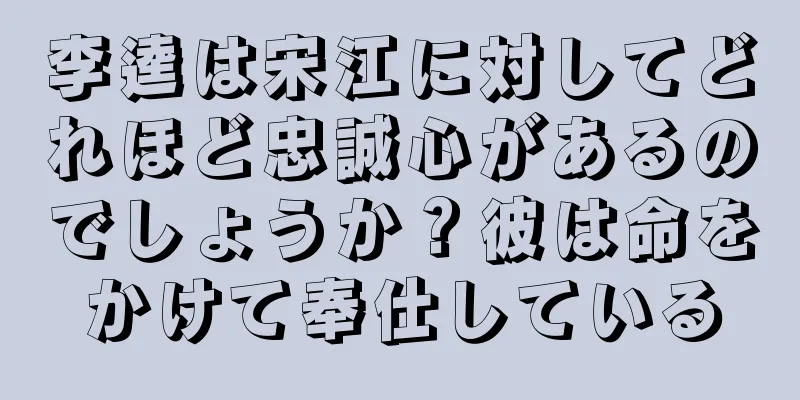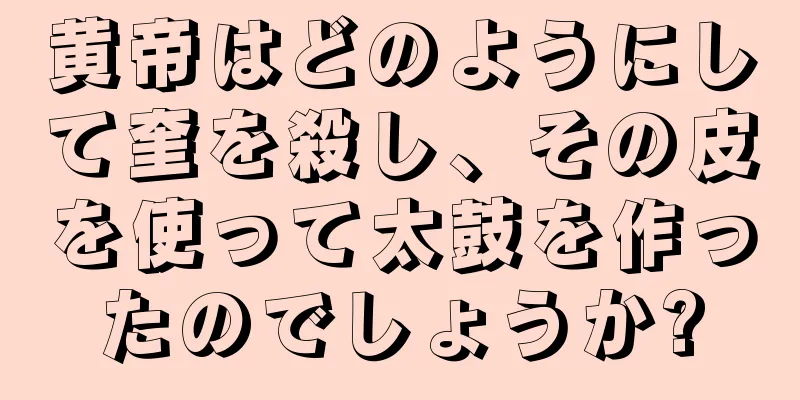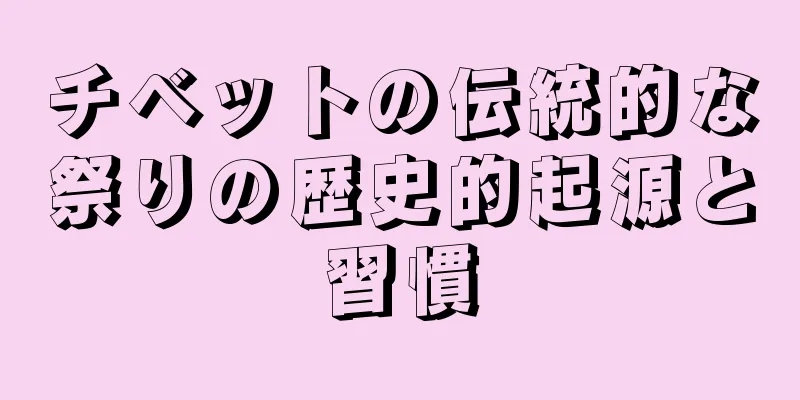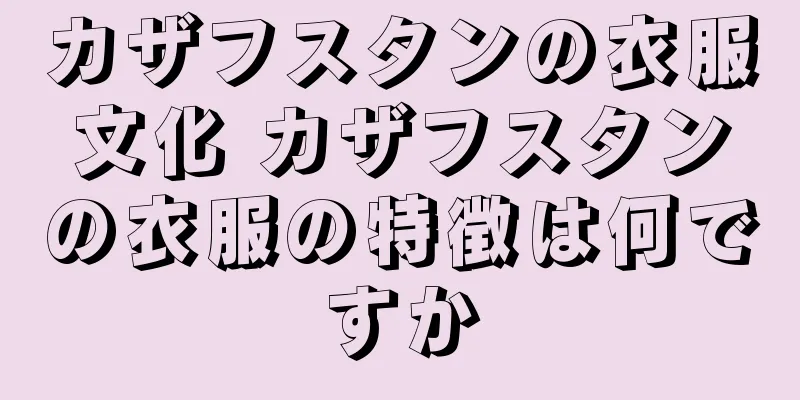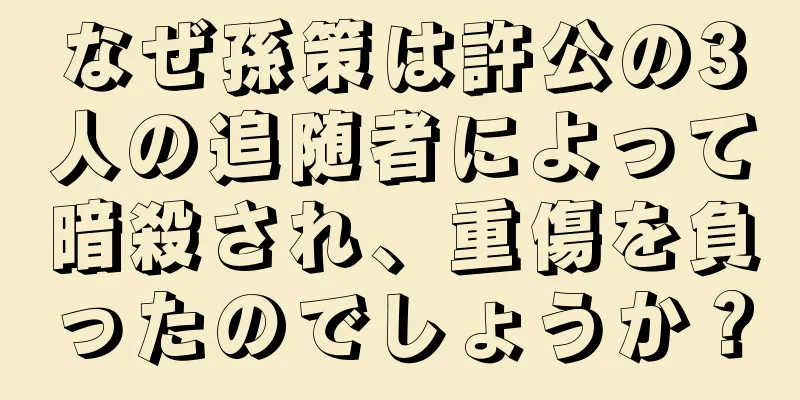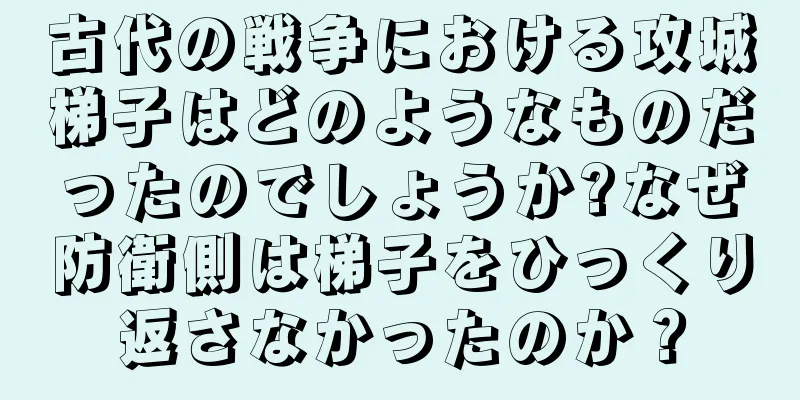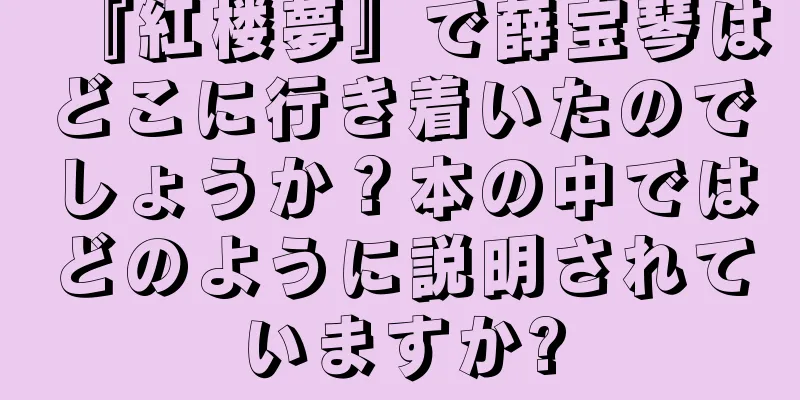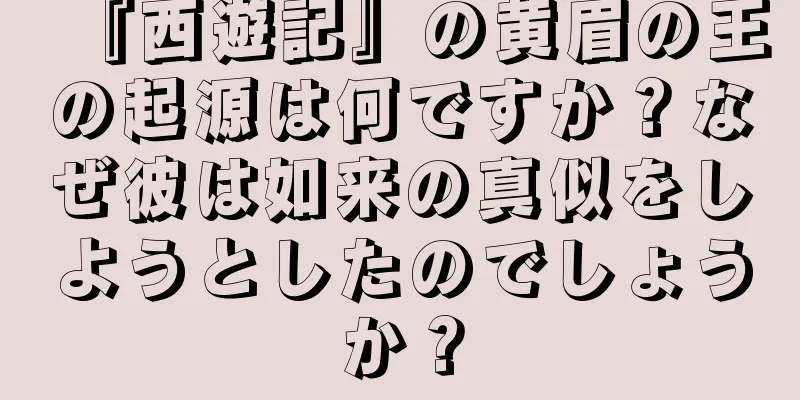長沙県の歴史は何ですか?漢王朝末期に長沙県で起こった3つの大きな出来事は何ですか?
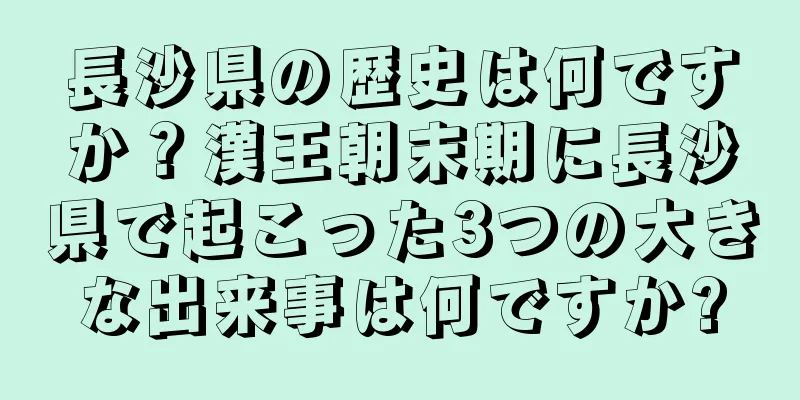
|
劉表に非常に興味がある方のために、『Interesting History』の編集者が詳しい記事を参考までに載せています。 劉表の治世下の荊州には、ある県がありました。漢代の数百の県や国の中では目立たない存在でしたが、その民は裕福で、何度も世を騒がせ、長江以南の県や国の中でも特異な存在でした。諸侯の利益をめぐる競争の中心となりました。 ここは長沙県です。 1. 長沙県の歴史 西周の時代にはすでに長沙に人が定住しており、春秋戦国時代には楚国がこの地に都市を建設し、「長沙」と名付けたことが、この都市名の始まりです。秦の始皇帝は五嶺を平定し、長沙県を建てた。西漢の成立後、劉邦は呉叡を長沙王に任命し、湘県を臨湘県に遷都した。後継者問題により呉氏の長沙王国が廃止された後、漢の景帝は長男の劉法を長沙王に任命し、王莽の時代まで存続した。光武帝が明王朝を復興した後、劉表が荊州を占領するまで長沙県が設けられた。 長沙は中原に比べると早くから開発されていたものの、未開の地であり、あまり重視されていなかった。そのため、劉邦は呉叡の領地をここに移しました。ここを頼りにすれば、呉一族が大きな動きをすることを恐れなかったからです。これも呉一族の長沙王国が存続できた理由の一つです。その後、劉法は漢の景帝に評価されなかったため、劉家の長沙王国は偽装亡命となり、劉法は生涯を通じて領地を変えることに執着した。これだけでも長沙県の現状がよく分かります。漢王朝の統治の中心は関中、中原、黄河流域にあり、長沙は辺鄙な県であったため、中原の諸家の注目を集めることはできなかった。まさにこの理由から、長沙県は何もせずに徐々に発展することができたのです。 二度三度嵐を巻き起こした 長沙県が徐々に繁栄するようになったのは漢王朝の末期になってからであった。これを証明する具体的な証拠はないかもしれませんが、いくつかの大きな出来事からそれを垣間見ることができます。 1. 孫堅が反乱を鎮圧 黄巾の乱の後、孫堅は再び涼州に遠征した。その後、「長沙の賊、屈興が将軍を名乗り、1万人以上の民を集めて城を攻撃し包囲した」、また「周超と郭石も部下を率いて霊と桂で蜂起し、興に応戦した」。これらの少数の民が反乱を起こしただけで、荊州の半分が制御不能になり、その勢力は非常に強大だったと言える。 この時、朝廷は孫堅を長沙の知事に任命した。孫堅は就任後、「自ら兵士を率いて戦略を実行し、数か月以内に敵軍を打ち破った」。反乱鎮圧の戦いは非常に迅速だった。彼は自分の郡の反乱を鎮圧しただけでなく、予想を超えて「国境を越えて反乱を探し、3つの郡は沈黙した」。この功績は隠し切れないほど大きかったため、武成侯の爵位を授けられた。 当時、漢王朝はまだ衰退しておらず、黄巾の乱を経験していたものの、朝廷はまだ権力を握っていた。そのため、朝廷の官吏である孫堅は、以前集めた「淮河と泗河の精鋭兵」を連れていくことはできず、せいぜい将軍と従者の兵数名を連れていく程度だった。そのため、孫堅が反乱を鎮圧するために使用した主力は長沙県の兵士たちでした。しかし、漢代の軍事制度では、国境の郡でない限り、軍隊をあまり多く持つことは不可能でした。孫堅が短期間で大軍を集め、屈興らの反乱を速やかに鎮圧できたことは、孫堅の実力を示すものであるが、当時の長沙には十分な兵力があったことを証明するのにも十分である。長沙県がこれほど多くの軍隊を養う余裕があったという事実は、長沙県が中原のどの大県にも劣らないほど豊かであったことを示している。 2. スダイの反乱 初平元年、関東諸侯は三公の勅旨を偽造して董を攻撃する軍を召集した。孫堅は長沙の太守として諸侯連合に加わり、軍を率いて北上し、途中で荊州太守の王睿を殺した。ご存知のとおり、州知事は国を率いて十分な軍隊を持つことができます。孫堅があえてそうしたことを行ったという事実は、彼が長沙にいた間に精鋭の軍隊を訓練していたことを示しています。孫堅は太守の軍隊を併合した後、南陽に到着した時にはすでに数万の兵馬を擁していたが、当時の郡太守としては、これは彼の管轄範囲をはるかに超えるものであった。孫堅は兵力が十分であったため、よく訓練された兵士と十分な食料を有していた南陽の知事を殺害し、南陽を袁術に与えた。この時の孫堅の強さは、間違いなく諸侯の中でもトップクラスであったことがわかります。 孫堅が去った後、蘇岱が長沙の知事に就任した。誰が彼を任命したのかは誰も知らないが、わかっているのは、彼が長沙の知事に任命された後、荊州の信頼できる知事である劉表が荊州に入るのを阻止する目的で反乱を起こしたということである。これが劉表の「荊州単独征服」につながり、彼の計画は挫折した。その後、劉表は襄陽に都を移し、荊州諸家の協力を得て蘇岱の反乱を鎮圧した。 孫堅は董卓と戦うために軍を編成し、西涼軍の戦闘力を見て、全力を尽くすつもりであり、残された兵が多すぎることは絶対にないだろうと考えました。しかし、後継者の蘇岱は短期間で大軍を召集し、南州の華容の首長北允らを謀反に駆り立てた。これは長沙が十分な力と豊富な人口資源を持っていたことを示している。 3. 張仙の反乱 官渡の戦いの最中、長沙の太守張仙が反乱を起こし、荊南の4つの県を占領した。これは最後の蘇岱の反乱からわずか10年後のことである。この10年間、劉表の権力は徐々に拡大し、北荊の中核地域の支配を強化することに忙しく、南荊に対する支配を緩めたため、南荊の地方の匪賊の勢力が再び拡大した。張仙の反乱の後、劉表は軍を率いて戦いに臨んだが、1年以上経っても臨郷を占領することができず、袁紹に約束した出兵計画は実行されなかった。張仙が戦病で亡くなり、荊南の人々の士気が下がったとき、劉表はその機会を捉えて息子の張毅の防御を突破し、再び長沙の乱を鎮圧した。彼はこの乱を口実に荊南の大粛清を行い、各県の知事を自分の民に置き換え、荊南の4つの県を完全に支配した。 小説の中で劉表の存在感は薄いが、その実力は弱いわけではない。張仙は劉表と荊州一族の攻撃を阻止し、反乱を長期間維持することができ、長沙県の軍事力が以前よりも回復したことを示している。 3. 王子たちは互いに競い合う 長沙は南荊の4つの県の長であった。張仙の反乱を鎮圧した後、劉表は韓玄を長沙の知事に任命した。南荊のこの大きな県を統治するために、彼は甥の劉攀と将軍の黄忠を長沙游県の守護に任命し、互いに牽制し合いながら長沙県を統治した。しかし、長県を守っていた劉邦は、何度も東呉の領土に侵入し、孫権に有力な将軍太史慈を建長に転属させました。劉表が荊南を平定した後、長沙の勢力は急速に回復したことがわかります。 劉表が亡くなり、赤壁の戦いが勃発して曹操が敗北すると、劉備はすぐに南荊の4つの郡を奪還するために人を派遣した。伝説上の「赤面の関公が長沙で戦う」という話はなかったが、劉備にとって長沙の地位は疑う余地がなかった。これは劉備が長年の客人生活を経て獲得した最初の土地であったため、劉備はこれを非常に重視し、諸葛亮をここに派遣して長沙と他の3つの郡を再編させた。戦後の秩序を維持し、民衆の心を掴むために、韓玄は引き続き知事に任命された。 しかし、南荊の4つの郡は中原から遠すぎたため、後に劉備は孫権から南州を借り受けて江陵に遷都した。劉備は南荊の4つの郡からの税を使って南州に駐留する軍を支え、曹操の圧力に抵抗した。それ以来、資源が継続的に撤退したため、長沙の力は継続的に弱体化しました。 そのため、劉備が益州を占領し荊州を要求したが、劉備は拒否した。孫権は激怒し、呂蒙を派遣して軍を率いて長沙と他の3つの郡を占領させた。長沙の知事は戦わずして降伏した。このため、呉と蜀は衝突寸前となり、曹操の脅迫により再び和平が成立した。しかし、孫権は霊陵県を劉備に返還しただけで、長沙を手放すことを拒否した。これは確かに霊陵が劉備の支配する地域に近いからであるが、長沙が霊陵よりも豊かだからでもある。 それ以降、長沙は戦火から遠く離れた後方地域に位置していたため、次第に地位が低下し、物資の輸出基地となって衰退していった。人口が急増し、経済の中心が南下し、江南地区が発展して初めて、長沙の地位は徐々に高まり、明代には「湖広は足り、天下は満ち足りている」という評判が生まれました。 長沙が漢末期に三度の嵐を巻き起こすことができたのは、十分な人口があったからである。『後漢書・郡州記』によると、長沙には13の市(県)があり、25万5千戸以上、105万人以上の人口があり、中原の裕福な県よりも多かった。漢代には1万戸以上の県が大県とされていたが、長沙府の13の県の平均戸数は2万戸近くあり、まさに奇跡的なことだった。冷兵器の封建時代においては、人口は最大の富であり、強さの象徴でした。そのため、長沙は短期間のうちに数々の激動を経験し、今でも嵐を巻き起こすことができるのです。 しかし、長沙は中原の支配中心地から遠く離れており、貴族たちからはあまり重視されていませんでした。いくつかの騒乱は一時的な影響を与えましたが、三国時代全体を通して大したこととはみなされず、非常に控えめなものでした。これは、三国時代の江南地域がまだ時代の主流になっていなかったことを示し、「楚だけが才能を持っていた」という後期の段階には程遠いものでした。 |
<<: 宋真宗趙恒は幼少期にどのような出来事を経験したのでしょうか?歴史書には彼について何が記録されているでしょうか?
>>: なぜ一週間は7日間あるのでしょうか?週制はどのようにして中国に伝わったのでしょうか?
推薦する
「Sumuzhay Grass」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
スムチャ草梅耀塵(宋代)露に覆われた堤防は平らで、別荘は煙に包まれている。雨上がりの草は青々と茂り、...
彭城の戦いの失敗は、范増が劉邦をどのように評価していたかを証明しただけだろうか。
劉邦と項羽が天下を争っていたころは、項羽はタフガイというイメージでしたが、後に項羽は自分のせいで劉邦...
「白牡丹」第17章:石成は機会を知り、湛慈寺に留まる。桂金は病気になり、盗賊の宿屋に行く
『白牡丹』は清代の洪綬が書いた小説です。その主な内容は、正徳帝が夢に見た美しい女性、白牡丹と紅牡丹を...
張孫無忌は30年間政権を補佐した。なぜ李志によって裏切り者として処刑されたのか?
水より冷たいものはなく、人間より身近なものはない、と私たちはよく言います。一般的に言えば、私たちの国...
商王朝が滅亡した具体的な理由は何だったのでしょうか?
商王朝の崩壊:殷または殷商としても知られる商王朝は、中国史上 2 番目の王朝であり、同時代の直接的な...
文学理論書『文心语龍』第四巻原文鑑賞
天の道が説かれ、天の運命が明らかにされ、馬龍が現れると、偉大な易経が生まれ、神亀が現れると、洪範が光...
なぜ白族の神々の崇拝が彼らの宗教的信仰だと考えられているのでしょうか?
本竹信仰は白族特有の宗教信仰です。本竹は本竹神とも呼ばれ、白族語では「武曽」と呼ばれ、「老祖」(男祖...
明代の服装:明代の官服
彼は黒い紗の帽子と布帽子をかぶり、丸い襟と細い袖の長いローブを着ていた。 「パンカラー」とは、襟の縁...
隋代の天文学者、劉卓のデータと歴史的貢献
導入劉卓(発音は卓)、慣用名は士源、新都長亭(現在の河北省薊県)の出身。西暦544年 - 610年。...
曹操は才能に基づいた人材の採用を重視していました。曹一族に最も多くの親戚や重要な役人がいたのはなぜでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
唐の玄宗皇帝の娘、万安公主の簡単な紹介
万安公主(?-?)、唐の玄宗皇帝の娘。母親は不明。開元4年(716年)5月20日、睿宗は百府殿で亡く...
「閻吉勝太政大臣が同胞を率いて北園を訪れた(第7部)」の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
厳吉勝大師とその同室者たちは、訪問者を北園に招待した。第7部楊万里(宋代)市内で竿についた蓮の鞘を買...
『紅楼夢』の薛宝才の凧にはいくつの意味が込められているのでしょうか?
『紅楼夢』の薛宝才の凧にはどんな意味があるのでしょうか? 7羽のガチョウが一列に並んでいるのは本当に...
李元巴はどうやって死んだのですか?袁天剛はそれが宇文成都と関係があると考えた
あなたは本当に李元巴と宇文成都を知っていますでしょうか?Interesting Historyの編集...
東周書紀第7章:公孫炎が戦車を奪い、高叔を撃ち、崔公が盗賊の殷公を褒める
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...