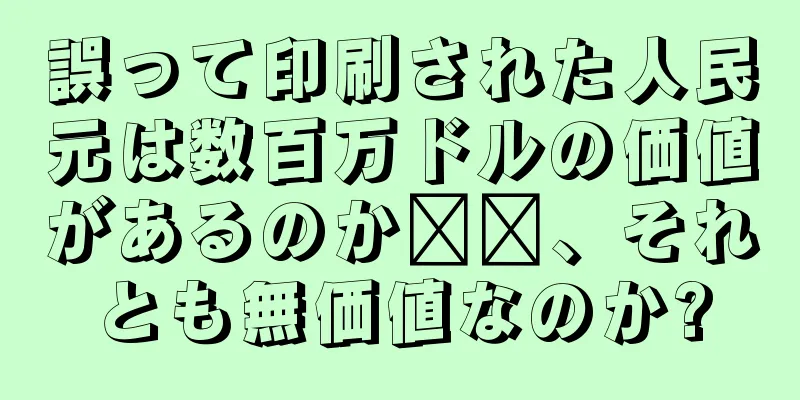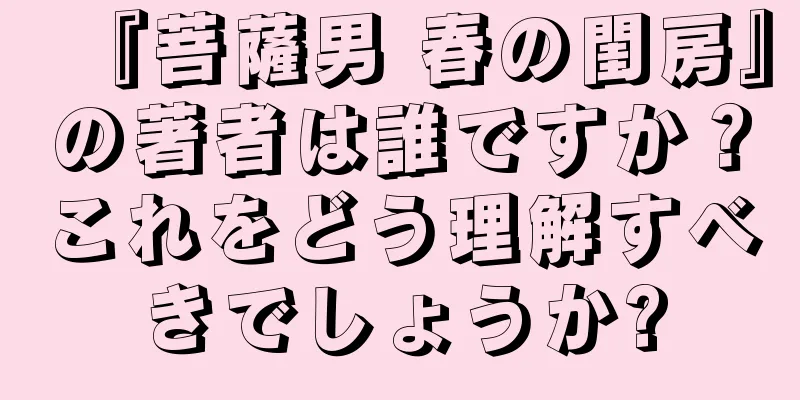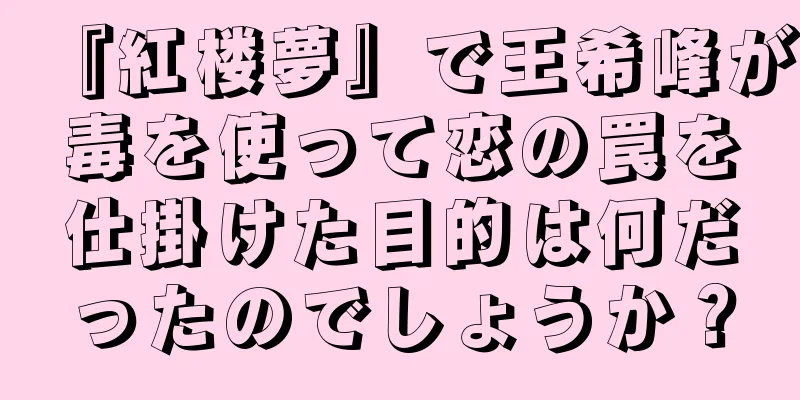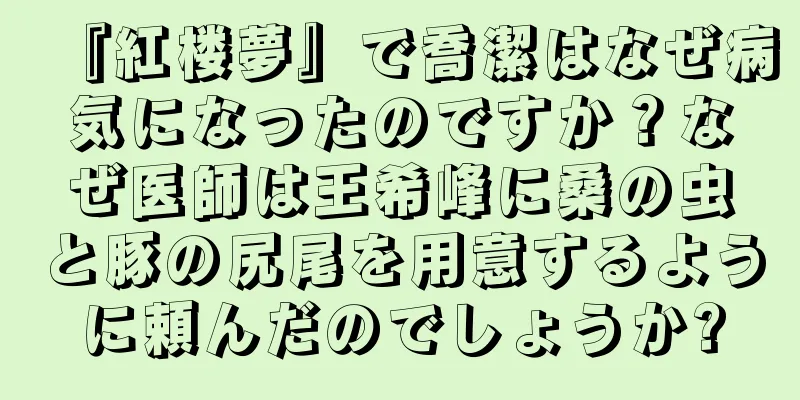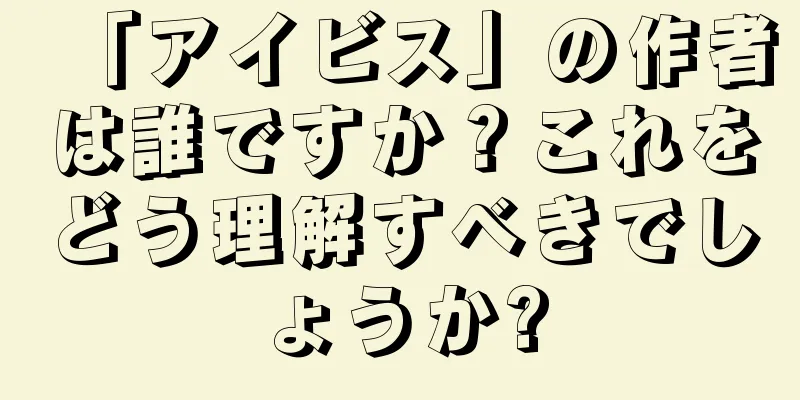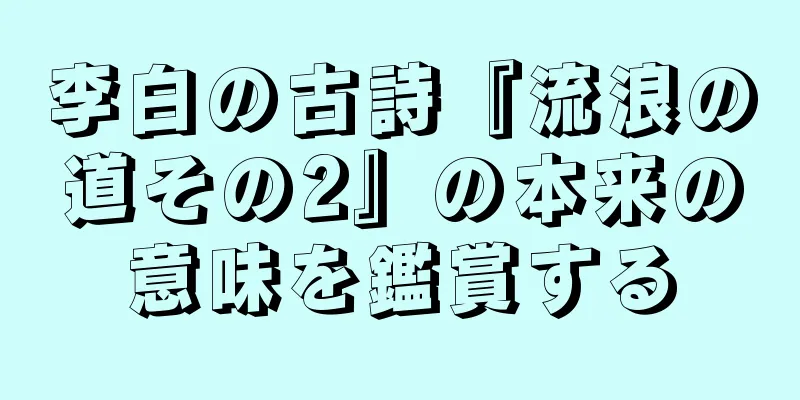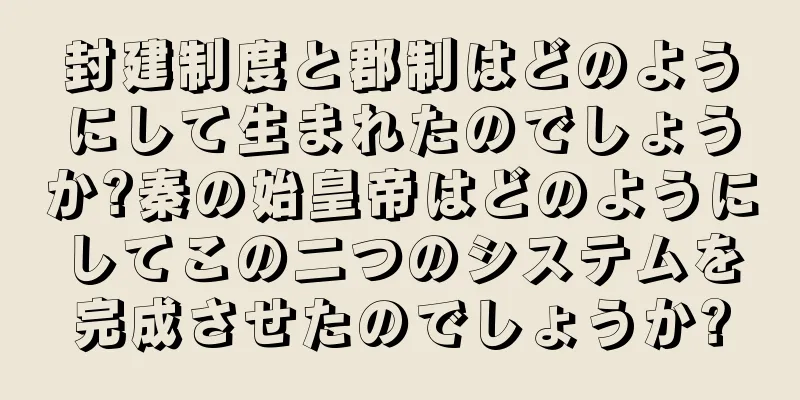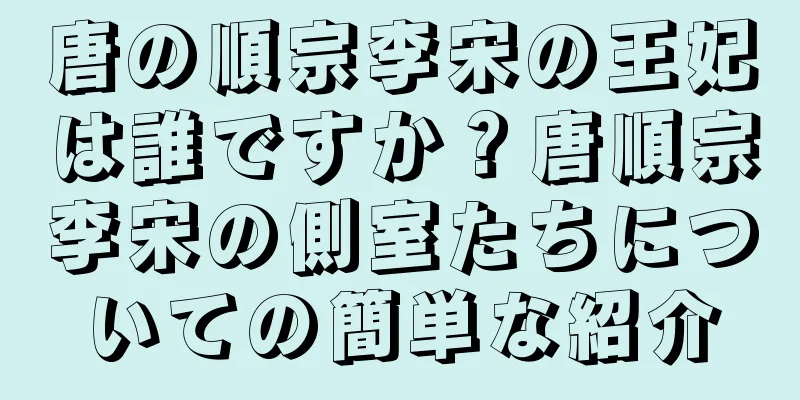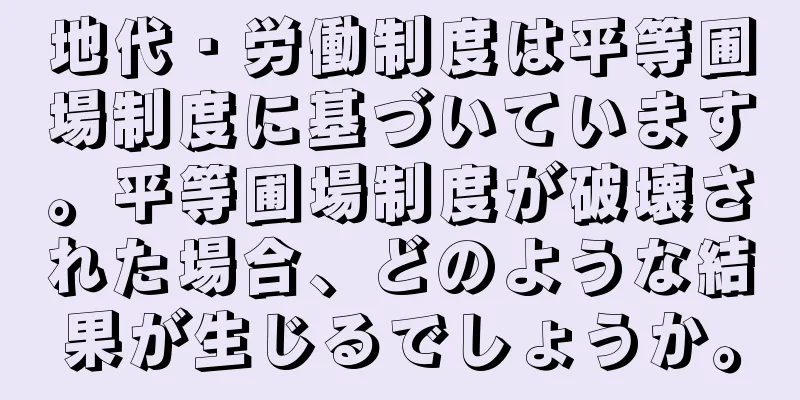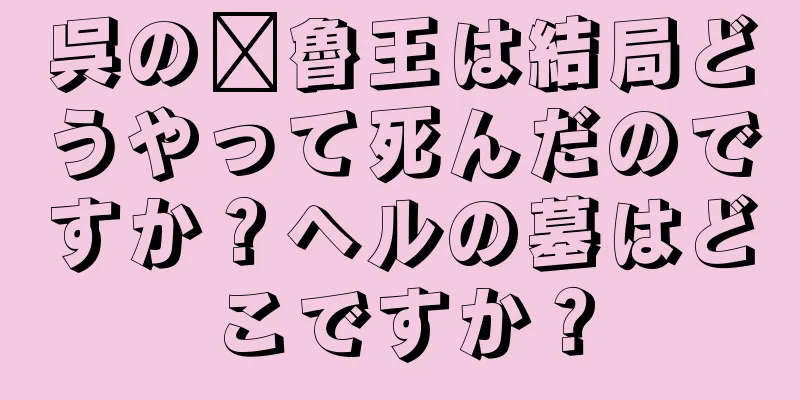明清時代の監督制度の主な実施者として、監察官はどのような役割を果たしましたか?
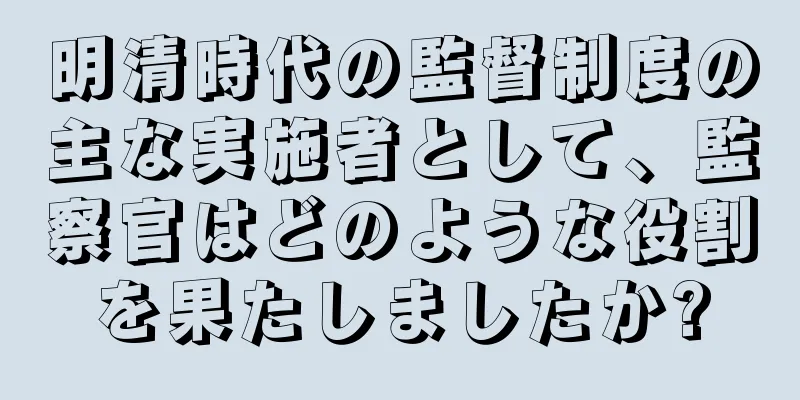
|
監察院は明・清時代の官職の名称で、前王朝の監察院から発展したもので、監督、弾劾、助言などを担当していた。司法部と大理寺とともに三法院と呼ばれ、重大な事件が発生した場合、三法院が共同で裁判を行うことから、「三法院合同裁判」とも呼ばれる。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 明の洪武15年(1382年)、前朝が設置した検閲官を改め、左検閲長と右検閲長を長官とし、その下に副検閲長と副検閲長が置かれた。さらに、13の地域それぞれに検閲官がいて、役人の検査と弾劾を担当していました。明代の検閲官は司法機関を監督するだけでなく、「重大な事柄については報告して裁判にかけ、軽微な事柄については即時に決定する」権限も持ち、最高監督機関となっていた。 清朝では、左副総監と右副総監の称号が総督と総督の国家称号として使用され、総督と総督の業務を円滑に行うために使用されました(明朝では、総監と副総監の両方が追加の称号として使用されていました)。雍正帝の治世の元年(1723年)、六つの検閲部がここに統合されました。乾隆帝の治世13年(1748年)、左千都于使の職は廃止された。清代の検閲局は法律と規律を監督する機関であり、死刑事件を審査するだけでなく、秋期裁判や熱期裁判にも参加し、すべての役人を監督した。 明清時代の監督制度の主な実施者として、監察機関は封建統治の正常な秩序を維持し、封建国家機構の円滑な運営を確保する上で重要な役割を果たした。 明朝の検閲 『明史官録』によれば、検閲官には二等級の左検閲長と右検閲長、三等級の左副検閲長と右副検閲長、四等級の左副検閲長と右副検閲長がいた。検閲官は13名おり、その総数は100名を超え、全員が第7位である。その他の機関としては、経験部、事務局、審査局、刑務部などがあります。首都以外で勤務中に検閲長、検閲副長、検閲副長の称号を与えられた役人には、総督、提督、国司、国司を兼ねる総督、国司を兼ねる提督などがいた。 清朝の検閲 『清代史稿 官録』によれば、当初は明の制度を踏襲し、検閲局が設立された。天宗10年、皇帝は「政務で過ちを犯した者、または上司に対して傲慢で無礼な者は、率直に話すことを許す」という勅令を出した。崇徳元年、成政と燦政の官吏が設立された。崇徳2年には宰相1人、左右に満蒙漢人2人の長官が置かれたが、後にこの制度は廃止された。順治元年、左検閲長が検閲官を務め、満州人と漢人各1名が所属していた。左副検閲官はそれぞれ2名ずつ、朝廷の事務を補佐する。漢左千都于使という人物がいた。彼は最初は漢軍に、後に漢人に雇われたが、乾隆13年に廃止された。他州の知事や総督には、右検閲官、右副検閲官、右補検閲官という右官位の称号が与えられた。乾隆帝の治世13年に右監察大将の称号は廃止された。 検閲長は検閲庁の長であり、漢代や唐代の大検閲官に相当します。副検閲長は検閲長に相当し、副検閲長は副検閲官に相当します。3人とも検閲庁の長であり、検閲庁の事務を担当または共同で担当していました。検閲官は、直接監督権を行使した、検閲局の重要な常勤職員でした。検閲府の管轄下にあったが、検閲府の統制を受けずに独立して行動し、独自に皇帝に報告することもできた。巡察使として派遣された者は、皇帝に代わって全国を巡視し、その権力はさらに強大なものとなる。検閲官の総権限は「すべての役人を弾劾し、不満を明らかにし、すべての地域を監督し、皇帝の目と耳、そして規律と道徳を担当する役人として機能すること」であった。具体的には、「裏切り者で邪悪な大臣、徒党を組んで権力を乱用し政府を混乱させる悪党は弾劾される」、「下品で腐敗した役人は弾劾される」、「誤った学識を持つ者、憲法改正を提案する手紙を皇帝に送る者、昇進を求める者も弾劾される」などである。上記3項目は、訂正権と弾劾権です。 「謁見の際、人事省と共に審査し、昇格、降格する。」これは監督審査権である。「大法廷の重罪人は外廷で審理し、法務省と最高裁判所が判決を下す。」これは司法権である。「内においては勅令に従い、外においては監督し、それぞれ勅令に従って行動する。」 「これは臨時の任務である。」 軍務官を兼ねる総督には提督の称号が与えられ、地方に将軍がいる場合は副部長または参事の称号が与えられ、管轄地域が広く、重い事柄がある場合は総督の称号が与えられます。整政、統治、監察、宰相などの役職は、いずれも状況に応じて特別に設けられたものであった。 ” 左派と右派の検閲官長 左都有史 左渡邊氏は、封建社会において監督権を行使するために特別に設置された機関である監察官の長であった。明代には、検閲官に左検閲長と右検閲長の二つの部署があり、どちらも二等官であった。清朝では左検閲総監が検閲官の事務を担当していた。彼の階級は何度か変わり、最終的に二等官に定着した。左副検閲総長は検閲官の事務を補佐し、左検閲総長の職務を支援する三等官であった。 右派検閲官長 有度有職は明・清時代の官職であった。雍正8年に一位に昇進した。清朝では総督が持つ称号であった。乾隆帝の治世14年に、総督に任命された者には右検閲長官の称号を与えるという勅令が出された。河川長官、貨物輸送長官、各州の知事には、すべて検閲官代理の称号が与えられた。彼らが陸軍省の大臣または副大臣の称号も持つかどうかは人事省によって決定された。左派と右派の検閲官長は検閲官庁の最高位であった。一位から。 左派と右派の検閲官長の給与 左・右の検閲長は第一位で、年俸は銀180両、米180斤であった。左・右の副検閲長は第三位で、年俸は銀130両、米130斤であった。また、雍正以後、官吏は「扶持銀」も受け取るようになり、その額は主に給与の10~100倍に及んだ。例えば、『大清徽典』によれば、総督の扶持銀は2万両に達し、総督は1万5000両に達することもあった。 |
<<: 検閲官の立場は歴史を通じてどのように進化してきたのでしょうか?清朝における左検閲総監の権限は何でしたか?
>>: 空城作戦は楚漢戦争の時にも登場したのでしょうか?劉邦はどのような行動をとったのでしょうか?
推薦する
『新世界物語』第 29 章には誰の物語が記録されていますか?
『十朔新于』は、魏晋の逸話小説の集大成です。では、『十朔新于・談話・第29号』には誰の物語が収録され...
薛定山の西征 第25章:竇一虎はシンバルに苦しみ、秦漢は弟を救うよう命じられる
清代の在家仏教徒である如廉が書いた小説『薛家将軍』は、薛仁貴とその子孫の物語を主に語る小説と物語のシ...
【于美仁・若い男の美しさは美しい女性の美しさを超える】作者:顧英、原文と作品の鑑賞
「于美人:若者の美しさは仙女よりも美しい」は古代中国の詩であり、作者は顧英です。ポピーその若者は仙女...
郭静と黄容はどうやって出会ったのですか?郭静と黄容には何人の子供がいましたか?
郭静と黄容はどうやって出会ったのですか?桃花島の主人「東邪」黄耀師と馮衡の一人娘。聡明で美しい。桃花...
楊延徳と楊武朗はなぜ出家したのでしょうか?
楊延徳の紹介 金刀師楊業の五男である楊延徳は、楊春と名付けられ、雅号は延徳であった。北宋朝廷の将軍で...
リン・ダイユはなぜシレンに嫉妬しないのか?彼女を信頼しているからなのか?
タイトル: 『紅楼夢』の林黛玉が西仁に嫉妬しない理由 - 歴史的背景の解釈段落1: はじめに『紅楼夢...
唐の順宗皇帝の娘、邵陽公主の簡単な紹介と結末
邵陽公主(?-?)、唐の順宗皇帝李宋の娘。母親は不明。唐の文宗皇帝の大和3年(830年)、荀陽公主、...
二科派安経記 第19巻:農夫はいつも忙しく、羊飼いの少年は毎晩栄誉を受ける
『二科派経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。 1632年(崇禎5年)に書籍として出...
道教の雷部の五将とは誰ですか?また、彼らの具体的な任務は何ですか?
道教の雷部の五将とは誰ですか? 彼らの具体的な任務は何ですか? 彼らはどこから来たのですか?雷部の五...
「休日に王世宇を訪ねるが会えない」の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
休暇で王世宇を訪問したが会えなかった魏英武(唐代) 9日間急いでいて、1日の休みがあったのに、あなた...
賈雲はどうやって『紅楼夢』の仕事を得たのですか?その背後にある意味は何でしょうか?
『紅楼夢』の登場人物、賈雲。賈家の一員。西廊に住む五番目の義姉の息子。本日は、Interesting...
戦国時代後期の作品『韓非子』全文と翻訳注
『韓非子』は、戦国時代後期の朝鮮法家の巨匠、韓非の著作です。この本には55章が現存しており、合計約1...
なぜ劉備は息子の世話をする大臣として諸葛亮と李延を選んだのでしょうか?権力は一人の手に渡ってはならない
劉備の出世が成功したのは、人をうまく利用したからである。彼は、適切な時に適切な人を利用することによっ...
杜甫は世の中の移ろいやすさと人間の移ろいやすさをよく理解していたので、「貧乏友情の歌」を書いた。
杜甫(712年2月12日 - 770年)は、字を子美、号を少陵葉老といい、唐代の有名な写実主義詩人で...
宋代の張暁祥の詩「山葵空・上元七角」を鑑賞する
以下、Interesting Historyの編集者が張暁祥の『山葵空・上元奇蹟』の原文と評価をお届...