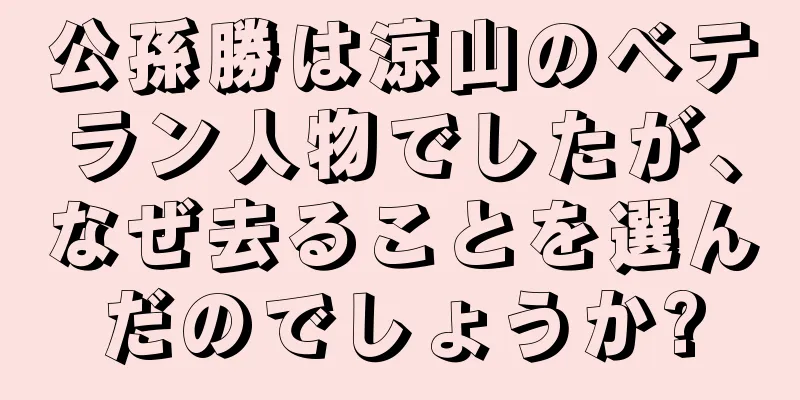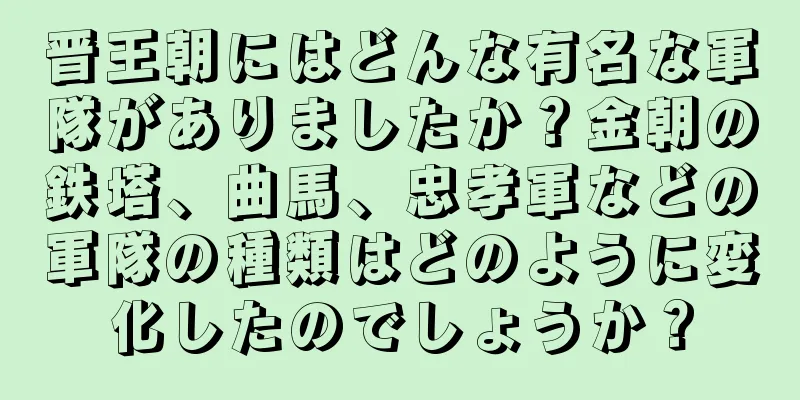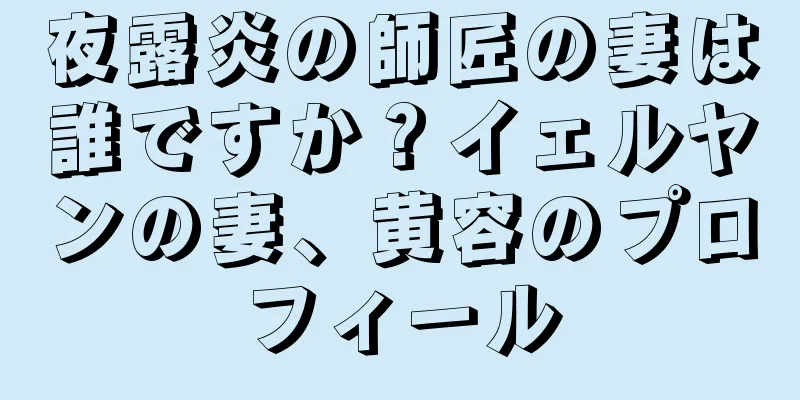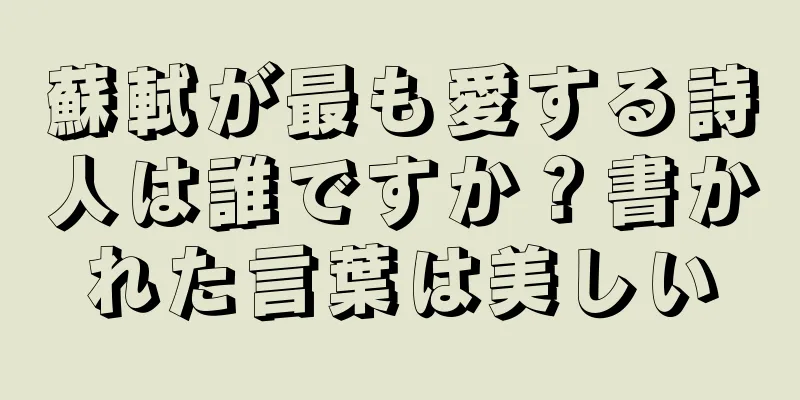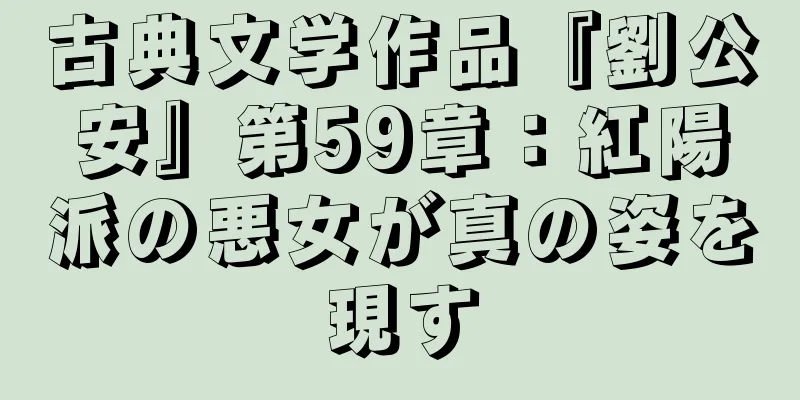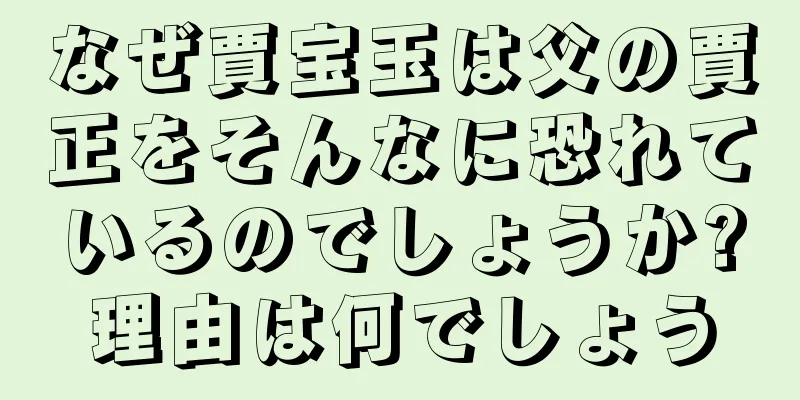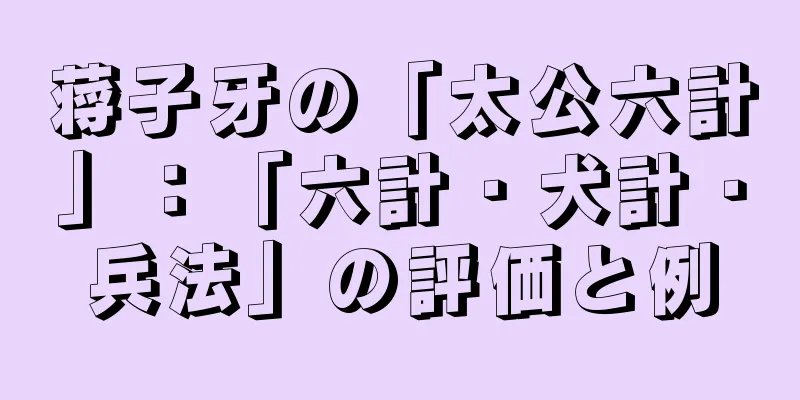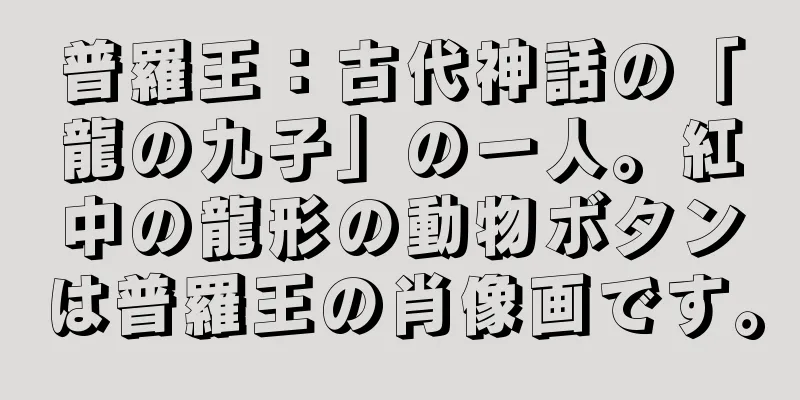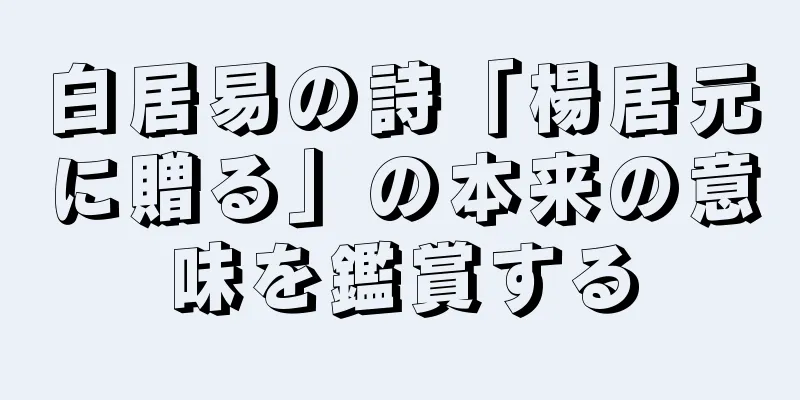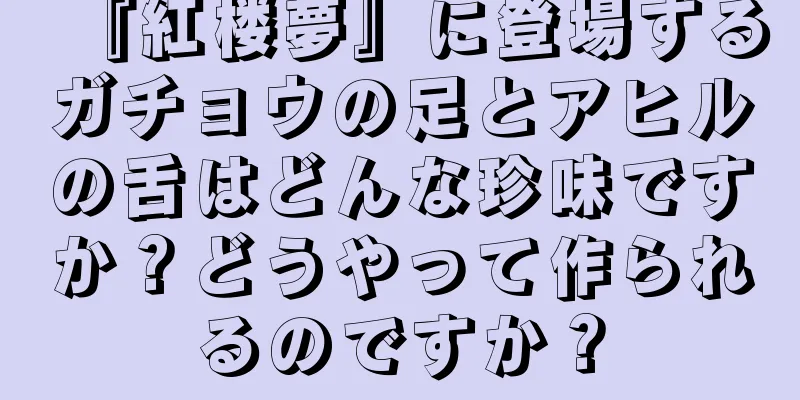宋代の男性の間で髪に花を挿すことが流行したのはなぜですか?それはどのような社会環境を反映しているのでしょうか?
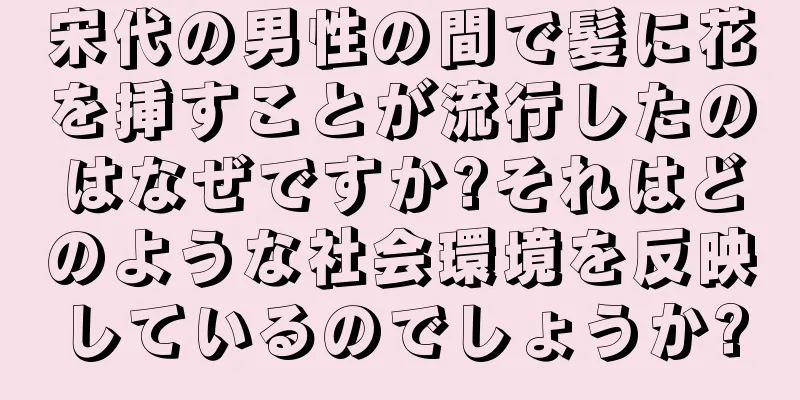
|
周知のように、有名な小説『水滸伝』は北宋時代の涼山の英雄108人の物語です。しかし興味深いのは、これらの力持ちの男たちの中には、実際に頭に花をつけるのを好んだ者が何人かいたことです。たとえば、短命だった二郎阮小武はザクロの花をつけ、病弱だった関索楊雄はハイビスカスの花をつけ、放蕩息子の燕青は四季の花をつけていました。特に、涼山座第95位の死刑執行人である蔡青は、異常なほど花を愛し、常に頭に花を添えていたため、「一花」というあだ名がつけられた。ギャングや盗賊だから、彼らの趣味は型破りだと思わないでください。実際、これは当時、宮廷や国を席巻したファッションでもありました。男性は髪に花をつけるのが大好きでした。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 男性が髪に花を飾るという流行は宋代に流行した。 宋代の男性が花をつける習慣について言えば、それは彼らがロマンチックであるかどうか、また彼らの家庭環境が裕福であるかどうかとは関係なく、当時の一般的な社会的傾向でした。 『宋代史車衣服記』によれば、髪に花を挿すのは当時すでに宮廷の礼儀作法であった。南宋時代の詩人、楊万里は『徳寿宮の誕生日祝いのスローガン』という詩の中でこう書いている。「なぜ羯鼓の音が春の到来を促す必要があるのか? 君主は元旦に春を先導するのだ。」何千人もの役人の帽子には牡丹、草本牡丹、バラの花が咲いています。これは、宮殿で旧暦の1月15日を祝う楽しい場面だけでなく、その時に誰もが頭に花をかぶっている壮大な場面も描いています。遠くからでも、色彩の乱舞とほのかな香りが見えます。 北宋時代の作家蘇軾は、かつて杭州の知事を務めた。牡丹が満開の頃、彼は吉祥寺に行き花を楽しみ、「吉祥寺で牡丹を楽しむ」という詩を作った。老人が髪に花を挿すのは恥ずかしくないが、花は老人の頭にあることを恥ずかしく思うべきだ。酔っ払った人が家に帰って通行人を助けたとき、その人は笑うべきだ。10マイルの真珠のカーテンが半分引っ掛かっている。この詩の最初の 2 行は、心が広く、束縛がなく、自由で楽観的な蘇軾のイメージを鮮やかに表現しています。彼はとても年老いていましたが、花の優雅な美しさを今でも愛しており、髪に花を挿す勇気を持っていました。このことから、宋代には、男性が髪に花を飾ることはもはや異例の服装や奇妙な服装とはみなされなくなったことがわかります。観客は宮廷の役人から庶民まで幅広く、社会的な慣習となっている。 国賓晩餐会に出席し、皇帝の権力を象徴する 宋代には、あらゆる階層の人々に日常的に愛されていただけでなく、男性が髪に花を飾ることは「国宴」、つまり宮廷の宴会の決まった作法の大きな特徴の一つとなった。 『歌の歴史・儀式』には、すべての大規模な国家の祝賀会や宴会では、髪に花をつけた祝祭の人物がいた、と記されています。これらの宴会には、春秋宴会、クリスマス宴会、文熙宴会、西宴会、屈宴会、銀福宴会などが含まれます。 しかし、男性が髪に花を飾るという社会的流行は北宋の時代に始まったわけではない。髪に花を挿す習慣は唐の時代にすでに存在していましたが、それがますます普及したのは宋の時代になってからでした。しかし、宋の太祖・太宗の治世初期には、宴会のときに髪に花を挿していたという記録はない。髪に花を飾る習慣が宮廷の宴会で正式に普及したのは、宋の真宗皇帝の治世になってからでした。宋の徽宗皇帝の時代には、「男性が髪に花を挿す」という習慣はまさに極限まで推し進められました。旅行から帰ってくるたびに、彼は可愛らしい「皇帝の帽子をかぶり、髪に花を飾り、馬に乗って」いた。宋徽宗は随行した大臣や衛兵にも花の簪を与えた。 同時に、徽宗は花を身につけることを推奨しただけでなく、規則も制定しました。例えば、彼は明確な命令を出した。宮殿の花模様の錦の上着を持っている者だけが宮殿に自由に出入りできる、というものだ。したがって、小さなかんざしの花は宮殿への「パス」であるだけでなく、上流階級のアイデンティティと階級の象徴でもあります。 「君主が好むものは、民衆もさらに好む」ということわざがあります。したがって、宋代の人々が髪に花を挿すことに熱心だった理由は、皇帝の好みと擁護と密接に関係していました。 その後、宮廷の礼儀作法として、皇帝は側近たちに花を鑑賞するよう命じるたびに、お気に入りの花を摘んで周囲の王子や大臣に与え、皇帝の権力の恩恵と栄光を象徴するために頭に付けるように頼みました。 成功するキャリアのスポークスマン もちろん、政治的な意味合いに加えて、ヘアピンには文人や詩人によって興味深い文化的意味も与えられてきました。沈括はかつて『孟禧秘譚』の中で「花を髪に挿した四人の大臣」の物語を記録した。北宋時代、揚州知事の韓奇の事務所の裏庭に「金帯」と呼ばれる牡丹の一種が植えられていました。花びらは上下とも赤く、真ん中に金色の雄しべが輪になっています。4本の枝が同時に1本の枝に4つの花が咲き、とても美しいです。韓奇は非常に喜び、当時揚州に滞在していた大理寺の役人である王桂、王安石、陳勝志の3人を招待し、一緒にこの素晴らしい光景を見ました。 韓其は酒を飲みながら花を鑑賞し、4つの花を切り取って各人の頭に1つずつ置いた。意外なことに、その後30年間で、この花見に参加した4人が次々と総理大臣となり、まさに「四花」の縁起を担ぎました。それ以来、牡丹は「縁起の良い花」として崇められ、幸運にも「金の帯」に出会って髪に挿すと仕事が成功すると言われました。 暗示や伝説ではありますが、簪の花の美しさを利用して富と栄光を追い求める人々の願望を体現しています。次第に、髪に花を挿すことはキャリアアップの重要な象徴とみなされるようになり、役人たちはそれを最高の名誉と縁起の良い兆候とみなすようになりました。花が咲くと、庶民は花見に出かけ、季節の花を髪に挿して優雅な姿を演出します。当時、これは首都で大きな見世物となった。もちろん、髪に花をつけるのを好まない人もいます。例えば、大きな壺を壊した司馬光。彼は簡素なスタイルを好み、髪に花を挿すのは男の英雄的精神に反する贅沢であると信じていたため、髪に花を挿す習慣に非常に嫌悪感を抱いていた。 仁宗皇帝の時代に、司馬光は科挙に合格し、朝廷で催された文熙宴に出席したと言われています。皇帝は一人一人に花を贈りました。皆は大変光栄に思い、すぐに花を頭に載せて皇帝の恩寵に感謝しました。ただ司馬光は非常に乗り気ではなく、他人に注意されてしぶしぶそれを着ました。彼はまさにファッショントレンドの異端者でした。しかし、単に自分がしたいからといって、髪に花をつけることを拒否することはできません。宋代も花を身につけることに慣れていない役人に対して厳しい措置を講じた。役人が与えられた花を頭につけていない場合、検閲官によって弾劾されることになります。このようにして、髪に花を飾ることは明確に規定されたエチケット体系となり、あらゆる社会階級に広く受け入れられるようになりました。 歴史を通じて、それぞれの王朝には独自の痕跡とスタイルがあり、それぞれの歴史的時代には独自の美的観点と人文主義的概念があります。宋代に花をかんざしに付ける習慣が流行し、優雅さを示すだけでなく、国民全体が参加する文学的、芸術的な色彩も加わりました。 文学と芸術が栄えたこの時代、富や階級、性別を問わず、人々の美への追求は、本能的な憧れと骨身に染み付いた深い愛情のようであり、頂点に達しました。宮廷の礼儀作法から民間の芸能に至るまで、「男性が髪に花をつける」ことは、北宋時代の啓蒙的で包容力のある社会環境を反映しているだけでなく、美的到達点、精神的アイデンティティ、普遍的な態度も反映していると言えます。 |
<<: 唐の時代には太子妃の恩恵がそれほど良かったのに、なぜ人々は皇帝と関わりを持ちたがらなかったのでしょうか。
>>: 歴代王朝の皇太子の立て方を詳細に分析した結果、乾隆帝はどのような皇太子制度を確立したのでしょうか。
推薦する
宋代の詩「鷺空:長門を再び通って、すべては違う」の分析。作者は詩の中でどのような比喩を使用しているか?
宋代の何朱の『鴎空:長門を再び通過すると、すべてが違っている』。以下、Interesting His...
儒教の古典『古梁伝』の桓公五年の原文は何ですか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
明代の大臣、方小如とは誰ですか?なぜ方小如は一族全員とともに処刑されたのか?
明代の大臣、方小如とは誰だったのか? なぜ方小如は一族全員とともに処刑されたのか?方小如は、号を羲之...
李青昭の別れの詩は、読んだら誰もが泣きたくなるだろう
長い時間の流れは止まらず、歴史は発展し続けます。『Interesting History』の編集者が...
宋江はなぜ涼山へ行ったのですか?なぜ彼は後から採用されたのですか?
宋江と言えば何を思い浮かべますか?次のInteresting History編集者が関連する歴史的出...
『鄒明甫を霊武に送る』の著者は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
鄒明福を霊武に送る(1)賈島彼はかつて西邑県の県令を務めたが⑵、彼の馬は3年間も太らなかった⑶。借金...
蘇軾の有名な詩の一節を鑑賞する: 私は廊下を歩き回り、それでも一人で座っている。月は雲に覆われ、ドアの鍵は重く閉ざされている
蘇軾は北宋中期の文壇のリーダーであり、詩、作詞、散文、書道、絵画などで大きな業績を残した。彼の文章は...
「雨への頌歌、第2部」の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
雨への頌歌、第2部李世民(唐代)暖かい風が緑の野原を吹き抜け、梅雨が香り高い野原に降り注ぎます。新し...
7大陸のうちどの国に氷河がありますか?氷河の融解を止めるにはどうすればいいでしょうか?
南極を除く世界の7大陸には国が分布しており、現在200以上の政治単位があり、そのうち169は独立国で...
欧陽秀の七字四行詩『つぐみ』の何がそんなに良いのでしょうか?
欧陽秀の七字四行詩『つぐみ』の何がそんなに良いのでしょうか。詩の最初の二行は風景を描写しており、真実...
古代王朝における外部の親族による政務への干渉はどのようにして始まったのでしょうか?なぜ漢王朝はこれによって滅亡したのでしょうか?
今日は、興味深い歴史の編集者が、漢王朝が外部の親族の政治介入によって滅亡した理由をお伝えします。皆さ...
漢民族のさまざまな地域における重陽の節句の習慣の簡単な紹介
重陽の節句は、陝西省北部の正式な収穫シーズンです。「9月は重陽の節句、収穫に忙しい。キビやホウキビ、...
ヤオ族はパンワン祭りをどのように祝いますか?ヤオ族のパンワン祭りの紹介
ヤオ地域での盤王祭を祝う古い風習は、晋代の甘肇の『蘇神記』、唐代の劉毓溪の『曼子歌』、宋代の周曲飛の...
『紅楼夢』で林如海が黛玉を賈夫人に託したのはなぜですか?
黛玉は『紅楼夢』のヒロインであり、『金陵十二美女』本編の最初の二人の登場人物の一人です。これについて...
鑫其は鄭厚清の送別会を催し、「曼江紅:鄭衡州厚清の送別会で詠んだもう一つの詩」を書いた。
辛其基(1140年5月28日 - 1207年10月3日)、元の字は譚復、後に幽安と改め、中年になって...