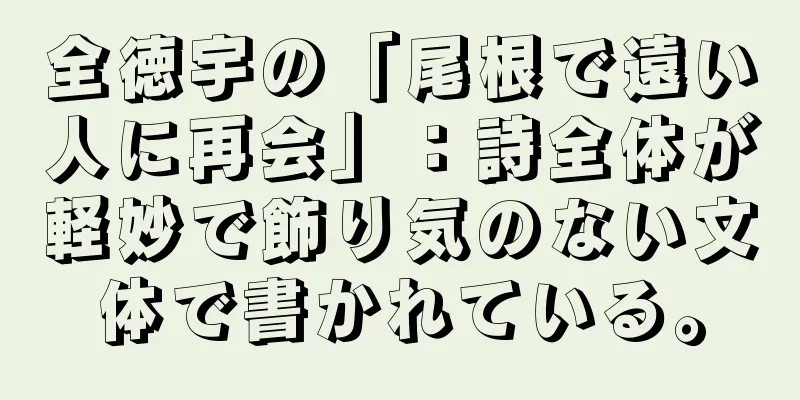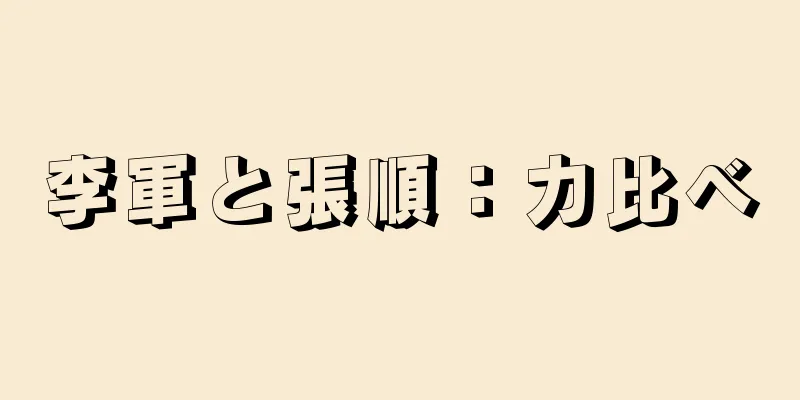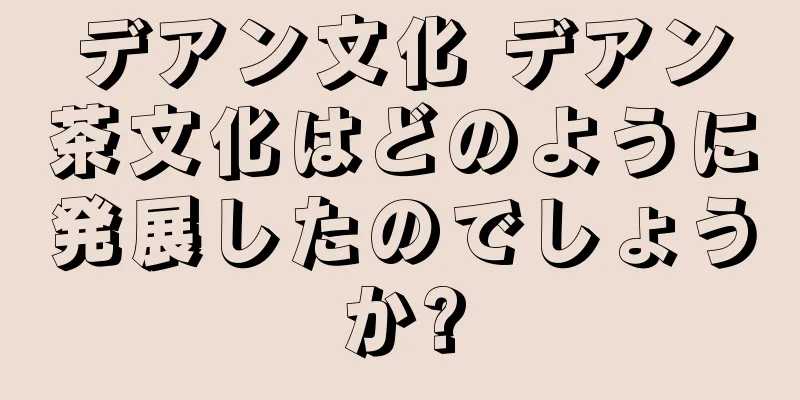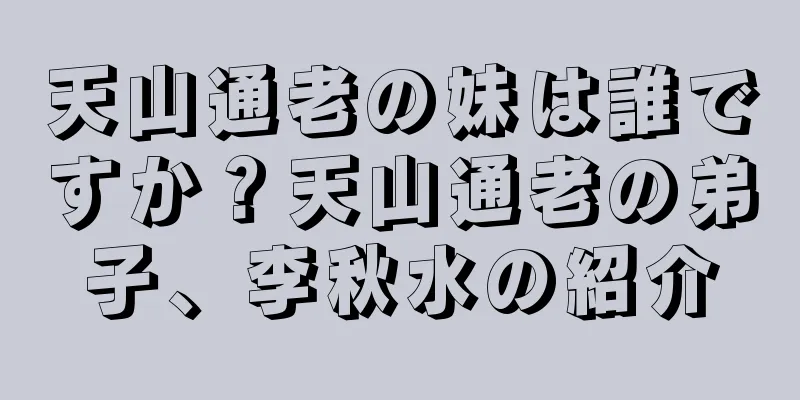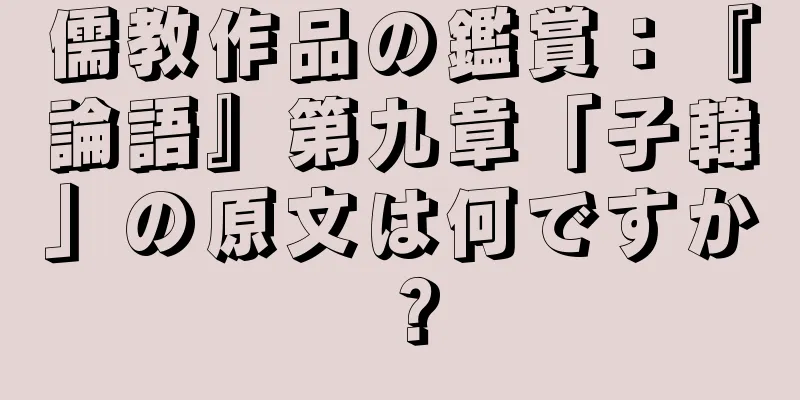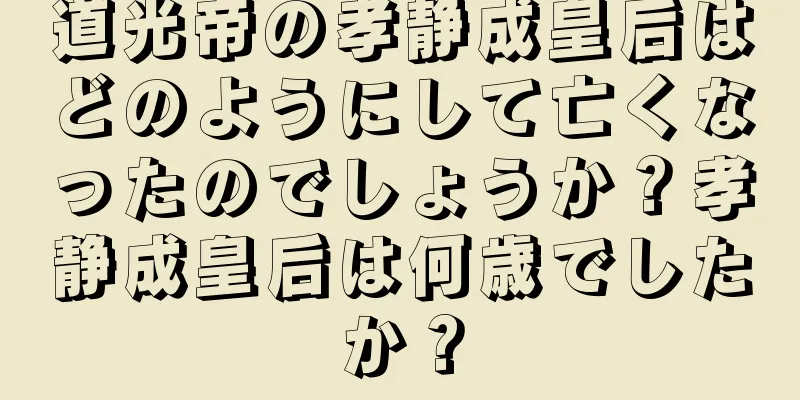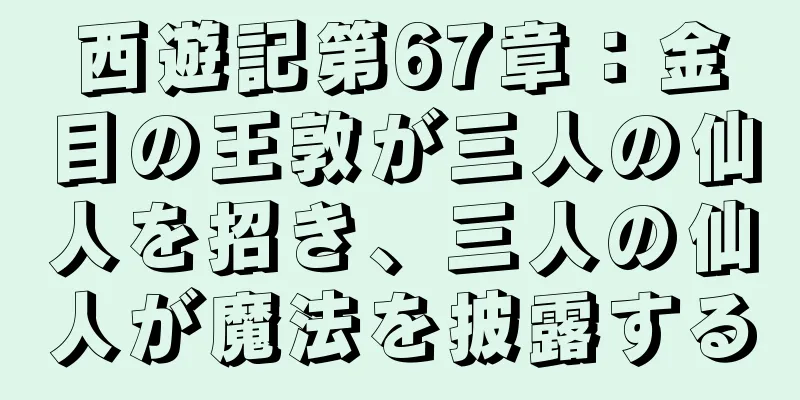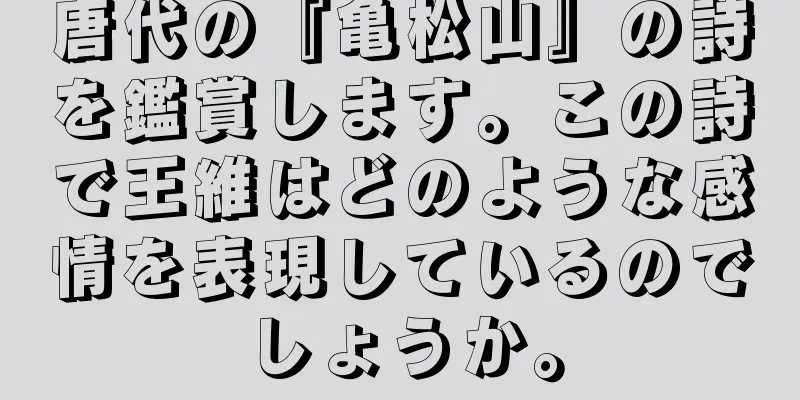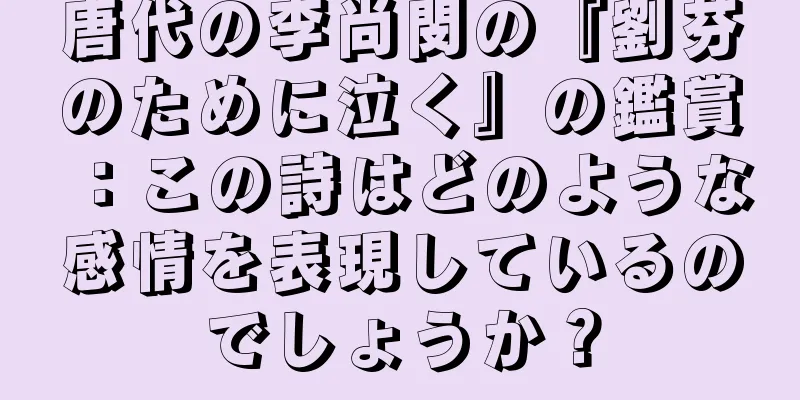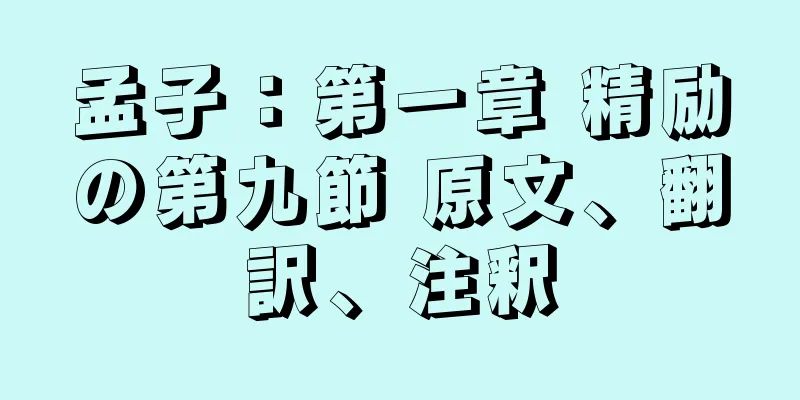貴族の衰退に伴い、隋の文帝はどのような官選制度を確立したのでしょうか。
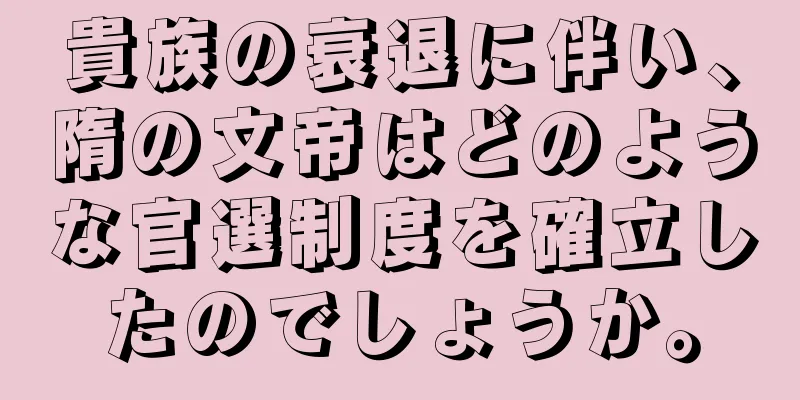
|
科挙制度は南北朝時代に始まり、唐代に本格的に形作られました。貴族の衰退と平民の地主の台頭により、魏晋の時代から続いてきた、官吏の選任において家柄を重視した九位制度はもはや継続できなくなった。隋の文帝は九階制を廃止した。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 大業二年(606年)、楊広は壬氏を増補した。当時、学者は戦略を、進士は時事問題を、明経は古典の知識をテストされ、科目別に人材を選抜する完全な国家制度が形成されていました。当時、明静は最上級の試験であり、壬氏は2番目でした。当時の学者を選抜する制度は単に「秀才」と呼ばれており、唐代の科挙とは多少異なっていました。楊広は進士試験を初めて設立し、科挙制度を定義しました。これは中国の歴史に広範囲にわたる影響を与えた極めて重要な出来事でした。当時の進士試験は主に政治論文に重点が置かれ、「優れた文才」を持つ人材を選抜した。 『同典』によれば、楊光は文学的才能よりも人格を重視したという。煬帝の治世中に、科挙の受験者数が増加した。大業三年(607年)には、すでに試験科目は10科目ありました。これにより科挙制度が誕生した。大業3年(607年)、楊広は勅令を出した。「文武の職に就き、孝行と年長者を敬う心を持ち、品行方正で、清廉で、品行方正で、法を遵守し、学問に優れ、文才に優れ、軍略に長け、腰が強く手足が丈夫な者を10の部類に選抜する。」大業5年(609年)、楊広は別の勅令を出した。「学問に精通し、才能と技能に優れ、腰が強く人より優れ、職務に精励し、政務を執り行い、品性が高く、権力者を遠慮しない者を4の部類に選抜する。」 しかし、隋代が進士制度と科挙を創設したかどうかについては、常に論争があった。薛登、楊万、杜有、劉素らは、「煬帝が最初に進士制度を制定した」と繰り返し主張している。陳志は、1902年に洛陽で発掘された「隋代北帝陳思道の墓碑」に基づき、進士制度は大業元年に始まったと考えている。隋の文帝と煬帝の勅令によると、隋の時代は依然として五位以上の官吏が候補者を推薦する必要があり、庶民が「願書を提出して参加する」ことは認められなかった。科挙制度の本質と主な特徴は備えておらず、依然として推薦制度であり、本質的には漢時代の推薦制度と同じであった。 原則として、学者は大臣や郡役人からの特別な推薦を受ける必要はなく、自分で科挙の願書を提出することが許されていました。これが科挙制度の最も重要な特徴であり、推薦制度との最も根本的な違いでもある。出世願を提出する制度や試験による罷免制度は南北朝末期にすでに兆候が見られたが、正式に登場したのは唐代になってからである。隋代に九階制は廃止されたが、その本質は依然として推薦制度であった。詳しくは科挙制度を研究した歴史家何忠礼の『科挙制度の起源分析 ―唐代進士制度の発祥についても』や金徴の『科挙制度と中国文化』を参照。 于大剛、唐長如、何忠礼、金徴などの歴史家は、科挙制度が唐代に初めて確立されたと考えています。何鍾礼は、隋代にはまだ推薦制度が実施されており、進士試験も唐代に始まったと信じていた。于大剛は隋代に進士試験が確立されたことにかなり懐疑的だった。彼はこう言った。「科挙の受験者を選ぶ方法が完全な試験制度だと言うなら、漢代に遡るべきだ。朝廷が受験者を選ぶために試験を開設し、学者が自分で書類を提出して受験したと言うなら、それは唐代の始まりであるべきだ。隋代に始まり、唐代に完成したとは言えない。」 学者が「自験願を提出する」ことが科挙制度の起源の主な象徴であるというのは、非常に貴重な知見である。唐昌如も于大剛と似た見解を唱え、唐代の科挙制度の重要な特徴は「資格証書を持って独学で科挙を受けることができるかどうか」であると考えていた。南北朝末期には、学者が「資格証書を持って独学で科挙を受ける」という個別の事例があり、当時の科挙制度がまだ未成熟であったことを反映している。何鍾礼は、封建社会全体の科挙制度を検討した結果、基本的に次の3つの特徴にまとめられると提唱した。「第一に、学者は原則として『推薦書を提出する』ことができ、大臣や県官から特別に推薦される必要はない。これが科挙制度の最も重要な特徴であり、推薦制度との最も根本的な違いである。第二に、『すべては試験問題で決まる』。言い換えれば、候補者の合否は厳格な試験によって決定されなければならない。第三に、進士科目が学者を選抜する主な科目であり、学者は定期的に試験を受ける。」多面的な議論を通じて、彼は、上記の「推薦書を提出する」という特徴と試験および罷免制度は南北朝末期にすでに兆候を示していたが、正式に現れたのは唐代であると考えている。隋代に九級制度は廃止されたが、推薦制度は依然として実施されていた。 |
<<: 腐敗した清朝全体と比べて、なぜ康熙帝と乾隆帝の統治は比較的強固だったのでしょうか?
>>: 多くの人々の印象では、明代末期の東林党はどのような団体だったのでしょうか?
推薦する
張遼の生涯でどんな大きな戦いが起こりましたか? 『三国志 張遼伝』はどのように記録されているのでしょうか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting Historyの編集者が張遼の生涯に...
バイカル湖はどこですか?バイカル湖に海洋生物がいるのはなぜですか?
バイカル湖は世界最大の淡水湖です。この淡水湖には多くの生物が生息しています。不思議なのは、この淡水湖...
『紅楼夢』では、賈家の百年物の高麗人参が腐った木に変わってしまいました。これを書く意味は何でしょうか?
賈家は名門公爵邸であり、一家に二人の公爵がいます。以下の記事はInteresting History...
『紅楼夢』では、馮忌は幼くして生まれました。その理由は何でしょうか?
『紅楼夢』を読んでいると、多くの人が王希峰に感銘を受けます。なぜなら、彼女は栄果屋敷の家政婦であり、...
王安石の「漁夫の誇り:千の山々に囲まれた平らな岸にある小さな橋」鑑賞
「漁師の誇り:何千もの山々に囲まれた平らな海岸に架かる小さな橋」時代: 宋代 著者: 王安石平らな川...
『紅楼夢』の妙玉はなぜ金陵十二美女の中に挙げられているのでしょうか?
苗嶼は『紅楼夢』にはあまり登場せず、賈家の一員でもないのに、なぜ金陵十二美女に数えられるのでしょうか...
墨子・第49章 陸からの質問(4)原文の内容は何ですか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
『墨子』は戦国時代の哲学書で、墨子の弟子や後世の弟子たちによって記録、整理、編纂されたと一般に考えら...
『江神子:于樹良に贈る梅花頌』の作者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
蒋申子:梅花詩と于淑良への手紙新奇集(宋代)ほのかな香りが漂い、道沿いに雪が降っています。夕方の風が...
コーヒーの起源 歴史上コーヒーの起源に関するいくつかの伝説
コーヒーの起源:コーヒーという言葉はどこから来たのでしょうか? コーヒーに似た発音を持つエチオピアの...
チュングアンの立場は?何に対して責任があるのですか?
春官の地位は何か?彼は何を担当しているの?春官は、宗伯という古代の官吏の名前で、荘勒時代の五官の一人...
『紅楼夢』で黛玉が肉をほとんど食べないのはなぜですか?食べちゃダメですか?
『紅楼夢』のヒロインである黛玉は、金陵十二美女本編の二人の名の中の一人です。彼女についてあまり知らな...
『紅楼夢』の王希峰はどうやって良い手を台無しにしたのですか?
王希峰は『紅楼夢』の登場人物。賈家の馮姐、または廉夫人としてよく知られている。非常に興味がある方のた...
「神の叙任」というテーマを探求すると、多くの場所で宿命論的な見方が示される
『冊封神』は、通称『冊封神』とも呼ばれ、『商周全史』『武王周征伐秘史』『冊封神』などとも呼ばれ、明代...
岑申の詩「閻河南中城に初桑郵便局で会って別れを告げて幸せ」の本来の意味を鑑賞
古代詩:「閻河南中城に初桑郵便局で会って別れを告げてうれしかった」時代: 唐代著者: セン・シェン4...
キッチン神様の本来の名前は何ですか?不死者になるにはどうすればいいですか?
周知のように、古代、どの台所にも「台所の神」を祀る祭壇がありました。では、台所の神の本来の名前は何だ...