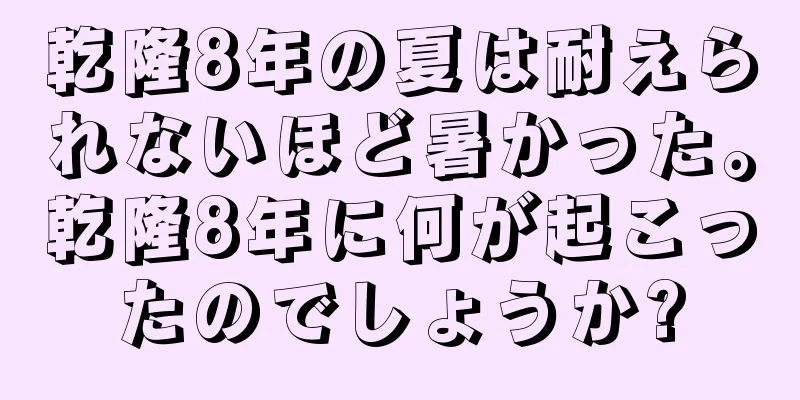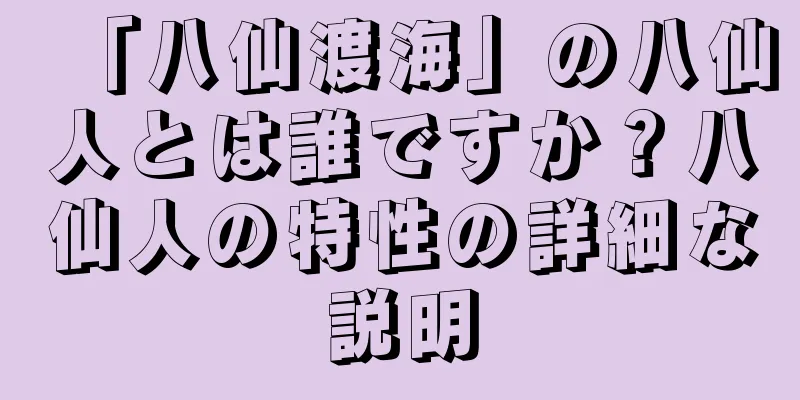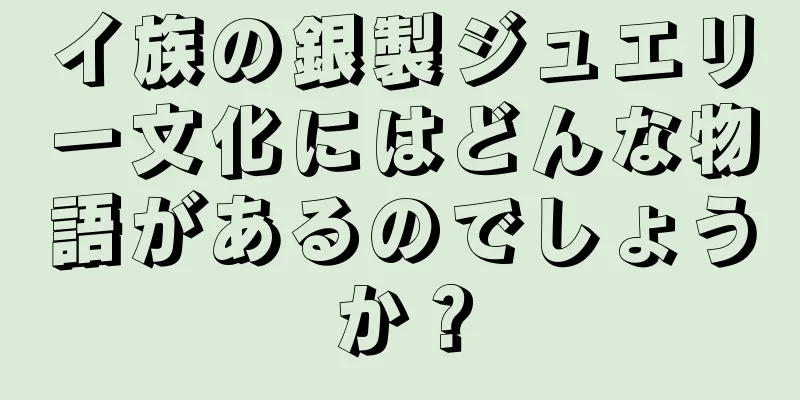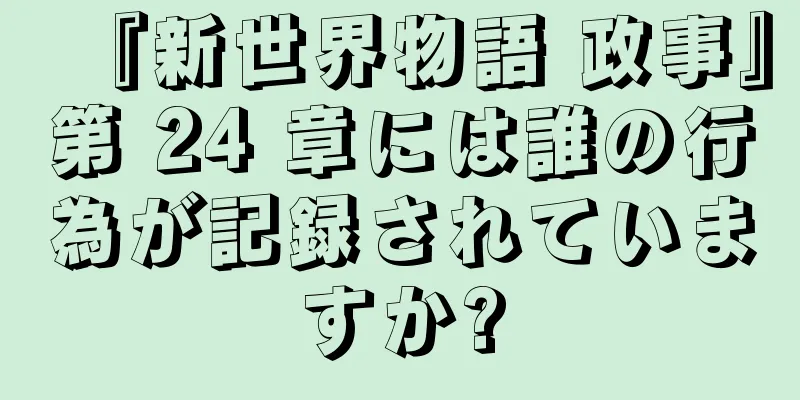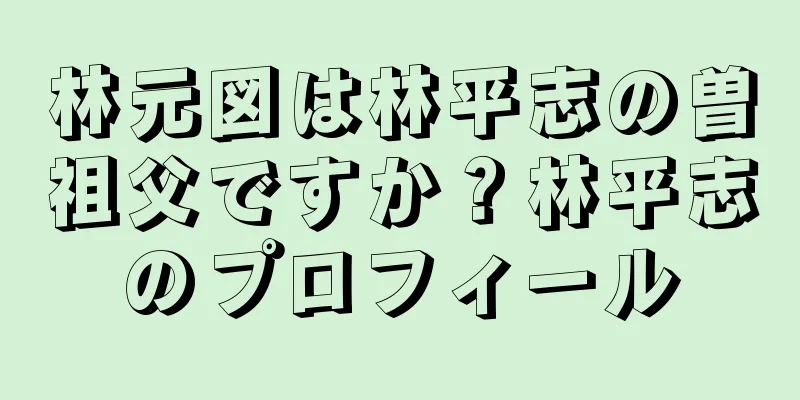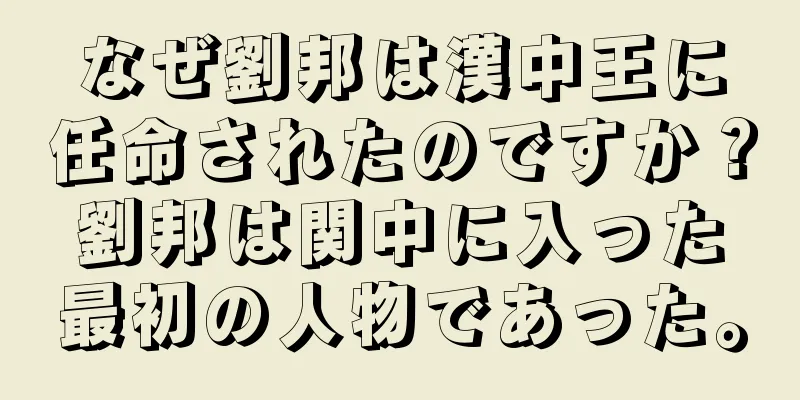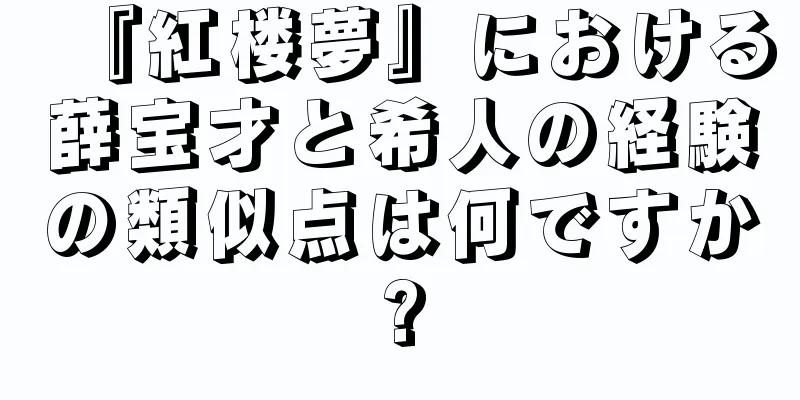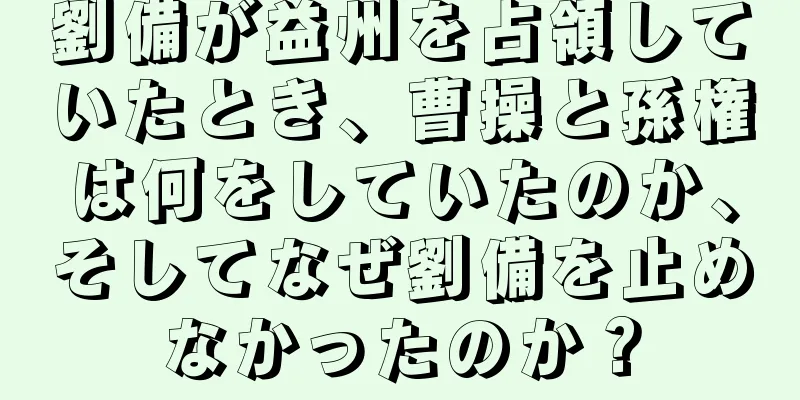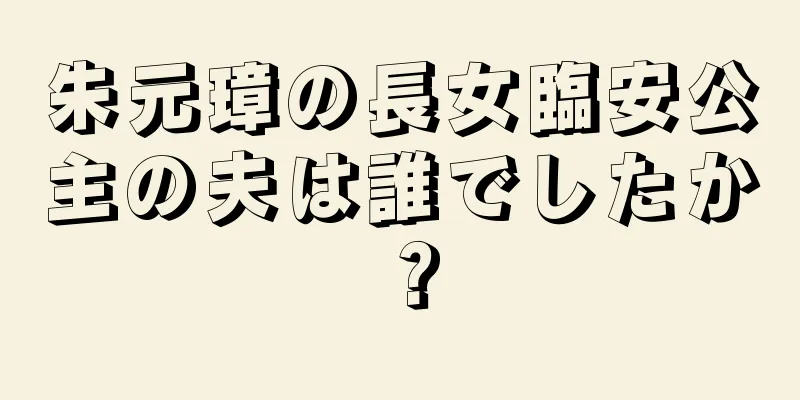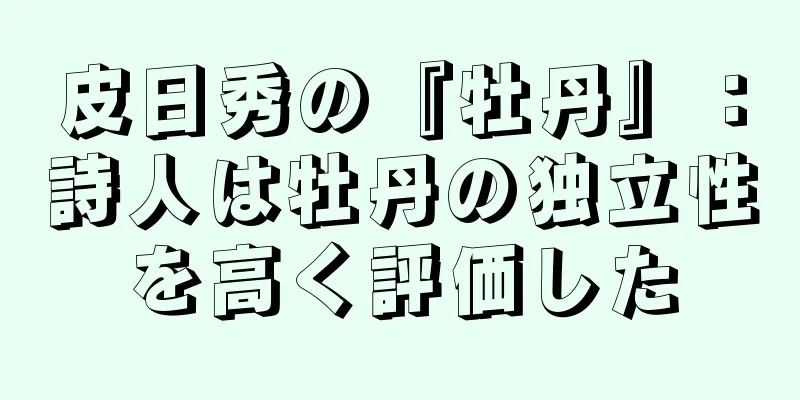なぜほとんどの慣用句は 4 つの文字で構成されているのでしょうか?これについて古代史書にはどのような記録が残っているのでしょうか?
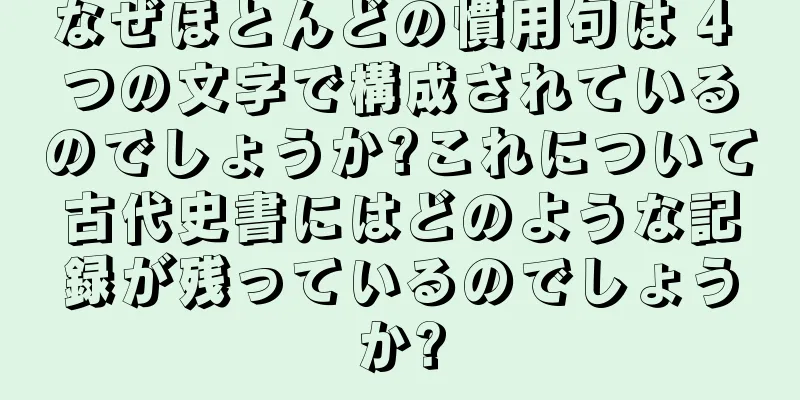
|
慣用句とは、一般的に使用され、意味の整合性と構造の堅固さを備えた特別な定型句です。字数から判断すると、ほとんどの慣用句は4字ですが、「莫须有」や「落水狗」のように3字、「小巫见大巫」や「世の中何も難しいことはない」のように5字、「已来,才会让自己」や「5步步才哈法」のように6字、「暴天下之大不去」や「これは堪え難い、堪え難いことは何もない」のように7字、「桃梅勿言,三人成弟」のように8字、9字、10字、さらには10字を超えるものもあります。成語は簡潔で意味が豊かです。適切に使用すれば、言語を簡潔にし、修辞効果を高めることができます。慣用句を正確に使うには、慣用句の意味を正しく理解し、把握する必要があります。 次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! なぜ慣用句のほとんどは 4 文字で構成されているのでしょうか。これはおそらく、4 文字の方が覚えやすいからでしょう。例えば、中国の古代詩集『詩経』は主に四字熟語で構成されており、古代の歴史書『史記』にも四字熟語がいくつか含まれています。その後、初心者は3、100、1000の『三字経』、『百姓姓』、『千字経』を読みます。最後の2つはすべて4文字の文章です。 『四字熟語雑集』第1巻、第2巻、第3巻と『龍柄鞭影』はいずれも4字入りです。子ども向けの教科書ではありますが、四字熟語が人々に愛され、楽しまれていることがよくわかります。前述のように、ほとんどの慣用句は4文字で構成されています。4文字未満または4文字を超える慣用句は比較的まれです。特に、4文字未満の慣用句は比較的まれです。そのため、日本人が中国語を話すときには「四字熟語」(吉田昇他編『中学校現代中国語』1978年版参照)という用語があり、また「四字熟語」(今泉忠義他編『中学校中国語』1978年版参照)と呼ぶ人もいる。しかし、「四字熟語」や「四字熟語」に収録されている例文の中には、私たちが熟語と呼ぶものではないものもあります。なぜなら、そのような表現は存在しないからです。 「左から右へ」、「上から下への命令」、「実行の躊躇」、「質問と応答」など。例えば、「春夏秋冬」「前後左右」「東西南北」を「四字熟語」とみなすが、私たちはこれに同意しない。 「春夏秋冬」は気象用語、「前・後・左・右」は日常生活でよく使われる方向名詞、「東・西・南・北」は地理でよく使われる方向名詞です。 それにもかかわらず、この慣用句が明らかに四文字語であることは否定できない。例えば、次の熟語は、語源から判断すると四字熟語ではありません。つまり、これらの熟語はすべて、四字熟語ではない言葉を改良した四字熟語です。次の熟語と語源の関係を見てみましょう。 (1)最も小さな細部まで見ることができること:「髪の毛の先は見えるが、薪の切れ端は見えない」(『孟子』第一部、梁恵王) (2)魚を捕まえるために木に登る:「自分のしたいことをするのは、魚を捕まえるために木に登るようなものだ」(孟子『梁慧王』第1部) (3)半分の努力で2倍の成果を上げる:「今の時代に、1万台の戦車を持つ国が仁を行えば、人々は逆さ吊りから救われたかのように喜ぶ。昔の人々の例に従えば、2倍の成果が得られるだろうが、これは今のことである」(孟子『公孫經』第1部) (4) 船に刻みをつけて剣を探す:「楚の男が川を渡っていたとき、船から剣が水に落ちた。彼はすぐに船に印を刻み、「ここに私の剣が落ちた」と言った。船は止まり、彼は印から剣を探すために水の中に入った。船は動いていたが、剣は動いていなかった。このように剣を探すのは、少し混乱しませんか?」(呂氏春秋、茶進) (5)貴州のロバは芸が尽きた:唐代に劉宗元が「三つの芸」という記事を書いたが、その中に「貴州のロバ」という副題がある。 「貴州のロバは芸が尽きた」は、この記事で語られている物語からの抜粋です。 (6) 古ぼけたほうきは金貨千枚の価値がある: (または「古ぼけたほうきは金貨千枚の価値がある」) 「村にはこんな諺がある。家に古ぼけたほうきがあれば、金貨千枚の価値を持つだろう。気づかないことの弊害だ。」(曹丕『古典随筆』) 以上のことから、この熟語の四字熟語としての性質が非常に明白であることがわかります。または、「秋の細部に目を光らせておく」や「木の上の魚を探す」など、4 文字を超える単語を 4 文字に短縮したり、「半分の労力で 2 倍の結果を得る」や「私のお金は 1,000 ゴールドの価値がある」など、2 つの文を 4 文字だけを使用して 1 つに結合したりします。あるいは、「船を彫って剣を探す」や「貴州のロバは芸が尽きた」のように、多くの単語を使った物語を4文字にまとめると慣用句になることもあります。 古代人の言葉の中には、格言と呼ぶにふさわしいものや慣用句になるものもあります。ただ、4つの単語にするのはかなり面倒なので、あきらめて導入語として使うしかありません。例えば、宋代の范仲厳の『岳陽楼碑』には、「自分のことを心配する前に世間を心配し、自分のことを喜んだ後に世間を喜ぶ」という言葉があります。意味は非常に良いのですが、文字数が多いため、慣用句にはなっていません。格言として捉え、時々記事に紹介することしかできません。しかし、例えば「まずは苦しみ、後で楽しむ」は言いやすく覚えやすいので、慣用句になることもあります。岳陽塔碑文の「百废俱兴」という文は4文字で構成されているため、慣用句になっています。 |
<<: 「チェス」は「中国将棋」とも呼ばれますが、なぜその原型は戦国時代の「六博ゲーム」なのでしょうか?
>>: なぜ羊肉を食べることが宋代の王族全体の「家訓」となったのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』に登場する乳母の中で最も有名なのは誰ですか?それらの違いはどれくらい大きいのでしょうか?
『紅楼夢』では、乳母の仕事は賈家の女主人の子供たちに食事を与えることです。次に、『Interesti...
唐代の李和による項羽への評価、この詩の本来の内容は何ですか?
項羽【唐代】李何、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!竹は千年不滅であり、...
公孫瓚はもともと北方で最も強力な王子の一人でしたが、なぜ袁紹に敗れたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
東周書紀第79章:桂女楽里密が孔子を妨害し、会稽の文忠が宰相と通達する
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...
龍舒虎は神の一覧には載っていないのに、なぜ神格化されたのでしょうか?
授神戦が終わった後、まず授神台を築き、授神名簿の候補者に一人ずつ神の称号を授けていきます。功績や不功...
前漢の七国の反乱を鎮圧したのは誰ですか?
前漢の「七国の反乱」を鎮圧した将軍は周亜夫です。紀元前154年、漢の景帝の治世3年目に、武王劉備は楚...
拓跋世義堅には何人の妻がいましたか?拓跋世義堅の妻は誰でしたか?
拓跋世義堅(320年 - 377年)は鮮卑族で、平文帝の拓跋涛の次男、列帝の拓跋淮の弟である。十六国...
西遊記の二郎神と孫悟空はどれくらい強いですか?どちらが優れているでしょうか?
『西遊記』は中国の四大古典小説の一つであり、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
唐伯虎の絵画の価値はどれくらいですか?唐伯虎の真作の価値はどれくらいでしょうか?
唐伯虎の絵画は現在どれくらいの価値があるのでしょうか?唐寅(1470-1523)は、伯虎、子維とも呼...
「ボールを投げる音楽:夜明けの天気の変化」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
ボール投げ音楽·夜明けの天気劉勇(宋代)朝は曇りで小雨が降っていました。清明節の近くの池に柳の枝垂れ...
太平広記・巻98・奇僧・星源尚作の原作の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
李玉と小周侯のラブストーリー 李玉が小周侯に書いた歌詞
リー・ユー・シャオ・ジョウ・ホウ南唐の最後の皇帝である李郁は歴史上有名な詩人でした。彼は生涯を通じて...
「彭公安」第182章:竹城を突破した英雄が虎穴に入り、龍のローブを盗んだ。
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
周密の『耀華人・竹店報勲』:物を描くことで政治を風刺した詩
周密(1232-1298または1308)は、号を公瑾といい、曹荘、小寨、平州、小寨とも呼ばれた。晩年...
五荘寺の土地神は、高麗人参の果実の最大の秘密を明かしたと何と言ったのでしょうか?
『西遊記』の物語の中で、高麗人参の実が長寿の実である理由は、五荘寺の土壌に関係しています。では、五荘...