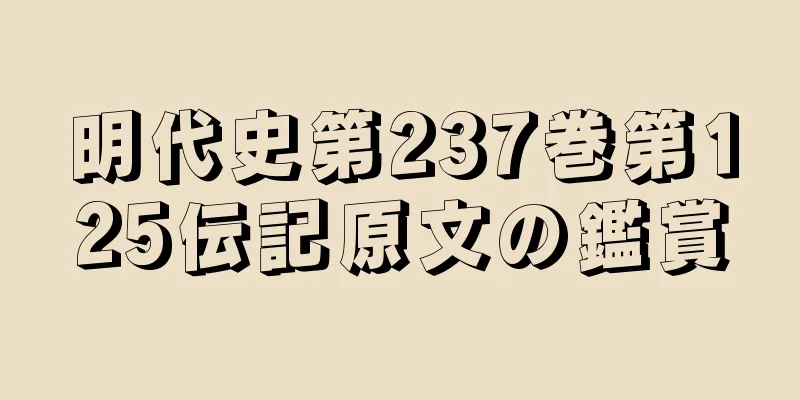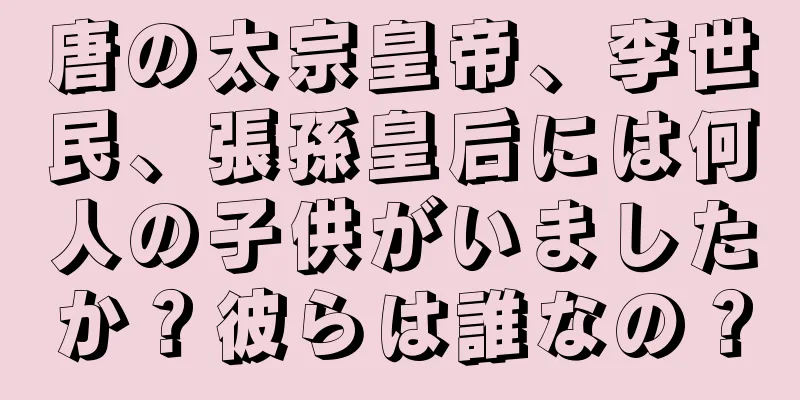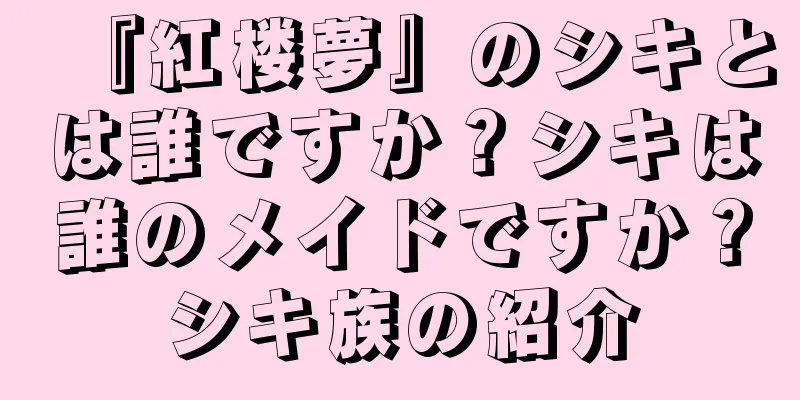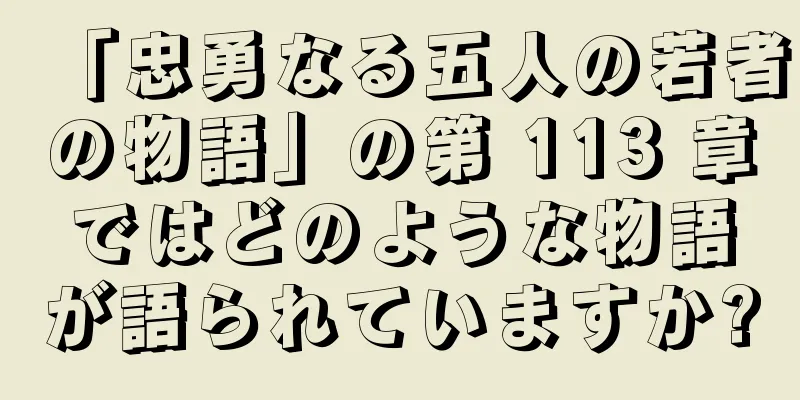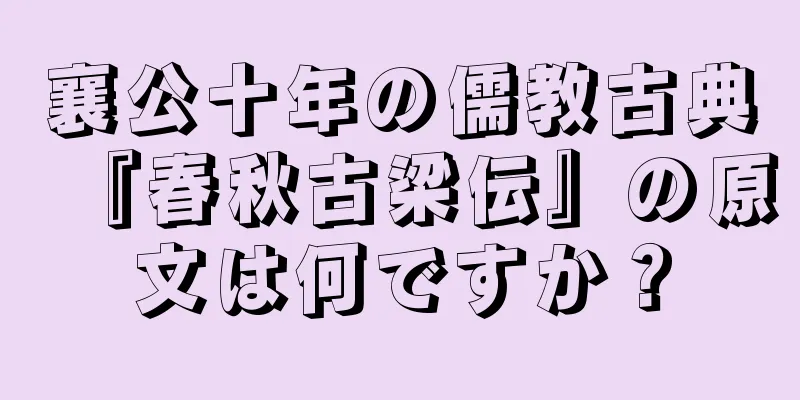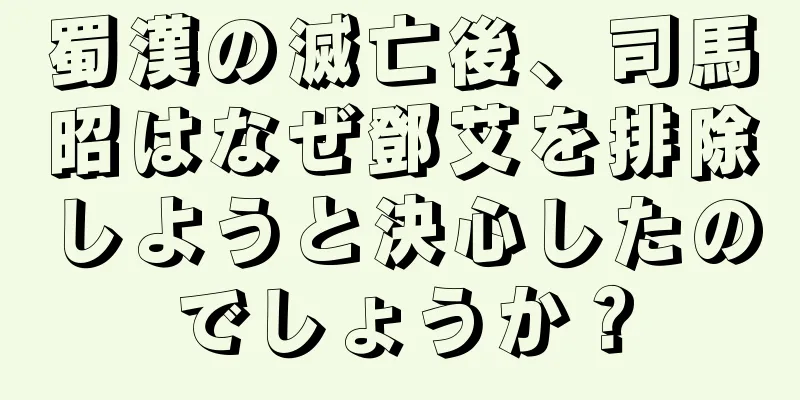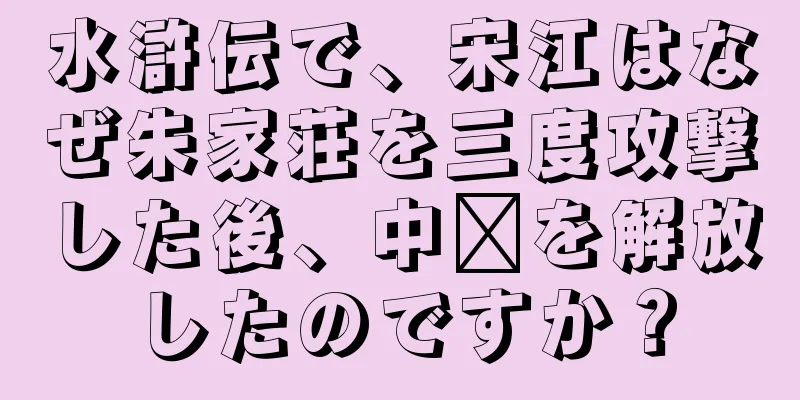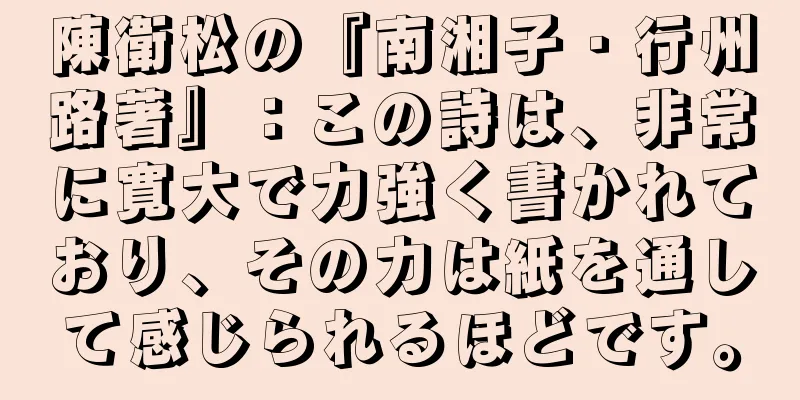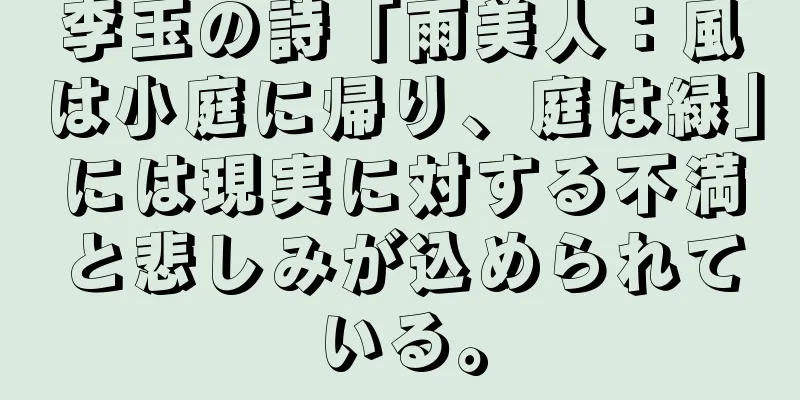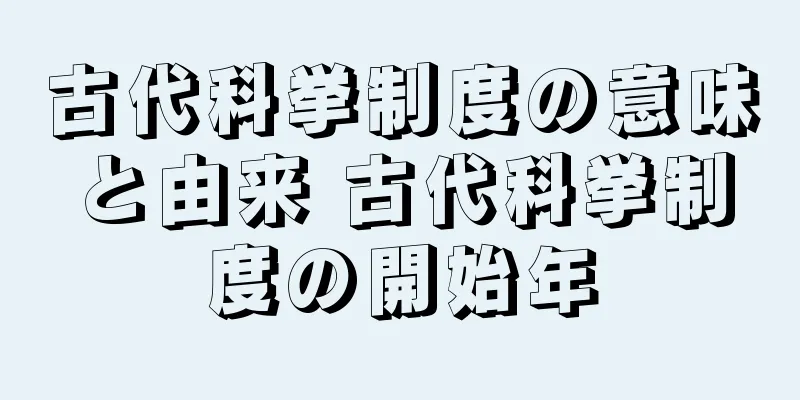白馬の戦いで、勇敢な将軍文殊は関羽に簡単に殺されてしまったのでしょうか?
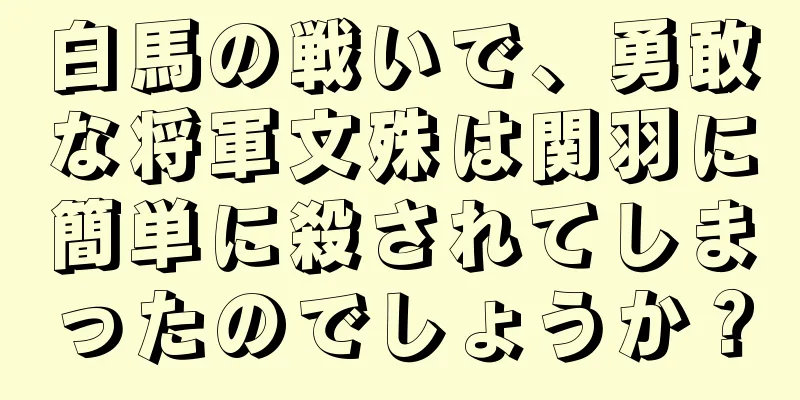
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、なぜ文殊と趙雲が引き分けになったにもかかわらず、関羽に殺されたのかを詳しく紹介します。見てみましょう! 顔良と文秀は袁紹が最も頼りにしていた将軍であり、袁紹はこの二人を非常に信頼し、よく褒めていました。この二人は袁紹の期待に応え、戦場で大きな貢献を果たした。文州と公孫瓚が盤江の戦いで戦った際、彼は単独で敵陣に突撃し、公孫瓚を追い詰めた。もし趙雲が間に合わなかったら、公孫瓚は文愁の手で殺されていただろう。しかし、この勇敢な将軍は白馬の戦いでわずか3ラウンドで関羽に殺されました。何が起こったのでしょうか? 1. 文殊、趙雲、関羽の戦い。 潘河の戦いでは文殊と趙雲の戦いが起こった。この戦いで、公孫瓚は兄の仇討ちをするために袁紹を攻撃した。公孫瓚の主力は、彼が長年かけて集めた「白馬義勇隊」として知られる精鋭騎兵隊だった。しかし、この戦いで公孫瓚は袁紹軍の頑強な抵抗に遭遇し、連続して敗北を喫した。 戦いの初日、文周は公孫瓚に決闘を挑んだ。文周と公孫瓚は10ラウンド以上戦い、その後文周は公孫瓚を慌てて逃げさせた。当時虎牢関の前では公孫瓚と呂布が数ラウンド戦って敗れており、武術の腕が低い人物ではなかった。これは文周の武術が並外れていることを示しています。 その後、文周は公孫瓚を戦列の最後尾まで追い詰め、救出に来た敵将を殺害し、公孫瓚が馬から落ちて死ぬまで激しく追いかけた。この危機的な瞬間に、若い趙雲が到着し、文周と戦い、公孫瓚を救出しました。趙雲と文周は50、60ラウンド戦ったが、明確な勝者は出なかった。公孫瓚の援軍が到着し、文周は逃げることができた。 しかし、公孫瓚の軍隊の中で自由に動き回れるこのような勇敢な将軍は、白馬の戦いで関羽に簡単に殺されてしまいました。当時、顔良は曹操と戦っており、単身敵陣に突入した関羽に殺された。顔良の仇討ちをするために、文秀は軍を率いて再び曹操を攻撃した。曹操との戦いの最中、袁の軍は曹操の罠に陥り、曹操軍の待ち伏せを受けて混乱を引き起こした。 文周はこの時もまだ勇敢さを見せていた。彼は敗北した元軍の中で立ち上がり、一人で戦った。これを見た曹操は張遼と徐晃を派遣して文愁と戦わせた。文周は張遼に矢を放ち、一矢は兜に当たり、もう一矢は馬の顔に当たった。その結果、張遼は失脚し、文周に追われることになった。危機的な瞬間、徐晃は突進して文周と戦い、張遼を救出した。 しかし、袁俊は混乱から立ち直り、再び急いで戻ってきた。徐晃は抵抗できないと見て、馬を向けて引き返した。この時、関羽は12人の兵を率いて文周と戦った。文殊と関羽は3ラウンドも戦わず、文殊は馬を向けて川の周りを逃げたが、関羽に追いつかれ、頭の後ろから一撃を受けて馬から落とされた。 2. なぜ文殊は関羽の手で簡単に死んだのですか? 関羽が顔良を殺したのは策略だったと多くの人が信じている。関羽が袁の軍に突入したとき、顔良は関羽の意図に気づかず、関羽の降伏によって殺されたと信じる者もいる。しかし、関羽と文殊の戦いは比較的公平なものでした。両軍は前線の戦場で戦っていた。しかし、とても勇敢で、若い趙雲と引き分けまで戦えた文周が、なぜ関羽にわずか3ラウンドで殺されたのでしょうか? 実際、今回の文周の殺害は、顔良の殺害と似ていた。彼らの戦闘での死は、関羽の武術、勇気、そして戦場の観察力を十分に証明した。この二度の斬首作戦において、関羽は自身の専門知識をフル活用し、予想外の結果を達成した。 関羽の武術の特徴は、速い馬と鋭い剣です。曹操から赤兎馬を受け取った後、関羽は素早く行動する能力を獲得しました。関羽の緑龍三日月刀の重さは83ポンド。この種の剣は、古代武器カタログでは、強力な力で頭を切り落とす能力があり、破壊不可能であると評価されています。そのため、関羽は敵の陣形を突破する優れた能力を持っています。 この能力は古代の戦争において非常に重要でした。古代の軍隊は陣形に細心の注意を払っていたため、指揮を執るのが難しく、陣形が崩れると敗北は避けられませんでした。敵の突撃部隊が陣形を組んで突撃と殺害を繰り返すと、簡単に混乱が生じて崩壊する。このような例は古代の戦争のいたるところに見られる。 関羽は白馬の戦いでさらに一歩進み、戦場での攻撃能力を使って敵の将軍に狙いを定めました。敵の将軍が殺されれば、敵の軍勢に混乱が生じる可能性もあります。そのため、顔良と戦う際には単身敵陣に突入し、顔良を殺害し、袁軍に混乱を引き起こして惨敗を喫した。 関羽が文殊と戦っていたとき、顔良を殺すよりも文殊を殺すほうが簡単だった。なぜなら、関羽が顔良を殺したとき、彼が直面していたのは、士気が高く、軍の編成が厳格だった勝利した元軍だったからです。関羽が文殊を殺したとき、関羽は袁の軍が攻撃を受けて混乱状態にあったときに直面していた。文殊は将軍であったが、曹の軍と単独で戦った人物であった。 関羽が文殊を倒す過程で、関羽が戦いのリズムをしっかりと把握していたことがわかります。その時、張遼と徐晃は、袁軍の混乱と撤退、そして文周が単独で曹軍と戦っている機会を利用して、文周と戦い、その機会を利用しようとした。文周がこれほど優れた武術家であるとは誰も知らなかったが、彼は張遼の馬を撃ち落とし、徐晃と戦った。徐晃は文州の兵たちが再集結して文州を助けに戻ってくるのを見て、退却を始め、馬に乗って戻った。 しかし、徐晃が退却しようとしたまさにその時、関羽が突進し、文愁の戦いを止めた。この本には、文殊と関羽は3ラウンドも戦わず、臆病だったため文殊は馬を向けて川を迂回して逃げたと書かれている。実は、この時点では非常に微妙です。この短い期間に、戦況は何度も逆転しました。 最初の逆転は、曹操が荷物と馬を捨てて袁の軍を誘い出し、追撃させて戦利品を奪い取ろうとしたことでした。その後、曹操は奇襲を仕掛け、袁の軍に混乱を引き起こした。 2 度目の繰り返しは、文周が攻撃を受けた後も恐れることなく、再編成を試みるために単独で曹の軍と戦うために立ち上がったことです。 3 回目の繰り返しでは、曹操は張遼と徐晃を派遣して文州を攻撃したが、文州に撃退された。この時、袁の軍は攻撃の混乱から立ち直り、兵馬が戻ってきていた。 4 回目の繰り返しは、関羽が到着して文愁を殺害する場面です。 関羽が文殊を殺したとき、文殊の軍はちょうど士気を回復し、混乱から立ち直ったところだったことがわかります。この時、関羽は十数人の兵馬を率いて文州に急行したが、文州の背後の兵馬はまだ文州からかなり離れたところにいた。関羽が文殊をすぐに殺せなかったら、文殊の部下が到着したときに、関羽がもう一度彼を殺す機会を得るのは困難だろう。 文秀が曹操の軍に単独で立ち向かい、曹操の平凡な兵士や将軍、さらには張遼や徐晃と対峙したときも、文秀は冷静で恐れを知らぬ態度を保っていた。しかし、関羽とその部下十数人に包囲されると、彼は臆病になった。関羽が顔良を殺した将軍であることを知っていたからです。彼は昼夜を問わず顔良と共にいて、顔良の武術を知っていました。顔良の死は文殊に大きな精神的負担をもたらし、関羽との戦いで不利な立場に追いやった。 さらに、文周は一人で関羽とその十数人の部下と対峙しており、部下はたくさんいたものの、間に合うことはできなかった。このため、この重大な局面で文周は非常に不利な立場に立たされた。文殊と関羽が3ラウンド戦った後、彼の選択は徐晃と同じで、馬を方向転換して陣地へ逃げ帰ろうとした。時間を遅らせて軍隊の到着を待つために、文周は川を迂回する戦略も採用しました。 関羽はこの一瞬のチャンスを捉えた。関羽が一刻も早く文殊を殺さなければ、文殊が部下と出会った瞬間に戦況は想像もできないほど逆転してしまうだろう。そこで、関羽は赤兎馬のスピードの利点を生かして文殊に追いつき、彼を殺した。文周は死ぬまで、自分が関羽の手でどのように死んだのか理解していなかった。 結論: 白馬の戦いでは、関羽が単独で袁軍に突入し、袁の将軍である顔良を殺害し、袁軍に大敗を喫させた。袁紹は顔良の仇討ちをするために文殊を軍隊の指揮下に派遣し、曹操を攻撃させた。文殊が最初に曹操の軍隊誘引の罠に陥り、その後曹操との戦いで関羽に殺されたことを誰が知っていただろうか。 実際、関羽は一瞬のチャンスを捉えて文愁を殺したのです。その時、曹の軍が袁の軍を攻撃し、袁の軍は混乱して撤退し、文秀だけが単独で戦った。張遼と徐晃の後ろで、袁の軍は再編成し、文州に向かって突進した。この危機的な瞬間、関羽は12人の兵士を率いて文州に急行した。 当時、文秀は将軍であり、部下たちも遠く離れておらず、関羽を倒すこともできなかったため、撤退する心境になった。もし彼が部下と再会することができれば、戦いの流れを変えるチャンスが得られるだろう。残念なことに、関羽の赤兎馬は素早く追いついて彼を殺しました。文殊の斬首の過程は、関羽の武術、勇気、戦況に対する洞察力を十分に示していたと言える。関羽の卓越した軍事能力を考えると、文愁の死は避けられなかった。 |
<<: もし孫権と関羽が力を合わせて北の曹魏を攻撃したら、世界の状況はどうなるでしょうか?
>>: もし龐統が死ななかったら、劉備は本当に諺の言うとおり天下を平定できたのだろうか?
推薦する
東周時代の物語:五つの羊皮と百里熙
はじめに:その年(紀元前655年、周の恵王22年、斉の桓公31年、晋の献公22年、秦の穆公5年、楚の...
魏英武は『楊子を初めて出発する時に袁大小書に宛てた手紙』の中でどのような感情を表現したのでしょうか?
「楊子を初めて去る時、校長袁達に宛てた手紙」は、魏英武が広陵から洛陽に帰る途中に書かれたものです。袁...
白居易の古詩「夕暮に立つ」の本来の意味を理解する
古代詩「夕暮れに立つ」時代: 唐代著者: 白居易夕暮れ時、地面はイナゴの花で覆われ、木々にはセミがい...
二十四節気の一つ、冬至について学ぼう
冬至について知らない人も多いでしょう。Interesting Historyの編集者と一緒に冬至を味...
「晩桃花」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
遅咲きの桃の花池のそばの竹や松の木陰に、夕方になると赤い桃の木が咲きます。沈む太陽がなければ、それを...
北宋時代の詩人、何卓の「戊戊花:春は悲しい、春は終わりに近づいている」
以下、面白歴史編集長が何卓の『滴蓮花・季徐 春憂春暮帰』の原文と感想をお届けします。ご興味のある読者...
もし周瑜が諸葛亮に弓を1万本作れと頼んだら、諸葛亮はどのように答えるでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』で秦克清の家族がなぜこんなに早く滅んだのでしょうか?真実とは何でしょうか?
秦克清は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物で、寧国屋敷の賈容の妻である。次回は、Interestin...
水滸伝で桀珍はなぜ涼山に行ったのですか?彼にはどんな物語があるのでしょうか?
水滸伝で桀珍が涼山に行く理由の紹介桀震は『水滸伝』の登場人物であり、涼山賊団に強制的に加わらされた典...
明代には、知事は重要な行政機関となっていたが、組織的には依然として何らかの「外部任務」とみなされていた。
北京の検閲庁の事務を統括する左・右検閲長官、副検閲長官、准検閲長官に加え、検閲庁にはほぼ全面的な地方...
「滕王閣の詩」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
滕王閣の詩(1)王毓滕王の高い楼閣が川岸を見下ろし⑵、玉をつけた鳳凰は歌い踊るのをやめている⑶。朝に...
哲学書:墨子:第1章:学者との友情、原文、注釈、翻訳
『墨子』は戦国時代の哲学書で、墨子の弟子や後世の弟子たちによって記録、整理、編纂されたと一般に考えら...
「陸仔」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
ルー・チャイ王維(唐代)誰もいない山には誰もいないが、人々の声は聞こえる。反射した光は深い森に入り、...
古典文学の傑作「淘宝夢」:第3巻:朱文易のキンモクセイ科
『淘安夢』は明代の散文集である。明代の随筆家、張岱によって書かれた。この本は8巻から成り、明朝が滅亡...
『紅楼夢』で薛家がいつも賈家の屋敷に泊まったのはなぜですか?
『紅楼夢』に登場する四大家はいずれも親密な関係にある。次の『Interesting History』...