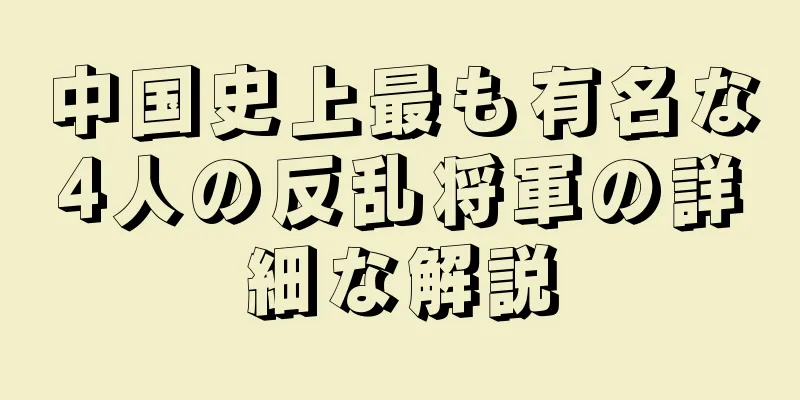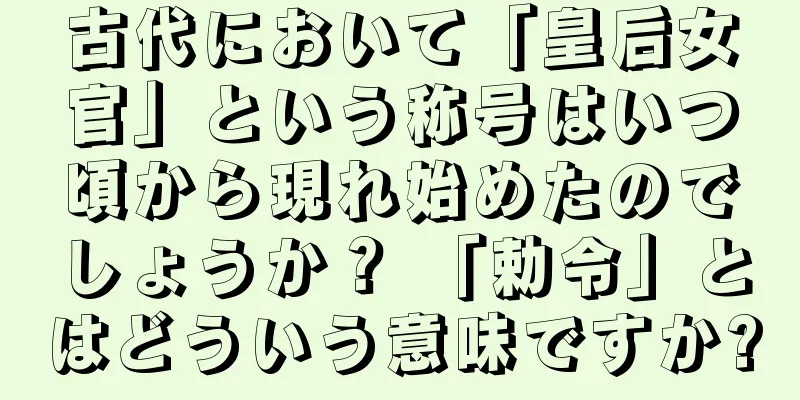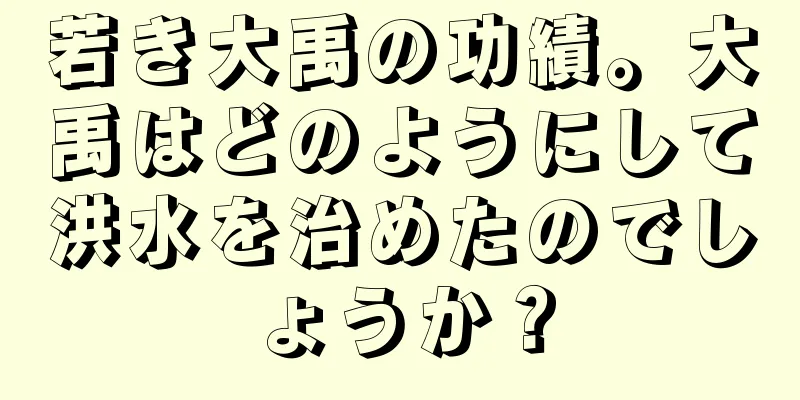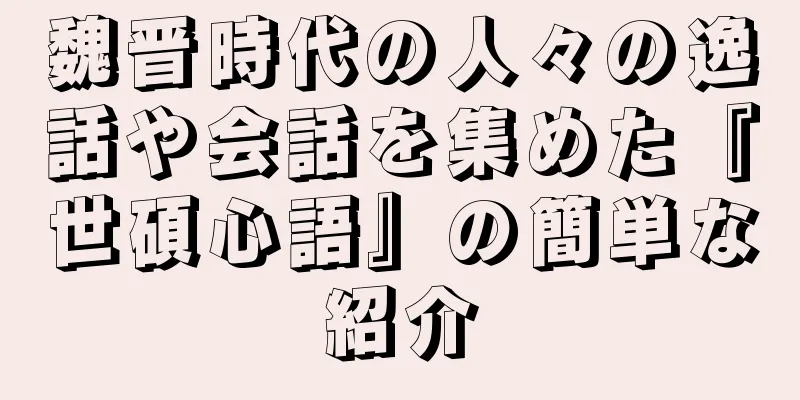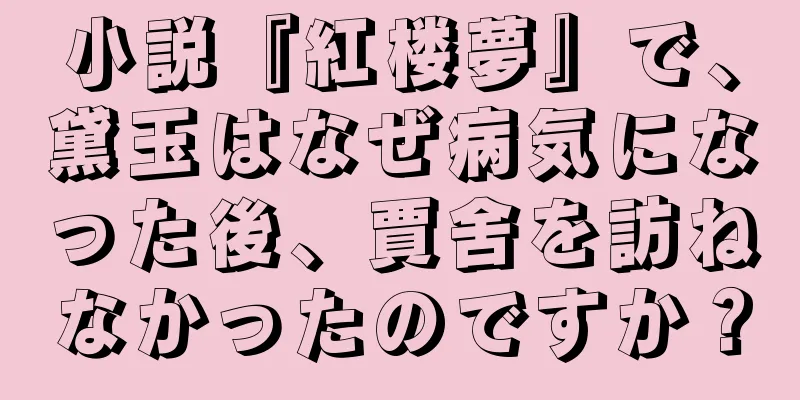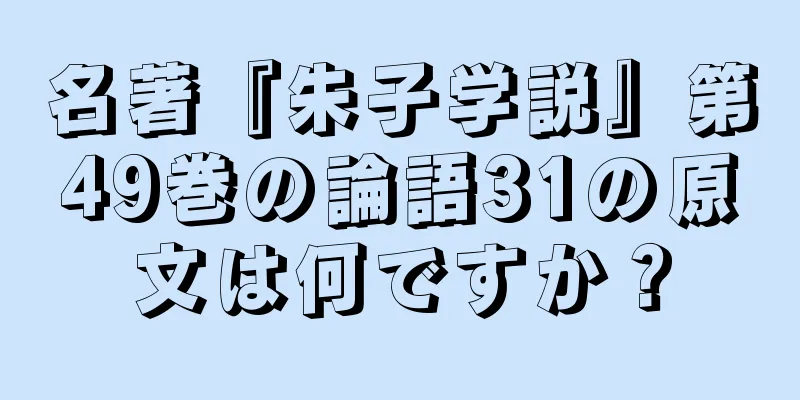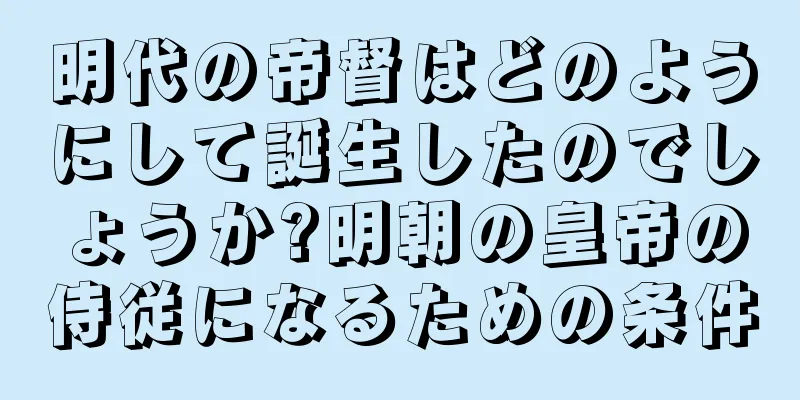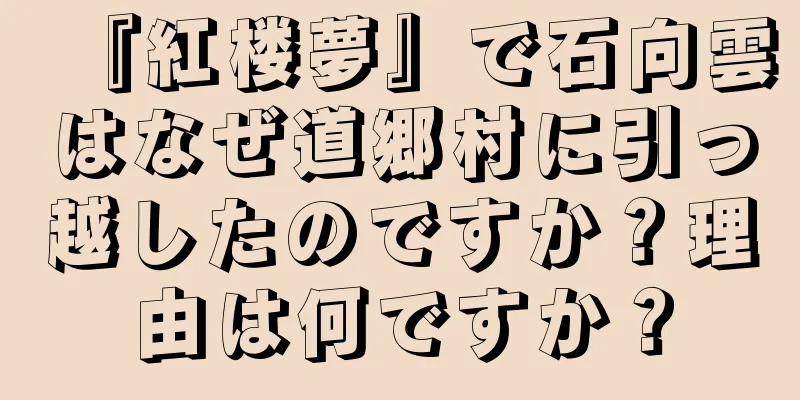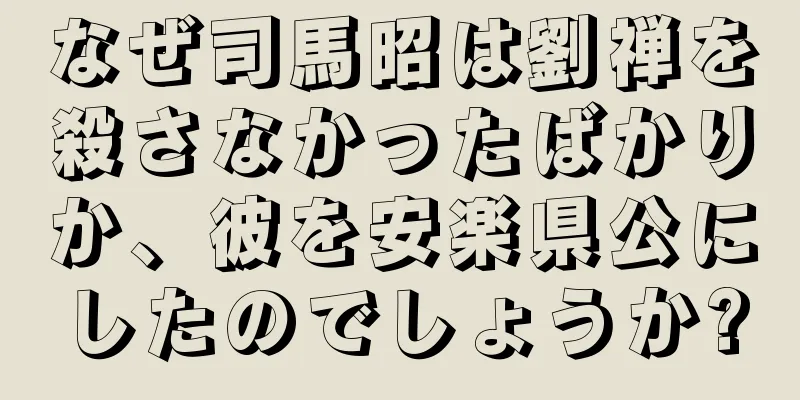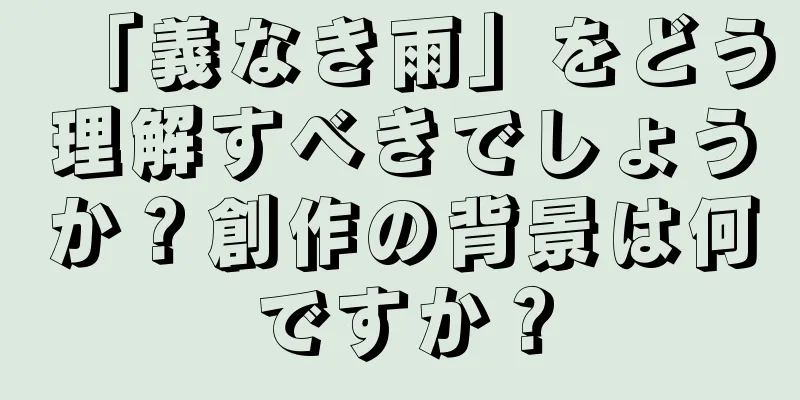諸葛亮の嫡子である諸葛瞻が、なぜ姜維をそれほど嫌っていたのでしょうか?
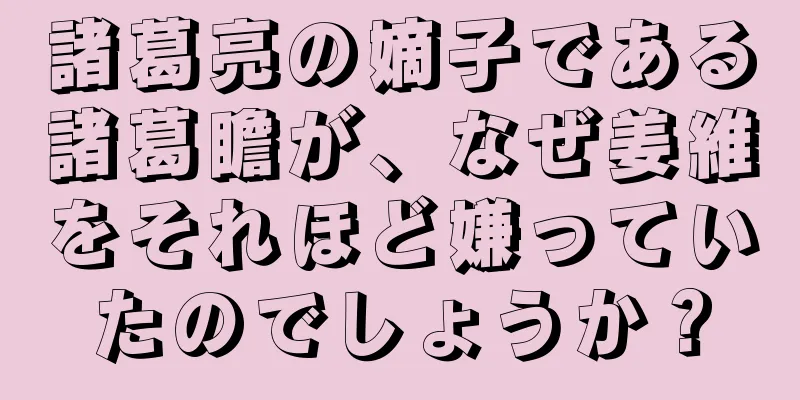
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が、諸葛瞻が蜀漢のために戦って死ぬ前に、内部で黄昊を排除できず、外部で姜維を抑えられなかったことを自ら責めた理由について詳しく紹介します。見てみましょう! 蜀漢の歴史において、姜維は最後の名将であった。費毅は在任中、北伐を決意し、軍を率いて曹魏を何度も攻撃した。費毅の死後、軍事力を掌握した姜維は、彼の意向に従って曹魏に対して大規模な攻撃を開始した。彼の攻撃は目的を達成しなかったものの、曹魏に大きな打撃を与えた。蜀漢が滅亡した後も、姜維は蜀漢政権の復活を企てて降伏を装った。さまざまな理由により、姜維は望みを果たせず、戦乱の混乱の中で亡くなりました。 諸葛瞻は諸葛亮の息子で、幼少の頃から聡明で、成長して劉禅の姫君と結婚した。当時の蜀漢の人々は諸葛亮を尊敬し、大いに称賛した。曹魏が蜀を滅ぼす戦争の際、姜維の主力は江閣線で鍾会に釘付けにされた。鄧艾はその機会を利用して軍を率いて銀平を抜け、江油を占領し、成都へと直行した。蜀漢の君主と大臣たちは、形勢を逆転させられることを期待して、諸葛瞻を蜀漢の最後の主力軍の指揮官に任命し、鄧艾と戦わせるしかなかった。 しかし、諸葛瞻は決断力がなく、軍を府城まで導いたところで進軍を止めた。その時、部下たちは、鄧艾に急いで進軍し、危険な地形を利用して鄧艾を封鎖し、平原に侵入させないように提案した。しかし諸葛瞻は動こうとせず、黄冲は不安のあまり泣き出してしまった。鄧艾はこの機会を利用してまっすぐに進軍し、諸葛瞻の先鋒を打ち破った。その後、両者は綿竹で決戦を繰り広げ、諸葛瞻は鄧艾と必死に戦ったが、結局は敗北した。諸葛瞻とその息子たち、その他は皆戦場で亡くなった。 『元河県地図』には、諸葛瞻が敗れたとき、「黄昊を討てず、姜維を統制せず、江游を守れず、三つの罪を犯した!」と他人に言ったという事件が記録されています。そして、最後の瞬間、諸葛瞻は江游を占領せず、戦略的地位に頼って敵を攻撃しなかったという敗北の原因を後悔しました。しかし、なぜ彼は黄昊と姜維に対してそれほど大きな憎しみを持っていたのでしょうか?黄昊は政界の混乱者だったので、名目上排除されました。姜維は諸葛亮の意志を継承し、北で戦うことを決意しました。なぜ諸葛瞻は彼をこのように扱ったのでしょうか? まず、この事件は正史には記載されていません。正史には諸葛瞻の息子である諸葛尚が言ったことしか記録されていません。その時、諸葛尚はため息をつきました。「父と子の恩義は大きいが、黄皓をもっと早く処刑しなかった。国を滅ぼし、民を滅ぼすようなことになっては、生きても意味がない」。諸葛尚はこう言うと、敵陣に突入し、戦死しました。諸葛尚の言葉から、父と子の争いの主な標的は依然として黄昊であり、姜維ではなかったことがわかります。 蒋琬と費毅の死後、劉禅が徐々に政権を握った。しかし、劉禅が権力を握った後、彼は誠実な大臣からの強力な監督を受けられなくなったため、徐々に道を誤った。その中で、劉禅の最大の失敗は、裏切り者の悪役である黄昊を任命したことだった。黄昊は劉禅の側近の宦官であった。劉禅の寵愛を得た後、国政に干渉し始め、蜀漢政権を混乱に陥れた。 当時、呉の使節薛は帰国後、蜀漢で見聞きしたことを次のように評した。「君主は自分の過ちを知らず、臣下は身を隠して処罰を逃れようとしています。朝廷では正直な言葉は聞かれず、野の民はみな青ざめています。ツバメやスズメが堂内に住み、子供や母親と一緒に楽しく過ごし、安全だと思っていると聞きました。突然、建物の屋根が崩れて燃えましたが、スズメやツバメは喜んでいて、差し迫った災難に気づいていません。これが彼の言いたいことでしょうか。」このことから、黄昊が蜀漢政権にもたらした害悪がわかります。 さらに、黄皓は姜維と対立しており、自分の取り巻きたちに将軍の地位を確保させたいとも考えていた。これを知った姜維は黄昊を排除しようとしたが失敗し、災難を避けるために蜀軍の主力を大中へ率いて麦を植え、農地を耕作し、漢中の防御門を開いた。姜維は曹魏が蜀を滅ぼす戦争を起こそうとしていることを知ると、劉禅に特に警告を発し、漢中の防衛を早急に強化するよう求めた。しかし、この件は黄昊によって阻止され、曹魏は漢中の防衛線を突破できないと劉禅を説得した。このように、黄昊の不行跡は戦う機会を逃し、蜀漢の滅亡の原因の一つとなった。諸葛瞻とその息子は蜀漢政権の崩壊を非常に悲しみ、黄皓を殺害したいと考えていた。 諸葛瞻が「姜維を外部から支配した」という記録が正史にないということは、この事件は歴史上起こらなかったということでしょうか? 歴史上の事実から判断すると、この事件は起こった可能性が高いです。景遼5年、諸葛瞻と董卓は共同で劉禅に陳情書を提出し、姜維は好戦的で功績がなく、国は疲弊していると考え、姜維の軍事力を剥奪し、顔羽を姜維の代わりとすることを望んだ。そうだとすれば、諸葛瞻の姜維に対する嫌悪感は依然として深刻である。 それで、姜維の北伐は諸葛亮の最後の願いでした。蜀漢の忠臣であり、諸葛亮の嫡子である諸葛瞻はなぜ姜維をそれほど嫌っていたのでしょうか。これは主に、姜維の個人的な能力に対する皆の評価によるものです。 『三国志演義』では、姜維は文武両道の才能を持ち、平均的な能力を持つ人物と評価されている。費毅の言葉を見れば、彼が姜維のことをどう思っているかが分かります。費毅は姜維が北伐を開始するのを止めようとしたとき、諸葛亮が北伐に成功しなかったのだから、我々も諸葛亮よりも悪く、北伐に成功する望みはない、と指摘した。したがって、我々は慎重に国を守り、将来有能な人材が現れて北伐を継続するのを待ちます。 費毅の言葉から、彼は姜維の能力を全く認識していなかった。しかし、姜維は自分の能力をそのようには考えていなかった。彼は北方探検が成功するかどうかは気にせず、とにかくそれを実行するつもりだった。北伐の初期には、姜維はいくつかの勝利を収めました。しかし、後期になると、姜維は戦いに勝つことすらできなくなりました。こうして、姜維はますます減少する軍勢を率いて北伐のため北上し、曹魏に対して絶望的な攻撃を続けた。このようにして、姜維は蜀漢の軍事力、人力、物資を枯渇させ、蜀漢を破滅の淵に引きずり込んだ。 当然ながら、諸葛瞻は姜維がこのように無謀な行動をとるのを黙って見ているわけにはいかない。彼は姜維を止めたかったが、残念ながら無力だった。魏延の死後、蜀漢は内紛で攻撃将軍を全員失い、姜維のような実力のある将軍に頼らざるを得なくなった。劉禅は軍事面では姜維に頼ることしかできず、結局姜維に代わることはなかった。 そのため、諸葛瞻は蜀漢全滅の原因を、国内における黄皓の権力濫用と、海外における姜維の積極的な軍事拡大に帰した。これは当時の蜀漢の実情とも合致している。さらに、姜維は漢中の防衛策を変え、賊を歓迎するために門を開いたため、敵は秦嶺山脈の自然障壁を容易に突破し、蜀漢の中心地を直接攻撃することができた。これらすべてが蜀漢の衰退を加速させた。 諸葛瞻はこの状況を変えたいと考え、躊躇することなく黄皓の腹心である顔羽を姜維の代わりに任命した。これは姜維の北伐を一時的に阻止することはできたが、渇きを癒すために毒を飲むようなものだった。実際、当時の舒漢の状況は薛の言った通りで、建物は今にも崩れ落ちそうで、一本の木では支えきれない状態だった。こうして諸葛瞻は黄昊と姜維への恨みを抱きながら戦死しなければならなかった。 |
<<: 九州とはどういう意味ですか?古代の九州とはどこの「九国」を指していたのでしょうか?
>>: 生年月日と8文字は何を意味しますか?伝統文化における誕生日
推薦する
なぜ劉備は李延に軍事権を譲ったのですか?蜀漢政権の安定のためだけに
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
ハイジの「秋の夕暮れ」の原文と鑑賞
秋の夕暮れ - ハイジ炎の頂点、沈む太陽の麓広大な夕暮れは豪華で最高です秋の悲しみの中で成熟する夕焼...
陳宮は若い頃は曹操に仕えていたが、なぜ呂布が兗州を制圧するのを助けたのだろうか?
陳宮は後漢から三国時代にかけての著名な人物で、若い頃は曹操に仕え、曹操の兗州入城に大きく貢献した。そ...
林振南の祖父は誰ですか?林振南の祖父、林元図の簡単な紹介
林元図は金庸の小説『微笑矜持放浪者』には登場しない名匠である。福建省扶威護衛社は彼によって設立されま...
宋代の太宗皇帝趙光義と江の物語
宋王朝の初代皇帝である宋太祖趙匡胤は、陳橋の反乱の後、黄衣をまとい、数百年続く宋王朝の基礎を築きまし...
『後漢書 劉儒伝』第76巻より抜粋した原文と翻訳
『後漢書』は、南宋代の歴史家・范業が編纂した年代記形式の歴史書である。『二十四史』の一つで、『史記』...
『紅楼夢』の賈家での黛玉の生活状況は本当に困難でしたか?なぜそんなことを言うのですか?
『紅楼夢』のヒロイン、黛玉。金陵十二美人本編に名を連ねる二人のうちの一人。以下、面白歴史編集長が関連...
宋代の詩「縮図木蘭花・端艇競走」を鑑賞するにあたり、この詩をどのように理解すべきでしょうか?
縮図ムーラン花·ドラゴンボートレース、宋代の黄尚、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持って...
呉俊の『蓮摘み歌』:詩全体が短くて濃厚で、清純な文体で書かれている。
呉俊(469-520)、号は叔祥、南朝梁の作家、歴史家。呉興市古章(現在の浙江省安吉市)の出身。彼は...
北方領土をほぼ支配していた韓信はなぜ反乱の機会を逃さなかったのか?
秦の滅亡後、項羽と劉邦は激しく対立した。鴻門の宴会で劉邦はすでに項羽と争う決意を示していたが、項羽は...
古代詩の鑑賞:詩集:緑摘み:朝から緑摘みをしていたが、バスケットいっぱいにはできなかった
『詩経』は中国古代詩の始まりであり、最古の詩集である。西周初期から春秋中期(紀元前11世紀から6世紀...
誕生日の男の子の額はなぜこんなに大きいのでしょうか?誕生日の星の「長寿の頭」についてはどんな伝説があるのでしょうか?
長寿の星は南極の仙人です。幸福、富、長寿の3つの星のうちの1つ。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹...
『紅楼夢』で蔡霞はなぜ頼王の息子と婚約したのですか?
「紅楼夢」のすべてをまず最初にレイアウトする必要があります。次のInteresting Histor...
なぜ曹操は袁紹に敬意を表し、心からの後悔を表明したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
武則天は李治の息子数人を処刑した。なぜ唐の皇帝高宗は傍観していたのだろうか?
歴史の記録によると、武則天のせいで亡くなった唐の皇帝高宗の李治の息子たちは、武則天の息子ではなかった...