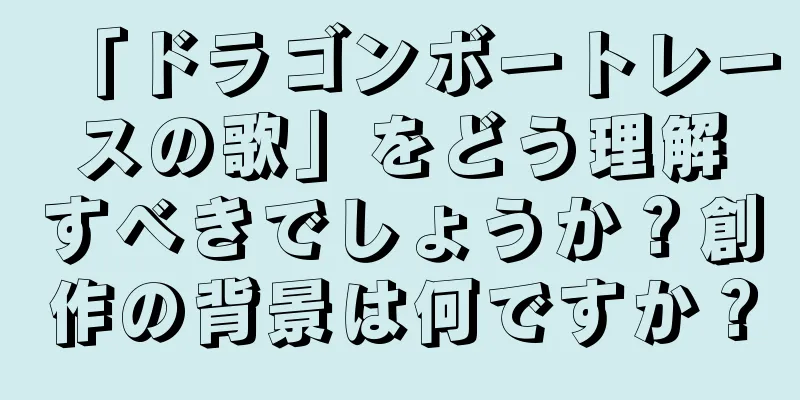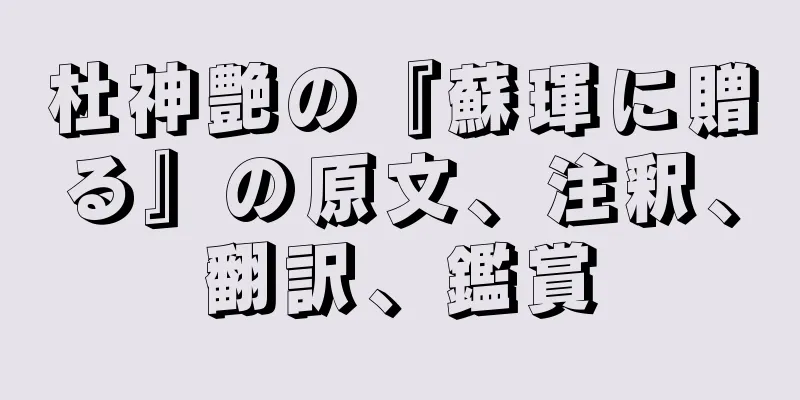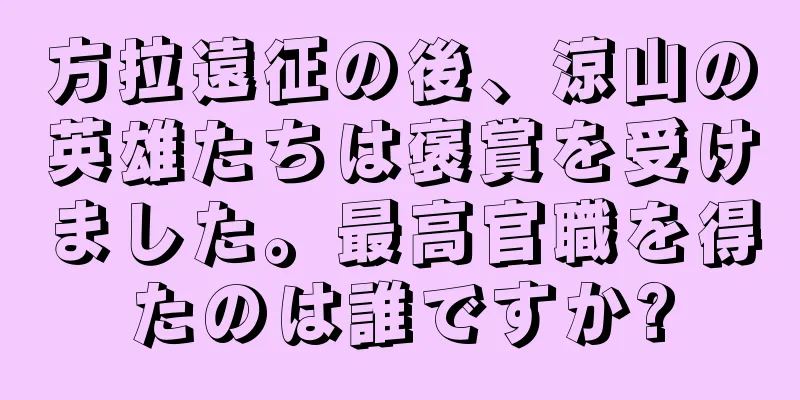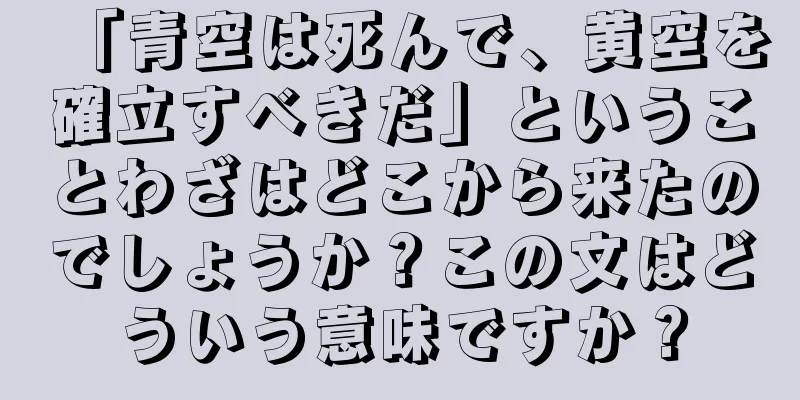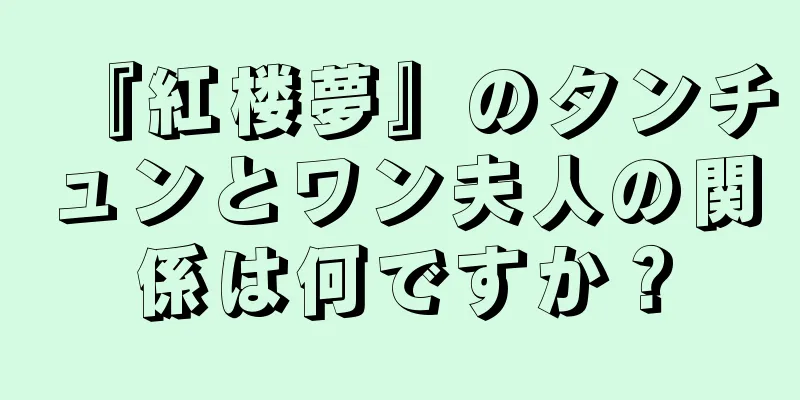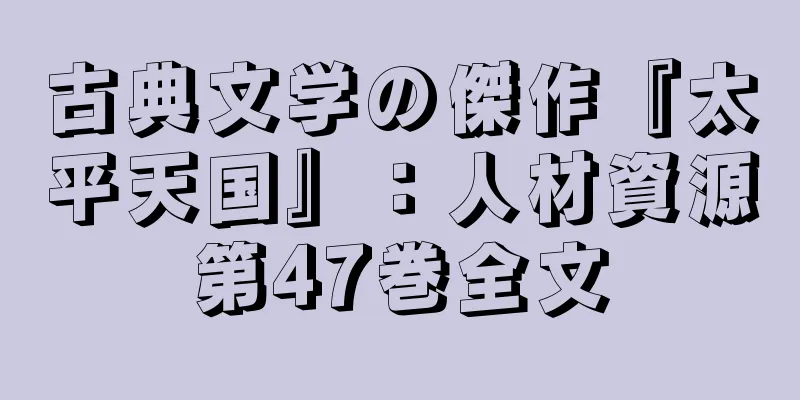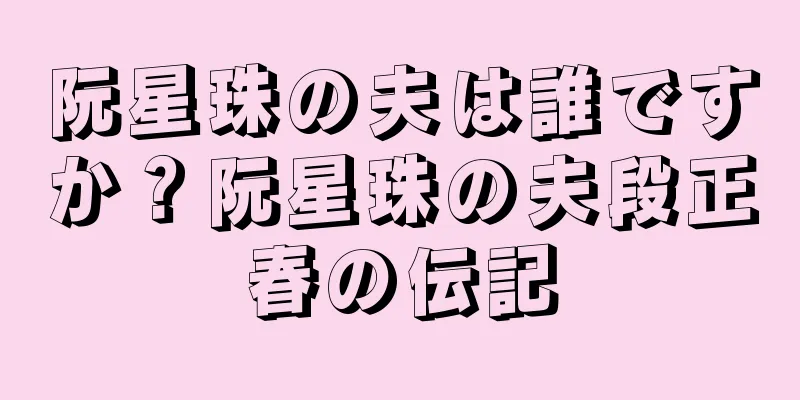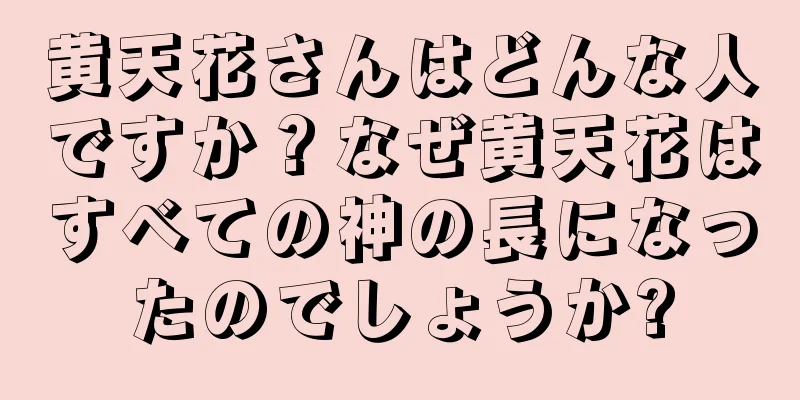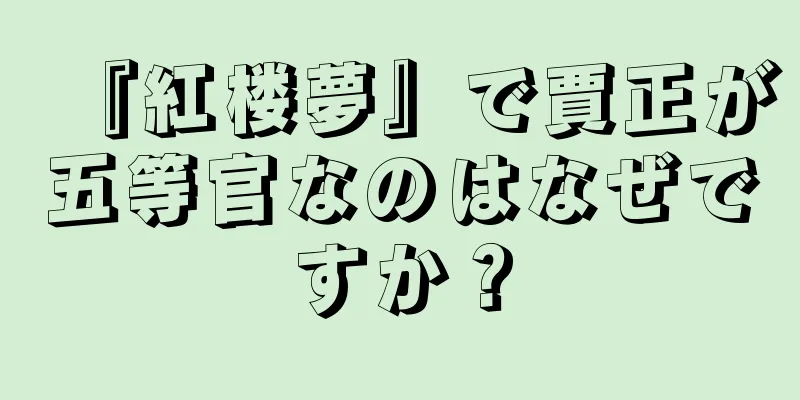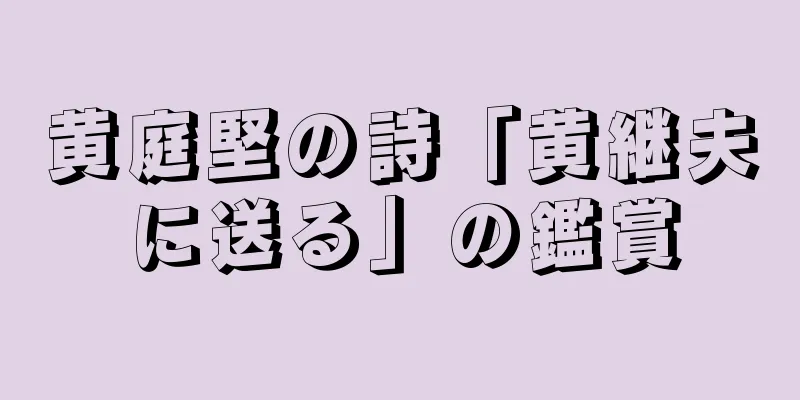なぜ喧嘩の話をしなければいけないのでしょうか?三国志演義では諸葛亮のライバルは誰もいなかったのですか?
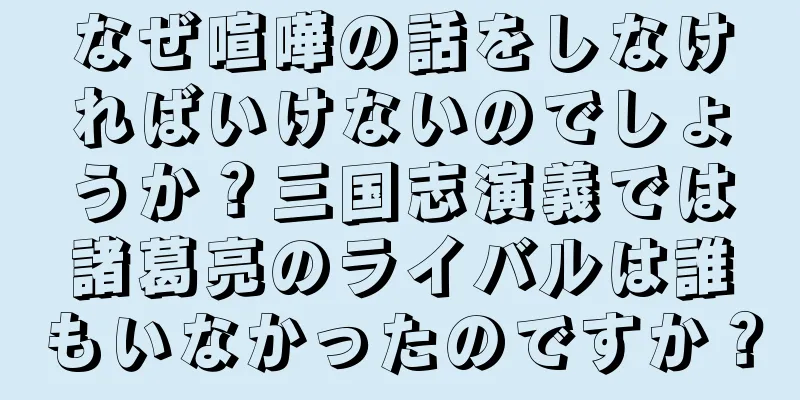
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、諸葛亮の怒りによって殺された3人(魏の2人、東武の1人)について詳しく紹介します。見てみましょう! 実は、当初、諸葛亮と周瑜の間には深い憎しみはありませんでした。しかし、周瑜は心の狭い人物でした。彼は常に諸葛亮をライバルとみなし、何度も諸葛亮と競い合いました。結局、彼は諸葛亮に太刀打ちできず、ついには怒って死んでしまい、「周瑜は三度怒った」という笑い話を残しました。 諸葛亮が周瑜を怒らせたのは、赤壁の戦いの後が初めてだった。当時、周瑜は曹操の軍が敗れている間に南郡を占領しようとしていました。しかし、曹仁と激しく戦い、辛うじて曹仁を倒したとき、諸葛亮が南郡を攻撃して占領し、周瑜は手ぶらで残されました。周瑜は非常に不満でした!周瑜は前線で死闘を繰り広げていましたが、諸葛亮は背後で優位に立っていました。誰もこれを理解できませんでした! 周瑜は諸葛亮に恨みを抱いていたため、孫権に計画を持ちかけ、孫権が妹を劉備と婚約させ、劉備が嫁に行くときに劉備を生け捕りにすることを望んだ。劉備は趙雲を連れて嫁に行ったが、趙雲は諸葛亮から与えられた三つの魔法の袋を持って、ついに劉備を窮地から救うことに成功し、孫権の妹も誘拐し、周瑜は妻と兵士の両方を失った。今回も周瑜は諸葛亮に負けたので、周瑜はまた怒った! 周瑜は二度続けて諸葛亮に「敗北」したことで激怒し、再び諸葛亮を攻撃しようと計画した。今回、周瑜は益州を攻撃し、劉備の領土を借りる必要があると発表し、敵のふりをして郭を滅ぼし、荊州を占領する戦略を実行したが、彼の計画はまたも諸葛亮に見破られた。周瑜は荊州を占領することができず、代わりに諸葛亮が一歩一歩計算し、非常に恥ずかしい思いをしました。通常、軍事では勝ち負けは当たり前のことであり、周瑜は撤退して諸葛亮と対峙し続けることもできました。しかし、周瑜は心が狭すぎて、すぐに方向転換することができず、怒りのあまり血を吐いて亡くなりました。残念でした。それ以来、同世代の偉大な英雄である周瑜は、諸葛亮の怒りを直接的に殺され、諸葛亮の成功への道の踏み石となりました。 諸葛亮が王朗を怒らせて殺すというのは、三国志演義の中でも非常にエキサイティングなストーリーです。王朗は諸葛亮が軍隊を率いて来ると聞いて、自分の雄弁さで戦わずして諸葛亮を必ず降伏させると皆に自慢しました。とても横暴でした! 原文: 朗は言った。「明日は軍隊を組織し、旗を掲げなさい。私が出てきて、ほんの少しの言葉を発するだけで、諸葛亮を降伏させ、蜀軍を戦わずに撤退させることができる。」 王朗は、自分が雄弁であり、戦わずして諸葛亮を黙らせ、降伏させることができると確信していた。その結果、二人が戦ったとき、王朗は状況が自分が想像していたものとは全く違うことに気づきました。諸葛亮を降伏させるよう説得できなかっただけでなく、諸葛亮に言葉を失い、反論することもできませんでした。赤壁の戦いの際、諸葛亮は多くの学者と激しい議論を交わしました。王朗がどうして彼の相手になるのでしょうか?また、諸葛亮は言葉による攻撃に長けていました。王朗が反論できないと分かると、さらに一歩進んで王朗を攻撃しました。最後には、王朗を叱りすぎて血を吐き、落馬して亡くなりました。すごいですね! 原文:「この白髪の老いたろくでなしめ!この灰色のひげの老いた盗賊め!お前は今日、冥界に戻るのだ。お前が二十四帝にどう立ち向かうのか?早くここから出て行け!お前は、逆賊である私に、お前と結末を決める方法を教えることができるのだ!」これを聞いた王朗は怒り狂い、叫び声を上げて馬の下敷きになって死んだ。 暴言に関しては、三国志演義では諸葛亮に匹敵する者はいないようです! 太和4年(230年)、曹真は曹叡の命により蜀を攻撃した。曹真は軍を率いて紫霧谷路から蜀を攻撃したが、途中で大雨に見舞われ、前進することができなかった。軍が閉じ込められ、形勢が不利なのを見て、曹真は憂鬱になり、病にかかった。諸葛亮は曹真が病に伏したと聞いて、すぐに密かに悪事を働き、曹真を騙そうと決意した。曹真に手紙を送るよう命じたが、その内容は曹真を侮辱し、曹軍の士気を低下させ、蜀軍の強さを誇示するという内容だった。 こういう手紙は、実は普段は大したことはない。曹真は数々の嵐を経験した男なので、嵐に左右されることはない。しかし、曹真は当時病気で落ち込んでおり、諸葛亮に影響されただけでした。手紙を読んだとき、彼は激怒し、考えれば考えるほど怒りが増し、結局死んでしまいました... 諸葛亮は本当に駆け引きが上手だったと言わざるを得ません。これはあなたの病気を利用してあなたを殺す典型的な例です! |
<<: 韓国人は飲酒の習慣がありますか?韓国のワイン文化の紹介
>>: 韓国の太鼓踊りの特徴は何ですか?ロングドラムダンス入門
推薦する
『後漢書』第85巻の原文は何ですか?
『礼記』にはこう記されている。「東方の人々は易と呼ばれている。」易は「根」を意味し、慈悲と生命への愛...
三国時代の司馬懿の息子は誰ですか?司馬懿の息子はみんなバカなのか?
司馬懿は三国時代の曹魏の政治家、軍事戦略家であり、三国を統一した人物です。では、三国時代の司馬懿の息...
杜遜和の『農夫』は封建社会の重税に対する強い抗議を表現している。
杜遜和は、字を延芝、号を九花山人といい、唐代末期の官僚詩人であり、写実主義の詩人である。彼は詩が優雅...
太平広記·巻71·道教·王敏をどのように翻訳しますか?具体的な内容はどのようなものですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
「秦元春:霊山千鈔が書かれたとき、燕湖の建設はまだ完成していなかった」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
秦源春・霊山千安府燕湖が建設されたとき、完成していなかった新奇集(宋代)山頂は西へ駆け上がり、何千頭...
岑申の古詩「精微」の本来の意味を理解する
古代詩「精微」時代: 唐代著者: セン・シェン彼は剣を持って北門から出て、いかだに乗って東の海へ向か...
古代の恋愛物語の一つ:真密と曹家の愛はどのように絡み合ったのでしょうか?
「長江の南には大橋と小橋があり、河北には真密が美しい」という故事歌があり、当時真密と大橋はどちらも驚...
シェ族の言語と文化のユニークな点は何ですか?
ある歌にこんな歌詞があります。「56の国籍、56の花、56の兄弟姉妹は一つの家族、56の言語、それを...
古代の詩の鑑賞: 雅歌集より「月が昇る」: 月が明るく昇ります。優秀な人材
『詩経』は中国古代詩の始まりであり、最古の詩集である。西周初期から春秋中期(紀元前11世紀から6世紀...
「梅の花」の作者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
プラムボッサム王安石(宋代)隅に数本の梅の花が、寒さの中でぽつんと咲いています。ほのかな香りがするの...
張陽浩が書いた三句は封建王朝の興亡を物語っている
山と丘が集まり、波が荒れ狂い、潼関路は山と川に囲まれています。西の都を見ると、ためらってしまう。秦と...
老子の『道徳経』第 17 章とその続き
『道徳経』は、春秋時代の老子(李二)の哲学書で、道徳経、老子五千言、老子五千言とも呼ばれています。古...
『山阳星星』の執筆背景は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】彭は九万頭の馬と十万金を腰に巻きつけ、揚州から鶴の背に乗ってやって来た。物事は進み、景...
曹操は世界中の英雄たちを味方につけることができたのに、なぜ関羽の忠誠心を得ることができなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
観音菩薩の乗るところとは何ですか?なぜ金色の毛の虎は太上老君の金色の首輪をつけているのでしょうか?
観音菩薩の山とは何でしょうか?金色の髪の虎がなぜ太上老君の金色の首輪をつけているのでしょうか?ご興味...