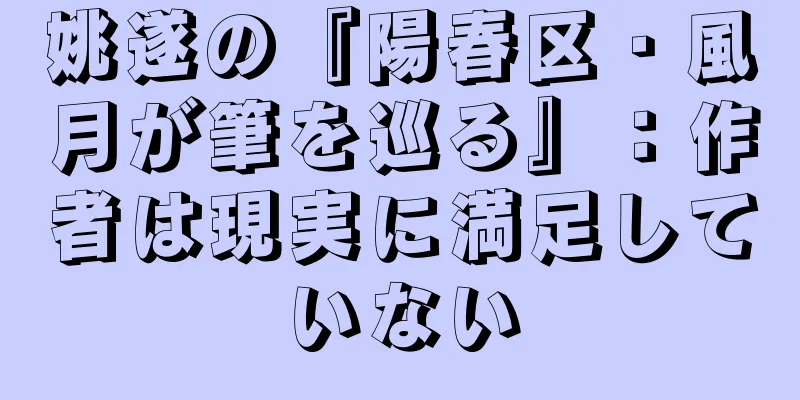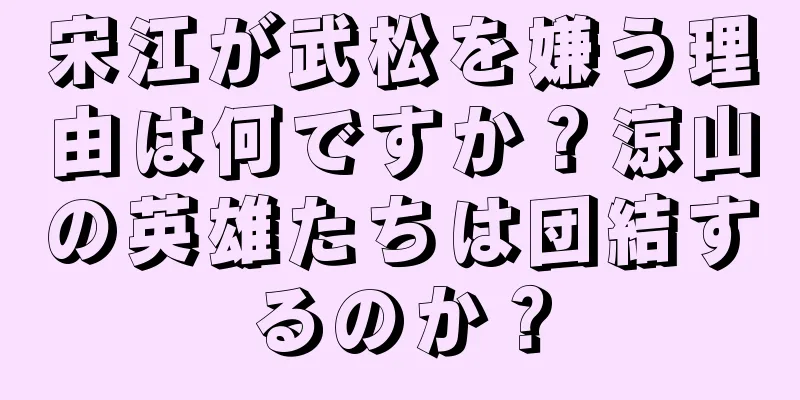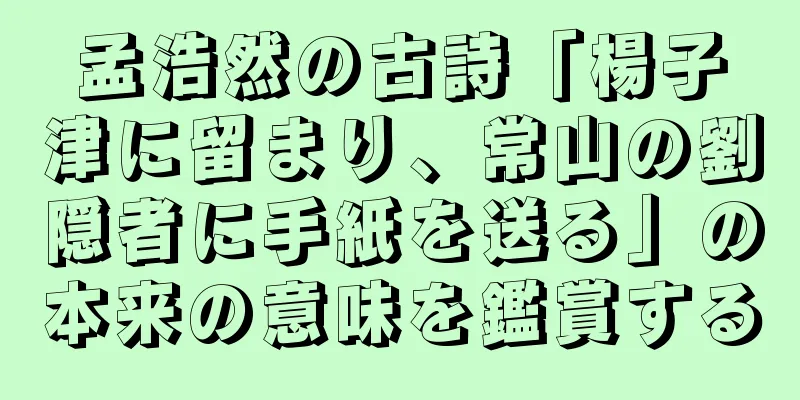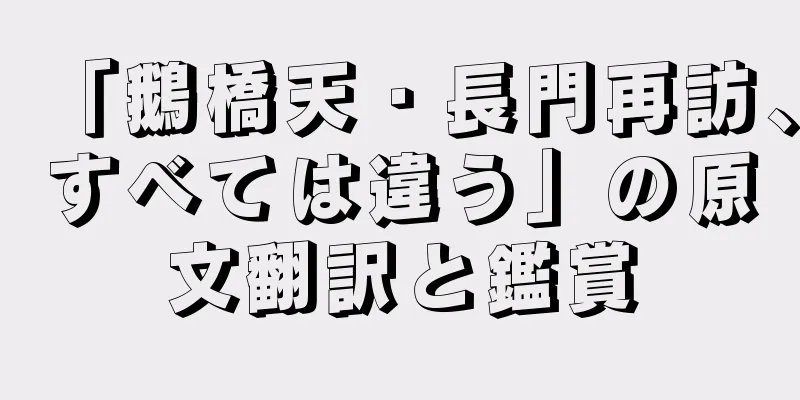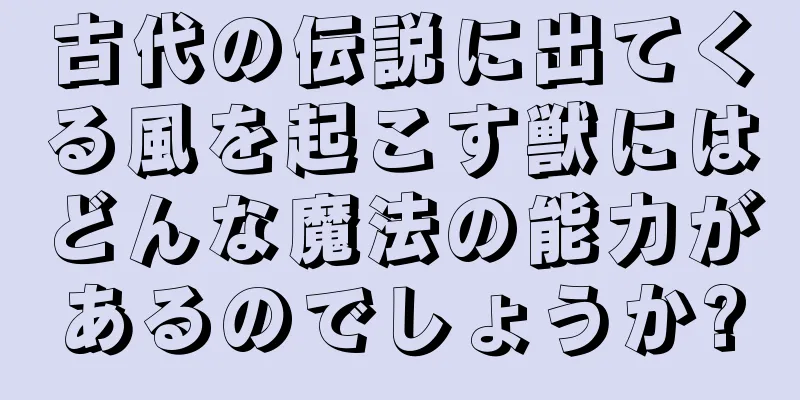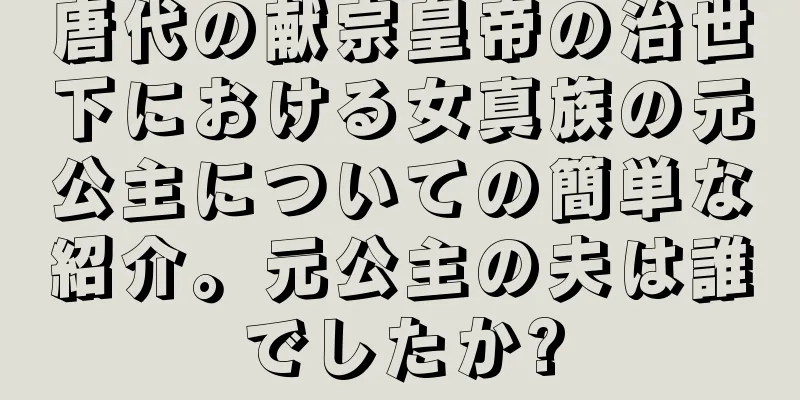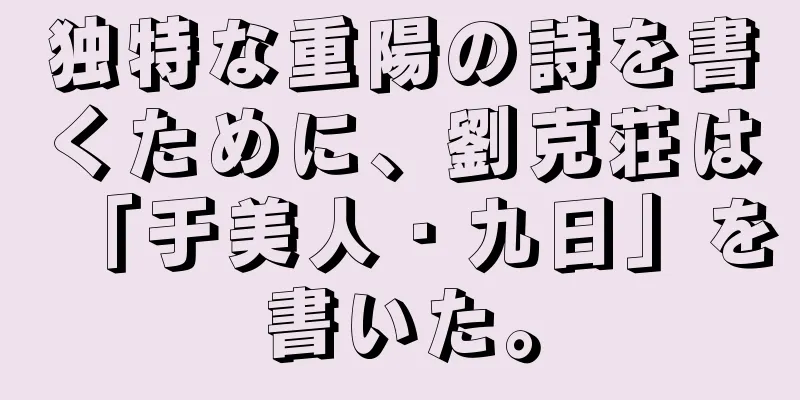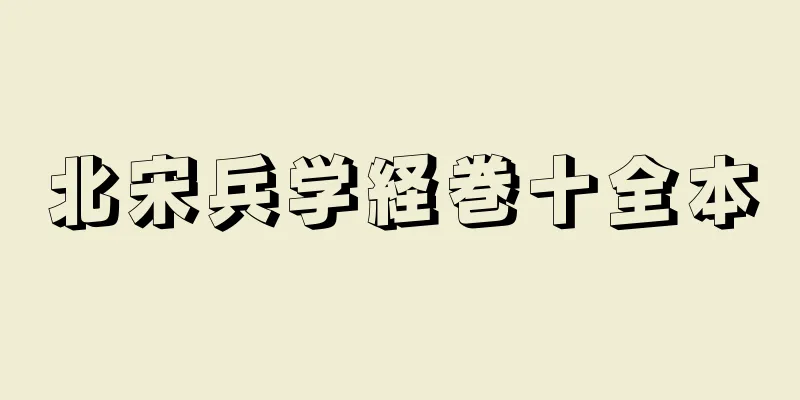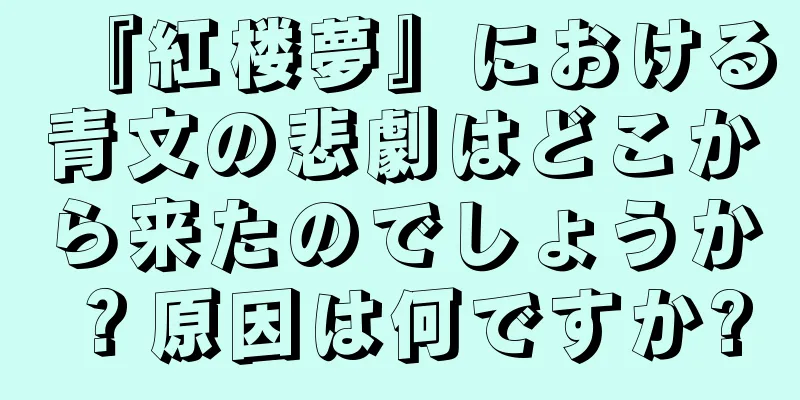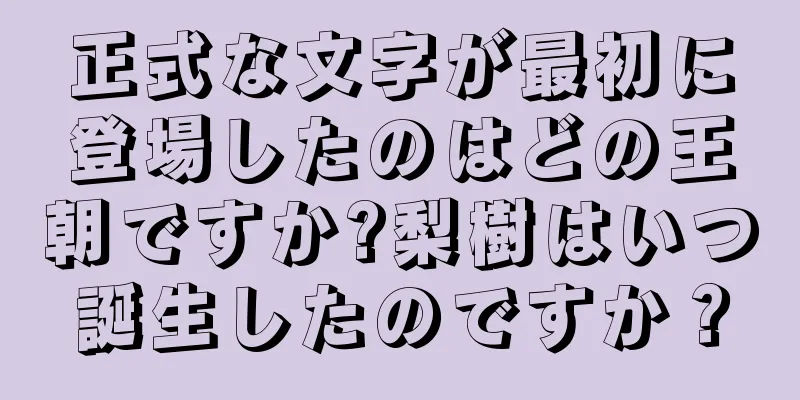ラフ族の民族文学のスタイルは何ですか?
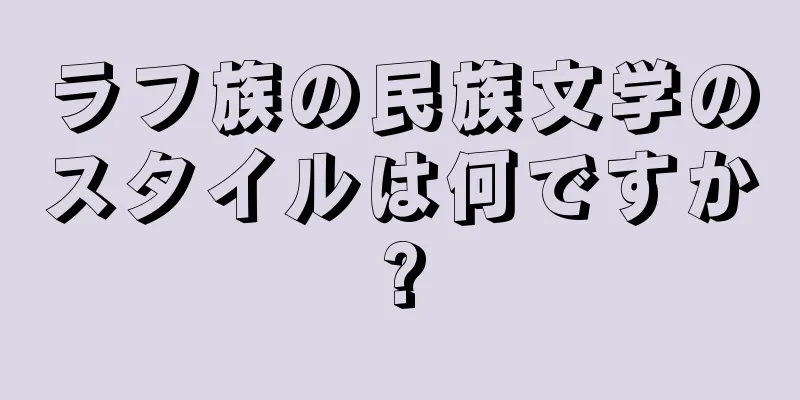
|
ラフ族の人口は30万人以上(1982年)で、主に雲南省の瀾滄ラフ族自治県、孟連ダイ族、ラフ族・ワ族自治県、双江県、西双版納の山岳地帯に居住している。ラフ語はシナ・チベット語族のチベット・ビルマ語族に属します。1957年に新しいラフ文字が改訂され、推進されました。ラフ文学は主に口承文学であり、神話、物語詩、伝説、物語、ラブソング、民謡、ことわざ、なぞなぞなどが含まれます。人類の起源、民族の起源、民族の移動に関する古代の神話や伝説は、壮大で魔法のようなファンタジーに満ちています。創世記『無上弥陀』は、「孟大弥陀」(天地創造)、「ヤブとナブ」(二人の兄弟の狩猟)、「孟叔密書」(肥沃な土地の探索)の3つの部分から構成されています。 この詩に登場する神エルシャは、ラフ神話の最高支配者です。天と地、太陽、月、星、そして自然界のすべてのものは彼によって創造されました。兄弟姉妹の結婚の描写は、ラフ族の原始的な氏族生活を反映しています。渡り鳥の生活に関する記述は、歴史的記録と概ね一致しており、歴史的、学術的研究価値があります。神話叙事詩「ザヌザビエ」は、エルシャ神に敢えて抵抗した巨人ザヌザビエを讃えています。ザヌザビエは最終的にエルシャに殺されますが、この叙事詩は、自然を征服し、抑圧に抵抗し、死ぬまで決して屈しないというラフ族の強い性格を反映しています。ラフ族は彼を「ボハイワハイ」と呼んだ。これは「最も賢く、最も勤勉な英雄」を意味する。民話のほとんどは、ラフ族が階級社会に参入したことの産物です。 「ラフ族の失われた印章の物語」「貪欲な竜王」「金を盗んだ族長」など、ラフ族の社会階級の差別と闘争を反映した作品。 「孤児と妻」、「亜竹溪と左闇」、「張超有と楊小達」などの愛をテーマにした物語は、誠実な愛を称賛し、移り気さと恩知らずを批判し、首長、領主、封建領主がどのように純粋な愛を破壊するかを明らかにします。 「孔雀とウズラ」「老猫とスズメ」「ヒョウと人間の技の競い合い」など、動物や植物に関する物語は、ラフ族の道徳観念を表現し、哲学に満ちています。ラフ族の民謡には、恋歌、慣習歌、家族歌、山歌、民謡などがあり、その中でも恋歌と慣習歌は特に特徴的です。最も民族的な特徴を持つラブソングは、「花を変える歌」、「道を尋ねる歌」、「橋を架ける歌」、「蜂を追いかける歌」です。 「歓花曲」は花を使って愛を比喩し、花を讃え、花を変え、花を守ることで愛への忠誠を象徴しています。民謡の中には「供養歌」が多数あるが、その中でも最も特徴的なのが「魂を呼ぶ歌」である。 「魂を呼ぶ歌」は、一年間の生産過程を時系列で語り、種を蒔き、収穫するよう魂を呼ぶものが多い。また、祭りの喜びとともに魂を故郷に呼び戻して再会させる歌もある。さらに、ラフ族の祖先の起源と移住の歴史を語り、祖先を偲んで人間界に帰るよう魂を呼ぶ歌もある。歌詞は比喩表現が多く、生き生きしている。 |
<<: 大足石刻の五山仏の特徴は何ですか? 「五山」の崖彫刻の紹介
>>: 大足石刻は洞窟芸術の普及促進にどのような役割を果たしていますか?
推薦する
唐代の詩「楓橋夜泊」を鑑賞します。この詩はどのような感情を表現しているのでしょうか?
唐代の張基が鳳橋に夜停泊した件について、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう...
文廷雲の最も簡潔で明確な詩は人々に悲しみと喪失感を与える
今日は、Interesting Historyの編集者が温廷雲についての記事をお届けします。ぜひお読...
『山水鎮魔物語』第14章:聖叔母宮の張り子の虎が金山を守り、張鸞が樹井園で梅児と出会う
『山水討魔伝』は、羅貫中が書き、後に馮夢龍が補った、神と魔を扱った小説で、中国の有名な古典小説の一つ...
『燕昭王』の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
燕王昭陳奎(唐代)南にある街師亭に登り、黄金テラスを眺めましょう。丘は高い木々で覆われています。昭王...
水滸伝で宋江が朱家荘を3度攻撃した最終結果は何でしたか?なぜ負けたのでしょうか?
宋江は、雅号を公明といい、『水滸伝』全編の第一の登場人物であり、非常に特別な存在です。彼は涼山蜂起軍...
『菩薩男 白昼に風が吹いて、もう半分冬』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
菩薩男:昼間に風が吹き、冬も半ば那蘭興徳(清朝)強風が国中を吹き荒れる中、冬もほぼ半分が終わり、カラ...
モーパッサンの『首飾り』は当時のどのような社会現実を批判したのでしょうか?
モーパッサンの『首飾り』。次回はInteresting History編集長が関連コンテンツを詳しく...
宋代の詩人何朱の『清遠霊伯国衡堂録』の原文、注釈、鑑賞
「清遠:霊波ではなく衡塘路」、次の興味深い歴史の編集者が詳細な記事の紹介をお届けします。青宇事件:霊...
徐晃はなぜ五大将軍の一人になったのでしょうか?陳寿は『魏書』を書いたとき、どのようなコメントを残しましたか?
五大将軍とは、三国時代の曹魏軍の5人の将軍、すなわち張遼将軍、楽進将軍、于進将軍、張郃将軍、徐晃将軍...
司馬遷の生涯はどのようなものだったのでしょうか?司馬遷は生涯でどのような功績を残しましたか?
司馬遷は中国の歴史における有名な作家、歴史家、随筆家です。では、司馬遷の物語についてどれくらい知って...
水滸伝で趙蓋はなぜ失敗したのか?原因は何ですか?
小説『水滸伝』の登場人物で、「刀太天王」の異名でも知られる趙蓋は、涼山坡の領主である。以下の記事はI...
「廉頗は年老いているのに、まだ食べられるのか?」この発言は、戦国時代の有名な将軍、廉頗とどのような関係があるのでしょうか?
「連托は年老いているのに、まだ食べられるだろうか」は、宋代の詩人辛其基の『荊口北姑亭昔懐かしき永余楽...
なぜ賈迎春は賈家の中で唯一の「赤字」の人物なのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
欧陽秀の『礼部が進士試験を審査する』:才能を大切にし、愛する真摯な気持ちが伝わってくる
欧陽秀(おうようしゅう、1007年8月1日 - 1072年9月22日)、字は永叔、晩年は随翁、劉義居...
三国志演義第97章:武侯は再び魏を攻撃する嘆願書を提出し、曹の軍を破り、姜維は偽の手紙を提出する
『三国志演義』は、『三国志演義』とも呼ばれ、正式名称は『三国志演義』で、元代末期から明代初期にかけて...