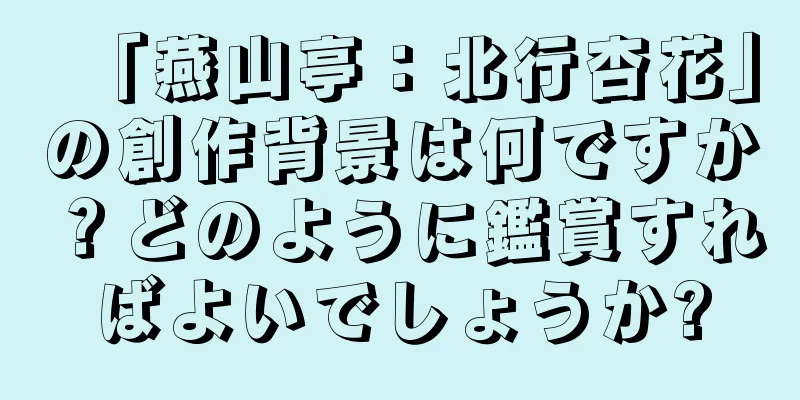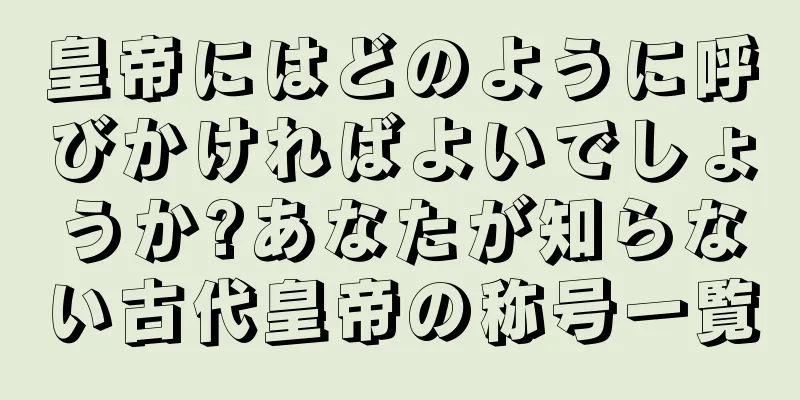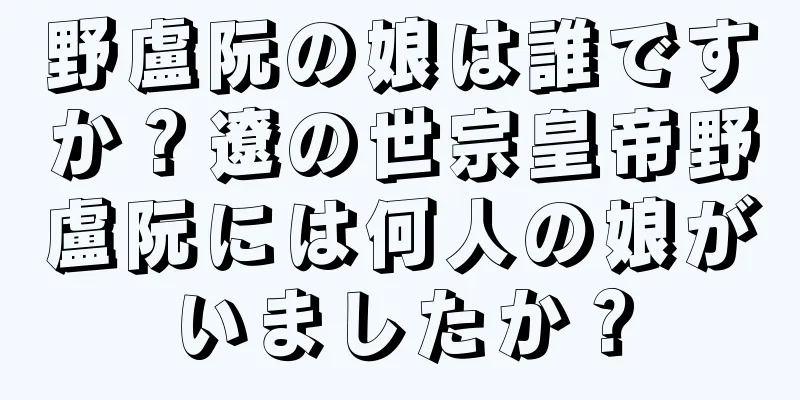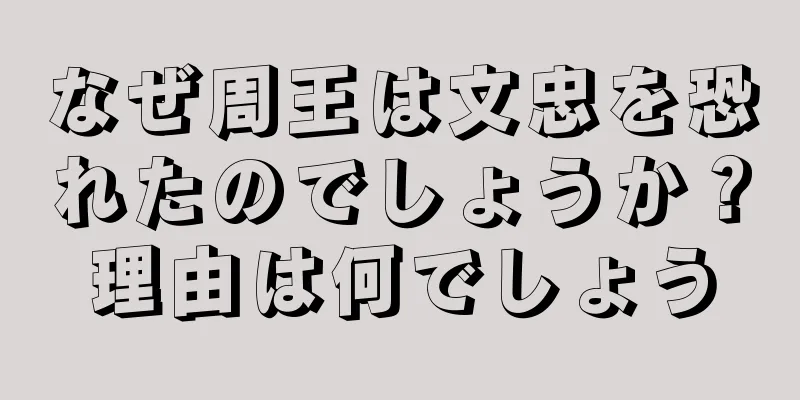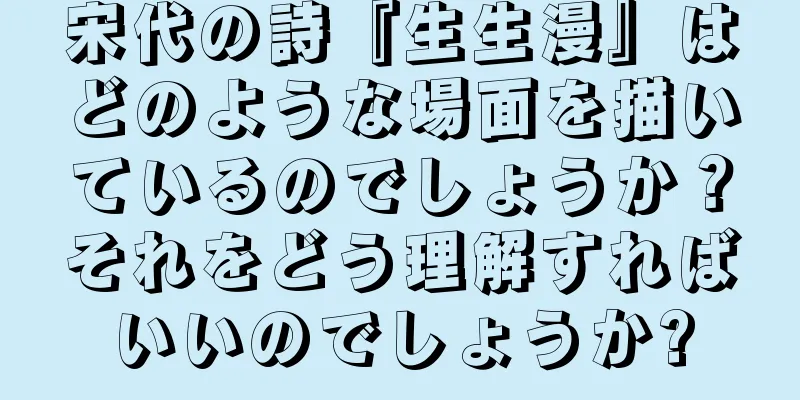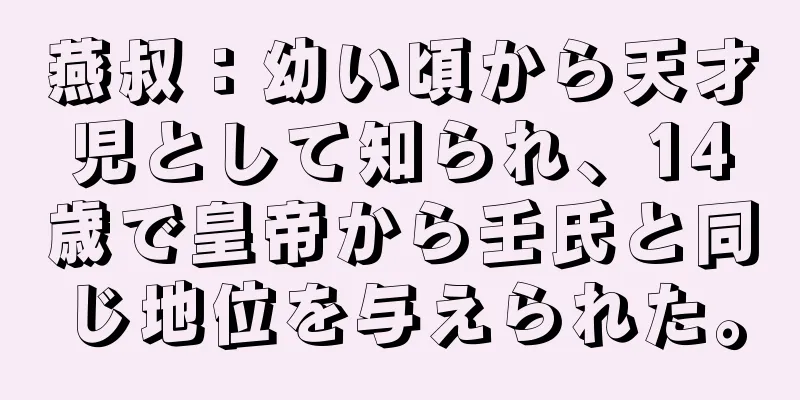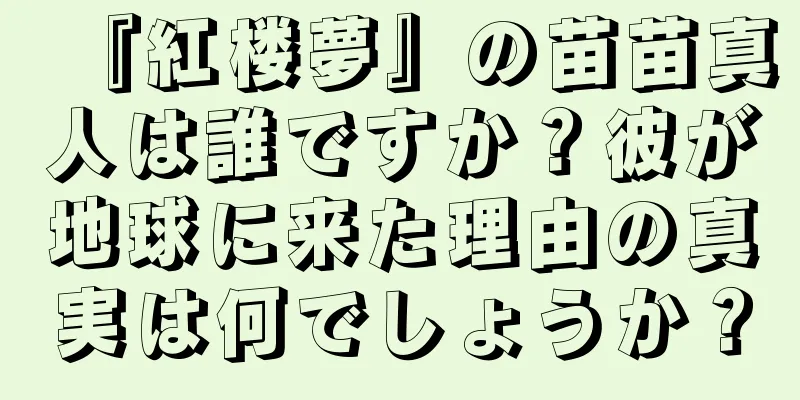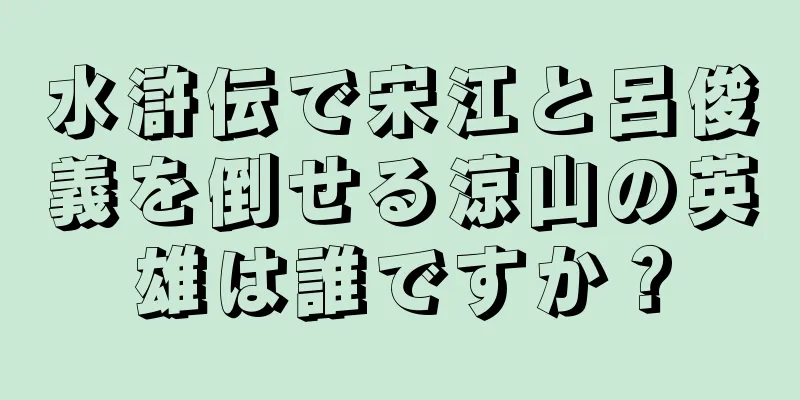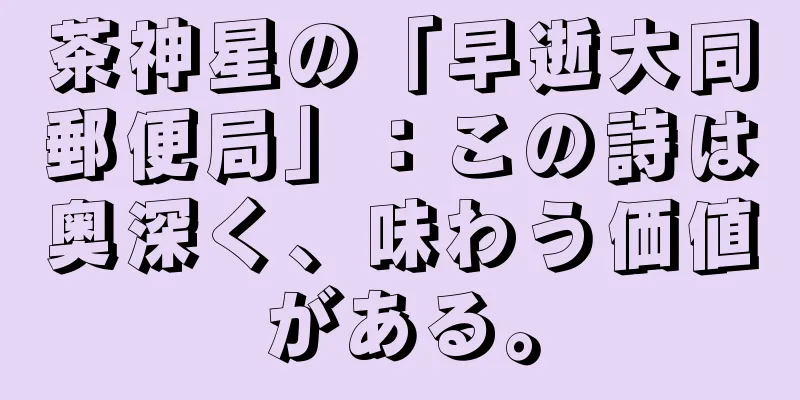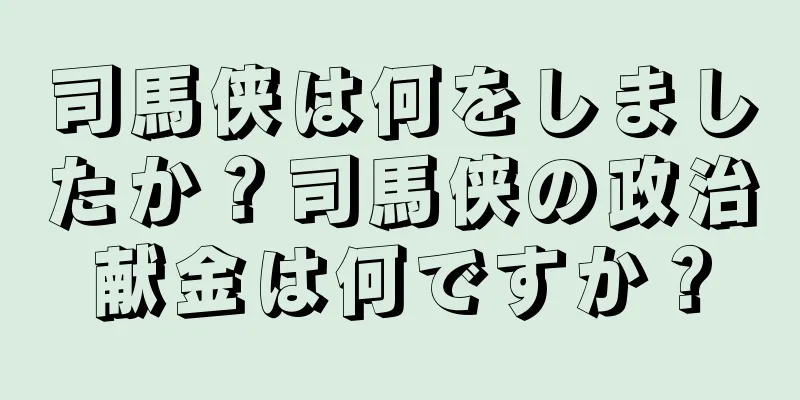なぜ劉備は諸葛亮と李厳を側近として任命したのでしょうか?
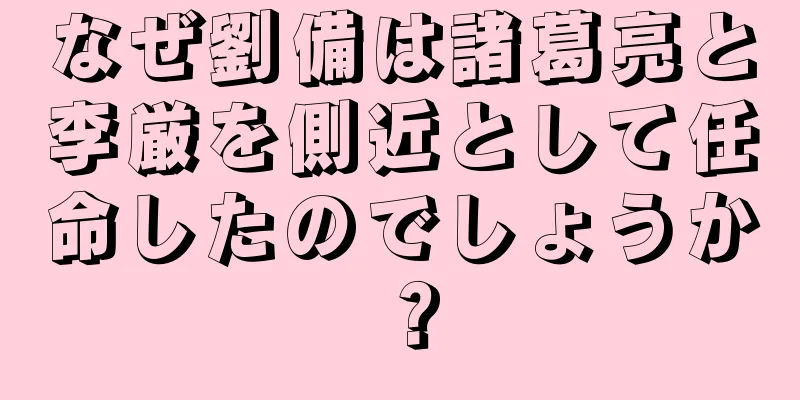
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が、李厳が誰なのか、そしてなぜ劉備が死に際に諸葛亮と軍事力と政治力を分担させたのかについて詳しく紹介します。見てみましょう! 李厳は後漢末期の南陽の人であり、若い頃から才能が有名で、荊州で劉表に仕え、梓桂県の知事に昇進した。曹操が南の荊州に下ったとき、劉表は死に、劉聡は降伏した。子貴はもともと荊州と益州の境目にあったため、曹操に降伏することを望まなかった李厳は西の益州に逃げ、劉璋の軍に加わった。 益州に到着した後、李厳は成都県の県令に任命された。彼はまだ県令を務めていたが、劉璋の政権が成都にあったため、この地位の重要性は明らかだった。 劉備軍が益州に入ったとき、李厳は前線に行く機会がなかった。建安18年(213年)になってようやく、前線は完全に崩壊したため、劉璋は李厳に綿竹地区の警備を引き継いで劉備に抵抗するよう命じた。しかし、劉璋が失敗する運命にあることをすでに悟っていた李延は、すぐに部下を率いて劉備のもとへ寝返らせ、劉備は李延を将軍に任命した。 翌年、劉備は成都を平定し、益州の戦いは正式に終結した。その後、李厳は前衛の知事と興野の将軍に任命され、ついに高官の地位に就いた。劉璋の統治下では益州の法律や規律が緩く、徳の高い政策もなかったため、李厳は諸葛亮、法正、易記、劉覇とともに『蜀法典』を制定し、蜀漢の法体系を確立するよう命じられた。 李延が劉備に寝返った後、官職は昇進したが、劉備に従ったのは比較的遅く、才能を発揮する機会がなかったため、当初は重要な任務を任されることはなかった。 建安23年(218年)、劉備と曹操が漢中をめぐって戦っていたとき、馬欽、高勝らが数万人を集めて邳県で反乱を起こした。李厳は援軍を待たずに、同県の5000人を率いて反乱を鎮圧し、馬欽と高勝の首をはね、すぐに新道県を包囲していたイ族の将軍高定を破った。このとき初めて、劉備は李厳の才能を真に認識した。この功績により、李厳は漢の補佐将軍に昇進し、引き続き前衛の知事を務めた。後に、漢中王の即位勧請状における主要人物11人の一人となった。 章武元年(221年)、曹丕が漢王朝を簒奪して皇帝を名乗った後、劉備が皇帝になるだろうことは誰もが知っていたが、常に蜀漢の忠実な臣であると主張していた劉備にはそうする理由がなかった。そこで、李厳はこの機会を捉え、管轄下の武陽県に吉兆が現れ、黄龍が赤水河を旋回し、9日以上そこに留まってから去ったという吉兆を報告した。まさにこの吉兆があったからこそ、劉備は皇帝になることができ、李厳はこうして劉備の全面的な信頼を得たのである。 劉備は皇帝を名乗って間もなく、断固として呉との戦争を開始したが、「夷陵の戦い」で惨敗した。劉備は敗れた後、永安に退却した。その後間もなく、尚書陵の劉覇が亡くなった。劉備は李厳に尚書陵の地位を引き継ぐよう命じた。その時初めて、李厳は地方官僚制度から飛び出し、真に意思決定レベルに入ったのである。章武3年(223年)、劉備は重病にかかり、李厳と諸葛亮が劉備の息子の世話を任された重臣となった。その中で、李厳は中央衛将軍に任命され、内外の軍事を担当し、永安の警備を担当した。 劉備は統治者として、権力の円滑な移行を考慮するだけでなく、子孫が王位にしっかりと座れるようにする必要もありました。劉備が諸葛亮と李延を息子を託す重臣に据えたのは、まさにこのためであった。個人的には、劉備がこのような取り決めをしたのは、次の2つの理由からであったと考えている。 第一は、朝廷の権力構造のバランスを取り、将来的に権力のある役人が出現するのを防ぐことです。君主としては、権力が発達する前は有能な大臣に絶対的な権力を与えることは悪いことではない。しかし、権力がある程度発達し、統治が安定してくると、内部の権力バランスの問題も考慮しなければならない。そのため、有力な大臣の出現を防ぐために、よりバランスのとれた権力構造を確立する必要がある。 初期の劉備の権力は比較的小さく、配下の有能な人材も比較的少なかったため、たとえ官制が無理なものであったとしても、その影響はそれほど大きくなかった。しかし、益州と漢中を占領した後、彼は権力構造の問題を考慮しなければならなかった。このため、劉備は漢中を占領して漢中王を名乗った後、法正を宰相兼衛兵将軍に任命した。法正を尚書令に据えたのは、諸葛亮をある程度牽制するためであった。何しろ、諸葛亮は当時、軍事顧問兼将軍として左将軍府を担当しており、その権力はあまりにも強大であった。 建安25年(220年)に法正が死去した後、劉備は劉覇を尚書陵の地位に任命した。章武2年(222年)に劉覇が死去すると、劉備は東呉との戦いで忙しく、そのため尚書陵の地位は「夷陵の戦い」後に李厳が引き継ぐまでしばらく空席となった。 劉備が荊州南部の4郡を占領した後、その勢力が急速に拡大し、官制が比較的混乱したが、尚書陵の地位は東漢の官制ほど高位で強力ではなかった。また、蜀漢政権における諸葛亮の特別な地位により、尚書陵による彼への統制は限られていた。しかし、どんなに効果が小さくても、制度を確立しなければなりません。そうして初めて、人が死に、政治が消え、権力の不均衡が生じるという事態は起こらないのです。 確かにその通りです。李延は若き皇帝の世話を任された重要な大臣であり、劉備は李延に内外の軍事を指揮する権限を与えていましたが、その権力は永安地域にしっかりと限定されていました。こうして蜀漢の権力構造は改善されたが、李厳は軍事力にあまり干渉しなかった。結局、彼は永安に長く駐留しており、彼が統制できる軍隊は永安駐屯軍のみであり、成都に影響力を広げる方法はなかった。劉禅が即位した後、益州太守に昇進した諸葛亮は、たちまち益州の軍事・政治指導者となった。軍を動員したいなら、劉禅の同意さえあればよく、李厳は効果的に彼を抑えることができなかった。 そのため、劉備が李厳を摂政に任命したのは、実際的というよりは象徴的な意味合いが強かった。李厳は諸葛亮を効果的に抑制することはできなかったが、事前に軍政分離の制度を確立する必要があった。結局のところ、諸葛亮が忠誠心があったとしても、彼の死後、蜀漢で軍事力と政治力の両方を掌握し、皇帝に取って代わる野心家が現れないと誰が保証できるだろうか? 2つ目は、内部の政治勢力のバランスを取り、蜀漢の統治の安定を確保することです。周知のように、後漢末期から三国時代にかけて、地方の貴族の勢力は大きく、劉備は外勢として益州に侵入したため、益州を占領して以来、省内では常に深刻な派閥争いが続いていた。 当時、劉備配下の文武官僚は主に4つの派閥に分かれていた。第一は劉備直系の張飛、関羽、趙雲、簡雍。第二は荊州派で、諸葛亮、馬良、馬素、黄忠、魏延、楊易、費毅など荊郷の人達。第三は益州派で、喬周、周書、杜瓊、張易、張易、馬忠など益州の地方の名士達。第四は東州派で、法正、李厳、徐静、黄権、劉覇、孟達、董和、董雲。 劉備は配下の派閥については、直系と荊州派を再利用し、東州派を掌握し、益州派を制圧する戦略をとった。劉備が益州に入った後、未亡人となった呉(劉延の嫁であり呉儀の妹)と結婚したのはこの目的のためであった。 劉備が荊州と益州を支配していたとき、彼は直系と荊州集団で他の2大派閥を制圧することができた。しかし、「夷陵の戦い」の失敗後、劉備は荊州を完全に失い、荊州集団が拠点を失っただけでなく、荊州から人材を引き抜き続ける可能性も失った。この戦いの前後、劉備の関羽、張飛、馬良、米朱、黄忠などが戦死または他界したため、劉備の直系と荊州集団は非常に大きな損失を被った。時が経つにつれ、荊州の喪失によって生じた内部派閥のバランスは必然的に崩れることになる。 このため、劉備は息子を他人に託す際に、おそらく東州グループを味方につける意図で、李厳を重臣に任命した。しかし、李厳は劉備の直系の子孫ではなかったため、幼い皇帝の世話を任される重臣となり、一定の実権を与えられたものの、諸葛亮ら直系の子孫を脅かさないように、その影響力は永安地域に限定されていた。 実際、内部の派閥争いは蜀漢にとって常に大きな潜在的危険であり、残念ながら根絶されたことは一度もありません。蜀漢末期の人材不足、さらには蜀漢が治世末期に戦わずして降伏したことも、ある程度はこれに影響されていた。 まとめると、劉備が李厳に軍事権を譲ったのは、実際的な意味よりも象徴的な意味合いが強く、蜀漢の権力構造と内部の政治勢力のバランスを取ることが目的だった。蜀漢の軍司令官である李延は、永安に駐屯していたため、実際には名ばかりの役職であった。永安付近で2万人の軍隊を動員できたが、他の軍隊を動員することはできなかった。諸葛亮は軍隊を直接率いる権限はなかったが、劉禅を使って海外に軍隊を派遣することはできた。 しかし、李厳の官職が名ばかりで実体がないからこそ、彼は諸葛亮に対して非常に不満を抱いていた。建興4年(226年)、諸葛亮が北上して戦ったとき、李厳は漢中の守備に軍を率いるよう李厳に命じたが、李厳は拒否した。その代わりに、5つの県を分けて巴州を置き、自らを巴州太守に任命して諸葛亮と対等にすることを要求した。しかし、諸葛亮は拒否し、二人は対立することになった。その後、李厳は利己的な理由で穀物や草の輸送を遅らせ、諸葛亮を北伐から撤退させました。度重なるトラブルにより、李厳は最終的に庶民に降格され、梓潼に移されました。そして、建興12年(234年)に怒りのあまり亡くなりました。 |
推薦する
七剣士と十三英雄の第17章:敵意を避けるために世界中を旅し、徐明高は金山を登る
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
『紅楼夢』の希仁はどのようにして王夫人の信頼を段階的に獲得したのでしょうか?
『紅楼夢』の希仁は野心的な女性です。賈夫人に認められた女性として、彼女は当然彼女の好みを知っています...
蘇軾の詩集「金門を訪ねて」「蘇中清」「鵝橋天」にはいくつの詩がありますか?
蘇軾の連作詩「金門を訪ねて」「蘇中清」「鵲橋天」には、何編の詩があるのでしょうか?これは、多くの読者...
唐の太宗皇帝が亡くなった後、張孫無忌は皇帝の叔父としてどのように国の統治を助けたのでしょうか?
貞観23年(649年)、唐の太宗皇帝は、仮宮殿であった翠薇宮で病死し、長孫無忌と朱遂良に国の統治を補...
『紅楼夢』で黛玉が内緒でお茶を飲むときに使っていたカップは何ですか?意味は何ですか
林黛玉は中国の古典『紅楼夢』のヒロインであり、金陵十二美女の第一人者です。本日は、Interesti...
古代の詩「馬車に帰って進軍する」の内容は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
馬車に戻って前進する [漢代] 匿名さん、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、...
包公の事件簿 第69章: 第三夫人
『鮑公案』は『龍土公案』とも呼ばれ、正式名称は『都本鮑龍土百公案全伝』で、『龍土神段公案』とも呼ばれ...
襄公15年の儒教古典『古梁伝』の原文は何ですか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
『紅楼夢』で劉おばあさんは衡武園にいる間、なぜ沈黙していたのですか?
『紅楼夢』の雄弁な劉おばあさんはなぜ恒武園にいた時、沈黙していたのか?一言も話さなかった。『興史』の...
認識の恩恵はどれほど重要ですか?そうでなければ、趙匡胤が権力を奪取する意図をどうやって持つことができただろうか?
「認められ昇進する恩恵」とは、あなたが成功したり活躍する前に、あなたを評価して昇進させてくれる最初の...
人類の進化の歴史から判断すると、惑星が知的生命体を誕生させることは難しいのでしょうか?
現在、人類は広大な宇宙の中で非常に孤独であり、他の高度な生命体が存在する兆候はありません。天文学的な...
古代王朝の興亡:古代中国王朝の終焉をどう判断するか
1. 首都の陥落は王朝の終焉の兆しでしょうか? 首都は国や政権の政治的中心地であり、その地位は極めて...
四木屋丁はいつ発見されましたか?なぜ「司馬武定」が「後馬武定」に変更されたのですか?
なぜ「司馬武定」は「後馬武定」に改名されたのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので...
小説『紅楼夢』に登場する王傅仁の侍女、蔡霞の最終運命はどうなったのでしょうか?
蔡霞は『紅楼夢』の登場人物。王夫人の侍女であり、時には趙叔母の二等侍女でもある。次に、興味深い歴史の...
FBIは何をするのですか? FBIはどのようにして設立されたのですか?
多くのハリウッド大作映画には、連邦捜査局(略して「FBI」)という有名な組織が登場します。 「FBI...