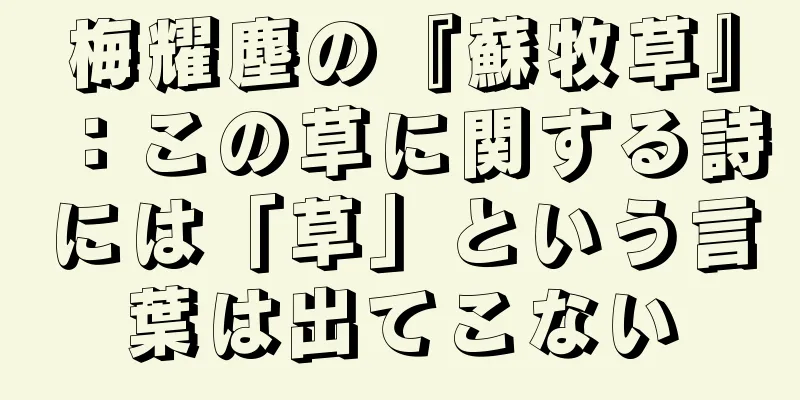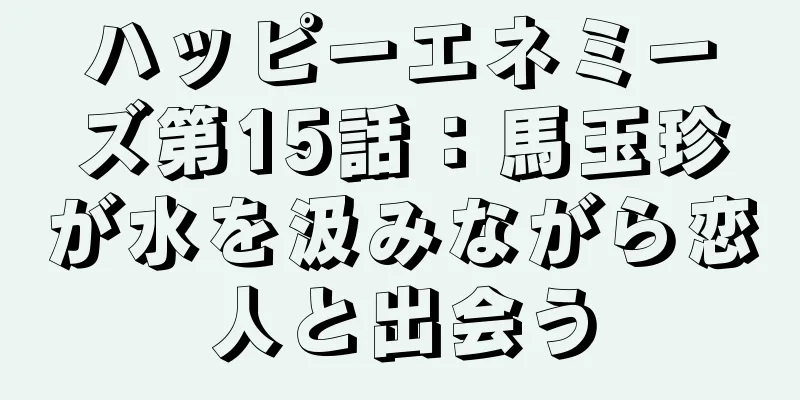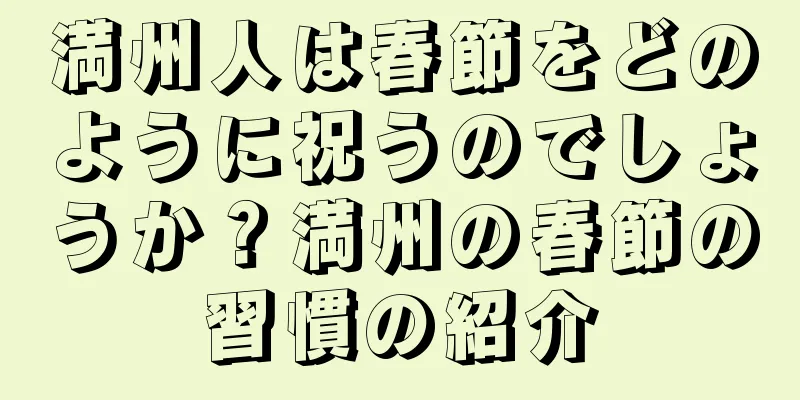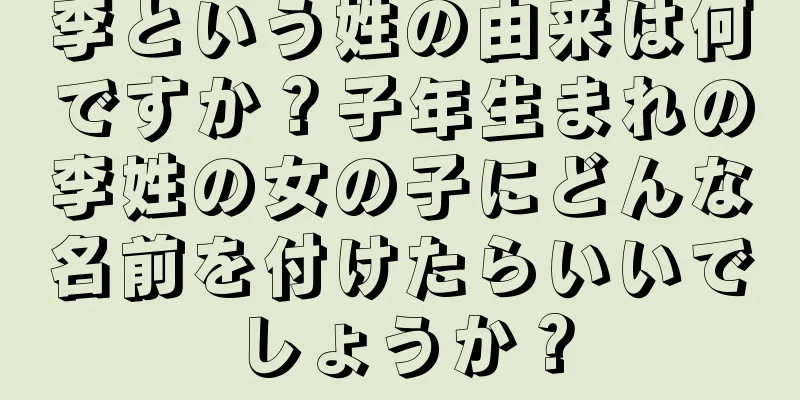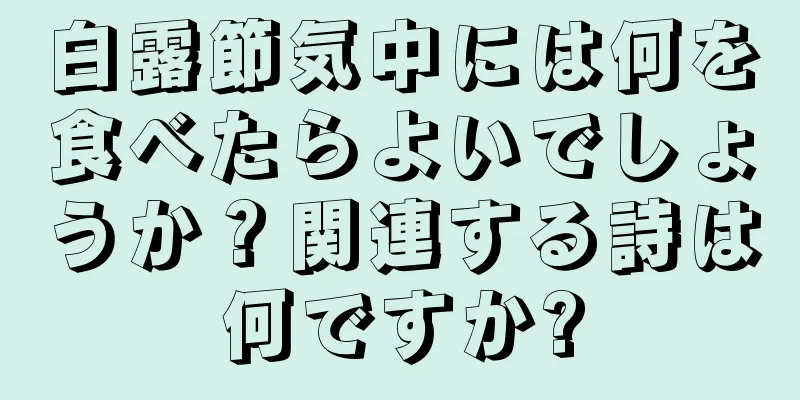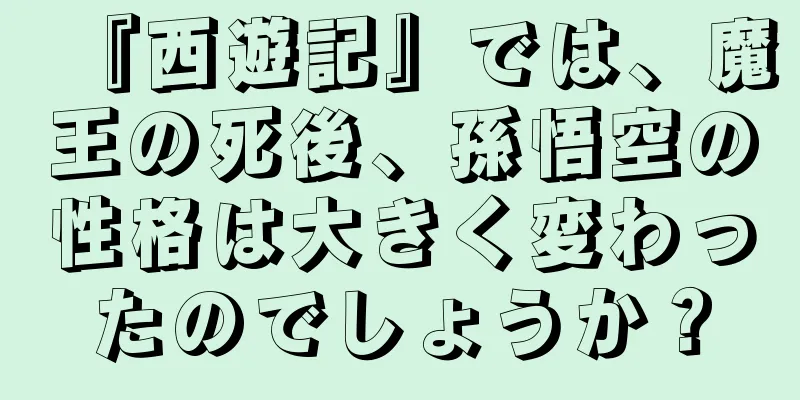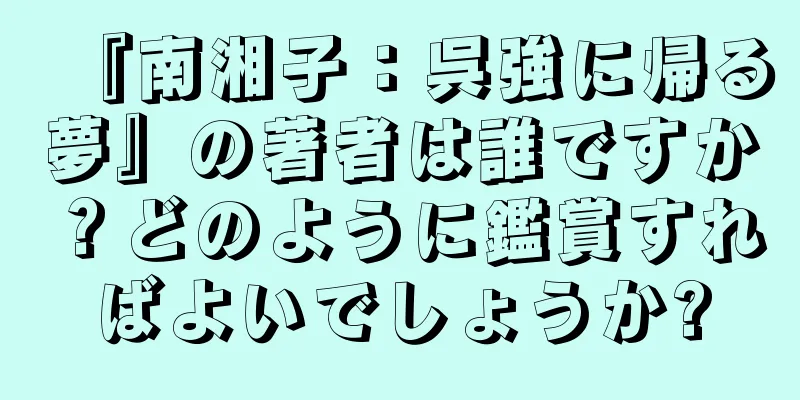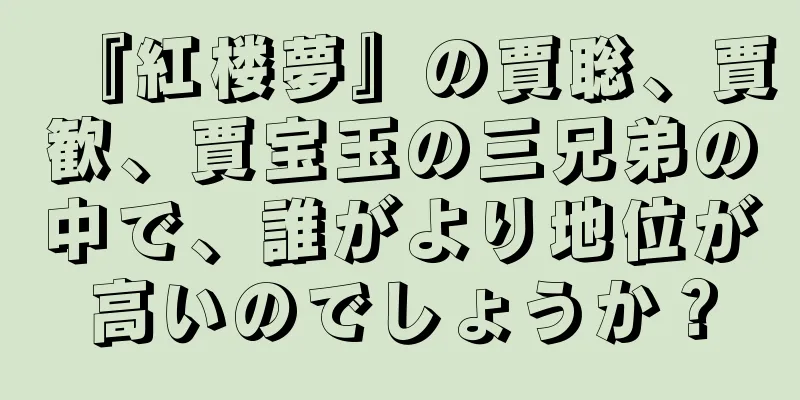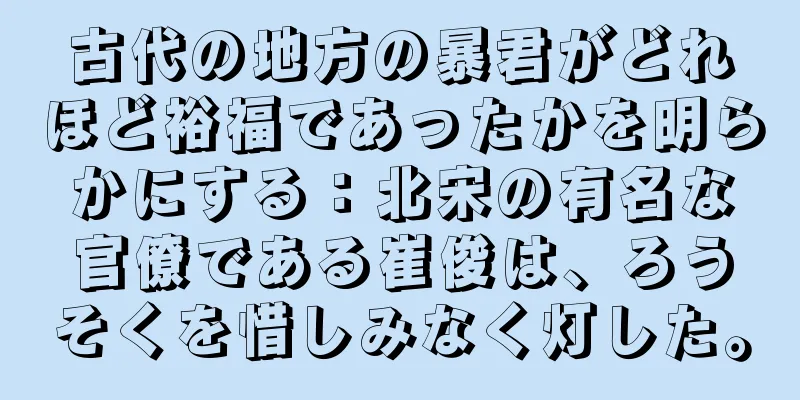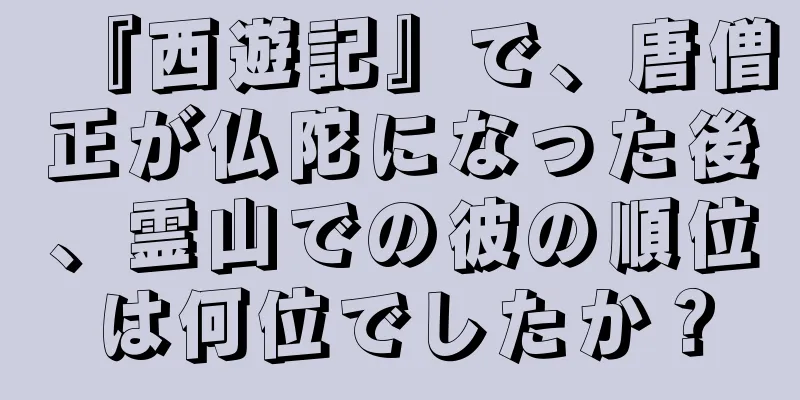孫子の戦略は張飛の戦略より劣っていたのに、なぜ張飛が簡単に勝つ可能性は低いと言われているのでしょうか?
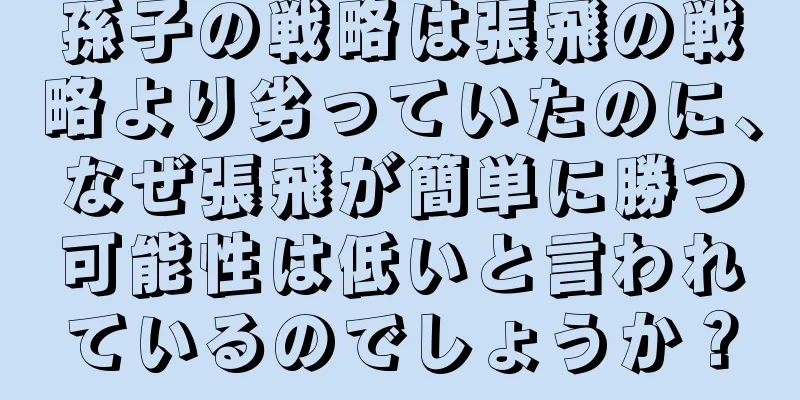
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が、孫策がどれほど強力であるか、そして孫策が張飛と一対一で戦うことができるかどうかについて詳しく紹介します。見てみましょう! 孫策の武術の腕前には期待できるし、努力すれば五虎退のレベルに達することもできるだろう。 江東には一流の将軍が不足しており、また一流の将軍と戦う機会も不足しているため、孫策の軍事力をすぐに評価することは不可能です。いつものように、私たちは依然として将軍を基準として選びます。 参考にする将軍は優れた武術の技能を持ち、一流の将軍や孫策と戦った経験を持っている必要があります。この3つの条件を満たすことができるのは太史慈だけです。 孫策はわずか3,000人の兵士で出発し、江東の広大な領土を征服しました。この過程で、孫策が戦った最もエキサイティングな戦いは、神亭嶺での太史慈との決闘でした。 慈は言った。「あなたたちが全員来ても、私は恐れません!」彼は馬に乗り、槍を持ち、まっすぐに孫策に向かって行きました。セは槍を手に彼に会いに来た。二頭の馬は対戦し、50ラウンド戦いましたが、勝者は出ませんでした。 セナ・リ・ケン・シェ、平地までずっと。慈竇は馬を回して再び戦い、戦いはさらに50ラウンド続いた。 孫策と太史慈は神亭嶺で100回以上(馬上での100回の戦いと徒歩での路上戦闘の数ラウンド)戦ったが、決着はつかなかった。 太史慈は当時劉瑶の将軍だった。彼は評価されていなかったが、何らかの成果を上げることを決意していたので、この決闘ではどちらも譲らず、少なくとも太史慈は譲らなかった。つまり、この 100 ラウンドは実際に有効であり、この 100 ラウンドで孫策と太史慈が同等の力を持っていると判断できます。 このように、太史慈の武術がどれだけ強いかを分析することで、孫策の武術価値を推測し、孫策が張飛の対戦相手であるかどうかを判断することができます。実は、太史慈は生涯でまともな一対一の決闘を経験していませんが、参考になるものが 2 つあります。 その一つは、赤壁の戦いの後、孫権が合肥を攻撃した際に、太史慈と張遼の間で行われた決闘である。 全初は槍を振り上げ、自ら戦おうとしたが、陣中の将軍が槍を手に飛び出してきた。それは太史慈だった。張遼は剣を手に彼に会いに来た。二人の将軍は70ラウンドか80ラウンド戦いましたが、明確な勝者は出ませんでした。 この決闘では、太史慈と張遼は70ラウンドか80ラウンド戦ったが、勝敗ははっきりせず、楽進が孫権に奇襲を仕掛けたことで中断された。戦いが続けばどちらが勝つかは分からないが、70ラウンドか80ラウンド戦えたという事実は、実は二人の武術の腕が同等だったことを示している。戦闘力に差があれば、50ラウンドで勝敗は明らかになるはずだ。つまり、この決闘に関しては、太史慈 ≒ 張遼です。 張遼は五虎将軍と決闘したことはないが、三国志ファンは一般的に張遼の武術の腕は二流であり、一流の五虎将軍には敵わなかったと考えている。この決闘を参考にすると、太史慈と同じくらいの実力を持つ孫策が張飛に挑んだ場合、引き分けよりも負けが多くなり、勝つ見込みはないだろう。 太史慈と張遼の決闘は、基本的に太史慈と孫策の武術の限界を決定づけたものであり、つまり、彼らの武術の限界は張遼以下ではなかった。しかし、結局のところ勝者も敗者もなく、太史慈はまだ限界に達していないのかもしれません。太史慈の武術の潜在能力の上限を反映したもう一つの決闘を探してみましょう。 三国志演義では、太史慈が孫策に降伏した後、登場シーンが少なすぎて、基本的に厳しい戦いを戦うことはありませんでした。張遼との戦いは、孫策に寝返った後、彼が実力を発揮する唯一の機会のはずです。しかし、『三国志演義』にこのことが書かれていないからといって、太史慈が常に余暇や隠遁生活を楽しんでいたというわけではない。 劉表の従者子攀は勇敢で、艾県と西安県を頻繁に襲撃した。戈は海塩と建長を6つの郡に分け、戈を建長の司令官に任命して海塩を管轄させ、将軍たちを指揮して潘に抵抗させた。パンは姿を消し、もはや脅威ではなくなった。 劉表の甥の劉攀と黄忠は昔からコンビだった。劉攀がいれば黄忠もいるはずだ。劉昴の武術の腕はあまり高くないので、孫策の領土に侵入する勇気があれば、必ず黄忠を連れて行くだろう。 軍の将軍が関与する敵対関係にある両者が、単に非友好的な態度で対立することは不可能である。地域紛争は必然的に起こるでしょう。 太史慈は東呉の主将として、必然的に黄忠と戦うことになった。 どちらの側からも大きな事件は報告されておらず、明確な勝者も敗者もいなかったことが示された。二人の決闘が成立したとすれば、太史慈の武術の腕は黄忠に匹敵するはずだと推測できる。 この比較では、太史慈(孫策を含む)は五虎将軍に挑戦できるほどの強さを持っています。もちろん、太史慈は張遼を倒していないので、彼の上限は張遼よりそれほど高くないだろう。五虎将軍、特に一対一の戦闘では最強の張飛に挑戦するなら、負けないようにするのが一番です。 三国志には24人の将軍がいるという民間伝説があり、その中で張飛は6位、孫策と太史慈は9位と10位にランクされています。上位10人の将軍の中で、1位の呂布を除いて、他の9人の中で誰が誰を必ず倒すかは分かりません。 孫策は武術の面では張飛より若干劣るかもしれないが、張飛が簡単に勝つことはありそうにない。さらに、孫策には独自の強み、つまり軍隊を指揮する能力の高さもありました(わずか3千人の兵士で拠点を築くことができたという事実がそれを物語っています)。将軍のうち元帥になれるのは2人半で、1人は関羽、もう1人は孫策、残りの半数は呂布です。 もし孫策が独り立ちして自分の事業を始めていなかったら、彼は間違いなく多くの英雄たちの間で最も求められる将軍になっていただろう。 |
推薦する
『紅楼夢』では、邢夫人と幽夫人の一族は皆衰退しましたが、なぜ彼らは立ち続けることができたのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
元代の衣服:主に長衣
元朝は領土が広く、民族が混在し、様々な文化が互いに補完し合っていました。農耕文化と草原文化、中原文化...
清代の詩の鑑賞:菩薩男 - 遠くの夕暮れに面した冷たく霧のかかった窓。この詩にはどんな比喩が隠されているのでしょうか。
菩薩人・霧窓寒向遠天夕暮[清代] 那藍興徳、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます...
『紅楼夢』の賈宝玉の私生活はどれほど乱雑なのでしょうか?このように書く目的は何ですか?
賈宝玉といえば何を思い浮かべますか? 『紅楼夢』が好きな読者の多くは、次のような疑問を抱いています。...
「枯れ蓮の葉三首」を書いた詩人は誰ですか?この歌の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】枯れた蓮の葉は灰色になり、古い茎は風に揺れています。昨夜の霜のせいで、香りは薄れ、色も...
『西江月:姚浦青梅遅咲き頌歌』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
西江月:ヤオプの青梅の枝に咲く遅咲きの花呉文英(宋代)枝には雪の跡があり、葉の中には春の豆が少し隠れ...
遼東三英雄として知られる明代の三大将軍が、なぜ魏忠賢によって陥れられたのか?
熊廷弼、孫成宗、袁崇煥はいずれも明代末期の名将で、遼東出身で、総じて遼東三英雄と呼ばれていました。実...
フィンランドのLS26機関銃:機関銃でライフル銃並みの精度を実現できる精度の王者
有名な「ソビエト・フィンランド戦争」では、M1931「ソミ」サブマシンガンなどのフィンランド軍が装備...
何志章の二つの詩「帰郷折詩」の長所は何ですか?
歴史上の有名な一節「子供は互いに面識もなく、客に笑顔でどこから来たのか尋ねる」は、何志章の『帰郷折詩...
黎族の食生活における習慣やタブーは何ですか?
肉食について:黎族の人々は一般的に猫の肉を食べません。彼らは猫を家の台所の神様だと信じており、飼い猫...
古典文学作品『西漢演義』第31章:韓信と張良が剣を売る
『西漢志演義』と『東漢志演義』は、もともと『江暁閣批判東西漢通志演義』というタイトルで、明代の中山の...
『紅楼夢』の青文は何が特別で、賈おばあちゃんが彼女を好きになるのでしょうか?
彼女と同じように老女の部屋から異動してきた女中の青文は、彼女よりも美しいだけでなく、賈おばあちゃんか...
『水滸伝』では平凡な成績だった穆紅が、いかにして天岡スターになったのか?
『水滸伝』では凡庸な成績だった穆洪が、どのようにして天岡のスターになったのか?これは多くの読者が知り...
楊在星は歴史上どんな人物だったのでしょうか?彼は結局どうやって死んだのですか?
南宋の時代に金と戦った名将、岳飛には多くの優秀な将軍がいました。楊在星もその一人で、武術に長け、無敵...
『紅楼夢』では、賈家は元春のために大観園を造ったのですか?
大観園は『紅楼夢』で賈家が元春の両親訪問のために建てた別荘です。次は、興味深い歴史の編集者が関連記事...