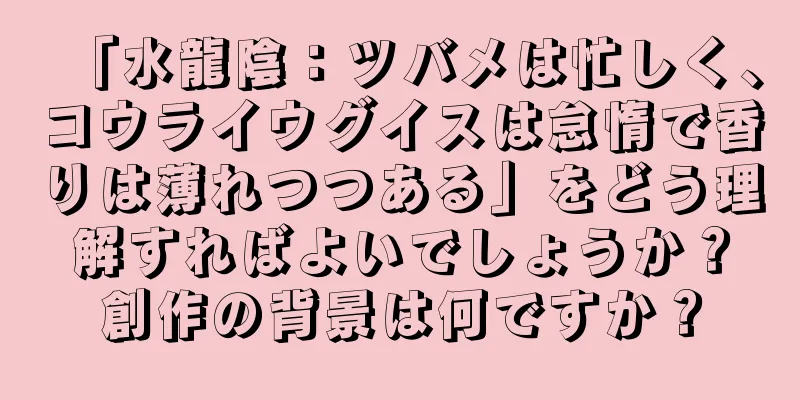諸葛亮は聡明で才能に恵まれていたのに、なぜ馬超のような勇敢な将軍を使わなかったのでしょうか?

|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。では、次の興味深い歴史編集者が、その年に一度しか戦わなかった馬超が、その勇敢さにもかかわらず諸葛亮に再起されなかった理由について詳しく紹介します。見てみましょう! 馬超(176-222)、号は孟奇、阜豊県茂陵県(現在の陝西省興平市)の出身。後漢末期の武将で、三国時代の蜀漢の名将。将軍伏波馬淵の子孫で、衛衛馬騰の長男。彼は若くして名声を博し、勇敢で戦闘に優れ、曹操の召集を何度も拒否した。かつては漢中太守の張魯に属していたが、214年(38歳の時)、馬超は張魯と世界情勢を議論することはできないと感じた。当時、劉備は成都で劉璋を包囲していた。馬超は民を率いて降伏し、軍を率いて成都を包囲した。蜀漢が建国されると、騎将軍、涼州知事に任命され、太湘侯の爵位を授けられた。彼は章武2年(222年)に47歳で病死した。 三国時代の武将の勇敢さを語るとき、間違いなく「金馬超」として知られる人物の存在が挙げられます。三国志最強の英雄である曹操は、生涯でほとんど負けることがなかった。最も危険だったのは、西涼で馬超に出会ったときだ。彼は潼関から逃げるために、ひげを切り、衣服を捨てなければならなかった。彼はまた、「馬が死んでいなければ、埋葬する場所がない」とため息をついた。ひげを切り、衣服を捨てる過程は特に驚くべきものである。 その時、曹操の軍は敗れ、西涼の兵士たちはあまりにも凶暴だったので、曹操の兵士たちは抵抗することができなかった。西涼の兵士たちが「赤い服を着ているのは曹操だ!」と叫ぶ声だけが聞こえた。曹操はすぐに赤い服を脱いだ。すると、大きな叫び声が聞こえた。「ひげを生やしているのは曹操だ!」曹操は驚いて、すぐに剣でひげを切り落とした。 軍の誰かが馬超に曹操がひげを切ったことを伝えた。馬超は人々にもう一度叫ぶように命じた。「ひげの短い方が曹操だ!」曹操はその叫び声を聞くと、すぐに服の端を引き上げ、顎を包み、逃げ去った。後世の人は次のような詩を書いた。「潼関での敗北後、孟徳は慌てて逃げ出し、錦の衣を脱ぎ捨てた。髭を刀で切られて驚いた。馬超の名声は天のように高かった。」 しかし、諸葛亮の知性と才能を考えれば、どうしてこのような強力な将軍を使わずにいられるのでしょうか? 実はこれには理由があります。 まず、「馬超を制御するのは難しい」。 関、張、黄、趙などの武将たちと違い、馬超は名家の出身で文武両道の人物であり、中原を制覇することが真の目標であった。諸葛亮はこのような人物を制御できるかどうか確信が持てず、放っておくことしかできなかった。それどころか、馬超の弟である馬岱は王の補佐官としてより才能があった。そのため、馬超が亡くなった後、馬岱が再び起用された。 第二に、「馬超が劉備に降伏したのは彼の当初の意図ではなかった。」 その時、張魯は諸葛亮の罠に陥り、馬超は降伏せざるを得なかった。馬超のような文武両道の人物は、力で完全に征服しない限り、喜んであなたのために働くことはないでしょう。当時、蜀漢陣営には馬超を抑えられる将軍はいませんでした。張飛のような勇敢な将軍でさえ、馬超と対峙して優位に立つことはできず、諸葛亮は知恵で降伏する戦略に頼らざるを得ませんでした。 馬超は劉備に降伏した後、生涯最後の7年間でたった一度しか戦わず、他の五虎将軍に比べてはるかに少ない回数でした。その後、曹魏は五方面から侵攻しましたが、そのうちの一つは馬超と親交のあった西羌族でした。 馬超は羌族などの遊牧民に対する強さで常に有名であり、羌族を威圧し脅迫することに多大な貢献をしました。このとき、馬超の戦闘意欲は非常に強く、諸葛亮は彼をこれ以上抑えることができず、流れに身を任せ、馬超が人生最後の戦いを簡単に終えられるようにしました。馬超は才能があるのに、蜀漢に降伏した後何もしなかったのは残念だ。残念だ! |
<<: どのような人が英雄とみなされるのでしょうか?暴君、悪役、そして英雄の違い!
>>: 真の統一とは何でしょうか?ナショナリズムが蔓延する中、中国はどのようにして偉大な統一を成し遂げたのでしょうか?
推薦する
清軍が最終的に関門に入ることができるかどうかの鍵は、なぜ呉三桂ではなく李自成にあると言われているのでしょうか。
清軍が最終的に峠に入ることができるかどうかの鍵は、呉三桂ではなく李自成にかかっていた。しかし、もし山...
『紅楼夢』における秦克清の判決は何ですか?恋人同士が出会うと、必然的に情欲を抱くというのはどういう意味でしょうか?
『紅楼夢』で最も謎の多い登場人物といえば、秦克清が筆頭に挙げられるだろう。次は興味深い歴史エディター...
徐玲の有名な詩の一節を鑑賞する:夫を想う女は二階にいて、窓辺で眠ってはいけない
徐霊(507-583)、号は暁牧、東海潭(現在の山東省潭城市)の出身で、徐志の息子である。南朝梁・陳...
古代に処刑された人々は誰だったのでしょうか?明代の方小如はなぜその十氏族とともに処刑されたのか?
今日は、Interesting History の編集者が、古代に一族全員とともに処刑された人々は誰...
蘇軾の『臨江仙・千穆父への別れ』は、作者の開放的で自由な性格を反映している。
蘇軾は北宋中期の文壇のリーダーであり、詩、作詞、散文、書道、絵画などで大きな業績を残した。彼の文章は...
『紅楼夢』で呉錦霄はなぜ大晦日の前日に賈邸に行ったのですか?理由は何でしょう
『紅楼夢』の容家と寧家は都の貴族として裕福で華やかな生活を送っていました。これについて考えるとき、あ...
呂兆霖の『城南の戦い』は唐代初期の外国との戦争の実態を反映している
呂兆林(?-?)、雅号は盛之、号は有有子、渝州樊陽(現在の河北省涛州市)の人であり、唐代の詩人である...
「スクリーン四行詩」をどう理解すべきでしょうか?創作の背景は何ですか?
スクリーン四行詩杜牧(唐代)周芳は画面に細い腰を描いたが、時が経つにつれて色が半分ほど褪せてしまった...
古代における「側室」の地位はどのようなものだったのでしょうか? 「Ji」と「Qi」は同じですか?
古代の「側室」の地位はどのようなものでしたか?「妾」と「側室」は同じものですか?一緒に学んで参考にし...
曹操が江東に軍隊を送る前に、賈詡はどのようなコメントや提案をしましたか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』で、西仁は宝玉と一緒にいたかったので家に帰りたくなかったのですか?
希仁の本名は真珠で、賈夫人に仕える女中であった。これについて言えば、皆さんも聞いたことがあると思いま...
水滸伝の蔡青のあだ名の由来は何ですか?彼にはどんな物語があるのでしょうか?
『水滸伝』の特徴は、官僚が民衆を反乱させて涼山へ向かわせるという点にある。 「涼山に追いやられる」と...
「Nine Quatrains, No. 5」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
九つの四行詩、第5番杜甫(唐代)川沿いの春も終わりに近づき、心が痛みます。香り漂う島を杖をついてゆっ...
『後漢演義』第89話の主な内容は何ですか?
劉玄徳は漢中を占領した後、王となり荊州を失い、関羽は義のために死んだ。しかし、黄忠は援軍を率いて陽平...
薛剛の反唐、第47章:王母を訪ね、彼女はニュースを聞いて泣き、馬将軍は率直に苦々しく語った
『薛剛の反唐』は、汝連居士によって書かれた中国の伝統的な物語です。主に、唐代の薛仁貴の息子である薛定...