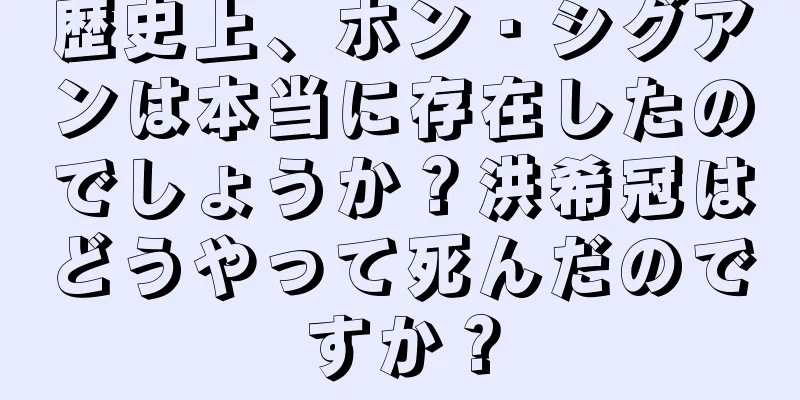古代における「側室」の地位はどのようなものだったのでしょうか? 「Ji」と「Qi」は同じですか?

|
古代の「側室」の地位はどのようなものでしたか?「妾」と「側室」は同じものですか?一緒に学んで参考にしましょう。 古代では、三人の妻と四人の妾を持つ制度が厳格に実践されており、いわゆる一夫多妻制であったが、より正確には、複数の妾を持つ一夫一婦制であった。古代では「礼儀」を重視していたため、妻が主導権を握り、残りは側室でした。側室は長女を敬わなければなりませんでした。当然、いわゆる寵愛を競う競争は古代では単なる冗談でした。長女は家族全体を支配し、側室には状況を好転させるチャンスがありませんでした。長女が亡くならない限り、長女になるチャンスがありました。 実は、古代に3人の妻と4人の側室を持つことは単なる仕掛けでした。古代人は妻を娶る選択の余地がなく、時には結婚する相手の容姿さえ見ることができなかったからです。結婚初夜にベールが上がったときだけ、相手の容姿を知りました。このような「礼儀作法」が形成されるのも、「平等な地位」の利害関係です。そのため、一部の裕福で権力のある家庭の妻たちはとても自信があり、夫たちはあえて一言も言いません。結局のところ、このような利害関係の結婚では、男性は「それを利用してトップに上り詰める」だけです。 もちろん、このような結婚には愛はありません。妻は山のような存在であり、家族内での地位は決して変わりません。しかし、このような関係に不満を抱く男性もおり、妾をめぐるスキャンダルが始まります。昔の妻が夫の好意を得るのは難しかったのはこのためですが、側室は真の愛でした。結局、側室を迎える基準は、夫が何を好むかです。 しかし、側室を持つことには制限がある。なぜなら、古代では人口は国の強さを測る必要条件ではあるが、十分条件ではなかったからだ。女性のほとんどが裕福で権力のある男性に占領されれば、独身男性の数が増え、人口の再生産率が低下し、それが国の戦闘力に直接影響するため、側室を持つことは制限された。明朝では、王子は側室を10人まで、郡君は4人まで、一般の官吏は40歳以上で子供がいない場合にのみ側室を持てると規定されていました。 しかし、昔の若者はそれほど気にしていなかった。上からの政策があるのだから、下からの対抗策は当然あった。側室を娶ることが許されなければ、妾を娶った。 妾とは、妾に従属する女性の一種で、妾よりもさらに地位が低く、書面による合意がなくても連れ戻すことができる。なぜなら、古代において「妾」とは、客を楽しませたり、客に仕えたりするために音楽や舞踊を披露する女性たちを指し、簡単に言えば側室の前身にあたる存在だったからです。 (運良く早く男性と結婚できた女性は側室と呼ばれるが、運が悪ければ女性の数が限られているため側室になることしかできない。) いくつかの歴史資料には「妓」の記録も残されている。妓の中には敗戦時に捕虜となった女性もいたが、買い戻された者もいたし、友人同士で贈り合った者もいた。これは特に唐代に顕著であった。妾が若い男の愛の対象であるならば、妾は彼にとって趣味を変えるための対象となる。白居易はかつて「九つの燭台の前に十二人の妾がいて、主人は彼女たちに酒を飲ませて楽しませる」という詩を書いた。これは鮮明な例ではないだろうか。 しかし、画面越しに見る人々を震え上がらせているのは、季の職務の内容だ。もともとは若旦那の趣味を変えるためのものに過ぎないと思われていたが、唐代の沈王李申と宰相楊国忠との「戦い」が、再び季の職務に挑戦を挑んだ。沈王李深は寒さを恐れていたため、側室たちを呼び寄せて寒さをしのいだ。楊国忠はそれを聞いて納得せず、雪の降る日に側室たちを全員呼び寄せ、さらに太った数人を選んで輪になって自分を囲み、公然と李深に挑戦した。昔、妾はいつでも楽しませるために歌ったり踊ったりする必要があり、そのため衣服は薄着であることが多い。その冬の大雪と吹き荒れる北風に耐えられた女性が何人いただろうか。 |
<<: 『封神演義』の熹奇と超歌は今どこにいるのでしょうか?神話の首都の地理的位置の分析!
>>: 古代ではコショウはどれくらい高価だったのでしょうか?皇帝は本当にそれを給料の支払いに使ったのですか?
推薦する
政府は明朝の将軍たちに使用人を雇う費用を支払ったのですか?使用人の用途は何ですか?
政府は明朝の将軍に使用人を雇う費用を支払ったのでしょうか?使用人の用途は何だったのでしょうか?『In...
皇帝の芸術とは何ですか? 「天皇の芸術」の真髄を3つの文章にまとめました!
統治の芸術とは何か?「統治の芸術」の真髄を3つの文章でまとめました!皆様のお役に立てれば幸いです。現...
徐在思の『人月園・甘露郷愁』:人生の浮き沈みと旅の孤独感を表現する
徐在思(1320年頃生きた)は元代の紀書家である。彼の礼儀名は徳科であり、かつて嘉興の役人を務めてい...
五虎将軍は世界中で有名だったのに、なぜ唐代は諸葛亮だけを名将とみなしたのでしょうか?
今日は、興味深い歴史の編集者が、唐代が諸葛亮だけを名将とみなした理由をお話しします。皆さんのお役に立...
『農桑紀薬』:薬草・レンコン全文と翻訳注釈
『農桑集要』は、中国の元代初期に農部が編纂した総合的な農業書である。この本は、智遠10年(1273年...
古典文学の傑作『太平天国』:帝部第四巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『紅楼夢』で劉おばあさんが初めて栄果屋敷に入ったとき、王希峰はいくらお金を渡しましたか?それはどういう意味ですか?
劉おばあさんは、中国の有名な古典文学『紅楼夢』の登場人物であり、王班児の祖母です。本日はIntere...
唐代の人々の話し方は広東語に似ていますか?
中期中国語は広東語のように聞こえますか? 「唐詩を300編読めば、詩を作れなくても暗唱できるようにな...
西遊記について知らなかったでしょうが、孫悟空には実は兄弟姉妹がいます!
はじめに:四大古典の一つである『西遊記』は誰もがよく知っており、今でも多くの人が喜んで語る話題です。...
三英雄五勇士第46章:韓章を毒で逃亡させ、貧しい人々を助けに行かせて趙青に会わせる計画
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
明代の数秘術書『三明通会』第2巻:四季について
『三明通卦』は中国の伝統的な数秘術において非常に高い地位を占めています。その著者は明代の進士である万...
旅詩とは何ですか?歴史上有名な旅行詩は何ですか?
旅の詩とは何でしょうか?旅の詩はどのような感情を表現しているのでしょうか?有名な旅の詩にはどのような...
唐代の制度はどのようなものだったのでしょうか?唐代の制度はどのような影響を与えたのでしょうか?
唐代の制度とはどのようなものだったのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみ...
古典文学の傑作『太平天国』:礼節編第27巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『紅楼夢』の冷子星の正体は何ですか?なぜ彼は賈家の状況を知っていたのか?
冷子星は『紅楼夢』の脇役です。このことについて話すときはいつも、詳しく話さなければなりません。 「あ...