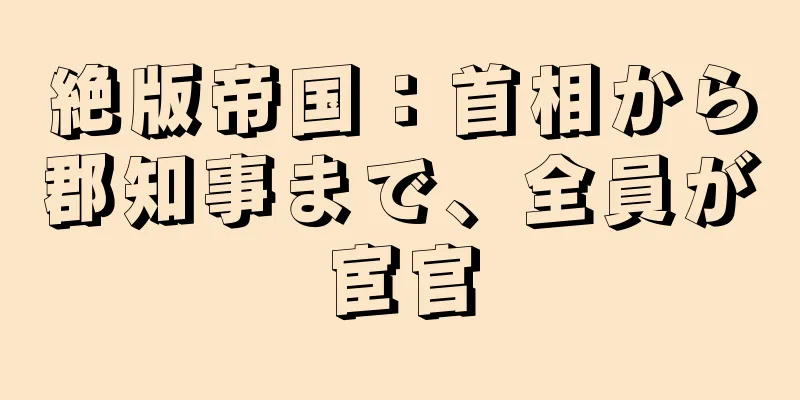曹丕の『典論』はどんな古典ですか?

|
曹丕の『典論』は中国文学評論史上初の専門論文である。それ以前に発表された文学評論作品は、『茅詩』のようにジャンルに焦点を当てたものか、王毅の『楚辞章居詩』のように特定の作品を題材にしたものであり、いずれも基礎文学理論の観点から普遍的な意義を持つ法則、範疇、命題を明らかにしたものではなかった。しかし、曹丕の『典論』の全文は600語余りに過ぎないが、論じられた内容には、すでに文学批評の姿勢、文体上の特徴の違い、作家の才能と作品のスタイルとの関係、記事の社会的地位と役割など、重要な理論的問題が含まれている。 『電論』で論じられた問題は簡潔に述べられただけで、詳細には触れられていないが、それが提起した問題がその後の文学批評に与えた影響は間違いなく広範囲に及んだ。それは建安年間の文学的自覚の重要な象徴となり、中国の文学理論と批評の自覚への道を開いた。 『典論』は中国文学理論史上非常に重要な位置を占めているため、歴史を通じて文学史や文芸批評の研究者の注目を集めてきました。記事の意味を説明したり、さまざまな角度からその理論的意味を探究したりする特別な研究は数多くあります。 『典論』は20章から成り、曹丕が皇太子時代に書いた政策的意味合いのある理論書、つまり曹魏の代に国家政策を策定する際に従わなければならない法典であると考える人もいる。曹丕が皇太子になったのは建安22年(217年)であるため、この見解は議論に値する。『典論』はおそらくこの年に書かれたものだが、本全体が一度に書かれたわけではない。この計算に基づくと、『典論』が曹丕が皇太子だった時代に書かれたと言うのは正確ではないかもしれない。つまり、曹丕は皇太子になる前は単なる王子であり、その上には漢の皇帝がおり、その下に父の曹操が王位に就いていた。彼が国家の政策や法律を策定できたかどうかは疑問である。また、『電論』には政治エッセイと物語エッセイの両方が収録されている。「エッセイ」などの章は芸術理論の問題を探求する作品であり、明らかに国家政策コードとして扱うことはできない。したがって、現代人の視点から判断すると、『典論』を総合的な理論的著作とみなす方が適切である。 『電論』という書名は、おそらくその書の性質と著者の執筆目的を反映しているものと思われる。 「経典とは規範と法則である」曹丕は書物を『典論』と名付けたので、その不変の理論を採用するつもりだった。 曹丕は『典論』を人々に広め、その息子である魏の明帝、曹叡は死後、この本を石に刻んで寺の門と大学に立て、『石経』と並べて置いた。これは、曹丕とその息子の心の中で『典論』が「不朽の格言」の古典とみなされ、儒教の経典に匹敵する地位にあったことを示している。同時に、曹丕がこの本を執筆した目的は、明らかに「不朽の言葉を確立する」という生涯の追求から生まれたものであることも示しています。曹丕は「独自の意見」で文学的名声を高め、後世に伝えたいと考えていました。このことは、曹叡が父の名声を広めるために石を彫るという具体的な手段によって確認されただけでなく、曹丕自身がこれについて明確な発言をしたことによっても確認された。 『典論』は「独自の見解を形成する」理論書であり、その性質は「不滅の格言」です。その地位は当時の支配者によって儒教の古典に匹敵する古典とみなされていました。著者の曹丕は、後世に自分の文学名を広め、不滅の願いを実現することを目的としてこの本を執筆しました。しかし、文学界の創作経験を総括し、文学の内的法則の諸相を探究する『古典論』という書籍の中の批評論文として、『随筆』自体に特定の論点がある。 著者はどのような意図で「論文」を書いたのか。しかし、このような問いに対して、これまでの研究者はそれぞれの理解に基づいて異なる意見を持ち、さまざまな発言がなされてきました。 『典論』の3番目の意見は、この論文が文学理論のさまざまな問題を一般的に論じているため、総合的な理論論文であると考える人もいます。これら3つの意見にはそれぞれ独自の理由があり、すべてテキストの各段落の意味に焦点を当て、さまざまな角度から根拠のある議論を分析しています。 さらに、曹丕が同時代の人々の作品を要約し、文学の規則性についての理解を解説する際の動機、態度、視点を探ることができます。そのためには、建安年間の社会的背景や文学的創作と合わせて研究する必要がある。建安時代は「文学の自覚」の時代であり、秦以前の哲学者の散文と漢代の詩と散文の輝かしい成果に続き、この時代の文学は五音節詩の大きな繁栄をもたらした。建安文学の繁栄には多くの理由があるが、文学史家たちがこの問題を論じる際には、必ず君主の奨励と模範的な指導が建安文学界の活発化の重要な原動力であったと指摘する。 |
<<: 古代中国では仲人にいくつの呼び名があったのでしょうか?古代の仲人は何と呼ばれていましたか?
>>: 曹丕が実施した「九階制」とはどのようなものだったのでしょうか?
推薦する
『山水鎮魔物語』第25章:八角井の船員が死体を回収し、鄭州殿の布大朗が三脚を献上した。
『山水討魔伝』は、羅貫中が書き、後に馮夢龍が補った、神と魔を扱った小説で、中国の有名な古典小説の一つ...
宋代の詩『応天長・天風布端』全文を鑑賞します。この詩の作者はどのような感情を表現したかったのでしょうか。
英天昌・田风布奴 [宋代] 周邦厳、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみ...
秦観が春の閨房について書いた詩:「画廊の春:東風が柳を吹き、日が長くなる」を鑑賞
秦観は春の閨房について「花堂春」という詩を書きました。次の興味深い歴史の編集者はあなたに詳細な記事の...
唐代の詩『麗州南都』をどのように鑑賞するか、また文廷雲がこの詩を書いた意図は何だったのか?
麗州の南方への移住、唐代の文廷雲については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみまし...
2015年のラバ祭りはいつですか?ラバ祭りで食べるもの
はじめに:莘八節は中国漢民族の伝統的な祭りで、私たちのお気に入りの伝統的な祭りの一つと言えます。人々...
トゥチャ族の習慣 トゥチャ族の結婚式の習慣における豚足の役割は何ですか?
農村部のトゥチャ族社会では、親戚や隣人との関係が密接です。ある家族に何かあると、みんなで手伝います。...
『孔雀は南東へ飛ぶ』では、なぜ焦仲青と劉蘭芝は一緒になれないのでしょうか?
「孔雀は南東へ飛ぶ」に非常に興味がある人のために、Interesting Historyの編集者が参...
薛剛の唐に対する反乱第83章:大臣たちは周の軍隊と戦って敗北し、羅昌は密かに唐を助けるために軍隊に加わった
『薛剛の反唐』は、汝連居士によって書かれた中国の伝統的な物語です。主に、唐代の薛仁貴の息子である薛定...
エウェンキ春祭りはエウェンキ族にとって最も重要な祭りです。
エウェンキ族にとって最も重要な行事は、人々が焚き火を囲んで集団でダンスを披露する春祭りです。猟師と女...
なぜ『紅楼夢』で黛玉は西仁を義姉と呼んだのですか?彼女は怒ってないの?
『紅楼夢』のヒロインである黛玉は、『金陵十二美女』本編に登場する二人のファーストネームのうちの一人で...
『紅楼夢』のタンチュンはどのようにして大観園を管理する機会を得たのでしょうか?
賈丹春は曹雪芹の『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の一人です。上記の疑問は、次の文章で『おもしろ歴...
杜甫の古詩「瞿塘二崖」の本来の意味を理解する
古代詩「瞿塘の二つの崖」時代: 唐代著者: 杜甫三峡はどこにありますか?二重の断崖がこの門を雄大に見...
孝文帝の改革以前、北魏の主な税収源は何でしたか?
孝文帝の改革以前、北魏の税制は主に部族への貢物、遊牧民からの畜税、一般農民からの地代と税で構成されて...
世界で最も多くの土地を失った 5 か国のうち、最も多くの土地を失った国はどこですか?
5. ドイツドイツは二度の世界大戦の後、大きな損失を被った。西では、ドイツとフランスの間で係争となっ...
歴史上「桃園の誓い」は存在しないのに、なぜ劉備は関羽と張羽を王にしなかったのでしょうか?
周知のように、桃園における劉、関、張の兄弟愛は、後世の兄弟愛のモデルとなりました。もちろん、実際の歴...