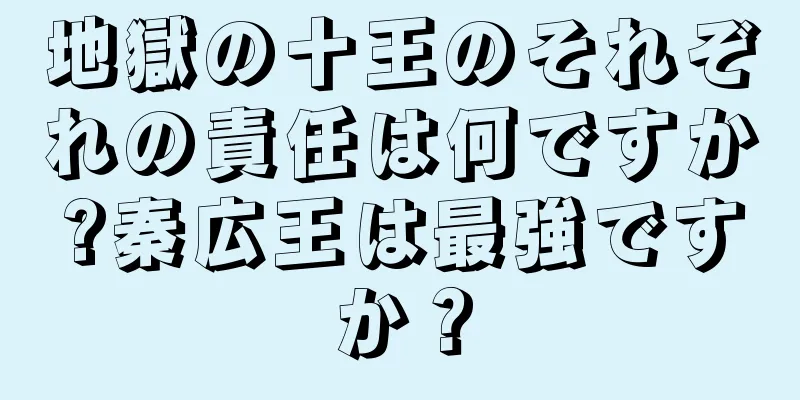古代において「長生き」とは皇帝のみを指すのでしょうか?明代の「万歳歌老」とは誰ですか?

|
今日は、Interesting Historyの編集者が、明代の「万歳歌老」とは誰なのかをお話しします。興味のある読者は編集者をフォローして見てください。 古代中国では、「万歳」という言葉は一万年生きることを意味するだけでなく、皇帝の同義語でもあります。「万歳」と「万歳夜」はどちらも皇帝を指します。多くの時代劇では、庶民や大臣が皇帝に頭を下げるとき、よく「皇帝万歳、皇帝万歳、皇帝万歳!」と叫びます。 中国文化は奥深く広大です。「長寿」という言葉は、王朝や状況によって意味が異なります。例えば、明朝の慣習によれば、大臣たちが「皇帝万歳」と叫ぶと、それは彼らの仕事が終わったことを意味した。これは大臣と皇帝の間の暗黙の掟のようなものでした。「万歳」という言葉が発せられるとすぐに、皇帝はそれをすぐに理解し、「皆さん帰っていいですよ」と言いました。 論理的に言えば、「長寿」は皇帝の標準であるはずですが、明朝には「長老長寿」というあだ名の大臣がいました。彼はどこから来たのでしょうか? 「万水閣老」の本名は万安。明代の太政大臣で、号は荀基。梅州の出身で、正統13年に進士となった。彼が「万水閣老」と呼ばれるようになったのは、政治家としての経歴の中で、恥知らずなことをしたためである。 万安は太書記であり、いわゆる太書記は明代の宰相であった。総理大臣になれるということは、この人には何らかの能力があるということだが、その能力はあなたが思っているものとは少し違うかもしれない。彼が最も得意とするのは、日和見主義と陰謀である。 成化7年(1471年)、天に不思議な現象が現れました。大臣たちは、皇帝と大臣たちが長い間離れ離れになり、多くのことが適切に処理できないと考えました。神は我慢できず、奇妙な現象を降らせました。唯一の解決策は、皇帝が大臣たちを召集して政治を議論することでした。率直に言えば、皇帝と大臣たちは長い間会っていなかったため、仕事の総括会議を開く時期が来ていたのです。 太秘書の彭石と尚陸は、大臣の中で最も活動的な二人であり、彼らの強い提言により、明の皇帝献宗は彼らを召集しなければならなかった。彭石と尚陸とともに皇帝に会いに行ったもう一人の人物がいた。その人は万安であった。 3人が宮殿に入った後、内務省の宦官たちは特に彼らに警告しました。「陛下と会うのは初めてなので、あまりしゃべらないでください。後回しにできることもあります。」3人の中で、婉安だけがこれを心に留めていました。他の2人は献宗皇帝に伝えたいことがたくさんあり、時間が足りず、すべてを報告し終えられないのではないかと心配していました。 彭石と尚陸は明朝の皇帝憲宗に会った後、都の役人の給料を削減しないことを提案した。憲宗は同意した。彼らが次のことを報告しようとしたとき、横にいた万安が突然頭を下げて「皇帝万歳」と叫んだ。これを見て、彭石と尚陸はひざまずいて同時に「皇帝万歳」と叫ばざるを得なかった。この綿密に準備された政治会議は、このようにして終わった。 大臣たちはついに明朝の献宗皇帝を捕らえ、解決すべき問題がまだたくさんあったが、万安の「皇帝万歳」の叫びによってそれらはすべて無駄になった。明代の皇帝、献宗はもともとこの会談を楽しみにしていたが、自分の配下の大臣たちが、給料を減らさないという些細なことで自分のところに来るほど「無能」だとは予想もしていなかった。それ以来、明代の皇帝である献宗は、大臣たちに非常に失望し、大臣を召集することを基本的にやめました。 その後、太政大臣の尹之も献宗皇帝と直接国政について話し合いたいと思ったが、万安は「彭公は皇帝に呼び出されると、何かおかしいと分かるとすぐに頭を下げて皇帝万歳と言った。これはおかしい!私の意見では、大臣として、国政について知っていることはすべて皇帝に伝え、宦官は皇帝に報告すればいい。皇帝と直接国政について話し合うよりずっといいではないか」と言って思いとどまった。 その時、彭石はすでに亡くなっていた。万安は自分に不利な証拠がないことを知っていたので、恥も外聞もなく自分の欠点をすべて彭石に押し付けた。この事件のせいで、万安は「万水閣老」という非常に皮肉なあだ名を付けられた。彼が閣老と呼ばれた理由は、万安が合計18年間太書を務めたためである。 この事件に加えて、万安は明朝の孝宗皇帝への追悼文の中で性技について語るという、前例のない、比類のないことを成し遂げた。明朝の孝宗皇帝は激怒し、万安を辞任させようとしたため、宦官の淮恩を遣わして万安に問い詰めた。「大臣がそんなことをするのか?」 予想外に、万安はあまりにも頑固で、ひたすら卑屈になり、辞任について話すことを拒否した。当時の人々は万安を嘲笑し、「彼の顔は千層の鉄の鎧のようであり、彼の心は九つの曲がり角を持つ黄河のようだ」と言った。 成化23年(1487年)、万安は隠居し、2年後に死去した。死後、太師の号と文康の諡号が贈られた。 |
<<: 古代史における派閥争いの典型的な事件の類似点と相違点は何ですか?
推薦する
元朝の皇帝舜の実の両親についてはどのような記録がありますか?後世の人たちはどんな予想外の意見を唱えたのでしょうか?
元朝の舜帝、斉臥斗桓帝は延暦7年(1320年)に生まれ、元朝の明宗皇帝の長男であった。智順4年(13...
『紅楼夢』では、ジェン・シーインのジャ・ユークンへの投資は価値がある
「紅楼夢」では、甄世銀と賈玉村が出会ったのは、賈玉村がまだ無名だった頃です。甄世銀は賈玉村に投資しま...
紫禁城の屋根の上にいる老人は誰ですか?紫禁城の屋根にはなぜ老人が彫られているのでしょうか?
紫禁城の屋根に彫られた老人が何者か知っていますか? 知らなくても大丈夫です。Interesting ...
「過去の夢」はどんな物語を語っているのでしょうか?楽園はどこにあるのでしょうか?
「南克易夢」の物語とは?地上の楽園はどこにある?我が国の歴史上、唐代の徳宗皇帝の治世に、東平県に淳于...
楚漢戦争が勃発した後、なぜ英布は項羽を裏切り、劉邦に服従することを選んだのでしょうか?
秦末農民反乱は、秦末農民反乱とも呼ばれ、中国本土では秦末に多くの英雄が台頭した事件に付けられた名前で...
王安石はなぜ解任されたのか?事件の全過程はどうだったのですか?
西寧七年(1074年)の春、全国に大干ばつが起こり、飢えた民が避難した。大臣たちは旅費免除の弊害を訴...
李白の『摘蓮歌』にはどんな蓮摘み娘が描かれているのでしょうか?
李白の『摘蓮歌』には、どのような蓮花採りが描かれているのでしょうか。この詩は、六朝以来の蓮花採りのイ...
「勅使」とはどういう意味ですか? 「皇帝の特使」が到着したとき、なぜ地方の役人たちはそれほど恐れたのでしょうか?
本日は、Interesting History の編集者が「帝国特使」の紹介をお届けします。皆様のお...
仏教はいつ中国に伝わり、どのようにして中国に広まったのでしょうか?
仏教はインドから中国に伝来した後、長い時間をかけて普及・発展し、中国の国民的特色を持つ中国仏教を形成...
陸俊義が張青を捕らえて殺したい場合、どのような方法がありますか?ウー・ソンがすべてを語った
呂俊義が張青を捕らえて殺すつもりだった場合、どのような方法を使ったでしょうか? よく分からない読者は...
「赤が緑に変わるのを見て、私の心は考えでいっぱいになり、あなたが恋しくてやつれて衰弱する」という有名なセリフはどこから来たのでしょうか?
「赤が緑に変わるのを見て、私の考えは混乱し、あなたが恋しいので私は疲れ果てています」という有名な言葉...
一族全体が関与しているとされる人々はなぜ逃げないのか?
九族に関係した人々はなぜ逃げなかったのか? やはり、古代には身分証明書もカメラも写真もなかったのだ。...
古代の「四大発明」の授業中止はどうなったのか? 「四大発明」はどれほどの影響力があるのでしょうか?
古代の「四大発明」が中断されたとき、何が起こったのでしょうか?「四大発明」はどれほどの影響力を持って...
皇室の側室制度は『二十四史』の中でどのように発展したのでしょうか?
皇帝のハーレムの女性メンバーに関しては、ここでは皇帝の楽しみと奉仕のために使われる女性たちを指します...
『紅楼夢』で王希峰はなぜ宝玉の誕生日パーティーに出席しなかったのですか?理由は何でしょう
『紅楼夢』第63話では、宝玉の誕生日は、家の中の女中たちが主人への孝行を示すために密かに開いたプライ...