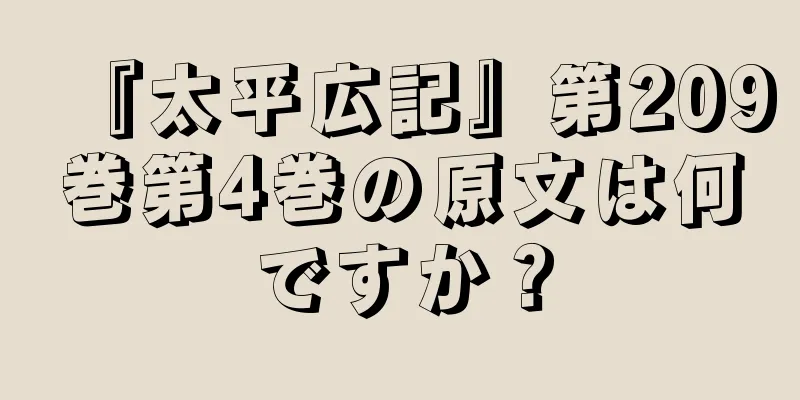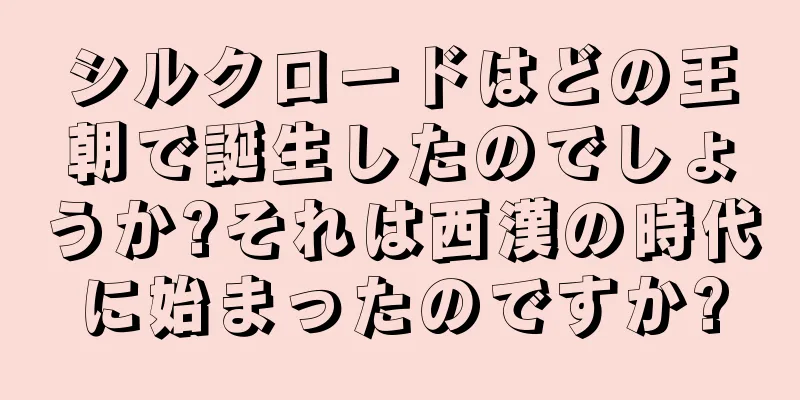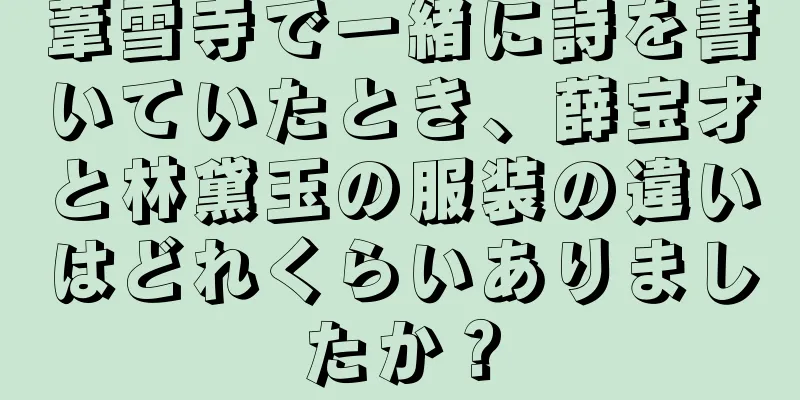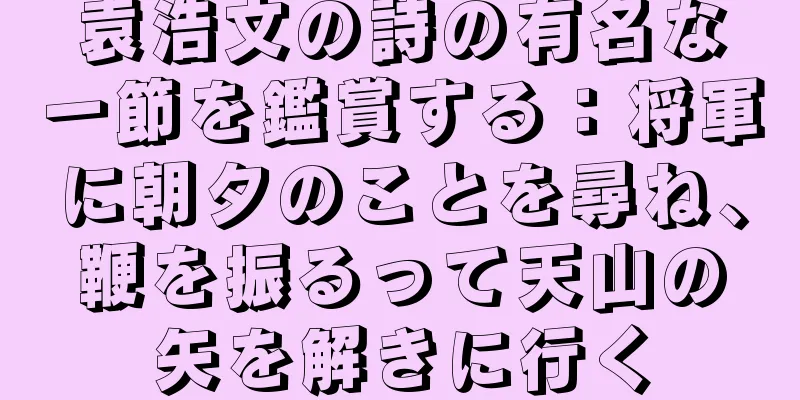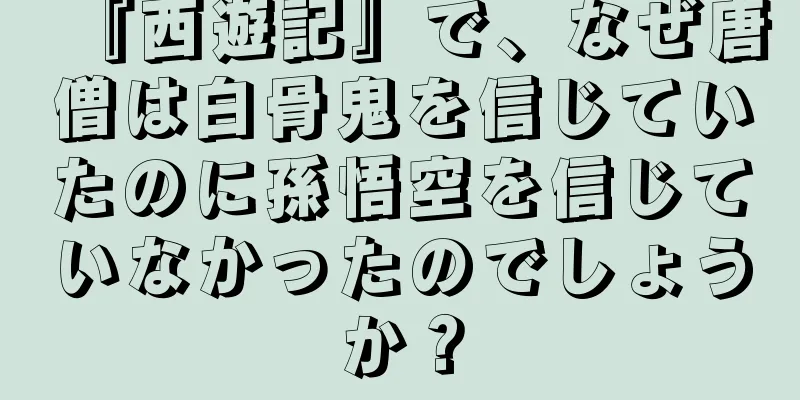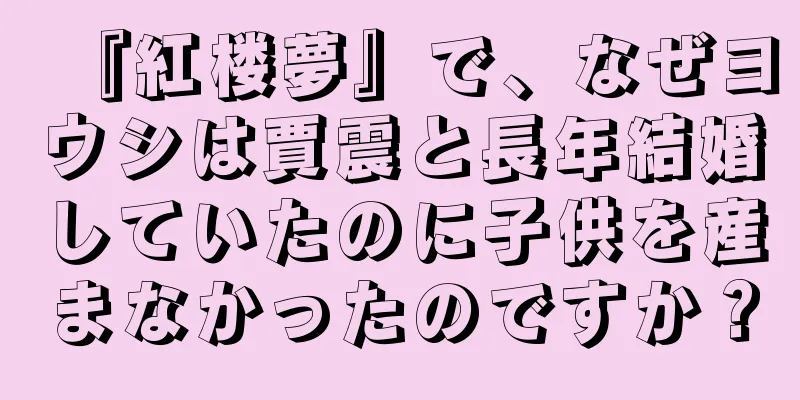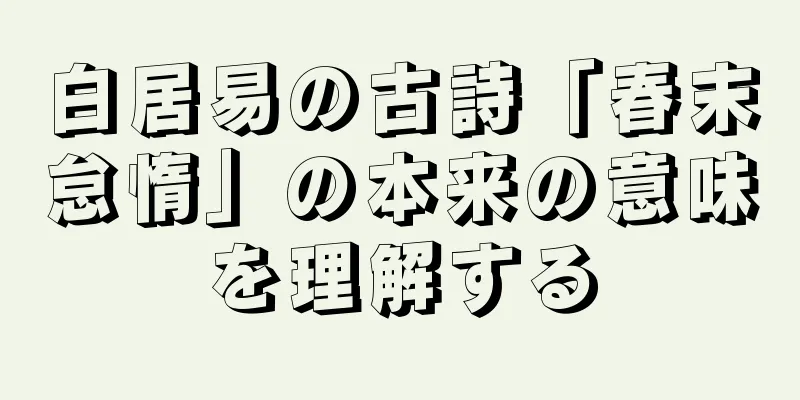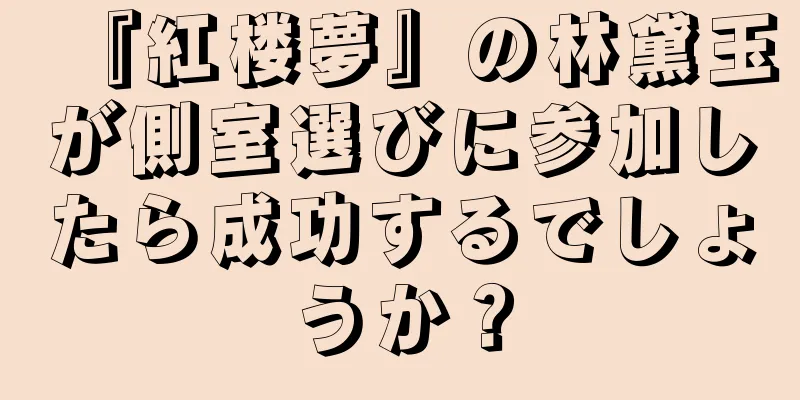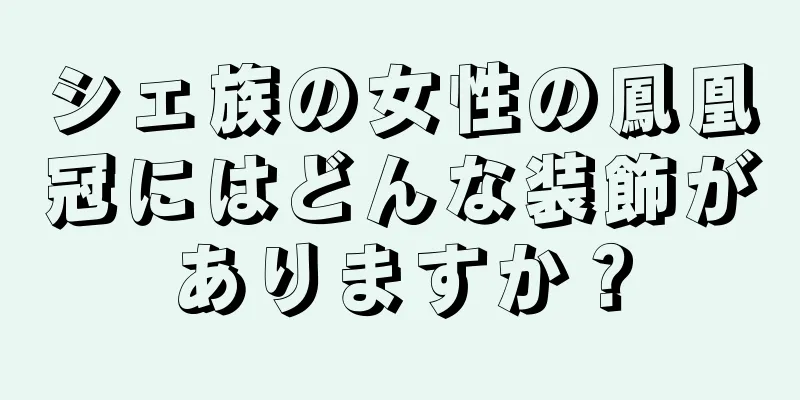「隋木」の原文は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
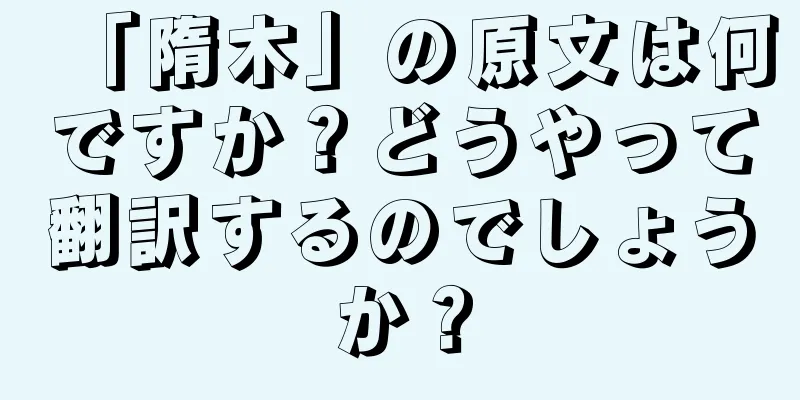
|
年末 杜甫(唐代) 年末、私は遠く離れた客人であり、国境では依然として戦争が続いています。 煙と砂塵が雪山を襲い、太鼓と角笛の音が川沿いの街を揺るがします。 世界は血に染まっている、誰が朝廷に仕えることを志願するのか? 季詩は死を愛する勇気があるか?孤独で強い心が衝撃を受ける! 翻訳 異国の地の客人として新年が近づいているが、国境戦線では戦争がまだ続いている。 敵が雪嶺に侵入したという警報が鳴り響き、軍の太鼓と角笛の音が江の城を揺るがした。 最前線の兵士たちは昼夜を問わず血を流し、命を犠牲にしている。宮廷内に戦いに参加したい者はいるだろうか? 国が危機に瀕しているとき、どうして私は命を惜しむことができましょうか。国に奉仕する方法はありませんので、私には英雄的な精神しかありません! 感謝 詩のタイトルにある「水木」という2つの単語は、まるで「年が暮れ、北風が吹いている」かのような寂寥感を直感的に感じさせます。さらに、2つの単語は平坦な調子で、詩全体の調子を低くして暗い色を投じているかのようで、詩はさらに憂鬱で暗い感じに聞こえます。この詩は国境紛争と困難な状況を描写しているが、宮廷では誰も敵と戦うために志願せず、詩人は孤独に孤立して異国の地をさまよっている。この詩は宮廷の卑怯で無能な大臣たちに対する詩人の非難と、果たされなかった野望に対する苦悩を表現している。詩全体は簡潔な言葉で、誠実な感情を込めて書かれています。 最初の連句は「年末、私は遠くの客人」です。「遠く」という言葉は成都の茅葺き屋根の家ではなく、私の故郷である河南省を指しています。詩人は四川省西部に亡命し、他人の家に住む旅人のような生活を送っていたため、自分は「遠く離れた客人」であると嘆いていた。しかし、西蜀の一角では依然として不安が残っていたため、次の文では「国境地帯では依然として軍隊が使用されている」と書かれています。 「还用兵」の「还」は静止という意味で、西蜀に避難して仮住まいはできたものの、ここでまだ戦争が続いているとは予想していなかったことを表しています。また、「还」という字は何度も繰り返されるという意味で、中原の戦争はまだ終わっておらず、四川の徐志道の反乱は鎮圧されたばかりなのに、吐蕃の侵略がまたやって来て、戦争はいつまでも終わらなさそうだという意味です。 「また」という言葉は、人生や時事問題に対する詩人の失望と嘆きを暗示しています。このことから、杜甫の言葉を洗練させる技術がわかります。ごく普通の言葉でも、杜甫が書いたものは鋭く意味深く、熟考する価値があることがよくあります。当時、吐蕃の脅威はますます深刻になっていました。その年の7月、吐蕃は和龍を侵略して占領し、10月には長安を攻撃しました。唐の代宗皇帝は山州に逃げました。12月には宋、衛、鮑の3州(すべて四川)を占領し、雲山に2つの新しい城を築きました。西川の知事高石は抵抗できず、四川全体が衝撃を受けました。 2番目の連句「煙と塵が雪山を襲い、太鼓と角笛の音が河城を揺るがす」は、前の連句「兵を用いる」に続き、吐蕃の蜀侵攻を具体的に描写しています。 「煙塵」とは吐蕃軍が通った空が塵で覆われていることを意味し、吐蕃軍のことを指します。 「太鼓と角笛の音が城壁を揺らす」とは戦争の準備を描写している。 「动」という言葉は、戦争の緊急性と状況の深刻さを示すだけでなく、チベット侵攻が社会にもたらした混乱も表しています。この連句は、非常に警告的で、生々しい。最初の文は雪嶺を描写し、2番目の文は河城を描写している。最初の文は吐蕃を描写し、2番目の文は唐軍を描写している。最初の文は聞いたもので、2番目の文は自分の目で見たもので、一つは遠く、一つは近く、吐蕃の来襲の激しさとそれが社会に引き起こした衝撃を要約し、生々しく描写している。 「天地は日々血を流している、誰が朝廷に仕えることを志願するのか」という連句は吐蕃の侵攻以来の情勢を指しており、安史の乱以来の現状を高レベルで要約したものでもある。内外の紛争の攻撃を受け、人々は日々血を流し、うめき声を上げており、国は極めて危機的な状況にあります。 「誰が朝廷に仕えることを志願するのか」という一文は、当時の貪欲で権力欲が強く、臆病で無能な文武両道の官吏に対する杜甫の風刺と叱責であり、彼の深い失望と怒りを表現している。杜甫は彼らとは違っていた。彼は若い頃から「王を堯や舜のように偉大なものにする」という野望を抱いていた。国が危機に瀕し、民が苦しんでいるとき、彼は国のために自らを犠牲にすることをいとわなかった。 最後の連句は「時を節約するために、どうして死を愛せよう」です。時を節約し、人々を救うために、どうして自分の命を愛し、安楽に暮らせるのでしょうか。杜甫は「志願」したかったのですが、命を犠牲にする意志はあっても、国に奉仕する方法がありませんでした。方佩を救出して以来、彼は朝廷から無視され、四川省西部に亡命して他人の世話を受けながら暮らしていた。彼の命もしばしば危機に瀕していたのに、どうして国政を司る機会や条件があったのだろうか。 「孤独は私の高尚な野望を震わせる。」人里離れた片隅で孤独に暮らした数年間、詩人の高尚な野望は日に日に消えていった。彼はそのことを思い出すたびに怒りを感じ、驚いてテーブルを叩かずにはいられず、心が張り裂けそうになった。 この詩では、最初の4行は主に時事問題を描写し、最後の4行は主に詩人の心情を表現しています。詩は明確な階層、整然とした構造を持ち、空虚な言葉はありません。すべての言葉に、詩人の現在の状況に対する深い憂慮と懸念、国に対する愛、凡庸で無能な文武官に対する失望と非難が込められており、また朝廷に評価されていないことへの苦悩と、満たされない野望も表現されています。 この詩の芸術的技法も非常に特徴的です。たとえば、換喩の修辞技法です。2番目の連句の「煙と塵」は国境紛争を表しており、後のテキストの「太鼓と角笛」に対応して、視覚と聴覚の両方の面から戦争の緊張を強調し、現在の状況の困難さを誇張しています。この詩にはまた、「请莹」などの隠喩的な表現も使われており、これは『韓書中君伝』に由来する。この詩は、朝廷には国のことを心配する人がいないことを暗示しており、それによって詩人杜甫が国政を深く憂慮していることを表現している。もう一つの例は、「並列表現」と「語呂合わせ」の使用です。詩の題名「遂牧」は表面的には年末を指していますが、より深いところでは杜甫が晩年を迎えたこと、また唐帝国が全盛期から衰退し、不安定な晩唐時代に入ったことを指しています。 この詩も、現実と想像の描写を組み合わせています。たとえば、「国境にはまだ軍隊がいて、煙とほこりが雪山を襲っている」や「朝廷で誰が志願するか」は杜甫の想像であり、想像上の描写です。「太鼓と角笛が城壁を揺らし、世界は毎日血を流している」は現在の状況であり、現実の描写です。朝廷に志願兵がいなかったことと、世慣れした杜甫の「死を覚悟した」ことの対比、杜甫の高邁な志と国に奉仕する方法がなかったことの対比など、表現技法にも対比がある。 「危機の時に死を愛する勇気はあるが、孤独で勇敢な心は怯えている」は、自らの言葉と行為の対比、「太鼓と角笛が城壁を揺らす」は、戦前と戦後の対比を暗示し、「私は遠くの客人である」で始まり、「私は孤独で勇敢な心は怯えている」で終わるのは、考えと気持ちの面からである。 背景 この詩は、おそらく763年(唐代光徳元年)末、吐蕃が蜀県北西部の宋州、渭州、宝州を占領し、杜甫が江東に向かおうとしていた頃に書かれたものと思われる。蘭州から船に乗って嘉陵江に沿って南へ航海する予定です。この詩は子を出発する前か、あるいは朗に到着した後に書かれたものかもしれない。 |
推薦する
劉邦と斉奎の息子である劉如意はどのようにして亡くなったのでしょうか?
劉邦が死ぬとすぐに、権力を握っていた呂太后は復讐の準備を整えた。特に、斉妃と趙の王太子如意とその母親...
紅楼夢で薛潘は何と言ったのですか?薛宝柴はなぜ一晩中泣いていたのですか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
『紅楼夢』では王夫人の劉おばあさんに対する態度はどのように変化しましたか?なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
『紅楼夢』では、王夫人の劉おばあさんに対する態度はどのように変化したのでしょうか?次は、興味深い歴史...
東周書紀第87章:秦の衛陽の改革、桂丘子の孫斌が山を去る
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...
『紅楼夢』で林黛玉は賈屋敷に入った後、どのように振る舞いましたか?
黛玉は中国の有名な古典『紅楼夢』のヒロインであり、『金陵十二美人』本編の最初の二人の登場人物の一人で...
鍾馗公は『紅楼夢』でいつ初めて登場しましたか?彼はなぜ賈邸に行ったのですか?
鍾順王は『紅楼夢』の中では非常に目立たないキャラクターであり、本人が直接登場することはありません。次...
「王朗思志に贈る短歌」の原文は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
王朗思志への短い歌杜甫(唐代)王朗は酒に酔って剣を抜いて地面を叩いた。悲しまないでください!私はあな...
古代の女性も男性と同じように運動していました。普段はどのような運動をしていたのでしょうか?
古代中国の女性もスポーツをしていましたが、彼女たちのスポーツは主に敏捷性と楽しさに基づいていました。...
『賈怡新書』第3巻の「時変」の原文は何ですか?
秦国は理性を失い、天下は敗れ、多数は少数を虐げ、賢者は愚者を欺き、勇者は怯む者から奪い、強者は弱者を...
シベ族の慣習や習慣におけるタブーは何ですか?
シベ族のタブー文化特定の歴史を持つ国であれば、長い発展の過程で何らかのタブーが生まれます。それは社会...
夷陵の戦いの後、勝者である孫権はなぜ勝利を追求しなかったのでしょうか?
三国志の強弱の転換点といえば、官渡の戦い、赤壁の戦い、夷陵の戦いという三つの大きな戦いを挙げなければ...
呉維野の「船をつかまえて」:著者は社会現実の矛盾を暴こうとしている
呉衛野(1609年6月21日 - 1672年1月23日)は、雅号を君公、号を梅村といい、陸喬生、観音...
蘇軾の詩「李公沢が高邑を通り過ぎ、石大夫と孫神老が花を愛でているのを見て、私に思い出させた」の本来の意味を鑑賞する
古詩「李公澤は高邑を通り過ぎ、石医師と孫神老に会い、花を鑑賞し、詩を思い出す、そして私の召使に宛てて...
唐代の唐三彩陶器の器体をどのように識別するか?胎児を偽造するのはなぜ簡単ではないのでしょうか?
陶器の素地や釉薬の形状、色彩スタイルなどの基礎知識は、唐三彩の真贋を論じるすべての記事で取り上げられ...
古典文学の傑作『太平天国』:第5巻蔡魯篇全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...