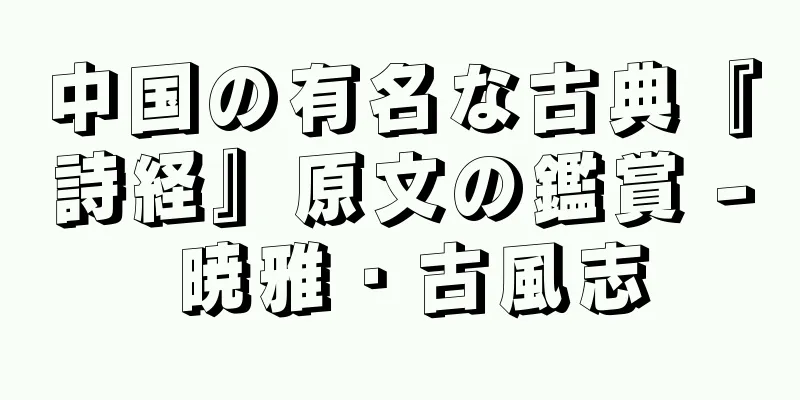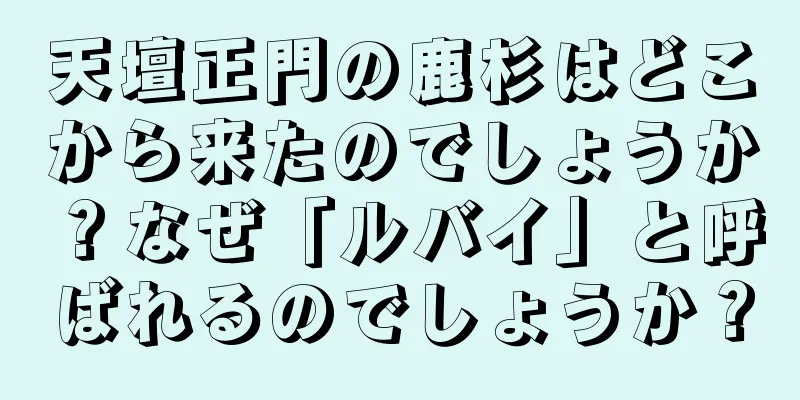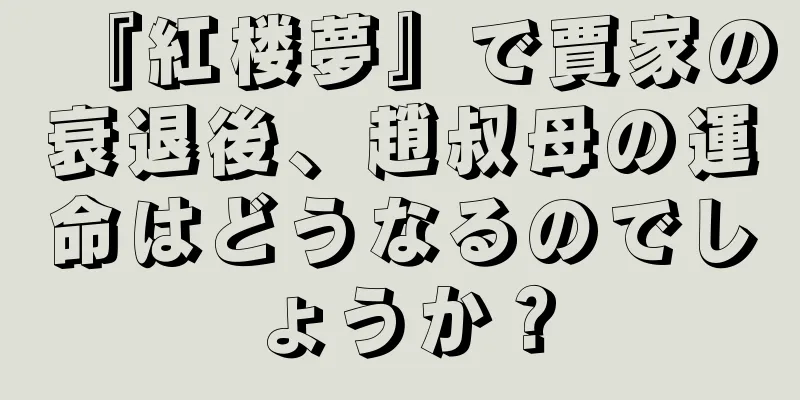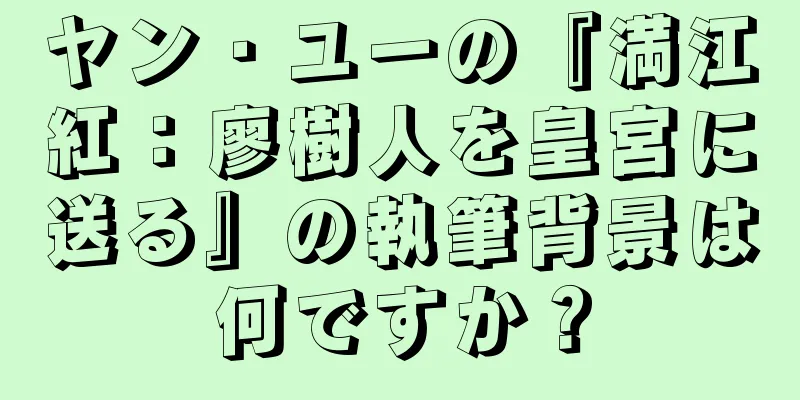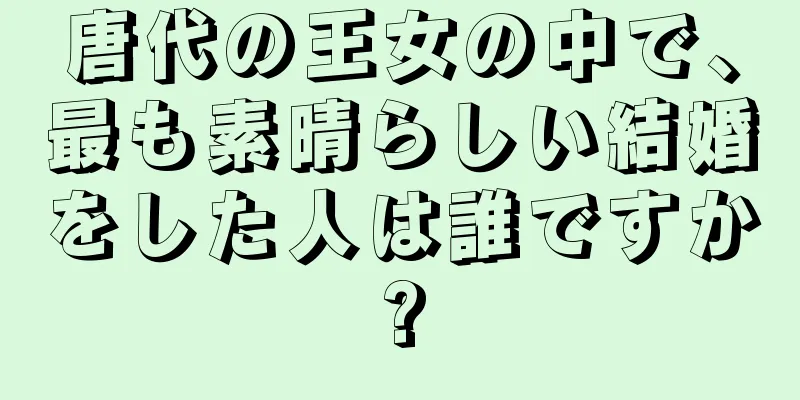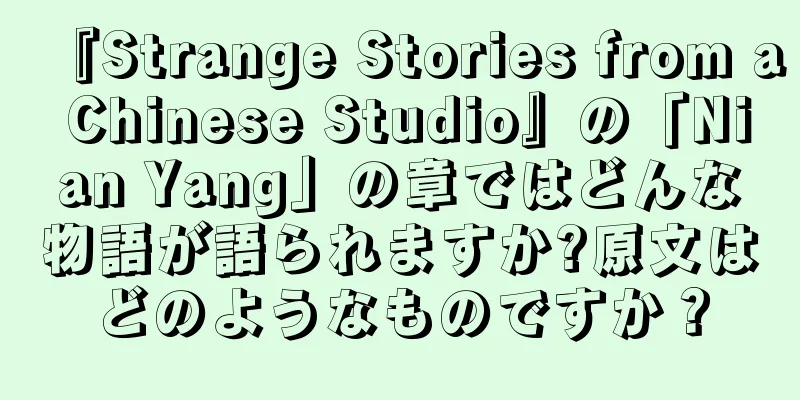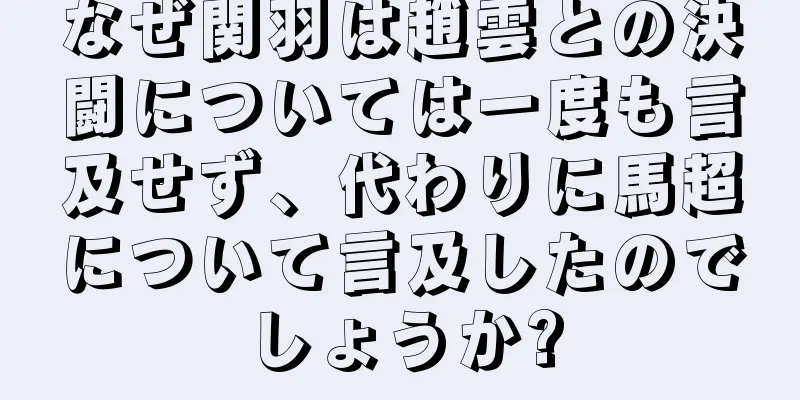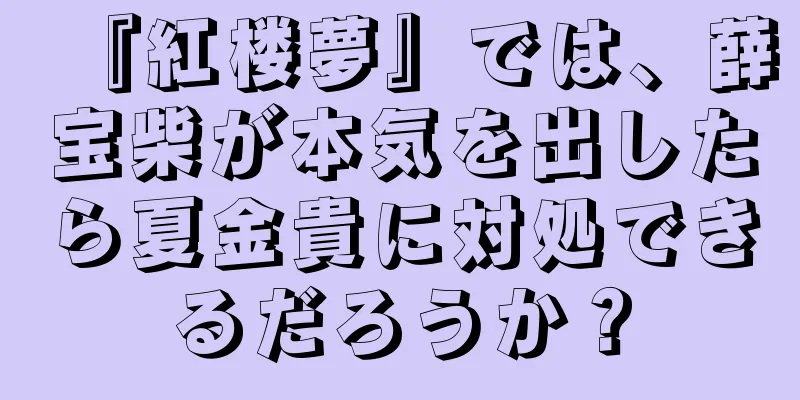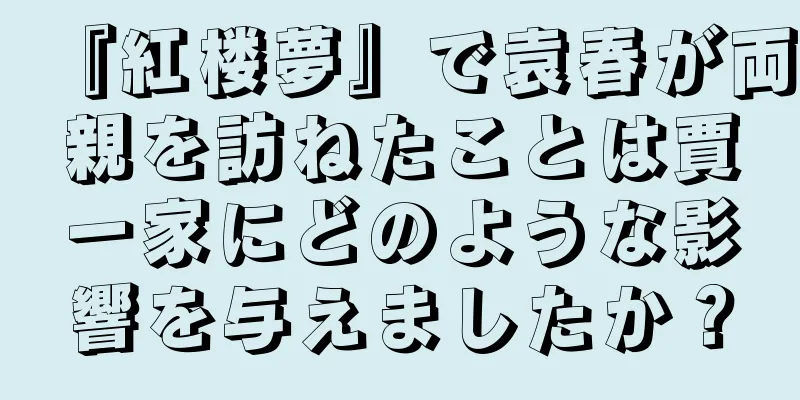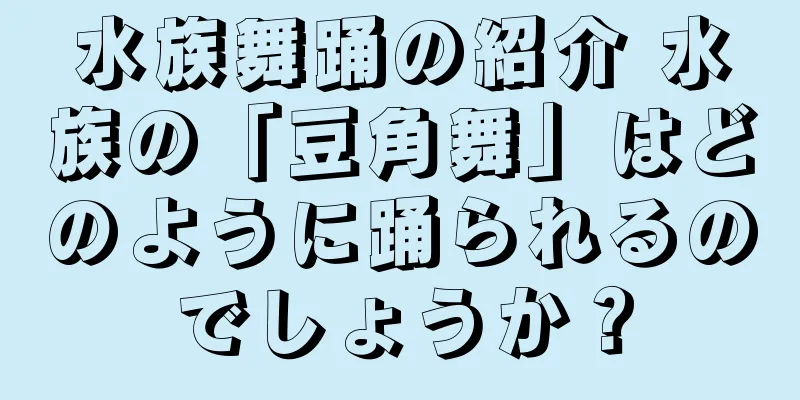陶淵明の最高傑作:晋代唯一の「帰郷」
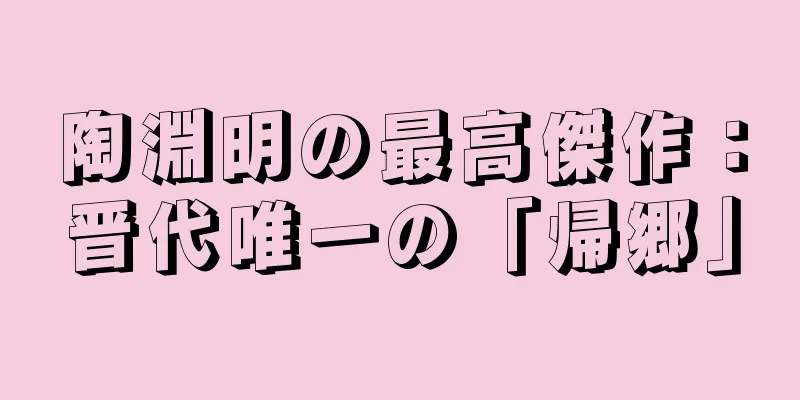
|
趙孟馨の書道作品「帰郷」より抜粋(データマップソースネットワーク) 李清昭は宜安居士と呼ばれていました。「宜安」という言葉は『帰郷記』の「宜安、座るところが狭い」という一節から来ています。李青昭さんが元明さんの記事を気に入ったのは、幼少の頃から父親の影響を受けたからだろうか。 陶淵明はこの『辞』の中で「兮」という字を多用しており、「兮」という字は『楚辞』(サオ風)の特徴である。そのため、多くの人は、円明の「帰依」は朱慈から来ていると信じています。しかし、円明の詩のスタイルは楚辞のそれとは大きく異なります。朱熹氏は次のように述べた。 「帰郷」という詩の言葉は寂しく悲しい。楚の声を使ってはいるが、恨みや悲しみは含まれておらず、実用的で意味深く、比喩も含まれている。 (明朗瑛の『七つの改訂』参照) 明代には孫岳峰が『文選』を評し、閔其華が注釈を加えて次のように述べている。 スタイルも「Chu Sao」に基づいていますが、「Sao」はより豪華で簡潔であるのに対し、「Sao」はより精巧で現実的です。その美しさは、すべての言葉が真実でありながら、すべての言葉が洗練されているという点にあります。一言で言えば、それは一種の自由で束縛のない興味を形成します。それは典型的な記事ではありませんが、優れた作品と言えます。 彼らは陶淵明の詩が「適切な記事」ではないと信じていますが、それはおそらく陶淵明が楚辞を学んだが、それを十分に学んでいなかったと考えているからでしょう。しかし、原典通りに学ばないからといって、それが良くないということではありません。清朝の劉熙載は次のように最もよく言い表しています。 「田舎に帰る」の「サオ」に習う必要はありません。どちらも独自の特徴を持っています。「真の古さ」と「古さの模倣」は異なることは明らかです。 (『芸術』『譜』第3巻) 『帰郷』と『李笙』の感情とスタイルにこれほど大きな違いがあるのはなぜか、清代の林雲明は非常に正確な分析をしている。 音節を注意深く味わうと、「Sao」は悲しくメロディアスであるのに対し、こちらは調和的で率直であることがわかります。蓋霊君は楚の親戚なので、王を懐かしむ温かい心を持っているはずだったが、袁良は晋の老人なので、ただ世間から逃げ出したいと願う冷たい目を持っていた。一つは吉と比、もう一つは易と気です。なぜなら、それらは異なる場所にあるからです。 (清代の林雲明の『漢詩集第一巻』第4巻) 霊君は屈原のことを指します。林雲明は、屈原は商代末期の夷子や碧干のように楚王家の縁戚であると信じている。屈原は前進することしかできず、後退することはできず、国に忠誠を尽くすことしかできず、引退することはできない。ボーイーやシュチと同様に、ユアンミンも新政権に協力しないという選択をする可能性があった。 なぜこの文章は「帰郷」というタイトルなのですか?林雲明は、陶淵明が彭沢県を離れたのは「帰郷」(中国語の古典では「去る」は去るという意味)であり、南村に戻ったのは「帰郷」であり、合わせて「帰郷」だと考えています。毛清凡も『残古文献』の中で、「職場にいるときは『帰る』といい、家にいるときは『帰る』という。だから『帰る』というのだ」と述べている。しかし、今日の学者の多くは、「来」は機能語であり、気分を表す補助語であり、実用的な意味はないと考えている。 「田舎に帰る」は短すぎるというわけではありません。長い記事を読むのが怖い人のために、金盛丹は次のようなアイデアを持っています。 古代人の長文は、すべて短い文の積み重ねでできています。たとえば、このスピーチは長くはありませんが、1つの段落に4つの文で構成されています。段落ごとに読んでみると、各段落が素晴らしいことがわかります。古代人は素晴らしい長文を書くことができませんでした。長い記事の美しさは、中間に短い段落を書くことにあります。 (安藤兵著『条文基準解説』第7巻より引用) そうすれば、「Returning」を 4 つの文から 1 つ 1 つ段落ごとに味わうことができ、おそらくそれほど長いとは思わないでしょう。しかし、各段落は 4 つの文のみで構成されており、断片的すぎます。 「帰郷」は押韻されており、陶淵明は合計5回押韻を変えています。つまり、陶淵明は押韻を利用してテキストを5つのセクションに分割したことになります。今では「田舎に帰る」を抜粋して4つのセクションに分けた本もありますが、第一セクションと第二セクションは韻律で区切られていません。最初の段落は「今日は正しく、昨日は間違っていたと気づく」までしか書かれていない。おそらく編集者は、ここまでの冒頭が俗世から退却する心理についてであり、続く「船は軽やかに航行する」から始まる段落で俗世から退却する具体的な行動について語られていると考えたのだろう。しかし、円明の韻文に従って分けると、最初の段落は冒頭から「非常にかすかな朝の光」までで、彭沢から帰る途中の気分や見たものを表現しています。次の行は「私は自分の家を見上げる」であり、家のドアが見えるから、自然と新しい段落が始まります。しかし、「子供を部屋に連れてくると、杯に酒がある」と「一人で杯を汲んで飲み、中庭の木々を眺めて元気づける」の韻は変化しているものの、意味的には依然として密接につながっているので、1つの段落にまとめます。この記事は多くの人が暗唱できるので、本文ではあまり詳しく説明しません。私は、原文と関連して古代人が残した代表的なコメントのいくつかを単に言及しているだけです。 家に帰りなさい。畑が草木で覆われそうなのに、なぜ家に帰らないのですか? 心は体に隷属しているのに、なぜ悲しくて寂しいのですか? 過去は変えられないが、未来は追い求めることができると理解しなさい。実際、あなたは正しい道から遠く離れておらず、今日が正しく、昨日が間違っていることを理解しているのです。船は軽やかに進み、風が私の服を吹き飛ばします。私は旅人に先の道を尋ねたが、薄暗い朝の光が嫌だった。 冒頭の「归去来兮」という語は2回使われ、最後の段落は「已矣乎」で始まる。清朝の呉起は『六朝選诗定论』でその役割を非常によく分析している。彼はこう言っている。「『归去来兮』は『归去来兮』という4つの語の代わりに使われている。最初の『归去来兮』という語は、夢から覚めたように使われている。帰ってきてからまだ時間が経っていないので、まだ夢であって目覚めではないのではないかと恐れ、もう一度呼ぶ。もうかなり時間が経ち、目覚めであって夢ではないので、もう一度『归去来兮』と呼ぶ必要はなく、『已矣乎』だけが使われ、退屈することなく諦めて世間から退いたことを示している。」 「田畑は草に覆われる」について、林雲明は「文章の冒頭にある『田』という二つの文字は、文章全体のアウトラインである」と提案した。呉奇も「『田』という二つの文字は二つの柱である」と述べた。なぜ「田」が二つの柱なのか?第二段落は家に帰ることについてであり、これは「庭」についてであり(「三道は草に覆われる」は庭が草に覆われていることを意味する)、第三段落は西の田んぼでの農業についてであり、これは「田」についてであるからである。 「心は肉体に隷従しているのに、なぜ悲しく寂しいのか」という二つの文について、宋旭易は「ここが老人が真理を悟ったところだ。この二つの文を使えれば、将来の行動に余裕が持てる」と信じていた(『顔周詩談』)。いわゆる「将来の行動に余裕が持てる」とは、官職に就いても隠遁生活を送っていても、精神が非常に穏やかであることを意味する。清代の邱家穗は、円明の由来について、この文章は東晋末期の官界の混乱を避け、晋の滅亡を悲しむ気持ちが込められていると考えており、文章中の多くの言葉や文章がこの意味を伝えていると信じていた。 [注2] 呉奇氏は、「今日は正しく、昨日は間違っていたと認識している」という一文が記事全体の主旨であると信じており、「記事全体は『今日は正しく、昨日は間違っていたと認識している』という考え方に基づいている」と述べた。これは理にかなっている。なぜなら、「今日は正しい」は引退を指し、「昨日は間違っていた」は官僚としての職務を指しているからだ。この一文は、円明の文章の主題であるだけでなく、彼の人生における分岐点でもあります。 私は自分の家を見て、喜びながらそこに向かって走ります。召使たちが彼を迎え、子供たちが玄関で待っていた。三つの道は人影はないが、松や菊はまだ残っている。子供を部屋に連れて行くと、瓶の中にワインが入っていました。私は一人でコップを持って飲み、中庭の木々を眺めて気分を盛り上げます。私は南側の窓に寄りかかって自分の誇りを表現し、自分にとってちょうど十分なスペースがあることの気楽さと満足感を味わいます。毎日訪れても楽しい庭園で、門はあるもののいつも閉まっています。老人は杖に支えられ、川のほとりで休みながら、時々遠くを眺めていた。雲は意図せずに山から出てきて、鳥は飛ぶのに疲れたら戻ってくることを知っています。空はだんだん暗くなり、太陽はもうすぐ沈む。私は一本の松の木を撫でながら、立ち止まる。 上で引用した朱熹氏の言葉によれば、この論文は「実用的で有意義だが、比喩も含まれている」とのことだが、これはこの論文が主に物語的であるが、時折比喩も使われていることを意味している。この2番目の段落は朱熹の議論と非常に一致しています。たとえば、「雲は山を離れるつもりはない」は、彼が意図せずに故郷を離れて官僚になったことの比喩であり、「鳥は飛ぶのに疲れたら戻ってくることを知っている」は、官僚としての疲れと田舎への引退の決意の比喩です。同じ時期に、陶淵明も「帰園野」という詩の中で同様の比喩を用いている。「籠の中の鳥は昔の森を懐かしみ、池の魚は昔の池を懐かしむ」。宋代の葉孟徳は「無心雲」の二行について「これは陶淵明の偉大な言葉だ。もし彼がこのような心境でなければ、このようなことを言うことはなかっただろう」と評している。(『碧舟録花』第1巻) この一節の末尾の「孤独な松」については、元の時代の呉士道が『呉立布詩談』の中で「(松は)私自身の比喩である。陶淵明が菊を好むことだけは知っているが、このことは知らない」(淵明は菊と松を好む。本書の「菊は衰退を説く」の章を参照)と述べ、「空はますます暗くなり、私は孤独な松を撫でてそこにとどまる」は、日が沈もうとする夕暮れに、淵明が一人で孤独な松を撫でている場面を描いている。太陽は皇帝の象徴であることが多く(「空に二つの太陽はなく、民の中に二人の王はいない」など)、沈む太陽は王朝の衰退の象徴です。松は最後に枯れる木であり、常に堅固で忠誠心のある人々を表すために使用されます。そのため、人々はこれらのイメージを、金王家の滅亡が迫っていることに対する円明の不安と、金王朝の生き残りとなる決意と結び付けるのは容易です。無理な推測はしたくないが、円明の経歴や彼が生きていた時代を考えると、彼がそのような考えを持っていた可能性は高い。 家に帰って、友達を作るのをやめ、旅行をやめてください。世の中が私に敵対しているのに、私に何ができるでしょうか。私は親戚の優しい言葉を楽しみ、ピアノを弾いたり本を読んだりして、悩みを和らげています。農夫は私に、春が来たので西側の畑で仕事があるだろうと言った。馬車を頼む人もいれば、一人でボートを漕ぐ人もいます。谷沿いには優雅に曲がりくねった道があり、丘沿いには険しく険しい道もあります。木々は生い茂り、泉は湧き出ています。すべての物事の時間に感謝し、人生の浮き沈みに感謝する。 陶淵明は家族と友情をとても大切にする人で、ピアノを弾いたり読書をしたりすることも大好きでした。したがって、「親戚の優しい言葉に心を打たれ、ピアノを弾いたり本を読んだりして憂さ晴らしを楽しむ」というこの一節は特に注目に値する。清代の呉漢芬は陶淵明の『帰郷』が読者に天国にいるような気分を与えると信じていた。もし「親族を喜ばせる」という二行がなかったら、私たちは皆、淵明が「変わり者」だと疑っていただろう。 [注3] つまり、陶淵明は人間味にあふれているからこそ、人情に無関心な孤高の隠者でもなければ、俗世間から離れた仙人でもないのである。 円明が「すべての物事の時を感謝していた」ときに、なぜ突然「自分の命が終わりに近づいていると感じたのか」、そして実際に何が起こったのかについては、次の章「誰が帰還の道を理解するのか」をお読みください。 清流の詩を詠む(データ画像源ネットワーク) もう終わりだ!この世界でいつまで生きなければならないのか?なぜ私はただ手放して、自分のやりたいことを受け入れないのか?なぜ私はこんなに不安なのか、どこに行きたいのか?私は富も名誉も欲しくないし、皇居に入ることも期待できない。私は心の中で良い日々を思いながら一人で出かけ、あるいは棒を持ち上げて畑の雑草を取り除いたりします。私は東澳に登り、口笛を吹きながら清流を眺めながら詩を詠んだ。自然の摂理を利用して終末に戻り、疑いなく天国の運命を享受しましょう! 「富と名誉は私の望みではない」というのは分かりやすいが、「皇位を得ることは望めない」というのは違う。 「皇帝の故郷」という言葉は仙境を指し、「荘子・天地」に由来しています。「千年の間、世間に飽き飽きしていた皇帝は、仙人となって白雲に乗って皇帝の故郷に向かった。」しかし、古代の多くの人々は、「皇帝」という言葉は神々と晋の皇帝を指す語呂合わせだと信じていました。そして「皇郷」とは「晋の王族」あるいは「晋の政治集団」を指します。まあ、不可能ではないが、この文は単に「不老不死を求めることは不可能である」という意味であると言ってもよいだろう。なぜなら、陶淵明は『色影霊』の「私は飛翔の術を持たない」など、多くの詩の中でこの意味を表現しているからだ。陶淵明には「飛翔の術」がないので、「皇郷」(仙境)は当然到達不可能である。 「归尽」という言葉について、呉起は、一方は袁明の生涯の終わりを意味し、もう一方は晋王家の運の終わりを意味すると信じていた。彼はまた、陶淵明が忠誠心を持っていたからこそ、朱熹の『紫禁城綱目』に歴史上の出来事として仙人の死だけが記録されており、その仙人が陶淵明であると信じていた。 清朝の方宗成は、最初の段落と最後の段落の文章と『孟子』を組み合わせて、円明の生涯を解釈した。 「心は肉体に隷従しているのだから、なぜ悲しんだり孤独になったりしなければならないのか」これは『孟子』の一節の意味です。 「私たちはこの世にどれくらい生きるのでしょうか? なぜ私たちはただ手放して結果を受け入れないのでしょうか?」これが一般的な考え方です。 「帰依の天性を利用し、疑うことなく天意を享受しよう」とは、君子は安楽に暮らして天命を待ち、何をするにも満足すべきであるという意味です。 (清代の方宗成による陶淵明詩の真意の解釈) 「小の本質に従う」と「大の本質に従う」とはどういう意味ですか? この 2 つの文は「孟子・高子」から引用したものです。 (公都子は尋ねた)「私たちはみな人間ですが、ある人は全体像を、ある人は細部を気にします。それはなぜでしょうか?」 孟子は言った。「聞く器官や見る器官は考えるのではなく、物事によって盲目にされる。物事が互いに作用し合うとき、それらは互いに引きつけられる。心の器官は考える。考えれば、理解できる。考えなければ、理解できない。これは天が私に与えたものだ。まず大きなものを確立すれば、小さなものはそれを奪うことはできない。これが偉大な人になるということだ。」 Gong Duzi asked Mencius: "Among all people, some are gentlemen and some are villains. Why is this so?" Mencius said: "Those who seek to satisfy the needs of the important organs of the body (from the general body) are gentlemen, and those who seek to satisfy the desires of the secondary organs of the body (from the minor body) are villains." Gong Duzi asked again the reason, and Mencius said: "Organs such as ears and eyes do not think and are often blinded by external things. The complexity of external things and their mutual entanglement will lead these organs astray. The function of the heart is to think. (Human goodness) can be obtained by thinking, but not by thinking. This organ is specially given to us humans by God. Therefore, this is an important organ, and it must be established first, so that the secondary organs cannot take away this goodness. In this way, you will become a gentleman." And "Live in ease and wait for destiny" and "Nothing is not self-satisfied" are both from "Book of Rites·Doctrine of the Mean": 君子は自分の立場に応じて行動し、それを越えようとはしません。金持ちに生まれたら金持ちのように行動し、貧乏に生まれたら貧乏人のように行動し、外国人の中に生まれたら外国人のように行動し、逆境に生まれたら逆境に生きる人のように行動しなさい。紳士はどこへ行っても満足する。上の立場の人は下の立場の人をいじめてはいけませんし、下の立場の人は上の立場の人に頼ってはいけません。他人に何も求めず、自分を正せば不満は出ません。上にある天を責めたり、下にある他人を責めたりしないでください。したがって、君子は安楽に暮らして運命を待ち、一方、悪人は幸運を期待して危険を冒すのです。 「自分の立場に応じて行動する」という儒教の人生に対する重要な姿勢は、この一節から来ています。この一節の一般的な意味は、君子は現在の立場でなすべきことをし、他のことには嫉妬しないということです。金持ちなら、金持ちの原則(あまり質素にならない)に従って行動すべきです。貧乏なら、貧乏人の原則(あまり贅沢にならない)に従って行動すべきです。少数派なら、少数派の原則に従って行動すべきです。逆境にあるなら、逆境の時の原則に従って行動すべきです。したがって、紳士はどんな状況でも冷静さを保つことができます。高い地位にある紳士は部下をいじめたりはしないし、低い地位にある紳士は上司にへつらったりはしない。他人に助けを求めず、自分の間違いを正すだけなので、紳士は恨みを買うことはありません。君子は運命を責めず、また他人を責めない。したがって、君子はごく普通の立場に留まり、運命が訪れるのを待ちますが、悪人は危険を冒して、得るべきではないものを求めます。 |
<<: 韓馥はどのようにして、後漢末期の中原における覇権争いで排除された最初の太守となったのでしょうか。
>>: 古代、結婚には6つの儀式がありました。唐と宋の時代には、6つの儀式はどのように簡素化されましたか?
推薦する
『韓非子』における形式より実質を重視する考え方は具体的に何を指すのでしょうか?
『韓非子』における形式より実質を重視する思想は、具体的には何を指すのでしょうか?形式より実質を重視す...
小説『西遊記』の中で、朱子王が自ら金宮を蔡太歳に譲り渡したのはなぜですか?
朱子王は小説『西遊記』の登場人物です。朱子王。今日、Interesting History の編集者...
王羲之はなぜガチョウが好きだったのでしょうか?
東晋の偉大な書家である王羲之について話すとき、人々はガチョウと引き換えに経文を書いたという広く流布し...
清朝の王子として、毎日の勉強時間はどのように規制されていましたか?
清王朝といえば、中国史上最後の封建王朝であったことは多くの人が知っていると思います。また、清王朝は私...
李白の古詩「南柳夜郎を妻に送る」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「南のイェランから妻に宛てた手紙」時代: 唐代著者: 李白夜朗は天空の故郷から離れてしまったこ...
岑申の「中央書記賈志の大明宮での早謁に対する返答」:「早謁」という言葉について書く
岑申(718?-769?)は、荊州江陵(現在の湖北省江陵県)あるいは南陽桀陽(現在の河南省南陽市)の...
キルギス民族の歴史 現代におけるキルギス民族の発展の概要
1840年のアヘン戦争以来、新疆への外国の侵略者の侵略に直面し、キルギス人は新疆の各民族の人々ととも...
『紅楼夢』で秦克清が賈家に嫁ぐことができたのはなぜですか?真実とは何か
秦克清は才能と美貌を兼ね備えた女性でした。 本日は、Interesting History編集長が詳...
元旦の起源:中国の元旦はどのように始まり、変化したのでしょうか?
正月は三皇五帝の一人である荘厳帝に由来すると言われ、5000年以上の歴史があります。 「正月」という...
『紅楼夢』で、林黛玉は湖で溺死したのか、それとも涙で死んだのか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
『紅楼夢』で薛潘はいつ黛玉と出会ったのですか?彼らの間にはどんな物語があるのでしょうか?
薛凡は『紅楼夢』の登場人物で、薛叔母の息子で、「戴八王」というあだ名がついています。今日は、Inte...
古代における袖の役割は何でしたか?袖に関する慣用句にはどんなものがありますか?
今日は、Interesting Historyの編集者が古代人の袖の役割についてお話しします。興味の...
「隣人への春の思い」の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
近隣住民への春の思い陳世道(宋代)雨粒は壊れた壁に文字を形成し、古い家には僧侶もツバメもいません。外...
『紅楼夢』の張旦春は女性の中で一番の妻候補でしょうか?なぜそんなことを言うのですか?
張旦春は紅楼夢に登場する多くの女性の中で、最も適した妻候補なのでしょうか?次は、興味深い歴史の編集者...
包公の事件 第59章: 邪悪な教師が弟子を惑わす
『鮑公案』は『龍土公案』とも呼ばれ、正式名称は『都本鮑龍土百公案全伝』で、『龍土神段公案』とも呼ばれ...