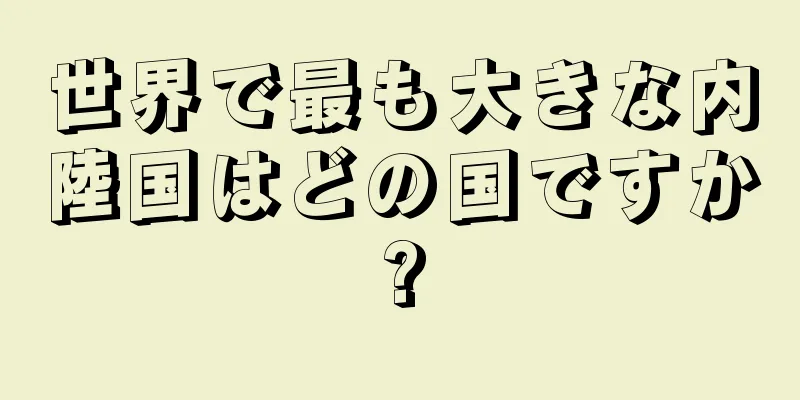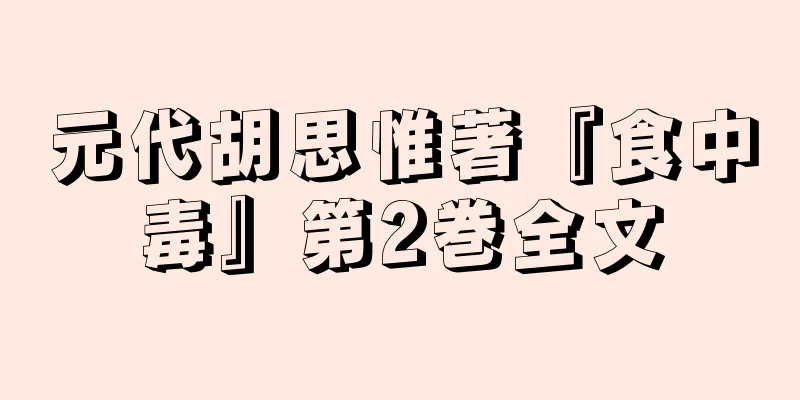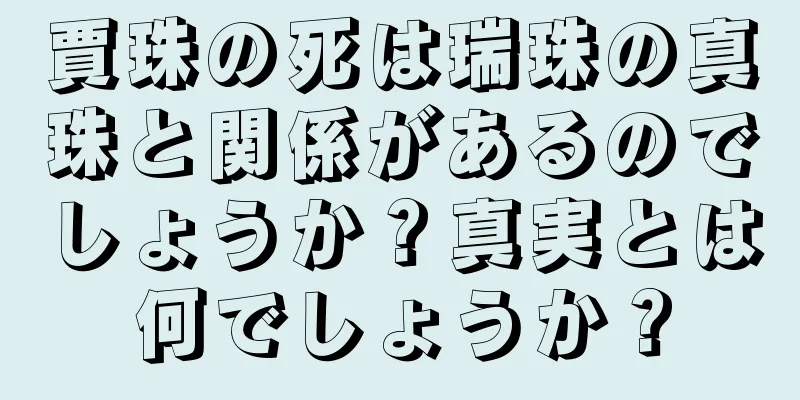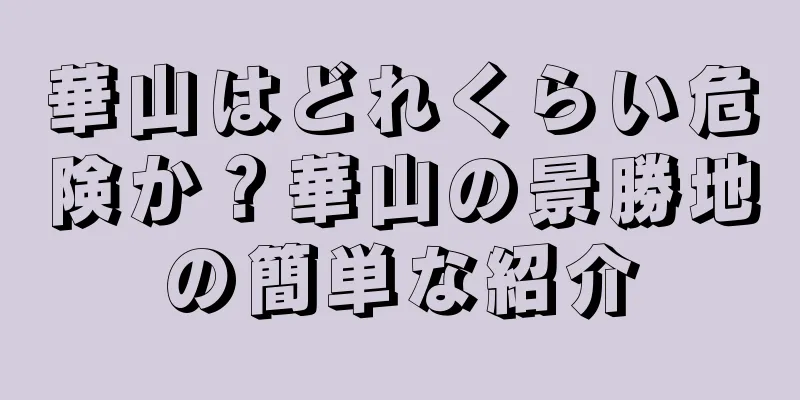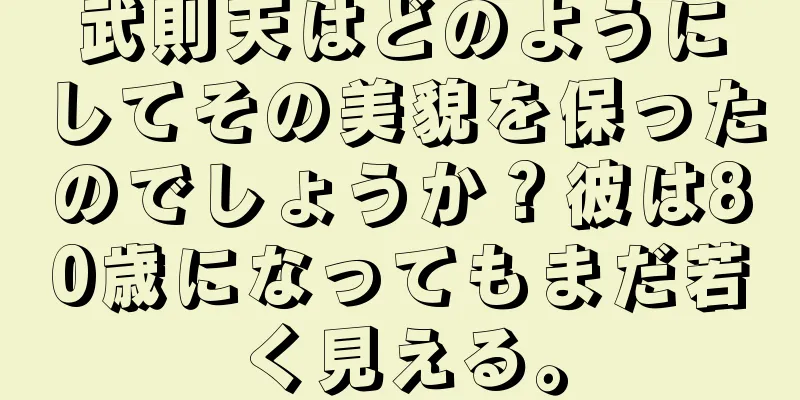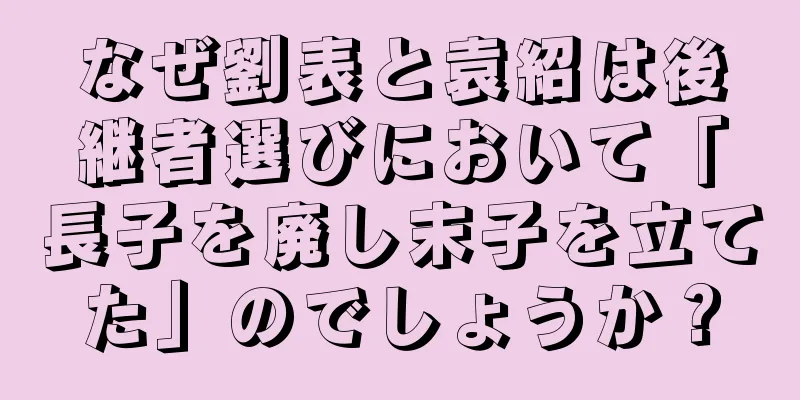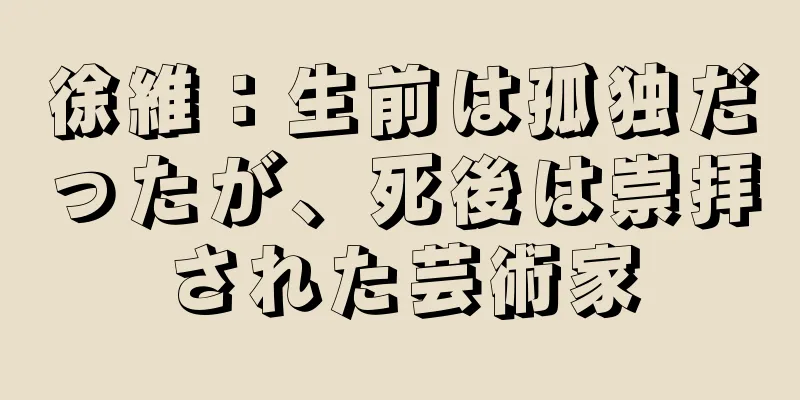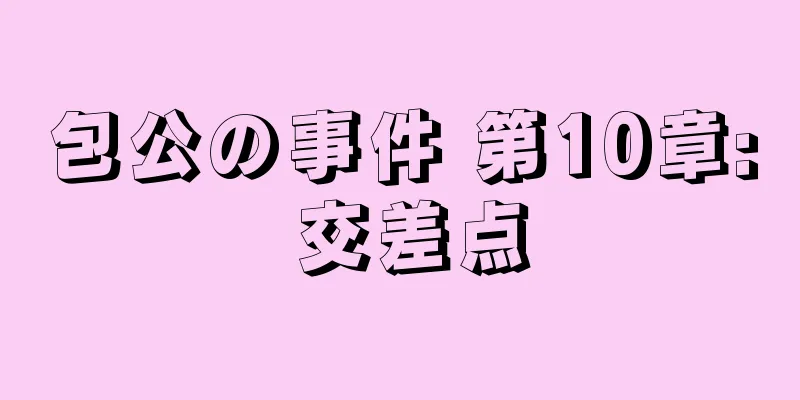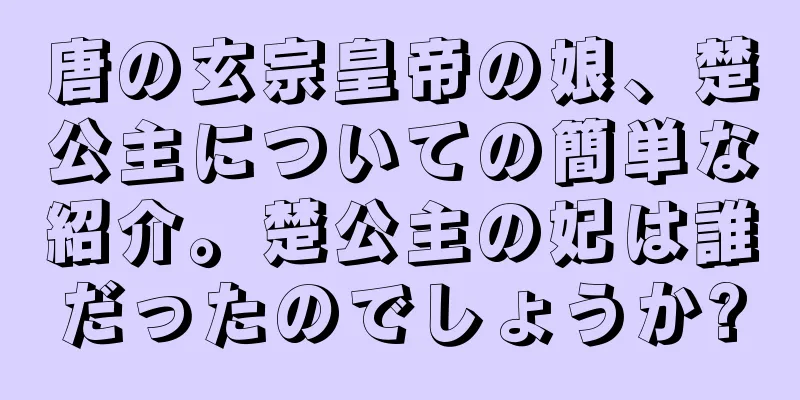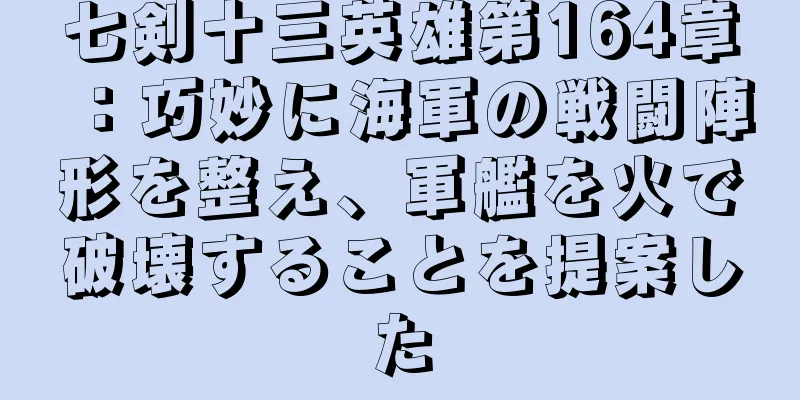『孫子』の著者は誰ですか?孫子の兵法はいつ生まれたのでしょうか?
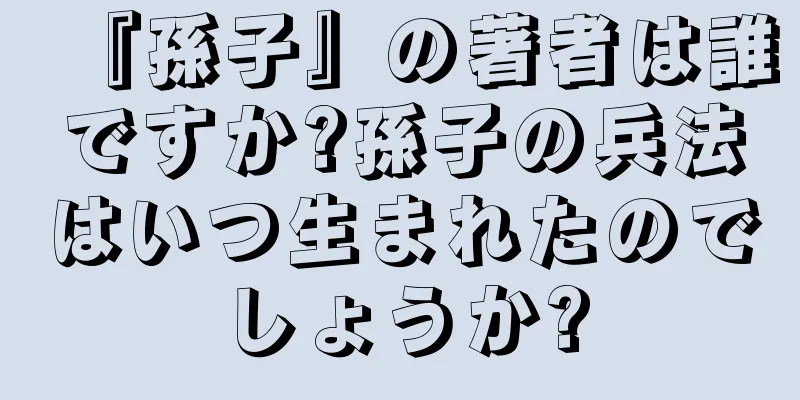
|
孫武は『兵法』の著者ですか? 『兵法』は中国最古かつ最も優れた軍事戦略書であり、常に「軍事古典」と呼ばれ、「代々軍事論の祖」と賞賛されています。その洗練された思想、素晴らしい戦略、深遠な哲学、そして優雅な言語は、我が国の何世代にもわたる軍事戦略家たちの成長を育んできました。それは、わが国の唐の時代、西暦8世紀に日本に伝わり、すぐに日本国内のあらゆる階層で高く評価され、多くの人々が研究し、注釈をつけ、説明し、応用しました。近年、欧米にも広まり、10数か国語に翻訳され、軍事分野以外にも、外交活動、企業管理、市場競争、スポーツ競技などにも活用され、世界で最も人気のある読み物の一つとなっています。 しかし、『孫子』の著者が誰であるかは長い間謎のままでした。 『史記・孫子・呉起伝』には、春秋戦国時代に孫武と孫臏という二人の孫子がいたと記されている。孫武は春秋時代後期の呉国の将軍であり、孫臏は戦国時代中期の斉国の軍師である。二人はそれぞれ独自の軍事戦略を時代を超えて受け継いでいる。 『漢書・易文志』の「軍師」の項には、『呉の孫子の兵法』と『斉の孫子の兵法』の記録もある。唐延時固の注釈によれば、第一巻の著者は「孫武」、第二巻の著者は「孫斌」である。しかし、孫臏の兵法書は後漢末期以降失われてしまった。このように、二人の『孫子』には、一つの『兵法』しかありません。そのため、宋代以降、多くの人々の間で疑惑と憶測を呼び起こしてきました。 『兵法』に書かれていることの多くは戦国時代に関するものであるため、この本は孫武が発祥で孫臏が完成させたと考える人もいますが、単に孫臏によって書かれたと主張する人もいます。 『孫子』は2つあるのに『兵法』は1つしかないので、孫武の存在を疑う人も多い。 『左伝』には孫武についての記述がなく、『史記』には孫武が「女性を使って軍事戦略を試した」と記されていることから、宋代の葉石は「そのため、郎儒と孫武について言及する者はみな虚偽の告発をしているだけであり、それは事実ではない」と指摘した。 (『学問紀言』)清朝の全祖王は上記の見解に完全に同意し、「呉淵のような人物は存在せず、彼の行為や著書はすべて外交官によって捏造されたものである」と信じていました。 (鮑其亭集、孫武論)現代の学者斉思和も『兵法書紀年研究』の中で、「孫武は実際には存在しなかった可能性があり、『孫武十三章』は戦国時代に書かれたものである」と主張している。 (燕京日誌第26号) 孫武は孫斌であると信じる者もいる。例えば、日本の学者斎藤節堂は、その論文「孫子論」の中で、「孫武と孫臏は結局同一人物である。武は彼の名前であり、臏は彼の愛称である」と書いている。 (蒋霞安編『先秦経研究』中巻参照)現代の学者銭牧も指摘している。孫子は呉と斉の両方に住んでいたが、司馬遷はその区別がつかなかったため、「誤って二人に分けてしまった」のである(『先秦哲学者年代順研究』)。この問題に関して、学界は非常に異なった奇妙な意見を持っていることがわかります。 1972年、山東省臨沂市銀雀山にある西漢時代の墓で、『兵法』と『孫臏の兵法』を記した竹簡が大量に発見された。この発見により、1700年以上失われていた孫臏の著作が再び日の目を見ることになっただけでなく、『史記・孫子伝』と『漢書・文芸録』に記された、2人の孫子が2つの兵法を持っているという記述の信憑性が立証された。しかし、一部の学者は、『兵法』が主に戦国時代の状況を描写しているため、春秋時代後期に孫武によって書かれたことを証明することはできないと考えています。 (1)兵法書に使われている用語の多くは、戦国時代に流行したが、春秋時代には見られなかったものである。例えば、「兵法篇」には「大勢と戦うのは少勢と戦うのと同じ、名と形である」とあり、「九地篇」には「覇権国の軍隊が大国を攻めるとき、その国の民は集まることができない」とある。ここでの「形名」と「霸王」はどちらも戦国時代によく使われた言葉です。 (2)『孫子の兵法』によれば、配備される軍隊の数は数十万に上る可能性があるとされている。たとえば、「戦闘の章」には「10 万の装甲部隊」とあり、「スパイの使用の章」には「10 万の軍隊を編成する」とあります。春秋時代、主要国は数百台の戦車と2万~3万人程度の兵士しか雇用していませんでした。 10万から数十万の軍隊が存在するようになったのは戦国時代の中期になってからである。 (3)春秋時代、大戦はたいてい数日で終わり、包囲戦も数ヶ月しか続かなかった。しかし、『兵法』で論じられている戦争は長期化することが多かった。例えば、『兵法』には「軍隊を長く使いすぎると国が資源を使い果たす」とあり、『間者の使い方』には「一日の勝利のために何年も戦う」とある。これはまさに戦国時代の状況である。 (4)『孫子』で論じられている戦術は主に機動戦であり、敵地への深い侵入と長距離展開を主張している。たとえば、「客の道は奥深く専門的であることである」、「一方向に敵と合流し、数千里離れた敵の将軍を殺す」(『九地』)、「最後に出発し、最初に到着する者。これが回り道と直接の戦略を知っている者である」(『軍闘争』)などです。これらは戦国時代の戦い方です。 (5)兵法書は特に「五」という数字の使い方が上手です。例えば「志」の章には「五つの音の変化は聞くに及ばず」「五つの色の変化は見るに及ばず」「五つの味の変化は味わうに及ばず」とあります。 「虚空と実在」の章には、「五大元素には永久的な勝利はない」とも書かれています。これらは戦国時代に「五行説」が流行した後になされた発言であるはずだ。 (6)『兵法』のスタイルは、『徳論』や『普愛論』など墨子の他の章のスタイルと似ています。各章のタイトルは、その章全体の主な考えを要約したもので、その前に「あるマスターが言った」と書かれています。このジャンルは、おおよそ『論語』や『孟子』より後、『荀子』や『韓非子』より前、戦国時代中期から後期にかけて登場した。 (VII)春秋時代においては、戦争は通常、君主自身、または中央軍の司令官によって戦われた。兵法書で軍事について述べる場合、将軍が唯一の責任者となります。たとえば、「将軍は王の命令を受ける」(『九変』)、「将軍が有能でも王が彼を制御しなければ、勝利は達成される」(『攻めの戦略』)などです。このパターンは戦国時代にのみ存在しました。 (8)春秋時代、出陣する軍隊は一般に自前の食料を持参し、いわゆる「包食して甲冑に座す」(左伝、文公12年)とされ、食料をすべて食べてから帰還し、敵に食料を差し出す者はいなかった。しかし、『兵法』では「食料は敵に頼る」ことと「賢い将軍は敵から食料を得ようとする」ことが繰り返し強調されている(戦争の章)。これも戦国時代の戦略です。 (9)春秋時代には貴族は「君主」と呼ばれていたが、君主を「君主」と呼ぶのは三家が晋を分裂させた後の慣習である。兵法書では君主を「君主」と呼ぶことが多く、これも兵法書が戦国時代に起源を持つことを示す証拠です。また、『間者伝』に出てくる「使者」「門番」「社連」も戦国時代の三時期に使われた用語である。 (10)銀雀山漢墓の竹簡には『孫子の兵法 間者の使い方』の一節があり、「燕の台頭は蘇秦が斉に留まったためである」と記されている。蘇秦は孫武の約200年後、戦国時代中期から後期にかけて活躍した。これは『孫子』の完成がいかに遅れていたかを示すのに十分すぎるほどである。この文は孫武の時代とあまりにも明らかに矛盾していたため、後に削除されました。 「兵法」が戦国時代に起源を持つとする上記の10の主張は、いずれもある程度真実である。もちろん、歴史上、明代の宋廉(『士分別』の著者)、清代の孫行艶(『孫子十評序』の著者)、そして『四科全蔵総目録要』の著者など、多くの学者が『史記』や『漢書』の記録に基づいて、『兵法』は春秋時代の孫武自身によって書かれたものだと信じていました。読者は歴史の真実を注意深く見極めるべきだ。 |
>>: インディア・アーサンというニックネームの由来を明かす。インディア・アーサンとはどういう意味ですか?
推薦する
『紅楼夢』の4大家の一つである賈邸の収入源は何ですか?
曹雪芹の『紅楼夢』に登場する賈家はもともと貴族の家系であり、その家系は隆盛を極めていた。今日は、In...
『紅楼夢』第25話のストーリーは何ですか?今回はどのように鑑賞したらよいでしょうか?
『紅楼夢25』第25話の主な内容は何ですか?第二十五章:ある日、宝玉、鳳潔らが王子藤夫人の誕生日パー...
李静の「蓮の香りは消え、緑の葉は枯れる」:李廷基は「すべての言葉が美しく、秋の考えはとても素晴らしい」と評した。
李靖(916年 - 961年9月12日)、本名は徐景同、徐瑶(李堯)、号は伯瑶、徐州彭城県(現在の江...
『紅楼夢』で、薛宝才が香玲に詩を学ぶのを助けた目的は何でしたか?
香玲はおそらく『紅楼夢』に登場する最も古い女性だと考えられます。今日は『Interesting Hi...
白居易の古詩「余暇」の本来の意味を理解する
古代詩「余暇」時代: 唐代著者: 白居易給与は高く、ポジションも低くなく、部門内での余暇時間もありま...
三英雄五勇士第68章:華帝と戦昭が結婚し、二人の英雄は景秀に運命を占わせる
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
曹操と呂布が兗州をめぐって1年にわたって戦った間に何が起こったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
万暦帝の寵愛を受けた側室、鄭妃はどのようにして亡くなったのでしょうか?鄭妃の簡単な紹介
鄭皇后(1565年 - 1630年)は、明代の神宗皇帝朱懿君の皇后であった。彼は大興市(現在の北京市...
「鳳凰笛歌:果てしない別れの悲しみ」を鑑賞、詩人韓震は巧みに擬人化を用いた
韓震(1019-1097)、号は于如、鎮定霊首(現在の河北省霊首県)の出身。北宋時代の大臣。宰相韓懿...
白居易の古詩「植竹」の本来の意味を鑑賞する
古詩「植えたばかりの竹」時代: 唐代著者: 白居易王さん、左懿は不幸だったので、家に留まり、秋の草が...
なぜ孫権は関羽を殺害しようとしたのでしょうか?どうしてそのような正義の人が人を殺すことをいとわないのでしょうか?
三国時代、世は乱れ、一時は情勢が不安定となり、世界中の英雄たちが中原で覇権を競い合いました。世界中の...
「于美仁:風は小庭に帰り、庭は緑なり」を書いた詩人は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】風が小さな中庭に吹き返し、雑草は青々と茂り、柳は春に満ちています。半日ほど静かに欄干に...
なぜ侍女は西太后に仕えていた間、一度もまともな食事をとらなかったのでしょうか?
慈渓周辺の侍女たちに非常に興味がある方のために、『Interesting History』の編集者が...
『隋唐書』第74章:建城が河東県を平定する
『隋唐代志』は、元代末期から明代初期にかけて羅貫中が書いた章立ての小説である。 『隋唐書紀』は瓦岡寨...
何卓の『石州人・小雨寒』:この詩は構成が精巧で、詩全体に「悲しみ」が流れている。
何朱(1052-1125)は北宋時代の詩人。号は方慧、別名は何三嶼。またの名を何美子、号は青湖一老。...