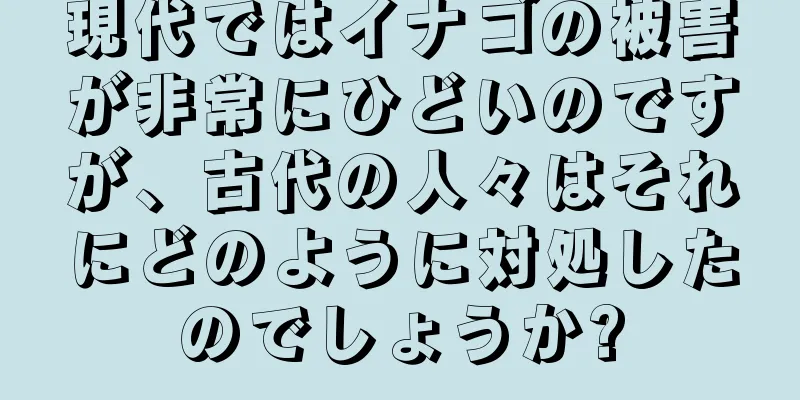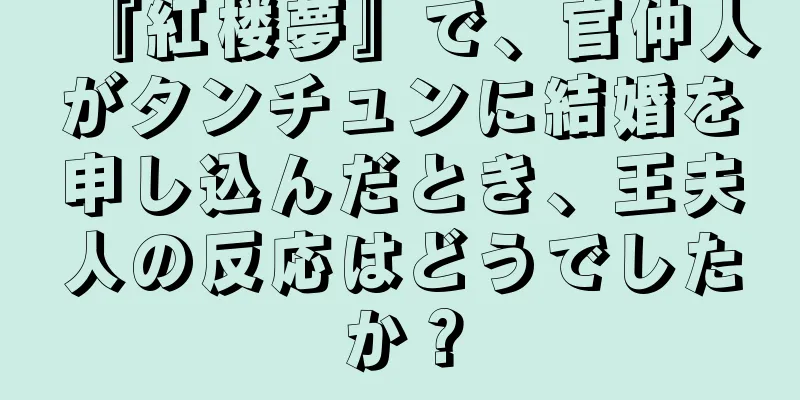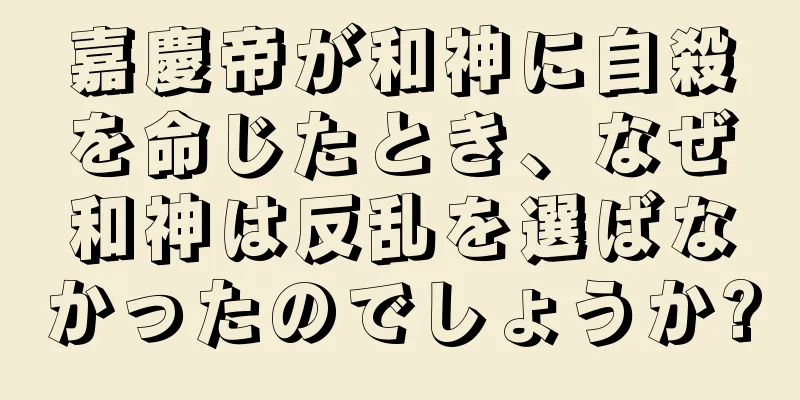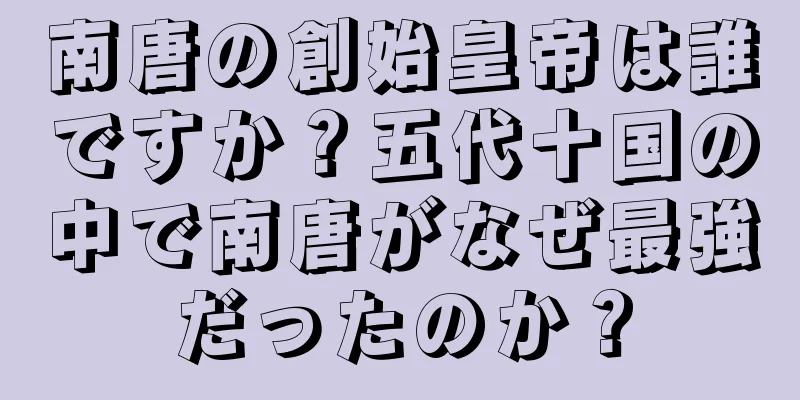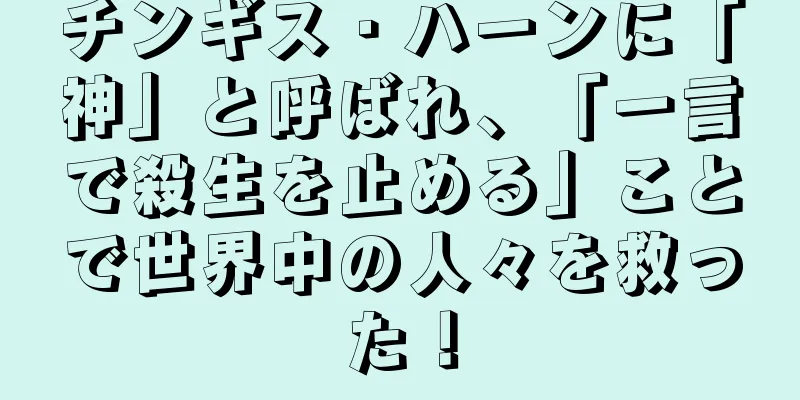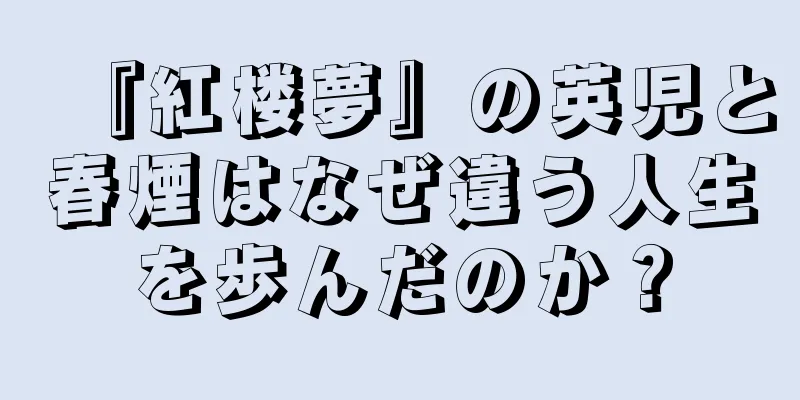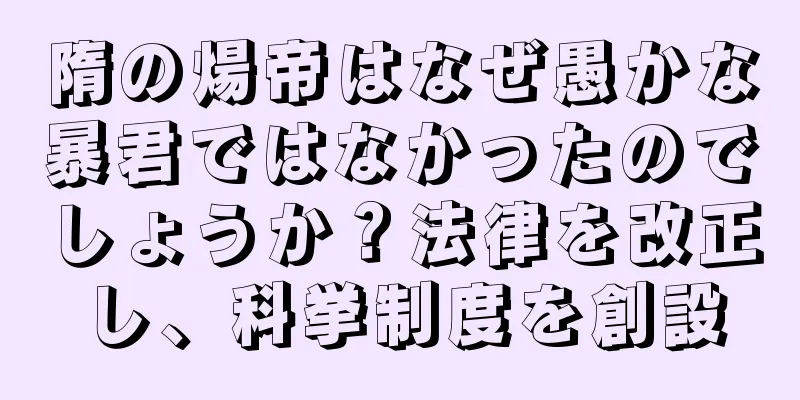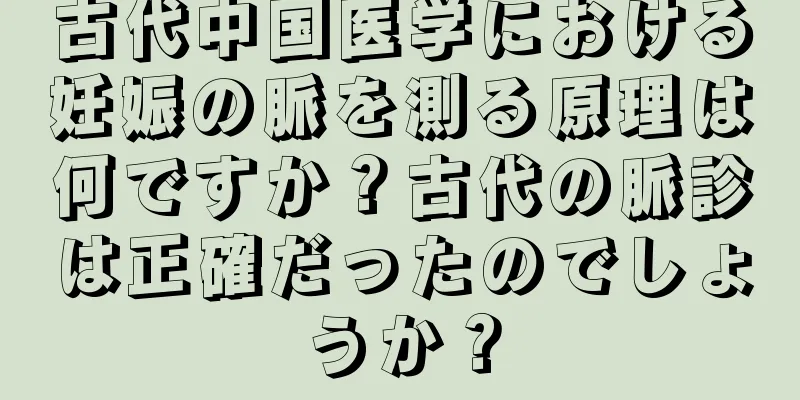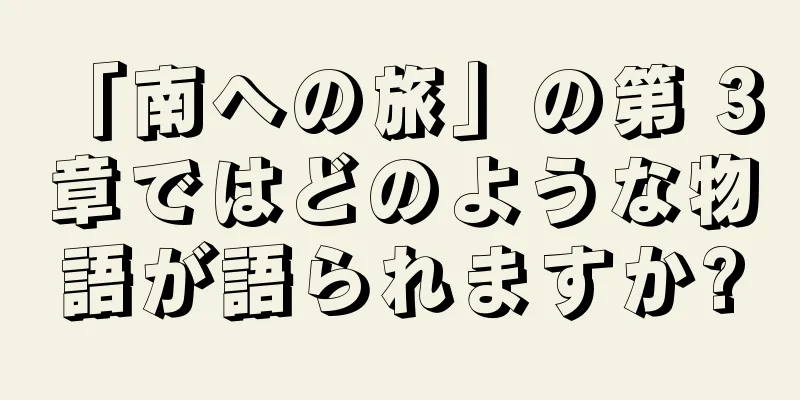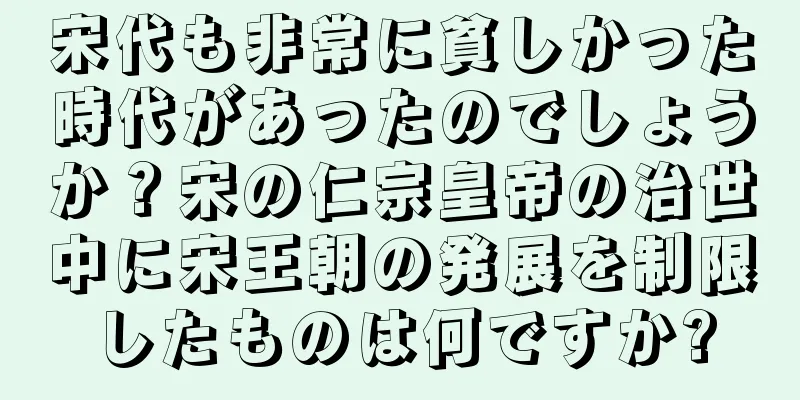清朝における挨拶とひざまずくことの違いは何ですか?
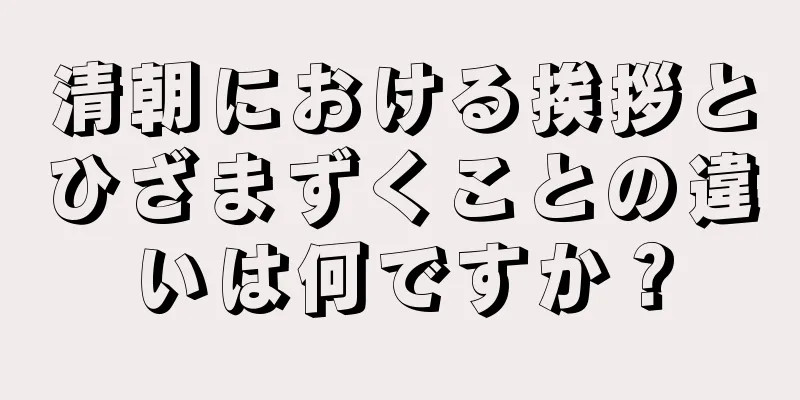
|
ご挨拶 敬意を表すことは、もともと明代の軍隊の礼儀作法であり、『大明慧典』にも記録されている。当時、全国の司令部や駐屯地では「片膝をつく」という作法が定められていた。 清朝では、八旗と緑陣営の間で明朝から受け継がれた古い慣習が依然として守られていました。本来、兵士は上官に会ったときにひざまずくべきであるが、甲冑を着ているため、片膝か半膝しか曲げない。時が経つにつれ、甲冑を着けていないときにも片膝を曲げることは礼儀となり、平伏したりお辞儀をしたりと同じように、挨拶の意味を持つようになった。 八旗家や一部の漢族の官僚の家では、この礼儀作法は、若者が年長者に会うとき、若者が年長者に会うとき、使用人が主人に会うとき、使用人が主人と親戚や友人に会うときに行われます。したがって、片膝を曲げることは挨拶とも呼ばれます。しかし、官庁や公共の場では、漢人であろうと満州人であろうと、丁寧にお辞儀するだけで、挨拶は許されません。 男性が挨拶する時の姿勢:まずは「直立不動」のように姿勢を正します。次に左足を前に踏み出し、左手で膝を支え、右手を下げ、右足で半膝をつき、少し停止します。まっすぐ前を見て、頭を下げたり、上げたり、傾けたりしないでください。肩のバランスを保ち、かがまないでください。左足と右足の間の距離は大きすぎず、左足が前に進む自然な距離を維持し、足を後ろに押し出さないでください。 女性の挨拶の姿勢は男性と同じですが、左右の足の間隔を狭くし、動きの幅を小さくし、両手を左膝の上に置き、右手を下げないようにします。 ひざまずいて 「ひざまずいて敬意を表す」という作法は、皇居や五公爵邸、王族の家族などでも行われていました。皇帝は毎日軍大臣を召集するだけでなく、他の役人も頻繁に召集した。これらは宮廷の儀式とは異なる秘密の会談であったため、役人は皇帝にひれ伏す必要はなかった。 召喚の手続きは、まず外務局に登録し、その後内務局で特定の日に召喚の回数を調整します。皇帝が朝食を食べているとき(まだ暗かった)、緑色の棒がテーブルに置かれ、食事の後、皇帝に一人ずつ会うように呼び出されました。宦官たちが(太政官などと)一緒になりたければ、彼らは撤退するでしょう。内祀所の宦官は、役人を暖かい部屋のドアに呼び寄せ、カーテンを開けて役人を中に入れ、宦官はホールの外に退いた。 役人は入って来て、立ち上がって「陛下、謹んでご挨拶申し上げます」と言った。それからひざまずいて立ち上がり、皇帝のところまで数歩歩き、赤い縁取りと白い中央の厚いフェルトマットの上にひざまずいて、応答した。報告が終わると、皇帝は「もう立ち去ってよい」と言った。すると役人は立ち上がり、ひざまずいて数歩後退し、皇帝の方を向いて立ち去ろうとした。返事をする際に感謝すべきことがあれば、その場で頭を下げて「陛下、お恵みをありがとうございます」と言います。返事をする際に間違ったことを言ってしまった場合は、帽子を脱いで頭を地面に打ち付け、間違いを認めたことを示します。皇帝は朝夕皇太后に敬意を表したり、皇太后に面会したりする際に、部屋に入るときだけでなく、出るときにもひざまずいて敬意を表した。 宦官は皇帝、皇太后、王妃、側室、その他の重要人物に物事を報告しなければなりませんでした。王子や王族の宮殿では、若い世代は年長者に会うときにひざまずかなければならず、奴隷は主人に会うときにひざまずかなければなりませんでした。 ひざまずく姿勢と挨拶の姿勢で共通しているのは、まず姿勢を正して左足を前に踏み出すという点です。しかし、ひざまずくときは、右足を完全にひざまずかせ、次に左足もひざまずかなければなりません。その後、右足が立ち上がり、次に左足が立ち上がって、立ち姿勢に戻ります。この一連の動作は、急いだり長引いたりすることなく、バランスの取れたリズムで実行する必要があります。その他の要件は弔問の場合と同様です。 清朝では、皇后・側室以下の公主・公女・側室・官妾(漢の官妾・官妾は除く)が朝服や吉祥衣をまとい、一拝一跪三叩頭、または六拝三跪九叩頭の儀礼で盛大な儀式を行った。 (一回の平伏は一回立つことです。一回のひざまずきは一回ひざまずいて立ち上がることです。三回のひざまずきは当然それぞれ三回です。三回の平伏と九回の平伏の違いも回数の違いです。) 宮廷衣装と冠を着けているときの平伏し方は男性と同じです。清朝末期、吉祥の服を着る人は吉祥冠をかぶらず、簪を着けていました。ひざまずいた後、頭を下げず、右手で2つの簪を支えていました。ここで説明が必要なのは「Su」です。この動きは、女性が挨拶をするときに行う動きに似ています。まず姿勢を正し、次にゆっくりと一番下まで降り、その後ゆっくりと立ち上がって、元の立ち姿勢に戻ります。また、体を曲げたり、頭を下げたりせず、肩を安定させ、背中をまっすぐに保つことも必要です。 |
<<: 中国の歴史上、なぜ海軍が存在しなかったのでしょうか?
推薦する
『詩経・大雅・清妙』原文・翻訳・鑑賞
清寺匿名(秦以前)牧清寺では厳粛で平和な様子が見られました。才能のある人はたくさんいますが、皆徳のあ...
皇帝の物語:唐の中宗皇帝、李献はなぜ衛皇后と安楽公主をそれほど溺愛したのか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...
龍清ニューディールと万暦改革の関係は何ですか?
実は、龍清ニューディールの背景は非常に複雑で、政治、経済、社会の3つの側面に分かれています。後世の歴...
楊季の「春草」は、詩人が人生の意味について哲学的に考察した内容が表現されている。
楊季は、孟仔、号は梅安とも呼ばれ、明代初期の詩人で、「武中四英雄」の一人である。詩風は優雅で繊細、五...
曹丕は曹叡の母である甄嬛を殺したが、なぜ彼女を後継者にしたのだろうか?
甄嬛は曹丕より4歳年上の西暦183年に生まれました。真密は美しいだけでなく、幼い頃から読書家でもあり...
『紅楼夢』の禿頭僧侶はなぜ薛宝才に処方箋を与え、岱玉には与えなかったのでしょうか?
古代中国の長編小説『紅楼夢』は、中国古典文学の四大傑作の一つです。次は、Interesting Hi...
那蘭星徳の「別れの後悔」は飾り気がなく、極めてシンプルで優雅である。
納藍興徳(1655年1月19日 - 1685年7月1日)は、葉河納藍氏族の一員で、号は容若、号は冷家...
蜀漢の皇帝・劉備といえば、彼は本当に庶民の出身だったのでしょうか?
歴史上の平民皇帝や庶民の君主の多くは、親族です。四代三公を擁した袁家、太守の息子である曹操、代々呉で...
明代の服装:明代の公式の服装
明代の官吏の主な服装は、黒い紗の帽子とパッチの付いたローブを着用することであり、パッチは官職を区別す...
「白牡丹」第13章:皇帝は山の裏切り者の罠から逃れ、突然の騒動に遭遇する
『白牡丹』は清代の洪綬が書いた小説です。その主な内容は、正徳帝が夢に見た美しい女性、白牡丹と紅牡丹を...
『夜の宮殿巡り 竹窓から雨音を聞く』の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
宮殿の夜のツアー:竹の窓から雨音を聞く呉文英(宋代)竹窓のそばで雨の音を聞きながら、長い間座っていた...
魏晋詩の鑑賞:七段詩、曹植は詩の中でどのような芸術形式を使用しましたか?
漢代の曹植の七段詩については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!豆を煮る...
川の龍、李軍は本当に皇帝になったのか?彼はどうやってそれをやったのですか?
川の龍、李軍川の龍、李軍は涼山坡水軍のリーダーであり、順位は26位です。彼は優秀な船乗りで、もともと...
第5章:海曹江は皇帝に降伏して都へ行き、周進石は詩を書いて処罰を逃れる
『海公小紅謠全伝』は、清代の李春芳が著した伝記である。『海公大紅謠全伝』の続編であり、海睿の晩年72...
結局、大勝した司馬家以外に諸葛亮の一族はどうなったのでしょうか?
三国時代の歴史には多くの豪族が存在した。三国時代初期には、袁紹の袁家が間違いなく最強だったと言われて...