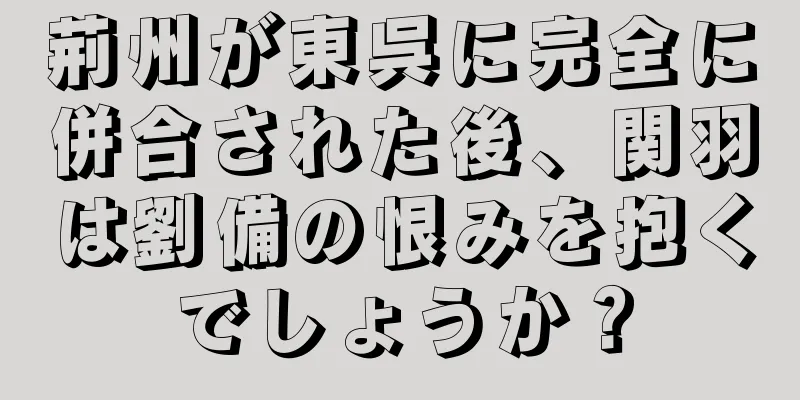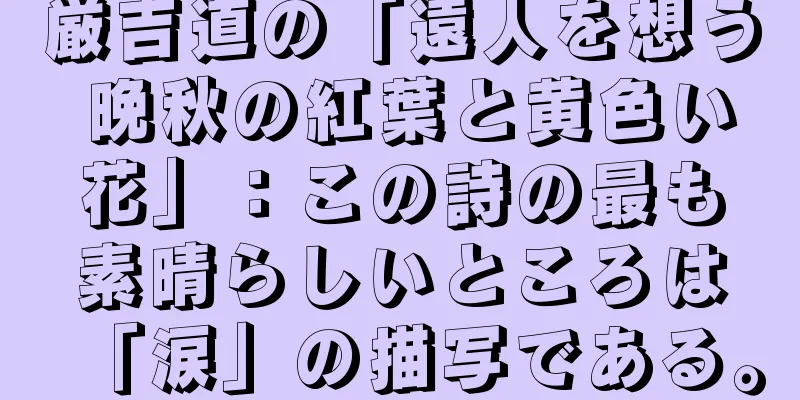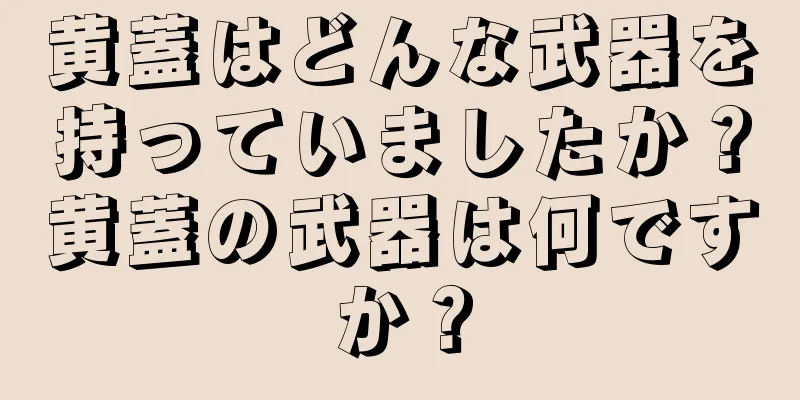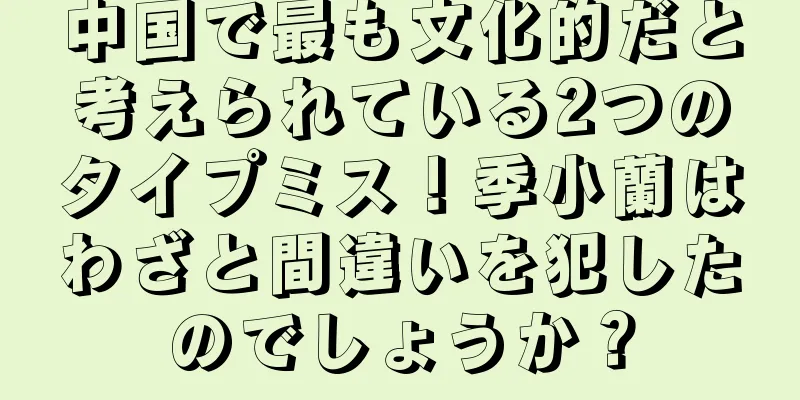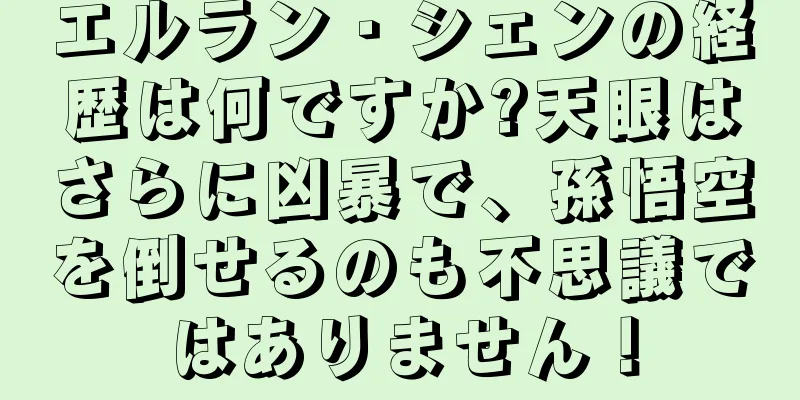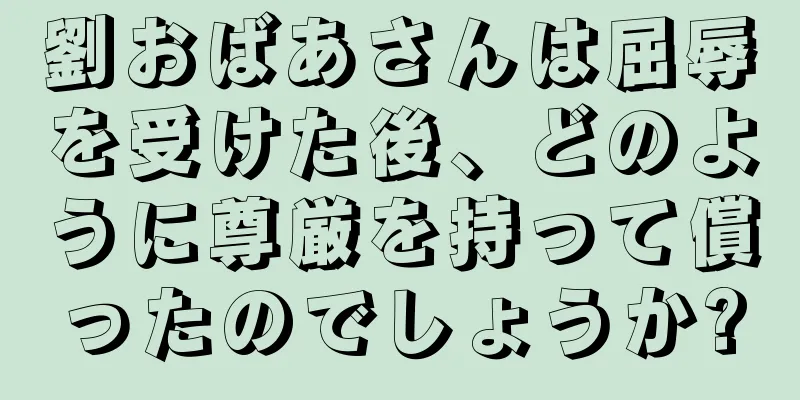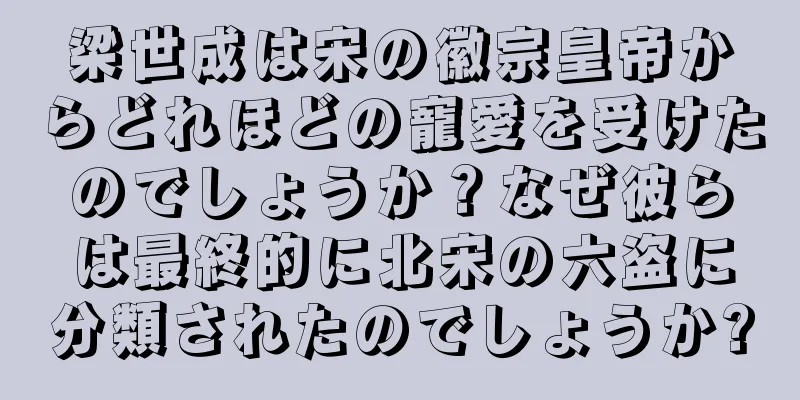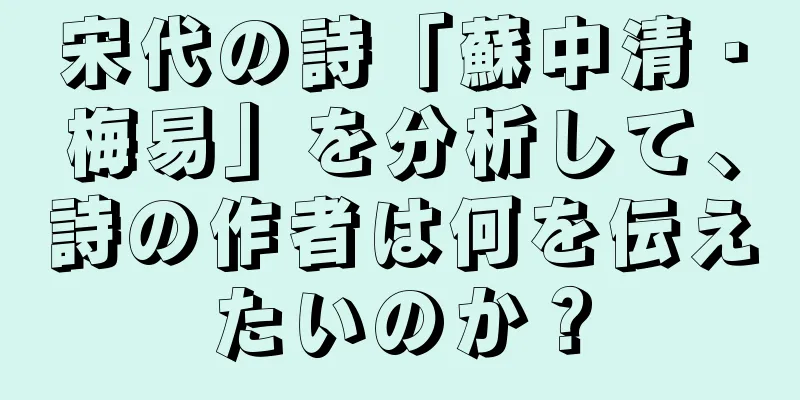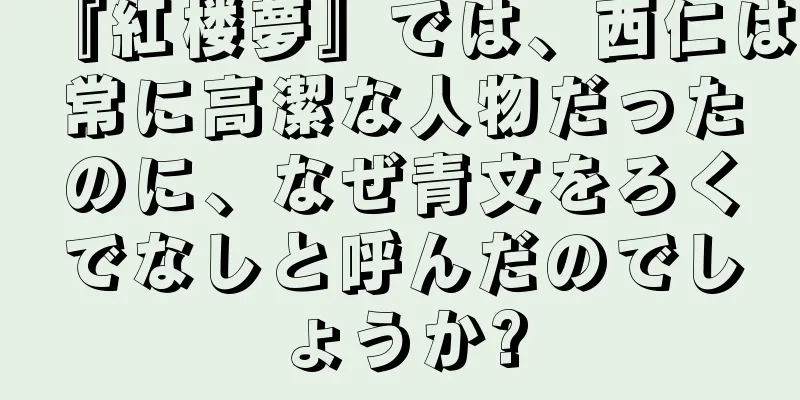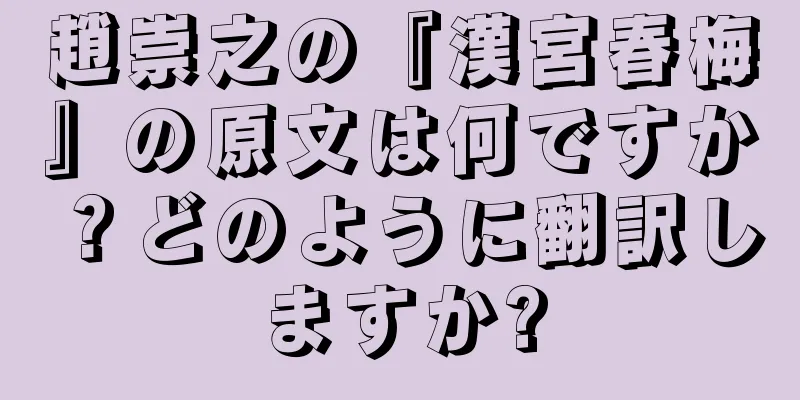「内なる賢者と外なる王」はどこから来たのでしょうか? 「内聖外王」の道とは何か?
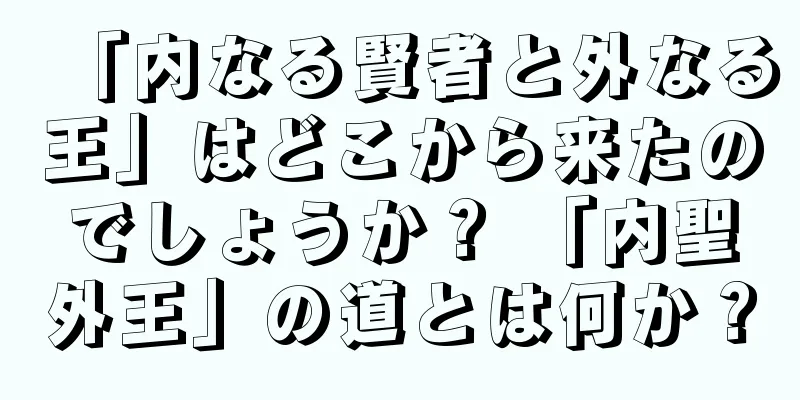
|
今日は、Interesting Historyの編集者が「内なる賢者と外なる王」の道とは何かをお話しします。興味のある読者は編集者をフォローしてご覧ください。 「内なる賢者と外なる王」に関しては、多くの友人は、この概念がどの学派に属するのかよくわかっていません。中国の伝統文化において、「聖人」という言葉が言及されるとき、当然のことながら、最もよく言及されるのは儒教です。結局のところ、聖人の道を追求することは、儒学者の生涯にわたる追求なのです。儒教のある段階では、「外王」という言葉には簒奪の意味がある。 結局、秦以前の儒教も秦以後の儒教も、国を支え、王のために世界を治めることがすべてでした。彼らは「内なる聖人」の心を持っていましたが、「外なる王」になるつもりはありませんでした。後漢末期から隋・唐にかけては文人も帝位争いに加わり、王莽や司馬懿といった儒学者や作家を通じて帝位を垣間見たが、後代の儒教では、儒学者たちはこうした天下を揺るがす文人を真剣に受け止めず、軽蔑さえしていた。歴史を記した文人が王莽の新王朝の記録を残そうとさえしなかったことからもそれがわかる。王莽の新王朝の地位は武周王朝よりもさらに低く、これは文人たちが「外王」に対して心から抵抗していたことを示している。 儒学者の心の中では、「内聖」は個人の修養の頂点であり、「外王」は階級の秩序を乱し、世界に混乱をもたらす行為です。この概念は、宋代の「実業の科学」まで形作られませんでした。「外王」は次第に偉大な業績を成し遂げ、称号や位階を与えられることと同一視されました。「内聖外王」という用語は、儒学の学問において次第に正しいものになりました。心学の創始者、王陽明は、主観的観念論と客観的観念論を統合し、新儒学を発展させ、同時に実務において並外れた成功を達成し、「内は聖、外は王」の典型的な儒教の代表的人物となった。 しかし、清朝末期になって初めて、多くの偉大な学者が「内聖外王」という言葉に注目し、研究し、それに関する論文を書き始めました。これらの説明と解説は、基本的に北宋代以降の朱子学と理学派に基づいており、すべて儒教の師匠による議論でした。そのため、今日では多くの人が「内聖外王」は儒教によって提唱されたと信じており、これらの儒学者の解釈を受け入れています。 実際、「内聖外王」は『荘子・天下』から来ています。 したがって、内なる聖人、外なる王となる道は、不明瞭で不明確であり、抑圧され、表現されない。世の中の人々はそれぞれ自分のしたいことをし、自分を正しい道とみなしている。 つまり、この言葉は道教徒によって提唱されたのです。 さて、この言葉の現代的理解は儒教に支配されていますが、それらはすべて推敲と発展であると言えます。荘子の態度の真の意味を理解したいのであれば、主流と『荘子・天下』の原典と荘子自身の修養と理解から発展した観点を区別する必要があります。 前述のように、儒教の見解では、「内聖」は自己修養であり、「外王」は世俗的な業績である。この説明の側面は、梁啓超の「内聖は自己修養に十分であり、外王は世を治めるのに十分である」という言葉に代表される。簡単に言えば、儒教の基準に基づいて善良な人となり、偉大なことを成し遂げることを意味します。道徳修養が頂点に達すると、人は「内なる賢者」になります。経済的成果が頂点に達すると、人は「外部の王」となる。 この見解は馮有蘭、牟宗三、徐元和、熊世礼らによって支持され、広範囲にわたる影響力を持った。銭済伯や張舜慧など、儒教と道教の相違点を発見し、荘子の本来の意図に即した解釈を与えた人も数多くいます。張順輝氏は次のように提案した。 荘周の教えは孔子や孟子の教えとは異なり、荘周のいわゆる聖人や王は、儒学者が呼ぶ聖人や王とはまったく異なります。 これは、あなたが今「内聖外王」として話していることが荘子の言ったこととはまったく異なることを明確に示しています。 なぜ同じではないのでしょうか? 銭仲書の父である銭継博は詳しく説明しました。 荘子は内賢外王道という学派に名付けた。荘子の深遠な思想はすべて「小瑶有」と「其無論」の2章に集約されている。「小瑶有」は生きとし生けるものすべての偉大な自由を比喩的に表現したもので、「其無論」はさまざまな意見の違いを説明するために使われている。 「小用有」の目的は、自分の本性に適応することであり、それは内なる賢者の道です。「奇無倫」の目的は、物事の変化に調和することであり、それは外なる王者の道です。 言葉は明確ですが、非常に正確です。 『荘子』を読んだ人なら誰でも、『小要有』が荘子の哲学における人間精神の最高の境地であり、個人の内面修養の究極であることを知っています。『去無論』は万物の統一について論じ、自分と世界がいかにして調和するかという問題を扱っています。したがって、荘子の言う「外王」とは、実際には万物と一体化し、調和して生きることを指しているのです。内賢は「自分の性質に適応する」ことを意味し、外王は「物事と調和する」ことを意味します。 「内なる賢者」、道教の「賢者」、儒教の「賢者」でさえ同じものではないことがわかります。荘子が内聖と呼んだのは、「坐して忘る」ことで「心の断食」を達成することであり、それは個人的な利己的な考えを排除し、欲望に囚われず、「心が物とともにさまよう」ことと「天地の精神だけを慕う」ことの自由で束縛されない状態を達成することである。儒教の「聖人」とは、最高レベルの道徳と業績を達成した人、つまり、極めて高い道徳的修養を持ち、人類の発展に多大な貢献をした人のことです。 道教の賢者は自分自身の賢者となり、儒教の賢者は他人の賢者となる。 儒教の聖人は聖人となる過程で、常に修行し、その行いが成功するように努めます。しかし荘子の目から見れば、こうした努力自体が道教に反し、個人が道教の「聖人」となることを妨げる障害となります。老子と荘子の哲学から見れば、儒教が到達できる最高レベルは単に「道と徳」の間の「徳」の部分であり、それはまだ本当の「道」からは程遠い。 孔子は老子と対話した後、神秘的な「道」を脇に置き、「徳」を極めるために努力し、代々の儒学者に受け継がれる「聖人の独特の学問」を創り出しました。 荘子が「外王権」と呼んだのは、「万物と一体になること」であり、外なるものに反抗することも、それに囚われることもなく、いかなる不服従の感覚もなく万物と一体になることです。複雑な外の世界を無傷で進むこの能力は、「内なる賢者」であると同時に「外なる王」であることの現れでもあります。 自分自身の修行を完璧にし、外界と調和して共存すること、これが荘子の内に聖人、外に王となる道である。 しかし、北宋以来、儒教は「内聖外王」という用語を借用して儒教の思想を説明するようになり、「内聖外王」は儒教の内なる道徳の追求と成果を達成するための外的な努力の最高基準となった。 |
<<: 席を配置する際、宋江のニックネームは、以前は最も使われていなかった「胡宝宜」だったのはなぜですか?
>>: 上品な響きの女の子の名前の選び方は?学者気質の女の子に似合う名前をご紹介!
推薦する
水滸伝の童夢の結末は何ですか?トン・メンの紹介
水滸伝の童孟の結末は?童孟は結局どうなったのか?水滸伝の童孟の紹介 水滸伝では、童孟は童維の弟で、地...
古代の人々はどうやって排便したのでしょうか?古代にトイレはいつ登場したのでしょうか?
古代人はどのように排便していたのでしょうか?古代にトイレはいつ登場したのでしょうか?興味のある読者は...
永遠のロマンス:彼女は中国で最も美しい女性であると言っても過言ではない
李世詩は間違いなく中国の歴史上注目すべき女性です。彼女は売春宿にいたにもかかわらず、6つの異なる歴史...
暴露:「女の子は成長すると大きく変わる」とは18歳という意味か、それとも18歳が変わるという意味か?
「女の子は成長すると18回変わる」という諺があります。では、「18」は「女の子は18歳になると変わる...
杜甫は反乱軍に捕らえられ、長安陥落後に長安に送られたので、「月夜」を書いた。
杜甫(712年2月12日 - 770年)は、字を子美、号を少陵葉老といい、唐代の有名な写実主義詩人で...
明朝の皇帝のうち、明の十三陵に埋葬されていないのはどの3人ですか?理由は何ですか?
1368年に太祖朱元璋によって明王朝が建国されてから、1644年に李自成が北京を占領した後、崇禎帝朱...
『湖上の赤い橋の絵車の音』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
環西沙·湖の上の赤い橋の上の彩色された車輪欧陽秀(宋代)湖の上の赤い橋は、塗装された車輪の音で反響し...
影絵はどのようにして生まれたのでしょうか?影絵の歴史の詳しい説明
影絵は中国独特の文化ですが、影絵がどのようにして生まれたのかご存知ですか? 今日、Interesti...
李白の詩「秋浦桃花の昔を思い出す、夜朗に逃げる時」の本来の意味を理解する
古詩:「野朗にいた頃の秋浦桃花公園への昔の旅を思い出す」時代: 唐代著者: 李白湧き水に桃の花が咲き...
「Birdsong Stream」の原文は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
鳥のさえずりの小川王維(唐代)人々が怠けていると、甘いキンモクセイの花が散り、静かな夜には春の山は空...
成漢の皇帝、李雄の物語。李雄に関する興味深い話にはどんなものがありますか?
李雄(274-334)は、名を仲君といい、李徳の三男で、母は羅であった。十六国時代の成漢の初代皇帝で...
『西遊記』で小白龍はどんな罪を犯したのですか?なぜ馬に変わったのでしょうか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
劉長青の『流仙人の嘆き 清河に沈む日』:これを読むと、さらに悲しく、胸が張り裂けるような気持ちになる
劉長清(生没年不詳)、法名は文芳、宣城(現在の安徽省)出身の漢民族で、唐代の詩人。彼は詩作に優れ、特...
ファン・リーファはなぜ薛英龍を殺そうとしたのか?薛英龍は本当に死んだのか?
范麗華はなぜ薛応龍を殺そうとしたのか?薛応龍は本当に死んだのか?これは薛応龍が密かに黒龍女を妻にして...
包公の事件 第89章:僧侶は顔をしかめる
『鮑公案』は『龍土公案』とも呼ばれ、正式名称は『都本鮑龍土百公案全伝』で、『龍土神段公案』とも呼ばれ...