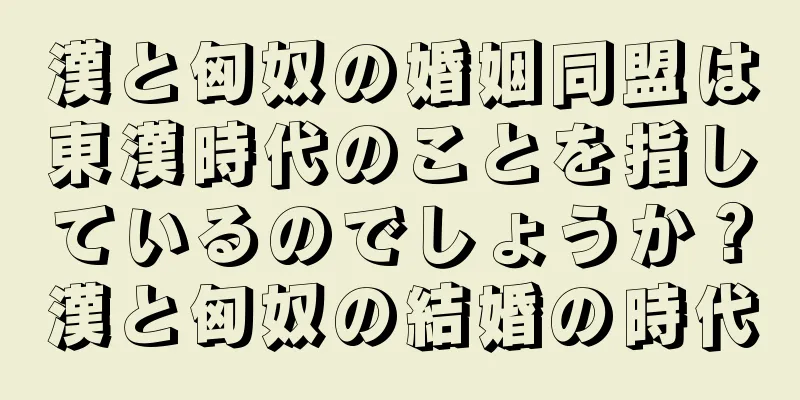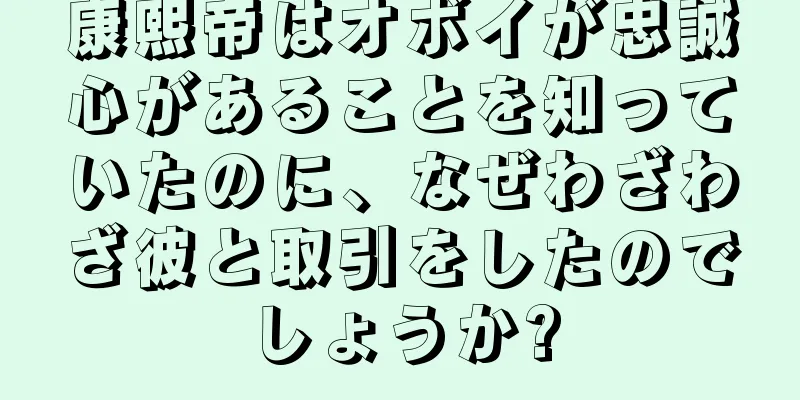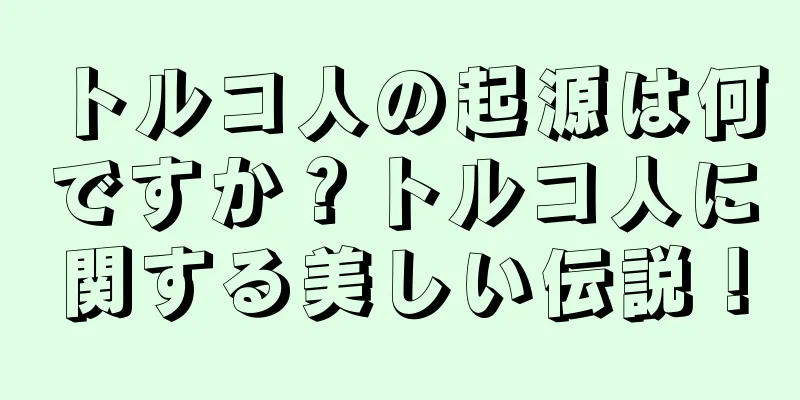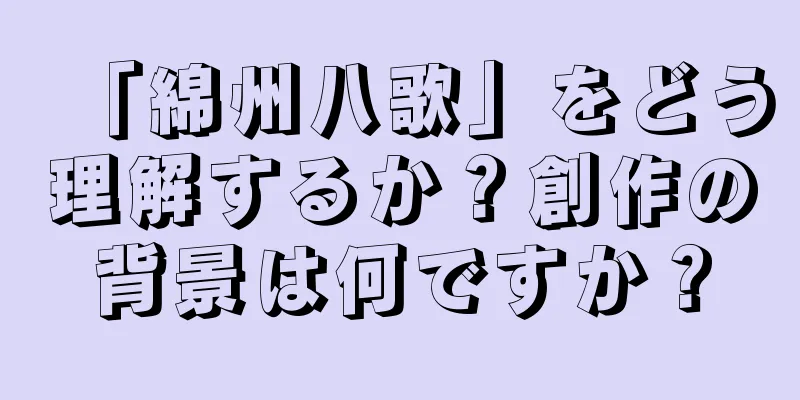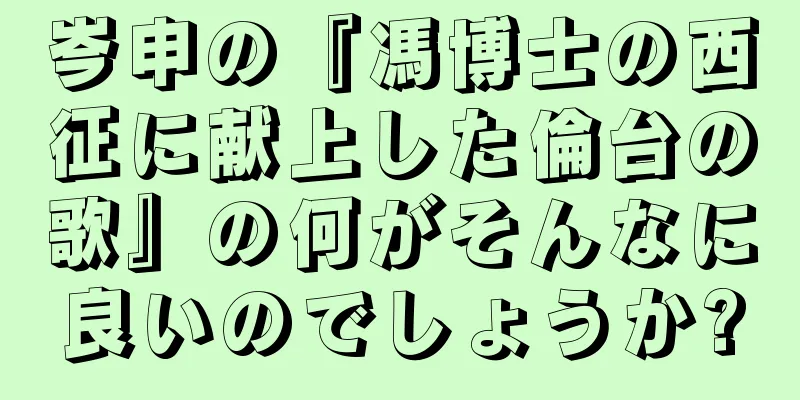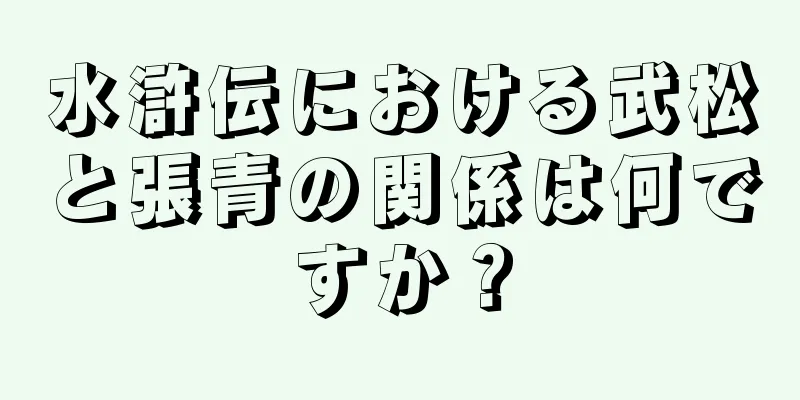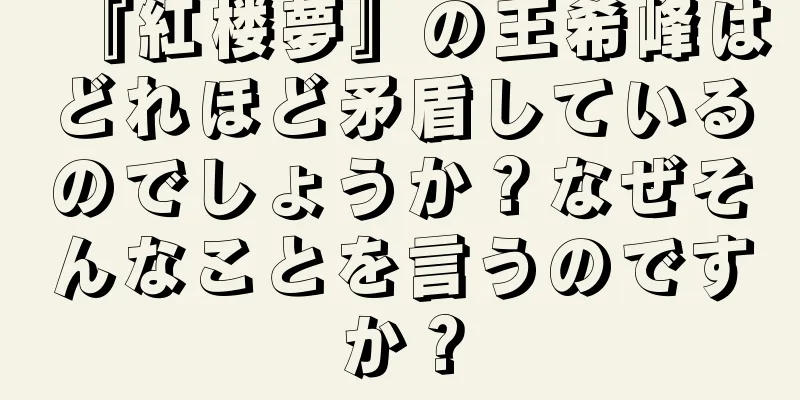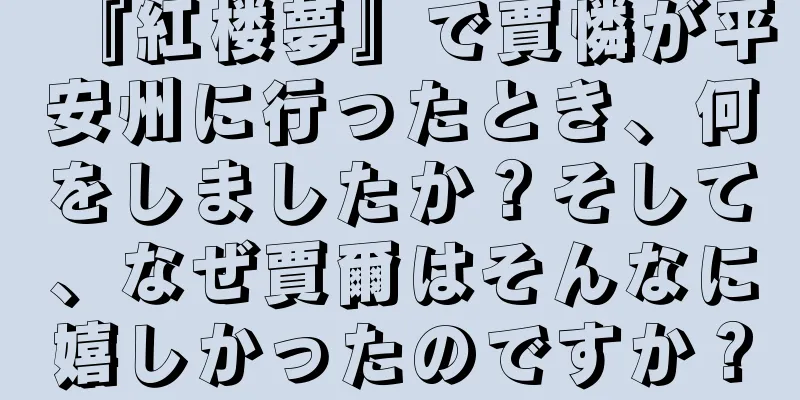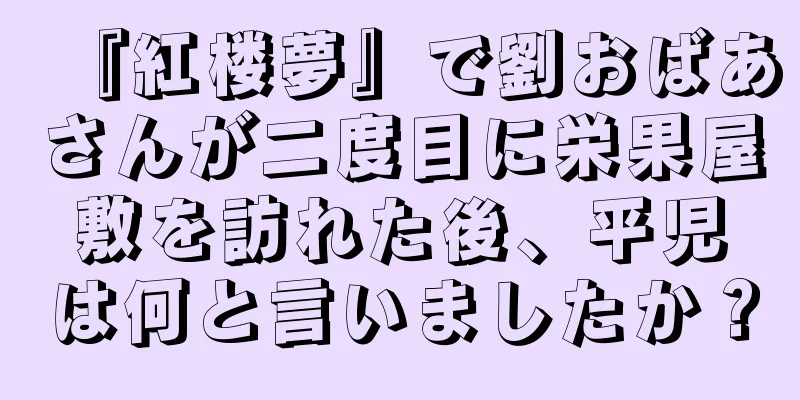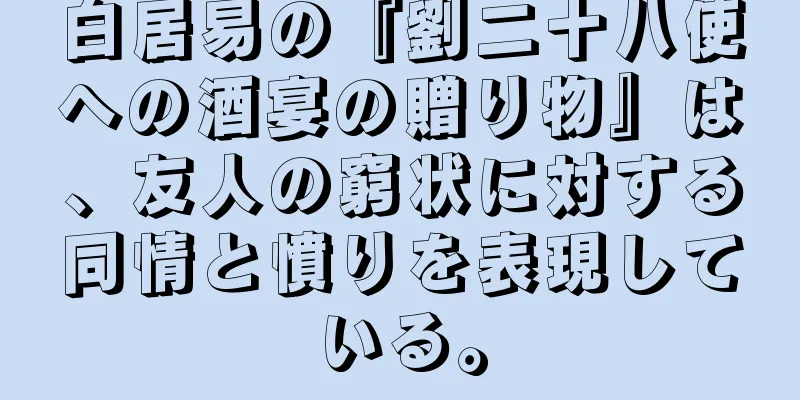三国時代の飲酒文化は非常に衝撃的で暴力的だった
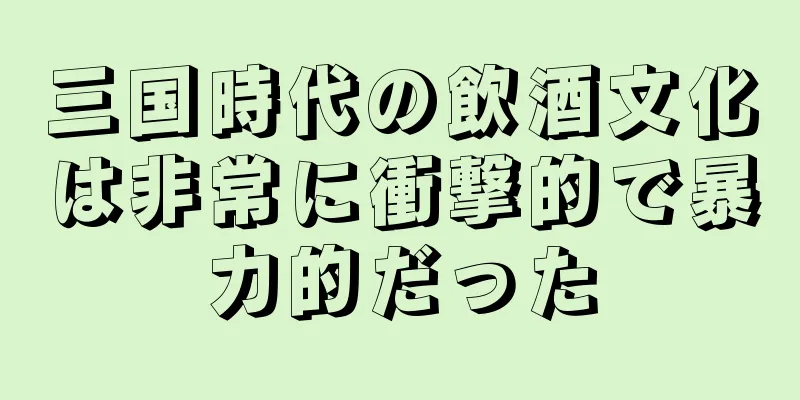
|
張飛は酒好きで、また他人に酒を飲ませるのも好きだった。軍将校たちのために宴会を催すとき、彼は杯に酒を注ぎ、料理を全部出す。そしてこう命じる。「今日はみんな思う存分飲まなくちゃ!」みんなも彼と一緒に飲まなくちゃならなかった。曹宝という酒の飲めない男がいました。彼は張飛に「将軍、私は本当に酒が飲めないんです」と懇願しました。張飛は激怒して「あなたは私の命令に従わなかった。100回鞭打つべきだ!」と言いました。将校全員が彼を説得しようとしましたが、張飛は依然として曹宝に50回の鞭打ちを加えました。 客が飲みたくない場合は、主人が無理やり飲ませる。この飲酒習慣は、現在でも華北と東北地方でよく見られる。しかし、張飛のように、飲酒を拒否した人を殴るということは稀である。おそらく1800年の進化を経て、現代人は三国志の人々よりもはるかに文明化されているのでしょう。 三国時代の飲酒文化は確かに非常に悪かった。張飛が殴って人を酒に誘うのが好きだっただけでなく、劉表もそれを好んだし、曹操もそうだったし、一見優雅に見える孫権でさえもそうだった。 張飛が酒を飲むよう説得する場面は『三国志演義』に出てきます。『三国志演義』は小説なので、信用できないかもしれません。劉表、曹操、孫権などが他人に酒を勧める話は主に『三国志』に見られる。『三国志』は正史であり、その信憑性はかなり高い。 曹丕は『酒経』の中でこう書いている。「荊州太守の劉表は南の地を治めていたが、酒を愛していた。彼は3種類の酒器を作った。大きいものは博牙、二番目は中牙、小さいものは夾牙と呼ばれていた。博牙には7リットルの酒が入り、中牙には6リットルの酒が入り、夾牙には5リットルの酒が入った。」これはどういう意味か?荊州太守の劉表は酒好きで、自分のために3つの酒器を作ったということだ。大きいものは「博牙」と名付けられ、7リットルの酒が入る。中くらいのものは「中牙」と名付けられ、6リットルの酒が入る。小さいものは「夾牙」と名付けられ、5リットルの酒が入る。 『中国史度量衡研究』244ページによると、後漢末期から三国時代の1リットルは現在の0.2リットルに相当するため、「伯牙」は2斤4符、「中牙」は2斤2符、「集牙」はちょうど2斤入ることになります。現在、中国本土の酒瓶の重さは通常1斤、ビール瓶の重さは通常1斤2オンスです。したがって、「Ji Ya」には酒瓶2本、「Bo Ya」にはビール瓶2本が入ります。 漢魏時代には蒸留酒はなく、醸造酒のみで、醸造法は比較的広範でした。北魏の賈思詢が『斉民要書』に記した醸造法によると、水と米の比率は1対1以下で、二次発酵を経なければ、完成した酒の温度はせいぜい5度を超えず、これは今日の江蘇省と浙江省のもち米甘酒と非常によく似ており、「酸っぱくて甘いのは私」というスローガンで宣伝することができます。 たとえアルコール度数の低いワインであっても、一般の人がそれを大量に飲むことはないでしょう。劉表はどのように飲んだのでしょうか。博雅、中雅、吉雅の3つの杯を一列に並べて、すべてに酒を注ぎました。次々と一気に飲み干し、7ポンド近くの酒を一気に飲み干しました。 張飛と同じように、劉表も酒をよく飲み、客にもたくさん飲むように頼みました。飲みたくない人がいれば、無理やり飲ませました。 前述のように、張飛が酒を飲ませるために使った方法は鞭打ちであり、非常に乱暴なものでした。劉表はもっと控えめで、人々に酒を飲ませるには針で刺すという方法を使った。曹丕は『酒経』の中でこう書いている。「(劉表は)また、棒の先に大きな針をつけておき、客が酔って寝てしまったら、その針で刺した。」酔っ払っているなら、飲み続けられるように刺してやる。とても親切ですね。 曹操自身は酒をあまり好まず、権力を握った後も一時期酒を禁止していたが、人々に酒を飲むよう説得することには非常に積極的だった。 『三国志 魏』第18巻には、「太祖が荊州を征服すると、万に着き、張休は降伏した。太祖は非常に喜び、張休と将軍たちを盛大な宴会に招いた。太祖が酒を振る舞うと、魏は太祖の後ろに立ち、刃渡り1フィートの大斧を持っていた。太祖が通るところはどこでも、魏は斧を振り上げて太祖を見た」とある。曹操が先頭で乾杯し、典韋は大斧を持ってすぐ後ろについていった。曹操が誰に乾杯しても、典韋は斧で敬礼した。意味は明らかです。飲まないのか?切り殺してやるぞ! 孫権は曹操よりも有能だった。 『三国志』の『張昭伝』には、「権は武昌で釣魚台で酒を飲んで酔っ払った。彼は人々に高官たちに水をかけるよう命じて言った。『今日は思う存分飲もう。酔って壇上から落ちるまで止めないぞ』」とある。当時の情景は次のようなものだったに違いない。孫権は高壇の上で文武の官僚たちを招いて宴会を開き、皆に酔うように命じた。客の一人が飲もうとしないとき、孫権はその客に水をかけさせ、「早く飲め。めまいがして落ちるまで飲め!」と命じた。これはもはや、酔うまで飲むのではなく、壇上から落ちるまで飲むことだった。孫権が人々に飲酒を勧める激しさを証明するもう一つの例がある。 『三国志』呉志の于凡伝には、次のように記されている。「孫権が呉王になったとき、宴会の終わりに立ち上がって酒を飲んだ。于凡は地面に倒れ、酔ったふりをした。孫権が去ると、于凡は起き上がった。孫権は激怒し、剣で彼を殺そうとした。」孫権は孫権に酒を飲むように説得したが、于凡は酔ったふりをした。孫権はそれを知り、激怒した。彼は彼を殺そうとした! 三国志の英雄たちは皆お酒が好きだったことから、お酒を飲める者だけが官僚になれるという暗黙のルールには歴史的なルーツがあることがわかります。三国時代に生まれてお酒も飲めないなんて、ありえない!! |
推薦する
李毅の「義兄に会えて嬉しい、また別れを告げて」:この詩には現実感が強く感じられる
李懿(746-829)、号は君有、隴西省古蔵(現在の甘粛省武威市)の出身。後に河南省洛陽に移住。唐代...
江世全の「年末帰郷」はどのような感情を表現しているのでしょうか?
江世全の「年末帰郷」はどのような感情を表現しているのでしょうか?この詩は、放浪者が久しぶりに家に帰っ...
秋楚麿は仙人になったのか?それを言うにはどんな方法がありますか?
中国の長い歴史には、多くの謎の人物や物語がありますが、そのうちの1つが秋楚基です。彼は南宋時代の有名...
赤壁の戦いの後、黄蓋は突然姿を消したようです。どこへ行ったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
宋代の詩「十一月四日風雨」を鑑賞します。陸游は詩の中でどのような情景を描写したのでしょうか。
宋代の陸游が11月4日に書いた2つの詩。次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介します。見てみましょう!風...
『新説世界物語』第75条はどのような真実を表現しているのでしょうか?
『十碩心于』は南宋時代の作家劉易清が書いた文学小説集です。では、『十碩心於・談話・75』に表現されて...
Fanという姓の先祖は誰ですか? 2020年に子年生まれで姓がファンの赤ちゃんにどのような名前を付けますか?
今日、Interesting Historyの編集者は、2020年にFanという姓を持つ子ネズミにど...
水滸伝で、なぜ呉容は宋江に従い、趙蓋を裏切ることを選んだのですか?
呉勇は小説『水滸伝』の登場人物で、涼山第三位にランクされています。次回は、Interesting H...
時間の順序は何を意味するのでしょうか? 『The Order of Time』の書評を共有します!
『The Order of Time』とはどのような内容ですか? 『The Order of Tim...
4つの偉大な古典からの最も感動的な引用60選:人生の全物語を語る
四大古典のテーマはそれぞれ異なります。『紅楼夢』は愛、『水滸伝』は義、『三国志演義』は闘争、『西遊記...
三英雄五勇士第3章:金龍寺の英雄が初めて敵を救い、人里離れた村のキツネが3度目の恩返しをする
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
廉頗が趙国に忠誠を誓っていたことは間違いないが、晩年、なぜ魏国に逃亡したのだろうか。
廉頗といえば、誰もが知っている人物です。「廉頗は年老いてもまだ食べられるか?」という一文を誰もが聞い...
古典文学の傑作『淘宝夢』:第3巻:湖畔亭の雪見
『淘安夢』は明代の散文集である。明代の随筆家、張岱によって書かれた。この本は8巻から成り、明朝が滅亡...
『江南を思い出す:泥を運ぶツバメ』の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
江南の思い出:泥を運ぶツバメ牛喬(唐代)泥を運んだツバメが絵画館の前に飛んできました。杏の木の梁の上...
二十四将軍の順位を見ると、曹魏陣営に属していた曹洪がなぜリストに載っていないのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...