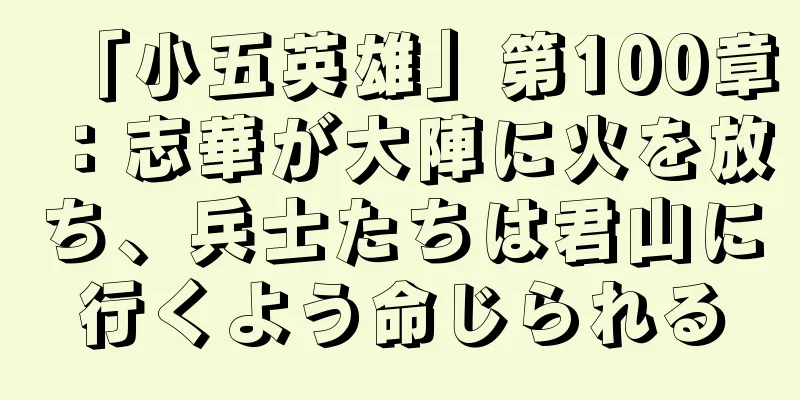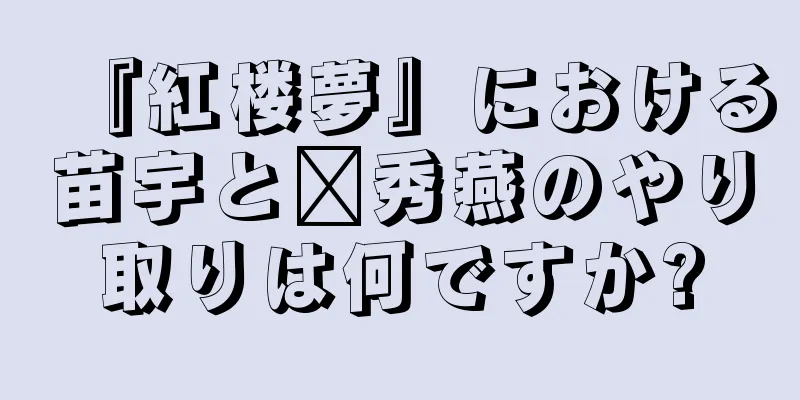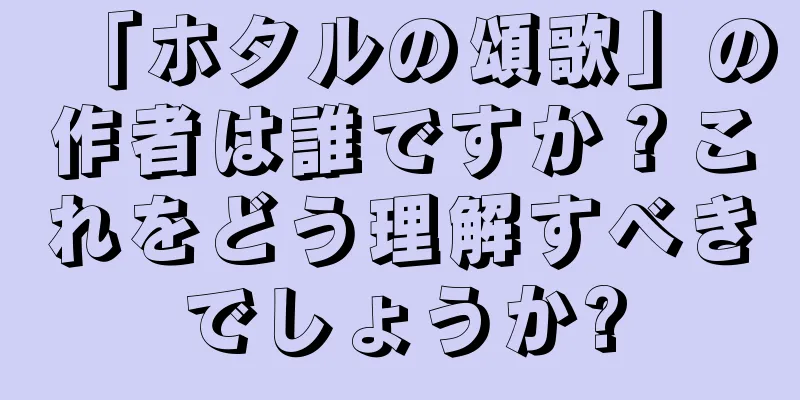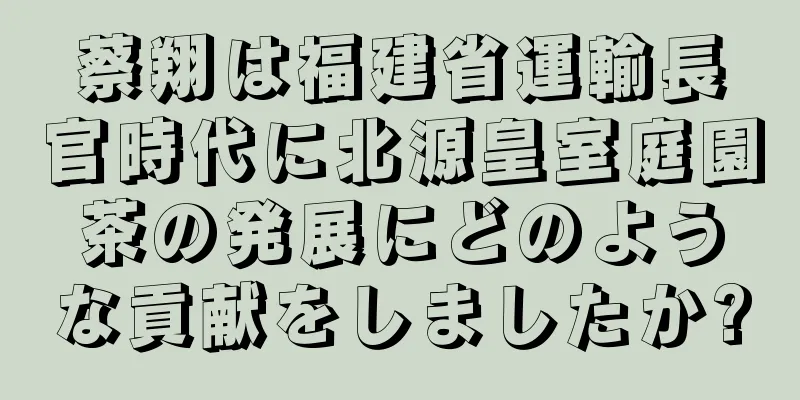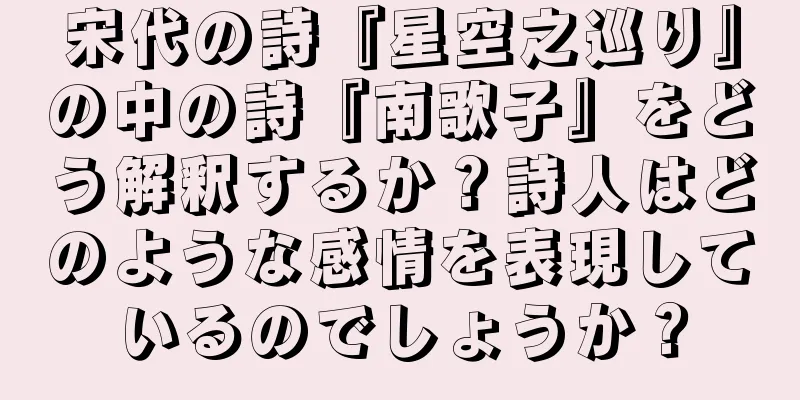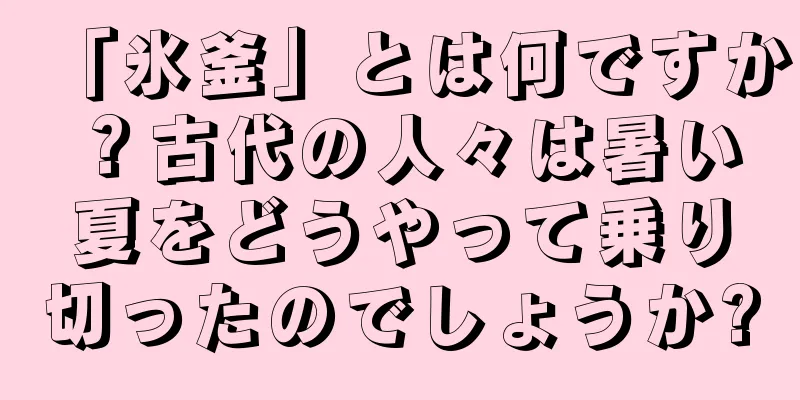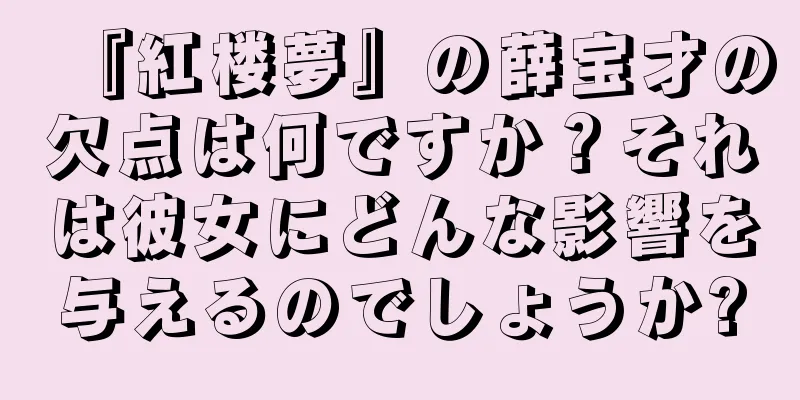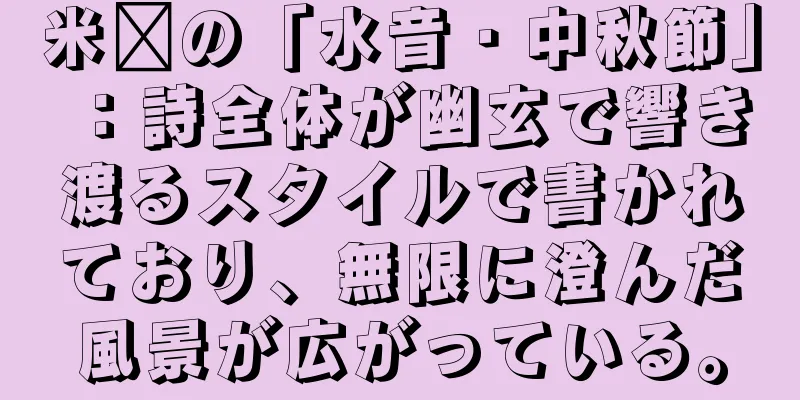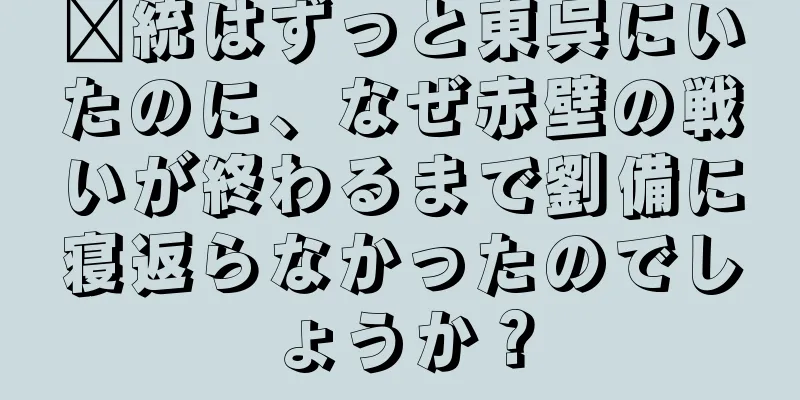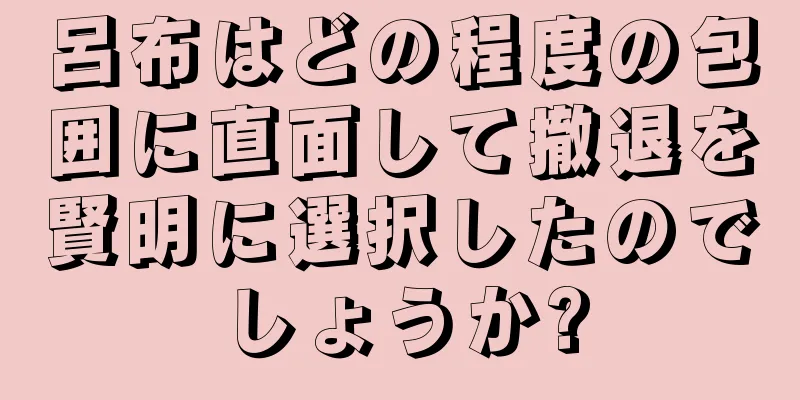魏、晋、南北朝時代に強力な王朝が出現しなかったのはなぜですか?貴族たちは権力の集中を抑えた!
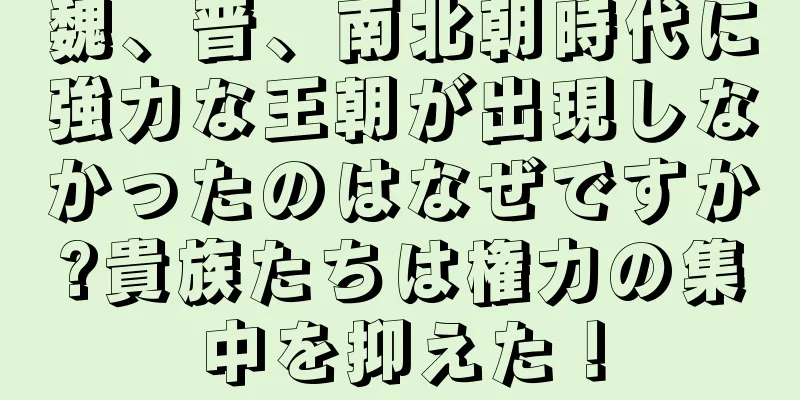
|
今日は、おもしろ歴史編集長が、魏晋南北朝時代に強大な王朝が出現しなかった理由についてお伝えします。皆様のお役に立てれば幸いです。 「青天は死に、黄天は立てよ。嫦子の年、天下は福なり。」 西暦184年(嫦子の年)、中朝の大半を襲った大混乱は、予期せず漢帝国を瀕死の状態に引きずり込んだ。 予期せぬことだったと言うのは正確ではない。 東漢の哲学者、王充の「氷の厚さは3フィートで、一日で冷えない」という理解がなかったとしても、人間は問題がそれほど単純ではないことを理解するのに十分な経験を持っているはずだ。 人々の心を推測することに重点を置いている文人は、常に王朝の崩壊を特定の皇帝や将軍の怠慢や不作為のせいにしたがる。 最も大きなスケープゴートになるのは、往々にしてその王朝の最後の皇帝である。もし彼に「幸運」があれば、罪を分かち合うのを助けてくれる美しい女性がいるだろう。幸いなことに、『三国志演義』の人気により、ほとんどの中国人は漢の献帝の悲劇的な人生に同情し、その責任は一般的に漢の霊帝に帰せられる。しかし、さらに深く調べてみると、混乱の種は実は王朝の初めに植えられていたことがわかります。 東漢王朝は、その権力は創始者である劉邦に由来すると信じていましたが、ほとんどの人は今でも東漢王朝と西漢王朝を2つの王朝として考えるべきだと信じています。結局、現在では改革者として再評価されている王莽は、前漢の統治体制に壊滅的な損害を与えました。劉秀は実際にその廃墟の上に新しい王朝を再建したのです。つまり、王朝の初めに混乱の種がまかれたことを認めるならば、責任を負わされるべきなのは劉邦ではなく劉秀である。 人口と土地は、国の存在を支える二つの主要な要素です。農業文明を背景とする帝国が効果的に運営できるかどうかは、人口と土地をコントロールできるかどうか、そしてより多くの資源を集中させる健全なシステムを確立できるかどうかにかかっています。古代中国では、この資源収集システムは「課税」と呼ばれていました。いわゆる「税」は、もともとは農地を基準に課税される農産物を指し、「税」の横にある「禾」という文字からわかるように、「賦」の本来の意味は人口を基準に課税される通貨である。もともとは軍事費を直接支払うために使われており、「fu」という文字が「贝」と「武」という2つの文字で構成されていることからもそれが分かります。 税金に加えて、労働力の直接徴発も農業帝国を運営するための基本的な手段です。この方法は「サービス」と呼ばれます。税金、賦課金、労働サービスの 3 つの形態は、土地と人口という 2 つの基本要素から始まり、国の利用可能な資源を最大限に集中させることができます。 この資源集中システムを体系的に実施した最初の国は、商鞅の改革によって改革された秦国であり、その結果、秦国は中央国を帝国の時代へと導きました。課税対象を上記の3つの形式に従って分類し、「税」という言葉を総称すると、王朝によって名称がどのように変化したとしても、実際には「財産税」と「人頭税」の2種類に分類できます。そのうち、税金と労働奉仕は「人頭税」に分類されます。人頭税の対象は主に成人男性であるため、「定税」とも呼ばれます。 人間が自然を変える手段を持たない自然経済の時代において、人口は最大の資源です。人頭税は権力を生み出す重要な手段です。この観点から見ると、商閻の改革が秦を六つの国の中で際立たせた理由と、本質的には同じままのこの帝国運営システムがなぜ中央の国で二千年以上も運営できたのかも理解できます。今日では、国民に依然として兵役が義務付けられている一部の国を除いて、人頭税は人々の生活からほぼ姿を消しています。これは、中国語では「税金」が政府による資源の徴収の一般的な名称となり、「兵役」という言葉が世界に残っている理由でもあります。 工業および商業活動から十分な税収を徴収する能力と、工業力によって人的資源がもはや最も重要な資源ではなくなったという事実は、人頭税がほぼ消滅した2つの主な理由です。しかし、「農業を促進し、商業を抑制する」ことを信条とする中央帝国にとって、世界が工業と商業の力によって変化したと真に実感できるまで、商陽モデルを変更する動機はありませんでした。結局のところ、自然経済の文脈では、このモデルの集中化された効率性は非常に強力であり、理解しやすいのです。 一連の運用メカニズムがいかに合理的に見えても、最高統治者がそれをすべて単独で実行することはできません。つまり、国がどのようなモデルであっても、ピラミッド型の組織構造の出現は避けられないということです。楽観的に見れば、人類が氏族社会から文明社会に移行したのは、ピラミッド型の組織構造が導入され、分散していた権力が集中するようになったからであり、悲観的に見れば、この国の経営層を支配層と呼ぼうが、官僚や資本と呼ぼうが、利益集団が形成されるのは必然である。税金の圧力は常に、管理されている最下層の人々に当然かかることになる。特に中央帝国について言えば、国内に血液を供給する主力は、人口の絶対多数を占める自家耕作農民たちであることがわかるだろう。 利益団体は常に自らの利益を国家の利益よりも優先させる方法を持っているため、自家耕作農家により多くの土地を管理させるのは、帝国がマクロリスクを軽減するための基本的な方法である。自耕農民が管理する農地の割合が王朝の健康指標(現代社会で言えば「中流階級」の割合)を決定するとも言える。一般的に言えば、旧体制の崩壊と人口減少によってもたらされた内閣再編の影響により、王朝は初期段階ではこの問題を比較的容易に解決することができます。しかし、時間が経ち、利益団体が形成されると、土地は必然的に少数の人々の手に集中することになります。 土地の併合は住民の「消滅」につながる可能性もある。いわゆる「失踪」は、実際には失踪ではなかった。土地を失った自耕作農民は人頭税の支払い義務を軽減することができなかったため、身を潜めて大地主に頼ることが一般的な選択肢となり、大地主にはこの人口の一部を積極的に報告する動機がなかった。つまり、王朝が長く続くと、中央政府に血液を供給できる土地と人口がどんどん少なくなるのです。漢王朝の場合、これらの資源は主に地元の「有力者」の手に集中していました。 帝国の統治者は誰も、自分が脇に追いやられるのを見たくない。 「人々を墓の中に移住させる」というのは、前漢時代にこの問題を解決するために使われた方法の一つでした。漢の元帝の時代までは、歴代の皇帝は自分の陵墓を建てる際に、対応する郡(歴史的には「霊県」と呼ばれていた)を設置し、皇帝の死後、多くの地方の暴君が関中の「霊県」に移されました。このポリシーには確かに一定の技術的効果があると言わざるを得ません。西漢末期には、霊県は関中の人口のほぼ半分を占めていた。 しかし、有力者の定期的な集中的な移住は、特に強い地元意識を持つ中国人にとって、地方レベルでの激しい抵抗につながることは必至だ。紀元前40年、1世紀半にわたって施行されてきたこの政策は終了しました。さらに32年後、領土併合問題が内政改造で解決しなければならない段階に達したとき、改革者王莽と彼の「新王朝」が歴史の舞台に登場した。この失敗した実験は14年間(新王朝9年1月15日~新王朝23年10月6日)続き、東漢と西漢の分岐点にもなった。 王莽の過度に理想主義的な制度改革はほぼすべての社会階級の反感を買ったが、最終的に改革を終わらせた支配的な勢力は資源を保有していた地方の暴君たちだった。東漢の創始者である漢の光武帝、劉秀自身が権力者の代表でした。確かに、初代皇帝の場合、本来の資質が必ずしも改造の決断に影響を与えるわけではない。 ほとんどの場合、帝国の長期的な安定のために、前王朝から残った古い勢力であろうと、政権樹立中に成長した新しい勢力であろうと、中央政府を弱体化させる可能性がある限り、容赦なく粛清されます。しかし、歴史上数少ない「完璧な」皇帝の一人である劉秀は、前漢のように新旧の勢力を粛清したり、地方を抑圧したりすることはなかった。土地を測量し、有力者に隠れた住民を引き渡すよう要求することは、中央政府の統制を強化するための好都合な手段となった。王朝の交代の間に勢力を強めた地方の暴君たちは、新しい時代においてもその存在を続けることができた。 劉秀のやり方が正しかったか間違っていたかは言うまでもないが、結局のところ、彼が政権をいとも簡単に樹立できたのは、地元の有力者の支援と前漢の政治的遺産と密接に関係していた。もし王莽が自らの王朝を樹立することにそれほど熱心でなく、漢の名においてこの改革を実行していたら、動乱の後ですでに末期状態にあった漢王朝は、おそらく過去のものになっていただろう。劉秀が破壊してから建てるという建国の方法を主張しなければならないと仮定すると、新莽王朝によってそらされていた矛盾の焦点は、彼と彼が継承しようとした政治的遺産に向けられることになるだろう。 劉秀が別の選択をしていたら歴史はどのように発展していたかは、タイムトラベル小説家にとって興味深いテーマである。ビッグヒストリーの観点から、2つの点が確認できます。1つ目は、210年間続いた前漢王朝は、再建する前に解体しなければならないほど内部矛盾を蓄積していたことです。2つ目は、後漢王朝が地方の有力者と妥協したことで、わずか1世紀半で再び混乱の淵に立たされたことです。パンドラの箱が開かれると、権力層全体が自らの利益を守ることに一層関心を持つようになる。 私が「強大な権力者」という問題から始める理由は、この階級の強力な影響力が三国時代を通じて貫かれているだけでなく、この時代の官僚制度と完璧に融合して「貴族」階級を形成しているからです。権力者が貴族家系になると、自らの利益を守るために必然的に経営体制全体を強固なものにし、事実上の貴族制を形成する傾向が出てきます。その影響は王朝を超えて、晋、南北朝にまで浸透し、唐代初期まで続きました。一つの帝国が次々と君臨し、また別の帝国が君臨するこの混沌とした世界では、次の統一された帝国が出現するまでの待ち時間は非常に長いのです。 いわゆる「貴族制」とは、政治権力が世襲貴族の代表者によって支配されているという事実を指します。絶対君主制に代表される「中央集権的」システムが出現する以前は、貴族政治は、文明段階に入った後に人類が採用したほぼ唯一のモデルでした。特定の世襲貴族制度がどのようにして内部循環を完了し、新鮮な血を補充し、君主を選出し、さらには王朝を交代させるかは、重要な点ではない。重要なのは、これが君主や王朝よりも長く存続した支配階級であり、この階級が土地と人口に対して支配力を持っていたということである。 さらに大きな問題は、貴族階級の存在により、国を統治するために必要な官僚も世襲制になっていることです。主に貴族の家庭から官僚を選出するこの方法は、中国の歴史では「世襲官僚制度」と呼ばれています。中国の歴史において、秦以前の時代は、公式には「奴隷社会」とされていたものの、実際は「封建社会」であり、世襲制の官僚制度を実施していた。 「封建時代」がより長く続いた国々では、世襲制の官僚制度もより長期間存続した。例えば、英国議会の上院として機能する「貴族院」は、現在この公的制度の典型的な代表例です。 世襲制の官僚制度の存在は、間違いなく国の中央集権的な権力をさらに弱めることになるだろう。中央王国が帝国時代に入り、意識的にオーバーヘッド現象を抑制し始めたとき、新しい公式システムを導入する必要がありました。この官制は漢の武帝の時代に施行された「曹坤制度」であった。その主な特徴は、地方官が管轄区域内の人材を審査・選抜し、上司や中央政府に推薦することです。こうして選ばれた人材は「孝行、誠実」を意味する「小廉」と呼ばれ、評価を経て官吏に任命された。例えば、曹操は174年に推薦制度を通じて官職に就きました。 しかし、「親孝行、正直」という要件には定量的な基準がなく、推薦制度自体も十分に制度化されていなかったため、高官の間で代々近親交配が続くことは避けられなかった。代々官僚を務めてきたこれらの人々は、今度は「4代で3人の官僚」を擁した汝南の袁家のように、地方の暴君となる。 三国時代には、権力者と官僚制度が有機的に融合し、貴族的な属性を持つ「家」が生まれました。曹魏に始まり、晋、南北朝時代に流行した新しい官僚制度、九階制度は、400年にわたって人材を選抜する主流の方法となりました。この制度の導入当初の意図は、選抜制度のルールを洗練させることであったが、貴族家の影響を受けて、必然的に世襲官吏制度の変種となってしまった。 貴族階級の形成が中国の政治に与えた最も大きな影響は、魏・晋の時代から隋の時代にかけて強力な王朝が出現しなかったことである。その結果、「魏晋南北朝」時代は中国史上最も有名な激動の時代となった。隋唐の第二帝国で科挙制度が活用・推進されて初めて、中央帝国は社会の底辺から才能ある人材を体系的に選抜できるようになり、この架空のモデルに対処する上で真の突破口が見いだされたのである。 この画期的な進歩自体が土地併合の問題を解決するわけではないが、固定された利害関係者による土地の独占を防ぐことはできる。そこから生じる政治現象は、王朝の内部矛盾が解消しなければならないほどに蓄積されると、上から下まで徹底的な内閣改造が必要になることが多いということである。 三国時代の存在を、歴史の大いなる展開という観点から考察することができれば、この時代に対する解釈に新たな意味が与えられる。この時代は、黄巾を巻いた農民集団がきっかけとなったというよりは、地方の暴君たちが長年蓄積してきた権力が爆発する機会を得て、三国時代の助けを借りて、権力の所有に直接影響を与えることができる「貴族階級」へと進化した、と言った方が正確でしょう。魏、蜀、呉の三国、そして最終的に利益を得たと思われた晋も、権力者によって選ばれた対象だったようだ。この観点から見ると、いわゆる三国時代はまさに「強者の饗宴」にほかなりません。 |
<<: 世界で最も奴隷が多い国!モーリタニアはなぜ奴隷制度を廃止しなかったのですか?
>>: なぜ学者は隋の煬帝を呪うことができないと言われているのでしょうか?学者と隋の煬帝との関係!
推薦する
清朝の衣装:清朝の公式宮廷衣装
清朝の官服、清朝の役人が着用した衣服。清朝の公式の制服制度も清朝の社会・政治制度の特徴を反映していま...
『東周記』第7章 - 公孫炎が戦車を奪い、高叔を撃ち、公子慧が盗賊の殷公を喜ばせる
鄭の荘公は皇太子から緊急の手紙を受け取ると、すぐに軍隊に帰還を命じたと言われています。 Yi Zho...
明代末期の将軍、毛文龍をどのように評価しますか?
毛文龍は明代末期の遼東戦争における重要人物であった。天啓元年(1621年)、太守の王華真から、約20...
朱淑珍にとって春とはどんなものなのでしょうか?彼女はどんな詩を残したのでしょうか?
朱淑珍は宋代の女流詩人で、唐宋代以降最も多くの作品を残した女性作家の一人である。李清昭ほど有名ではな...
燕王丹の紹介 燕王丹はどのようにして亡くなったのでしょうか?
燕王丹の紹介燕王丹(紀元前226年?- )は、姓は冀、名は丹で、燕王喜の息子であり、戦国時代後期の燕...
ロシアの習慣とタブーの紹介
ロシア人は明るく、ユーモアがあり、国民としての自尊心が強く、一般的に親切で礼儀正しい。客人を迎える最...
なぜ馬超は劉備に降伏し、龐徳は曹操の部下になったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
張良はなぜ劉邦が皇帝になってから隠遁生活を送り、公の場にほとんど姿を現さなかったのでしょうか?
「十分なものを持つよりは、十分に持っているときにやめるほうがよい。何かを鋭く保つことは不可能である。...
関羽率いるこのあまり知られていない軍隊とはどのような軍隊でしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
襄公17年に古梁邇が書いた『春秋古梁伝』には何が記録されていますか?
古梁邁が書いた『春秋実録古梁伝』には、襄公17年に何が記されているのでしょうか?これは多くの読者が気...
『西遊記』では白龍馬が金龍に変身して柱に巻き付いていたが、これは「名ばかりの昇進、実質の懲罰」なのか?
西遊記では、白龍馬が経典を手に入れた後、金色の龍に変身して柱に巻き付きました。多くの友人は困惑してい...
歴史上の盗賊たちも詩を朗読するのが上手で、レベルがかなり高かったですよね?
歴史上の盗賊たちも詩を暗唱するのが上手で、レベルがかなり高かったことが判明しました。興味深い歴史の編...
三家分裂の過程とは何ですか?三家分裂の歴史的意義は何ですか?
三家分裂の過程とは何だったのでしょうか?三家分裂の歴史的意義とは何でしょうか?今日は、Interes...
解釈:西漢王朝の紹介と西漢王朝の歴史の概要
はじめに:前漢王朝とも呼ばれる西漢は、古代中国の王朝です。後漢王朝とも呼ばれる東漢王朝とともに、総称...
中国ではお茶は非常に長い歴史を持っています。様々な場面でお茶をどのように飲んでいますか?
中国人は昔からお茶を飲むのが好きで、一人でお茶の香りを楽しみながら飲むのも、自宅で心を込めてお客さん...