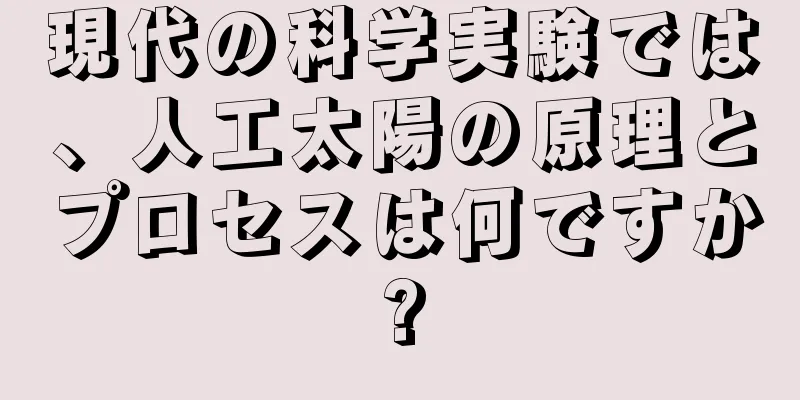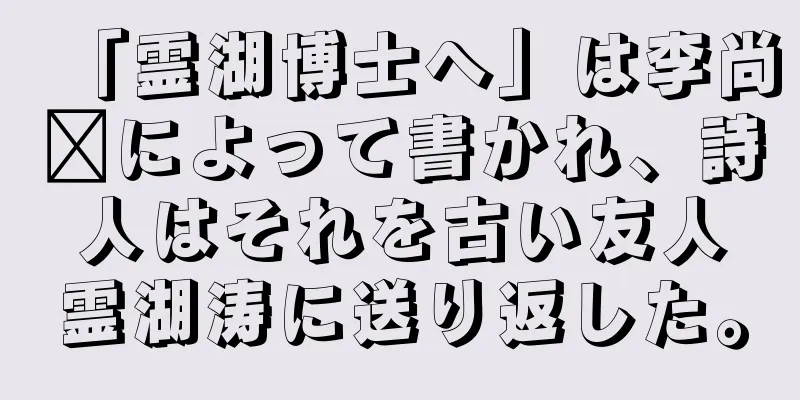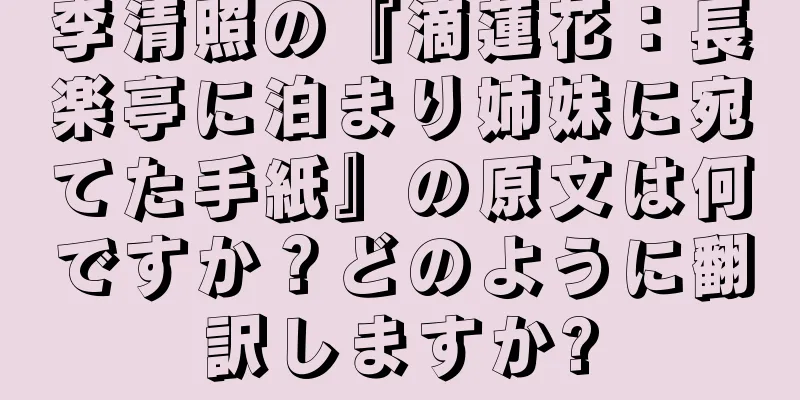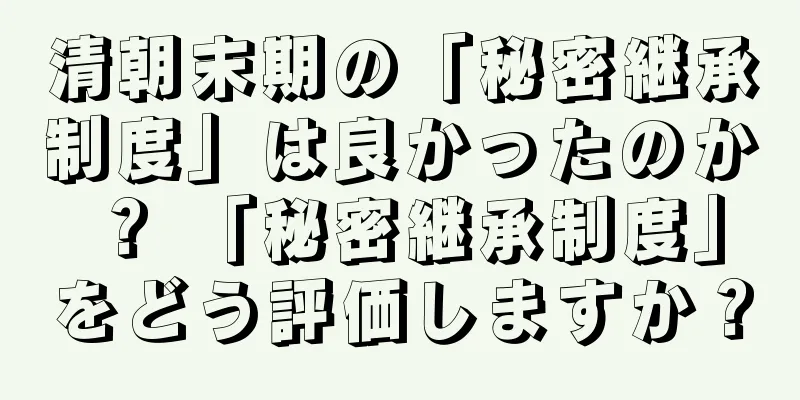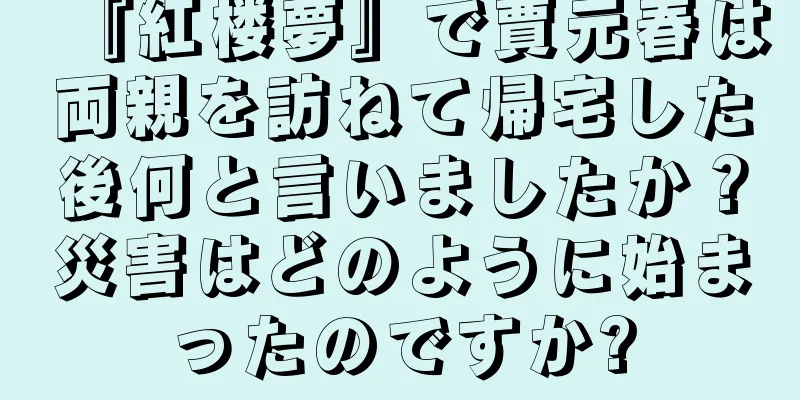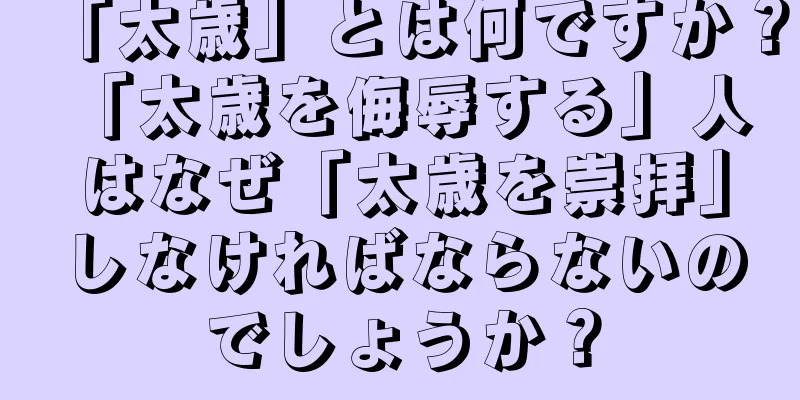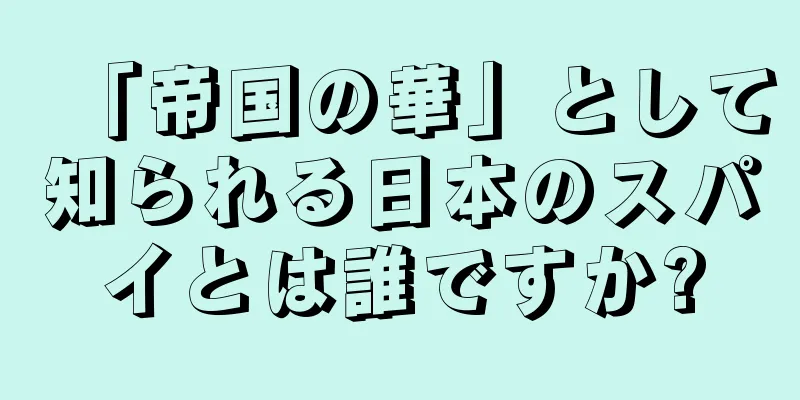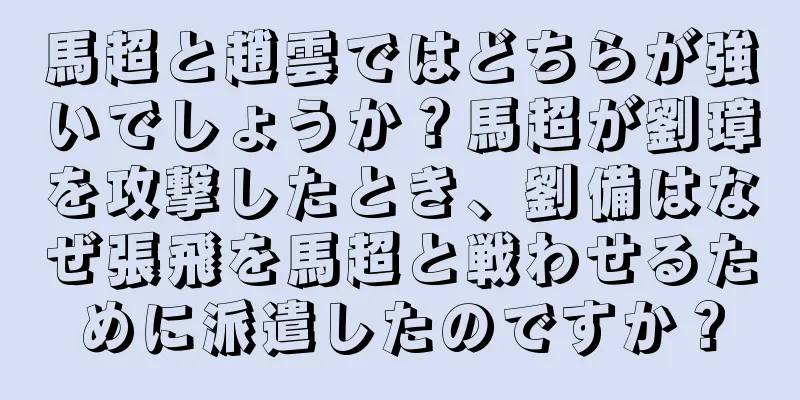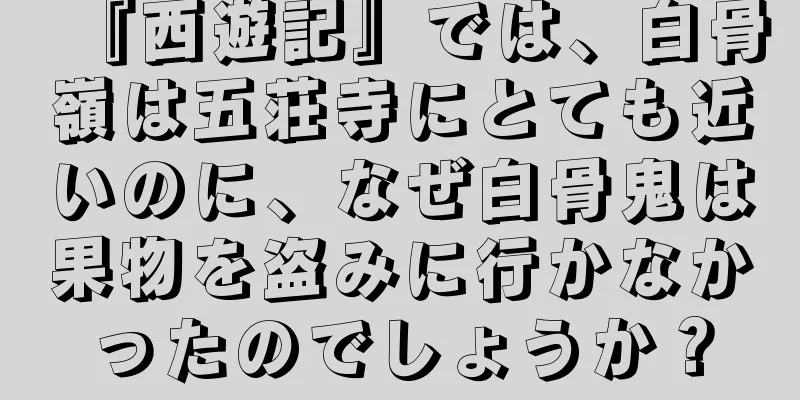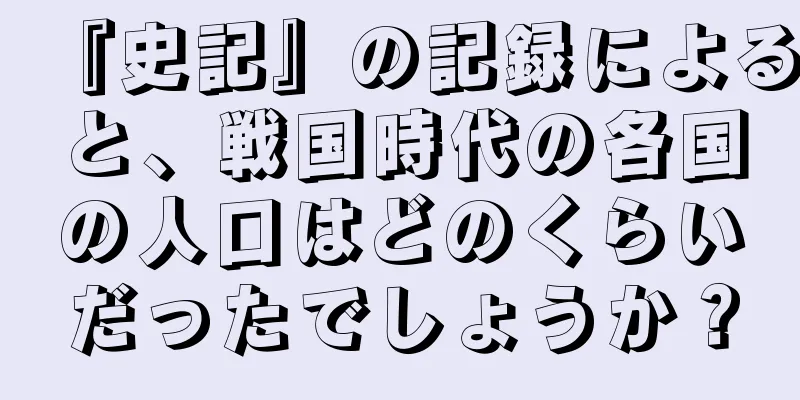春秋時代の鄭州の地理的位置はどれほど不便だったのでしょうか?直接影響を受けた回数は80回
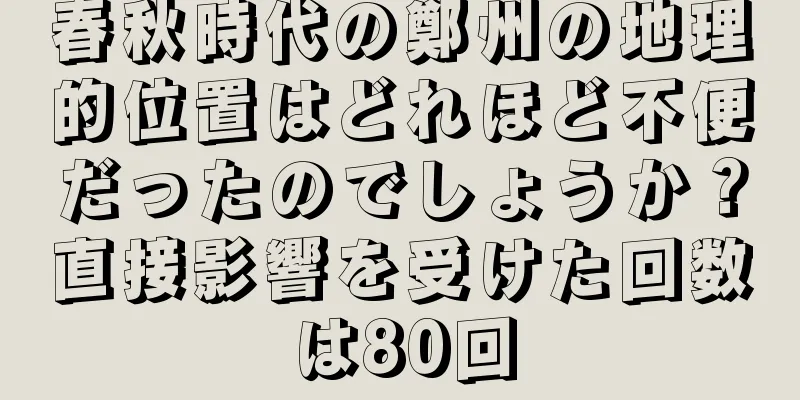
|
『諸代戦争記』の統計によれば、春秋時代には約380の戦争が起こった。そのうち、鄭州は80回も災害に直接被害を受けました。春秋時代全体の歴史を振り返ると、諸侯が覇権を争う戦いが始まると必ず鄭国が登場します。もちろん、通常は殴打の対象として現れます。では、それは鄭州自体が好戦的だからでしょうか? いいえ! すべては鄭州の地理的な位置に起因しています。鄭は西周のかなり後期に成立した大国であり、その領地は当初現在の新鄭にあったわけではなく、現在の陝西省華県が最初の領地であった。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 絵から明らかなように、鄭国は領地の位置から、東は郝井、西は漢谷関に位置し、周の東門の守護国であったことが分かります。それは周の西門の守護国である宝鶏の西国(孝国の前身)と同様に、周の最も信頼される臣下でした。実際、最初の君主である鄭の桓公は、西周王朝最後の王である周の幽王の父である宣王の兄弟でした。しかし、この建国者は非常に先見の明があり、幽王の治世中に国が混乱しているのを見て、城が火事になったら民衆に影響が出るのではないかと心配しました。そこで、全容が郝京を攻撃する前に、春秋時代に東果と快のあった場所である新鄭に民衆と財産を一時的に保管しました。 しかし、周の平王が東に移動した後、鄭州はかなり不親切な方法で王位を継承しました。鄭の桓公がなぜ新鄭にのみ移住したのかについては、『国語』の「鄭攸史伯桓公盛衰記」ですでにその因果関係が十分に説明されており、私たちは史伯の先見の明に感心し、彼が本当に天人であると嘆息するしかない。もちろん、この記事の議論の焦点は、依然として東進した鄭国の地理的位置に集中しています。 春秋時代初期、覇権争いに参加していた君主は、基本的に斉、秦、晋、楚の四大国でした。もちろん、秦国は覇権争いに参加したかったが、漢谷関の西側で晋国によって阻止された。蕭の戦いの後、彼らは隴西の蛮族の討伐に全力を尽くした! 四大国のうち、荊軻と呼ばれた楚は、周の建国以来、中国の君主たちから最も軽蔑される異国であった。しかし、楚は最も野心的で強力な拡張主義者であった。その数百年にわたる北方への拡張は、人々にロシアのように不屈であると感じさせ、北に住む中国人に南からの冷たさを感じさせた。したがって、春秋時代初期に栄帝が華夏人に与えた深刻な被害とは別に、楚国が華夏人に与えた被害が最も深刻であった。 したがって、春秋時代の歴史全体は、中国の諸侯が楚の国の北進に抵抗し続けてきた歴史である。当時、属国が覇権国として行動する資格があるかどうかを測る第一の基準は、楚国を倒すことだった。これは、最初に台頭した斉の桓公、その後に台頭した晋の文公、晋の文公の後継者である晋の道公、そして晋の景公にも当てはまりました。そのため、岐路に立たされた不運な男、鄭州は、関与せざるを得なかった。鄭と宋はともに中原の中核地域に位置していたが、広大な黄淮平原における鄭に比べれば宋は脇役に過ぎなかった。第一に、鄭国は周王朝の王室の本拠地である洛陽に近かった。第二に、鄭国は洛陽に通じる重要な峠である虎牢関を支配していた。また、鄭州は黄河の中下流と冲水河畔に位置し、華北平原から南に向かう主要な渡し場である延津を支配していた。 (古代、黄河は河南省の延津県から華県まで北に流れ、霊長津や南津などの渡し場があり、総称して延津と呼ばれていました) 当時、楚の国土拡大には主に二つのルートがありました。一つは英都(江陵)から出発し、漢江に沿って北上し、襄陽を経て南陽盆地に入るルートです。南陽盆地の北西には富牛山、南東には銅白山があり、この二つの山脈は丘陵地帯を挟んで中原に通じる出口がある。この丘陵地帯は方城峠と呼ばれ、現在の方城市とイェ県のあたりに位置している。北へ向かう楚の軍隊と商人のほとんどはこの道を通った。歴史的にはこの道は「夏の道」(楚は夏へ行き、道は方城から出て、人々は北へ向かう)と呼ばれていた。方城関を過ぎると、鄭州の領土に到着します。鄭州から宋州、そして斉魯の中心にある秦義山脈に至るまで、この地域は平坦で開けており、山や川に邪魔されることなく、たとえ川があったとしても、軍隊の飲料水の供給路となっている。そのため、楚軍が鄭国に到着すると、鄭国を通過して北の延津を越えるか、虎牢関を通って洛陽に入り、周の三脚を狙うかのどちらかが考えられた。 楚国が勢力を拡大するもう一つの方法は、方城下路から東に進み、汝河と汶河を渡り、成都湾丘(現在の綏陽)を通り、松都商丘を通り、陸都曲阜に行き、最終的に斉国に到達するというものでした。前述のように、鄭と宋はともに中原に位置していたが、春秋時代初期の覇権を争う主なライバルとして、鄭は楚と晋よりも戦略的価値が高かった。 当時、晋国の軍事と政治の中心は山西省南部にあり、中原に進出するには黄河を南に渡る必要がありました。晋国は茅津渡し、孟津渡し、延津の3つの重要な地点を経由して黄河を南に渡った。 茅金渡は現在の平魯県に位置し、対岸には三門峡慧興があり、西郭と南郭(黄河南岸)が東へ移動した場所である。晋は茅津渡しを渡ったが、洛陽に到達するには、まだ数百マイルに及ぶ蕭山の密林と草原を越えなければならず、さらに虎牢関を越えて鄭国に到達しなければならなかった。 孟津渡し場、現在の河南省孟津県。武王が周王を攻撃したとき、ここで諸侯と会議を開き、その後黄河を渡って直接超歌を攻撃した。孟津渡しは東周の首都洛陽の北の門であった。晋国と王室との情緒的なつながりや、王を支援するための軍隊の派遣など、ほとんどのことがこの場所を通じて伝えられました。 燕津フェリーについては前回の記事で触れました。茅津渡しと孟津渡しと比べると、晋国は特に延津渡しを好んだ。なぜなら、茅金と孟金を越えた後、金は虎牢関を通らなければならなかったからである。もし鄭が楚側に立っていたら、金は待ち伏せされる危険があった。延津の場合はそうではありません。金国が延津を越えれば、中原の中心地に直接到達するか、鄭国から物資を調達するか、鄭の首都新鄭を包囲することになります。 したがって、晋と楚の両国にとって、このような重要な地域を自らの手に握れば、間違いなくさらなる安全がもたらされるだろう。楚が鄭を支配すれば、そこを緩衝地帯として利用することができ、北の国境を守るだけでなく、金が中原に軍隊をスムーズに展開するのを防ぐこともできる。逆に、楚が鄭を制圧できなかった場合、第一に楚は方城下路を守るために大量の軍隊を配備する必要があり、第二に楚が東北に配備できる軍隊も弱体化するだろう。春秋時代の歴史では、楚国が宋国を何度も包囲したが、その前提条件は常に鄭国を制圧し、自国の補給と輸送路を確保することであった。そうでなければ、楚軍が国境の外に留まり、金軍が突然軍隊を派遣して方城と下口を封鎖し、楚軍の食糧供給と帰還路を遮断した場合、楚軍の生き残りは帰ってきたときに路上で罵倒することになるだろう! もちろん、鄭は王室に近いため、皇帝を利用して王子たちを支配することは、春秋時代の王子たちが好んだだけでなく、後世の人々も楽しんだことだった。 最終的に、鄭の桓公、鄭の武公、鄭の荘公の指導の下で三代にわたる発展を経て、鄭国は春秋初期の小さな覇権国として知られるようになり、その軍事力は侮れないものとなった。晋と楚は互角であったが、鄭が強制的に加わらなければならなくなったら、間違いなくそれが最後の手段となるだろう。さらに、この時代の後代の君主たちは曹操のような戦略も朱文のような武術も持ち合わせていなかったため、周の王族と仲違いして王族の支持も失った。これは、守るべき戦略的な場所がなかった鄭国にとって決して良いことではなかった。 |
<<: 春秋時代にはいくつの属国が存在しましたか?どの属国が一流の強さを持っているでしょうか?
>>: 戦国時代の秦はなぜ自ら皇帝を名乗らなかったのでしょうか?チーが同意しないのではないかと心配したから
推薦する
「Until Now」の原文は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
最後まで杜甫(唐代)冬至を過ぎて日が長くなり始めました。私は遠く江南にいて洛陽のことを考えています。...
明代史第237巻第125伝記原文の鑑賞
傅浩里、江志礼、包建潔、田大宜、馮応静(何東如、王志涵、辺公時)、呉宗瑶、呉宝秀、花宇(王正志)傅浩...
揚げパンと秦檜にはどんな関係があるのでしょうか?揚げドーナツには他にどんな名前がありますか?
豆乳と揚げドーナツの組み合わせは、朝食によく使われます。 「揚げ果物」、「揚げシチュー」、「揚げ鬼」...
香玲が『紅楼夢』で悠容おばあちゃんの役を演じているのはどういう意味ですか?それはどういう意味ですか?
香玲は『紅楼夢』に登場する最初の女性キャラクターであり、『金陵十二美女』第二巻に登場する最初の女性キ...
『進士録』第5巻「自戒」の原文は何ですか?
1. 連溪氏はこう言った。「君子は誠実で正直でなければならないが、それを達成するには怒りと欲望を抑え...
王維の古詩「送興貴州」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「邢貴州に別れを告げる」時代: 唐代著者 王維景口ではシンバルの音が騒々しく、洞庭湖では風と波...
李尚銀は松の木についての詩を書き、私たちに初心を忘れないようにと伝えた。
今日、私たちは初心を忘れないようにと言っています。実際、私たちは若い頃の志を忘れず、初心を忘れないよ...
黄帝内経霊書第42章の原文の鑑賞
黄帝は言った。「私は師から九針を受け、内緒で各種の処方箋を読みました。導気、動気、鍼灸、焼灸、鉗子、...
政治と経済が発展するにつれて、朱元璋は社会救済に対してどのような態度をとったのでしょうか。
政治と経済の発展に伴い、明代の社会救済事業は大きく進歩しました。公的救援機関はより充実し、民間の社会...
張児はどのようにして死んだのか?歴史は張児をどう評価すべきか?
紀元前206年(漢の高祖元年)、劉邦は秦を滅ぼした。この時、項羽の軍は漢谷関を突破し、新豊と鴻門(い...
「秦の政治制度と法制度は代々受け継がれる」という言い伝えがあるのはなぜですか?秦王朝はどのような制度を確立したのでしょうか?
諺にあるように、何をするにも最高を目指し、常に他人より先を行き、決して遅れを取らないように努めましょ...
『紅楼夢』のZhuierとは誰ですか?彼女の結末はどうなったのでしょうか?
諺にもあるように、高官は人を押し殺すことができる。この諺は賈家にも非常によく当てはまる。多くの読者が...
ジン族の最も盛大な祭り、ハ祭の秘密を解き明かす
春節、清明節、端午節、中元節、中秋節などの祭りを漢族、チワン族などの民族と一緒に祝うほか、哈節(長哈...
水滸伝の108人の英雄の中で、「虎」という異名を持つのは誰ですか?
『水滸伝』には108人の将軍が登場し、それぞれの将軍に非常に特徴的なニックネームがあることは誰もが知...
劉晨文の「秦娥を偲ぶ:中寨の元宵節を懐かしむ」:詩全体が悲しく、悲痛な調子である
劉晨翁(1232-1297)、雅号は慧夢、号は許熙としても知られる。彼はまた、徐喜居士、徐喜農、小娜...