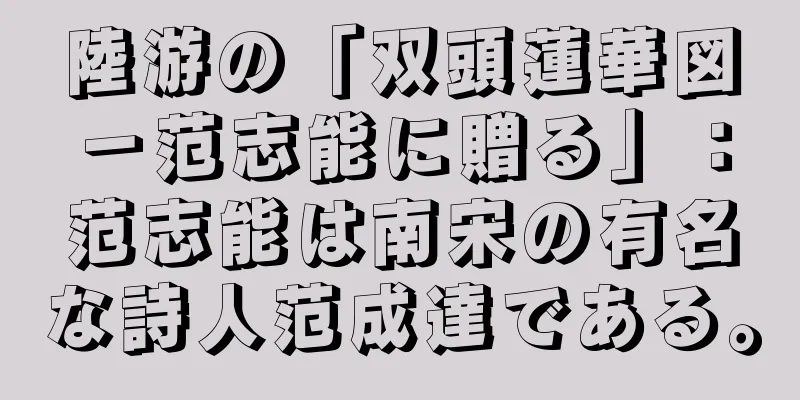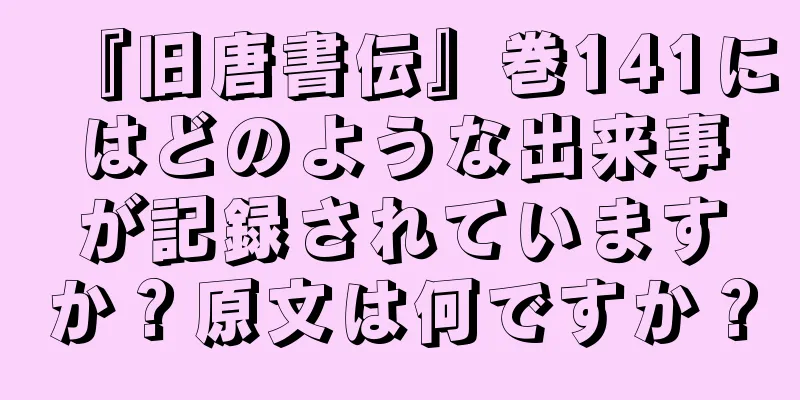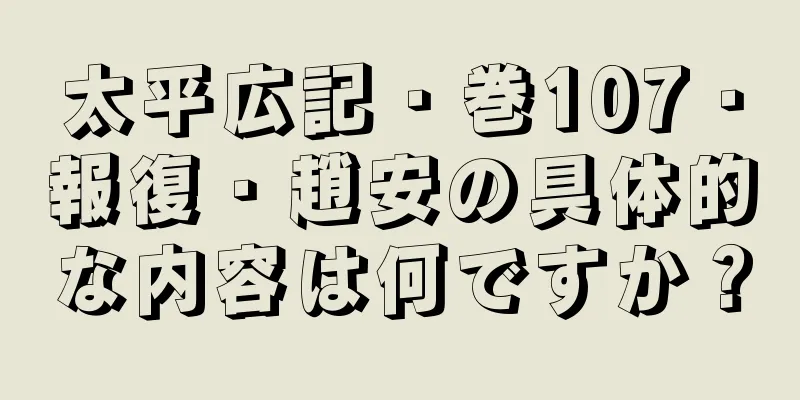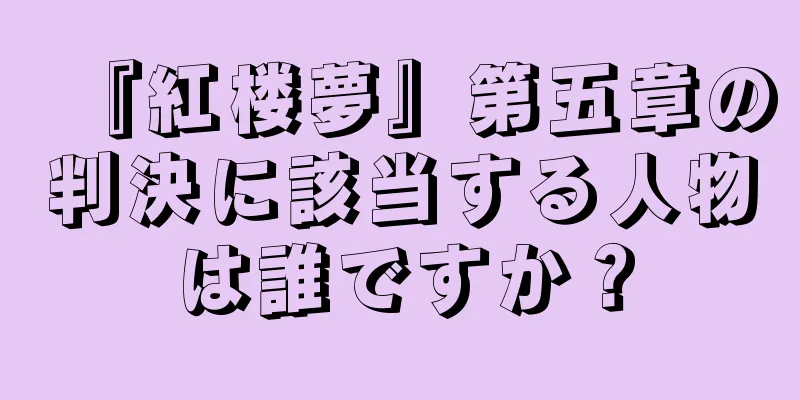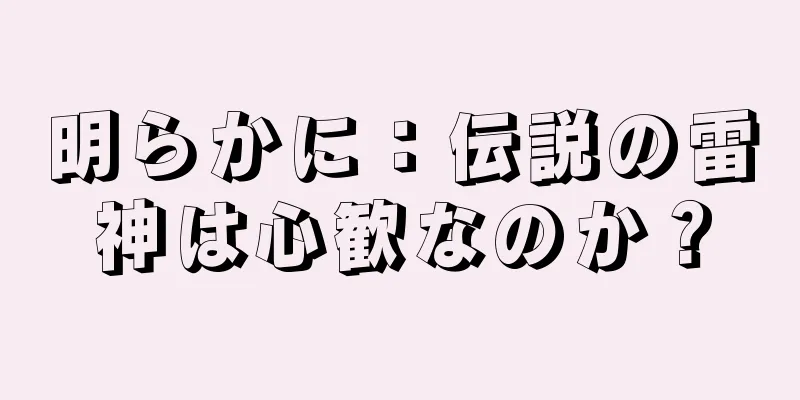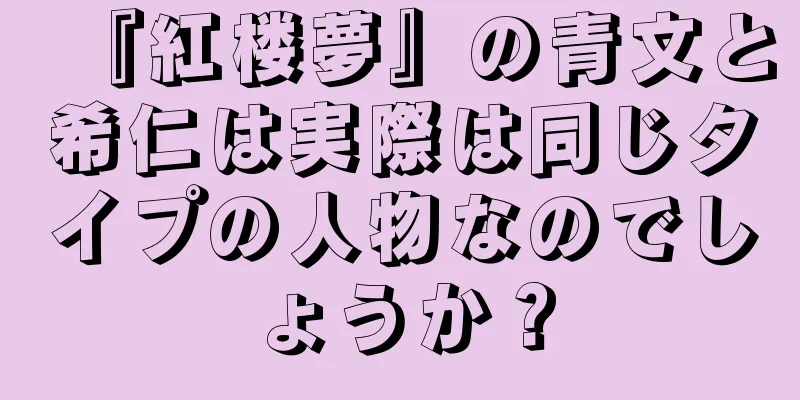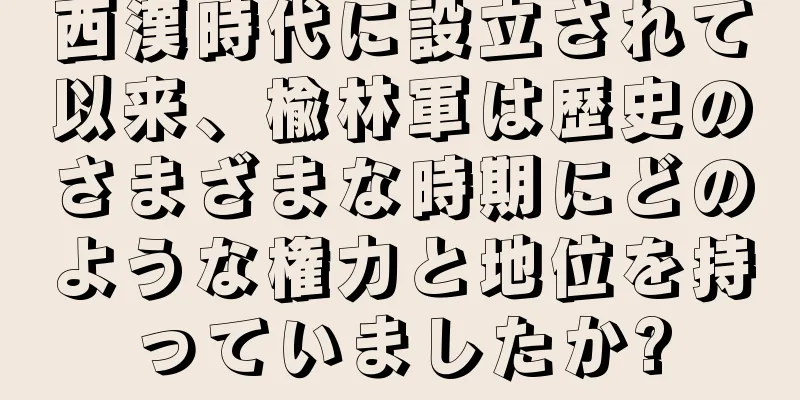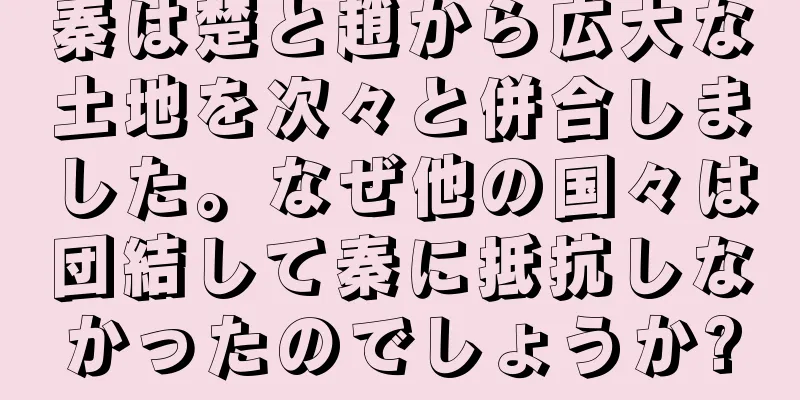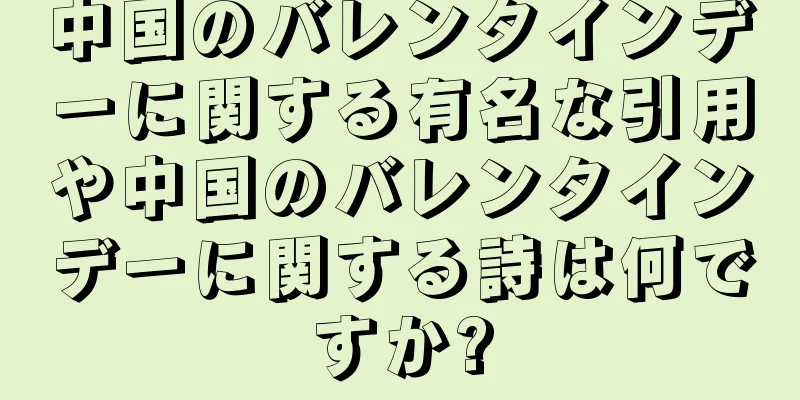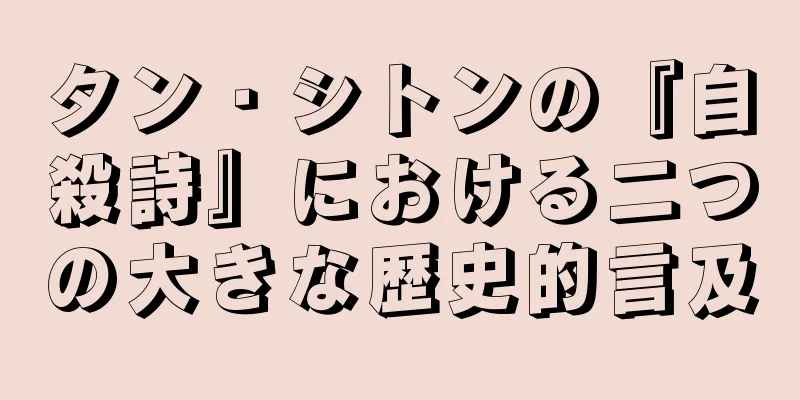なぜ楊貴妃は自殺したのではなく、身代わりの計画によって救出され、その後逃亡したと考える人がいるのでしょうか?
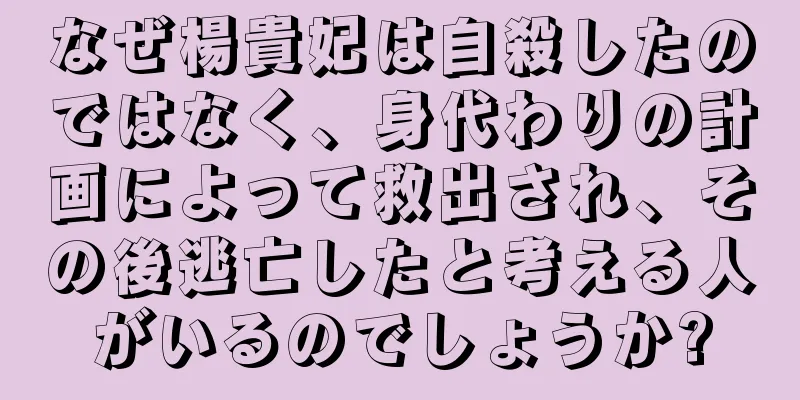
|
楊貴妃が馬尾郵便局で自殺したという記録が正史に残っている。例えば、唐代の学者、李昭は『国史補遺』の中で次のように述べている。「玄宗は蜀に行き、馬尾宿に着いた。彼は高力士に命じて、仏教寺院の前の梨の木の下で皇帝の側室を絞殺させた。馬尾宿の老婆が錦のかんざしを持ち去った。通りすがりの人は皆、遊びでそれを借りるために百銭を払わなければならなかったと言われている。老婆は大金を稼ぎ、非常に裕福になった。」それは楊貴妃が馬尾義の仏教寺院の梨の木の下で亡くなったことを意味し、遺体を移動しているときに靴が片方脱げてしまい、老婆がそれで大金を儲けたという。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! この歴史的出来事に関して、『旧唐書』と『新唐書』の李昭の上記の記録は類似している。司馬光の『資治通鑑』に引用されている楊貴妃の絞首刑に関する史料はより詳細で、反乱軍が楊国忠を殺害した後も、皇帝を守っていた六軍の兵士たちは依然として前進を拒否し、唐玄宗の個人的な命令も効力を持たなかった。唐の玄宗皇帝は高力士に軍の総司令官である陳玄礼にその理由を尋ねるよう命じた。陳玄礼は答えた。「国忠は謀反を企んでおり、皇帝の側室が彼に仕えるのは不適切です。陛下が彼の恩寵を捨てて処刑されることを望みます。」これを聞いた後、彼は頭を辞めたがっていた現時点では、ガオはXuanzongにも言いました。エド・リシは帝国の側室を仏教寺院に連れて行き、彼女を絞め殺しました。 これは公式の歴史に記録されているだけでなく、いくつかの詩、歌、非公式の歴史、演劇の伝説でもこの言葉が認められ、採用されています。例えば、元和元年(806年)の冬、白居易は左営県の副司を務めており、親友の陳洪と王志もその県に住んでいました。ある日、彼らは仙游寺を訪れ、唐の玄宗皇帝と楊貴妃の悲恋物語について語り合いました。彼らは非常に感動しました。王志は白居易にこのテーマで詩を書くよう提案しました。白居易は有名な『長恨歌』を書き、陳洪は『長恨歌伝』を書きました。陳洪は歴史家だった。楊貴妃が馬尾邑で絞首刑に処せられたとき、陳洪は次のように記している。楊国忠が処刑された後、「周囲の人々は決断を下せなかった。皇帝は彼らに頼み、当時声を上げた者たちは、側室を使って世間の恨みを鎮めようとした。皇帝は彼女が死ぬことは避けられないと知っていたが、彼女が死ぬのを見るのは耐えられず、袖で顔を覆い、連れて行かせた。慌てた楊貴妃は、結局、棒で殺された。」 それにもかかわらず、楊貴妃は自殺したのではなく、戦争の混乱の中で亡くなったと信じる人もいます。この理論は主に唐代の詩の記述に見られます。治徳2年(757年)、杜甫は安禄山が占領していた長安で「河源嘆き」という詩を書いた。この詩には「輝く目と白い歯は今どこにあるのか?血に染まったさまよう魂は家に帰れない」という一節があり、楊貴妃が馬尾宿舎で絞首刑にされなかったことを暗示している。なぜなら、絞首刑にされたら血は出ないからだ。李毅の七字四行詩『馬尾を過ぎて』と七字律詩『馬尾を過ぎて二首』には、「蓮の血を洗わないように頼む」「馬のひずめは太真流の血で染まっている」などの一節があり、これも楊貴妃が反乱軍に殺され、斬られて死ぬ場面を反映している。杜牧の『華清宮三十韻』の「馬尾の血は騒がしく、近衛兵の槍は飛び散る」、張游の『華清宮佘社人』の「美しい妾の血は埋もれる」、文廷雲の『馬尾邑』の「魂が戻ってくる煙は証拠もなく消え、埋もれた血は青草の上に悲しみを生むだけだ」などの一節は、楊貴妃の血が馬尾邑で飛び散ったと信じられており、彼女は絞首刑に処せられなかった。 また、楊貴妃は黄金を飲み込んで死んだという言い伝えもあります。例えば、劉玉熙はかつて「馬尾星」という詩を書きました。彼は詩の中でこう書いている。「扶風路には緑の野、馬尾路には黄色い塵、道端には楊貴妃の墓が3、4フィートの高さがある。村の子供たちに聞いたところ、皇帝が蜀に行ったとき、軍隊がおべっか使いを殺し、皇帝は邪悪な妃を捨てた。官吏は戸口に隠れ、妃は皇帝の服を引っ張り、頭を下げて美しい目を向け、風と太陽は天の光であった。妃は金のかけらを飲み、すると突然順英は消えた。一生杏の丸薬を飲んでいたが、顔色は以前と変わらない。」この詩から判断すると、楊貴妃は黄金を飲み込んで亡くなったことになる。陳銀科氏はこの発言に非常に驚き、『元百世鑑正公』でそれを検証した。しかし、陳銀科は楊貴妃が絞首刑に処される前に黄金を飲み込んだ可能性を否定しなかった。 それだけでなく、楊貴妃は自殺したのではなく、身代わりの計画によって救出され、その後逃亡したと信じる人もいます。さらに、この噂は唐の時代から存在していた。 楊貴妃は馬尾夷で死んだのではなく、放浪の庶民となり、女道士になったと信じる人もいます。このことわざは当時すでに存在していました。白居易の『長悲歌』には、「迷わずに龍の車に引き返し、躊躇して立ち去ることができなかった。馬尾坂の下の泥の中に、楊貴妃が死んだ場所の跡はない。」と記されている。これは、反乱を鎮圧した後、玄宗皇帝が蜀から長安に戻り、楊貴妃が絞首刑にされた場所を通り過ぎたが、躊躇して立ち去ることができなかったが、彼女の遺体は馬尾坂の下の泥の中にもう見つからなかったという意味である。その後、彼は錬金術師たちを派遣して捜索させましたが、彼らは空と冥界を捜索しましたが、どこにも見つかりませんでした。白居易はここで、皇帝の側室は昇天もせず、亡くなってもおらず、まだ人間界で生きているということを暗示している。近代では于平波氏が『詩歌曲雑論』の中で白居易の『長恨歌』と陳洪の『長恨歌伝』を研究した。白居易の『長悲歌』と陳洪の『長悲歌伝』の本来の意図はおそらく他の強みであると彼は信じている。記事のタイトルが「長衡」であれば、馬尾夷まで書けば十分です。なぜ臨瓊道士と玉妃太真を後から想定する必要があるのでしょうか? 玉氏は楊貴妃が馬尾夷で亡くなったのではないと考えています。当時、六軍が反乱を起こし、皇后が誘拐され、簪や宝石が地面に落ちた。詩には唐の玄宗皇帝が「彼女を救うことができなかった」と明記されており、正史に記録されている死の勅令は当時存在しなかったであろう。陳洪の『長悲歌物語』にある「人を遣わして連れ去らせた」という言葉は、楊貴妃が使者によって連れ去られ、遠く離れた場所に隠されたことを意味している。白居易の『長悲歌』には、唐の玄宗皇帝が楊貴妃が宮廷に戻った後、再び埋葬しようとしたとある。しかし、結果は「馬尾坂の下の泥は、彼女の美しい顔が亡くなった場所を明らかにしなかった」というものだった。彼女の骨さえも見つからなかった。これは、楊貴妃が馬尾宿舎で亡くなったのではないことをさらに証明している。注目すべきは、陳洪が『長恨歌伝』を執筆したとき、後世の人々が理解できないことを恐れて、「世間が知っているのは『玄宗皇帝伝』だ」と指摘したことだ。そして、「世間が聞いたことがない」のは現在まで伝えられている『長恨歌』であり、楊貴妃が死んでいないことを明確に示唆している。 楊貴妃の日本における所在については諸説ある。死者は身代わりであり、楊貴妃は山口県大津郡油谷町肥薩に逃れたという説がある。その身代わりは侍女だった。軍司令官の陳玄礼は妾の美しさを愛し、彼女を殺すことに耐えられず、高力士と共謀して侍女と取り替えた。高力士は妾の遺体を馬車で運び、陳玄礼が遺体を検査し、計画は成功した。楊貴妃は陳玄礼の側近の護衛のもと南へ逃れ、現在の上海付近から出航し、日本の油屋町肥薩に到着した。 1963年、ある日本人女性がテレビ視聴者に自分の家系図を見せ、自分は楊貴妃の子孫だと主張した。有名な日本の映画スター、山口百恵も楊貴妃の子孫であると主張している。 唐代の玄宗皇帝が安史の乱を鎮圧した後、錬金術師たちを海に派遣して探させたと言われています。九金で楊貴妃を見つけた道士は、唐の玄宗皇帝から贈られた仏像2体を楊貴妃に与え、楊貴妃はお返しに玉の簪を贈った。この2体の仏像は、現在も日本の葛生院に安置されています。楊貴妃は日本で亡くなり、葛生院に埋葬されました。現在でもこの地域には楊貴妃の墓と言われている五重塔が残っています。五重塔は楊貴妃の墓の上に建てられた5つの石塔の集合体です。楊貴妃の墓の前には2枚の木の板があります。1枚は五重塔について、もう1枚は楊貴妃についてです。「楊貴妃の墓は謎とロマンに満ちている――唐の玄宗皇帝の側室、楊貴妃にまつわる伝説」と書かれています。 楊貴妃は日本ではなくアメリカに行ったという奇妙な言い伝えさえある。台湾の学者、魏居賢は著書『中国人がアメリカを発見』の中で、楊貴妃は馬尾夷で死んだのではなく、遠いアメリカに連れて行かれたことを証明したと主張した。 民間の伝説では楊貴妃が死から蘇ったと伝えられており、これは人々の彼女に対する同情と追悼を反映しています。しかし、実際には楊貴妃は馬尾夷で亡くなった可能性が高い。 『高力士伝』では楊貴妃の死は「一時的な集団懲罰」によるものだとされている。つまり、六軍の兵士たちは楊国忠を憎み、楊貴妃をも巻き込んでいたのです。これは Gao Litu の視点です。 『外伝』は楊貴妃の口述伝に基づいて書かれたものであり、馬尾の変の状況から判断すると、唐の玄宗皇帝が楊貴妃が死んでいなかったと説明するのは困難であった。楊貴妃が首を吊った後、彼女の遺体は仏教寺院から宿場町に運ばれ、中庭に置かれました。唐の玄宗皇帝も陳玄礼ら兵士たちを召集して検問を行なった。楊貴妃が馬尾夷で亡くなったことは、『新旧唐書』や『歴鏡』などの歴史書に明確に記録されています。唐人の『高力士伝』『補唐史』『明皇雑記』『安禄山事績』などの雑史でも同様です。 歴史の記録は比較的詳細であり、楊貴妃が馬尾郵便局で絞殺されたことは認められていると言えるでしょう。しかし、楊貴妃が女道士になるために逃亡し、日本に亡命したという主張も合理的であり、十分な証拠があり、簡単に否定できるものではない。これらすべては、新たな歴史資料の発見によって解明される必要があります。 |
<<: なぜ歴史上、唐王朝は繁栄した唐王朝と呼ばれているのでしょうか?開元時代はどれほど強大だったのでしょうか?
>>: 李林甫はどのような手段を使って李龍基を助け、楊玉環を高貴な側室にしましたか?
推薦する
「高陽酔人」という慣用句の歴史的起源はどこですか?これをどう説明すればいいでしょうか?
[慣用句]: 高陽の酔っぱらい【ピンイン】: gao yang ji tú 【説明】:高陽:河南省祁...
十六国時代の後趙の君主、石虎とはどのような人物だったのでしょうか?歴史は石虎をどのように評価しているのでしょうか?
後趙の武帝石虎(295-349)は、号を基龍といい、桀族の出身で、上当の武郷(現在の山西省毓社北部)...
謝凌雲の「顔歌星」:この詩は悲しく感動的であり、人工的な感じは全くない
謝霊雲(385-433)、本名は鞏義、号は霊雲、号は可児、陳君陽夏県(現在の河南省太康県)の人。東晋...
『紅楼夢』の元陽が宋徽宗の鷲と趙孟頫の馬はどちらも良い絵だと言ったのはどういう意味ですか?
『紅楼夢』第46話では、賈舅は袁陽に恋をし、星夫人に賈夫人に求婚するよう頼みました。今日は、Inte...
『紅楼夢』では、賈家にはカンと椅子があります。貴族の身分を示すには、どれに座るべきでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
老子の『道徳経』第 4 章の分析とさらに読む
『道徳経』は、春秋時代の老子(李二)の哲学書で、道徳経、老子五千言、老子五千言とも呼ばれています。古...
『紅楼夢』の宝琴は林黛玉や薛宝柴よりも優れたキャラクターですか?
薛宝琴は『紅楼夢』とその派生作品の登場人物で、四大家の一つ薛家の娘である。彼女はとても美人で、金陵十...
五夷十六国の時代、傅充には何人の兄弟がいましたか? 傅充の兄弟は誰でしたか?
傅充(?-394年)は、洛陽県臨衛(現在の甘粛省秦安市)出身のディ族で、前秦の高帝傅登の息子である。...
邢道容も霊霊県の将軍だった。なぜ趙雲に降伏しなければならなかったのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
唐代雍徽法典注釈全集
わが国の法制発展の歴史において、最も代表的な刑法典は唐代に成立し、封建時代全体を通じて法典の制定に影...
『紅楼夢』で、薛宝才は賈宝玉が自分を嫌っていると知りながら、なぜ彼と結婚したのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
三国志演義 第29章 小覇王が怒って于吉を殺し、青目の男が江東を占領する
『三国志演義』は、『三国志演義』とも呼ばれ、正式名称は『三国志演義』で、元代末期から明代初期にかけて...
東漢の有名な将軍、殷定の先祖は誰ですか?殷定と管仲の関係は何ですか?
殷史(?-59年)、礼名は慈伯。彼は南陽州新野県(現在の河南省新野市)に生まれた。光烈皇后尹麗華の異...
トルイはチンギス・ハーンの4番目の息子です。彼の息子たちに関する歴史的記録はありますか?
チンギス・ハーンの4番目の息子であるトルイは、モンゴル帝国の政治家であり軍事戦略家でした。彼には全部...
『鳳凰物語』第七章:月洞で琵琶を弾き、朝五時に嘆き、寒宮で愚痴を言う
清代の小説『双鳳凰伝』は、夢によって元帝の側室に選ばれた王昭君が、毛延寿の憎しみと嫉妬によって冷たい...