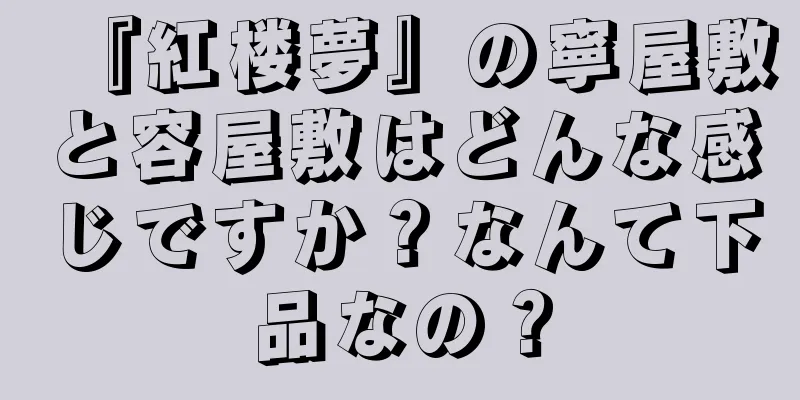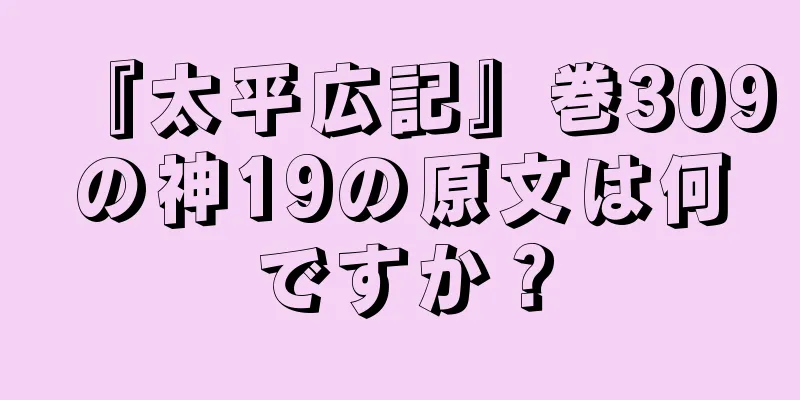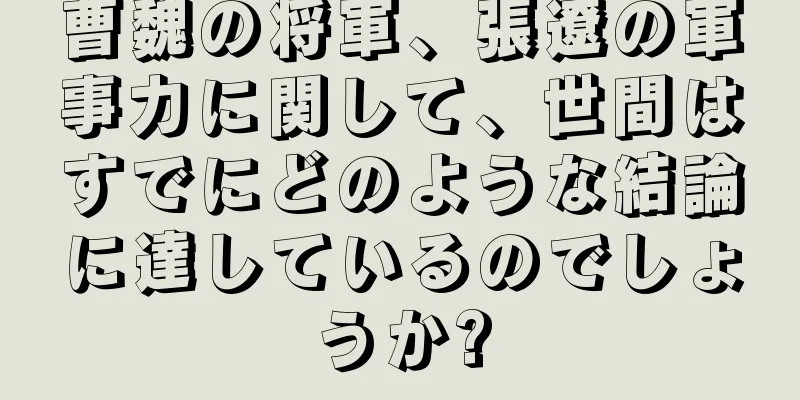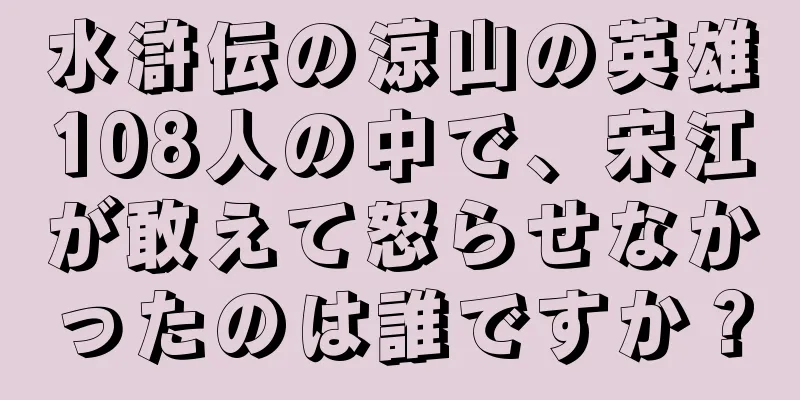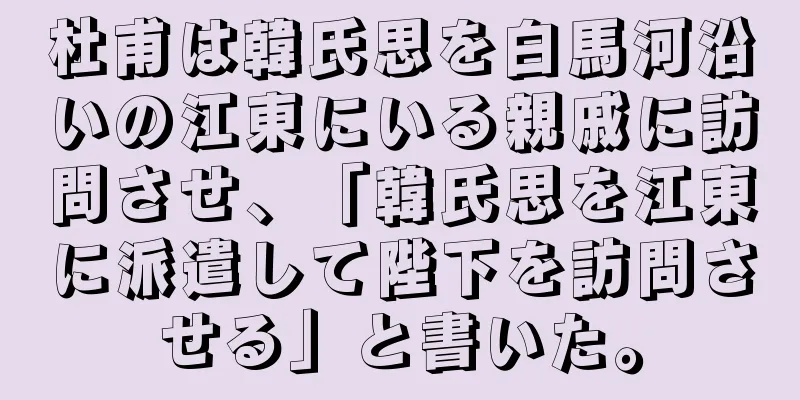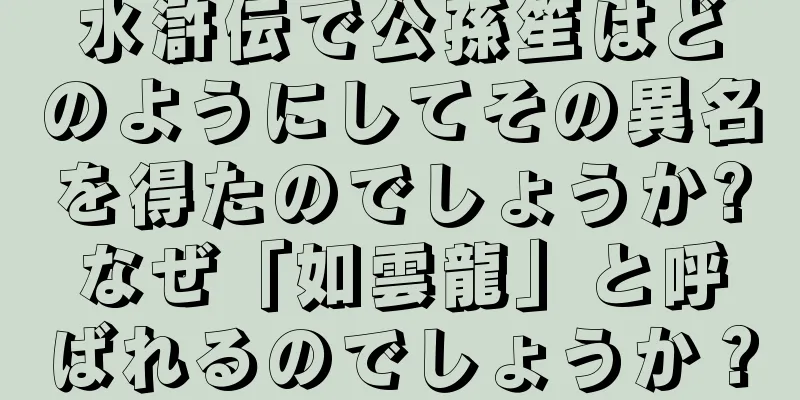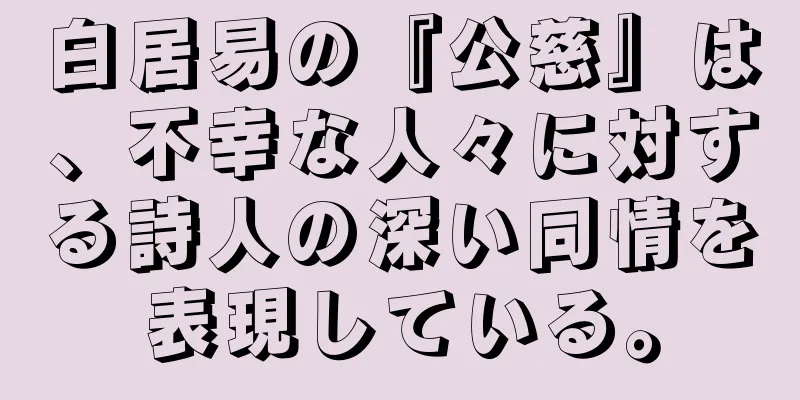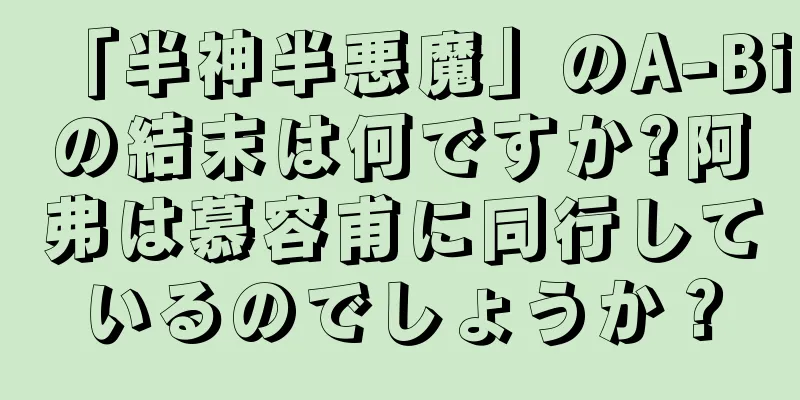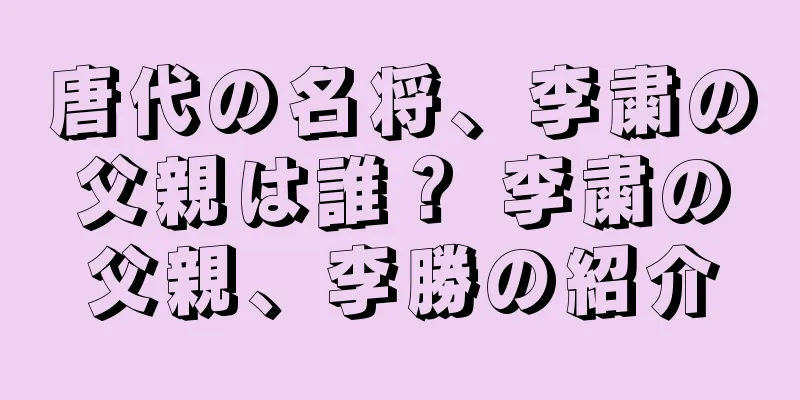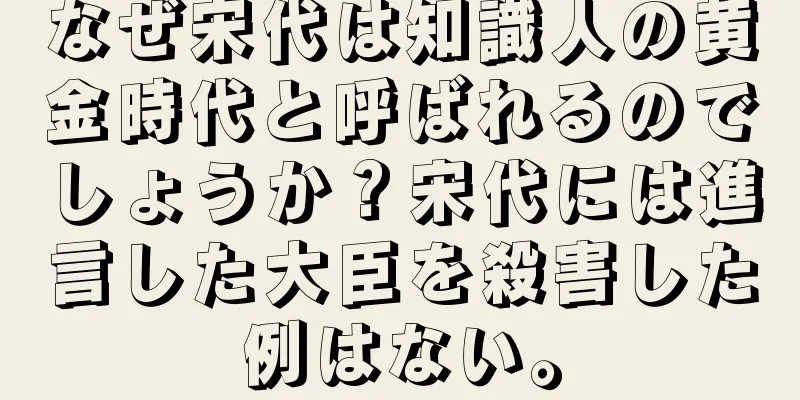五章源の特別な地理的位置は何ですか?諸葛亮はなぜここで病死したのでしょうか?
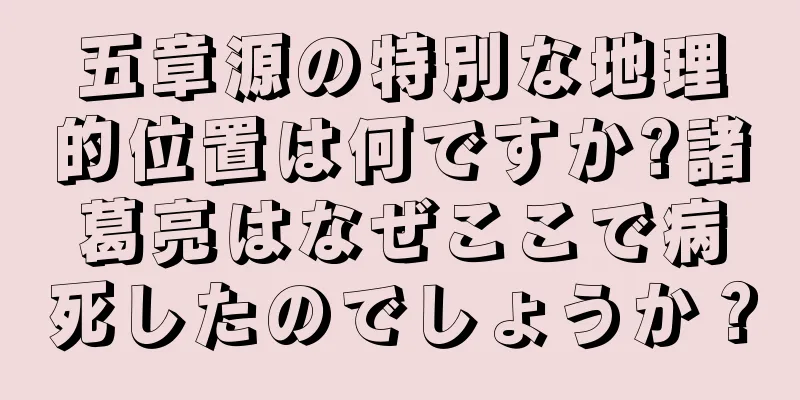
|
五丈源という地名については、皆さんもよくご存知だと思います。西暦234年、諸葛亮は最後の北伐で軍を率い、過労による病でこの地で亡くなりました。このため、五丈源という地名は誰もが知る名となった。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! しかし、五丈原は一体どこにあるのでしょうか? 諸葛亮はなぜここに閉じ込められ、前進も後退もできず、疲れ果てて憎しみに満ちたまま死んでいったのでしょうか? まず、五章源のユニークな地理的位置を見てみましょう。 1. 五章源の地理的位置 長安市は関中平原に位置し、北は黄土高原、南は秦嶺山脈、中央を渭河が流れ、800里の秦川平原を形成し、「千里の黄金城、豊かな土地」として知られています。そのため、長安の南側は、白鹿園、紅谷園、楽有園、五丈園など、多くのそびえ立つ山々と平野に囲まれています。 五章源の地理的位置 蜀の漢中から魏の長安まで、その間には長い秦嶺山脈が広がっています。漢中から秦嶺山脈を越えて長安に着く場合、古来から選択できるルートは陳倉路、宝下路、唐洛路、紫霧路の4つしかありませんでした。これら 4 つの道路は関中に直接通じていますが、いずれも険しく危険であり、秦嶺山脈を越える必要があるため行軍が非常に困難です。今日私たちが話している五丈園は、宝夏徳(下鼓とも呼ばれる)の最北端の出口に位置しています。 五章源は南は秦嶺山脈、北は渭河に隣接しています。 地図からわかるように、五章源は秦嶺山脈の北側の山麓に位置し、北には関中平原を横切る渭河が流れ、東には渭河の支流である石頭河が流れています。そのため、五丈原はちょうど謝谷の出口に位置し、南は秦嶺山脈、北は渭河、東は石頭河に三方を囲まれ、軍事的に閉鎖された空間を形成しています。 諸葛亮の第五次北伐は関中から出発し、謝谷を出て、最終的に五丈原に到着した。実際、五丈原から長安城までの距離はわずか200マイル余りで、当時諸葛亮は征服しようとしていた長安城に非常に近いこの場所に軍隊を駐留させた。 五丈原の風景 すると、もう一つの疑問が浮かび上がります。なぜ諸葛亮は第五次北伐で謝谷ルートを選んだのでしょうか? 2. 諸葛亮の第五次北伐 諸葛亮の北伐について話すとき、私たちは通常「彼は岐山に6回行った」と言います。実際には、諸葛亮は北伐を5回しか行わず、そのうち岐山方面に向かったのは3回だけでした。他の2回のうち1回は陳倉路を通り、もう1回は謝谷を通りました。 いわゆる岐山方面とは、実際には秦嶺山脈を避け、岐山古道から大きく曲がり、隴西方面から西から東へ関中平野に入る4つの険しい山道を指します。地図からわかるように、この行軍は長い迂回をしたものの、秦嶺山脈の険しい四つの山道を避けており、軍の前進と後方への食糧や草の補給に有利であった。 諸葛亮の北伐のルート では、なぜ諸葛亮の第五次北伐は岐山を通らずに、謝谷から出撃することを選んだのでしょうか。主な理由は 2 つあります。 1. 曹魏はすでに旗山方面の守備を強化している。 諸葛亮の最初の北伐は岐山を経由して迂回した。迂回する間に、趙雲に部隊を率いて謝谷から進軍するよう手配し、曹魏にこれが蜀軍の主力であると誤解させた。実際、諸葛亮は東に陽動して西から攻撃し、岐山の近くに現れて曹魏の不意を突いた。残念なことに、馬謖の不注意により街亭を失ったため、蜀軍は曹魏の援軍を封じ込める戦略的な拠点を失った。曹魏の援軍は続々と到着し、諸葛亮はこれまでの努力が無駄になり、漢中へ撤退せざるを得なくなった。 諸葛亮の第4次および第5次北伐ルート この北伐の後、曹魏は隴渓地域の戦略防衛軍を増強し、街亭関をしっかりと守った。そのため、諸葛亮が第四次北伐を開始したとき、彼はやはり岐山から軍隊を派遣したが、ほとんど利益は得られなかった。西暦234年、すでに53歳になっていた諸葛亮は、自分に残された時間があまりないことを悟り、一度の戦いで目的を達成しようと決意し、謝谷から軍を派遣することを選択しました。 2. 諸葛亮はこの遠征のために十分な戦略的準備をした 謝谷から部隊を派遣する際の最大の欠点は、食糧と飼料の輸送と補給である。秦嶺山脈の山道は険しく、馬車で移動する食糧輸送部隊が効率的に通過するのは困難である。 諸葛亮は第五次北伐に向けて十分な準備を整えた。一方で、漢中地域で大規模な農業振興政策を実施して人々の農業を奨励し、他方では、穀物や飼料を貯蔵するために、薛谷沿いに多くの穀倉を建設した。同時に、彼は木製の牛馬も発明しました。これは人力で動かす木製の機械構造で、山道で食料や飼料を運ぶのに使用できました。 木製の牛と流馬 これらすべての措置は、謝谷から軍隊を派遣し、後方の十分な食糧と草の供給を確保しながらできるだけ早く関中平原に到達し、曹魏に軍事的脅威を与えるという一つの目的を達成するために行われたものであった。諸葛亮は、これまでのどの北伐よりも徹底した準備として、丸3年を費やした。彼は人生の最後の瞬間を、蜀王国にとって最大の戦略的優位性を獲得するために使いたかったことがわかります。 3. 蜀軍はなぜ五丈原で止まったのですか? では、諸葛亮は十分に準備していたのに、なぜ謝谷を去った後、五丈原に立ち寄ったのでしょうか。理由は2つあります。 まず第一に、それは五丈原の地理的位置に関係しています。 先ほども申し上げたように、五章源の地理的位置は非常に特殊で、秦嶺山脈を背に、北は渭河、東は石頭河が流れ、山、川、渓流に囲まれた地理的空間に位置しています。諸葛亮が東の長安を攻撃したいのであれば、川を渡る方法を見つけなければなりませんでした。 魏と蜀の行軍経路の地図 この時、すでに魏の司馬懿は渭河の岸に沿って長い陣地を築き、蜀軍の到着を待っていた。同時に、諸葛亮が密かに川を渡るのを厳しく阻止し、将軍郭淮に渭河の北岸に沿って機動・防御させ、昼夜を問わず巡回させた。諸葛亮が関中に入るとすぐに魏軍に迎え撃たれ、両者は渭水沿いで対峙し、しばらく勝敗が決しなかったことが分かります。このような状況下で、諸葛亮は五丈原に軍を駐留させるしかなかった。 もう一つの理由は、司馬懿の防御戦略です。司馬懿は、蜀軍の最大の弱点は食糧と飼料の問題と諸葛亮の健康であり、時間が長引けば長引くほど蜀軍にとって不利になるだろうと正確に分析した。これを踏まえて、司馬懿は「堅固な守りで城を守る」という戦略を採用し、諸葛亮がいくら挑発しても出てこなかった。諸葛亮は敵を奮い立たせるために、司馬懿を臆病で臆病な女性として嘲笑し、女性用の衣服一式を送りさえした。しかし、この方法を用いても、司馬懿は無関心のままでした。 当時の諸葛亮は窮地に陥っていたと想像できる。進軍しようとしたが、司馬懿に阻まれた。司馬懿と死闘を繰り広げようとしたが、相手は出てこなかった。司馬懿の陣営を迂回して密かに川を渡れば、川の半ばで郭淮に阻まれるだろう。 司馬懿の静止画 これで、諸葛亮が最終的に閉じ込められた場所が他の場所ではなく五丈原になった理由が理解できます。まさにこの地の特殊な地理的条件と、司馬懿の「城を固めて守り、敵の疲弊を待つ」という戦略のせいで、結局一歩も前に進めないというジレンマに陥ってしまったのである。 4. 前進できなかったのに、諸葛亮はなぜ撤退を選ばなかったのでしょうか? この時点で、諸葛亮は前進できず、健康も悪化していたのに、なぜ撤退を選ばなかったのかと疑問に思う人もいるかもしれない。 この疑問に答えるには、当時の諸葛亮の心境を分析する必要があります。この遠征の前に、諸葛亮は4回の北伐を実施したが、いずれも失敗に終わった。第五次北伐の前に、彼は人生の最後の時期を魏との戦争で有利に過ごし、蜀漢の領土的、戦略的優位性を獲得するために全力を尽くすために十分な準備を整えた。今、彼はまたもや失敗してしまった。残された時間が限られているという事実に直面して、彼はもちろん諦めるつもりはなく、後退するつもりもない。 では、なぜ諸葛亮は魏を攻撃することにこだわったのでしょうか? 双方が平和に暮らすほうが良いのではないですか? この問題に関して、諸葛亮はかつて『二の書』の中で、蜀は一つの国しか持たず、九つの国を持つ魏と競争したければ、できるだけ早く北進して領土の優位性を最大限に獲得しなければならないと考えていた。そうでなければ、時間が経つにつれて、魏と蜀の力の差は広がり、遅かれ早かれ蜀の滅亡は避けられなくなるでしょう。 諸葛亮はかつてこう言った。「私が匪賊を攻撃するのは、私が弱く、敵が強いからだ。しかし、匪賊を攻撃しなければ、私の国も滅びる。ただ座って滅びを待つより、攻撃したほうがよい。」彼が言いたかったのは、「私が今魏を攻撃しているのは、私が弱く、敵が強く、勝算が高くないからだ」ということだった。しかし、北伐が行われなかったら、蜀王国は遅かれ早かれ滅亡していたでしょう。死を待つよりも、力を集中して魏国に攻撃を仕掛け、勝利して利益を得るよう努めたほうがよいでしょう。 この一文は、諸葛亮の当時の心境を大体要約している。彼はこの精神に基づき、「国は中途半端ではだめ、漢と賊は共存できない」という旗を掲げ、ほとんど軍事的なやり方で曹魏に対して毎年北伐を行った。なぜなら、もし自分が死んだら、蜀漢には魏に対抗できる者が誰もいなくなり、彼らは滅亡に直面することになるだろうということを彼はよく知っていたからだ。 そのため、53歳の諸葛亮は五丈原に閉じ込められ、前進することができなかったが、軍を撤退させることを望まなかった。彼はむしろ、後方での軍糧の損失を減らすために兵士を五丈原の耕作に派遣し、司馬懿と対峙し続けることを選んだ。 ついに234年8月、諸葛亮は五丈原で亡くなった。この時、彼はここで曹魏と百日以上も対峙していた。 |
<<: 「もし、臥龍と鳳凰のどちらかが手に入れば、世界は平和になる」という文章の後半部分は何ですか?劉備はなぜ最終的に失敗したのでしょうか?
>>: 三国時代において、強大な力を持つ魏国だけが覇権を握っていたが、呉国の運命はどうなったのだろうか。
推薦する
「福建中部の秋の思索」が制作された背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
福建省中部の秋の思い杜荀和(唐代)雨が紫の菊の色を均等に広げ、風が赤いバナナの葉をざわめかせます。北...
王毓の「秋に王長世に別れを告げる」:この詩は作者の本当の気持ちを率直かつ直接的に表現することから始まります。
王毓(650-676)、号は子安、江州龍門県(現在の山西省河津市)の出身。唐代の作家で、文仲子王通の...
遼東に魏、蜀、呉と同じ性質を持つ燕国を建国したのは誰ですか?
陳寿の『三国志』と羅貫中の『三国志演義』はどちらも、世界が魏、蜀、呉の3つの部分に分かれていたと述べ...
女性の王国の女性はなぜ自国以外で結婚しないのでしょうか?女の王国の女性は結婚したいと思っているのでしょうか?
女人王国の女性はなぜ国外で結婚しないのでしょうか?女人王国の女性は結婚に熱心ですか?一緒に調べて参考...
『紅楼夢』では、賈の母親は賈静の誕生日パーティーに出席しませんでした。なぜですか?
賈夫人の姓は施であり、施夫人としても知られていました。彼女は中国の古典小説『紅楼夢』の主人公の一人で...
第二奇談集第32章:張夫娘は忠実で忠誠心があり、朱天熙はその評判にふさわしい
『二科派経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。 1632年(崇禎5年)に書籍として出...
羌族の教育モデルとは?羌族文化の簡単な紹介
幼児教育の解放後、地方自治体は幼児教育を重視し、幼稚園の数は徐々に増加し、規模も徐々に拡大しました。...
アンティークコレクションを始める上での6つの大きな障壁は何ですか?
骨董品を収集したり本を読んだりしても、一部の骨董品の名前、年代、用途について理論的に理解できるだけで...
曹操の『謝魯行』原文、注釈、翻訳、鑑賞
曹操の『謝魯行』、興味のある読者はInteresting Historyの編集者をフォローして読み進...
広州のアーケードはどんな感じですか?アーケード文化の特徴は何ですか?
Interesting History編集部がお届けする、広州のアーケード文化をご紹介します。これま...
『山坡楊里山昔話』の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
山鄂陽梨山郷愁張 陽浩礼山を見渡すと、阿房宮は焼け落ちていました。今、あの贅沢はどこにあるのか?まば...
明の皇后孝静怡夏武宗朱厚昭の簡単な紹介
孝静怡皇后(姓は夏)は、明代の武宗皇帝朱后昭の皇后であり、上原の出身であった。正徳元年に皇后に即位し...
皇帝の物語:劉裕は本当に歴史上6人の皇帝を殺したのか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...
シャオ・ファンジーには何人の兄弟姉妹がいますか?シャオ・ファンジーの兄弟姉妹は誰ですか?
梁孝芳之の景帝(543年 - 558年)は、雅号は慧襄、愛称は法真としても知られ、梁孝懿の元帝の9番...
『紅楼夢』で賈夫人は石向雲に対してどのような態度を取っていますか?何が変わったのでしょうか?
賈おばあさんは、屋敷の誰もがおばあさんと呼ぶ、寧容屋敷で最年長であり、最も尊敬されている人物です。次...