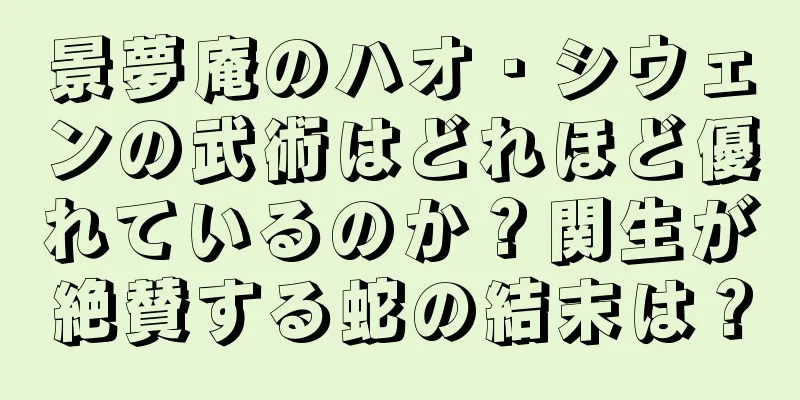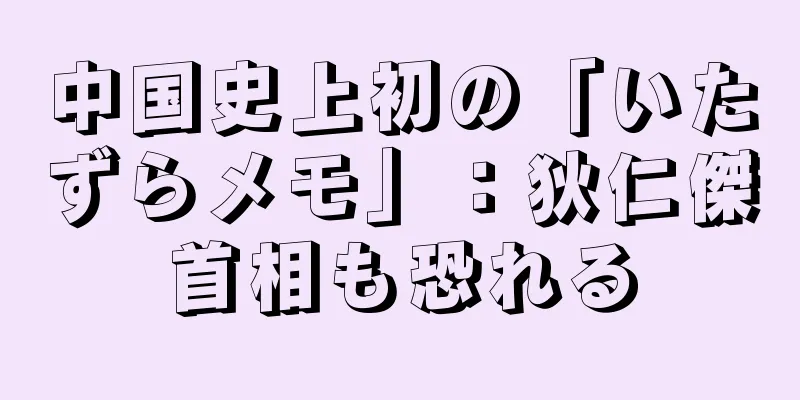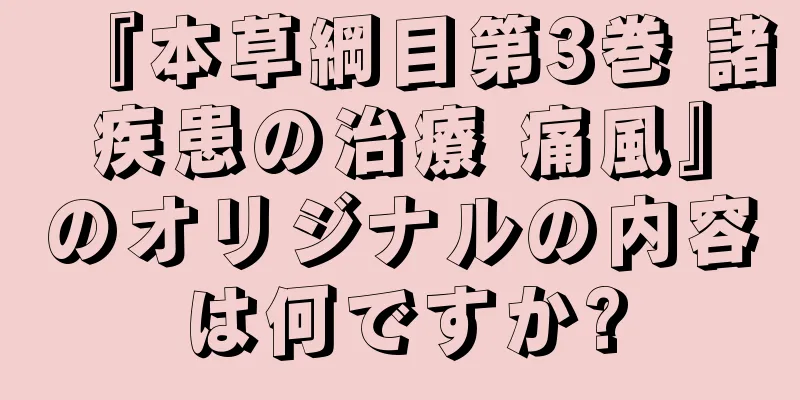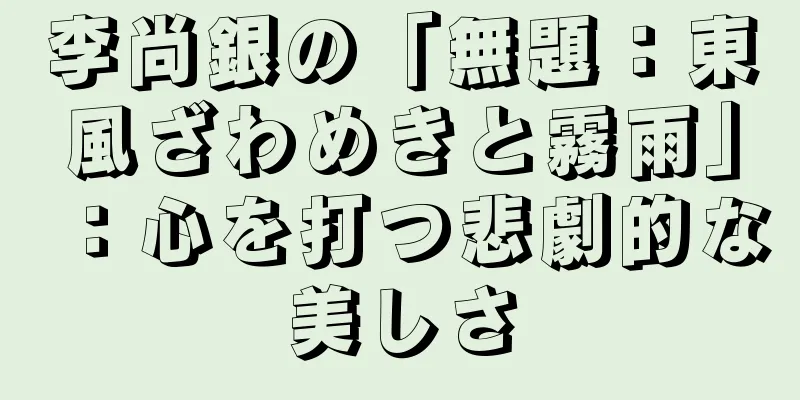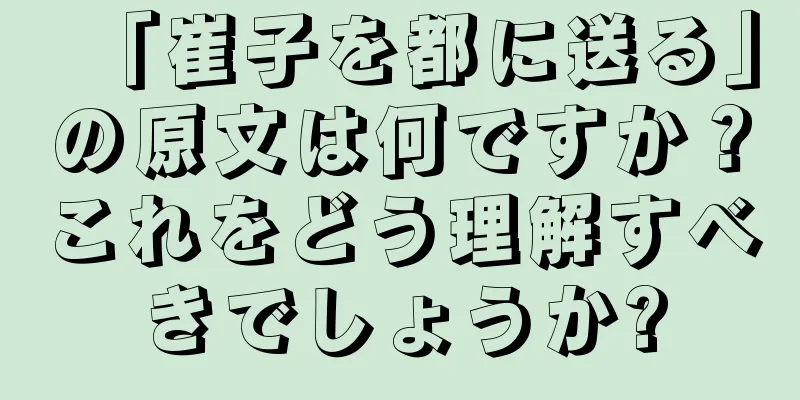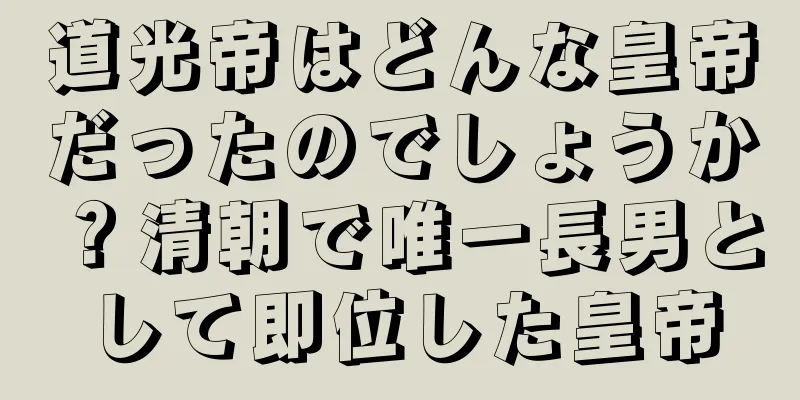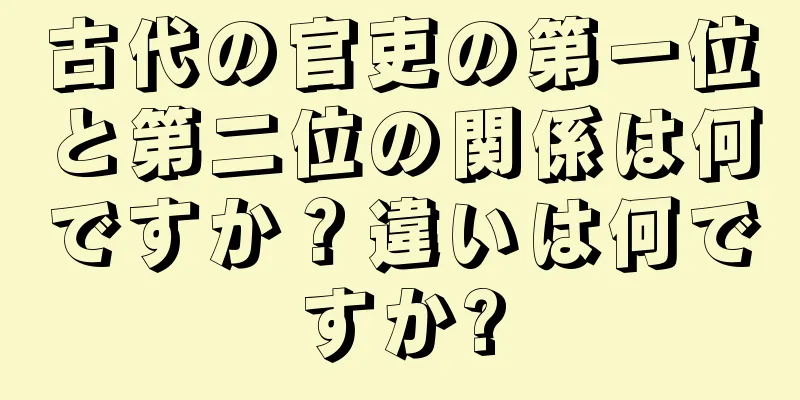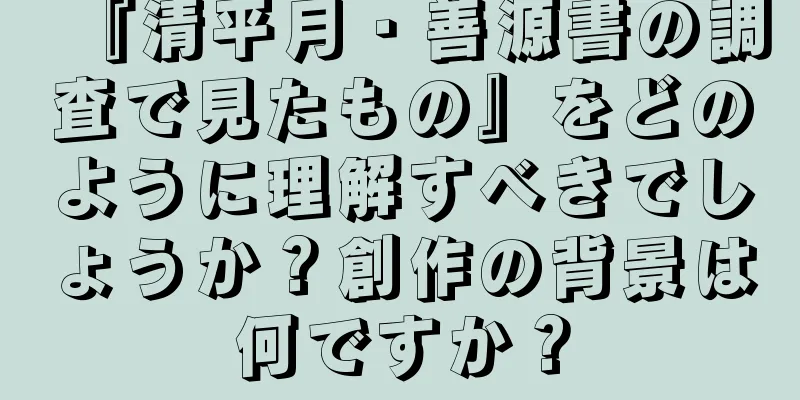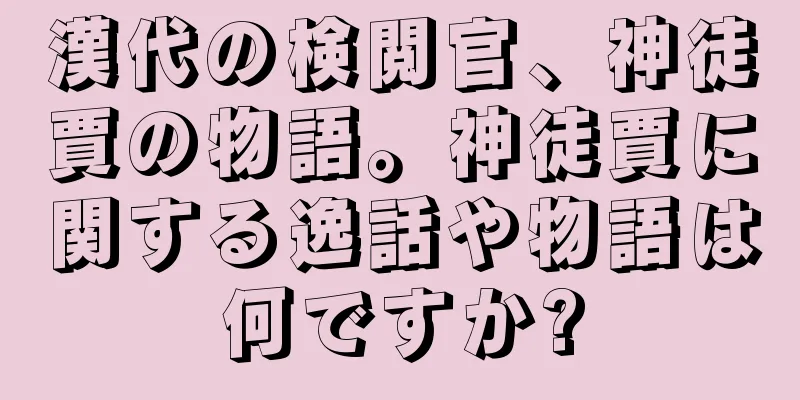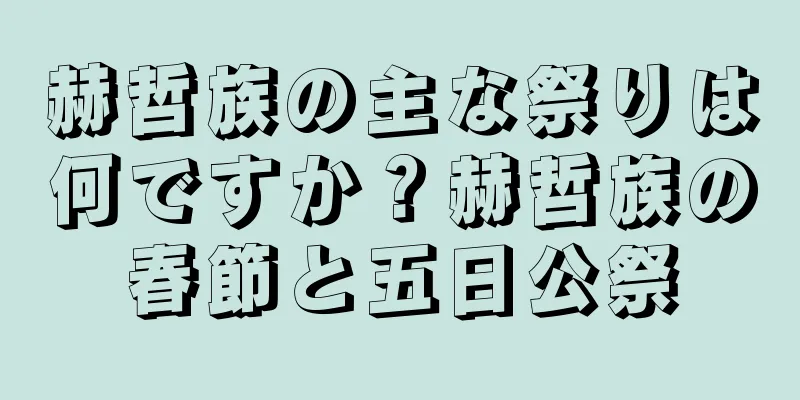Upper StudyとSouth Studyの違いは何ですか?清朝時代における「上書院を歩く」とはどういう意味だったのでしょうか?
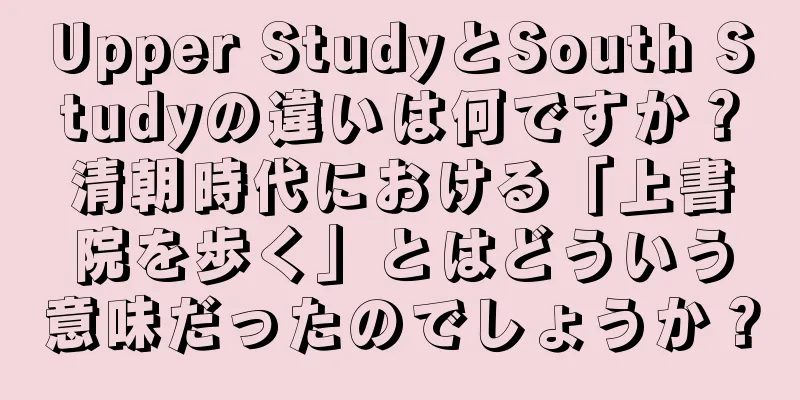
|
清朝の宮廷において、上書坊と南書坊は極めて重要な教育拠点であった。知識を伝えるだけでなく、王子たちに国を治めるための指針も提供した。時には、人材を募集したり、官僚の昇進の足掛かりとなる場所であったこともあった。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 「尚書坊」とは「王子や孫たちが学校に通い、勉強する場所」です。清朝の道光年間以前は「尚書坊」と呼ばれていましたが、道光年間に勅令により「尚書坊」に改められました。 上書坊は乾清門の東側南棟に位置し、雍正の初期の頃に建てられ、北向きの扉があり、全部で5つの部屋があります。王子が6歳になると、書斎に入り、勉強をします。通常、上書坊の主任教師として、満州語と漢語の大学の学者1人、2人、または3人が派遣され、漢語の教師が数人、満州語とモンゴル語の教師が数人おり、「安達」と呼ばれ、そのほとんどは高官でした。また、内安達と外安達の区別があり、内安達は満州語とモンゴル語を教え、外安達は乗馬と射撃を教えました。料理長は用事があるときに来ればよく、毎日勤務する必要はありません。師匠たちは交代で当番を務め、皇帝の皇子や孫たちに会うときは、ひざまずかずに手を握って挨拶するだけでした。毎日、私は朝に銀市(午前3時~5時)で自習室に行き、授業は茅市(午前5時~7時)で始まり、学校は烏市(午前11時~13時)で終わります。大型連休には1日休みがあり、夏休み中は授業時間が半分になります。 皇帝の皇子や孫たちは師をとても尊敬していました。例えば、嘉慶帝の師である朱文珍(朱桂)は、10年以上も尚書坊で働いていました。乾隆帝が亡くなったとき、嘉慶帝は急いで朱桂を北京に呼びました。北京に到着すると、朱桂は泣きながら朱桂の手を握りました。彼は南書院に勤務し、税部の三蔵を管理するよう命じられ、太子の守護に昇進し、紫禁城の西華門の外に家を与えられた。その後、彼は鉄仁閣の太守に任命され、工部省を担当した。朱桂が亡くなったとき、嘉慶帝は自ら朱家の家を訪れ、弔問した。朱家の門は低く、皇帝の馬車は入ることができなかったため、嘉慶帝は中に入って深く泣き、特別に文正の諡号を与えた。この教師と生徒の友情は当時伝説となった。 乾隆54年3月7日、乾隆帝は偶然、高書院の教師の当番表を調べたところ、2月30日から3月6日までの7日間、教師が誰一人として当番をしていなかった。乾隆帝は教師の怠慢と王子や孫たちの無断欠勤に激怒し、軍大臣を召集して尋問させ、欠勤した教師たちを厳しく叱責した。彼は満州族の内閣学者2人を罷免するよう命じたが、後にこれは不適切であると感じ、寛大な処置を取り、まず罷免した教師2人を40回の鞭打ちで打ち、結果を見るために高書院に留まらせた。清朝の歴史上、上書院の師匠が棒で殴られたのはこれが唯一の例である。 清代の学者傅歌の『庭語叢譚』第11巻には、「尚書坊」について比較的詳しい説明があり、そこには「尚書坊は乾清宮の南東の棟に位置し、北を向いており、王子たちが勉強する場所である」と書かれている。王子は6歳のとき、学校で勉強を始めました。翰林学院の院長である皇学の主任教師は、翰林学院の職員数名を推薦し、翌日、皇帝は彼を脇殿に呼び出し、品性が高く誠実な者を審査した後、ある王子の家庭教師として選びました。彼はさらに1、2人の助手を派遣し、彼らに上階の書斎を歩き回るよう依頼した。こうして選ばれた人たちは皆、公務員になる希望を持っています。 王子は毎日朝早く学校へ行き、午後2時半に帰りました。放課後は徒歩で弓術の練習をし、5日に1回は頤和園で馬上弓術の練習をしました。王子は、結婚して爵位を授かった後も、季節を問わず勉強をやめませんでした...王子が幼い頃に学校に入学したとき、彼は先生と同じテーブルに座りました。先生が文章を読み、王子がそれを繰り返しました。繰り返し暗記した後、彼はそれを100回読み、その後、前の4日間で学んだ生徒たちと一緒に100回読みました。 6 日前までに書かれたものはすべて、おなじみの本と呼ばれます。それは約 5 日ごとに中断することなく何度も繰り返されますが、これは普通の人には理解できません。毎日の宿題は、入学時にモンゴル語の文章を2つ覚え、竹弓を数回弾き、清朝の文献を25分間読み、毛正の最後の四半期から漢籍を読み、神初2四半期までに学校を終えることです。放課後に夕食を食べます。毎朝、天皇、皇太后、皇后の宮殿の前で。一般的には、元旦、端午節、中秋節、万寿、子寿の5日間が休みとなる以外は通常通りで、大晦日を含め残りの日も休みとなります。 尚書坊興宗は、実は清朝の太子の師匠の代理であった。清朝の人々は「歩く」という言葉を好んで使っていたが、これはおそらく、追い立てられることを意味していた。例えば、誰かが太書に昇進し、太政会議で働くよう求められた場合、皇帝の勅令は通常、「張三に太書の称号を与え、一等帽子を与え、太政会議を歩かせよ」というものだった。はっきり言えば、「尚書房行蔵」は正式な役職ではなく、単にその人がどの部署で働いているかを示すものにすぎません。 南書坊は紫禁城の月花門の南に位置し、かつては康熙帝の書斎であった。康熙帝の治世16年(1677年)に設立され、宮廷講師の張英と内閣学者の高士奇が務めるよう命じられた。これが、南学に勤める翰林学者の選抜の始まりとなった。 翰林は南書院に入り、当初は文学係として働き、いつでも読書や講義を手伝うために呼び出された。彼はしばしば皇帝に仕え、皇帝の顧問として古典、歴史、詩、散文について議論した。皇帝が巡視に出かける時は必ず護衛兵が同行していた。皇帝の即興の詩やコメントはすべて記録されました。さらに、天皇に代わって勅令や法令を起草したり、国政に携わったりすることが多かった。彼らは皇帝に近い立場にあるため、皇帝の決定、特に大臣の昇進や降格に一定の影響力を持っています。そのため、当番の人の地位は目立ったものではないものの、非常に尊敬されています。 雍正年間に太政官が設立されると、勅令の起草は太政官とその他の官吏の専属的責任となった。翰林の学者たちは南書院で研究していたが、もはや政務には参加しなかった。清朝時代、学者たちはここを重要な場所とみなし、そこに入ることができるのは名誉なことと考えていました。中国第一歴史文書館には『南書房紀録』が所蔵されており、これは現在までに発見された数少ない南書房文書のうちの1つである。 「書院」はもともと役人が読書や勉強をする場所でしたが、清朝が入城する以前は、宮廷で勤務する儒教の役人を指す特別な用語として使われていました。玄野は引き続き古い名前を使用し、紫禁城に南書院と上書院という2つの書斎を設けました。南書院は、内廷に仕える翰林の役人が皇帝に詩や書、絵画を献上する場所であり、上書院は王子たちが師匠のもとで勉強する場所であった。 南書房はもともと康熙帝自身の研究対象でした。康熙帝の16年10月に、儒教の役人がそこで奉仕し始めました。それは、玄野が文字を学び、歴史を読み、経典について議論し、先代の統治者の経験と教訓を吸収し、漢民族の長年の文化的伝統の影響を受けるのを助ける上で非常に重要な役割を果たしました。 玄野自身は康熙9年にすでに日講と勅講を始めており、毎日講師を務める翰林の官吏たちと交流していた。しかし、この接触は講義に限られており、知識への渇望を満たすには程遠いと彼は感じていた。 康熙16年10月、玄野は内閣太書に提案した。「私は本を読まず、時々書きます。私の従者には書道の知識と優れた人がいません。そのため、講義についていくことができません。今、翰林書院から2人を選んで私のそばに仕え、文学の意義に注意を払わせたいのですが、彼らは皆自分の仕事があり、外城に住んでいます。時々呼び出されなければ、すぐに来るのは難しいです。内城に空き部屋を割り当て、昇進を止め、数年宦官として仕えた後、使用してください。」 (清朝記録) 当時、選ばれたのは二人だけで、一人は翰林学院の学士で毎日の講義を担当する役人である張英、もう一人は北京に取り残されていた浙江省の貧しい学者である高世奇でした。内務省は彼らのために西安門の中に二つの空き部屋を見つけ、彼らは毎日宮殿の南書院で勉強することを義務付けられました。その後も玄野は南書院に大臣を加え続けた。南書坊は玄野の文化生活に深く関わる場所となった。 南書房は行政機関ではなく、筆、墨、紙、硯などの物資や宦官、雑役人などはすべて内務省から供給されていた。毎日、当番の役人は宮殿の衛兵に付き添われて正午に南書院へ出勤し、正午に宮殿を出発しました。南部研究室で奉仕する牧師には新しい称号はなく、依然として元の役職で呼ばれていました。 張英は就任前は翰林学院の講師だった。就任後は「四等俸の張英講師」と呼ばれた。当直官が翰林学院出身者でない場合は、就任後に状況に応じて官名が与えられる。庶民の家に生まれた高世奇は、南書院に着任後、中書社人の称号を与えられ、「内閣中書社人、六位の俸禄を持つ高世奇」と呼ばれた。一般的に「南書坊ウォーキング」と呼ばれています。李光帝のように南書院の正式な役人ではなかったが、皇帝と親しい関係にあったため、南書院に出入りする大臣もいた。 南部研究室に勤める牧師たちは、執筆と切り離せない関係にあった。南書院で最初に働いた高士奇はかつてこう言った。「私は康熙帝の定思年間から召使となり、季節を問わず皇宮の南書院で働き、ほぼ13年間、書物を研究し、筆と硯で日々を過ごしています。」(『天路の私に関するメモ』) 南書が設立された当初、玄野は詩作を学んだばかりで、詩に非常に興味を持っていました。張英と高世奇に詩を書いて贈るように命じただけでなく、王時珍、陳廷景などの従士たちを内廷に呼び寄せて詩を詠ませることもよくありました。時々、夜遅くになると、彼は彼らを南の書斎に留め、ご褒美として豪華な宴会を催しました。彼は、張や高らと比べ詩や随筆を書くのが上手ではないことを知っていたので、詩人たちとの関係は比較的平等だった。 康熙十七年八月、玄野は張英、高士奇、講師の陳廷静、王時珍、葉芳夷に南書で詩集を朗読するよう命じ、次のように要望した。「私は諸事の合間に詩を朗読しますが、古人に習うことができません。あなたがそれを編纂し、何度も見せてほしいとおっしゃったので、お見せします。修正が必要な部分があれば、はっきりと述べて、何も隠さないでください。」(『秋季主典』)玄野の詩はあまり良くなく、ましてやまだ初心者であった。しかし、身分の低い詩人たちはあえて批判せず、いつものように「歴史上のどの皇帝もこんなことはできない」と賛辞を述べた。皇帝という最高の地位にあったため、大臣たちの本当の意見を聞くのは困難だった。 当時、宮廷の詩集や散文集が出版されたり、内廷で書籍を編纂したりする際に、南書院の役人が編集や校正を担当しました。例えば、康熙帝の治世17年、南書房は宣業帝の勅旨を編集するよう命じられ、康熙帝の治世55年、蘇州の織物製造業者である李胥は3冊の勅詩集の出版を引き受けたが、改訂、校正、署名の作業は南書房の責任であった。康熙帝は正月に大臣たちに書を授けた。内容は「幸福長寿」「福寿」「松鶴」「松寿」など縁起の良い言葉がほとんどで、南書の官吏が書いたものが多かった。 康熙帝の時代以降、一部の文人は、南書房が依然として勅令の起草を担当していたことを随筆に記している(『延埔雑注』『小亭徐録』『楊吉寨叢録』『恩復堂注』などを参照)。しかし、康熙帝の治世中の日誌から判断すると、そうではなかった。 張英と高世奇が正式に南書に仕えてから2か月後、康熙帝は勅令を出し、次のように明確に指示した。「内書に仕えることに選ばれた張英と高世奇は、慎み深く勤勉であり、今後は優遇され、外事に干渉することは許されない。彼らはみな学者であり、これらの理由を知りながらも、私の命令に厳格に従わなければならない」(『斉居書』)。張英、陳廷静、王時珍らは南書院に赴任する前は記録係を務めていた。国事にはあまり関与していなかったが、政治に直接関わっていた。南書院に入った後は記録係を務めなくなった。 宣業と国政を協議し、勅旨の起草の許可を求めた者は、内閣の太書や学士などの官吏であり、南書の人々ではなかった。日記には、ほぼ毎日「皇帝は乾清門に行き、各省庁の役人から政務報告を聞いた。役人が去った後、内閣の太書記と学士が皇帝に嘆願書を捧げ、承認を求めた」という記録があります。玄野が病気で政府の会議に出席できないとき、彼は内廷の南書院から官吏を召集して政務を議論するのではなく、「内閣の書記長と院士を茅琴殿に召集して直接政務を議論した」(『求家主典』)こともあった。このことから、当時康熙帝の勅旨を起草したのは南学の官吏ではなく、内閣太書であったことがわかります。 しかし、南学の役人たちは政治への介入を一切控えていたわけではない。かつて南書院に勤めていた皇学士の王洪胥はこう語っている。「以前、皇帝が巡幸中、密かに小碑を準備するよう皇帝の命を受けたことがあります。私は自ら雨書院に行き、宮司に手渡して首長に報告し、首長はそれを密かに皇帝に届けました。宮司が報告を戻した日に、私は自ら出向いてそれを持ち出します。この時は皇帝は留守で、南書院からは誰も来ないので、極秘です。今回また密命を受けたので、私が先に首長に渡し、他の危険を避けるために慎重に送受信するのが適切だと思われます」(『王洪胥密かに小碑を準備』)。 王洪胥は康熙帝の命により極秘に勅書を提出したが、南書の他の官吏も同様のことをした可能性がある。しかし、このような天皇に提出する秘密の建白書は、前述の天皇に対する勅書の起草とは形式的にも内容的にも全く異なるものである。勅旨の起草は、当時、最も重要な機密事項であった。起草に携わった大臣は、直接政務に携わる者でなければならなかった。密勅の提出は、大臣が自らの所見を天皇に報告するに過ぎず、報告された事項がすべて機密事項というわけではなかった。これは大臣が義務を果たしていると言えるでしょうが、もちろん誰もがこれを実行できるわけではありません。 玄野は南学の役人たちと非常に親密な関係にあった。彼はよく「他の学者と一緒に花を鑑賞したり、釣りをしたり、同じクラスの先生や友達のように経典の意味を分析したりした」(暁亭徐禄)。康熙17年3月、五台山は「天然痘茸」の一種を宮廷に献上した。玄野はその茸を「新鮮で珍しく、美味しい」と感じ、人を遣わして南書坊に届けさせ、そこで勅書を編集していた張英らに食べさせ、「山の風習を知らせる」ようにした(秋季集)。 李光帝が病気のとき、玄野は彼をとても大事に世話しました。燻製の鱗魚や新鮮な鹿肉を与えただけでなく、李光帝の家族が毎日宮殿に来て玉泉水を飲んで胃腸を養うことも許可しました。張英の父が亡くなり、張英は葬儀に出席するために帰省の許可を求めた。玄野は葬儀の費用として特別に銀500両を与えた。大臣たちに果物やワイン、食べ物を褒美として与えることは、一般的なことだった。玄野自身も南書院によく行き、臣下たちが詩を書いたり絵を描いたりするのを眺めていた。嬉しい時には自らも筆を取り、臣下たちに褒美を与えていた。 南学の幹部は主に翰林学院出身者であった。当時の翰林官僚の多くは科挙に合格した優秀な学者であり、同時に南学に仕える官僚は当時の有名な学者の推薦を受けることが一般的であった。しかし、玄野はまだ心配しており、彼らの才能を個人的に調べたいと考えていました。清代初期の有名な詩人で講師であった王時珍と宮廷学者であった陳廷静は、宣耶帝によって茅琴殿に召喚され、その場で詩を作り、南書坊に入る前に皇帝から賞賛を受けた。 康熙24年、玄野は翰林書院と湛氏宮の官吏に対して再度の試験を実施した。この試験で日誌をつけ一位を取った役人がいたので、玄野は彼を南書に選んで働かせた。康熙帝の治世33年、玄野は翰林書院、湛氏宮、帝室に命じて、毎日4人の官吏を選び、交代で指南書院に通わせ、その中から選ぶようにした。 玄野が南書の官吏を選ぶ際に用いた主な基準は、徳と才能に要約できます。もちろん、彼は封建統治に有益な徳と才能を求めていました。彼らは自分の立場や家族の背景をあまり気にしません。例えば、都に取り残された貧しい学者で、南書に初めて仕えた高士奇は、太書の明珠から字が美しいと推薦され、例外的に南書に抜擢された。南書の官吏の戴子もまた、天文学や数学に精通し、詩や文章を書くのが得意な庶民であった。 彼が発明した連射銃法は三藩の鎮圧に大きな役割を果たした。彼も例外として選ばれ、南学に入学した。影響力のあった朱一尊は、有名な「四平」の一人であり、康熙帝の治世18年に博学雄弁の試験に選ばれて初めて有名になりました。当時、国内外の世論は彼を「野蛮な翰林」と非難したが、宣野は朱一尊が詩文や散文、文献研究に優れていると信じ、南学に選んだ。 玄野が南学の官吏の才能に注目していたことを示す最も良い例は、方宝の採用である。方宝はもともと全国を震撼させた『南山コレクション』事件の指名手配犯だった。『南山コレクション』の序文を書いたため死刑囚となった。偶然、玄野は李光帝が方宝の漢詩が優れていると言っているのを聞いて、方宝の罪を赦し、長春園に連れて行って「湖南東廟帰化碑文」と「凰仲は万物の根本理論である」を書かせるよう命じた。 玄野はそれを読んだ後、非常に満足し、方宝の文章は「ここ十年で学問を終えた翰林の先輩たちでさえも超えることはできない」とさえ言った(王熙全集)。それ以来、方宝は犯罪者から南書院の役人へと転身した。 南学の官吏たちは玄野の学問に大きな影響を与えた。玄野は「彼らがまとめた講義録は正確かつ詳細で、統治に大きな利益をもたらす」と評した(『多素堂全集』)。南書院で13年間働いた高士奇は、玄野を学問の海へと導いた人物であった。彼はかつて従者たちにこう言った。「私が初めて勉強を始めたとき、宦官たちは私に四経と現代のエッセイの書き方を教えてくれました。私が学問のやり方を理解し始めたのは、私が士奇に出会ってからでした。私が初めて士奇の古代の詩とエッセイを見たとき、私は一目で時代がわかるようになり、それは素晴らしいことだと思いました。すぐに私も同じことができるようになりました。」 (清代史草稿) 玄野は子供の頃から書道が好きで、暇なときに書道を練習することが皇帝が持つべき教養であると信じていました。彼は書道に長けた歴史家である沈全を南書院に招き、書道のやり方を教えさせた。沈全が亡くなった後、玄野は彼をとても懐かしがり、李光帝にこう言った。「私が初めて書道を習ったとき、父の全は私の長所と短所を指摘してくれました。今でも、書くときはいつも彼の勤勉さを思い出します。」 (『清代志草稿』) 沈全の指導のもと、玄野は多くの有名な書道を模写した。その後、彼はこれらの書道を宮廷書道局に命じて『茅琴書道集』という特別版として出版させた。 康熙帝の治世以降、南書院には文人を備えた官吏が勤める慣習が定着し、「南書院は絶えず寵愛され、優れた資料を保管する重要な場所となった」(『小亭序録』)とされている。 |
<<: 天清宮は後宮の正殿でした。雍正帝は即位後、なぜ修心殿を寝室に変えたのでしょうか?
>>: 文源閣に主に影響を与えた建物は何ですか?清朝のどの皇帝が建設を命じたのでしょうか?
推薦する
西漢の創始英雄、曹申に関する逸話とは?曹申の逸話と物語の紹介
曹深(発音:cān、紀元前190年頃)、愛称は荊伯、漢族の沛の出身。西漢の建国の英雄、名将、蕭何に次...
唐の皇帝高祖李淵はどのようにして太原で反乱を起こし、皇帝になったのでしょうか?
隋の末期には農民反乱が続き、隋の煬帝は徐々に国の支配力を失っていった。あらゆる分野の英雄たちが旗を掲...
公公はなぜ怒って不周山を殴ったのでしょうか?公公が怒って不周山を殴ったという話はどこから来たのでしょうか?
みなさんこんにちは。これは「興味深い歴史」の編集者です。今日は、公公が怒って不周山を殴った話をお話し...
『紅楼夢』の黛玉小湘妃という称号に隠された深い意味は何でしょうか?
紅楼夢の黛玉小妾の称号に込められた深い意味とは?次は、興味深い歴史の編集者が関連記事をお届けします。...
薛剛の唐に対する反乱、第71章:父と息子はお互いを認識せずに戦い、夫婦は会って周の軍隊を打ち負かす
『薛剛の反唐』は、汝連居士によって書かれた中国の伝統的な物語です。主に、唐代の薛仁貴の息子である薛定...
「酔いから覚めたら春は去っていた」という詩はどのような感情を表現しているのでしょうか。この宋代の詩をどのように鑑賞すればよいのでしょうか?
ヤマウズラの空:酔い覚めたら春はまた去っていた [宋代] 顔継道、次の興味深い歴史編集者があなたに詳...
なぜ朝鮮半島には苗字が少ないのでしょうか?
韓国の姓の少なさと少数の姓への集中は、朝鮮半島の長い封建時代の歴史と中国や日本との複雑な関係に関係し...
賈廉が秋童を側室として迎えたとき、彼の後妻である幽二潔と侍女の平児はどう思ったでしょうか。
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
皇帝の物語:秦の昭襄王はなぜ白起の殺害を命じたのか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...
『前漢民謡』第一章の主な内容は何ですか?
李大涛を利用して淫乱女王の快楽を受けるために明治に花や木を移植する計画皇帝には皇帝の計画があり、皇帝...
ファン・イーとは誰ですか?彼女は複雑な性格をしている。
方怡とは誰ですか? 方怡は魏小宝の7人の妻の1人です。彼女は方家の子孫であり、穆王邸の劉、白、方、蘇...
曹植の最も古典的な作品の一つ「七段詩」を鑑賞する
以下、面白歴史編集長が曹植の『七段詩』の原文と評価をお届けします。興味のある読者と面白歴史編集長は一...
『紅楼夢』で劉おばあさんはなぜ喬潔を救ったのですか?理由は何ですか?
劉おばあさんは『紅楼夢』に登場する田舎のおばあさんです。次は『Interesting History...
『紅楼夢』で趙叔母の葬儀費用が西仁の葬儀費用より銀20両も少なかったのはなぜですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
『後漢書 丁鴻伝』の原文と翻訳、『丁鴻伝』より抜粋
『後漢書』は、南宋代の歴史家・范業が編纂した年代記形式の歴史書である。『二十四史』の一つで、『史記』...