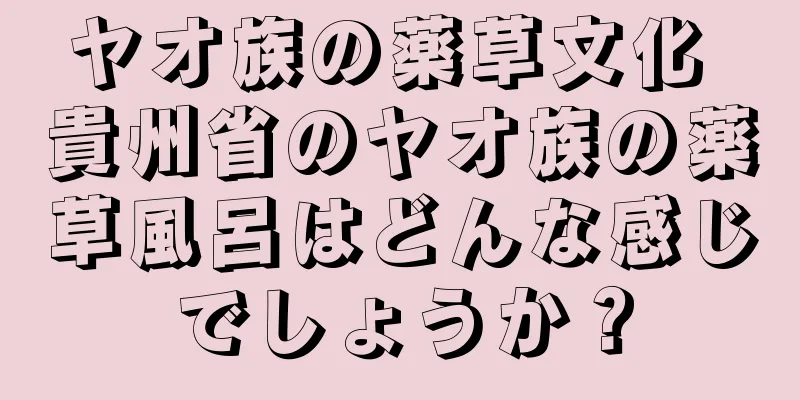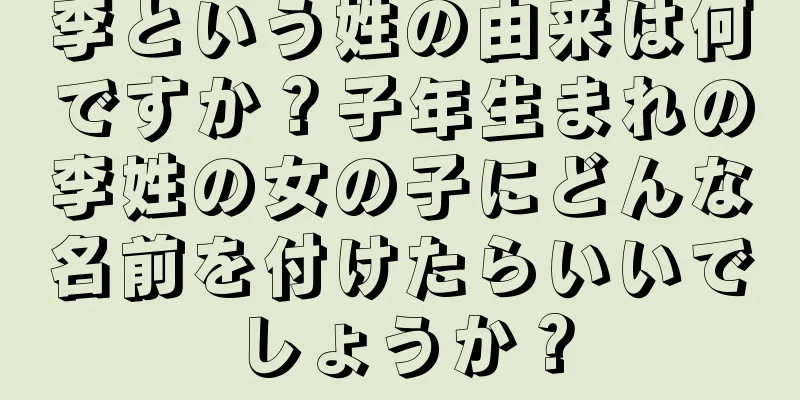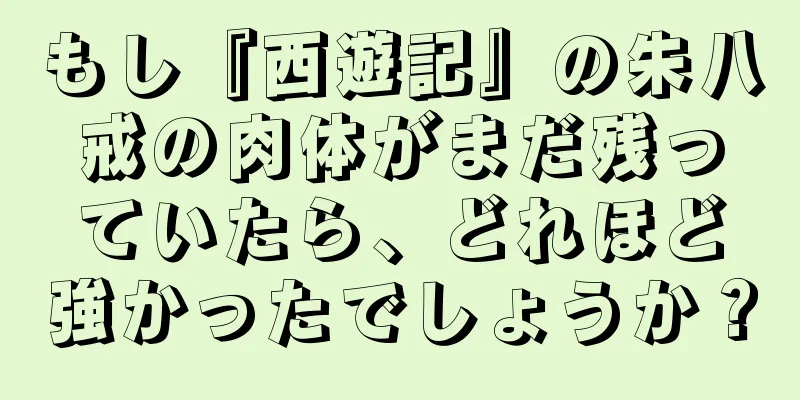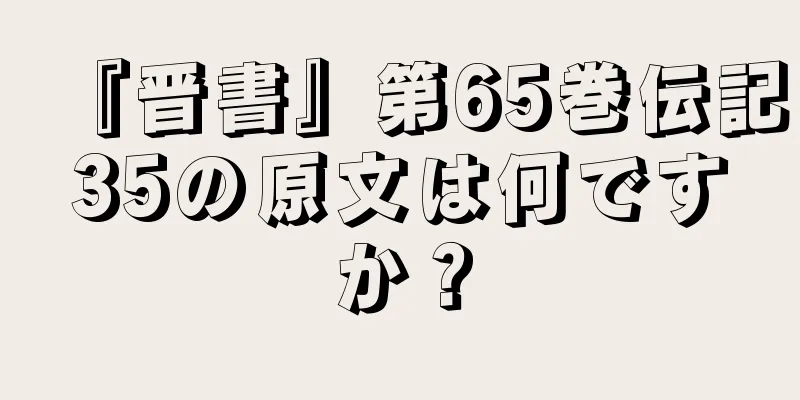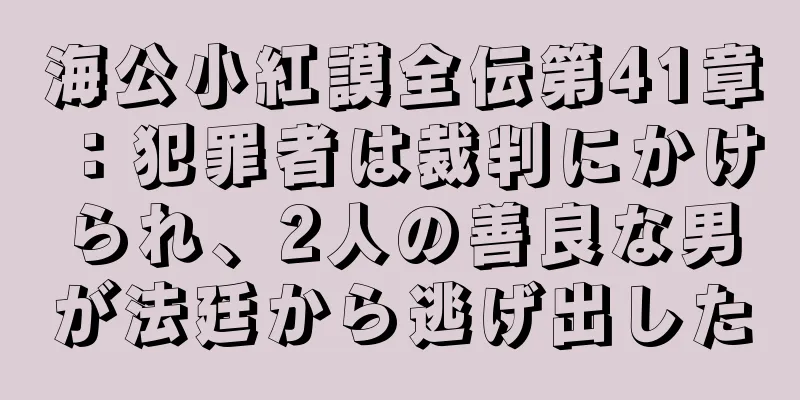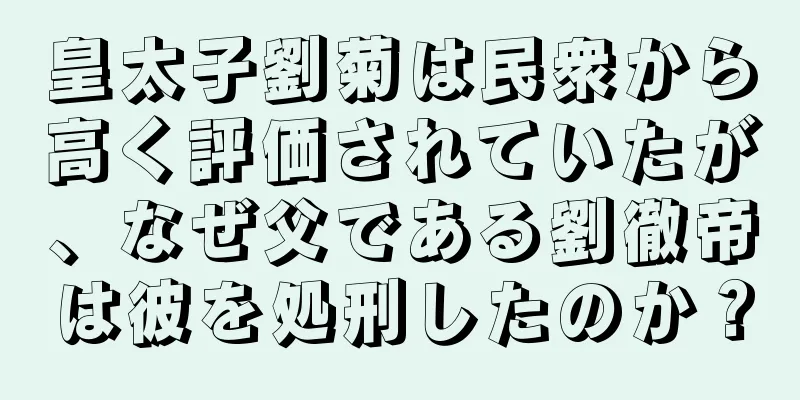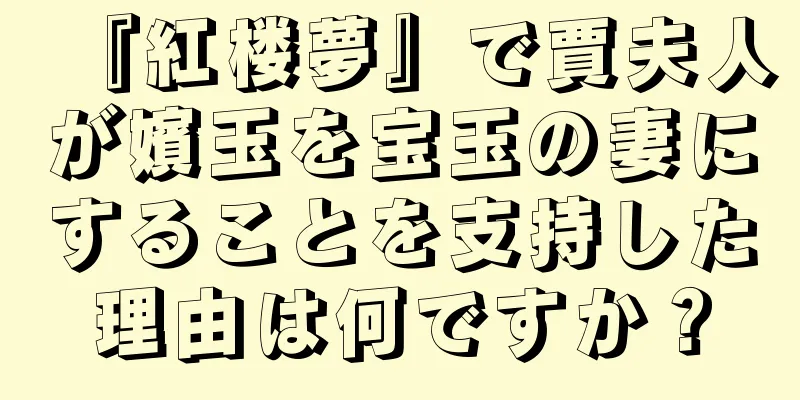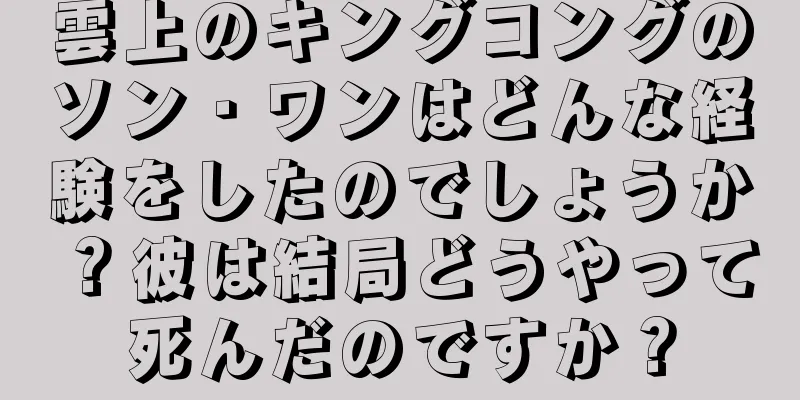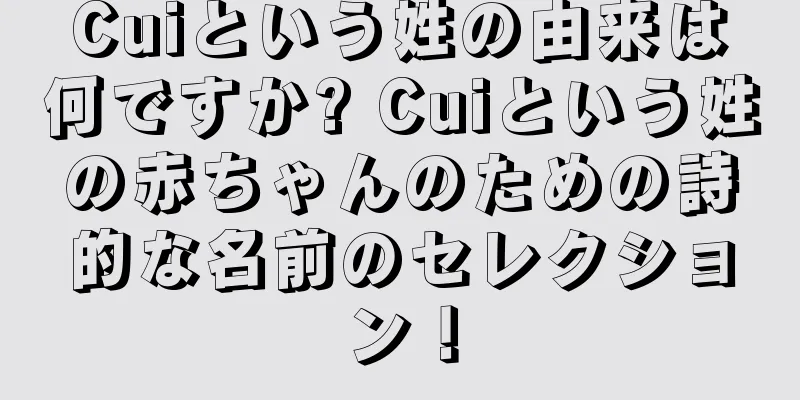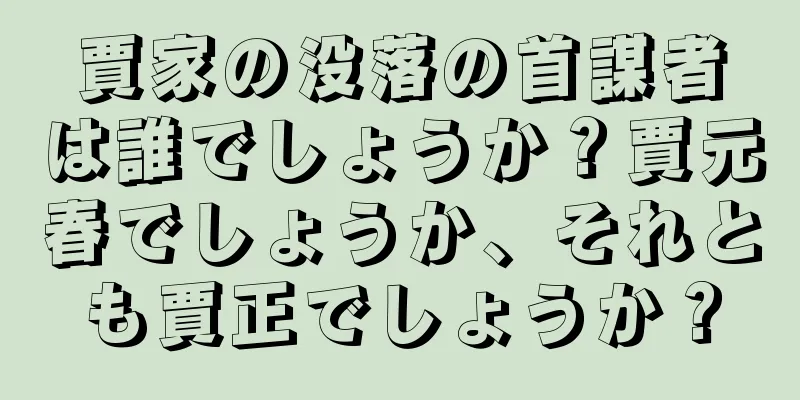北宋時代の経済はすでに前例のない繁栄に達していたのに、なぜ抜本的な改革を行う必要があったのでしょうか。
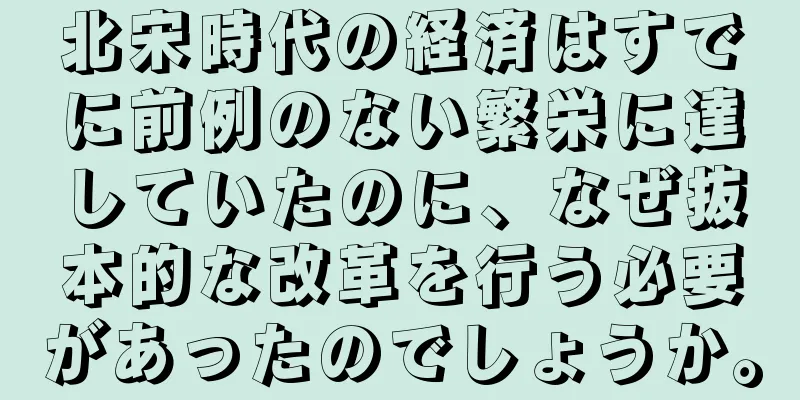
|
北宋時代は、中国の封建社会において前例のない繁栄を極めた時代でした。有名な絵画「清明上河図」に描かれた汴京の喧騒から、中学生が何度も言及する欧陽秀、范仲厳、蘇軾、劉勇などの文豪、映画やテレビドラマ「清平楽」や「明蘭伝」に描かれた繁栄の時代まで、北宋時代の経済的、文化的繁栄は、繰り返し世界に伝えられています。 後世の徹底的な研究により、北宋時代の経済と文化がかつてないほど繁栄していたことは間違いではなかったことが判明した。軍事力を除くすべての指標(税収、人口、穀物生産、対外貿易、科学技術など)は、前代どころか後代の水準をはるかに上回っていた。しかし、このように繁栄した王朝は、「清歴新政策」、「西寧改革」、「元豊改革」という3つの変革を経験した。その中でも、西寧の改革(王安石の改革とも呼ばれる)は非常に大きな影響を及ぼしたため、歴史家によって商鞅の改革とよく比較されます。こうなると、次のような疑問が湧いてきます。かつてないほど経済と文化が繁栄した北宋王朝は、なぜ大きな変化を遂げたのでしょうか。次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう。 実際、どの王朝にも隠れた危機や問題が存在します。例えば、漢代には外戚による政務への干渉、西晋代には内紛と民族紛争、唐代には分離主義政権と宦官による乱政、明代には派閥争いと宦官による乱政、清代には鎖国政策と強い政治的圧力があった。北宋も当然例外ではなく、その特殊性ゆえに、直面した危機や困難もより顕著な特徴を持っていました。 北宋時代の最も深刻な問題は「三つの過剰」であった。 「三余」とは、北宋時代の「官吏の余剰」「兵士の余剰」「経費の余剰」問題の総称である。この用語は、唐宋八大家の一人である蘇哲が、西寧二年(1069年)に宋神宗に宛てた『帝書』の中で初めて提唱された。『帝書』の中で蘇哲は「経済を害するものは三つある。一つ目は官吏の余剰、二つ目は兵士の余剰、三つ目は経費の余剰である」と提唱した。 いわゆる「官吏過剰」とは、北宋の行政機構が巨大で、官吏の数が極めて多く、年々増加し続けていたことを指す。「兵吏過剰」とは、北宋の軍隊の規模と兵吏の数が極めて多かった現象を指す。「経費過剰」については、「官吏過剰」と「兵吏過剰」の問題に対応した結果である。膨大な官吏と兵吏の数はすべて国家財政によって支えられていたため、必然的に経費が膨大になり、経費をまかなうには足りず、翌年の食糧を先食いしてしまうこととなった。 客観的に見れば、「三つの重複」問題は北宋に特有のものではなく、中国のすべての王朝に存在していた。しかし、北宋の「三つの重複」問題が最も深刻であったことは疑いの余地がない(それについては疑いの余地はない)。 1. 深刻な地方分権化と官僚主義の蔓延が見られます。北宋の初代皇帝趙匡胤は、「皇帝は代わる代わる帝位に就き、今年は私の番だ」という五代十国の混乱した状況からやって来た。彼は陳橋の乱、孤児や未亡人への虐待によって皇帝になった。 そのため、北宋は建国当初から、独裁や反乱を防ぐために中央政府から地方レベルまでの完全な地方分権制度を確立しました。例えば、中央政府は、宰相の軍事力を分割するために枢密院(主席は枢密顧問官と枢密副顧問官)を設置し、宰相の行政権力を弱めるために副宰相に「三局正使」を設置し、宰相の財政力を分割するために、全世界の税を管轄する塩鉄部、歳入部、物品税部の三部(主席は三部)を設置した。 地方政府は道、州、郡の3段階に分かれており、各道には鎮撫使、交通使、刑事監察官、穀物使がおり、それぞれ戸籍、財政、司法、救済を担当していた。各州には知事がおり、知事の権力が強大になりすぎないように、互いに牽制しバランスをとるために通班という役職が設けられました。 さらに、北宋代には、街道氏、城宣氏、関所氏、方魚氏など、地方に多くの非公式の役職が設けられました。こうした地方分権化の措置は、ある程度、中央政府に対する地方の反対を防ぎ、権力の集中と国家の統一を維持したものの、問題は、広く確立された官職の機能の多くが重複し、「一人の官僚が複数のことをする」や「十羊のうち九羊飼い」といった官僚の数が増加するだけの肥大化した官僚制度をもたらしたことである。 2. 科挙制度が拡大し、縁故主義が蔓延した。北宋時代は学者の黄金時代とも言える。軍事より文化を重視する国是は科挙制度に完全に反映されていた。『宋書』の記録によると、「隋唐代に進士試験が初めて制定されたとき、毎年選ばれる者は30人以下であった……咸衡・商元期には70~80人に増加した」「太平興国8年には1万2600人に、春化2年には1万7300人に増加した」とある。北宋時代の科挙における官吏選抜枠は、隋唐時代に比べて飛躍的に増加したことがわかる。 もちろん、これは貧困家庭の子供たちが立ち上がるための道を提供し、社会的公平性を維持したが、同時に、官僚を大量に配置するための措置と相まって、ある程度「余剰官僚」の育成を促進した。しかし、科挙制度の公正な選抜に比べ、北宋代に蔓延した皇帝縁故主義制度は「余剰官僚」問題の深刻化の大きな原動力となった。 恩寵は実は中国古代の世襲制度の一種で、先祖の功績により子孫に学問や官職の権利を与える待遇を指す。北宋に特有なものではないが、北宋時代の恩寵の名称は前例がなく多様で、隠居恩寵、功績褒賞恩寵、盛大な儀式恩寵などに分かれていた。例えば、「曹斌の死後、親族、家臣、教師20人以上に官職を与えた」や「雷有忠の死後、息子8人に官職を与えた。これらは功績のある官吏に恩寵を与えた事例である」。北宋代には寵愛制度が制度化され、この制度によって官吏となった者の数は科挙制度に次いで多かった。さらに後代の政治腐敗により寵愛制度はより横行し、野放図となり、官吏の数が急増したことは間違いない。 3. 反乱を防ぐために、兵士の募集を緩和する必要があります。 『国史大綱』『二十二史注』『宋慧堯集』『宋史』『続志士同鑑長編』などの文献の記録によれば、北宋時代の兵士の主な供給源は、兵士の息子(父や兄弟の代わり)、飢餓で餓えた人々、流刑にされた犯罪者などであったと結論付けられます。 その中で、飢饉の年に飢えた人々を軍隊に徴兵するという慣行も、宋の太祖によって制定されました。これは、下層民が危険を冒して集結して反乱を起こすのを防ぐことができ、兵士の数も増やすことができるため、一石二鳥と言えるでしょう。しかし、問題は、封建社会では飢饉の確率が非常に高く、飢饉の数は兵士の数に比例していたことです。以前の王朝よりも緩やかなこの徴兵制度は、間違いなく兵士の大規模な増加につながるでしょう。 4. サービス期間は非常に長く、増加するだけで減少することはありません。北宋時代の「余剰兵」問題が深刻だったのも、兵士の兵役期間が極端に長かったためである。北宋時代には復員という概念はほとんど存在せず、兵士は若いうちから兵役に就けなくなる年齢になるまで兵役に就き、終身制に等しかった。 『国史要綱』には、「徴兵された兵士は20歳から老齢まで、40年以上にわたって一生軍隊に勤務するが、実際に役に立つのはせいぜい20年である。彼らは一生食料を支給されるので、20年間は役に立たず、食料を政府に頼ることになる」と記されている。 北宋時代の兵士は平均して兵舎で40年間過ごしましたが、朝廷に貢献できるのは20年間だけで、残りの20年間は国庫から援助されていました。これにより、北宋軍には非常に奇妙な現象が起こりました。兵士の数は減るどころか、むしろ増加したのです。統計によれば、北宋の軍隊の数は建国初期の20万人以上から、清暦のピーク時の120万人以上に増加するまで、わずか70年余りしかかからなかった。 5. 報酬は高額だがコストが高い。多数の兵士や役人を支えること自体が大きな財政負担だが、役人の高額な給与やその他の費用が「重複経費」問題をさらに悪化させている。なぜなら、研究によれば、北宋時代の官僚の給与と福利厚生は、すべての王朝の中でも最高だったと考えられるからです。 「余剰兵士」と「余剰役人」によるもう一つの重要な出費は、知事の交代と軍隊の交代である。地方官吏や将軍が地方で長期間活動した後に派閥を形成し、中央政府を脅かすのを防ぐために、北宋の知事と地方軍は3年ごとに交代する制度を実施する必要があり、その結果、「官吏が人民を知らない」、「将軍が兵士を知らない」という状況が生まれました。 通信や交通が未発達だった古代では、3年ごとの交換は間接的にコストを増加させ、「冗長性」の問題を悪化させることは確実でした。不完全な統計によると、宋仁宗以降の北宋の年間税収の半分以上は軍隊の維持に使われた。官吏や王族貴族の維持、遼や西夏からの年間貢物などを考慮すると、中期から後期にかけての北宋の財政収入は前王朝の数倍にもなったが、それでも収入よりも支出の方が多かった。 「三つの過剰」問題を解決するために、北宋の統治者は巨額の財政支出を下層農民に転嫁し、彼らの負担を増大させなければならなかった。 五代から北宋に受け継がれた賦役制度は、火に油を注ぐ副作用があった(宋代の賦役制度については多くの内容があるので、ここでは詳しく紹介しない)。 『宋會要録』には、「徴税はしばしば間に合わず、民の負債は決して返済されない。洪水や干ばつがないにもかかわらず、依然として多くの人が借地から逃げ出し、他の場所へと流れて行く」と記されている。北宋代には、天候に恵まれた年でさえ、重税と税金のために多くの農民が破産し、難民となった。宋王朝の319年間に、歴史書に記録されている農民反乱は430回以上あり、平均して年に1~2回発生しました。しかし、宋王朝の特別な徴兵制度と大量の軍隊により、農民反乱の規模は他の王朝に比べてはるかに小さいものでした。 歴史の記録を注意深く調べると、北宋時代のいわゆる経済的、文化的繁栄は、実際には文人階級と工業・商業階級に限られており、また少数の大都市に限られていたことがわかります。農民への負担は増え続け、官僚機構は巨大で肥大化し、兵士は老弱者ばかりだったため、行政効率は低下し、軍事戦闘力も低下した。その結果、歴史家は宋王朝を「貧しく弱い」王朝と評するようになった。 宋人宗の「清里新政策」、宋神宗の「西寧改革」、そして「元豊改革」はいずれもこうした矛盾を変えようとしたが、さまざまな理由から例外なく失敗に終わった。しかし、北宋には勇気と決断力のある君主が常に欠けていた。学者と官僚の共同統治は官僚貴族の強い反対に遭い、改革は進められず、富国強兵の目標は夢物語となった。 |
<<: 張飛の武器は張八蛇槍と呼ばれていますが、張八蛇槍はどのように作られたのでしょうか?
>>: なぜ六つの国は商閻の改革に従わず、自らを強くしなかったのでしょうか?
推薦する
崔昊の詩「華陰を旅する」は荘厳で意味深い。
崔昊は唐代の詩人、官吏で、唐代の最高貴族「崔伯陵」の出身である。初期の詩は女性の愛と生活に関するもの...
文殊菩薩は何を担当しているのでしょうか?文殊菩薩像の意味は何ですか?
文殊菩薩は何をなさるのでしょうか?文殊菩薩の像にはどんな意味があるのでしょうか?ご興味がありましたら...
古典文学の傑作『太平記毓覧』:礼部第4巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
薛潘は賈宝玉を陥れたのか?賈宝玉を殴らせたのは薛潘だったのか?
賈宝玉が殴られたことに関しては、それにつながる手がかりが2つあることは明らかです。一つは金川の死です...
南宋時代の小説や詩の特徴は何ですか?小説や詩の代表的な作品は何ですか?
南宋時代の文学は小説や詩評においてより顕著である。なぜなら、小説や詩評は比較的政治色が少なく、読者層...
年功序列の観点から、秦忠とその妹の秦克清はどのような道を歩んだのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
水滸伝で銃撃戦が起こったら、誰が宋江を助けるのでしょうか?彼は命を救うことができるでしょうか?
わが国の四大傑作の一つである『水滸伝』は、国内外で有名です。今日は、Interesting Hist...
李白の古詩「呂正君の兄弟に贈る」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「呂正君の兄弟に贈る」時代: 唐代著者: 李白賢明な君主は徳の高い人々や優雅な人々を訪ねました...
「金塔記後」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
黄金の塔の後李嶽(五代)梁の元帝は言った。「王仲玄はかつて荊州にいて、数十冊の本を著した。荊州が滅ぼ...
宋江が裁判所の恩赦を受け入れなかったらどうなるでしょうか?皇帝は彼を攻撃するために軍隊を派遣し続けるのでしょうか?
宋江は、雅号を公明といい、わが国の四大名作の一つである『水滸伝』の最も代表的な人物である。彼は危機の...
『紅楼夢』で、薛宝才はなぜ金伝児が亡くなった直後に王夫人を探しに行ったのですか?
薛宝柴は『紅楼夢』のヒロインの一人であり、金陵十二美女の一人です。興味のある読者とInteresti...
『紅楼夢』の林黛玉はなぜ賈玉村を尊敬しているのでしょうか?理由は何でしょう
林黛玉は中国の古典小説『紅楼夢』のヒロインです。次回は、Interesting History編集長...
『三朝北孟慧編』第143巻の主な内容は何ですか?
燕行第二巻の第43巻。それは建炎庚武4年10月1日に始まり、義維12月27日に終わった。六つの宮殿は...
塩と鉄の論争:漢昭帝時代の中国初のマクロ経済統制
塩鉄論争は、漢の昭帝の治世中に、官営の塩と鉄の問題をめぐって中央政府が行った国家政策に関する論争であ...
『紅楼夢』における黛玉の死と北京太子との関係は何ですか?
『紅楼夢』のヒロインである黛玉は、金陵十二美女本編の最初の二人の登場人物の一人です。まだ彼女を知らな...