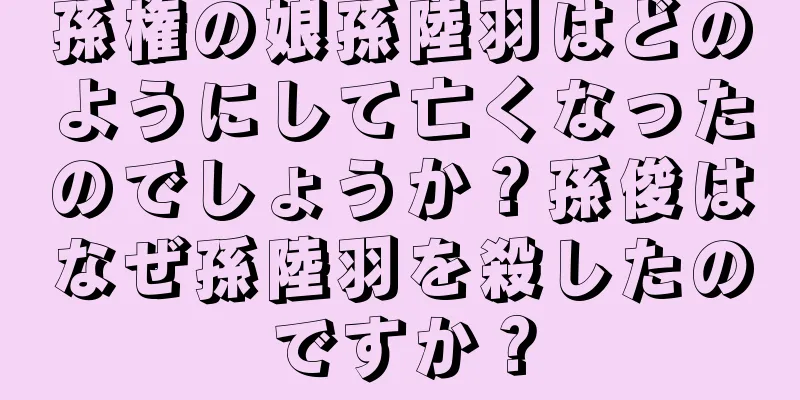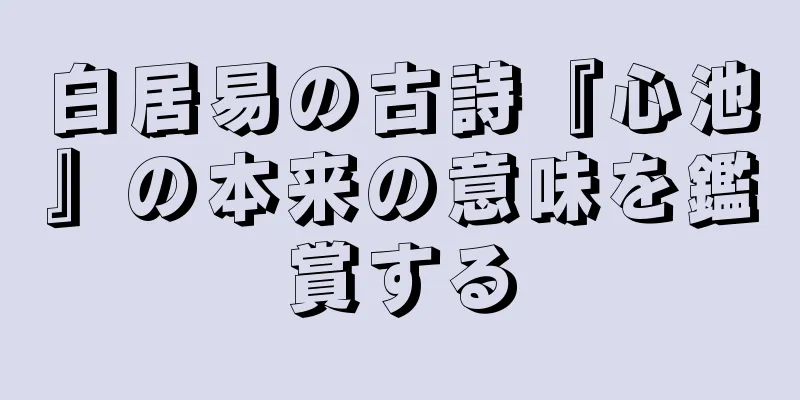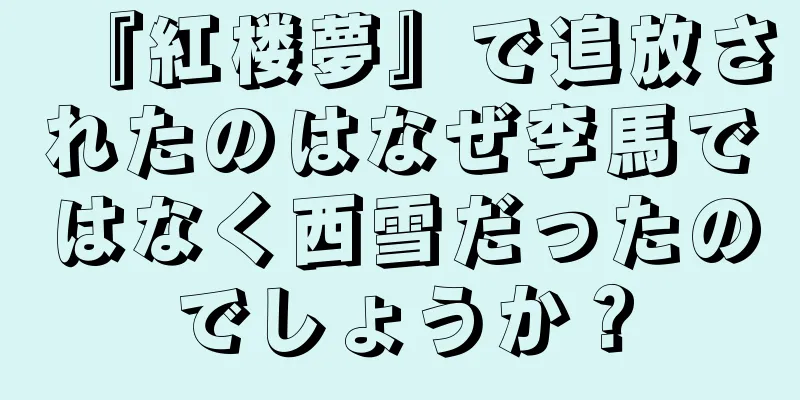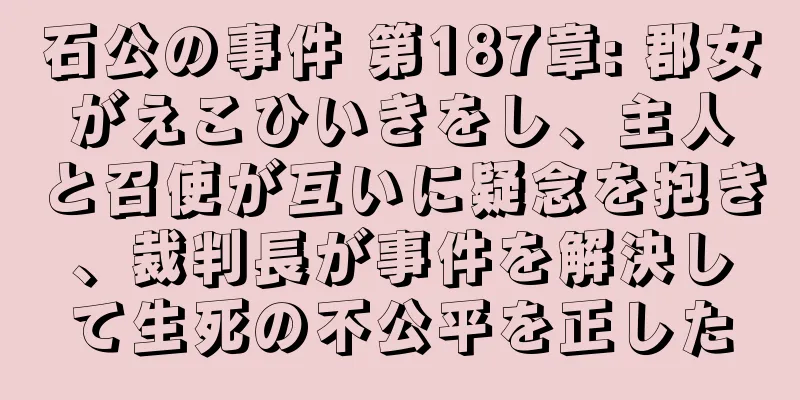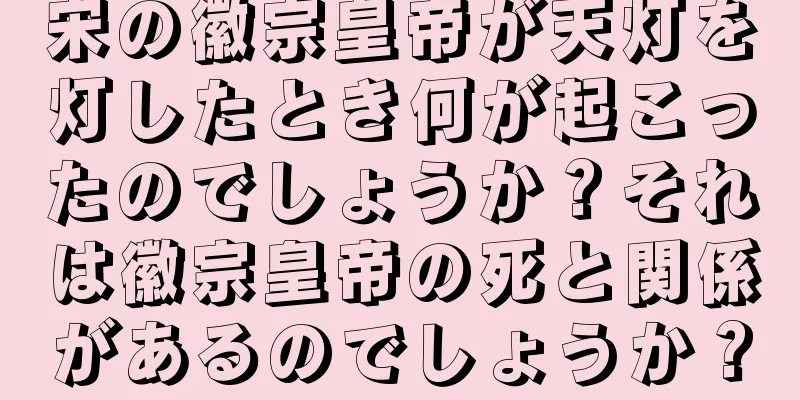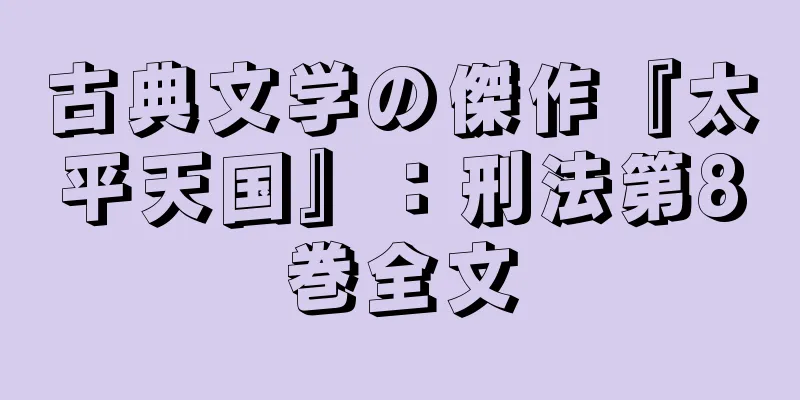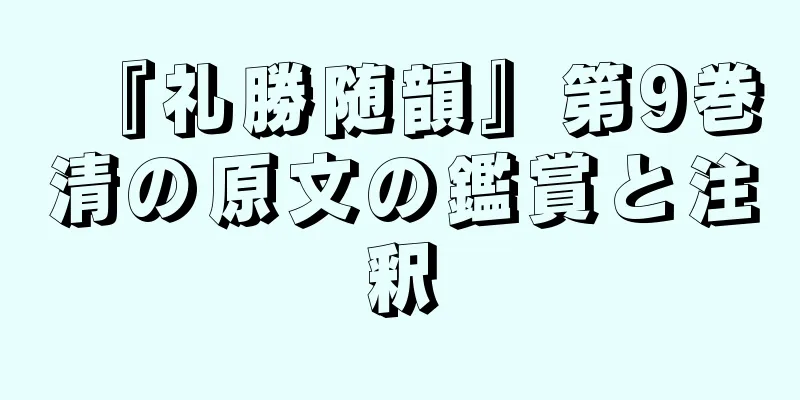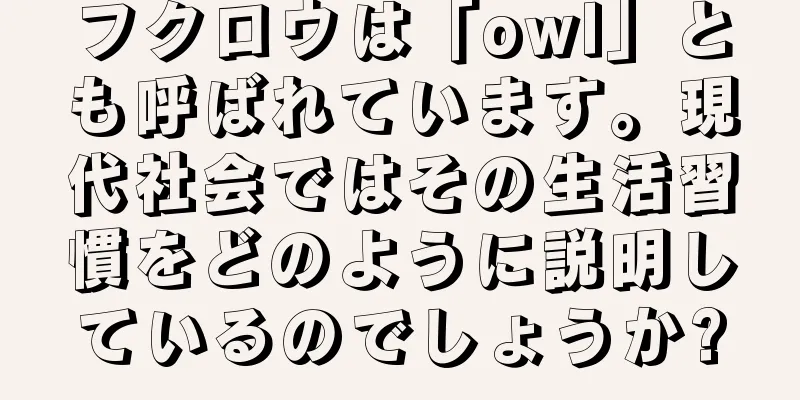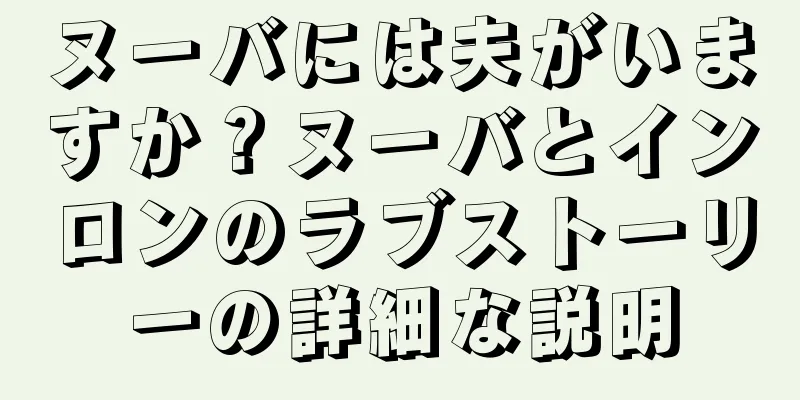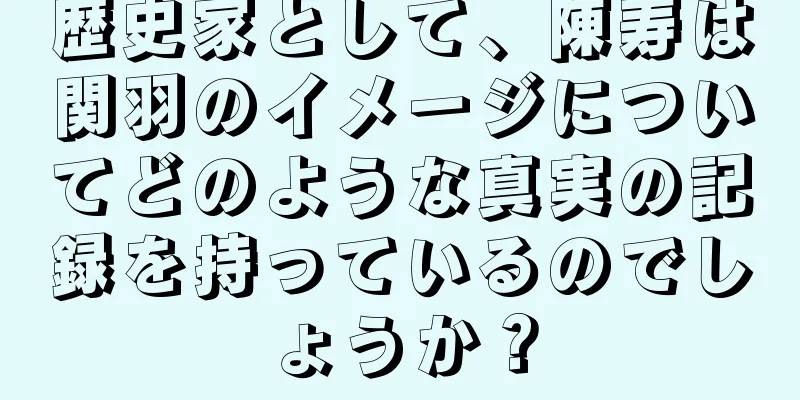清朝の皇帝は毎日朝廷を開いていたのですか?早朝の法廷を欠席しても大丈夫ですか?
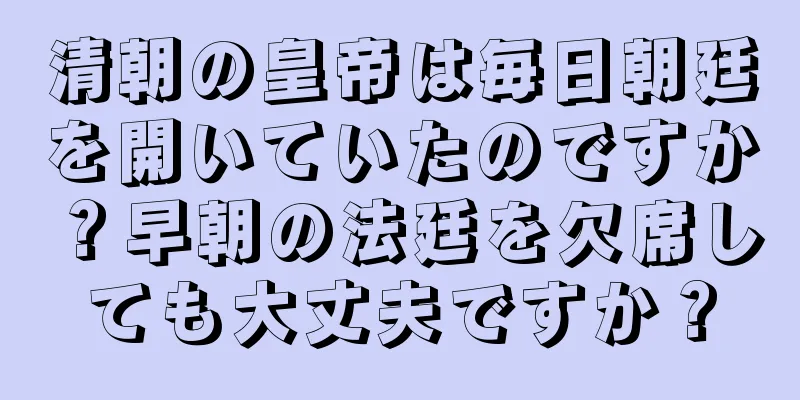
|
「皇帝が到着し、大臣たちは早朝から皇帝の言葉を聴くために集まっています」や「陳情書をお持ちの方は前にお進みください。お持ちでない方は宮廷から退出してください」は、清朝時代の映画やテレビ番組でよく見られるセリフです。清朝の皇帝は毎日宮廷に出席しなければならなかったと多くの人が考えています。実はそうではありません。次の興味深い歴史編集者が詳細を紹介します。ぜひ読んでみてください〜 皇帝が朝廷に出席するのは当然のことである。これはどの王朝の皇帝にも当てはまり、清朝も例外ではなかった。しかし、これは清朝の皇帝が毎日朝廷に出席しなければならなかったという意味ではありません。皇帝は夜明け前に起き、宦官の指導の下で龍の玉座に座り、文武の役人から三跪き九叩頭の儀式を受けました。 読者の皆さんに責任を持って申し上げますが、清朝の「初期の朝廷」制度については、公式の歴史資料には記録がありません。これは、清朝の政治体制の運営と無関係ではありません。軍事上および国家上の重要な事柄はすべて常に秘密にされており、法廷で公に取り上げられたり助言されたりすることは決してなかった。 清朝には決まった朝廷はなく、太和殿で開かれることもなかった。もしあるとすれば、朝廷の審問は多少似ていますが、場所は大和殿ではありません。大和殿は国内最高位の建物です。皇帝は即位、即位後、結婚、誕生日、元旦などの重要な機会にのみ大和殿に座り、大臣からの祝辞を受け取ります。ここで話題になっているのは朝のお祝いであることに注意してください。 では、清朝の皇帝はどこで政務を執ったのでしょうか。実は、それは決まっていませんでした。例えば、順治元年、紫禁城の三つの主殿が焼失し、ドルゴンが摂政になりました。彼の執務室と審問所は武英殿に設置されました。順治が権力を握った後、彼は3つの主要な殿堂を修復し、乾清宮に住み、そこでほとんどの国事を処理しました。 清朝には夜明け前に全官吏を召集して警備に当たらせる制度はなかった。清朝初期には六つの省が処理すべき事柄は内閣に集約され、内閣は皇帝に報告した。例えば、康熙帝が初めて帝位に就いたとき、彼はまだ8歳でした。当時の彼の主な仕事は学校に通うことであり、政務は4人の大臣によって行われていました。康熙帝が政務を担当していたときでさえ、それは放課後、昼食前でした。 康熙帝が権力を握った後、「皇門の後ろで朝廷を開く」という慣例を実施しました。一般的に、冬と夏は午前6時に、春と秋は午前5時に行われました。最初は乾清門で行われ、後に太和門に変更されました。康熙帝は仕事に非常に熱心で、治世中、北京にいるときは必ず朝廷の会議を欠席した。例えば、三藩の鎮圧、台湾の回復、帝政ロシアとの戦いなど、重要な決定はすべて朝廷の会議で下された。 しかし、康熙帝以降、皇門で朝廷を開くことを主張できる皇帝は多くなかった。雍正帝と乾隆帝は依然としてそれを維持したが、道光帝以降、皇門で朝廷を開く慣習は基本的に廃止された。 官僚の観点から見ると、清朝に早朝裁判制度を導入する必要は実はなかった。文武両道の役人が一堂に集まる機会は、それほど多くはなく、重要な儀式のときなどに限られ、年間20回を超えることはなかった。したがって、官吏全員参内という発言は、あくまでも象徴的な発言にすぎず、皇帝に直接政務を報告し、協力し合えるのは官吏全員ではなく、ごく少数の者に限られる。 雍正年間、西北の軍事が複雑化したため、外朝と内朝の連絡が不便で機密保持に不便であったため、太政会議が設立されました。太政官は軍事と国家の重要な事柄を担当していたため、太政官は毎朝、修心殿の西側の暖かい亭で皇帝に報告しなければなりませんでした。 緊急事態が発生した場合、皇帝はすべての文武官を朝廷に召集するのではなく、軍務大臣、太守、六省九部の官吏に陽心宮で朝廷会議を開くよう命じました。皇帝の大臣以下の官吏には、このような高官級の会議に参加する資格がなかった。 さらに、もう一つ指摘しなければならない点があります。清朝は万里の長城の外で誕生したため、万里の長城内の気候に適応できなかったようです。そのため、康熙帝の時代から、首都の周囲に多くの王宮庭園が造られました。まず、彼らは、紫禁城は特に夏は居住に適さないと考えていました。第二に、故宮の雰囲気は荘厳で威厳があり、リラックスすることが難しいため、さまざまな王宮庭園で働くのは自然なことです。 例えば、康熙帝は晩年のほとんどを長春園で過ごしましたが、その後継者である雍正帝や乾隆帝は主に円明園で活動しました。役人にこれほど遠く離れた裁判所まで出向くよう求めるのは空想に過ぎないことは想像に難くない。 実は、雍正帝以来、皇帝は早朝に朝廷を開くことはなくなりました。ここで言う朝廷とは、武臣たちを修心殿に召集することを意味しています。役人は基本的に宮殿の外にある6つの省庁で働いていました。大きな出来事があったときは、まず大政奉還に報告し、大政奉還は事の重大性に応じて皇帝の裁決を求める時期を決めました。一般的に言えば、大抵のことは大会議で処理できるので、皇帝が対処しなければならない大きな問題はそれほど多くありません。 清朝の皇帝には朝廷に出席する制度がなかったのに、なぜ歴代王朝の中で最も勤勉だったと言われるのでしょうか。実際、清朝の皇帝は皇帝の追悼行事に多くの時間を費やしていました。追悼式は清朝独特の制度で、簡単に言えば、その本質は皇帝と大臣の間の私的なコミュニケーションです。 追悼文の内容は、挨拶、感謝、仕事の報告、さらには民俗習慣や人間関係などでもよい。もちろん、最も重要なのは大臣同士が互いに報告し合うこと、つまり内外の大臣が互いに監視し、暴露し合うことである。 追悼制度は比較的良い方法であると言える。明代の金一衛や東昌ほど不気味で恐ろしいものではなく、抑止力としても優れている。清朝の皇帝は、ほとんどの時間を記念碑の視察に費やしました。たとえば、13年間統治した雍正帝は、ほぼ毎日夜遅くまで記念碑の視察をしました。乾隆帝も同様でした。 そのため、一見非常に合理的であるように見える早朝の法廷開廷という現象は、清朝において固定した制度を形成することはなかった。夜明け前に起きて馬車や輿に乗って法廷に赴かなければならなかった官吏は、ほとんどが朝廷の重要な官吏であり、一般の官吏にはこの資格がなかった。 |
<<: 明代の通宝貨幣は何種類ありますか?明代における通宝の発展史の詳細な説明
>>: 清朝時代のシルクハットと羽飾りの見分け方は?清朝のシルクハットと羽根飾りの詳しい説明
推薦する
『紅楼夢』では、賈夫人は林黛玉を気に入っていたのに、なぜ褒美として何も与えなかったのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
『晩秋の曲江一人旅』の制作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
晩秋の曲江一人旅李尚閔(唐代)春の憎しみは蓮の葉が成長すると生じ、秋の憎しみは蓮の葉が枯れると生じま...
宋代の詩「鄂州南楼書道物語」を鑑賞して、黄庭堅は詩の中でどのような感情を表現したのでしょうか?
鄂州南楼書史、宋代の黄庭堅、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみましょう...
壮族の食べ物:壮族の日常の食べ物や祭りの食べ物の特徴は何ですか?
チワン族は中国の少数民族の中で最も人口が多く、主に広西チワン族自治区と雲南省に居住しており、その大部...
曹丕は馮曦をとても尊敬していたのに、なぜ曹丕は馮曦を墨北に派遣して過去を思い出させたのでしょうか?
三国時代の使者といえば誰を思い浮かべますか?おそらく、この馮熙、雅号が子柔であった人物を挙げる人は少...
斉の宰相である顔子は何で有名でしたか?ヤン・ジが国を治める物語
かつて斉の宰相を務めた、春秋時代の有名な政治家、思想家、外交官である「顔子」は、斉の政治に一生を捧げ...
人々は楊堅に驚き、なぜ彼が最も偉大な皇帝の一人なのか疑問に思うかもしれません。
もちろん、世界で最も古い国の一つである中国にも、歴史上の人物が二人います。彼らは皆古代中国の皇帝であ...
『紅楼夢』で劉おばあさんが大観園を訪れたとき、なぜ転んだのですか?その背後にある意味は何でしょうか?
劉おばあさんは、中国の古典文学作品『紅楼夢』の登場人物です。興味のある読者と『Interesting...
皇帝の物語:宋の高宗皇帝はなぜ岳飛の金朝に対する北伐を支持しなかったのか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...
蘇軾の『西江月梅花図』:趙雲への深い愛と限りない憧れが込められている
蘇軾は北宋中期の文壇のリーダーであり、詩、作詞、散文、書道、絵画などで大きな業績を残した。彼の文章は...
『紅楼夢』で李婉は妙豫に対する不満をどのように表現したのでしょうか?
李婉は金陵十二美女の一人で、栄果屋敷の長男である賈珠の妻です。今日は、Interesting His...
最後の皇帝溥儀には何人の弟がいましたか?溥儀の弟の簡単な紹介
溥儀、フルネームは愛新覚羅溥儀、雅号は姚之、号は昊然(こうらん)としても知られる。清朝最後の皇帝であ...
近代美術の創始者ピカソはどんな画家だったのでしょうか?
ピカソの作品は比較的抽象的だと多くの人が考えており、そのためピカソの作品を理解できない人が多くいます...
諸葛亮はなぜ死ぬ前にできるだけ早く誰かを派遣して魏延を排除しなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
オロチョン族の民俗切り絵 オロチョン族の芸術と文化
オロチョン族の切り紙アドンの切り紙:オロチョン族が馬に乗って狩りをする場面(オロチョン族の切り紙芸術...