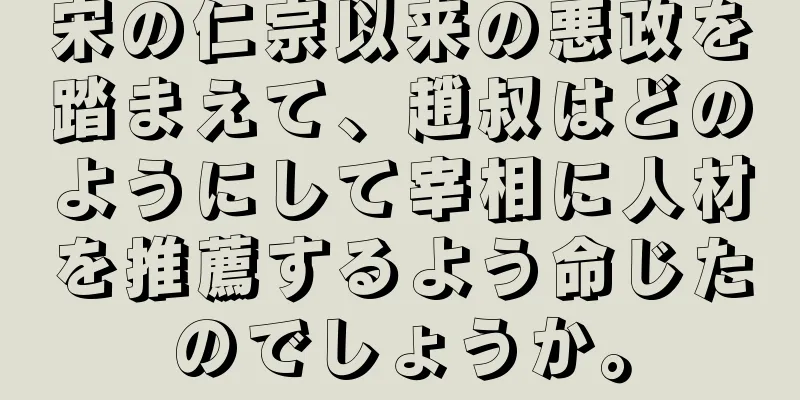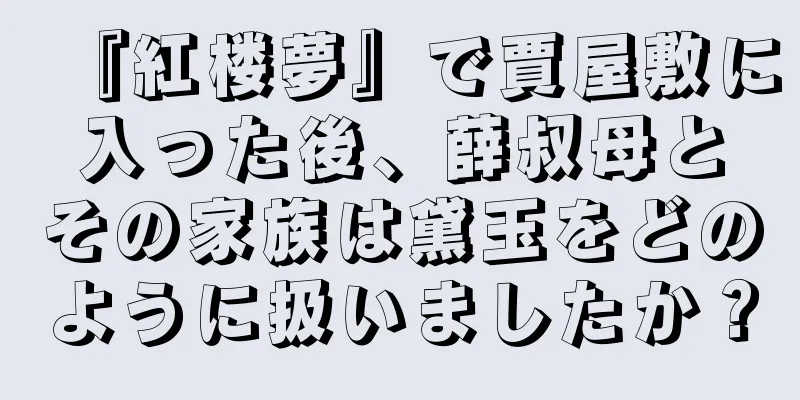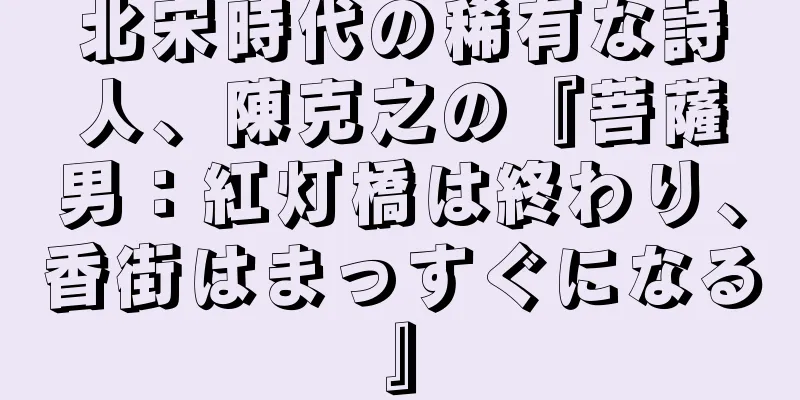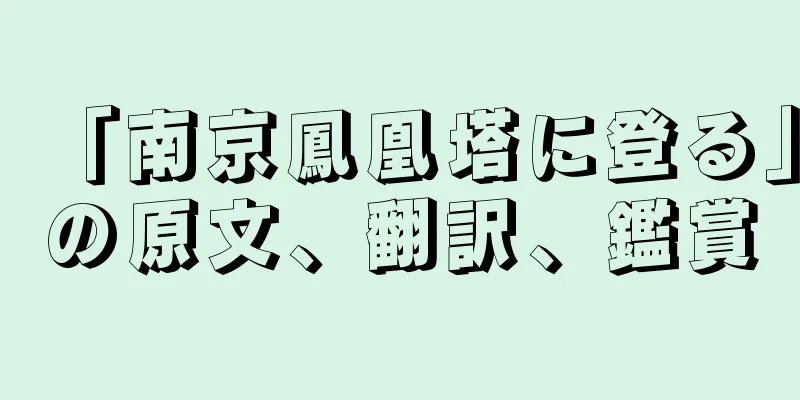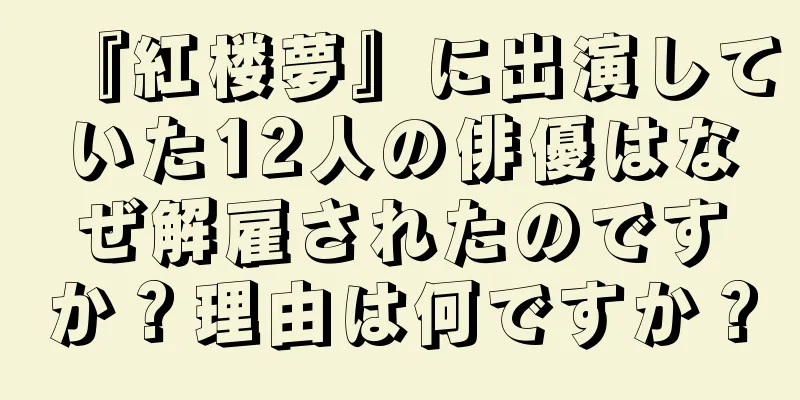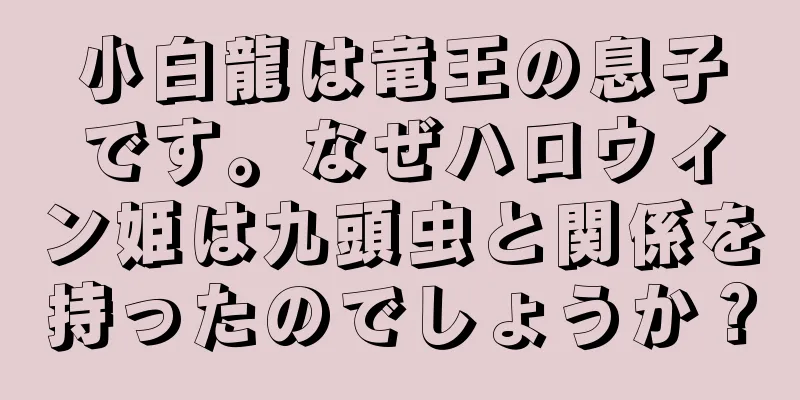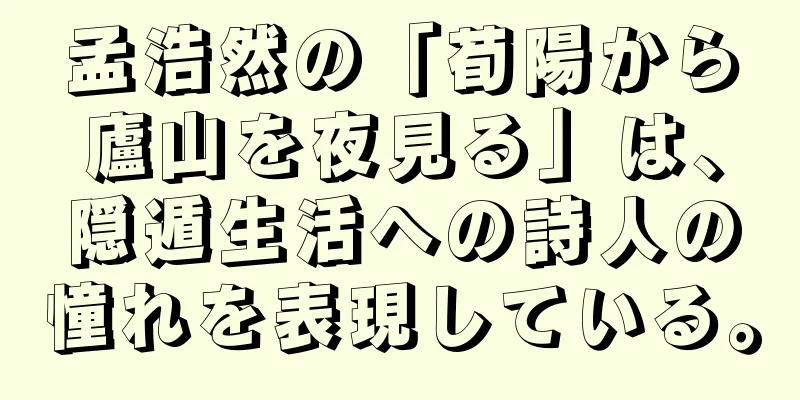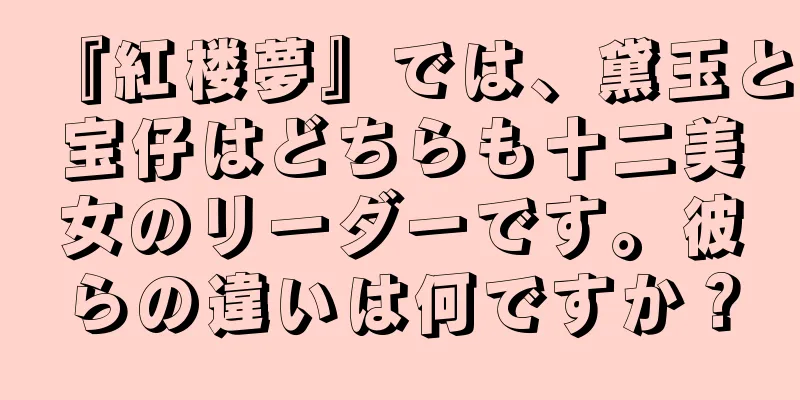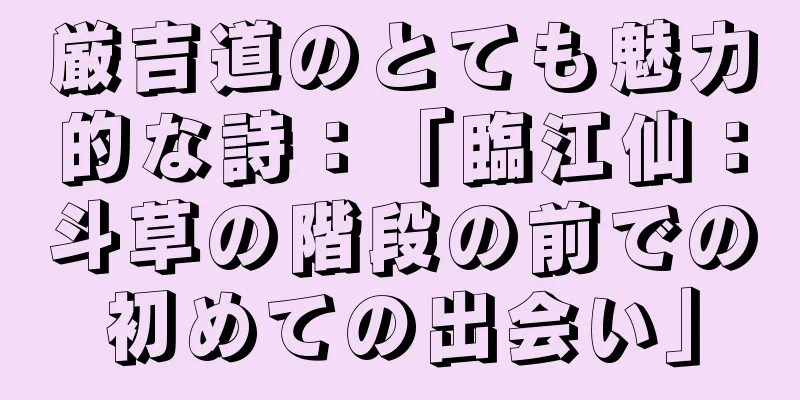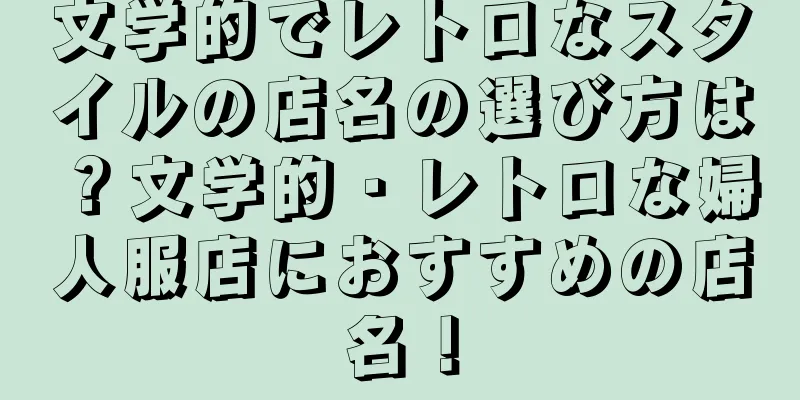もし袁紹が早死にしていなかったら、彼は形勢を逆転させて曹操を倒すことができただろうか?
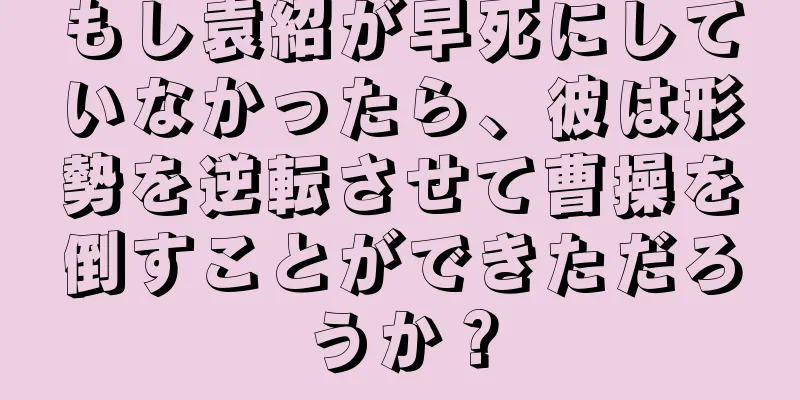
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、官渡の戦いの後、袁紹にまだ形勢逆転のチャンスがあるのかどうかについて詳しく紹介します。見てみましょう! 東漢末期、袁紹は天下最強の武将であり、曹操も弟に等しかったため、当時の多くの人々は袁紹が天下を統一する可能性が高いと信じていました。しかし、官渡の戦いで優勢だった袁紹が曹操に敗れ、衝撃を受けました。2年後、袁紹が突然亡くなり、曹操に大きなチャンスが訪れました。結局、曹操は袁紹一派を破り、北を統一し、天下最強の王子、天下統一の最大の希望を持つ王子になりました!そこで疑問なのは、官渡の戦いの後、袁紹には形勢を逆転させるチャンスがなかったのか?もし袁紹が早死にしていなかったら、形勢を逆転させて曹操を倒すことができただろうか? 官渡の戦いは、小規模な勢力が大規模な勢力を破った歴史上の典型的な例です。袁紹と曹操はともに4つの国を占領していましたが、曹操が占領した国は戦争の洗礼を受け、その力は長い間弱まっていました。一方、袁紹が占領した4つの国は常に比較的平和を保っており、総合的な力は非常に強固でした。そのため、表面上は曹操と袁紹の領土の大きさは似ていたものの、実際には袁紹の総合力は曹操よりはるかに強かったのです。袁紹の部下が曹操との長期戦を勧めたとき、袁紹はそれを拒否しました。総合力は曹操より強かったからです。曹操が発展するのをぐずぐず待っていたら、曹操に対して大きな優位性を維持できないかもしれません。 実際、官渡の戦いの初期から中期にかけて、すべては袁紹の予想通りでした。曹操軍は非常に強力でしたが、袁紹軍も弱くはありませんでした。両者は激しく戦い、どちらも相手を倒すことができず、綱引きをするしかありませんでした。このとき、「戦争は国力で戦う」という言葉の意味が浮き彫りになりました。袁紹は総合力が強く、後方補給能力も強かったため、遅れる余裕がありましたが、曹操は総合力が弱く、後方補給能力も弱かったため、遅れる余裕はなく、荀彧に直接手紙を書いて撤退の意向を伝えました。 『三国志演義』:5年目に邵と戦い続けた。太祖は官渡を守り、邵はそれを包囲した。太祖の軍隊は食糧が不足していたので、太祖は于に手紙を書き、易が徐に戻って紹介したいと伝えた。 曹操の考えに荀攸は冷や汗をかくほど怖がった。曹操が撤退すれば軍の士気は完全に崩れ、曹操軍は援軍を阻止できなくなり、曹操は完全に敗北するだろうからである。そこで荀攸はすぐに曹操に手紙を書いて、もう少し待つように頼んだ。荀攸は兵站補給問題の解決に全力を尽くすつもりだ!結局、荀攸の説得により、曹操は撤退計画を断念し、袁紹との持久戦を主張した。曹操が粘り強く主張すると、袁紹の抜け穴を本当に見つけたのである! 袁紹の抜け穴は武巣穀倉だった!袁紹が曹操を圧倒して優位に立つことができたのは、兵站補給が非常に強力だったからであり、武巣穀倉は袁紹最大の補給倉庫だった。曹操はこの穀倉の場所を一度も見つけられなかった。曹操が心配していたとき、許攸が降参し、武巣穀倉の具体的な場所を教えてくれた! 徐有はもともと袁紹の傘下のトップ戦略家だったが、家族が金に貪欲だったため、沈佩に逮捕された。徐有の家族の行動は徐有の共謀によって引き起こされた。徐有自身もこれらのことに関与していたとさえ言えるので、家族の逮捕の知らせは彼を怖がらせた! 徐有は、勝利後に袁紹が自分に対処することを心配し、曹操に降伏することを選んだ。曹操が袁紹を倒すのを手伝えば、徐有は袁紹に罰せられないだけでなく、曹操から功績を得られるかもしれない! このように、徐有は袁紹を裏切り、曹操を率いて武巣の穀倉を攻撃し、袁紹に致命的な打撃を与えた! それ以来、袁紹の敗北は運命づけられていた! 官渡の戦いで、袁紹は大きな損失を被りましたが、倒れませんでした!当時、袁紹の後方では、彼が戦いで死んだと信じていた人が多く、人々の心は不安定でした。多くの人が反乱を起こし、領土を分割する機会を狙っていました。その結果、袁紹が戻った後、反乱を鎮圧し、再び足場を取り戻しました!袁紹は、官渡の戦いで敗北した主な理由は、徐游が敵に降伏し、曹操を率いて武巣の穀倉を焼き払ったためであると信じていました。この戦いは彼のせいではないので、彼は再び大軍を集め、曹操と再び戦い、誰がより強いかを確認する準備をしました。 蒼亭の戦いで袁紹は再び大敗を喫し、曹操との差を痛感したため、二度と曹操を攻撃することはなかった。その後間もなく、袁紹は病死しました。彼の死後、彼の息子たちは権力をめぐって争い始めましたが、結局曹操に次々と敗れました。建安12年(207年)、曹操は北方を完全に統一しました。 官渡の戦いの後、袁紹は完全に敗北を認めていなかったことがわかります。彼はまだかなりの力を持っており、少なくとも曹操に劣っていませんでした。曹操が官渡での勝利を利用して袁紹を攻撃し続けなかったのは、このためです!率直に言えば、官渡の戦いの失敗は袁紹の攻撃能力を失わせただけで、袁紹にはまだ十分な自己防衛能力があり、曹操は袁紹のグループを完全に打ち負かすことができませんでした! この時点で意見の相違が生じました。袁紹は敗北したが、まだ力は残っていたと考える人もいました。もし彼が早死にしていなかったら、力を蓄え、形勢を逆転させて曹操を倒せたかもしれないと考えました。袁紹は曹操を倒すチャンスを完全に失ったと考える者もいる。たとえ彼がまだ生きていたとしても、ただ生き延びているだけであり、彼の一族が形勢を逆転させて再び曹操を倒すことは不可能だ。では、この 2 つの記述のうちどちらが正しいのでしょうか? 実はこの記事は、2番目の主張、つまり袁紹が形勢を逆転させるチャンスは決してない、という主張を支持している。その理由は非常に単純だ。袁紹のグループは強力だが、その内部構造は一枚岩ではない。袁紹のグループには多くの派閥があると言っても過言ではない。まさにこの理由から、たとえ袁紹が非常に良い決断をしたとしても、それを効果的に実行することは不可能です。なぜなら、グループ内に派閥や制約が多すぎて、まったく意見が一致しないからです。この問題については、荀攸と郭嘉が実際に説明をしています。 荀彧は曹操配下で最も有力な軍師であると言えますが、実は荀彧は当初袁紹に従っており、袁紹は荀彧を非常に重視し、賓客として扱っていました。しかし荀攸は、袁紹陣営には派閥が多すぎて、利害関係が広すぎて、自分の才能を発揮できないと考えました。そこで荀攸は袁紹を断固として見捨て、曹操に従うことを選択しました。当時、曹操は曹一族のほぼ全員に囲まれており、派閥も複雑ではありませんでした。 曹操と袁紹はもともと友人であり、天下の君主たちと争う過程で、両者はしばしば同じ戦線に立っていたため、両者の関係は依然として良好であった。しかし、それらの小君主が排除されると、曹操と袁紹の競争も始まりました。 当時、曹操陣営の人々は袁紹に背くことに同意しませんでした。彼らは以前に何度も協力していたし、袁紹は確かに強く、曹操よりもはるかに強かったので、誰もが少し恐れていました。 誰もが躊躇していたとき、荀攸が立ち上がって話しました! 『三国志』: 虞は言った。「邵は兵が多いが、法は整っていない。田鋒は反抗的で反逆的、許有は貪欲で乱暴。沈佩は権威主義的だが戦略がなく、馮季は毅然として独善的。この二人は将来を知るために残しておくべきだ。有一族が法を犯したなら、見逃してはならない。見逃さなければ、有は必ず改心するだろう。顔良と文周は勇敢な男で、一戦で捕らえられるだろう。」 荀攸は袁紹の配下の人材を一人ずつ評論し、袁紹のグループはそれほど強くなく、曹操は彼を完全に打ち負かすことができると皆に信じ込ませた! この評論の最終的な目的は、実は袁紹のグループは多くの派閥があり、強力な共同軍を形成できないと言うことだった! 田鋒、許攸、沈佩、馮冀は才能があるが、彼らは異なる利益陣営に属しており、一緒に働いて良い仕事をすることは不可能である。 その後の官渡の戦いの状況もこの問題を物語っている! 徐有が前線で袁紹のために懸命に働いている間、彼の家族は沈沛に捕らえられた。これが有能な顧問のすべきことだろうか?沈沛が本当に袁紹のことを気にかけているなら、官渡の戦いに勝利するまで徐有の家族を捕らえるのを待つことができたはずだ。なぜ彼は重要な局面でこのようなことをしたのか?これは明らかに自分の利益のためであり、袁紹の利益を無視して徐有を罠にかけたのだ! 袁紹の死後、袁紹陣営の崩壊は、荀攸の見解を再び証明した。袁紹のグループは強力に見えたが、多くの派閥があり、共同軍を結成することはできなかった。袁紹には形勢を逆転させて曹操を倒すチャンスはなかったのだ! 郭嘉はもともと袁紹の顧問だったが、袁紹陣営の欠点を見て、袁紹もこれを変えることができなかったため、袁紹を離れ、最終的に曹操に加わった!建安2年(197年)、曹操は張秀に敗れ、袁紹は手紙を書いて彼を辱めた。曹操は非常に怒っていたが、自分の実力が袁紹に及ばないことを心配していたため、郭嘉は有名な「十勝十敗」理論を提唱した! 「十勝十敗」理論については詳細が多すぎるため、ここでは詳しく説明しません。興味のある友人は自分で調べてください。しかし、その最終的な目的は、実際には荀攸の見解と非常に似ています。つまり、袁紹のグループには制約が多すぎて派閥が多すぎるため、関係する事柄が多すぎてすべての関係者の利益を考慮しなければならないため、袁紹は優柔不断になります。曹操側では、袁紹の構造と比較して、はるかにクリーンで、利益団体が多すぎず、実行が強力であるため、曹操は間違いなく袁紹を倒すことができます。 実際、その後の出来事も郭嘉の見解を証明しました。袁紹のグループは強力に見えましたが、民衆は団結しておらず、混乱していたため、袁紹には形勢を逆転させて曹操を倒すチャンスがありませんでした。 |
<<: 電気がなかった古代、人々は暗くなってから何をしていたのでしょうか?
>>: 中華民国の子供の日は4月4日です。馬頭ブランドのアイスキャンディーは最高の贈り物です。
推薦する
明王朝とはどのような王朝でしたか?明王朝はなぜ歴史上最も暗い時代だったのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、明王朝とはどのような王朝であったかをお伝え...
歴史上、鍾会はなぜ許褚の息子を殺したのでしょうか?何のお祭りがあるんですか?
古代には多くの有名人がいましたが、その中には物議を醸す人もいました。その中でも許褚はさまざまな人生を...
『南歌子 散雨後池で会おう』の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
南歌子:雨の池で会いましょう何朱(宋代)池には小雨が降り、衿や袖にはそよ風が感じられます。夏の木陰で...
宋代の詩『清平楽』の鑑賞。この詩はどのような感情を表現しているのでしょうか。
清平楽·博山王寺に独り泊まる[宋代] 辛其記、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきま...
三国志の歴史の中で袁紹はどのように亡くなったのでしょうか?
袁紹はどのようにして亡くなったのか?袁紹(?-202年)は、号を本初といい、汝南市如陽(現在の河南省...
李白の「古月歌」はどのような感情を反映しているのでしょうか?
詩人李白の「古月歌」にはどんな感情が反映されているか知りたいですか?この詩は、月を食べるヒキガエルを...
「柳への頌歌」をどう理解すればいいのでしょうか?創作の背景は何ですか?
柳への頌歌何志章(唐)翡翠は背の高い木に形作られ、何千もの緑のリボンが垂れ下がっています。誰がこの立...
中国の歴史において、最も大きな貢献を果たした短命の王朝はどれでしょうか?
中国の歴史を語るとき、まず挙げられる王朝は漢、唐、宋です。この3つの王朝は長く続きました。漢は400...
前漢時代の儒学者、光衡の物語の分析と光衡の墓はどこにあるか?
クアン・ヘンの物語中国の歴史に名を残す光衡は、華々しい生涯を送り、数々の名話を残しました。その中でも...
『紅楼夢』の賈家はどれほど栄光に満ち、どれほど荒廃しているのだろうか?
『紅楼夢』に登場する賈家は、百年の歴史を持つ栄華を誇った貴族の家系です。『Interesting H...
南宋時代にはどのようにして紙幣が銅貨に取って代わり、主な交換手段として使われるようになったのでしょうか。
南宋時代には紙幣が大量に流通し、徐々に銅貨に代わって主要な交換手段となった。南宋時代の紙幣は「交子」...
王長齢の詩の有名な詩句を鑑賞する:呉機と楚の王女の岳炎は蓮の船で競い合い、衣服を濡らした
王長陵(698-757)は、名を少伯といい、唐代の官僚であり、有名な辺境の詩人であった。彼は李白、高...
本草綱目・第1巻・順序・臓腑虚過剰の薬方とは具体的にどのような内容ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
『本草綱要』第 8 巻「カルダモン」の元の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
ゾウの起源となる姓はどれですか?ゾウ姓の子孫は誰ですか?
蚩尤が黄帝に敗れた後、山東省西部の蚩姓の部族は伊羅を中心に鄒突と改名し、別の部族は山東省に残ったと伝...