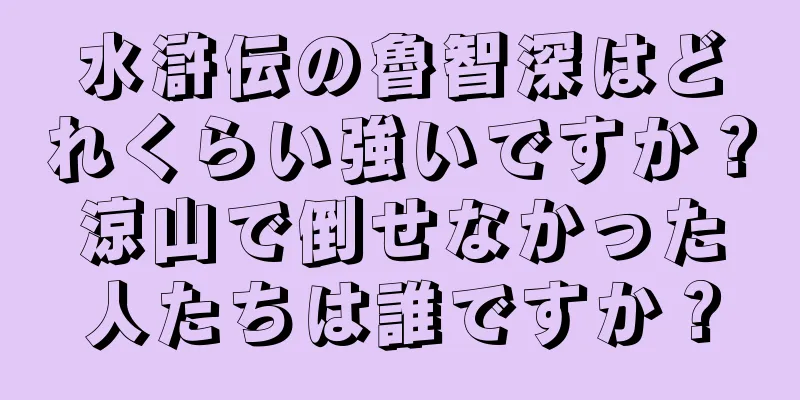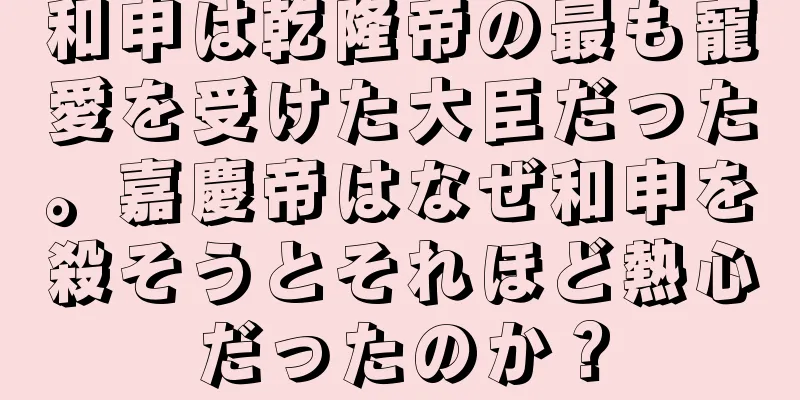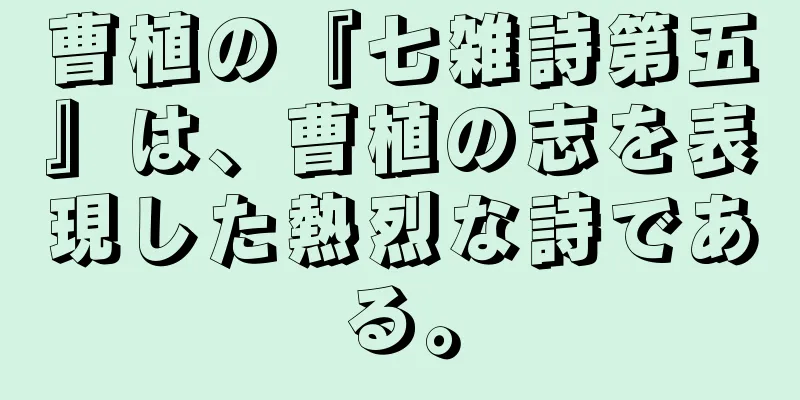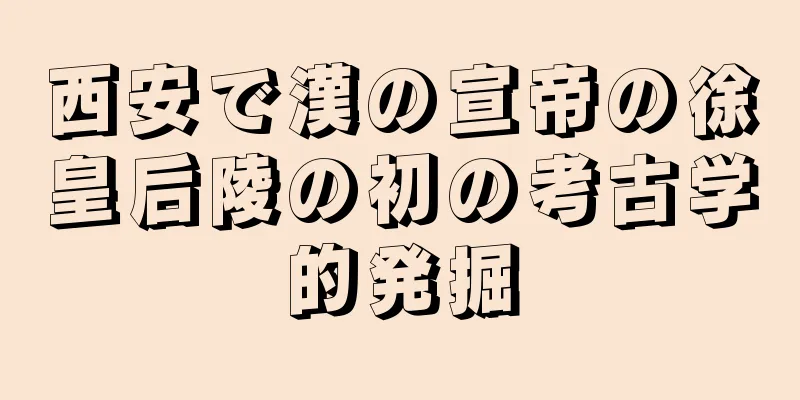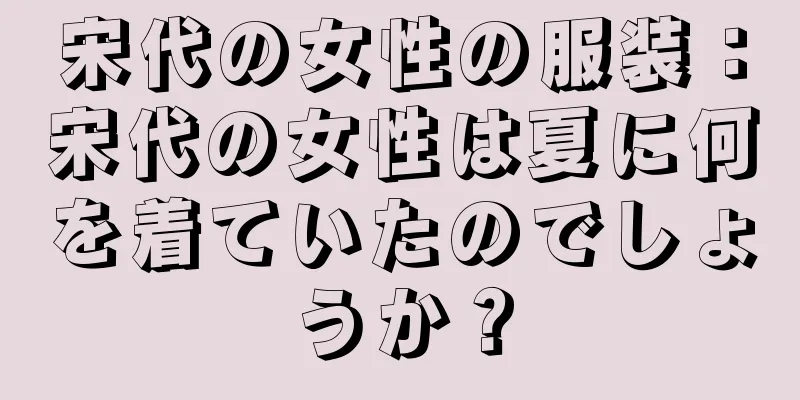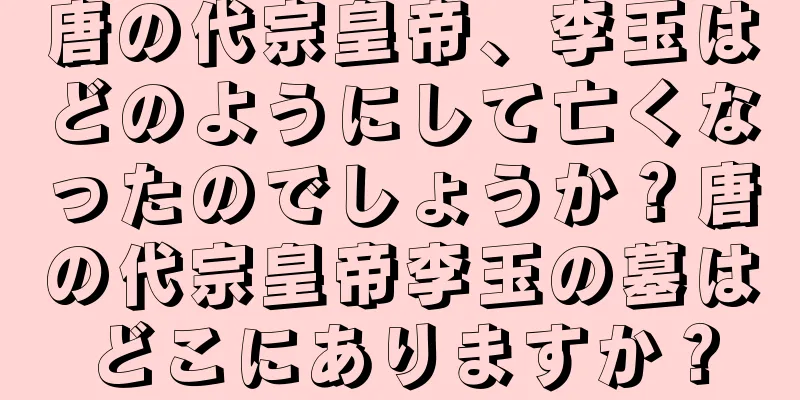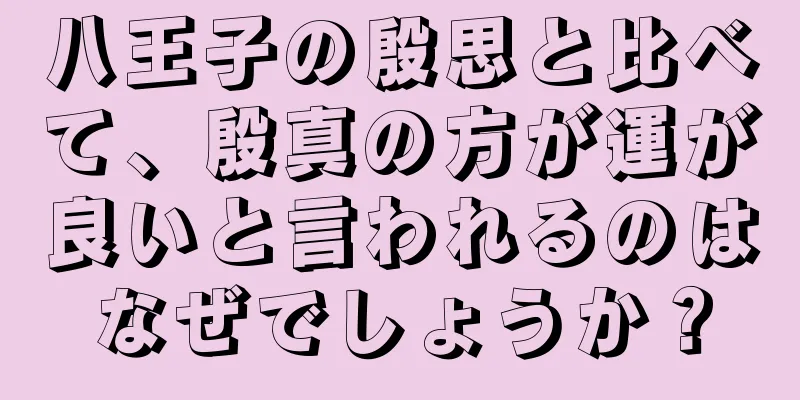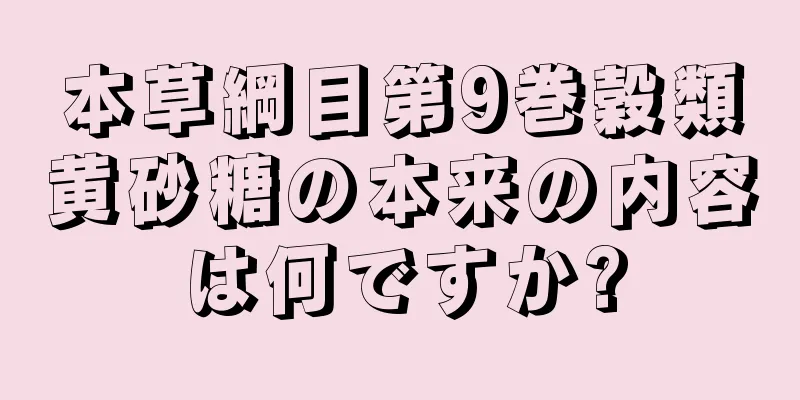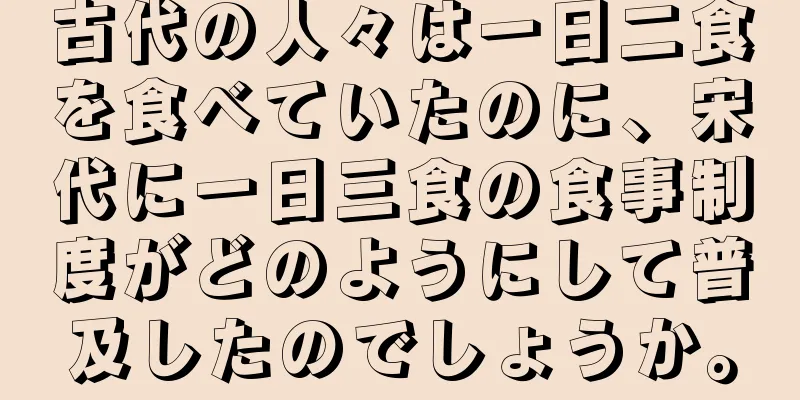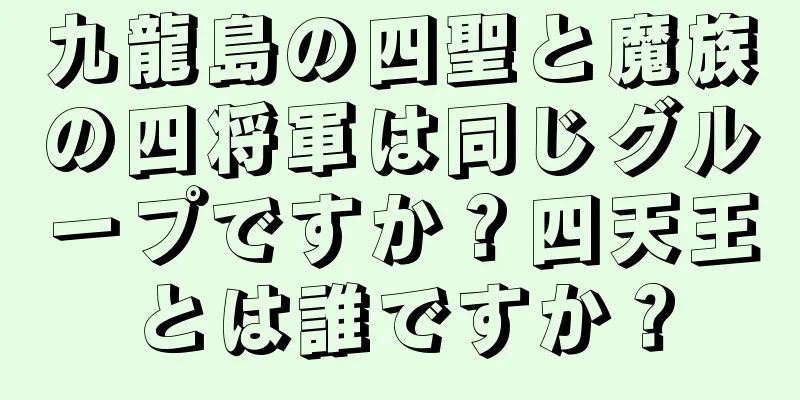日本の囲碁の発展の歴史 中国囲碁と日本の囲碁の違い
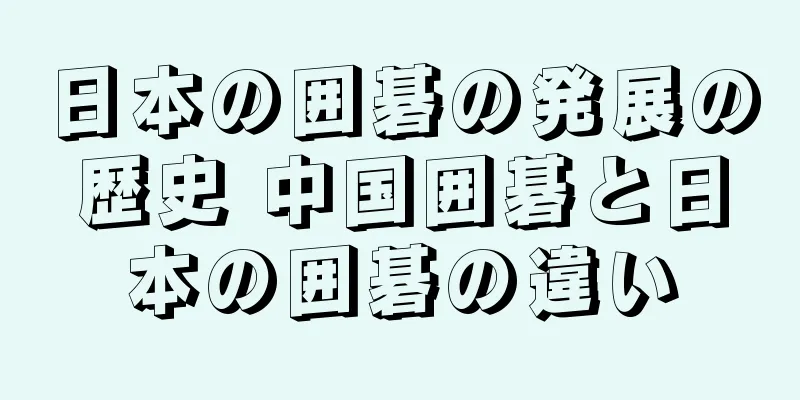
|
囲碁は中国で誕生しました。日本の囲碁も中国から伝わり、さらに発展しました。囲碁はアジアの特産とも言えます。「中国は囲碁の生みの親であり、日本は囲碁の養母である」とさえ言われています。では、日本の囲碁と中国の囲碁の違いは何でしょうか? 日本の囲碁の歴史 日本で初めて導入された 囲碁が日本にいつ伝わったのかについては、いまだに正確な答えはわかっていません。日本の有名な古代学者である吉備真備(694-775)が20年間唐で学んだ後、735年に日本に初めて持ち帰ったという言い伝えが日本人の間で広まっています。しかし、信頼できる歴史記録によれば、天武天皇は685年に大臣たちを宮殿に召集し、直接会談を行ったそうです。 689年に持統天皇が囲碁を禁止し、701年に文武天皇がそれを解除したという記録もある。その後、712年に完成した日本最古の歴史書『古事記』には、「岐志」という文字が地名や人名として使われている例が多く見られます。さらに、718年に公布された「僧尼の命令」には、「賭博を罰し、最も優れた者だけが石で遊ぶ」とも記されていた。これらの記録はすべて、吉備真備が日本に帰国した735年より前のものです。明らかに、「吉備が最初に仏教を伝えた」という説は成り立ちません。上記の日本の記録よりさらに古いものとしては、我が国の正史の一つである『隋・倭国書』(636年に完成)があり、そこには日本人が「将棋、槍、劫符遊びが好きだった」と記されています。これに基づき、上記の日本の資料によって裏付けられると、囲碁は7世紀に日本人に受け入れられたと言えるでしょう。これは比較的安全な記述です。さらに、1980 年版の『大日本百科事典』では、囲碁は早くも西暦 1 世紀から 4 世紀にかけて中国から朝鮮半島を経由して日本に伝わり、大和時代 (西暦 4 世紀から 7 世紀) までには支配階級の間で人気を博していたとされています。しかし、この理論は推測に基づくものであり、確固たる証拠はありません。 囲碁は人気がある 奈良時代(西暦710-794年)までに、囲碁は日本の宮廷で人気を博しました。古代の遺物を収蔵する奈良の正倉院には、聖武天皇(724-948)が使用したチェスのゲームが収蔵されている。日本の歴史書『続日本紀』にも、次のような記録がある。738年、宮中に大伴宿也と連藤登という二人がいて、政務の合間に将棋をしていた。口論の末、宿也が刀で藤登を殺した。注目すべきは、このときすでにプロのチェス選手が登場し、宮殿に出入りしていたことである。 759年に編纂された日本の和歌集『万葉集』には、チェスプレイヤーによる2首の歌が収録されている。 近代以前の中国と日本の囲碁の歴史において、西暦848年に両国の国民的プレイヤーがチェス盤の上で向かい合って座ったという話がありました。 In this regard, the Duyang Miscellaneous Collection, Volume 2, compiled by Su E in the Tang Dynasty, has a wonderful description: "In the middle of the Dazhong period, the prince of Japan came to the court, and the emperor set up a variety of entertainments and delicacies as a courtesy. The prince was good at Go, so the emperor ordered Gu Shiyan to be his opponent. When Shiyan played against him, the winner was still undecided after 33 moves. Shiyan was afraid of humiliating the emperor's order, so he sweated and thought hard before he dared to move his fingers. This is called the head of calming the spirits, which resolved the situation of the two attacks. The prince stared and retracted his arms, and was defeated. He turned back to the Honglu and asked: What move did the waiter make? The Honglu replied slyly: The third move. Shiyan is actually the best player in the country. The prince said: I would like to see the first one. He said: The prince won the first one.第三は第二になることができ、第二を倒すことによってのみ第一になることができます。今、私は第一になりたいと急いでいますが、可能ですか?王子は盤を覆い、ため息をつきました。小さな国の一つは、大きな国の3つに及ばない、それは本当です。今日でも、それに興味を持っている人の中には、顧世巌の三十三鎮神頭図があります。「一部の日本の囲碁歴史家は、「囲碁の優れた国」であるという意識のために、この記述を認めたがりませんが、「旧唐書・玄宗本志」にも次のように記録されています。「(大中二年、西暦848年)3月、義有の王子が朝廷に来て地元の産物を捧げました。王子は囲碁が上手だったので、皇帝は顧世巌に彼と対戦するように命じました。」これは、古代中国と日本の囲碁プレイヤーが互いに対戦した唯一の記録です。その後数百年にわたり、日本は基本的に中国の伝統的な囲碁のやり方に従ってきました。中国の『玄玄棋経』は、日本の囲碁プレイヤーが必ず読むべき権威ある書物です。 平安時代(794-1185)に入ると、囲碁は上流階級の女性の間で大人気となり、11世紀に出版された『源氏物語竹河』などの書物に詳しく記されています。鎌倉時代(1185-1333)になると、戦場での生活に慣れた武士たちの間で囲碁が徐々に広まりました。戦の緊張した合間にも、武士たちは白と黒のゲームに魅了され続けました。これは囲碁の思考法が実際の戦争における戦略や戦術に似ているためだと考えられます。同時に、囲碁は僧侶の生活にも入り込みました。1199年、日本の囲碁聖人である玄尊は『囲碁流』という本を編纂しました。これは分かりやすく、日本における囲碁の普及への道を開きました。 4社が競合 日本のプロ囲碁プレイヤーであり囲碁の歴史専門家でもある頼三陽氏と中山典之氏が著した『日本外史』の統計によると、戦国武将の30%~50%が囲碁愛好家であり、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑はいずれもかなりの囲碁の腕前を持っていた。この頃、寂光寺の僧侶で囲碁の名人であった日海(1558-1623)がようやく現れ、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に次々に仕えた。織田信長の邸宅で日海が優れた将棋の腕前を見せたのを見て、信長は彼を「名人」と賞賛し、豊臣秀吉はかつて将棋会を開き、無敵の日海に年俸200石を与えた。秀吉の死後、徳川家康は日海を江戸に召し、初代名人将棋師に任命した。 いわゆる「棋聖」は、徳川幕府が最も強い囲碁の棋士に与える名誉ある称号です。その任務には、囲碁に関する事務の管理、将官の囲碁の指導、囲碁の段位証書の発行権の独占などが含まれる。徳川家康も毎年500石を日開に納めていた。李亨は寂光寺の堂宇を「本因坊」と名付け、自らも名を算左と改め、本因坊の祖となった。これが今日まで受け継がれる名門本因坊の起源です。当時、優れた将棋の腕前で米の扶助を受けていた正統派の家系は、安井家、井上家、林家の3つで、本因坊家と合わせて「将棋四家」と呼ばれていました。 当時、戦争で荒廃していた日本では、統治者たちはチェス盤が戦場のようなものだと気づき、囲碁を好み、囲碁プレイヤーを強力に支援しました。こうして、囲碁は戦争によって衰退することはなかったばかりか、代々名を馳せる李海のような名人が出現し、四大流派が覇権を競う繁栄した時代が到来した。 1644年、幕府は「五条囲碁」制度を制定し、囲碁のプレーヤーには「四囲碁家」とその他の六段のプレーヤーが含まれていました。名家も例外として参加可能です。 「五条チェス」に参加することは、武士が将軍の前で戦うのと同じくらい高貴なことと考えられていました。やがて、「チェスハウス」の称号をめぐって、各派の間で激しい戦いが勃発した。この時期は日本の囲碁の歴史において重要な節目です。 「棋聖」を争う最初の戦いは、二代目本因坊実悦と二代目安井実智の間で行われました。 1645年から1653年までの9年間に、両チームは6試合を戦い、結果は3対3の引き分けでした。両者は膠着状態にあり、どちらも「チェスの席」の地位を獲得することができなかった。規則によれば、「チェスマスター」になるには以下の条件を満たす必要があります。 ① 卓越したチェスの腕前により「四大名人」から満場一致で推薦される。 ② そしてゲームに勝つ。 ③正式な地位を得る。 舒悦の死後、舒之は官界での権力を頼りにし、1668年に官吏から「斉舒」に任命された。しかし、三代目本因坊道悦は異議を唱え、勝負を要求した。 1675 年までに、両者は 20 試合を戦い、結果は 12 敗、4 勝、4 引き分けという惨めな敗北でした。1676 年に、このゲームは「チェス ハウス」に戻されました。道悦は弟子の道策に本因坊の指導権を譲り、引退した。この戦いは日本の囲碁史上最も激しい対決の一つであった。延宝4年(1677年)、第4代本因坊道策が名人碁将に選出された。あらゆる学派において非の打ちどころがないとして有名人に選ばれたのはダオチェだけであり、これは前例のないことであった。道作は「囲碁聖人」と呼ばれ、従来の力任せの碁法を覆し、全体の調整を重視した現代的配置理論を生み出し、現在に至っています。 1682年、道作は4人の息子に、来訪中の琉球最高峰の将棋士、浜比嘉新雲守王との対局を許可した。これは日本人と外国人の対局であったが、道作は見事に相手を打ち負かし、当時の日本の将棋のレベルの高さを示した。日本では、この頃から日本の囲碁のレベルは中国を上回ったと一般に信じられている。しかし、現代囲碁界の巨匠である呉清源氏は、当時の日本の囲碁作品のほとんど、『発展論』、『気経中妙』、『四火集妙』などは中国の『玄玄気経』に基づいていると指摘し、中国囲碁の発展のピークは乾隆年間であったと考えている。日本の有名な作家、川端康成はかつて呉清源氏に、乾隆帝時代の名人たちの権力は日本でどれほどのものだったかと尋ねた。呉氏はこう答えた。「すでにかなり高い権力を持っており、日本の「名士」に劣ることはないだろう。」道策の後は、井上四代道助、本因坊五代道智が歴代「名人棋聖」を務めた。道之は1727年に亡くなり、その後「将棋室」は長い間空席のままであった。チェス界はかつて、優秀な選手の不足により低迷していた。 1766年、九代本因坊左玄と六代井上春祥の対局が始まりました。翌年、左玄は5勝1引き分けの圧倒的な差で相手を破り、名人に昇格しました。1770年、名人として認められました。その後、囲碁界は徐々に復興し、19世紀初頭から中頃にかけて囲碁活動は最盛期を迎えました。この頃、本因坊玄丈十一世と安井八世は、お互いの棋力が互角で、どちらが優位に立つことも難しいと悟っていた。二人は互角で、ともに八段準名人の地位にあり、将棋界の二大頂点の時代と称された。この時代は、十二世本因坊承和と十一世井上印象が「棋聖」の座をめぐって公然と、また暗に争った時代もありました。歴史の記録によると、1841年当時、日本には七段以上の棋士が8人、六段が6人、五段が10人、五段以下の棋士が257人いた。洪華時代(1844-1848年)には431人のチェスプレイヤーが記録されている。 近代の発展 1853年、アメリカ艦隊が日本に到着し、国境に上陸しようとした。日本政府全体が衝撃を受け、事態は危機的状況に陥った。そのため、囲碁コミュニティは衰退し始めました。まず、「五条チェス」のシステムは1862年に廃止されました。第二に、第十四代本因坊秀和の後継者であり、囲碁聖人として知られる秀策が、同年に疫病で亡くなった。さらに、明治維新により棋士制度が廃止され、各家庭が給与を返上したため、棋士の生活は一気に困窮することになった。 1879年、第18代本因坊・村瀬英雄は、第12代本因坊、その三男・中川亀三郎、そして東京の囲碁打ち58名と力を合わせ、囲碁の復興を目的とした日本初の囲碁団体「方円社」を結成した。一方、林家に養子として入っていた秀一の息子、第17代本顕坊秀吉は、本因坊一族の窮状を目の当たりにし、再び本顕坊の名を襲名して方円社と対峙し、共に将棋界の繁栄を推し進めた。黄遵憲は『日本史』の中で、当時の日本における囲碁の流行について「囲碁の名人が多く、富豪や高貴な学者の子息も皆囲碁に通じている。親しい友人が夜の宴会を開き、心ゆくまで酒を飲むと、碁盤が並ぶ」と記している。『日本雑歌』にも、その根拠となった詩がある。「百杯の美酒を飲んだ後、盤を持って下台へ行き、世俗のことは気にせず、瀛州の玉靴下を賭ける」。この頃、中国囲碁界はアヘン戦争以来衰退しており、囲碁の運勢も芳しくなかった。今世紀の初め、日本の囲碁六段の高部道平氏が中国に渡り、中国のトップクラスの多くの囲碁選手を破りました。日本の囲碁のレベルは中国を上回りました。 チェスアカデミー設立 その後、毗勝会、中央囲碁学院、流花会など、数多くの囲碁協会が設立されました。数回の分裂と合併を経て、1925 年の春にチェス界全体が最終的に集結し、日本チェス協会が設立されました。チェス協会の本部は東京にあり、各地に支部があります。囲碁アカデミーは囲碁雑誌や書籍を出版し、囲碁プレイヤーを育成し、ランキングシステムを確立しています。日本囲碁協会の設立により、一部の貴族が囲碁界を独占していた囲碁宗家制度が終わり、囲碁プレイヤーが自由に競い合うことが奨励され、囲碁技術の向上が効果的に促進されました。これは日本の囲碁の歴史において画期的な出来事です。すぐに数人の有名な棋士が囲碁研究所を脱退し、金純一を指導者に選出し、棋聖協会を結成し、読売新聞に日本囲碁研究所に挑戦するよう説得した。第21代本因坊秀斎と鑑真純一の囲碁界の決戦は、全国の囲碁ファンを熱狂させた。この機会は、Go コミュニティに大きな刺激を与え、さらに繁栄させました。戦いの末、秀斎が勝利した。他の戦いでは、氣研究所に木谷実が率いる若くてエネルギッシュな新人のグループがいたために、氣翔協会は敗北した。 1927年、朝日新聞に大手碁(日本囲碁協会の奨励会)の結果が掲載され、他の新聞にも囲碁欄が開設された。日本では囲碁は次第に一般大衆に根付き、確固たる地位を築き、黄金時代を迎えました。 清元時代 1928年、わずか14歳の呉清元が日本に渡り、1933年に59歳の秀才と対局した。彼は初めて、1、3、5の手番に「三三」「星」「天元」という新しい配置を採用した。これは道作以来の日本の伝統的な配置理論への挑戦であった。日中対立の雰囲気が漂うこの激戦は3か月間続き、日本中に大反響を巻き起こした。結果的に、さまざまな非技術的な理由により、呉清源は名人に1ポイント差で負けました。しかし、本因坊を除いて、ほとんどのチェスプレイヤーは呉清源が真の勝者であるべきだと認識しています。さらに、呉清源は伝統的な日本の囲碁理論の束縛を打ち破り、現代囲碁理論の先駆者となった。 1937年、秀斎名人は引退し、本因坊の称号を毎日新聞社に譲渡しました。その後、毎日新聞社は日本将棋連盟に寄付し、すべての棋士が実力に応じて本因坊の称号を競うチャンピオンシップトーナメントを開催することを決定しました。これは毎年恒例の本因坊トーナメントです。 1939年、読売新聞社主催の「チェス十番勝負」も木谷実と呉清源の対決で始まった。予想外にも、第6ゲームでは呉清源が木谷実を5対1の一方的なスコアで破った。いわゆる「十局入り」とは、両者のポイント差が4(4:0、5:1、6:2など)になると、たとえ10局未満であってもゲームは終了とみなされ、ポイントが高い方が勝ち、負けた方は降格されることを意味します。 1941年、閻金俊一は呉清源と対戦しました。呉が4対1でリードしていました。重要な第6局で、何らかの理由で試合が中断されました。 1943年、黒番で一度も負けたことのない新進気鋭の藤沢九之助(後に藤沢友斎に改名)が、まず呉清源と対戦することになっていた。世論は第10局までに呉清源が負けると予想していたが、予想外に第7局までに呉が4対3でリードし、藤沢がその後3局連続で勝利した。当時、10ゲームの合計スコアで呉清源を破ったのは藤沢だけで、6対4のスコアで勝利しました。第二次世界大戦中の1945年5月、日本囲碁研究所は米軍の爆撃を受け、敗戦初期の囲碁プレイヤーたちは再び苦難の時代を迎えた。 戦後の日本の囲碁 第二次世界大戦後、日本経済の復興とともに囲碁人口は増加を続け、新聞主催の囲碁大会も復活し、次第に日本囲碁の全盛期を迎えました。 1949年、藤沢邦助は王手会で優秀な成績を収め、初めて九段に昇段した。呉清源は橋本宇太郎と岩本文雄を10回戦で破り、1950年に日本囲碁協会から九段を授与された。同年9月、橋本は日本将棋連盟を脱退し、関西将棋連盟を設立した。 1951年10月、呉清源と藤沢の間で待望の10番勝負が行われ、囲碁ファンの注目を集めた。呉清源は依然として非常に強く、7勝2敗1引き分けで藤沢を破った。 1954年、坂田栄雄首相が呉に挑戦し、呉が6対2で勝利した。 1956年、呉は当時の日本のトップクラスのチェス選手たちを破り、日本のチェス界で絶対的な優位性を獲得した。 「もし呉清源が本因坊戦に参加できれば(呉は国籍の問題で本因坊戦には参加しなかった)、間違いなく優勝するだろう」と語る人もいた。呉にとって、本軒坊の現チャンピオンと毎年3回チェスをするのはほぼ日課となっており、呉は常に勝っていた。呉清源は日本の将棋界の頂点に立つスーパー棋士となった。 囲碁の発展 囲碁が活発に発展する中、毎年開催される本拳房大会は、プレイヤーの勝利への欲求を満たすには程遠いものとなっている。このような状況の中、長らく空席となっていた「名人」の座を選出するため、読売新聞社は1962年にプロ棋士が参加する第1回「名人戦」を開催した。本因坊と同レベルのチャンピオンシップトーナメントです。その他のプロ将棋大会としては、産経新聞社が主催し1963年に始まった「九段トーナメント」や、新聞三社が共催し1975年に創設された「天元トーナメント」などがある。 1977年、読売新聞社は最高賞金と最多のスター出演者による「囲碁聖人トーナメント」を創設した。 1950年代に始まった「王位戦争」、1976年に始まった「碁聖戦争」(「碁聖」と区別するため、中国では一般的に「小碁聖」と呼ぶ)とともに、日本の七大タイトルとして総称されている。 中国囲碁と日本囲碁の違い 実際、日本の囲碁と現代の中国の囲碁には微妙な違いがあり、それは唐代の中国の囲碁の特徴も反映しています。例えば、黒が先手です。中国の囲碁は、明清時代から白が先攻の慣習となっている。しかし、『望有清楽記』の将棋記録から判断すると、唐宋時代の囲碁は主に黒が先攻であった。また、「目」という文字はおそらく日本で作られたものではないでしょう。「目」は古代中国の書物にも出てきます。韓歓譚の『新論』では、囲碁を打つときは「囲碁をする者は隅を守り、目を作る」(「罫」とも書き、目と同じ意味)とされ、梁武帝の『囲碁譜』では「四角い目には傾きがなく、まっすぐな道には曲がりがない」とされている。中国語では「纲举目张」のように、「目」を使って四角を表すのが一般的である。現在でも、話し言葉では数字を「数数」と呼ぶのが一般的です。「Mu」は「数数」を意味し、「dianmu」は「点数」を意味します。また、「ムー」は「道」や「魯」と同様に、古代中国の軍隊の単位です。「ムー」は最小の軍隊単位です。古代の軍隊におけるいわゆる「頭ムー」は「ムー」部隊の長です。囲碁は戦争を真似る。軍隊の名前を借りるのは普通だ。 唐代以前は「道」が主に使われ、宋代以降は「路」が一般的に使われました。唐代には「目」と「枰」が主に使われていました。日本の囲碁は唐代から伝わったため、宋代以降中国で普及した「路」は使われていません。また、『敦煌棋経』ではチェスは「碁」と書かれており、宋代の『望有清楽集』では「棊」、現代では「棋」と書かれていることにも注目すべきである。日本での「碁」の使用は、それが導入された当時の特徴を示しています。 中国本土では数値的手法が採用されており、呉清源氏はそれが世界で最も科学的な手法であると考えている。中国の台湾省では、現在台湾島でのみ使用されているポイントカウント方式を採用しており、非常に面倒です。日本も韓国も数値方式を採用しているが、これは現在最も議論を呼んでいる方式でもあり、不合理な点も多い。現在では、競技が開催される場所のルールを採用するのが一般的です。中国本土の大会ではカウント方式が採用されており、黒駒には7.5ポイントのハンディキャップが与えられます。日本と韓国の大会ではナンバー方式が採用されており、黒駒には6.5ポイントのハンディキャップが与えられます。 ルールでは黒に2と3/4のハンデがありますが、日本のルールでは勝敗は「地」の数で決まります。中国のルールは、盤上で生き残った駒の合計数に基づいています。これには「ダブルライフチェス」の駒の数も含まれます。したがって、同じチェスのゲームの結果を計算するために異なるルールを使用すると、逆の結果が生じる可能性があります。また、状況が非常に微妙で「一枚駒」が 1 つしかない場合、日本のルールでは、駒に勝てばもう 1 つの「地」を獲得できるということも言及する価値があります。一枚駒は、最終的な「地」の数の計算とは直接関係がありません。中国のルールによれば、勝敗は生きているチェスの駒(単独の将棋を含む)の総数によって決まります。 |
<<: 司馬懿は「高尚な野望を持ち、狼のような容貌をしている」のに、なぜ曹操は彼を排除しなかったのか?
>>: 後漢から三国時代にかけて、諸葛亮の他にあだ名を持っていた人物は誰ですか?
推薦する
『汝孟玲:渓亭の夕暮れをいつまでも忘れない』の著者は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
如夢玲:渓流亭の夕日をいつまでも思い出す【宋代・李清昭】私はいつも小川沿いの小屋での夕日を思い出す。...
『世界の物語の新記録』の第 9 章ではどのような物語が語られていますか?
周知のように、『新世界物語』は魏晋時代の逸話小説の集大成です。では、『新世界物語・知識と真贋』第九篇...
『西遊記』ではなぜ悟空が花果山の猿たちに大惨事をもたらしたと書かれているのでしょうか?
『西遊記』ではなぜ悟空が花果山の猿に災難をもたらしたと書かれているのでしょうか?これは多くの読者が知...
「狼涛沙:幕の外の雨がゴボゴボと鳴る」は南唐の最後の皇帝、李裕が書いたもので、故郷への尽きることのない思いが込められている。
李郁は五代十国時代の南唐最後の君主であり、唐の元宗皇帝李靖の6番目の息子でした。李毓は皇帝の座に就く...
スイレンは木を削って火を起こす技術を発明しましたが、なぜジュロンは火の神なのでしょうか?
ご存知のとおり、火を上手に使えるようになることは人類の進歩において最も重要なステップです。人類が火を...
関羽、張飛、趙雲、呂布、顔良、文秀が戦ったら誰が勝つでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
李和の「神府馬と皇運河水を詠む」:作者はお世辞を言っているようで、深い意味はないようだ
李和(790-816)、雅号は昌吉とも呼ばれる。彼は河南省富昌県長谷郷(現在の河南省益陽県)に生まれ...
「邯鄲の紅波台に登って酒を飲みながら出兵の行進を見る」の原文、翻訳、鑑賞
邯鄲の紅波台に登り、宴会を開き、軍隊の派遣を見守る李白(唐)私は赤い羽根を二つ持って、燕と趙の間を旅...
「彭公安」第302章:7人の英雄が夜に八卦山を探検し、魔術師は敵を捕らえるために命を危険にさらします
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
『紅楼夢』で劉おばあちゃんが二度目に栄果屋敷を訪れたとき何が起こりましたか?
『紅楼夢』の中で、劉おばあさんが大観園を訪れた場面は、本全体の中でも最も古典的な章の一つと言えます。...
少年青年の英雄、第35章(パート1):老人は科挙で不思議な前兆を示し、安小姐は桂園で先導する
清代の作家文康が書いた『家中英雄』は、主に清代の康熙・雍正年間の公的な事件を描いたものです。主人公は...
秦の始皇帝は天下統一後、どのように国を統治するつもりだったのでしょうか?なぜ封建制度を廃止する必要があるのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、秦の始皇帝が封建制度を廃止した理由について...
李世民は歴史上非常に有名な皇帝です。彼の息子たちに何が起こったのでしょうか?
李世民は歴史上非常に有名な皇帝ですが、彼の息子についてはあまり聞きません。彼には14人の息子がいたが...
白玉堂の武器は何ですか?白玉堂の武器はナイフですか、それとも剣ですか?
白玉亭は中国の古典小説『三勇五勇士』の主要人物である。浙江省金華市出身。容姿端麗で気高く、文武両道の...
漢の章帝には何人の息子がいましたか?漢の章帝の息子たちの簡単な紹介
漢の章帝劉荘(西暦57年 - 西暦88年4月9日)は、漢の明帝劉荘の5番目の息子でした。彼の母は賈妃...