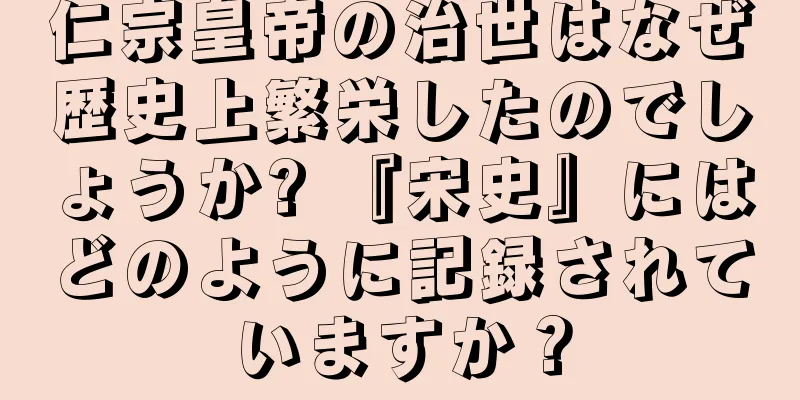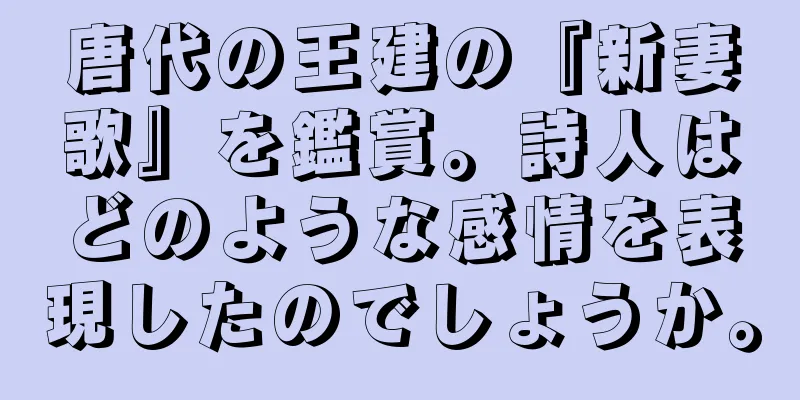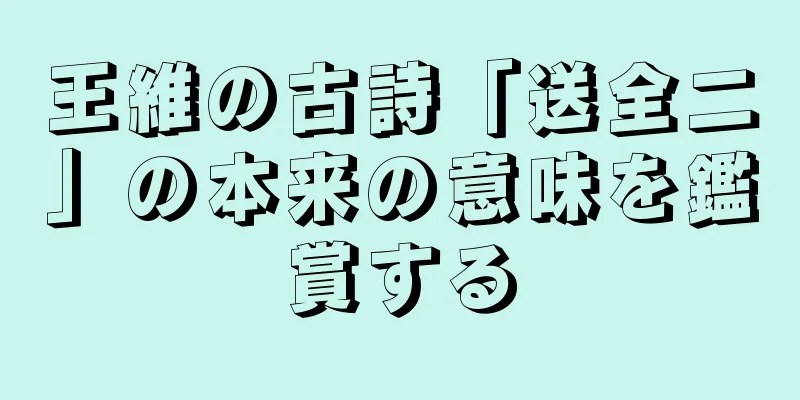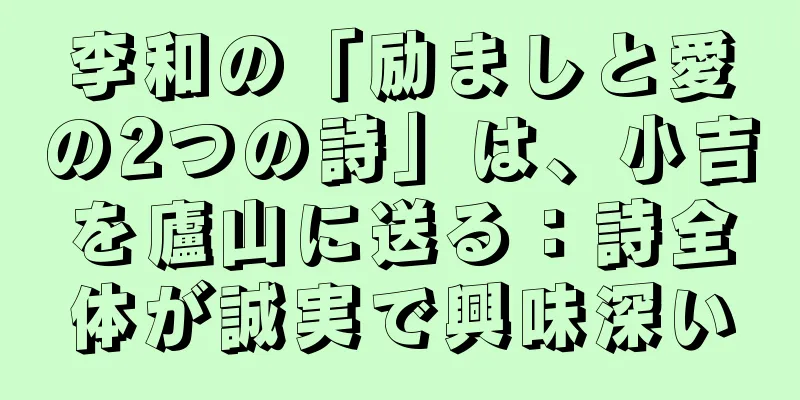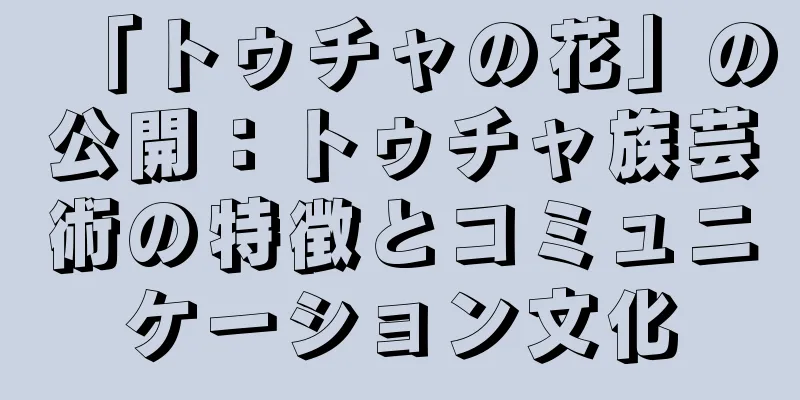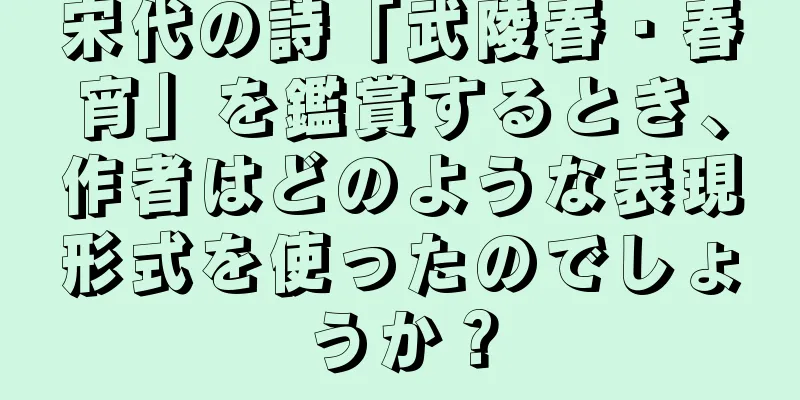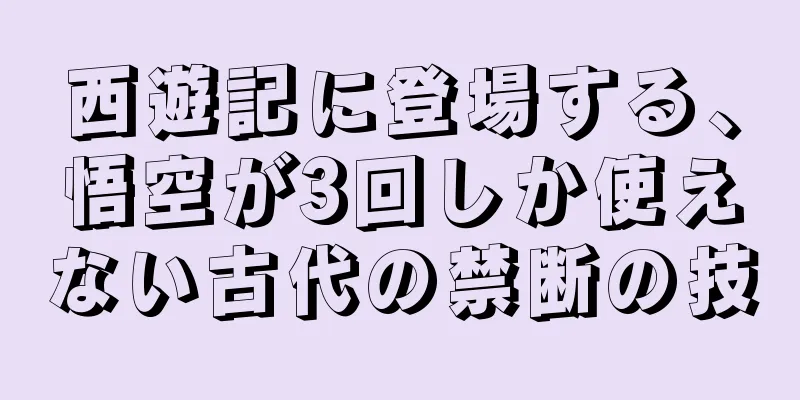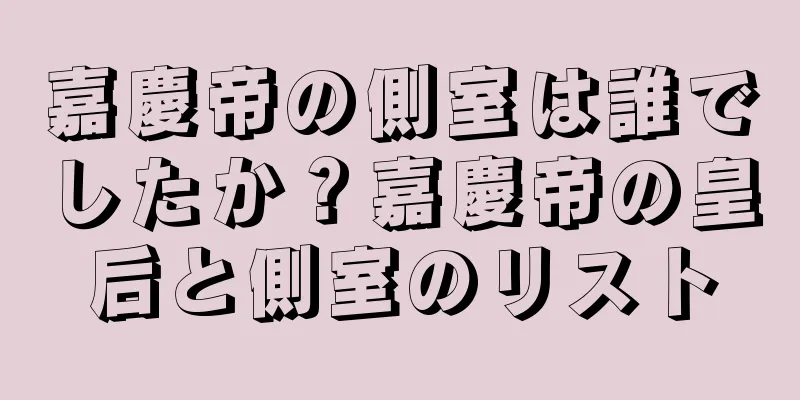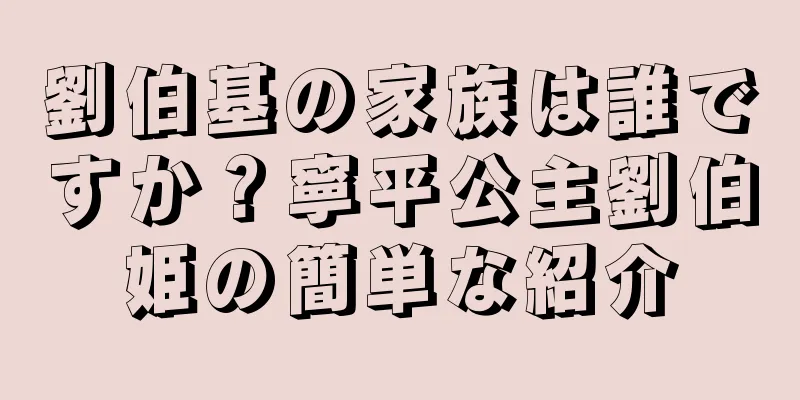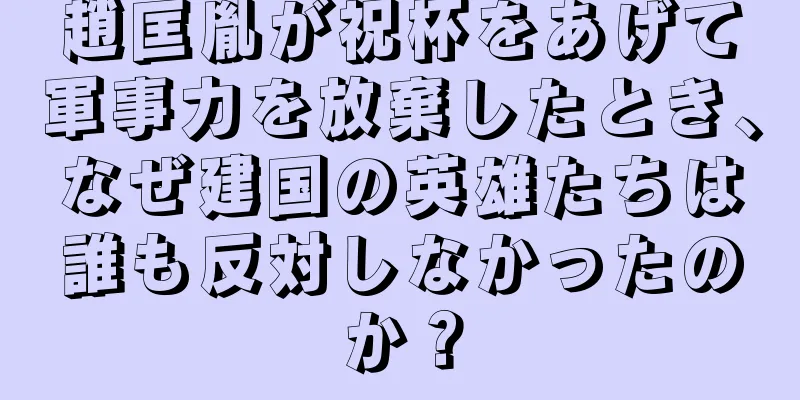プミの歴史 プミの歴史的な移住
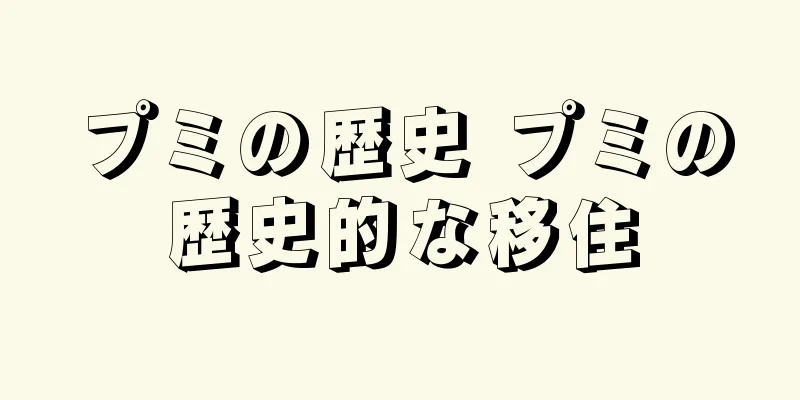
|
民族の伝説や歴史記録によると、プミ族の祖先は、古代に青海チベット高原の甘粛省と青海省のバヤンカラ山脈周辺に住んでいた古代チャン族である。プミ族の祖先は、より生活に適した楽園を求めて、高地から金沙江沿いに移住した。彼らは四川江と亜龍江の間の渓谷から次第に南下し、温暖で湿度の高い四川・雲南省境地域へと移り住み、水と草が豊富な場所に定住した。かつては四川省西部の大渡河両岸と亜龍江流域で百郎班木氏族などの部族連合を形成し、「百余国、130万世帯、600万人余り」と称された。 『三国志』の張儀の伝記によると、漢代に「定竺県」(現在の木里・塩源地域)に住み、「莫沙夷」とともに「鶏尿塩」を焼いていた「夷帥班木王」は、プミ族の部族王であったに違いない。 「バンムプミ」も綴りは異なるものの同音異義語であり、発音は基本的に一致しています。漢代には、白クコは雲南省の北西部国境まで広がり、唐とチベットの対立期には、金沙河と亜龍河中流域の白クコが吐蕃軍とともに雲南省北西部の金沙河両岸の県に進出した。 唐代と宋代には、「西扇」(すなわちプミ)に関する歴史的記録がより具体的かつ明確になりました。 『宋史』には「西夷の人に賄賂を渡して市場で良い馬を求めた」「西夷の馬は老いてから来た」「戦争に備えられる」などの記録が数多く残っており、当時のプミの祖先が良馬の飼育に長けていたことが分かります。プミ族の起源について、元代の周志忠は『外地記』の中で次のように記している。「プミ族は西域の出身で、羊や馬を飼育し、戦いを好み、中国人と交流することはほとんどない。」 「Bu Ci」は「Bai Lang」を意味し、同音異義語ですが翻訳が異なります。明代の景台『雲南地図』第4巻「丘丘州」には、「州内の山谷に移住者が住み、西藩と呼ばれ、いわゆる西栄である」と記されている。いわゆる西栄とは「西羌」のことである。古代では羌と栄は互換可能であり、総称して「羌栄」と呼ばれていた。これは、明代の人々がプミ族の起源を正しく理解していたことを示している。 西暦7世紀から9世紀頃、吐蕃の勢力が強大になったため、徐々に外へ広がり、バ族(プミはチベット語で「バ」と呼ばれ、当時プミは吐蕃の臣下であった)を組織して、2つの川(金沙江と亜龍江)の土地を占領した。プミ族の居住地はその後、四川省の延辺、雲南省の寧朗、華平、永勝などに広がった。政府は塩源に置かれ、プミ語で「ワバ」政権と呼ばれた。宋代には「樊城県」、元代には「巴娃治」(モンゴル語で「赤虎将」の意)と呼ばれた。それ以来、プミ族は雲南省北西部の寧朗地域に定住しました。 現在の永寧地域は、古代からプミ族とモソ族が混在して居住していた地域です。現在、永寧地区にはプミ族に関係する地名が数多く残っています。例えば、永寧巴地区には「八珠」(現在は「八珠」と呼ばれている)という村があり、これは「プミ族の集まる場所」を意味します。 永寧靴屋街の歴史的な名前は「八卦谷」であり、「プミ族が踊る場所」を意味します。托店郷には「バナワ」という地名があり、プミ族とモソ族が共存していることを意味します。永寧市の托子頂古村は「西帆坪」とも呼ばれ、寶馬坪の二番目の村には「西帆渓」という川があります。新営潘には「八東湾」という場所があり、外国人が集まった城という意味です。 元王朝はプミ族の移動と発展において重要な段階であった。宋王朝の保有元年(1253年)の秋、フビライ・ハーンは大軍を率いて南に向かい、プミ族が住んでいた西昌を通過して大理を攻撃した。塩源、寧朗などでは、樊城の諸侯や沿線に住む西樊の族長たちが真っ先に降伏し、歩兵と騎兵を率いて先鋒となった。 プミ族は優れた馬を持ち、乗馬や射撃に長けていたため、戦闘における勇敢さでフビライ・ハーンに高く評価された。途中で占領した峠のほとんどは西樊の兵士によって守られていた。その結果、プミ族の生活圏は金沙河の西にある蘭坪まで広がった。渭渓、麗江など。清代の于清元は『衛西録』に次のように記している。「巴志は西凡とも呼ばれ、姓がない。 元朝の静帝が雲南を征服した時、祖先と離れて川を渡ったが、川の真ん中で一緒に逃げてきた人々は、どこのモンゴル族の出身か分からなかった。」この歴史文書は、モンゴル軍とともにプミ族が大理に南下したことを記している。プミ族は途中でモンゴル軍に加わったため、あるモンゴル族の出身だと誤解されていた。 元と明の時代以降、中国の歴史書にはプミ族の分布に関する正確な記録が残されている。 『雲南天斉記』第30巻には、「西樊、永寧、北勝、斉斉はすべて金沙江の北側である」と記されている。景台『雲南地図帳』第4巻には永寧州について次のように記されている。「その管轄下にある4つの首府のほとんどは西方諸部族である。」 |
<<: 清朝における正紅旗の主な機能は何でしたか?苗字は何ですか?
>>: プミの習慣 プミの人々はどのようにして「魂を呼ぶ」のか
推薦する
明代読本『遊学瓊林』第1巻 地理 全文と翻訳注釈
『遊学瓊林』は、程雲生が書いた古代中国の子供向けの啓蒙書です。 『遊学瓊林』は、明代に西昌の程登基(...
軍事著作「百戦百策」第10巻 戦争の恐怖 全文と翻訳注釈
『百戦奇略』(原題『百戦奇法』)は、主に戦闘の原理と方法について論じた古代の軍事理論書であり、宋代以...
『紅楼夢』では、薛家は賈邸に住んでいる間、すべての費用を自費で支払っていましたか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
後世の多くの芸術作品では、なぜ高藍は河北の四柱の一人なのでしょうか?
河北の四柱は、張国良の三国志演義に登場する概念です。彼らは、東漢末期に河北を支配した大軍閥、冀州太守...
『半神半悪魔』の段正春は卑劣な人間なのか、それとも恋に悩む男なのか?
『半神半魔』の段正春をご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。『おもしろ歴史』編集者がお教えします。...
道教の雷部の五将とは誰ですか?また、彼らの具体的な任務は何ですか?
道教の雷部の五将とは誰ですか? 彼らの具体的な任務は何ですか? 彼らはどこから来たのですか?雷部の五...
『紅楼夢』で邢秀燕が薛可と一緒にいるのはなぜですか?理由は何ですか?
邢秀燕は『紅楼夢』に登場する邢忠とその妻の娘であり、邢夫人の姪である。今日は、Interesting...
明代の小説『金平梅』から、明代の人々が元宵節をどのように祝ったかを探ります。
明代の元宵節に興味のある読者は、Interesting History の編集者をフォローして読み進...
張居正が実施した「一鞭法」の利点と欠点は何ですか?
「一鞭制」は明代中期以降の課税と賦役に関する重要な改革であった。もともとは「条編」と名付けられ、「分...
古代の硬貨の価値を決定する 5 つの要素は何ですか?
概要:わが国の古代貨幣は、商代の貝貨、戦国時代の刀銭や布貨、秦代の四角穴丸貨、清末期の機械鋳造貨幣に...
前梁王張鈞とはどんな人物だったのでしょうか?歴史は張鈞をどのように評価しているのでしょうか?
前梁文王張鈞(307年 - 346年)、号は公廷、前漢の常山王張儒の19代目の孫、前梁明王張世の子、...
「彭公安」第20章:英雄たちは呉文華を捕らえ、張茂龍は呉文華を捕らえる計画を立てる
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
古典文学の傑作『太平天国』:人材資源編第5巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
古典文学の傑作『論衡』第19巻:記号の検証
『論衡』は、後漢の王充(27-97年)によって書かれ、漢の章帝の元和3年(86年)に完成したと考えら...
道教にはお守りがありますか?何千年も受け継がれてきたこの秘密の技術がどこから来たのかご存知ですか?
(智典江山「儒教、仏教、道教」講演第31号)今日は道教のお守りの技法について簡単にお話しします。超自...