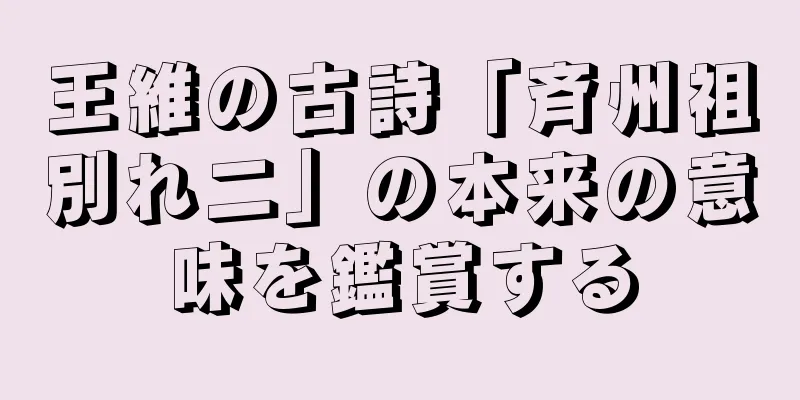「山西村訪問」をどう理解するか?創作の背景は何ですか?

|
山西村を訪問 陸游(宋代) 農民の泥ワインを笑ってはいけません。豊作の年には、客をもてなすのに十分な鶏や豚がいるからです。 山と川に囲まれて出口がないと思ったら、曲がりくねった道と花の向こうに別の村が見つかります。 笛と太鼓は春節の到来を告げ、衣装はシンプルで古風なもの。 これからは、私がのんびり月に乗ることを許して下さるなら、私は夜中でもいつでも杖を持ってあなたの家のドアをノックします。 翻訳 旧暦の12月に農民が醸造する濁った味気ない酒を笑ってはいけません。豊作の年には、農民は豪華な料理で客をもてなします。 山々が重なり、川が曲がりくねっていて、行く手がないのではないかと不安でしたが、突然、緑の柳と鮮やかな花々の間に山里が現れました。 コミュニティデーが近づくと、道のあちこちで神々を迎える笛や太鼓の音が聞こえてきます。素朴な服と帽子を身につけるという古代の素朴な習慣が今も守られています。 今後も美しい月明かりの下で散歩に出かけられるようになったら、いつでも松葉杖を持ってあなたのところに伺います。 感謝 これは江南の農村の日常生活を描いた旅情詩である。詩人は題名の「旅」という言葉にこだわっているが、村を巡る過程を詳しく描写しているのではなく、旅の途中で見聞きしたものを切り取って、旅の尽きることのない喜びを表現している。この詩は、まず詩人が農家に出かける様子、次に村の外の風景、村での出来事、そして最後に頻繁に行われる夜の外出について描いています。それぞれの詩はそれぞれに重点が置かれていますが、いずれも村を巡る旅をテーマにしており、山村の美しい自然風景と村人の素朴な風習が全体の絵の中で調和して一体化しており、美しい芸術的構想と静かで時代を超越したスタイルを形成しています。この詩の主題は比較的ありふれたものですが、発想が斬新で技法も平易で修辞的な装飾がなく、自然に面白くなっています。 最初の連句は、収穫の年の田舎の平和で楽しい雰囲気を描いています。 「足鸡豚」の「足」という文字は、農家のおもてなしの心と寛大さを表しています。 「笑わないで」という二つの言葉は、田舎の素朴な民俗習慣に対する詩人の尊敬の念を表現しています。 二番目の連句は山と水辺の風景を描写しており、哲学的な考えが含まれており、何千年にもわたって広く引用されてきました。 「山川が密集していて、出口がないと思うが、見上げると柳や花が見え、また別の村がある。」流暢で華やか、明るく陽気な詩は、詩人が緑豊かな山々の間を散歩し、山の澄んだ泉が曲がりくねった小川を流れ、草木がますます青々と茂り、曲がりくねった山道がますます見分けにくくなっている様子を思い起こさせるようです。途方に暮れていた詩人は、突然目の前に花や柳が咲き、豊かな花や木々の間に農家が数軒隠れているのに気づきました。詩人は突然悟りを開いたように感じました。彼の顔に明らかに表れていた興奮は想像に難くない。もちろん、このような状態は先人たちによって説明されてきましたが、この 2 つの文は特に婉曲的で独特です。この連句を読んだ後、人々は人生のある状況が詩に描かれているものと驚くほど一致していることを感じ、それによって詩にもっと親しみを感じるでしょう。ここで描かれているのは、詩人が山道を歩いていて、道がないのではないかと思いながら、突然明るい気持ちになったことです。これは詩人の将来への希望を反映しているだけでなく、世の中の物事の盛衰の哲学をも伝えています。そのため、この二行の詩は、自然の風景を描写する範囲を超え、強い芸術的生命力を持っています。 二番目の連句は自然から人間の出来事へと移り、南宋初期の田舎の習慣を描いています。読者にとって、詩人が伝統文化に対して抱いている深い愛情を理解するのは難しくない。 「彼女」は土地の神です。春節は立春から5日目に行われます。農民たちはコミュニティに犠牲を捧げ、希望に満ちて豊作を祈ります。祭りの起源は「周礼」にあります。蘇軾は『當連花・密州商院』の中で「太鼓を打ち笛を吹き、農民社会に加わる」とも述べている。宋代でも依然として非常に流行していたことがわかる。ここで陸游は「簡素な服装と古風なスタイル」で地元の古い風習を称賛し、土地と人々への愛情を示した。 最後の連句では、詩人は文体を変えて、一日中「旅」をしていたことを示しています。このとき、月は空高く昇り、地球全体がかすかな月明かりに包まれており、春節後の村に一層の静けさを与えており、非常に興味深いです。だから、この二つの文章が私の心から自然に流れ出てきました。これからは、時々杖に寄りかかったり、月に乗って、木の戸をそっとノックしたり、お年寄りの農夫とお酒を飲みながらおしゃべりしたりできたらいいなと思います。この光景はとても楽しいと思いませんか?故郷を愛し、農民と親交を深めた詩人の姿が紙の上に生き生きと浮かび上がります。 詩人は弾劾されて故郷に戻った後、必然的に落ち込み、憤慨した。偽善的な官僚制度に比べれば、故郷での質素な暮らしは、当然私に限りない安らぎをもたらすだろう。また、詩人はのんびりしているように見えますが、それでも国政に関心を持っています。国を統治していた人々は近視眼的で長期的な計画を持っていませんでしたが、詩人は信念を失わず、悪い時代の後にいつか良い時代が来ると固く信じていました。この心境はまさに彼が訪れた場所と一致し、二人のやり取りから「高い山」と「暗い柳」という連句が生まれ、後世に語り継がれています。 陸游のこの七字詩は、構成が厳格で、主線が際立っています。詩の八つの文には「旅」という言葉は一つもありませんが、「旅」という言葉はいたるところに見られ、詩人は旅への興味に満ち、旅について考え続けています。そして層は明確です。特に真ん中の二連句はバランスが良く、表現しにくい情景をうまく表現しており、まるで玉皿に落ちる真珠のように滑らかで流れるようで、非常に高い芸術的レベルに達しています。 背景 この詩は、陸游が官職を解かれて家で悠々自適な生活を送っていた1167年(宋孝宗皇帝の千島3年)の早春に書かれたものです。しかし、彼は落胆しなかった。彼は田舎暮らしに希望と光を感じ、その気持ちを詩に込めました。この詩は彼の故郷である山陰(現在の浙江省紹興市)で書かれたものです。 |
<<: 『冬夜読書して子遊を示す』をどのように理解すべきでしょうか?創作の背景は何ですか?
>>: 「卜算子·咏梅」の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
推薦する
清代の『修雲歌』第85章にはどんな物語が語られていますか?
ポー・リアン・ティアンの道教の友人たちは、エビ族の龍娘を殺して栄光を勝ち取るために再会する怪物の群れ...
安史の乱の際、安慶緒は弾薬も食料も尽きていました。突風のおかげで、60万人の唐軍を打ち破り、「集団墓地」を残しました。
今日は、Interesting Historyの編集者が「集団墓地」がどのようにして生まれたのかをお...
『桃源郷雪の悲劇』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
桃園の道士薛の傷劉玉熙(唐代)祭壇の横の松の木は空の鶴の巣のようで、古い道には白い鹿がのんびりと散歩...
「Presented to My Cousin, Part Two」を鑑賞するにはどうすればいいでしょうか?創作の背景は何ですか?
弟への贈り物、パート2魏の劉璋山には背の高い松の木が茂り、谷には風がざわめいています。風がどれほど強...
役人は裁判所に行くとき、何を手に持っているのでしょうか?紛失した場合はどうなるのでしょうか?
皆さんは時代劇を見たことがあると思います。このシーンを覚えていますか?昔、役人や大臣は宮廷に行くとき...
劉長青の詩の有名な一節を鑑賞する: 憧れと悲しみに満ちた砂州の白い蓮を誰が見るだろうか?
劉長清(生没年不詳)、法名は文芳、宣城(現在の安徽省)出身の漢民族で、唐代の詩人。彼は詩作に優れ、特...
唐の皇帝高宗、李治、王妃の簡単な紹介。王妃はどのようにして亡くなったのでしょうか?
王后(628?-655)は、汪州斉県(現在の山西省斉県)の出身で、羅山霊王仁有の娘であり、母の姓は劉...
孟姜奴の神話 万里の長城で泣く孟姜奴
万里の長城で泣く孟姜女:秦の時代に、孟姜女という優しくて美しい女性がいました。ある日、彼女は庭で家事...
後漢末期の文学者曹操:「濠里河歌」の注釈と翻訳
『昊麗歌』は後漢末期の作家曹操が書いた詩です。この詩は、昔の月譜の題名を使って時事問題を詠んだもので...
辛其の辞を鑑賞:「西江月 - 息子と姉妹に家族の事情を見せる」
以下、Interesting Historyの編集者が、辛其記の『西江月:息子の曹に家事を譲らせる』...
白居易の古詩「春暮れ」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「春の終わり」時代: 唐代著者: 白居易美しい景色が残暑を吹き飛ばし、暑さがやってくる中、感慨...
李清昭は高層ビルに情熱と威圧感に満ちた傑作を書いた
今日は、Interesting Historyの編集者が李清昭についての記事をお届けします。ぜひお読...
海渾侯の墓にある孔子幢に孔子の姓がなぜ「孔子」と書かれているのですか?
海渾侯の墓にある孔子の額に孔子の姓がなぜ「孔子」と書かれているのか?これは多くの読者が気になる疑問で...
水滸伝で飛雲賦の人物が燕青だったら、武松のように無傷で逃げ切れるだろうか?
武松が飛雲埔で暴れまわる場面は、『水滸伝』の非常に古典的な場面です。「歴史の流れを遠くから眺め、歴史...
「中国」という言葉は実は古代史では単なる形容詞だったのでしょうか?
はじめに:今日、「中国」は「中華人民共和国」の略称であることは知られていますが、「中国」という名前は...