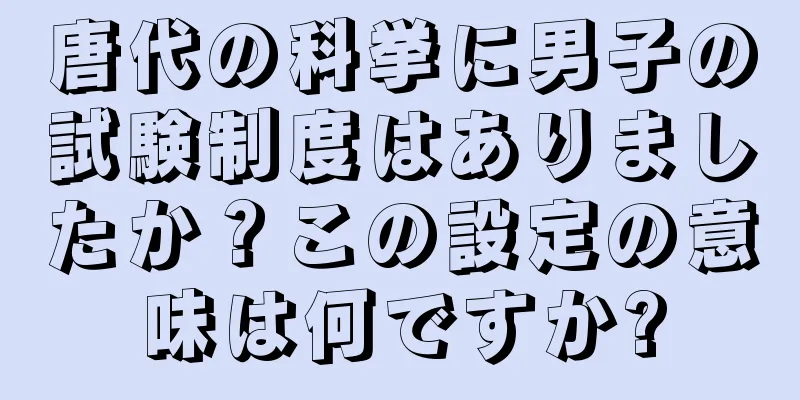三山関の将軍、孔玄はどれくらい強いのでしょうか?孔玄は『封神演義』でどのような役を演じますか?

|
今日は、Interesting Historyの編集者が『封神演義』の孔玄に関する記事をお届けします。ぜひお読みください~ ここで言う孔玄とは、もちろん『神々のロマンス』に登場する商の周王の陣営の三山関の将軍、孔玄のことである。孔玄は『神々のロマンス』の中では重鎮ではないが、多くの伝説がある。また、孔玄は非常に強力で、商王朝の第一の達人とも言える。道士の陸牙でさえ孔玄に打ち負かされる可能性がある。孔玄はどれほどの力を持っているのでしょうか? 彼は本の中で何位にランクされていますか? 孔玄の本当の起源は何ですか? 『封神演義』の孔玄の設定は、彼が世界初の孔雀であり、彼の五色の神光はすべてを吸収すると言われています。相手が誰であろうと、楊堅、哨、道士の然登、道士の陸牙でさえ、彼の五色の神光の前では気軽に攻撃する勇気はありません。彼らは逃げることしかできず、反撃する勇気はありません。彼は商王朝の最初の産物と言えます。このような強力な戦闘力に直面して、蒋子牙は白旗を掲げて孔玄との戦いを避けなければなりませんでした。 孔玄は確かに非常に強力な人物だったようです。孔玄を鎮圧し、自分の乗り物と弟子にした道士の准夷が後に介入しなかったら、戦いの形勢は逆転しなかったかもしれません。その後、孔玄は道士の准胤の弟子となり、孔雀王と称えられ、また、西周の桀教攻撃に協力するよう命じられ、大いに役立った。何しろ、彼は非常に有能で、どの陣営にいたとしても、その陣営の方が勝利する可能性が高い。 そういえば、そのうちの一つ「孔雀大王」が注目を集めたのではないでしょうか。孔雀王には称号があり、仏陀の母として知られています。これについては『西遊記』にいくつかの説明があります。なぜなら、釈迦がちょうど10フィートの黄金の体を修行していたとき、孔雀に一口で食べられてしまったからです。当時、孔雀の地位は非常に高く、世界の鳥のリーダーは鳳凰であり、鳳凰は孔雀と鵬を産みました。孔雀は人食いだったので、釈迦を一口で食べてしまいました。 釈迦はもともと孔雀の糞とともに出ようとしたが、そうすると自分の本身が汚れてしまうので、仕方なく孔雀の背を切り裂いて霊山へ行った。出た後、孔雀が人を食い続けることがないように、人々に害をなすものを排除するために、孔雀を殺そうとした。しかし、他の仏陀たちは、このように孔雀の体から出てきたのだから、孔雀はあなたの母親だ。それを殺すことは、自分の母親を殺すことと同じではないか、と諭した。そこで釈迦は諦めて、孔雀を霊山に残し、孔雀王と名付けた。 『西遊記』のこの筋書きの本来の意図は如来と金翼の彭鷲の関係を説明することですが、孔雀も絡んでおり、孔雀王の地位が非常に高いことも示しています。孔雀王に指名された孔玄も当然同じで、有能で地位も高いです。もちろん、他の敵に特別な注意を払うことはありません。孔玄は皆と戦った。道士の俊臥が彼の五色の神光を破らなかったら、最終結果は予測不可能だっただろう。 |
<<: 不周山はなぜ不周山と呼ばれるのでしょうか?この山は今どこにありますか?
>>: 孫悟空は五行山の下に閉じ込められたとき、何を食べましたか?なぜ鉄剤を摂取し、銅ジュースを飲む必要があるのでしょうか?
推薦する
何卓の「ヤマウズラの空:長門を再び訪ねて、すべては違う」:深く感動的で美しい哀悼詩
何朱(1052-1125)は北宋時代の詩人。号は方慧、別名は何三嶼。またの名を何美子、号は青湖一老。...
李賀の『金銅仙人の漢への別れ』はどのような感情を表現しているのでしょうか?
唐代の李和は『金銅仙の漢への別れ』という詩の中でどのような感情を表現したのでしょうか?これは多くの読...
古代の貢物制度とは何だったのでしょうか?朝貢制度は世界の統一にどのような積極的な役割を果たしましたか?
今日は、Interesting Historyの編集者が貢物制度についての記事をお届けします。ぜひ読...
宋代の詩「石州人」の鑑賞 - 小雨が降ると寒さが来る。作者はこの詩の中でどのような比喩を用いているのでしょうか。
宋代の何朱の『宋州人・小雨寒』について、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう...
唐代の重要な軍事書『太白陰経』全文:人略第一部:将軍には知恵と戦略がある
『神機滅敵』は『太白陰経』とも呼ばれ、道教の著作です。古代中国では太白星は殺生の達人であると信じられ...
『紅楼夢』では、王夫人が賈煥を攻撃しました。賈煥はなぜ何もしなかったのですか?
周知のように、「紅楼夢」の趙おばさんは娘と息子、賈丹春と賈歓を出産しました。賈歓は末っ子です。では、...
孟子:孟子書第24章と第25章、原文、翻訳、注釈
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸...
紅楼夢 第19話 美しい夜の恋、花は言葉の意味を理解する、静かな日、玉は香りを与える
賈妃が宮殿に戻った翌日、皇帝に謁見してお礼を言い、帰路の報告をしたところ、皇帝は非常に喜んだと伝えら...
なぜ回族様式の建築はそんなに有名なのでしょうか?明・清時代の回族商人とどのような関係があるのでしょうか?
徽州の建築が有名な理由は、主に徽州の商人のほとんどが栄華を極めた帰国後、豪華で精巧な邸宅や庭園で自ら...
文廷雲の「春の日」:この詩は色が淡く、明確で遠い芸術的概念を生み出している。
文廷雲は、本名は斉、雅号は飛清で、太原斉県(現在の山西省)の出身である。唐代の詩人、作詞家。彼の詩は...
大工仕事が大好きだった明代の僖宗皇帝は、どのようにして明王朝の基盤を破壊したのでしょうか。
明の冲宗朱有嬌といえば、明の歴史に詳しい人なら誰でも、彼が歴代の王朝の中でも非常に特異な皇帝であるこ...
『紅楼夢』で宝仔は宝玉に自分の気持ちをどのように表現しましたか?
「紅楼夢」におけるバオ、ダイ、チャイの感情的な絡み合いが、この本のメインテーマです。次に、『Inte...
最後の皇帝溥儀には何人の弟がいましたか?溥儀の弟の簡単な紹介
溥儀、フルネームは愛新覚羅溥儀、雅号は姚之、号は昊然(こうらん)としても知られる。清朝最後の皇帝であ...
「一口で十分」という慣用句をどう理解すればいいのでしょうか?この慣用句の背景にある物語は何ですか?
「一口で十分」という慣用句をどう説明すればいいのでしょうか?その裏にはどんな物語があるのでしょうか?...
唐代の詩人袁震の『悲哀を癒す三詩第二』の原文、翻訳、鑑賞
袁震の『悲しみを和らげる三つの詩、その2』については、興味のある読者は『Interesting Hi...