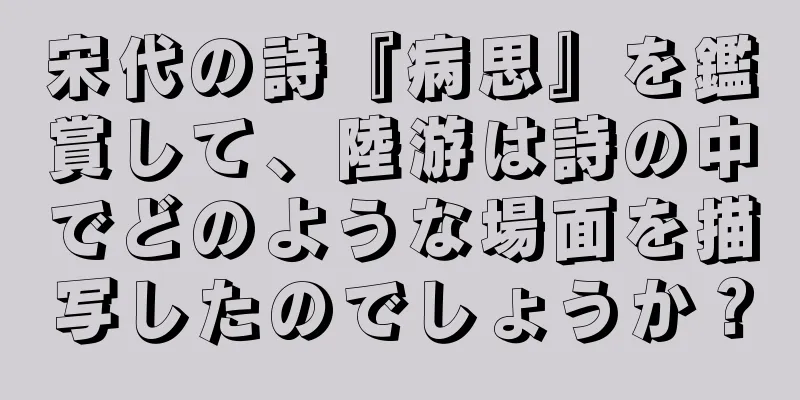唐代の科挙に男子の試験制度はありましたか?この設定の意味は何ですか?
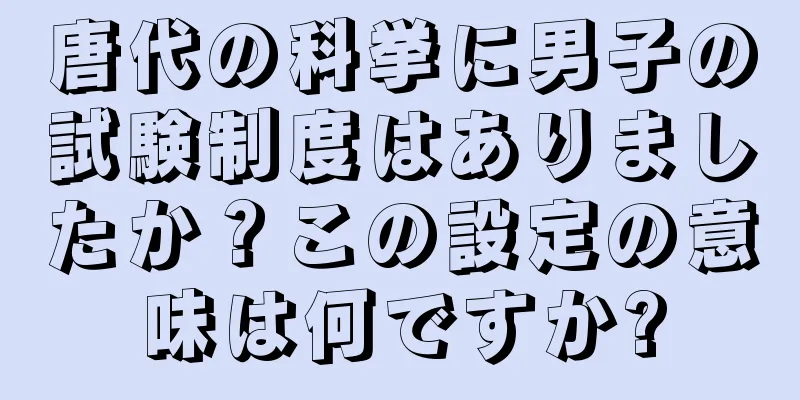
|
どの王朝にも神童はいた。こうした早熟な子供たちを最大限に育成するため、唐代は科挙の同子部門を設けた。しかし、その過程で多くの紆余曲折があり、結局は発展しなかった。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 唐代の科挙には、早期教育に成功した者のために特別に設けられた男子の部がありました。これは漢代と魏代から続く伝統である。儒教の古典を少なくとも一つ暗唱できる12歳以下の早熟な子供は、県や王国から中央政府に推薦され、面接に合格すると「児童予備役」の称号を与えられる。 漢の舜帝の時代、国書長官の左雄は、孝行な官吏を選抜する年齢制限を40歳以上にすることを提案した。実際、左雄も階層制の幹部養成方式を支持していた。当時、「汝南の謝康と河南の趙堅は、わずか12歳で経文を習得していた」という人物がいた。彼らは左雄自ら董子郎に任命された。また、『三国志』巻15には、司馬朗が12歳で男子官吏の試験を受けたときのことが記録されている。試験官は彼が「体が丈夫」であることを見て、実年齢がすでに限度を超えているのではないかと疑い、厳しく尋問した。司馬朗は怒って言った。「私は生まれつき体が大きすぎる。若くて体が弱いが、高官を羨ましがることはない。早く出世するために年齢を低くするのは私の野望ではない!」 儒教の古典を暗唱するのは子供にとって特に難しいことではないが、一度それをクリアすれば官僚になるための近道となる。そのため、試験会場にはボーイスカウトのふりをする若者がたくさんいるが、これが司馬朗の言った「早く出世するために年齢を低くする」ということである。さらに、当時は骨年齢を検知する技術的な手段がなく、試験監督者に賄賂を贈ることもできた。 唐代における男子の選抜条件は、それ以前の王朝よりも厳格であった。年齢は主に10歳未満に制限され、地方の最高位の行政長官の推薦が必要であった。武則天の治世中、裴耀青は8歳で『毛詩』『商書』『論語』の試験に合格した。 11歳で少年試験に合格した王秋という人もいました。他の人が経文を暗唱しているときに、彼だけは作文を書かなければならなかったので、有名になりました。 男子は官吏の資格を取得してから、官吏に任命されるまでにどれくらい待たなければならないのでしょうか。裴耀青と王秋を例に挙げてみましょう。裴耀青は8歳で科挙に合格し、20歳で書記に任命されました。つまり、彼は20代になるまで任命されなかったということです。王丘は20歳になって科挙に合格して初めて鳳里郎に任命された。しかし、30歳で官吏の資格を取得し、40歳でようやく就任できるという平均的なレベルの人々と比較すると、男の子が就任できる時期ははるかに早い。そのため、息子を官吏にしたい親は、この近道を利用したいと考え、小細工は避けられない。 そこで唐の徳宗皇帝の時代に、礼部大臣の楊万がこの「吉兆の道」の廃止を求める申文を提出した。今後の決定がないまま中断され、再開されたという事実は、それがどれほどの論争を呼んだかを示しており、それはおそらく、今日の「数学オリンピック」を開催すべきかどうかという議論に匹敵するだろう。 |
<<: 唐代には、官吏になるには科挙に加えて推薦も必要でした。
>>: 最善の政治戦術は何でしょうか?趙匡胤は誠実さをもって国を征服する方法を教える
推薦する
『黄帝内経素文』第三章「気生通天論」
黄帝は言った。「古来より、知る者は生命の起源が陰陽に基づいていることを知っていた。」天と地の間、六方...
『封神演義』の李静は強いですか?李静の師匠は誰ですか?
『封神演義』の李静は強いのか?李静の師匠は誰なのか?『興国史』編集者が詳しい記事をお届けします。李靖...
『紅楼夢』で、王希峰はなぜ蔡霞と賈歓の結婚を阻止しようと必死だったのでしょうか?
封建社会の女性は最も哀れな存在でした。裕福な家庭の女中たちにとって、結婚は親でさえ決められないことが...
「竹林の七賢」という名前はどのようにして生まれたのですか? 『晋書・済康伝』にはどのように記録されているのでしょうか?
竹林の七賢とは、魏末期から晋初期の有名な学者7人、阮済、季康、善涛、劉霊、阮仙、項秀、王容を指します...
『于洛春:道西不作叢栄主』の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
玉露春・桃溪は平穏に生きていない周邦厳(宋代)桃渓にはレジャーで泊まる場所がなく、秋のレンコンは枯れ...
子年生まれの姓がXunの男の子にどんな名前を付けたらいいでしょうか? 「Xun」という姓に合う、高得点の二文字の名前のおすすめ!
本日は、Interesting Historyの編集者が、姓がXunの高得点の2文字の名前のおすすめ...
唐代の重要な軍事書『太白陰経』全文:人略第一部:心を探る章
『神機滅敵』は『太白陰経』とも呼ばれ、道教の著作です。古代中国では太白星は殺生の達人であると信じられ...
東漢の名将である傅俊と雲台二十八将軍の一人である傅俊の生涯について簡単に紹介します。
傅俊(?-31)、号は紫微、潘川県襄城の人。もともと襄城の村長であったが、劉秀が反乱を起こした後、劉...
「翡翠の少女はどこで私にフルートの演奏方法を教えてくれるのでしょうか?」の「翡翠の少女」とは誰ですか?なぜこの詩は教科書に載らないのでしょうか?
今日は、おもしろ歴史編集長が「玉娘はどこで笛を教えているのか」の「玉娘」とは誰なのかをお伝えします。...
「水滸伝」で最後に登場し、良い結末を迎える主人公は誰ですか?
『水滸伝』で最後に登場したが、良い結末を迎えた英雄は誰でしょうか?この人物は、涼山の108人のリーダ...
『新説世界物語・賞賛と評判』第73条の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
有名な古代書物『新世界物語』は、主に後漢末期から魏晋までの著名人の言行や逸話を記録しています。では、...
リー族の結婚習慣の民族的特徴は何ですか?
黎族の結婚と家族の確立は、黎族社会の発展の産物であり、母系社会と父系社会の特徴を併せ持ち、封建社会の...
張中蘇の有名な詩句を鑑賞する:夢の中で峠をはっきりと見たが、金威への道は分からない
張仲粛(769年頃 - 819年頃)は唐代の詩人で、雅号は慧之としても知られています。彼は富里(現在...
古典文学の傑作『前漢演義』第61章:韓信が夏越と張同を殺す
『西漢志演義』と『東漢志演義』は、もともと『江暁閣批判東西漢通志演義』というタイトルで、明代の中山の...
岑申の古詩「春に南使に会って趙志胤に贈る」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「春に南使に会い、趙知胤に贈る」時代: 唐代著者: セン・シェン正座して、心は春に酔いしれ、菊...