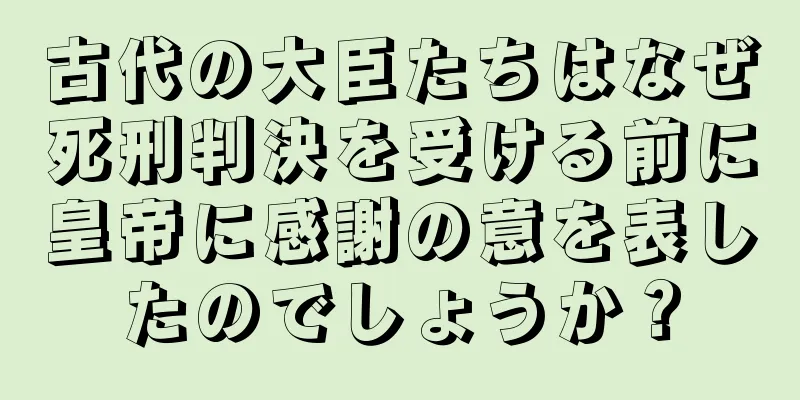太平広記・第80巻・錬金術師・張時政の原作の内容は何ですか?どう理解すればいいですか?

|
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初期までの記録物語を主にまとめた雑集で、分類書である。著者は宋代の李芳、胡孟、李牧、徐玄、趙臨季、王克珍、宋白、呂文忠など14名。宋代の太平興国年間に完成し、『太平毓覧』と同時期に編纂されたため、『太平広記』とも呼ばれる。次に、Interesting History の編集者が、皆様のお役に立てればと、関連する紹介をさせていただきます。 太平広記·第80巻·錬金術師·張時正 【オリジナル】 唐王は荊州に隠れ、庶民の張世政は傷の治療に長けていた。ある兵士が足を負傷し、張さんに治療を依頼した。張さんは薬酒を飲んで肉を割り、指2本分ほどの骨片を取り出し、軟膏を塗って密封したところ、数日後には元通りになった。 2年以上経った後、彼は突然すねに痛みを感じ、再び張さんに尋ねました。張さんは「以前感じた骨の痛みは冷えが原因でした。すぐに探した方がいいですよ」と言いました。確かにベッドの下で見つかりました。お湯で洗って脱脂綿に包んで保管するように言われ、痛みはすぐに治まりました。王子の弟たちは王子と親しい友人であり、よく魔法の技を習うように王子に頼んでいた。張さんは草を一掴みして何度もこすったところ、草はすべて蛾になって飛び去っていきました。壁には、コップに水を満たし、一滴も残さず飲んでいる女性の絵もありました。ためらいながら、絵の中の女性は半日ほど顔を赤らめていた。彼の技術は誰にも受け継がれなかった。 (『易氏』より) 【翻訳】 唐の時代、王迪が荊州に駐在していたとき、外傷による骨折の治療に長けた張世正という老人がいた。ある兵士が足を骨折し、治療のために張時政のもとを訪れた。張さんはまず彼に薬酒のようなものを飲ませ、それから肉を切り開き、指二本分ほどの折れた骨片を取り出し、切り口を軟膏で塞いだ。数日後、負傷した足は回復し、以前と同じように見えました。 2年以上経って、突然足が痛み始めたので、兵士は再び張世正に尋ねに行きました。張さんは言いました。「前に取り出した骨が冷たくて、足が痛いのです。すぐに探しに行きなさい。」案の定、ベッドの下に骨が見つかりました。張さんはそれをお湯で洗って脱脂綿の中に隠すように言いました。すると男性の足の痛みはすぐに治りました。王倩の弟子たちは張世征によくいたずらをしたり、ゲームで手品を見せるように頼んだりした。張世正は一握りの草を取って何度も手でこすったところ、草はすべて小さな蛾になって飛び去っていきました。それから彼は壁に女性を描き、彼女にワインを一杯注ぎました。彼女はそれを一滴も残らなくなるまで飲みました。しばらくすると、絵の中の女性は長い間顔を赤らめていました。張世正は自分の魔法を他人に伝えることはなかった。 |
<<: 太平光記・第80巻・錬金術師・周銀科を翻訳するには?具体的な内容はどのようなものですか?
>>: 太平光記·第80巻·錬金術師·陳秀福をどのように翻訳しますか?具体的な内容はどのようなものですか?
推薦する
劉易卿の『陳易大孝』が創作された背景は何ですか?
劉易清(号:季伯)は南北朝時代の作家で、宋の武帝劉毓の甥である。劉毓は『冥界記』と『奇蹟記』を著した...
もし張飛が部下によって殺されていなかったら、劉備は夷陵の戦いに勝利できたでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『西遊記』の比丘王とはどんな人物ですか?誕生日の人はなぜ長寿の日付をあげるのでしょうか?
比丘王国の物語は、通天河、三島、五荘寺と密接に関係しています。 Interesting Histor...
何洵の「胡星安に別れを告げる夜」:この詩はまさに「感動的で深い」
南朝梁の詩人、何洵は、字を中厳、東海譚(現在の山東省蒼山県長城鎮)の人である。何承天の曾孫、宋の何毅...
北周の明帝、宇文禹の妻は誰ですか?宇文禹には何人の妻がいましたか?
宇文禹(534年 - 560年5月30日)は、通称童湾図と呼ばれ、代県武川の出身。北周の文帝宇文泰の...
「卜算子·我住长长」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
【オリジナル】私は揚子江の源流に住んでいて、あなたは揚子江の下流に住んでいます。毎日会えなくて寂しい...
蘇軾の連作詩『陶淵明風九詩』はどのように書かれたのでしょうか?
ご存知のとおり、蘇軾は唐宋の八大家の一人で、文学の才能に恵まれています。それでは、彼の詩集『陶淵明風...
『紅楼夢』では、西仁は常に高潔な人物だったのに、なぜ青文をろくでなしと呼んだのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
乾隆帝の7番目の娘、和静公主の簡単な紹介
和靖一公主(1756-1775):乾隆帝の7番目の娘。乾隆帝の治世21年、1756年7月15日に生ま...
『太平広記』第300巻の神代の原文は何ですか?
河東県の副長の妻である杜鵬菊、三人の衛兵、李曦、葉静能、王長齢、張嘉有ドゥ・ペンジュ景隆の末期には、...
晋の明帝、司馬紹には何人の子供がいましたか?司馬紹の子供は誰でしたか?
明晋の皇帝司馬紹(299年 - 325年10月18日)は、字を道済といい、晋の元帝司馬睿の長男で、晋...
『紅楼夢』で、周睿の妻はなぜ密かに二人の女中を縛り、王希峰に罪を押し付けたのでしょうか?
周睿夫人は王夫人の女中であり、冷子星の義母であった。ご存知ですか、次の興味深い歴史編集者が説明します...
梁宇勝の武侠小説に登場する有名な人物で、「毒手狂乞食」の異名を持つ金世易の簡単な紹介
梁玉生の武侠小説に登場する有名な人物。通称「毒手狂乞食」。彼が行くところはどこでも、醜い民衆を怖がら...
項羽の義父である范増はなぜ追放されたのか?結局、彼は帰宅途中にうつ病で亡くなった。
樊増とは誰ですか?なぜ項羽は樊増を「父」と呼んだのですか?なぜ最後に追い払ったのですか?樊増は項羽の...
「言論の自由に関する5つの詩、第3号」の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
自由談義の詩 5 篇 第 3 節白居易(唐代)亀の甲羅やノコギリソウの茎を使わずに疑問を解決する方法...