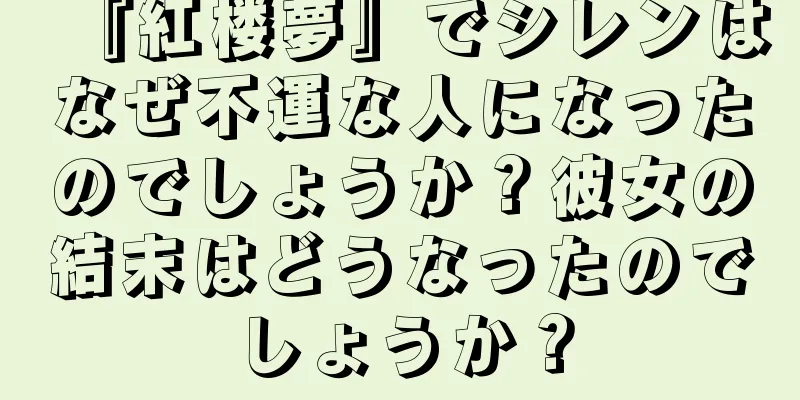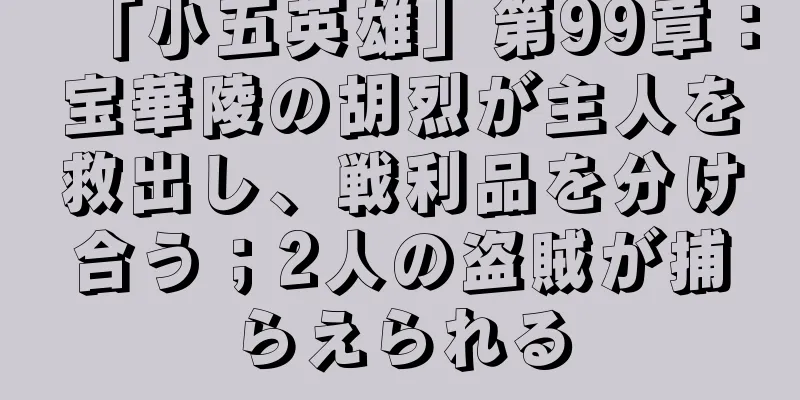交台堂のレイアウトの特徴は何ですか?宮殿の宝物は何ですか?

|
交泰殿は、北京の故宮の内庭の奥にある 3 つの宮殿のうちの 1 つです。交泰殿の名称は『易経』に由来しており、「天と地の合一、健康と幸福」を意味します。 では、交泰殿の配置の特徴は何でしょうか?また、交泰殿を守っている宝物は何でしょうか? 歴史的起源 明の永楽18年(1420年)に完成しました。清朝の嘉慶年間に再建されました。 建物の特徴 交泰殿は正方形の平面で、幅と奥行きがそれぞれ3部屋ずつあり、尖角の黄色い釉薬瓦屋根と金箔屋根が特徴で、中和殿より小さい。ホール内には玉座があり、玉座の後ろには乾隆帝が書いた「交台殿銘」が刻まれた4枚の衝立があります。 ホールの屋根の中央には8階建てのケーソンがあります。屋根は片軒で四隅が尖っており、屋根の上部は銅でメッキされ、黄色い釉薬をかけた瓦が葺かれ、梁には龍や鳳凰、篆刻が描かれている。 主室の四方には扉があり、三交六椀の菱形の扉と、龍と鳳凰の裾板がそれぞれ4つずつある。南側の副室には敷居窓があり、他の3面の副室はすべて壁になっている。ホールの天井には真珠を持った龍が描かれた天井があり、床には金色のレンガが敷き詰められています。殿内の主室には玉座があり、そこには康熙帝が書いた「武威」の額が掛かっている。玉座の後ろには乾隆帝が書いた「交台殿銘」の衝立がある。東の部屋には銅製の梵鐘がありましたが、乾隆帝の時代以降は使われなくなりました。 交泰殿の西側の部屋の片側には嘉慶3年に作られた自動鳴時計があります。宮殿内の時間はこれに基づいています。この鐘時計は高さ約6メートルあり、中国最大の古代の置時計です。 宮殿内のもの 二十五の宝物は皇帝が権力を行使するために使用した印章です。乾隆13年(1748年)、皇帝は皇帝の権力を表す二十五の宝物を交泰殿に置きました。これらの皇帝の印章は内閣によって統制され、宮殿の監督官によって管理されていました。使用するには皇帝の承認が必要でした。ここに保管されている各皇帝の印章はそれぞれ用途が異なり、「皇帝の印章」は進士を入閣させる際に勅令を発布したり、皇帝の名簿を発表したりするために使われ、「法印」と「明徳印章」は大臣を指導したり、官吏に褒賞を与えたりするために使われ、「六軍を統べる印章」は軍事に使われます。印章は黄色い絹で覆われた宝箱に収められており、現在もその宝箱は元々の位置に保たれて、交台殿に展示されています。 銅製のケトル クレプシドラ: クレプシドラとも呼ばれ、古代中国のタイマーです。 3000年前にはすでに、中国の人々は時計器を使った時間計測法を発明していました。交泰殿に展示されている銅製の梵字梵字梵字は、乾隆帝の治世10年(1745年)に作られたもので、中国で現在まで残っている梵字梵字梵字の中で最も保存状態が良い梵字梵字です。 大型自鳴時計:交泰殿に展示されている大型自鳴時計は、嘉慶3年(1798年)に清宮内務省によって製作されたものである。外殻は中国風の亭を模した木製の箱で、高さは5.8メートル、上層、中層、下層の計3層構造となっている。時計台の裏側には小さな階段があり、その階段を上って時計を巻くことができます。自動鳴動時計が動き出すと、自動的に時間を鳴らすことができます。この鐘時計は200年もの間存在し続けていますが、今でも正常に正確に作動し、時を告げる音は明瞭で大きく響きます。これは、その製造プロセスが非常に洗練されていることを示しています。 |
<<: 漢宮春朝図の何がそんなに素晴らしいのでしょうか? 「漢宮の春の朝」の背景にある物語は何ですか?
>>: 道連図切手はなぜ人気があるのでしょうか?道連図切手にはコレクション価値があるのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』で賈家の財産を最終的に没収したのは誰ですか?まさに北京の王様
賈家は名家であり、世襲称号を持つ公爵邸でもある。これについて言及するたびに、詳細をお話ししなければな...
前秦の創始者、傅洪の物語。傅洪に関する興味深い話にはどんなものがありますか?
傅洪(285-350)、号は広氏、本名は普洪、洛陽臨衛(甘粛秦安市龍城)の人。ディ族に属し、部族長普...
第4弾人民元2角紙幣の特別バージョンは何ですか?
人民元第4セットでは、1980年の20セント硬貨は市場で8002という数字の別名を持っています。この...
婉曲的で愛情にあふれた李白の最も優しい詩は、恋煩いの傑作となる
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が李白につい...
『紅楼夢』で賈宝玉が殴られたのはなぜですか?薛家とは何の関係もないが、薛家内で争いを引き起こした
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
野呂一烈の紹介 廖仁宗野呂一烈は生涯で何を成し遂げたのか
遼の仁宗皇帝野呂一烈は、遼の徳宗皇帝野呂大師の息子であり、契丹族の一員であり、西遼の3代目の君主であ...
水滸伝の英雄たちはなぜ脂身の多い肉を好むのでしょうか?
水滸伝の英雄たちを知らない人は多いでしょう。『おもしろ歴史』編集者と一緒に、彼らの魅力を知りましょう...
明代玄宗皇帝の胡善祥皇后朱瞻基と胡公璋皇后の生涯についての簡単な紹介
「公朗張皇后」胡善祥(1402-1443)は、明の玄宗朱湛基の最初の妻であり、刺繍制服衛兵隊の隊長胡...
ヤン・レンの「木蘭花・春風は庭の西にのみ吹く」:この詩は閨房のための作品である
顔人(1200年頃生きた)は、雅号を旗山、雅号を喬曦といい、邵武(現在の福建省)の出身であった。生没...
詩人楊万里のカモメへの真摯な愛情を描いた「昭君元・松梟歌」鑑賞
楊万里(1127年10月29日 - 1206年6月15日)は、字を廷秀、号を程斎、程斎野客と号した。...
唐寅の『酒を飲み月を向く』:作者は常に李白と自分を結びつけている
唐寅(1470年3月6日 - 1524年1月7日)、号は伯虎、号は子維、別名は六如居士。蘇州府呉県南...
明代の衣服:明代の学者の帽子
明代の学者がかぶっていた帽子は主に四角い平たいスカーフでしたが、中には後ろに2本のストラップが垂れ下...
杜甫の『朝雨』:読者の自然の純粋な美しさへの憧れをかき立てる
杜甫(712年2月12日 - 770年)は、字を子美、号を少陵葉老といい、唐代の有名な写実主義詩人で...
沈全奇の『喬智之に贈る古義:科挙補遺』:岳府の古称「杜不堅」を借用
沈全奇(656年頃 - 715年頃)、号は雲青、湘州内皇(現在の安陽市内皇県)の出身で、祖先の故郷は...
司馬炎は少数民族をどのように扱ったのでしょうか?太康の統治の具体的な現れは何ですか?
司馬炎は少数民族に対する待遇として宥和政策と征服政策を組み合わせた政策を採用したが、一部の役人はこの...