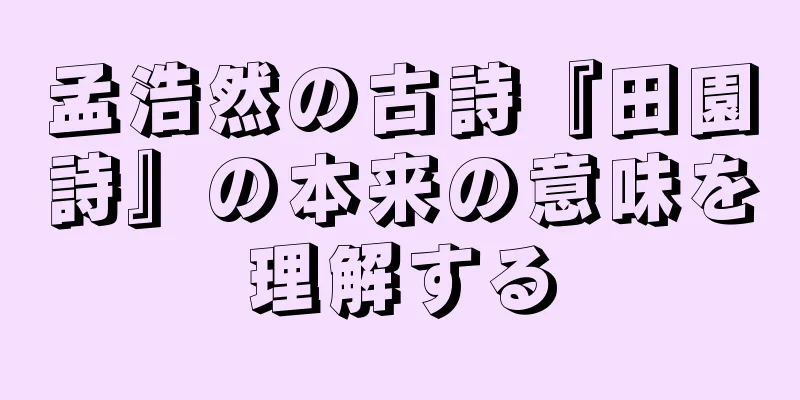なぜ幕府維新ではなく明治維新なのでしょうか?

|
1860年3月3日、孝明天皇の安政7年目の朝、空から大雪が降り始めました。北緯35度に位置する江戸城では、春の大雪は異例のことだった。しかし、鉄拳で知られ「赤鬼」の異名を持つ徳川幕府老中、井伊直弼は、伝統に従って上申祭を執り行うため、江戸城内に入城した。午前9時、衛兵が井伊直弼を乗せた輿を取り囲み、江戸城本丸桜田門前に到着すると、まるで輿を止めて文句を言おうとするかのように、一人の人物が歩み寄ってきた。井伊直弼の二人の従者はすぐに彼を止め、何が起こっているのか調べる準備をしました。しかし、その瞬間、その人物は突然、日本刀を取り出し、何も知らない侍長の頭に切りつけたのです。同時に、鋭い銃声とともに、道路の両側から十数個の黒い影が馬車に向かって突進してきた。数人の衛兵を切り倒した後、二つの黒い影が馬車の前に駆け寄り、井伊直弼を引きずり出し、一刀でその首を切り落とした。 これは、18人の熱血青年たちが徳川幕府の最高権力者を幕府の隠れ家で衆人の前で殺害した、近代日本史上有名な桜田門外の変です。この事件は徳川幕府に大きな打撃を与えたが、日本中の志士たちに限りない自信と勇気を与え、8年後の明治元年に向けての奮起を促した。そのため、桜田門外の変は伝統的に明治維新の導火線とされ、桜田門前に倒れた若き志士たちは日本の近代化の先駆者であった。 しかし、これは伝統的な見方に過ぎず、その表面の裏にはもっと衝撃的な真実が隠されています。 なぜ野党は井伊直弼を殺そうとしたのか。それは、井伊直弼が「安政の大獄」を起こし、吉田松陰をはじめ100人以上の政敵を弾圧・迫害し、死刑に処せられ、野党の憎悪の対象となったからである。 では、なぜ井伊直弼は「安政の大法要」を起こしたのでしょうか。それは、孝明天皇が幕府権力に反対する者に対して「凡武の密勅」を発令し、それが井伊直弼の目に留まったため、幕府の権威維持のため大規模な政敵粛清を決意したからです。 では、なぜ孝明天皇は「奉武の密勅」を発布したのか。それは、天皇や野党が、井伊直弼率いる幕府が日米修好通商条約など数々の公然の条約に調印したことに不満を抱いていたからである。これらの条約は自由貿易と国の商業開国を認め、日本を西洋諸国に開放し、200年以上続いた日本の鎖国を終わらせた。天皇と野党は「攘夷」を要求し、鎖国政策を維持し、すべての外国人を日本から「追放」した。そこで天皇は、第一に外国との条約締結に反対し、第二に幕府の改革と朝廷の権力強化を要求する密勅を発布した。 孝明天皇 なんと衝撃的な史実でしょう!実は開国を唱えたのは井伊直弼と幕府であり、明治維新に反対し鎖国を主張したのは野党の「志士」たちだったのです!確かに日本近代化の先駆者は桜田門前に散りましたが、その先駆者は「志士」ではなく、井伊直弼だったのです! 倒幕運動の初期段階では、幕府の統治に反対する倒幕派のスローガンは「尊皇攘夷」であったため、この段階の倒幕派は尊皇派とも呼ばれていたことが判明しています。いわゆる「尊皇」とは、幕府の権力を奪うことであり、当初は権力の一部の共有、すなわち「公武合一」を求めたに過ぎなかった。公武合一とは、朝廷(通称公家)のことで、武士とは徳川幕府の武士政権(通称武士)のことである。 「朝武合」とは、権力のない朝廷が武士と権力を分かち合うことを意味したが、後に幕府全体を倒そうとする試みへと発展した。その理由は「攘夷」、つまり幕府の開国政策が幕府の無能さと売国行為の表れであると考え、これに反対するためであった。討幕派にとっては「尊皇」が目的であり、「攘夷」が理由であり、幕府が「攘夷」に無能であるからこそ、「尊皇」して幕府を倒さなければならなかったのである。清国反対運動が盛り上がっていた時代、清国反対の浪士たちは「孫子志士」に変装して、刀を携えて一日中街を歩き回り、建国を唱える「裏切り者」を見つけると「天罰だ」と叫び、刀で切り倒した。井伊直弼を暗殺したのは、この「志士」集団だった。 時が経つにつれ、反清朝派は次第に「攘夷」思想の遅れと非現実性に気づき始めた。特に、1863年の薩英戦争、1864年の下関戦争以降、討幕派の二大勢力であった薩摩藩と長州藩は相次いで欧米諸国の進出を実感し、次第に「攘夷」から「開国」へと思想が変わっていった。 これは幕府の政策が実は正しく、討幕運動全体が不当なものとなることを意味するが、討幕派はそれを決して認めないだろう。彼らは無能で裏切り者の幕府権力を打倒するというスローガンを叫び続け、徐々に幕府を窮地に追い込んでいったが、同時に密かに「攘夷」のトーンを下げていった。幕府が崩壊し、明治政府が樹立されると、新政府は突然態度を変え、もはや「攘夷」という言葉を使わず、明治維新を開始した。 これを読んで、幕府は本当に不当な扱いを受けたとため息をつく人もいるかもしれない。明らかに正しい「開国」政策だったのに、討幕派から反逆罪で訴えられたのだ。しかし、討幕派が政権を握ると、彼ら自身が「売国」を始めたのだ。しかし、滅亡した幕府は汚名を晴らす術もなく、時が経つにつれ次第に反動的な封建勢力の代表とみなされるようになった。 しかし、これは歴史の表面的な現れに過ぎず、その背後にはより深い問題がまだ隠されています。 明治時代は大成功を収めたのに、なぜ幕府は倒されたのか。ある日、日本人は「攘夷」を叫んで幕府の逆賊を倒し、翌日には明治天皇に従って西洋の「文明開化」を学んだのはなぜか。 これまでの分析から、幕府と倒幕派の闘争は、実は改革派と保守派の闘争ではなく、二つの勢力間の権力闘争であったことがわかります。究極的には両者とも改革を望んでいたが、唯一の違いは明治維新を望むか幕府維新を望むかということであった。幕府が滅亡したのは、井伊直弼の開国政策に間違いがあったからではなく、幕府が犯した一連の過ちによって統治の正当性が失われ、最終的に権力闘争に敗れたためである。 幕府の統治の正当性が失われたのは、主に長期にわたる鎖国政策によるもので、この鎖国政策は日本を貧困と弱体化に導き、西洋列強の「黒船」に全く抵抗できずに面目を失うに至った。当然、これは統治者に対する国民の信頼を大きく損なうことになるだろう。その後、幕府は西洋列強との死闘を放棄し、開国条約を締結することを選びました。今日の視点から見れば、これは確かに現実的で賢明な選択ですが、当時は、長い間封建教育によって心が閉じ込められていた一般大衆にとって、それを受け入れることは困難でした。この時、井伊直弼率いる幕府は、朝廷や天皇の意見を待たずに日米修好通商条約を締結したり、反対派に対して安政の大獄を決行するなど、無条件の強硬策をとった。これらの措置は、社会的対立を緩和し、人々の理解を得ることはできなかったばかりか、対立を激化させ、他者を有利にし、自らを世間の非難の的とした。また、日本では数百年にわたる徳川幕府の高圧的な統治により、天皇や大名から庶民に至るまで、誰もが幕府の統治に長い間不満を抱いていました。この時期、西洋の侵略者の抑圧により、当然のことながら、民衆はよりひどい状況に陥っています。少しでも反幕府派を刺激すれば、新旧の恨みが表面化し、すべての責任が幕府に押し付けられるのは簡単です。 したがって、結局のところ、幕府の最終的な滅亡は幕府自身の責任である(開国政策そのものを責めるべきではないが)。幕府の長期にわたる暗黒封建政治が、幕府自身の統治の正当性を破壊したのである。実際、矛盾の激化と正当性の欠如が臨界点に達すると、おそらく奇跡でもない限り、いかなる改革政策も非改革政策も幕府を救うことはできなかった。井伊直弼の悲劇は、彼が幕府の権力を握ったとき、表面上は幕府が依然として強力であるように見えたが、この臨界点は越えられていたか、少なくともそれに非常に近かったこと、そして彼の愚かな政策措置が幕府がこの臨界点をさらに越えることを確実としたことであった。一度臨界点を超えると、幕府の運命は決まり、改革すれば尊攘派の攻撃を受け、改革しなければ世の流れに逆らって最終的には滅亡の運命から逃れられなくなる。 日本が最終的に幕府維新ではなく明治維新を選んだという事実は、政府改革が成功するかどうかは、政府が依然として統治の正当性を持っているかどうか、そして国民の信頼を依然として獲得できるかどうかにかかっていることが多いことを示しています。清朝末期の中国の状況も実は非常に似ていました。清朝末期の清政府のニューディール政策の方向性も改革と憲法制定だったが、国民はもはや清政府を信頼していなかった。中国の革命家たちはこの微妙な状況を賢明に把握した。そのため、同門会の綱領はまず「タタール人を追放し、中国を復興する」と述べ、清朝の外国人支配の違法性を直接指摘し、次に「共和国を樹立し、土地の権利を平等化する」と述べ、これは同会の政治綱領の単なる序文に過ぎなかった。張太燕はもっと正直にこう言った。「反逆する蛮族は我々の同族ではない。もし彼らが法律を改正できないなら、彼らを改正すべきだ。もし彼らにできるなら、彼らも改正すべきだ。もし彼らが民を救えないなら、彼らを改正すべきだ。もし彼らにできるなら、彼らも改正すべきだ!」つまり、革命を起こすかどうかは、法律を改正するか民を救うかの問題ではなく、あなたを排除することの問題なのだ。あなたを殺す理由は何ですか?あなたは外国人であり、正当性がないからです!この論理は、今日の合理的な考え方では意味をなさない。民主共和国の基盤は万人の平等です。なぜ満州人が中国の指導者になれないのでしょうか。しかし、当時の革命党のこのアプローチは実際にうまくいきました。なぜか?それは、清朝が幕府と同じく、最後の改革のチャンス(同治新政から八ヶ国連合軍の中国侵攻までの約40年間)を逃し、矛盾激化と正当性喪失の臨界点を超え、制御不能な状況に陥ったためである。どんなに改革しても無駄であった。 過去の経験は将来への教訓です。徳川幕府と清政府の悲劇は、改革には時間的余裕があり、改革がいつでも成功するとは限らないことを教えてくれます。社会矛盾と正当性の危機の蓄積が臨界点を超えると、その時点で政府がいかに強力に見えても、実際には運が尽きているのです。したがって、私たちは「改革が行われない危機よりも、『不完全な』改革が行われることを望む」のです。 |
<<: 明治維新の先駆者、坂本龍馬の紹介 坂本龍馬はどのように亡くなったのか
>>: 西魏の梁滅亡の戦い:転置の思想が十分に発揮された戦い
推薦する
古典文学の傑作『夜の船』:文学部全文と短い手紙
『夜船』は、明代末期から清代初期の作家・歴史家である張岱が著した百科事典である。この本は、あらゆる職...
漢の武帝はなぜ西王母を崇拝したのでしょうか?東漢の民間墓から西王母の宴会の絵が発見された!
今日は、興味深い歴史の編集者が、漢の武帝が西王母を崇拝した理由をお話しします。皆さんのお役に立てれば...
覚醒世界物語第12章:李観茶が苦情を収集し、朱推観が考えを変えて法律を施行する
『婚姻天下開闢』は、明代末期から清代初期にかけて習周生が書いた長編社会小説である。この小説は、二人の...
孫光賢の「故里を想う・如」:この詩は「情緒」という言葉を中心に展開される。
孫光賢(901年 - 968年)は、孟文と号し、宝光子と号し、陵州桂平(現在の四川省仁寿県湘家郷桂平...
『清平月 博山行物語』の制作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
清平楽:博山への道新奇集(宋代)蹄鉄が柳の横を飛んでおり、露が重い旅の服を濡らしている。ねぐらにいる...
『紅楼夢』における秦克清の判決は何でしたか?彼女はなぜ賈震と不倫関係になったのか?
秦克清は『紅楼夢』の登場人物であり、金陵十二美女の一人である。次はInteresting Histo...
秦漢時代の靴と靴下:秦漢時代の人々はどのような靴を履いていたのでしょうか?
秦漢時代には靴の種類が多く、主に靴、サンダル、下駄、草履、長靴、ブーツ、長靴などがありました。 Lu...
Zhan Zhao は何を間違えたのでしょうか?鮑正はなぜ瞻昭を処刑したのですか?
今日、Interesting Historyの編集者は、なぜ鮑正が仕方なく瞻昭を処刑しなければならな...
黎族は時間の概念をどのように分けているのでしょうか?
時間の概念は、人々が太陽について理解していることから生まれたのかもしれません。一日を通して太陽の位置...
明代『志譚(抜粋)』:軍事情報部狄青全文と翻訳注釈
『シンクタンク全集』は、明の天啓6年(1626年)に初めて編纂された。この本には、秦以前の時代から明...
東晋の才女、謝道雲の代表作『泰山歌』鑑賞
謝道源(ゆん)は生没年不詳、号は霊江。楊夏陳君(現在の河南省周口市太康県)の人。東晋の宰相謝安の姪、...
「夕焼け」を鑑賞するには?著者は誰ですか?
日没杜甫(唐代)牛や羊は長い間伏せており、皆が木の戸を閉めていました。風と月は澄んだ夜にありますが、...
チワン族の伝統楽器「三弦」の紹介
チワン族の三弦楽器はチワン族の撥弦楽器です。その形は漢族やラフ族の小三弦に似ており、音色は鮮明で明る...
イ族の少数民族の習慣は何ですか?
イ族の習慣と風習:生存と発展の必要性を満たすために、イ族の祖先は非常に早い時期に分派を形成しました。...
「正禄閣の夜」を鑑賞するには?著者は誰ですか?
正禄閣の夜李白(唐)船は広陵に下り、月が正禄閣を照らします。山の花は刺繍の頬のようであり、川の火はホ...