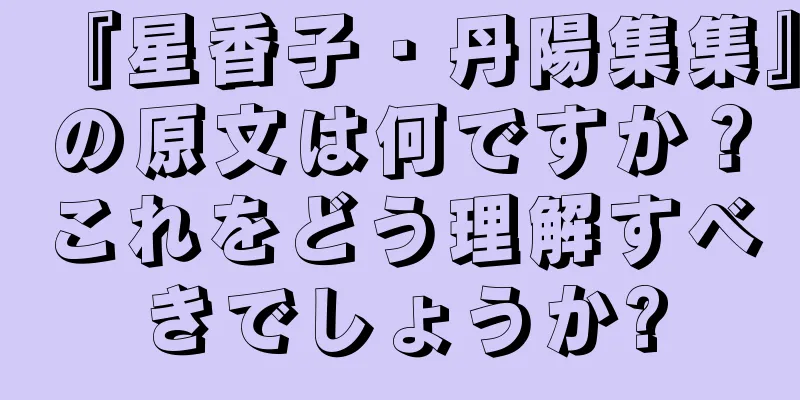「一代の官吏は九代絶える」の次の文は何ですか?なぜそんなことを言うのですか?

|
本日、Interesting History編集長が「一代の官吏が九代絶える」という次の一文をお届けします。皆様のお役に立てれば幸いです。 「常語」という言葉は、西漢の司馬遷の『史記』にある朱少孫の「西門豫の鄴治」という記事で初めて登場します。「民衆の間でよく言われているのは、『河神に嫁を取らなければ、水が来て民を溺れさせる』というものである。」 ことわざの言葉はシンプルだが、大きな知恵が含まれている ことわざは、古代の労働者が生活の中で蓄積した一種の定型的な文章です。私たちの日常生活では、ことわざをよく聞いたり使用したりします。たとえば、「朝焼けが明るいときは外出するな、夕焼けは何千マイルも旅する」という古典的なことわざは、ほとんどすべての人に知られており、かつては教科書にも掲載されていました。これは、その実用性を示しています。 口語表現は非常に単純で、一般的に非常に簡潔であり、その表現は話し言葉に非常に近いです。 しかし、このような短い文章の中に、人生のあらゆることが非常に生き生きと合理的に表現されており、これは古代人の知恵の結晶であると言わざるを得ません。 ことわざは生活の中から生まれ、生活の中で応用されるもので、昔の人が人生の些細なことや願いを長い年月を経てまとめ、後世に口伝えに伝えた経験の言葉です。 「一代の官吏は九代絶える」という諺があります。次の一文は古典であり、先祖が残した偉大な知恵です。 1世代の役人が9世代にわたって絶え、貧しい農民が新たな一歩を踏み出すのは難しい 「一代が官吏をすれば九代絶える」この文は、主に旧社会における農民の生活状況を指している。 昔、我が国の官僚制度は不健全な傾向を抑制することができず、素行の悪い人が官僚になれば、庶民が苦しむことになりました。古代では、官僚が庶民を搾取する現象が非常に深刻で、貧しい農民は9世代にわたって状況を立て直すことができない可能性が非常に高かった。 しかし、もう一つの現象があります。それは、役人自身の家が9代にわたって事態を立て直すことができなかった状況です。 役人が悪行で処罰されれば、その子孫が困ることになる。 まず、この文中の「九世代」は、特定の九世代を指すのではなく、一般的に数世代を指します。この文のもう一つの意味は、ある世代の朝廷で官吏として仕える人がいて、もしその人が何か悪いことをしたり、皇帝に対して不忠な行為をしたりした場合、その子孫が関与する可能性が高いということです。 「十人の役人のうち九人は腐敗している」と言われています。古代では、役人になると非常に貪欲で暴力的になる人が多くいました。これらの人々は権力を握ると、さまざまな悪事を働きました。 彼らは周囲の人々を抑圧し、排除し、中には路上で無謀な行動をとったり、農民の労働の成果を略奪したりする者もいる。そのような行為は当然誰もが嫌うものとなるでしょう。 そして、もしこれらの役人が、怒らせてはいけない人を怒らせた場合、注意しないと彼らは破滅するでしょう。悪事を働いた官僚たちが死んだ後、かつての敵が復讐し、子孫が苦しむことになる。こうして、彼らの子孫は当然「九代絶滅」することになる。 皇帝と一緒に暮らすのは虎と一緒に暮らすようなものだ。何か悪いことをすれば、家族全員が巻き込まれることになる。 敵からの復讐の可能性以外にも、皇帝に近づくことは危険なことです。これは当時の社会背景と関係があります。 古代は封建社会で、皇帝が全権力を握っていました。皇帝は天下のあらゆる物事に対して最終決定権を持っていました。当時、学者が科挙に合格して宮廷の官吏となることは容易なことではなかった。階級の転換を果たしたとはいえ、実際は皇帝のために働いているのである。 『朔虎全伝』には、「古代人は言った。『皇帝と一緒にいるのは虎と一緒にいるようなものだ』、だから常に注意しなければならない」と記されている。 古代では、皇帝がすべての事柄の最終決定権を持っており、誰かが誤って皇帝を怒らせた場合、皇帝は通常、容赦なくその人の首を切った。しかし、一人が死ぬだけでは大したことはないが、状況が深刻であれば、その家族全員が巻き込まれる可能性が高く、いわゆる一族九代殺しとなる。 したがって、古代人にとって、役人になることは非常に危険なことでした。何も問題がなければ問題ありませんが、何か問題があれば、それは生死に関わる問題でした。 『史記』によれば、秦の始皇帝が六国を統一した後。かつての属国が反乱を起こすのを防ぐため、「三氏族絶滅」が正式に法典に盛り込まれた。三氏族絶滅は主犯の子孫である男系を全滅させるだけであり、他氏族は対象としなかった。 しかし、後には9氏族、10氏族が処刑されるケースもあった。 皇帝は自らの意志に従って行動し、生殺与奪の権を握っていた。もし部下の役人が彼の意志に従わなかった場合、最も深刻な結果は当然一族全体の処罰となるでしょう。一人が罪を犯した場合、彼の一族全体が関与することになります。 歴史上、そのような例があります。例えば、明代初期、朱元璋が官僚の行政を正したとき、多くの腐敗した官僚とその家族全員が処罰されました。彼らが投獄されただけでなく、彼らの家族の他の構成員も罰せられました。 明代の『実録』には次のようにはっきりと記されている。「建文帝の治世中、小如は文元閣の学者であった。荊南軍が侵入した時、彼は勅令に従うことを拒否し、一族は皆殺しにされた。」 古代では、役人が汚職で捕まると、9世代にわたって絶滅する恐れがありました。 古代では、役人の間での腐敗は許されませんでした。一部の王朝では、皇帝が誰かが腐敗した役人であることを発見すると、その人の財産を没収するだけでなく、処刑することもありました。犯罪がそれほど深刻でない者には、3 つの氏族が関与している可能性があるが、犯罪が比較的深刻な者には、9 つの氏族が関与している可能性が高い。 これは、古代に悪徳官僚だった場合、子孫を残すことはほとんど不可能だったという意味でもあります。これが「九代絶える」ということわざの意味です。 昔の官吏は地位が高く生活に困ることはなかったが、ちょっとした事故で危機に陥り、子孫も巻き込まれることから「一代の官吏は九代絶える」ということわざがある。 この観点から見ると、この文はまだ意味をなしています。すべての物事には長所と短所があり、機会とリスクは共存しています。また、後半の文章も非常に古典的で、社会の現実を十分反映していると言えるでしょう。 文の後半も同様に古典的です。「1 つの家族が裕福になれば、9 つの家族が貧しくなります」 文の後半は「1つの家族が裕福になれば、9つの家族が貧しくなる」です。この文をどう理解すればよいのでしょうか。10 家族のうち 1 家族が裕福になると、残りの 9 家族は貧困に陥り、裕福な家族と貧しい家族の間に強い対比が形成されることを意味します。 言い換えれば、一人の富は他の何千もの家族の貧困を犠牲にして得られたものなのです。 ある地域に汚職した役人がいると、その地域の人々は苦しむことになることが多い。考えてみて下さい。古代の腐敗した役人たちのお金はどこから来たのでしょうか? もちろん、それらは庶民の手から奪われたのです!彼らは官僚としての優位性を利用して民衆を抑圧し、民衆は非常に悲惨な生活を送っていたに違いありません。 収入があまりなかった古代人にとって、このようなことはかなりの頭痛の種でした。多くの人々が搾取されて全財産を失い、腐敗した役人の存在により食べる物さえない家族もいる。 そのため、当時の人々は腐敗した役人を嫌っていました。皇帝が腐敗した役人を根絶することができれば、人々は間違いなく拍手喝采するでしょう。 古代の富豪にとって富裕層になるまでの道は困難であり、彼らは主に民衆の援助に頼っていました。 古代の統治者は小農経済を奨励し、ある程度商業の発展を抑制していたため、そのような社会環境では人々が「豊かになる」ことは困難でした。 もちろん、それでも大富豪になる人はいるが、ビジネスで成功して大富豪になる人は少ない。大抵は役人とのコネで大富豪になり、それを利用して庶民に危害を加える。 これは地主と農民の間の社会的矛盾に似ています。ある一家が裕福になって地主になると、農民を搾取し、土地を奪い、財産を奪うケースが多くあります。これにより、貧しい人々はさらに貧しくなり、彼らの生活は暗く陰鬱になります。 そして、まさにそのような人々の存在ゆえに、人々は悲惨な生活を送っているのです。 一人が金持ちになれば、当然残りの人は困るので、「一家が金持ちになれば、九家が貧しくなる」ということわざがあります。こうしたいわゆる「金持ち」は尊敬に値せず、社会からも認められていない。 この現象は封建社会では非常に一般的だったため、「1 つの家族が裕福になると、9 つの家族が貧しくなる」ということわざがあります。 まとめ 「一代が官吏になれば九代が絶える。一家が富めば九家が貧しくなる」という言葉の真理は、非常に深い。 このことから、古代人が残した格言は、私たちが想像する以上に賢明なものである場合もあることがわかります。数千年前に残された言葉が今でも当てはまるのは、本当に素晴らしいことです。 |
<<: なぜ後代の検閲官は忠臣の評価において魏徴ほど優れていなかったのでしょうか?
>>: なぜ益州の現地学者たちは、外部の勢力が劉璋に代わることを望んだのでしょうか?
推薦する
「覚醒結婚物語」第20章:チャオ・ダシェは家に帰り、夢の中で徐大因が通り過ぎて悪魔を祓うと告げる
『婚姻天下開闢』は、明代末期から清代初期にかけて習周生が書いた長編社会小説である。この小説は、二人の...
涼山にはどんな洞窟がありますか?なぜ楊志は武松の次にランクされているのですか?
涼山の座席配置にどの洞窟が含まれているか分からない読者のために、次の興味深い歴史の編集者が詳細な紹介...
古典文学の傑作「夜船」:九六布・葬送全文
『夜船』は、明代末期から清代初期の作家・歴史家である張岱が著した百科事典である。この本は、あらゆる職...
汪維は民衆を慰めるために検閲官として辺境に派遣され、「外辺」を執筆した。
王維(701-761)、字は墨傑、字は墨傑居士。彼は河東省蒲州市(現在の山西省永済市)に生まれ、祖先...
「六策・文涛・上賢」の原文は何ですか?どうやって鑑賞すればいいのでしょうか?
【オリジナル】文王は太公に尋ねた。「君主として、我々は何をすべきか? 何をすべきか? 何を取るべきか...
『紅楼夢』で、林黛玉が本を読んでいたとき、賈おばあさんは怒っていましたか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
どの王朝以降、女性の結婚は自由ではなくなったのでしょうか?
古代では、女性は結婚すると両親の取り決めに従わなければならなかったという印象を多くの人が持っています...
『紅楼夢』の薛家はなぜ自ら率先して完璧な縁結びの理念を推進したのでしょうか?
『紅楼夢』で言及されている金婚式の象徴は、薛宝才の「金の鍵」と賈宝玉の「魔玉」である。 本日はInt...
蘇州古典庭園の紹介:明代留園の歴史的背景とは?
蘇州の古典的な庭園は春秋時代にまで遡り、晋と唐の時代に発展し、宋の時代に繁栄し、明と清の時代に最盛期...
『後漢書 劉毅伝』の原文と翻訳、『劉毅伝』より抜粋
『後漢書』は、南宋代の歴史家・范業が編纂した年代記形式の歴史書である。『二十四史』の一つで、『史記』...
古典文学の傑作『太平天国』:礼節編第19巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『裴使随行岳陽楼登頂』を鑑賞するには?創設の背景は何ですか?
裴使に随伴して岳陽楼に登る杜甫(唐代)湖は広大で雲が流れ、遅い晴れた空に建物が寂しく佇んでいます。儀...
「東風に酔う・重陽の節句」を書いた詩人は誰ですか?この歌の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】御料水の赤い葉と清流に刻まれ、黄色い花を愛でる人々が歌塔で酔ったように歌っている。空は...
鄭和の西域航海の記録はなぜ消えてしまったのか?もう一度見つけることはできるでしょうか?
周知のように、明朝永楽3年、成祖朱棣は鄭和に大艦隊を率いて航海に派遣しました。鄭和は西太平洋とインド...
宋代の詩の鑑賞:郭垂紅、蒋逵は詩の中でどのような芸術技法を用いたのでしょうか?
宋代の郭垂紅、蒋奎については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!私が作っ...