『史記』の記録によると、戦国時代の各国の人口はどのくらいだったでしょうか?
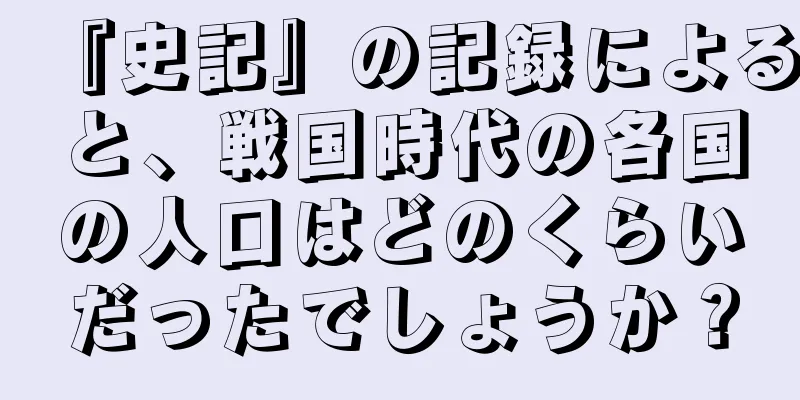
|
『皇紀』には「秦と山東の六州を合わせると、兵力は五百万余り、人口は千万余り」とある。ここでは、戦国時代後期の各国の兵力総数は五百万余り、戸籍数は数千万であったと推測されている。この計算は、一家に二人いれば一人は戦争に行くという仮定に基づいているが、この方法は確かに正確ではない。斉国の首都である臨淄の人口について、歴史書には「臨淄には7万世帯があり、各世帯には少なくとも3人の兵士となる男性がいた」と記されています。これは、臨淄のすべての世帯に少なくとも3人の男性が軍隊に入隊して戦争に行ったことを意味します。各世帯に女性が一人しかいないとすると、臨淄市の人口は少なくとも30万人近くになる。 7 つの国すべてにこのような大都市があります。たとえ各属国にこのような都市が 2 つしかなかったとしても、秦、楚、宋、魏などの裕福な国は言うまでもなく、人口は 400 万人以上になります。 有名な歴史家范文蘭は、秦以前の時代には「兵士5人につき1人の兵士が派遣された」と述べています。この計算は『史記』の計算とは異なります。戦国時代後期の軍隊の総数は500万人以上であったため、当時の軍隊の総数は2500万人を超えていた可能性があります。それで、これは可能でしょうか?次の興味深い履歴エディターが詳細に紹介しますので、見てみましょう! 『史記』には「そこで七十二人の郡長官を召集した」と記されており、斉の衛王の治世中、斉国には少なくとも七十二の郡鎮があったことが分かる。 「大県は2万世帯、中県は1万5千世帯、小県は1万世帯」と言われている。臨淄市では、どの世帯にも少なくとも3人の男性がいる。李逵は「5人家族で100畝の土地を持つ」と言い、孟子は「8人家族は時間を奪われてはならない」と言った。郭堅が呉を攻めた時、「兄弟が4人か5人いる者もいた」とある。これは、春秋戦国時代には、主要な属国では5人以上の世帯が多数存在していたことを示している。この計算を用いると、斉の七十の都市がすべて小県であったとしても、斉の七十の都市の人口は依然として300万から400万人であり、七つの主要な属国を合わせた人口は2000万人強であった。 しかし、斉国の実際の人口はこれよりはるかに多いかもしれません。『管子』には、「一万台の戦車を持つ国は、百万ヘクタールの耕地、百万世帯、千万人の話し手、百万の権利を持つ人々、一万台の戦車、四万頭の馬を持つ」とあります。これは、斉の桓公の時代には、ほとんどの大国の人口が千万人を超えていたことを示しています。斉国は領土を拡大し続け、戦国時代には管仲が信じた「数千万」の勢力にまで達していたと思われる。そして、戦国時代後期には、度重なる争いで人口が減少。斉国は1000万人の人口が減っても、数百万人程度は残っていれば普通だった。 もちろん斉は七国の中では大国だった。戦国時代末期に燕に征服されてから人口が激減し、数千万の属国から400万の属国に格下げされたこともある。しかしやはり大国だった。魯、魏、漢などの小国と比べると、人口規模は依然として大きなアドバンテージがあった。燕はその後反撃を受け斉の領土を失ったが、それでも東北地方の強国であり、領土は非常に広大であった。寒く厳しい地であったが、他国との戦争が頻繁にあり、人口も少なくなく、斉と正面から対峙することもできた。総人口は斉に匹敵する、およそ300万から400万であったと思われる。 春秋戦国時代は、15歳以上の男性は大抵軍隊に従軍することができた。国内に大きな混乱がなければ、男性は60歳前後で引退して故郷に戻ることができた。つまり、この40年間、家出男たちは、家で年老いた両親への孝行も、妻子を養う夫としての責任も果たせなかったのだ。中国は農業文明国です。どの家庭にも必ず農耕に従事する人がいます。年老いた両親は家に留まり、男たちは妻子を残して戦争に出かけます。普通の家庭が一人息子を育てているなら、つまり一家に五人いれば、戦争があるたびに男の一人が軍隊に行くのは当然です。ファン・ウェンランの「兵士5人につき兵士1人」はこれを考慮に入れるべきだ。 秦と楚はそれぞれ百万の軍隊を持っていたと知られています。「一人の兵士は五人から成る」という法則に基づくと、両国の人口を合わせると一千万人になります。数百年前の春秋時代、管仲の心の中の大国はすでに数千万人の人口を抱えていた。燕と斉に匹敵する魏と趙は、秦と戦うために数十万の軍隊を動員することができたので、国内の人口は数百万人になるはずです。 戦国時代後期、漢の国力の衰えにより、人口は急激に減少した。『史記』には「漢は北に公城、成高城、西に益陽関、上班関を有し、面積は900里余り、武装兵は数十万。世界で最も強い弓と弩弓はすべて漢から来たものである。益陽を占領し、6万人を斬首した」と記されている。益陽のような重要な場所に駐屯するために、朝鮮人はわずか6万人の軍隊を派遣しただけである。戦国時代後期、朝鮮の人口は最も少なかったことがわかる。 しかし、結局、韓国は戦国時代の七大国の一つであり、その国力は魏、魯、宋などの国よりもまだ強かったのです。それら辺境部族国家は韓国とは比べものにならない。韓国の兵力は30万から40万と言われており、仮に全て参加したとしても人口は100万人近くになる。ただ、秦と楚の人口を合わせるとすでに数千万人に達していた。最も保守的な計算方法を用いても、他の5カ国の人口を合わせた数も数千万人に達するはずである。したがって、戦国時代後期の総人口が2000万人を超えていても問題はない。 「千尺の城に万戸の町が向かい合う」ということわざがあるように、戦国時代後期を想像してみてください。あの曲がりくねった川のそば、あのそびえ立つ山々のそばに、戦火の煙さえなければ、人々は平和に都市で暮らし、働いていたでしょう。なんと幸せな光景でしょう。 |
<<: 秦は楚と趙から広大な土地を次々と併合しました。なぜ他の国々は団結して秦に抵抗しなかったのでしょうか?
>>: 現存する記録によれば、「軍事顧問」という役職の出現は、少なくともどの時代にまで遡ることができるでしょうか?
推薦する
「病気の牛」をどう理解するか?創作の背景は何ですか?
病気の牛李剛(宋代) 1,000エーカーを耕し、1,000箱を収穫すると、疲れ果てて傷つく人は誰でし...
纏足はなぜ「金蓮華」と呼ばれるのでしょうか?三寸金蓮華の起源
「三寸金蓮華」といえば、なぜ女性の足は纏足によって「金蓮華」と呼ばれるのかと疑問に思わざるを得ません...
「水滸伝」の阮小奇の結末は?遊んでいたせいで解雇された彼は、残りの人生を平和に過ごした!
今日は、Interesting Historyの編集者が「水滸伝」の阮小奇の結末についてお伝えします...
『唐尚行』の著者は誰ですか?この古代の歌の本来の意味は何でしょうか?
【オリジナル】私の池にはガマが生えていますが、葉がとてもまばらです。私以上に仁と義を実践できる人はい...
景坡錦の機能は何ですか?それはどういう意味ですか?
景坡族の独特な経験が独特の文化を生み出しました。景浦の女性の錦織りの模様は、古代景浦象形文字であると...
『定慧園に暮らす』の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
私は定慧寺の東に住んでいます。丘にはたくさんの花が咲いています。クラブアップルの木もあります。地元の...
太平広済・第98巻・奇僧・舒草師をどのように翻訳しますか?原文の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
『紅楼夢』の石向雲と林黛玉の性格はどんな感じですか?違いはありますか?
石向雲と林黛玉は、『紅楼夢』に登場する非常に異なる性格を持つ二人の登場人物です。まだ知らない読者のた...
掃討僧の少林寺カンフーの秘密を解き明かす
金庸の武侠小説『半神半魔』に登場する掃部僧は、謎めいて不可解な少林寺の僧侶である。彼は長い間少林寺に...
なぜ『紅楼夢』で西仁は黛玉について悪いことを言ったのですか?両者の関係はどのようなものですか?
「紅楼夢」では、黛玉に対する西仁の態度が発展し、変化します。今日は、Interesting Hist...
李和の「蝶が飛ぶ」:この詩は作者の詩風と感情の別の側面を示している
李和(790-816)、雅号は昌吉とも呼ばれる。彼は河南省富昌県長谷郷(現在の河南省益陽県)に生まれ...
周史書第七巻の原文の鑑賞
宣帝宣帝の本名は雲、号は千伯。高祖帝の長男。彼の母は李皇太后であった。武成元年に通州に生まれる。保定...
名著『中書』第七巻 歴史原文の鑑賞
孔子は言った。「太熙以降、歴史を書いた者はほとんど呪われ、君子は称賛されなかった。」楚公が困ったとき...
唐代の重要な軍事書『太白印経』全文:戦争装備カテゴリ·水攻装備
『神機滅敵』は『太白陰経』とも呼ばれ、道教の著作です。古代中国では太白星は殺生の達人であると信じられ...
『水滸伝』に登場する108人の登場人物の中で、真の英雄と言えるのは誰でしょうか?
『水滸伝』は中国文学の四大傑作の一つであり、その物語は各家庭によく知られています。次はInteres...









