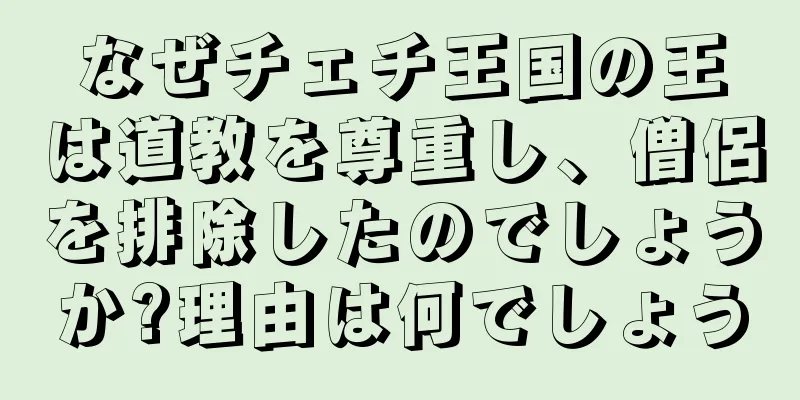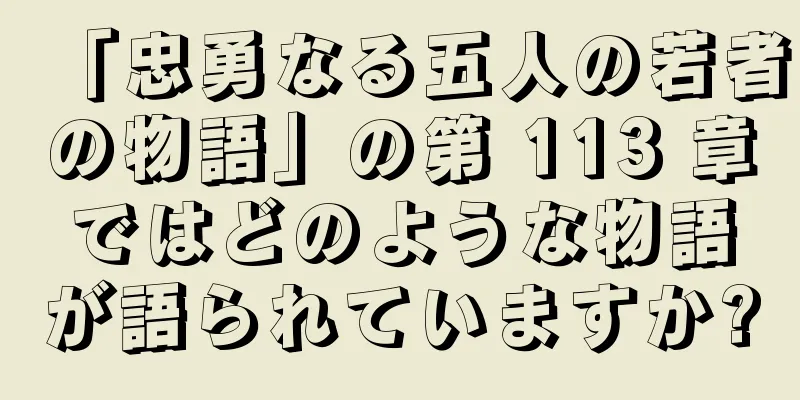秦は楚と趙から広大な土地を次々と併合しました。なぜ他の国々は団結して秦に抵抗しなかったのでしょうか?
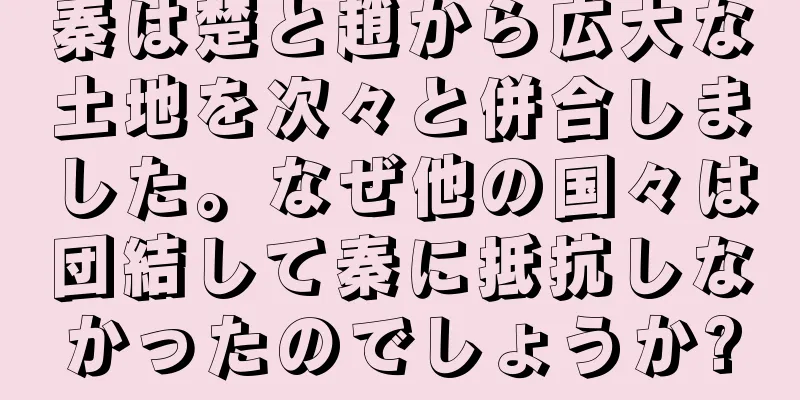
|
戦国時代は激動の時代であると同時に、百家争鳴の時代でもありました。全国から才能ある人々が様々な国に集まり、王たちに自分たちの考えを採用して有名になるように説得しようとしました。蘇秦と張毅も同様であった。人材の活用という点では、秦国が最も優れていた。したがって、秦国が最終的に世界を統一したのは当然のことでした。しかし。各国の王子様どころか、蟻ですら生き残ろうとするのでしょうか? 戦国時代初期から中期にかけて、秦の天下統一の意図があまり明確ではなかったとすれば、諸国が協力できなかったのも無理はない。しかし、戦国時代後期、秦は楚と趙から広大な土地を次々と併合しました。その意図は明らかでした。なぜ諸国は偏見を捨てて団結し、秦に抵抗しなかったのでしょうか。次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう! 3回の戦いで6カ国の首都は疲弊し、秦と戦うこととなった。 戦国時代、国境に位置する秦、趙、斉、楚の4つの国が最も強国となる資格を持っていました。辺境に位置するため、領土を拡大し、資源を獲得することができます(海に近い斉国も同様です)。 戦国時代初期の覇者・魏国のように他国を圧倒するほどの実力はあったものの、外に進出することはなく、また中原に位置し四方の敵に囲まれていたため、やがて力尽き、斉国によって覇者の座から引きずり下ろされた。 まさにその通りです。秦国が道中遭遇した敵は、まさにこの3国でした。秦国はこれら3つの国を倒すことによって、ついに天下を統一した。この三つの戦争とは、五国の斉侵攻、燕・嬰の戦い、そして昌平の戦いである。 五つの国が斉を攻撃 斉が魏を覇権の座から引きずり下ろして以来、斉の威信はますます高まり、その後の徐州王は斉の東の大国としての地位をさらに確立しました。この頃、斉はすでに魏に次ぐ大国となり、楚と肩を並べるまでになった。対照的に、秦の台頭と魏の衰退により、秦は東方へと拡大する首都を得た。商鞅の改革を経験した秦も急速に強くなっていった。したがって、遅かれ早かれ斉と秦の間に戦争が起こるでしょう。 やがて斉の閔王が機会を与えた。斉の閔王の傲慢さと、あらゆるところに敵を作ったという事実は、他国の不満を引き起こした。こうして、斉を攻撃するための連合軍の大規模な作戦が始まった。 五ヶ国の連合軍が斉の軍を破った後、彼らはそれぞれの国へ戻り始めました。岳頤がこの機会を捉え、斉の70以上の都市を占領し、斉をほぼ滅ぼすとは誰が想像したでしょうか。田丹は後に火牛陣で国を復興させたが、斉の基盤は完全に略奪され、もはや再興することはできなかった。 燕と嬰の戦い 斉の衰退後も、楚と趙は依然としてかなりの力を持っていた。そこで、秦の昭襄王は、国の力をさらに高めるために、楚を攻撃することを決意しました。楚は領土が広く、資源も豊富でしたが、兵士の戦闘力が弱く、攻撃の絶好の標的でした。そこで、燕と嬰の戦いが起こりました。 燕と嬰の戦いで、秦の将軍白起は楚の二つの首都燕と嬰を占領し、楚に大きな打撃を与え、楚の領土の大部分を併合し、秦の力を大幅に増強した。燕と嬰は、楚国が常に管理に努めてきた地であり、その地位は周王家の郝京と洛邑に劣らないことをご承知おきください。秦が燕と嬰を征服したことで、楚から大量の物資を調達できただけでなく、楚が西方で秦に対して築いていた防衛線も破壊され、大きな意義があった。 最も重要なことは、彼らが楚国から広大な土地も獲得したことです。戦国時代、土地は人口と食糧を意味していました。この戦いの後、楚国が誇っていた領土の優位性は失われ、その国力は大きく弱体化した。 昌平の戦い 趙国は中原を征服しながらも静かに力を蓄え、秦国の恐怖を掻き立てた。当時の六つの国を見てみると、秦に脅威を与えることができたのは趙だけだった。 したがって、この時の趙国は秦国が天下を統一する上で最後の障害であったと言える。こうして、昌平の戦いが勃発した。 昌平の戦いの際、昭王は秦王の諜報活動に陥り、廉頗を趙括に交代させた。しかし、経験不足のため趙括は白起の罠に陥り、結局40万人の軍を白起に引き渡してしまった。 白起は趙軍が反乱を起こすのではないかと恐れ、彼らを全員殺した。多くの兵士を失った趙国は、秦国と競争することができませんでした。歴史の記録によれば、当時の趙国の若者と中年の男性は皆亡くなり、残ったのは老人、弱者、女性、子供だけだった。 この3回の戦いの後、6つの国は秦に完全に抵抗することができず、同盟は無駄になりました。 この3回の戦いの後、山東省の6つの国は秦に抵抗することができなくなりました。これは地理的な観点からもわかります。秦国は中原の半分を占め、体制的にも優位に立っていました。山東省の6つの国はどうやって抵抗できたでしょうか。どうやって抵抗できたでしょうか。 邯鄲の戦いでの勝利が全てを証明したと言う人もいる。邯鄲の戦いで秦が敗北したことを否定はしないが、邯鄲の戦いは昌平の戦いからわずか数ヶ月後のことであり、秦の活力はまったく回復していなかった。さらに、将軍と大臣の間に不和があり、それが敗北につながった。しかし、秦の制度上の優位性に頼っていたため、秦の回復力は山東六州よりもはるかに強かった。たとえ消費しても、山東六州には余裕がなかった。 |
<<: 後世の人々が東周時代を春秋時代と戦国時代に分けた主な理由は何ですか?
>>: 『史記』の記録によると、戦国時代の各国の人口はどのくらいだったでしょうか?
推薦する
『杜甫への遊び心ある贈り物』をどう鑑賞するか?著者は誰ですか?
杜甫への遊び心のある贈り物李白(唐)私は梵克山の頂上で杜甫に会った。彼は正午なのに帽子をかぶっていた...
紅楼夢第58章:偽りの鳳凰が杏の木の上で泣き、真実の愛は赤い紗の窓の後ろの愚かな理由によって判断される
『紅楼夢』は、中国の四大古典小説の一つで、清代の章立て形式の長編小説です。通俗版は全部で120章から...
石衡と徐有珍の関係は?石衡と徐有珍の結末は?
石衡徐有珍石衡と徐有貞はともに明代の官僚であり、明代のクーデターに関わった人物である。石衡は主力とも...
『太平広記』第201巻:才能ある人は誰ですか?
人材尚官易 東方 秋素燕 李勇 李華 李白郝尚芳官 韓于里月路 洪建 都孤記 都建里徳宇 潘燕 宋志...
『紅楼夢』の悪役の多くはなぜ「王」という姓を持っているのでしょうか?
『紅楼夢』に登場する悪役の多くはなぜ「王」姓なのか?これは多くの読者が特に知りたい疑問です。次の『興...
『太平広記』第94巻に登場する8人の奇妙な僧侶とは誰ですか?
華厳宗の僧侶 唐秀静の僧侶 易光禅師 玄藍法師華厳僧侶華厳和尚は神秀から学びました。禅宗(宗はもとも...
山西商人の盛衰の背景には何があるのでしょうか?団結しすぎるのは良くない!
Interesting History の編集者をフォローして、歴史上の山西商人の盛衰を探ってみまし...
曹丕が帝位に就いた後、曹植は残りの人生をどのように過ごしたのでしょうか?
曹植の「七段詩」の話は広く流布している。曹植はかつて皇太子の座を巡って曹丕と争ったが、惨めな敗北に終...
長安は多くの王朝の首都でした。明王朝の時代になぜ西安に変更されたのですか?
長安といえば、何を思い浮かべますか?次のInteresting History編集者が、関連する歴史...
なぜ宋代の歌詞は中国文学史上最も有名なのでしょうか?
はじめに: 『宋辞』は新しいスタイルの詩であり、宋代に流行した漢文学の一ジャンルであり、宋代文学の最...
帝国の女医第37話:ユンシアンとイェセンが仲違い
イェセンは雲仙が英宗に会うことを許さなかった。英宗は拓不花に会わせるよう頼んだ。拓不花は巧みに二人の...
『紅楼夢』で王夫人が青文を追い払おうとした本当の目的は何だったのでしょうか?
王夫人は、中国の古典小説『紅楼夢』とその派生作品の登場人物です。以下の記事は、Interesting...
ナラン・シンデの「良いことがやってくる:家への道」:詩全体が詩人の悲しい気分を浮き彫りにしている
納藍興徳(1655年1月19日 - 1685年7月1日)は、葉河納藍氏族の一員で、号は容若、号は冷家...
三勇五勇士第48章:裏切り者を訪ねて処刑し、追従者を降格させ、真の義人を皇帝の前に連れて行く
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
古代の天才児、孫武は、幼少期から文武両道の才能を発揮しました。孫武はどのようにしてその知性と才能を発揮したのでしょうか。
孫武は古代中国の有名な軍事戦略家でした。彼の愛称は長慶でした。彼は紀元前534年頃に生まれ、紀元前4...