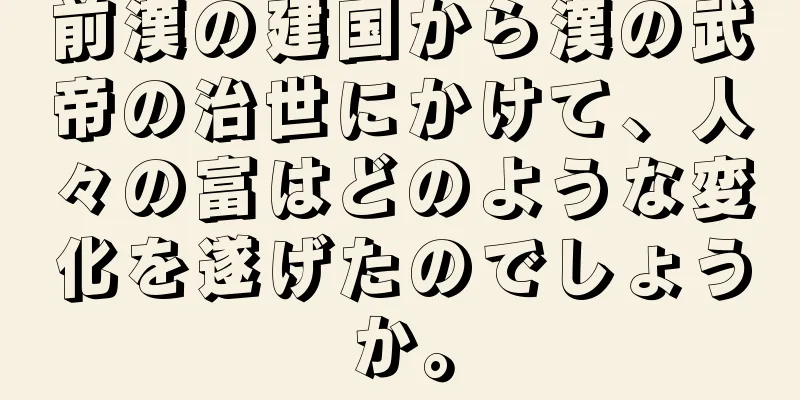諸葛亮は司馬家に何度も迷惑をかけたのに、なぜ東晋の時代に武興王と名付けられたのでしょうか?

|
三国志の歴史を語るとき、諸葛亮は避けて通れない人物です。『三国志演義』が広く普及したことにより、諸葛亮の人物像は人々の心に深く根付いています。劉備のもとで呉と同盟を結んで曹と戦い、蜀漢による三国分割の実現に大きく貢献した。劉備の死後、南中を平定し、岐山に6回出向いて北伐を開始し、「離都追悼」という詩に蜀漢への忠誠が記されている。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 周知のとおり、諸葛亮の蜀漢における最高官職は蜀漢宰相であった。また、益州太守、近衛監も務めた。蜀漢後期には荊州が失われ、蜀漢の領土は益州と漢中のみとなったため、諸葛亮は蜀漢に全権を集中したと言え、官位・軍事力ともに頂点に達した。 しかし、宰相も益州知事も役職に過ぎず、称号面で諸葛亮の最高の地位を与えたのは蜀漢ではなく、宿敵である司馬一族であった。蜀漢時代、諸葛亮の最高位は武湘侯であり、魏延の南鄭侯ほど高くはなかった。しかし、司馬一族が建国した東晋は彼を武興王と称した。 数千年の間、多くの人々は困惑してきました。諸葛亮は岐山に6回行き、何度も司馬懿の家族に迷惑をかけました。上房谷の戦いでは、司馬懿、司馬昭、司馬師を殺しそうになりました。彼らは宿敵であったのに、なぜ諸葛亮を王にしたのでしょうか? 「諸葛亮は内戦は得意だが、外戦は苦手」と推測する人もいます。諸葛亮は何度も北伐をしましたが、曹魏を攻撃して中原を統一するためではなく、二人の権力を奪取するためでした。結局、諸葛亮が勝利し、二人を排除することに成功し、蜀漢の滅亡を早め、間接的に司馬家を助けました。そのため、諸葛亮は武興王と名付けられました。しかし、これは本当でしょうか?諸葛亮が権力を奪取したかった二人は誰だったのか見てみましょう。 一人目は三国時代の蜀漢の高官、李厳で、諸葛亮とともに幼い皇帝の世話を任された大臣でした。彼らは二人いて、一人は部長でもう一人は副部長です。しかし当初、諸葛亮は政治権力を握る宰相にすぎず、李厳は内外の軍事問題を担当する中央衛兵将軍も務めていた。劉備が諸葛亮の権力のバランスを取るために李延を残したと言う人もいます。 諸葛亮は北伐の度に1、2か月分の食糧と飼料しか持参せず、李厳に後方の警備と食糧と飼料の補給を任せた。この間、李厳に江州を離れて漢中に駐屯するよう命じた。これにより李厳は古巣を離れることになっただけでなく、李厳と漢中督の魏延の間に亀裂が生じることになった。しかし、李厳は諸葛亮の計画を見抜いて去ることを拒否した。結局、諸葛亮は李厳が食糧と飼料を適切に管理していないという口実を見つけ、李厳を解任することに成功した。 2番目は魏延です。魏延は三国時代の蜀漢の稀有な武将で、劉備から高く評価されていました。かつて劉備は張飛を見捨てて、魏延を漢中の太守に任命した。劉備は魏延の師であったと言える。それどころか、諸葛亮が初めて魏延に会ったとき、彼は魏延は生まれつき反抗的な性格で、魏延を殺したいのだと言った。これは諸葛亮による威圧と誘導の策略であったが、魏延と諸葛亮の関係は最初から良好ではなかった。 その後、諸葛亮は宰相の名の下に多くの北伐を指揮し、漢中は必ず通らなければならない場所となった。辺境の役人である魏延は当然、諸葛亮に従い、その命令に従わなければならなかった。その後、諸葛亮は魏延の提案した戦略を何度も拒否したが、蜀漢末期には有能な将軍がいなかったため、諸葛亮は魏延を愛憎していた。病死寸前まで、自分の陣営には魏延を制御できる者がいないのではないかと恐れ、思い切った手段に出ることにした。死ぬ前に、魏延と対立していた楊毅を総大将に据えた。結局、魏延の傍らに潜んでいた馬岱が魏延を刃物で殺害した。 このため、多くの人は、司馬一族が諸葛亮を王に据えたのではないかと推測しています。諸葛亮は権力を強めるために劉備の支援する勢力を排除し、それが最終的に蜀漢の動乱を悪化させ、蜀漢の滅亡を早め、間接的に司馬一族が三国を統一する条件を整えたと彼らは考えています。 しかし、著者はそうは考えていない。諸葛亮は権力欲が強すぎるかもしれないが、皇帝への忠誠心が根強い伝統的な学者でもある。劉備が王になるよう勧められたとき、漢の献帝が権力を握っていたため、諸葛亮は劉備が不満を抱いていることを知っていたにもかかわらず、あえて彼に勧めた。劉備の死後、彼はすべての面倒を見て国のために尽くし、模範的な働き手と呼べるだろう。 諸葛亮は、自らの政治的理想を表明し、漢王朝を復興し、自らの価値を実現し、後世にその名を伝えようとした人物に過ぎなかった。東晋がかつての敵であった諸葛亮に死後、武興王の称号を授けた本当の理由は、たった2つの言葉、「プロパガンダ」の中に見出すことができる。かつての敵であっても、すべての君主は王朝の安定のために皇帝に忠誠を尽くすという考えを広めた。しかも、諸葛亮はすでに亡くなっており、その称号は単なる称号に過ぎなかった。 |
<<: どのような力関係の下で、薄皇后は最終的に漢の景帝によって廃位されたのでしょうか?
>>: 司馬一族が建国した金王朝はなぜ中国史上最も暗い時代だったのでしょうか?
推薦する
隋の時代の『古鏡』に描かれた王度冒険の秘密を明かす:それは真実か嘘か?
古代中国では王度を知る人は多くなく、歴史書にも王度に関する記録は多くありません。しかし、王度が書いた...
遼朝以降、「奴伯」という言葉は皇帝のどのような活動を指すようになったのでしょうか。
「ナボ」は契丹語の音訳であり、遼皇帝の陣営を意味する契丹語である。遼代以降、「納泊」という言葉は、仮...
劉備の部下を再配分すれば、「龍中作戦」は成功するだろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
古代の文人は冬をどのように描写したのでしょうか?関連する詩は何ですか?
どの王朝にも冬を描写した詩は数多くあります。Interesting History の次の編集者が、...
三国時代、関羽の他に華雄を殺せる者は誰でしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
済公伝第135章:済公は雷に怪物を倒すよう頼み、飛龍は聖僧を心から崇拝する
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
李和の「秋が来る」は詩人の憂鬱で苛立った感情を表現している。
李和は、字を昌吉といい、中唐時代の浪漫詩人である。李白、李商隠とともに「唐の三里」の一人とされ、後世...
農家の主な考えは何ですか?農家は何を侵害すべきではないと考えているのでしょうか?
農家学派は百家思想の一つで、「農家学派」とも呼ばれ、秦以前の時代に農業生産と農民の思想を反映した学派...
「小芝」をどう理解すべきでしょうか?創作の背景は何ですか?
小さいほど杜甫(唐代)天候と人間の営みは互いに促し合い、冬至は春の到来をもたらします。 5つの模様を...
『楚光熙来待』の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
楚光熙が来ないのを待っている王維(唐代)朝から重い扉が開かれ、馬車の音を聞くために立ち上がる。ペンダ...
「Zigui」の作者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
サブルール于静(宋代)あらゆる叫びは残酷さの叫びであり、あらゆる叫びは永遠の不正である。薄い煙、明る...
賀波の紹介 賀波に関する神話と伝説
何伯は古代中国の神話に登場する黄河の神です。彼の本名は馮毅であった。 「ビンイ」とも呼ばれる。包朴子...
「神々の叙任」で最も不当な扱いを受けた二人は、命令に従って行動したが、結局は悪者になってしまった!
本日は、Interesting History の編集者が「神々のロマンス」に関する関連コンテンツを...
陰嬌と陰洪は『神々の英雄』にいつ登場しましたか?陰焦と陰洪にはどんな神が与えられたのでしょうか?
「神々の英雄一覧」に非常に興味がある方のために、Interesting History の編集者が詳...
『岳飛伝』の主人公は誰ですか?どのように鑑賞しますか?
『岳飛全伝』は清代に銭才が編纂し、金鋒が改訂した長編英雄伝小説である。最も古い刊行版は『岳飛全伝』の...