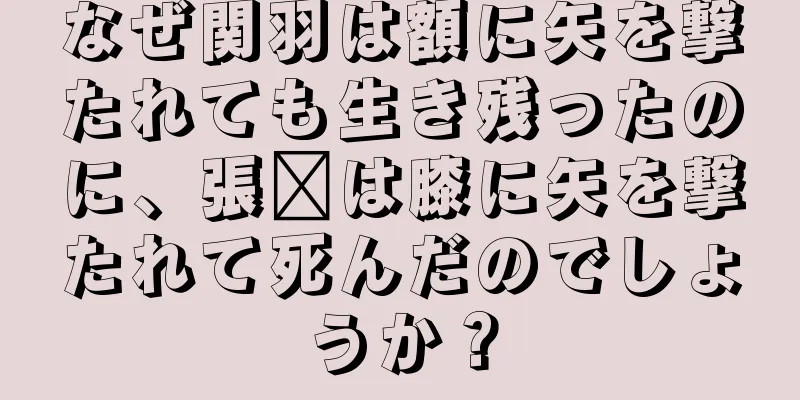馬超も劉備に貢献したのに、なぜ関羽は馬超に対してそれほど大きな評価を持っていたのでしょうか?

|
三国志の歴史に詳しい人なら、関羽という武聖人は忠義に満ちていたものの、性格に大きな問題があり、麦城で敗北して命を落としたことを知っています。つまり、関羽は非常に傲慢で、外部に対してだけではなく、蜀においても五虎将軍の二人である馬超と黄忠を軽蔑し、降伏を求めて自分のところにやってくる老将軍など恐れるに値しないと感じていたのです。残った趙雲は軍を率いることはめったになく、傍観してあまり発言しないことが多い。 関羽の傲慢さは『三国志演義』にも描かれており、『三国志演義』では特に関羽が五虎将軍の一人である馬超に対して強い意見を持っていたことでさらに強調された。馬超は降伏したが、劉備が蜀に入ったときにも貢献した。関羽はなぜ馬超に対してそれほど大きな評価を持っていたのだろうか?その裏には何か隠された物語があるのだろうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介するので、見てみましょう! 三国志演義では、次のように説明されています。馬超は最初曹操に恐れられていたため、曹操は馬超の一族を皆殺しにし、二人の間には個人的な恨みが生まれ、それが後に馬超が曹操を破り、命を守るために髭を切り、袈裟を捨てざるを得なくなったことに繋がりました。その後、曹操は馬超を追撃し、馬超は韓遂と張魯に次々と降伏したが、曹操のせいでどこへでも逃げなければならなかった。その後、諸葛亮はちょっとした策略を使って馬超を味方につけましたが、これは後に蜀に入るための準備でもありました。 関羽は、このように蜀に入城した馬超を嫌っていたと言える。彼は義を重んじる人物であり、多くの人々に寝返った馬超を軽蔑していた。さらに、馬超が降伏する前に、張飛と百回以上戦ったが、明確な勝敗はなかった。馬超の武術は自分の武術に匹敵すると言われていたので、関羽は当然納得せず、常に馬超と競い合いたいと思っていた。残念ながら、諸葛亮に止められた。 編集者は、この二人は同じタイプではなく、比較するのは本当に難しいと感じています。関羽は部隊を率いて陣形の前で戦い、決闘する能力に優れていますが、馬超は戦場で陣形を崩す能力に優れています。彼が率いる西涼鉄騎兵は、近接戦闘と遠距離攻撃の両方の能力が非常に強力です。そうでなければ、曹操は髭を切り、袈裟を捨ててまで曹操を殺すことはなかっただろう。それどころか、馬超は戦場での決闘が得意だった。負けるべき相手に勝ち、引き分けで戦いを終わらせた。例えば、馬超は裸で許褚と戦い、夜に張飛と戦った。どちらの戦いも接戦だったが、馬超はあまり成果をあげなかった。 あと2つ、言及すべき点があります。三国志演義には、馬超が初めて劉備の軍に加わったとき、彼はまだ自分が若き主君であることを忘れていませんでした。劉備と対峙したときでさえ、彼は彼を名前で呼びました。関羽は忠誠を非常に重視する人でした。桃園の誓いの後、彼は常に劉備に大きな注意を払い、彼を辱めませんでした。馬超は関羽の心の中の一線を越えたと言える。 もう一つの点は、馬超自身はそれほど優れた人物ではなかったにもかかわらず、蜀に入る戦いや大規模な漢中の戦いでは彼が必要とされたことです。多くの戦いが彼を蜀に留め、馬超の権力は何度も弱まりました。性格も悪く、軍事力もない将軍を前にして、関羽は当然ながら、彼と同じレベルに立つことを嫌悪した。 馬超は生涯を通じて勇敢な人物であったが、47歳で病死するという悲惨な結末を迎えた。これは彼が幼い頃から様々な不幸を経験していたことにも関係しており、蜀に定住した後も評価されず、憂鬱になって亡くなった。そのため、馬超が関羽の挑発に対して沈黙を守った主な理由は、地位では蜀に及ばず、戦いでは勝てず、関羽ほどの力もなかったためであり、反論する術もなく、屈辱に耐えることしかできなかった。 |
<<: 実際の歴史では、周瑜の方が強かったのでしょうか、それとも魯迅の方が少しだけ優れていたのでしょうか?
>>: 馬超の地位は魏延よりずっと高いのに、なぜ魏延が主将なのでしょうか?
推薦する
別れの詩とは何ですか? 歴史上有名な別れの詩にはどのようなものがありますか?
別れの詩とは何でしょうか?有名な別れの詩にはどのようなものがありますか?今日は、Interestin...
「衡月寺に参って岳寺に泊まって楼門に書を記す」は韓愈が書いたもので、比較的簡潔で荘厳な内容である。
韓愈(768年 - 824年12月25日)は、字を随之といい、河南省河陽(現在の河南省孟州市)の人で...
道光帝は無能な皇帝だった。なぜ嘉慶帝は彼に帝位を譲ったのか?
道光帝は在位中にアヘン戦争が勃発したため、中国近代史上初の皇帝となった。多くの人々は道光帝が無能な皇...
宋代の詩「蘇中清・林出金皿に落ちる杏」を鑑賞して、この詩の作者はどのような感情を表現したいのでしょうか?
蘇仲清:林から落ちた杏を金皿に盛った図 [宋代] 周邦厳、次の興味深い歴史編集者が詳しい紹介をお届け...
伍子胥の紹介と生涯 伍子胥はどのように亡くなったのでしょうか?
伍子胥の父である武社は楚の国の太子の家庭教師で、堅太子の教育を担当していた。太子は費無忌によって陥れ...
岑申の詩「賊徒から裴判官を河陽将軍に送り返す」の本来の意味を理解する
古代詩:「賊軍から裴判官を見送り、河陽将軍府に帰る」時代: 唐代著者: セン・シェン東部郊外の包囲は...
明らかに:狄仁傑はどのようにして唐代の名探偵になったのか?
狄仁傑は官僚の家に生まれた。祖父の狄曉旭は唐の太宗の貞観年間に尚書左城を務め、父の狄智勲は桂州の書記...
袁潔の「賊退却官吏」:この詩はより深く、感情はより憤慨している
袁桀(719-772)は唐代の中国作家であった。雅号は慈山、号は曼蘇、河蘇。彼は河南省廬山出身でした...
戦国時代後期の作品『韓非子』:艾塵による全文と翻訳注
『韓非子』は、戦国時代後期の朝鮮法家の巨匠、韓非の著作です。この本には55章が現存しており、合計約1...
家家楼の46人の友達には、それぞれに人生の物語があります。秋福と家家楼の46人の友達は44位にランクされています。
バイオグラフィー9月9日、秋福は母の誕生日を祝いました。秋福は父に代わって祝い、佳里楼の46人の友人...
最も透明な詩人、生と死を軽やかに見つめる唐詩
生と死は人生における大きな出来事です。人生は旅ですが、この旅の始まりと終わりは記念する価値があります...
古典文学の傑作『太平天国』:陸軍省第81巻
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
李世民はなぜ玄武門の変を起こしたのか?彼らの争いに対して何もしなかったのは李淵だった。
李世民が玄武門の変を起こしたのは、李建成が弟の李建成との帝位争いで優位に立っていたためである。この状...
『紅楼夢』では、王夫人は王希峰を信用していないのですか?なぜそんなことを言うのですか?
『紅楼夢』で王夫人は王希峰を信用していなかった?今日は『おもしろ歴史』編集者が新たな解釈をお届けしま...
商鞅の改革は3段階に分かれています。それは国を強くするためのものだったのでしょうか、それとも国を滅ぼすためのものだったのでしょうか。
戦国時代、魏出身の商阳は秦の国で一連の改革運動を実施しました。これは歴史上、商阳の改革として知られて...