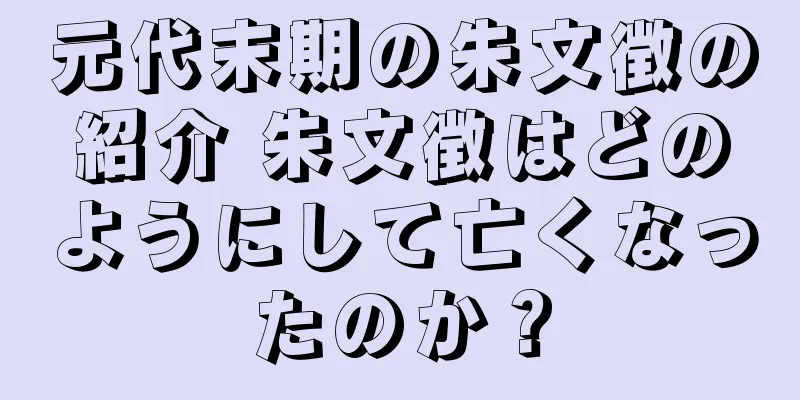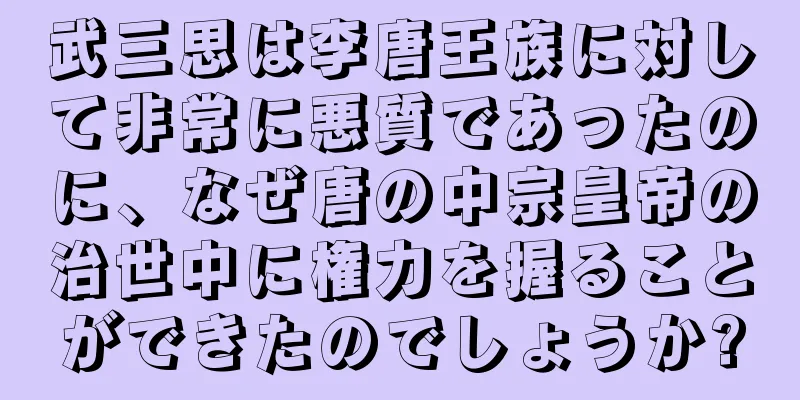なぜ関羽は額に矢を撃たれても生き残ったのに、張郃は膝に矢を撃たれて死んだのでしょうか?
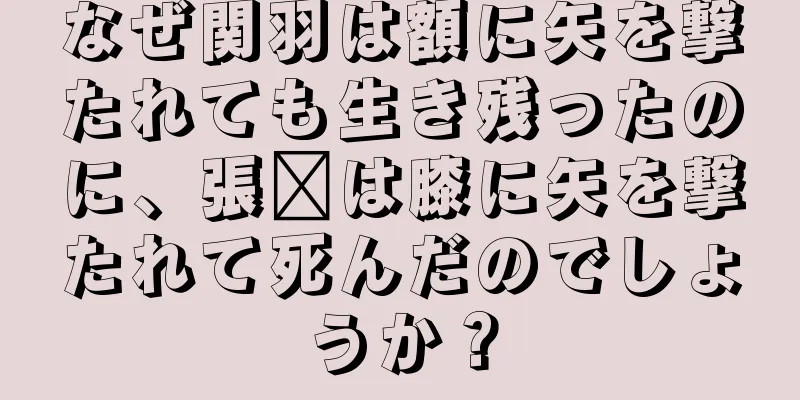
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、関羽が額を撃たれても死ななかったのに、張郃が膝を撃たれて死んだ理由について詳しく紹介します。見てみましょう! 一般的に考えれば、頭部は人体の中でも非常に脆弱な部分であり、頭部が負傷すると死に至る可能性が高いといえます。膝も体の重要な部分ですが、膝を負傷しても実際には命にかかわるわけではありません。例えば、事故により足を切断する人も多くいますが、最終的には生き残ります。では、なぜ関羽と張郃の状況は大きく異なっていたのでしょうか? 関羽は額を撃たれても生き残ったのに、張郃は膝を撃たれて死んだのはなぜでしょうか? 実は、この驚くべき効果には主に 2 つの理由があります。 1. 異なる保護 関羽は龐徳との戦いで額を撃たれた。しかし、古代人は実は頭部をかなりしっかり守っていました。戦場は混沌としていて、矢が飛び交っていました。矢に撃たれて死ぬのを避けるために、ほとんどの古代の将軍はヘルメットをかぶっていましたが、これは弓矢の威力を大幅に弱めるものでした。実際、現代の戦場でも、多くの軍隊はヘルメットの開発を依然として非常に重視しています。ヘルメットは兵士の命を大きく救うことができるからです。 『三国志演義』:徳昌は言った。「私は国の恩恵を受けている。そのために死ぬのは私の義務だ。私は自分で羽を殺したい。今年中に羽を殺さなければ、羽は私を殺すだろう。」その後、彼は自ら羽と戦い、羽の額を撃った。 『三国志演義』の記録によると、関羽との戦いで龐徳は関羽の額に矢を放った。しかし、関羽のその後の行動から判断すると、龐徳は関羽の兜に当たっただけで、矢の衝撃は兜に遮られ、関羽の頭部を傷つけなかった可能性が高い。そのため、外部から見ると関羽が撃たれたように見えましたが、実際には関羽は負傷していませんでした。 関羽とは異なり、張郃の負傷部分は十分に保護されていませんでした。古代の技術と生産性の限界により、すべての兵士が戦闘時に鎧を着用できるわけではありませんでした。一般的に、上級将軍と特別部隊のみが鎧を着用していました。さらに、これらの鎧は、頭部、胸部、腹部など、人体の重要な部分のみを保護し、人体の下肢に対しては、鎧の保護強度はそれほど強くありません。 古代の西洋世界では、全身を覆う全身鎧があり、矢による負傷は少なくなっていました。しかし、これは人の柔軟性を低下させることにもなりました。古代中国の王朝が直面した敵のほとんどは、大規模な鎧を装備する能力がなかったため、古代中国の鎧のほとんどは完全に覆われておらず、主に上半身を保護していました。 この場合、矢が張郃の膝に当たった理由は、防御力が弱かったためだと理解しやすいです。論理的に言えば、たとえ膝を撃たれても、適切な処置を受けていれば死ぬことはありません。しかし、当時曹操軍は待ち伏せされており、張郃は適切な助けを得ることができず、結局矢傷で亡くなりました。 『三国志』:諸葛亮は岐山に戻り、何に将軍を率いて西の洛陽へ向かうよう命じた。梁は岐山を守るために戻った。彼は木門まで追いかけ、梁の軍と戦った。彼は飛んできた矢に右膝を撃たれて死んだ。彼は諡号を荘侯と名付けられた。 2. さまざまな弓と矢 防御力の違いに加えて、関羽と張郃を襲った矢も大きく異なっている可能性があります。 ご存知のように、諸葛亮は発明が得意です。北伐の指揮中に、多くの先進的な武器を発明・作成し、曹魏に多大な損失をもたらしました。ここで最も強力な武器の1つは連射クロスボウです! これまで、クロスボウは強力な武器でしたが、連続して発射することはできませんでした。 しかし、諸葛亮によって改良されたクロスボウは実際に連続して発射することができ、戦場で大きな貢献をしました。諸葛亮は弩を改良できたので、当然矢も改良したはずです。ですから、張郃を撃った矢は、関羽を撃った矢とは全く違うものだった可能性が高いのです。 『三国志』:梁は創意工夫に長けていた。連射式弩や木製の牛馬はすべて彼の考案だった。 その時、張郃は諸葛亮に待ち伏せされ、膝を矢で撃たれました。通常であれば、出血が間に合う限り、張郃は戦場からの撤退を主張できたはずですが、結局張郃はこれが原因で亡くなりました。おそらく、その時は出血が止まらなかったのでしょう!諸葛亮は出血専用の弓矢を発明したのかもしれません。一度人体に矢じりを刺し、一度引き抜いたら、単なる包帯では役に立たなくなります。結局、張郃は過度の失血で亡くなったのかもしれません! |
<<: モンゴルの習慣 モンゴルのアオバオの習慣は何ですか?
>>: モンゴルのゴールデンファミリーとは何ですか?その背後にある物語は何ですか?
推薦する
儒教古典『周礼』原典の鑑賞:官吏礼第9章
公爵が役人と一緒に食事をする際の作法。役人たちに、それぞれの階級に応じて警戒するよう命じなさい。上位...
五虎将軍の中で最も弱い武術家は誰ですか?諸葛亮はそれをどう評価したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
古代の計時機器である日時計はどのようにして時間を計測するのでしょうか?
日時計は太陽の影を利用して時間を計測する装置です。 「日時計」とも呼ばれ、太陽の影を利用して時間を計...
『醜い奴隷 青春は悲しみの味を知らない』の執筆背景は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
醜い奴隷:若者は悲しみの味を知らない【宋代・辛其記】若者は悲しみの味を知らず、ただ高い階に登ることが...
「忠勇五人男物語」の第35章ではどんな物語が語られていますか?
かんざし泥棒の劉元外は剣を持って踊るように誘われ、鍾太宝は喜びを加えた蒋思さんは酒を飲んで顔を覆い、...
「中国のスタジオからの奇妙な物語」:ある男が物乞いを救い、物乞いは彼に命を与えた!
「中国のスタジオからの奇妙な物語」:ある男が物乞いを救い、物乞いは彼に命を与えた!Interesti...
世界で最も有名な4つのバンドは誰ですか?どのバンドが1位になりましたか?
今日は、Interesting History の編集者が世界の 4 大バンドを紹介します。興味のあ...
唐代の衛兵はどのようにして誕生したのでしょうか?なぜ衛波鎮の衛兵が最も有名なのでしょうか?
実は、当初「ヤビン」は個人の兵士や警備員のみを指していました。その名前は主に古代のヤ旗に由来しており...
『紅楼夢』ではなぜ次男が賈家の家長なのですか?賈舍が栄果屋敷を失った理由を解明
周知のように、封建社会では長男が後継者です。ではなぜ『紅楼夢』では次男が賈家の当主なのでしょうか?今...
玉兎仙女と唐僧侶は前世で関係があったのでしょうか?彼らの関係はどのようなものですか?
しかし、よく考えてみると、その数はほんのわずかで、白骨鬼、龍穴の老母、斑点のある鴛鴦魚女、蠍鬼、鉄扇...
「ヨン・ユー・レ:沈む太陽が金色に溶ける」のオリジナル翻訳と鑑賞
ヨンユル:夕焼けに溶ける金色李清昭(宋代)沈む太陽は金色に溶け、夕雲は一つに溶け合う。人々はどこにい...
北宋以前の裁判制度はどのようなものだったのでしょうか?北宋時代にはどのような革新がありましたか?
大理寺は宋代における最高位の中央司法機関であった。その多くの機能の中で、司法裁判が主なものであった。...
劉禅と諸葛亮は名目上は王と大臣であったが、実際は「父と息子」であったと言われるのはなぜでしょうか。
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
水滸伝における呉容のイメージとは?彼女はどんな行為をしたのですか?
公孫勝は、史乃安の古典小説『水滸伝』に登場する重要な人物である。公孫勝は道士名を易清先生といい、河北...
劉備が諸葛亮を三度訪問するたびに関羽と張飛を連れて行った二つの理由は何ですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...