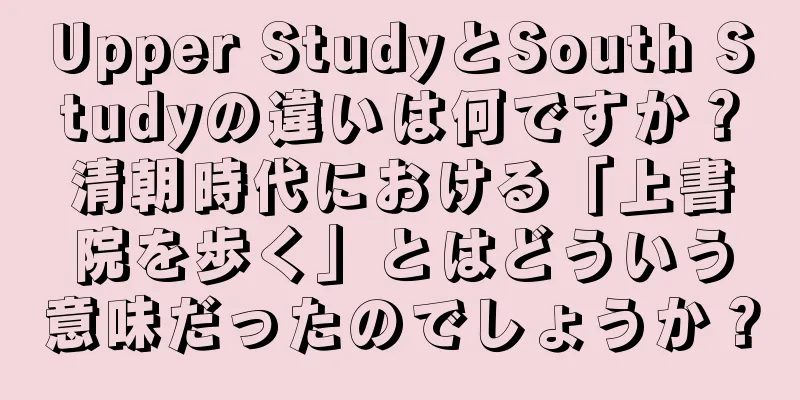大足石刻は洞窟芸術の普及促進にどのような役割を果たしていますか?

|
大足石刻は重慶市大足区にある世界文化遺産です。唐、五代、宋の時代に彫られ、明、清の時代にも彫られ続けました。では、大足石刻は洞窟芸術の普及にどのような役割を果たしたのでしょうか。次の『Interesting History』編集者が詳しい答えを教えてくれます。 大足石刻は彫刻芸術そのものの美的・形式的法則に焦点を当てており、洞窟彫刻が崖彫刻へと発展した優れた例です。 3Dモデリングの技術では、リアリズムと誇張の相補的な方法を使用して、表現が難しい状況を模倣し、表現が難しい感情を伝えます。精神と心を伝えるために、さまざまなキャラクターにさまざまな性格特性が与えられます。 善と悪、美と醜の強い対比を強調し、表現内容は生活に近く、言語は大衆的で、意味は簡潔で、強い芸術的魅力と大きな社会教育効果を兼ね備えています。素材の選択に関しては、古典から派生していますが、古典に縛られることはありません。非常に包括的で創造的であり、悪を罰し善を促進し、心を鎮め行動を規制するという世俗的な信仰の道徳的要件を反映しています。レイアウトの点では、芸術、宗教、科学、自然が巧妙に組み合わされています。美学の面では、神秘性、自然、優雅さを融合し、学問を重視する中国の伝統文化の美的要求を完全に体現しています。 表現面では、宗教彫刻の古い慣例を打ち破り、創造的な発展を遂げ、神々を人間化し、人間と神が一体化するなど、非常に中国的な特徴を持っています。つまり、大足石刻は多くの面で洞窟芸術の新しい形式を生み出し、中国風と伝統的な中国文化の含意を持ち、伝統的な中国美的思想と美的嗜好を体現した洞窟芸術のモデルとなったのです。同時に、中国の石窟芸術の発展と変化の転換点として、大足石刻には以前のものと異なる多くの新しい要素が現れ、後世に大きな影響を与えました。 大足石刻は、強い世俗的信仰と質素な生活の雰囲気により、洞窟芸術の中でも独特な存在であり、洞窟芸術の生き生きとした性質を前例のないレベルにまで押し上げています。コンテンツの選択と表現手法に関しては、世俗的な生活や美的嗜好と密接に融合するよう努めています。仏像、菩薩像、羅漢像、金剛像、あるいは一般の人物像に至るまで、その人物像はどれも生き生きとしており、物語の筋書きも現実の生活を忠実に描写したものに非常によく似ています。 石の彫刻は主に仏像ですが、儒教や道教の像も含まれています。洞窟彫像の特徴を持ち、洞窟芸術の範疇に属する。初期の「寺院ホール」スタイルの構造はすべて崖の彫刻でした。たとえば、大仏湾の彫像はすべて露出しており、崖とつながっており、非常に直感的な感覚を与えます。それは宗教的な制約を打ち破り、彫像をより人間的なものにします。彫刻の形態には、丸彫り、高浮き彫り、浅浮き彫り、凸浮き彫り、凹彫りの 5 種類がありますが、高浮き彫りが主な形態で、その他の形態が補完されています。数多くの人物や社会生活の場面が登場するだけでなく、大量の文書記録も添えられており、生き生きとした歴史絵図となっています。 |
推薦する
朱敦如の有名な詩の一節「煙と塵は一万里」を鑑賞する。中原を振り返ると涙が溢れてくる
朱敦如(1081-1159)、号は熙珍、通称は延和、沂水老人、洛川氏としても知られる。洛陽から。陸軍...
西海竜王事件とは何を指すのでしょうか?小白龍との関係は?
僧侶が仏典を求める旅の途中で、孫悟空は悪魔や怪物を鎮圧し、常に悪魔や怪物の宿敵であり、仏典を求める旅...
第22章:朝廷全体が勝利を祝い、北平の蜂起が再開される
『続英雄譚』は、明代の無名の作者(紀真倫という説もある)によって書かれた長編小説で、明代の万暦年間に...
隋唐時代物語 第12章 棗橋林の財産が暴かれ、災難が襲う。順義村は土俵で敵と対峙する
『隋唐志演義』は清代の長編歴史ロマンス小説で、清代初期の作家朱仁火によって執筆されました。英雄伝説と...
秦王朝は最初の統一王朝でしたが、なぜその子孫は自らを漢民族と呼んだのでしょうか?
秦王朝(紀元前221年 - 紀元前207年)は、中国史上初の統一王朝であり、戦国時代に秦国から発展し...
『菩薩男洛陽城美泉』をどのように理解すべきでしょうか?創作の背景は何ですか?
菩薩男:洛陽市の美しい春魏荘(唐代)洛陽市の春の景色は美しいが、洛陽の有能な人々は故郷を離れて老いて...
古代の恋愛物語の一つ:王美娘と秦忠の恋は幸せな結末を迎えるのでしょうか?
「油売り花魁」は、明代の小説家馮夢龍が編纂した小説集『天下を覚ます物語』に収録されている物語で、美貌...
楊万里の詩「悲しき春」の鑑賞
春の悲しみ王朝: 宋著者: 陳玉毅オリジナル:政府には敵を鎮圧する計画がないので、ただ座って、夕日の...
石大足の「秋晴れ、河水広し」:この詩は、憂鬱で絶妙な傑作です。
史大足(1163年 - 1220年?)、号は邦清、通称梅溪、汴(河南省開封市)の出身。彼は生涯で科挙...
王維の「渭川の農民」:この詩の核心は「帰還」という言葉であり、故郷に帰りたいという願望である。
王維(701-761)、字は墨傑、字は墨傑居士。彼は河東省蒲州市(現在の山西省永済市)に生まれ、祖先...
安倍晴明とは誰か:日本で最も優れた陰陽師、安倍晴明の簡単な紹介
安倍晴明(あべ はるあき、延喜21年2月21日 - 寛弘5年10月31日)は、平安時代中期に活躍した...
南漢の創始者は劉延です。この政権はどのようにして宦官王朝になったのでしょうか?
実際、宦官に関して言えば、古代において、男性が皇帝の側室や宮廷の女官と姦通するのを防ぐために、宦官が...
『三朝北孟慧編』第218巻はどんな物語を語っているのでしょうか?
延行第二巻は118巻あります。それは紹興21年8月1日に始まり、同日に終わりました。サンディは、ジア...
「待合の梅は枯れた」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
【オリジナル】待合室の梅は枯れ、小川の橋の柳は細くなっている。香り高い草と暖かい風が手綱を揺らします...
世界で最も長寿の植物は何ですか?これらの植物の価値は何ですか?
植物は生命の主要な形態の 1 つであり、樹木、低木、つる植物、草、シダ、緑藻、地衣類などの身近な生物...