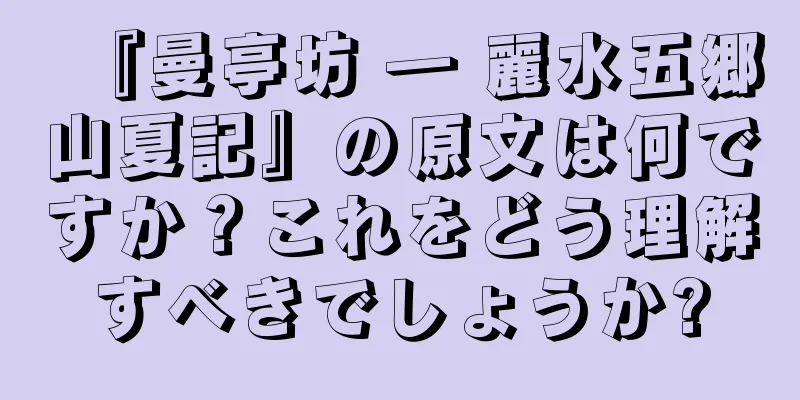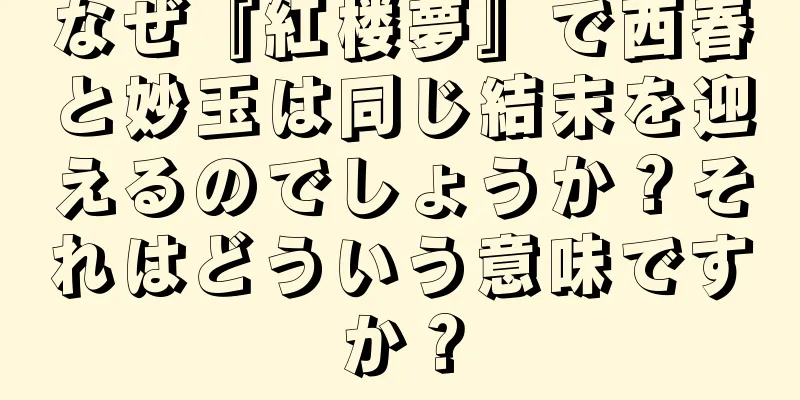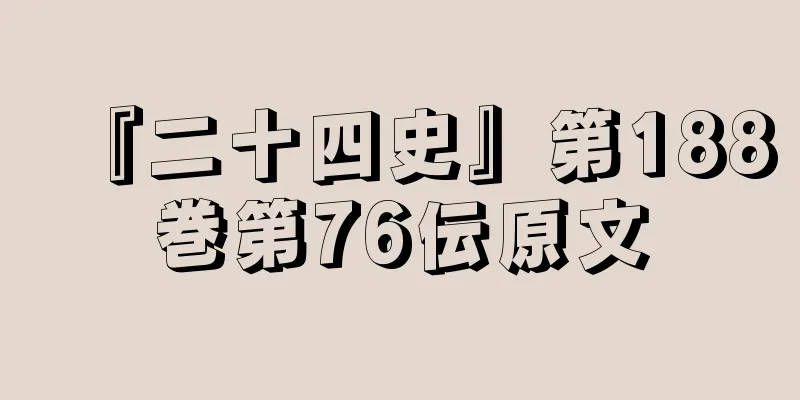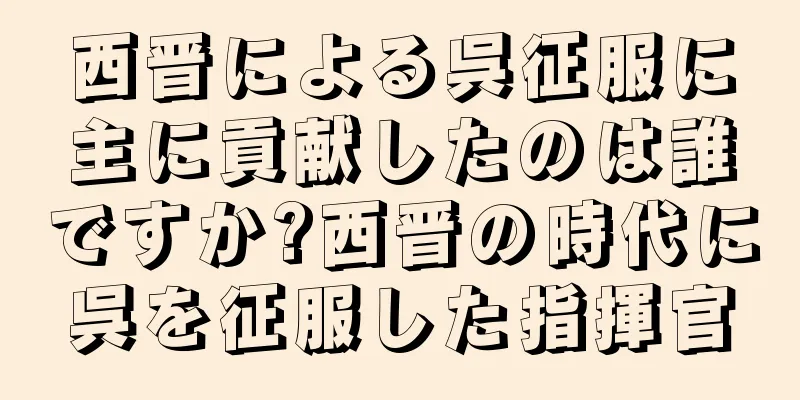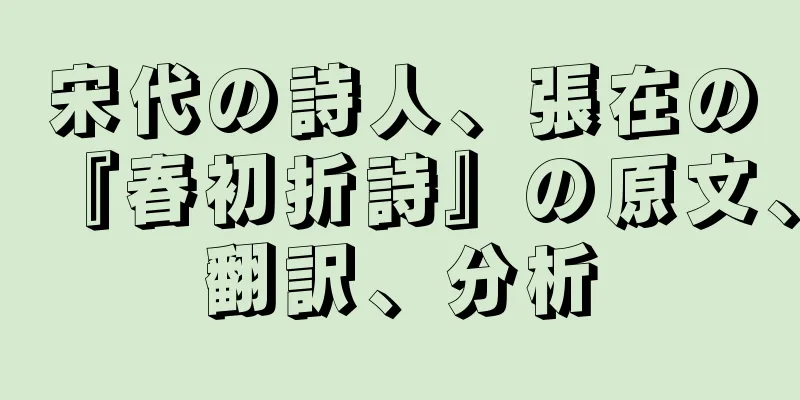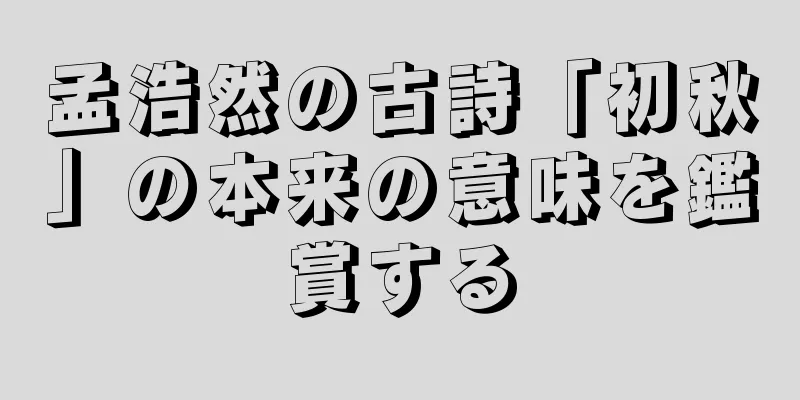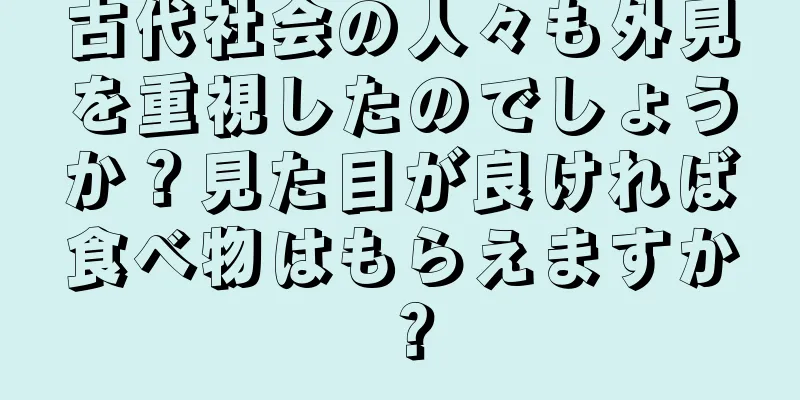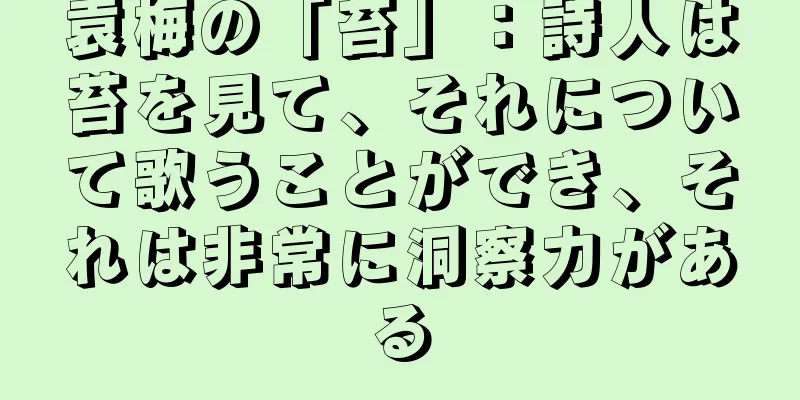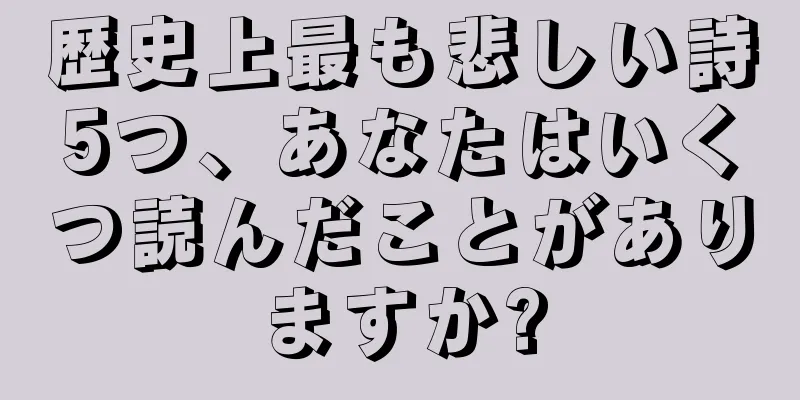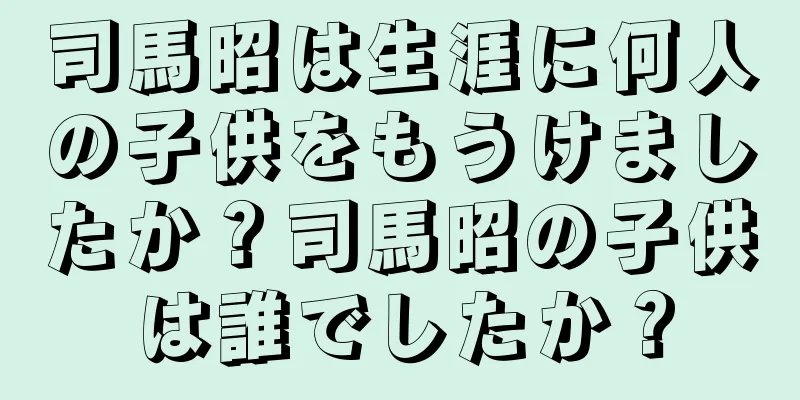唐代の詩の鑑賞:山越えの農夫、この詩にはどのような芸術技法が使われているのでしょうか?
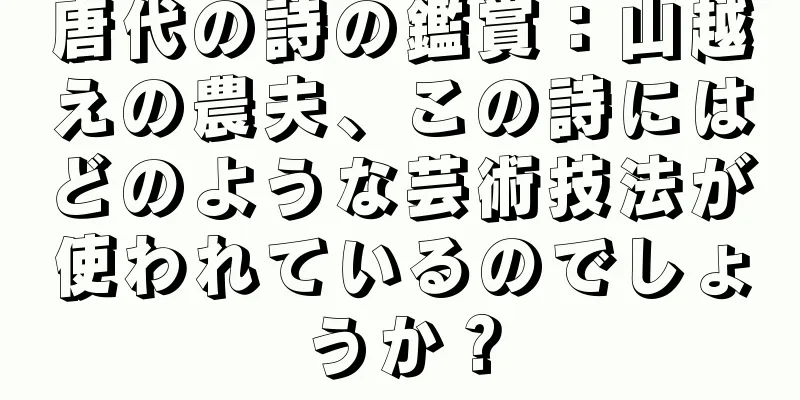
|
唐代の古光の郭山農家については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう! 板橋の泉を渡る人々の音、正午の茅葺き屋根の軒下で鳴く鶏の音。 お茶を焙煎するときの黒い煙に腹を立てるのではなく、穀物を乾燥させるときの澄んだ空に喜びましょう。 山間の農家を訪ねる様子を詠んだ六字四行詩です。詩全体は24文字から成り、作者は山を旅し、農家に到着し、茶の焙煎と穀物の乾燥を見学するという4つの場面を順番に描写し、興味深い訪問体験を鮮明に再現しています。著者は、長江南部の山村で茶を焙煎したり穀物を乾燥させたりする労働風景を、物から人まで、そして山間の農民たちの素直な性格や素朴な感情まで生き生きと描いています。明るい音色、活発なリズム、そして独特の芸術的スタイルを持っています。 最初の文「板橋の泉を渡る人々の音」は、旅の途中の光景を捉えています。著者が渓流にかかる木製の橋を渡っていると、湧き水のせせらぎの音が聞こえてきた。文章には「山」という言葉は出てこず、山の景色に関係する「板橋」と「泉の音」だけが書かれており、山旅の雰囲気を醸し出しています。 「板橋を渡る人、泉の音を聞く」というのは無理があるように思えますが、板橋を渡る人、泉の音を聞く人の独特の感覚を本当に表現しています。 「泉声」の「音」という言葉は、湧き水に生命を与え、山々の静けさを引き立てます。この文は農家の近くの環境を説明しており、「pass」という言葉を暗示しています。 「川を渡る人々」の「人々」は詩人自身であるが、詩人がそれについて書くとき、彼は絵の外を見ているようだ。詩の主題が対象と一体化し、風景の一部になっているようだ。この短い文章を読むと、まるで自分がそこにいるかのような、声が聞こえるような、そして作者がその人里離れた場所に入ったときのくつろいだ幸せな気持ちを共有できるような気持ちになります。 最初の文から 2 番目の文にかけて、時間と空間が飛躍しています。 「昼に茅葺き屋根の軒下で鶏が鳴く」は、作者が山や坂を越えて農家の玄関にたどり着く場面を描写している。鶏の鳴き声は目新しいものではないが、この詩に取り入れられると、山奥の農家がにぎやかな俗世の趣と豊かな生命の息吹で一気に満たされる。茅葺き屋根の家はまさに「山の農家」そのもの。正午の鶏の鳴き声は山里の静寂を破るかのように聞こえますが、同時に山の農家独特のゆったりとした静けさも感じさせます。この文の6つの単語は、順に3つの感情のグループを形成しており、最初の文で同じように形成された3つの感情のグループとは対照的で、6語詩の特徴を示しています。音節で言えば、2 語ごとに休止を挟んで、正確に 3 フィートの音を形成します。この文構造と低級の八庸韻の韻の使用により、特にリズミカルに聞こえ、音節が大きく響きます。 最初の 2 つの文は、独立していながらも密接に関連した 2 つの画像であると言えます。前の絵「春の音に合わせ板橋を渡る人々」は、山間の農家の近くにある板橋を描いたものです。橋の下には山の湧き水がゴボゴボと流れています。人々が橋の上を歩くと、目に映り、耳に届くのは澄んだ湧き水のゴボゴボという音だけです。詩の中に絵があるのですが、この絵は泉の音が聞こえる音の絵です。 2番目の絵画「茅葺き屋根の軒下で昼に鳴く鶏の図」は、「山間の農家に到着する」様子を描いたものです。暖かい日差しの下、茅葺き屋根の軒先は静かで、聞こえるのは数羽の鶏の長い鳴き声だけだった。世間の喧騒から遠く離れた、家族全員が働く山間の農家の独特の雰囲気が伝わってきます。 「農耕期には、誰もが農作業に時間を費やすので、誰も怠けることはない」(王維の『晴天野景』)。正午の鶏の鳴き声の静けさの描写は、まさにその静けさの背後にある忙しさと対照的です。表現技法の点では、この文は動きを使って静けさを対比させており、内容の暗示性の点では、一見静かそうに見えることで忙しさを暗に表現しています。したがって、3文目と4文目では、筆致は自然に山間の農民の仕事へと移ります。 「お茶を煎る時の黒い煙を怒るな、穀物を干す時の晴れた空を喜べ」この二文は、詩人が山の農家に到着した後、忙しく働いていた主人が詩人に言った謝罪の言葉でした。詩人が山の農家に着く数日前、連日雨が降り、茶葉は湿っていて、収穫した粟は太陽に当たらない状態だった。詩人が到着した日は、雨上がりに太陽が顔を出し、家族全員がお茶を煎ったり粟を干したりするのに忙しかった。家の中はお茶を煎ったり薪を燃やしたりする煙でいっぱいで、外の乾燥場にあるキビは時々ひっくり返す必要がありました。それで、親切なホストは心から申し訳なく思いました。 山の農夫の言葉は、農夫の表情や口調を生き生きと描写しているだけでなく、農夫の素朴さやおもてなしの心、雨上がりの天気のときの農夫の忙しさや喜びも生き生きと伝えています。このような本物の言語とシンプルな文字は、前述の静かな環境と調和し、シンプルで本物の生活の美しさを表現しています。最初の文「春の音」は雨上がりを意味し、2番目の文「鶏の鳴き声」は空が晴れてきたことを示し、前後の部分が首尾一貫し一体化しています。 「山」は「板橋」と「泉の音」で表現されます。板橋があれば、その下には必ず川があり、川に音が聞こえれば、それは間違いなく渓流です。 最初の 2 つの文は環境から始まり、登場人物を指摘していますが、3 番目の文は登場人物から始まり、環境を取り上げています。文体の変化は山農のイメージを際立たせるためで、著者は「茶を煎る煙が黒い」の前に「怒るな」という言葉を加え、労働風景を描きながら山農の心情を綴っている。農夫の率直な性格と労働者としての真の資質は、煙に巻かれたことを責めないでほしいと客に頼む口調に表れている。 「怒らないで」という二つの言葉は理にかなっていて、感情に満ちています。 「怒ってはいけない」に続く第4文では、「でも嬉しい」という言葉を使って、山農の素朴な気持ちと明るい性格を再び表現し、山農のイメージの描写を深め、詩全体の明るい調子に鮮やかなタッチを加えています。 六字連句は、各行の文字数が偶数で、六字が明確に三拍に分かれているため、自然に平行で流麗になり、整然とした文体になりやすい。多くは平行で始まり、平行で終わり、比較的流麗な言葉遣いになる。顧光の六字四行詩も起承転結の形式を採っているが、平易で自然な言葉で書かれており、前部と後部の文構造が変わっているため、読んでいて単調さや堅苦しさを感じず、むしろ軽妙で自然、新鮮で素朴である。詩のスタイルと内容は、高度に調和した美しさを示している。 |
<<: 唐代の詩の鑑賞 - 田んぼ、この詩ではどのような芸術技法が使われているのでしょうか?
>>: 唐代の詩の鑑賞:秋の夜に王さんと幸せな出会い、この詩ではどのような芸術技法が使用されていますか?
推薦する
「女仙の非公式歴史」第69章:三如王子は、雄県の道士二松にリーダーを縛るために提示します
『女仙秘史』は、清代に陸雄が書いた中国語の長編歴史小説です。『石魂』や『明代女仙史』とも呼ばれていま...
南宮公主は匈奴と結婚したのですか?南宮公主と二人の夫
現在、ドラマ「魏子夫」が放映中だ。ネットユーザーの中には、南宮公主が劇中に登場せず、ほんの少ししか触...
四大発明のコンセプトはどのようにして生まれたのでしょうか?四大発明を最初に指摘したのは誰ですか?
中国文明の重要な業績の多くは、四美女、四季小説、四書、五経など「四偉」または「五偉」と呼ばれています...
古代の人々は公の場で一人称を表現するためにどのような言葉を使ったのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、古代の最初の人物がどのような人物だったかを...
朱棣は明王朝の威信を高めるためだけに鄭和を西海に派遣したのでしょうか?
明王朝は中国の歴史上、漢民族によって建国された最後の統一された封建王朝でした。明朝初期には、最も有名...
野呂景は政治的に何をしましたか?野呂景の政治的措置は何でしたか?
耶律経(931-969)は、別名舒禄とも呼ばれ、後周の時代には祖先郭靖の禁忌を避けるために耶律明と呼...
あまり知られていない李玉の作品「カラスは夜鳴く」。読んだことがありますか?
975年、金陵城が陥落し、李郁は南唐最後の王となった。捕らえられた李郁は汴京城に連行され、投獄された...
秦の六国統一に貢献した武将の中で、より有能だったのは誰でしょうか?
戦国時代後期、秦の統一戦争の時代、秦国には多くの名将がいて、人材を登用し、一歩ずつ統一を果たしました...
『張立本女謡を聞く』の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
張立本の女性詩を聴く(1)高石彼女は楚宮⑵の宮女のような高帽と広い袖を着け、涼しい夜⑶の閑静な庭園を...
白骨の悪魔とは誰ですか?最も哀れで興味深い妖精
白古静は骨から変化した悪魔を意味する民間名です。 『西遊記』の原典『西遊記詩篇』では、白骨はまだ霊に...
水滸伝に登場する108人の英雄の中で、誰がその強さを過大評価されているのでしょうか?
水滸伝の英雄とは、一般的に水滸伝に登場する梁山泊の英雄のことを指します。今日は、Interestin...
「李都衛の古剣」をどう理解するか?創作の背景は何ですか?
李都衛の古代剣白居易(唐代)古代の剣は冷たく、ぼんやりとしており、何千年もかけて鍛えられてきました。...
李玉の「斗蓮子嶺:深庭の静寂」:この短い詩は美しい霞んだ詩である
李毓(937年8月15日 - 978年8月13日)は、徐州彭城県(現在の江蘇省徐州市)出身で、江寧県...
本草綱目第8巻・生薬・ギボウシの原文の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
「酔っぱらいの意図は飲まないことである」の次の文は何ですか?それはどこから来たのか
「酔っぱらいの意図は飲まないことである」の中国語の解釈【解説】:もともと著者は、亭に泊まった本当の目...