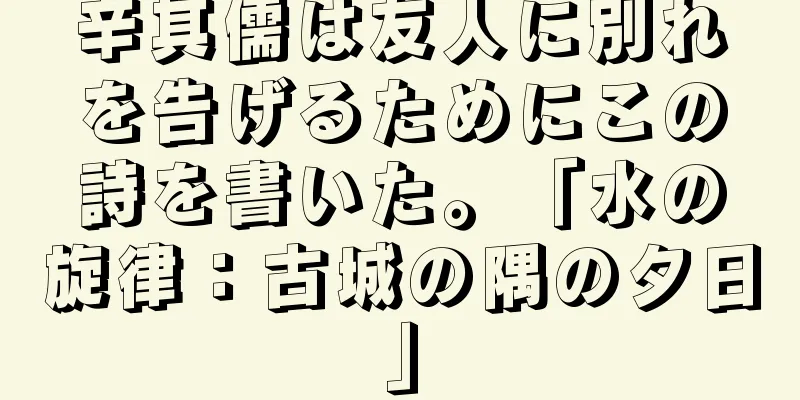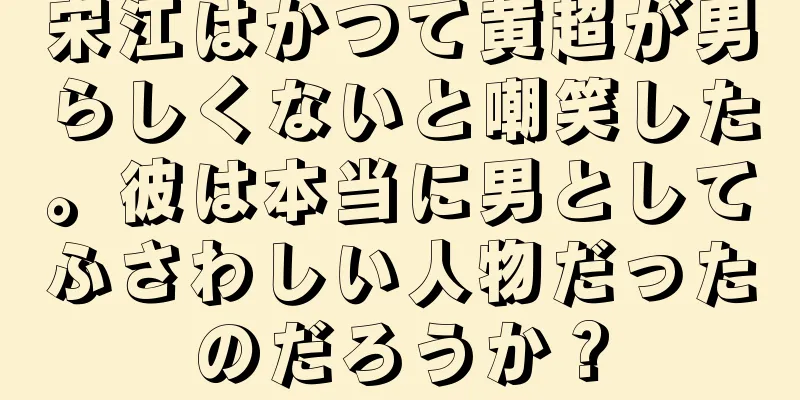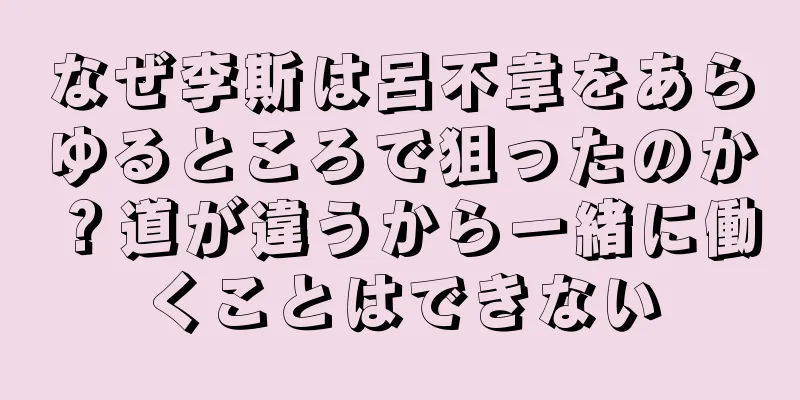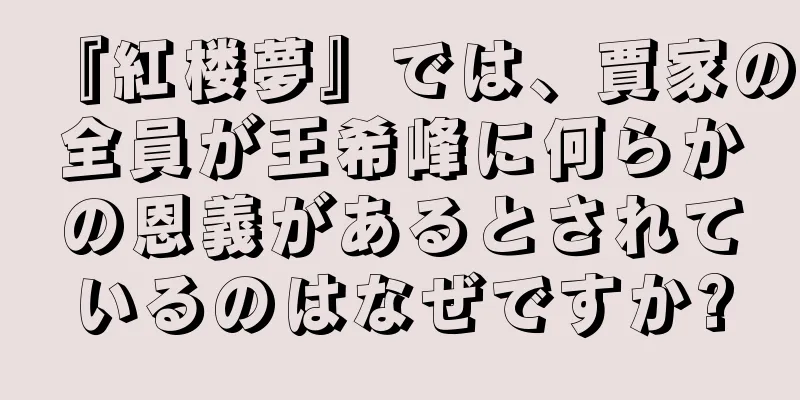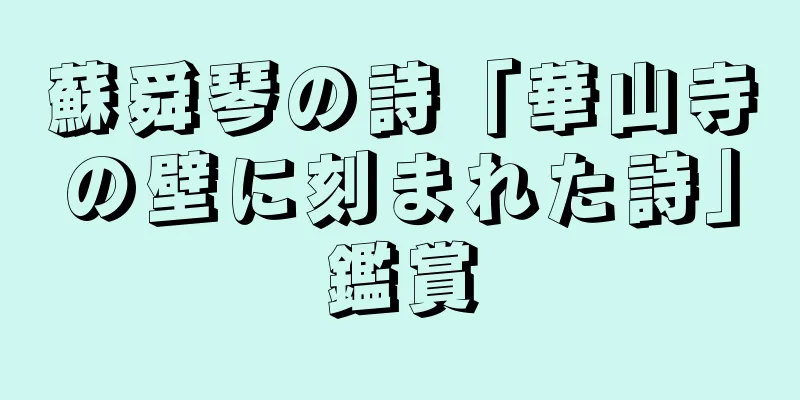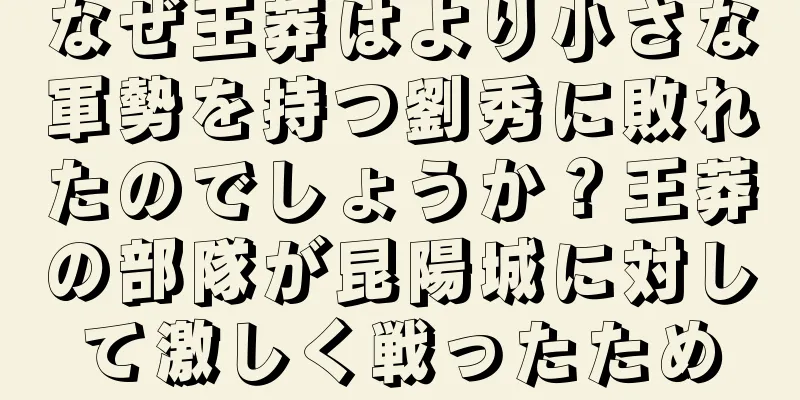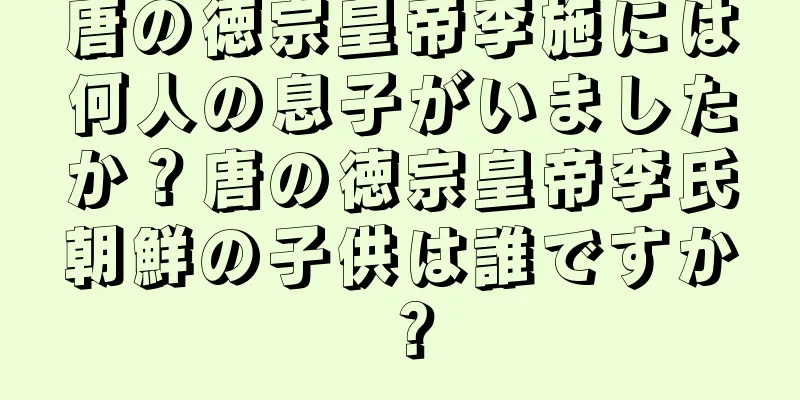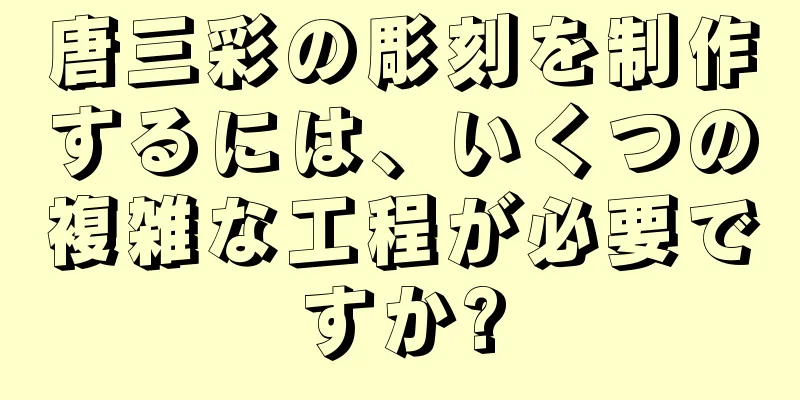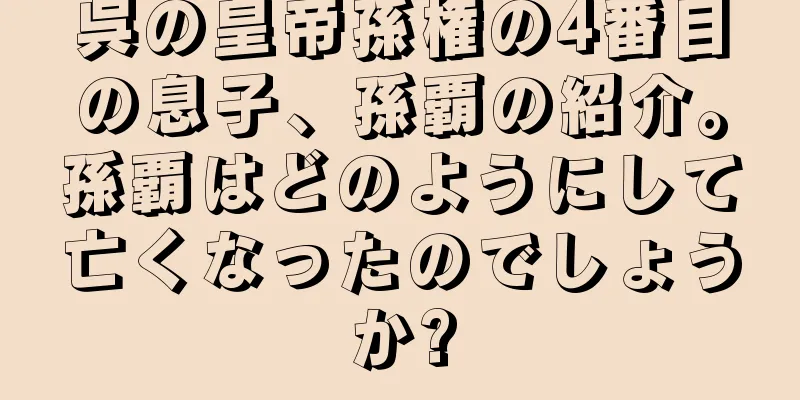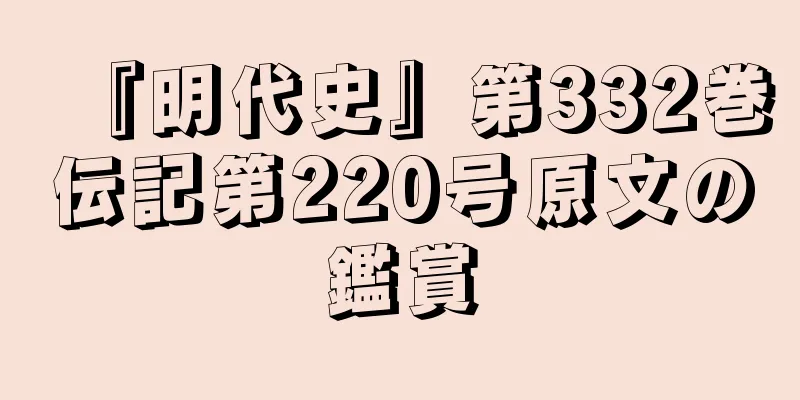その年の戦いで、顔世三は死んだものの、三番目の若旦那は敗北した。
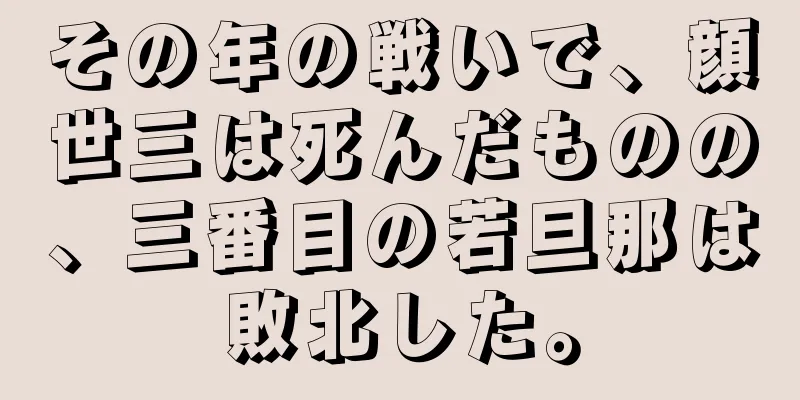
|
古龍は武侠小説における「江湖」という概念を初めて人々の心にもたらした人物であり、それ以来、江湖は大人の心の中の童話となり、「江湖」は文学上の概念となった。古龍の武侠小説の中で最も記憶に残る登場人物は、顔世三と謝小鋒である。 どちらも『三小坊主の剣』からの引用で、謝小峰はエクスカリバー山荘の三小坊主です。タイトルを合わせると、この本の主人公が謝小峰であることは容易にわかります。しかし、古龍は序盤に大量の文章を使って燕世三の性格を描写し、その後三小坊主に関する内容が徐々に展開されました。このことから、古龍が燕世三の性格を重視していることが分かります。本全体の2番目のキャラクターと言うよりも、この本の2番目の主人公と言ったほうがいいでしょう。 なぜなら、経験と武術の面では、ヤン・シサンは謝小鋒の鏡のような存在だが、鏡の中の人物は正反対であるため、謝小鋒は「剣神」であり、ヤン・シサンは「剣魔」である。 主人公についてはすでに多くのことを知っていますが、ヤン・シサンについて学びましょう。彼の名前にも良い由来があります。「ヤン・チー」という男と「ヤン・ウー」という男がいたと言われています。ヤン・シサンは、自分がこの二人を合わせたよりも強いと感じたので、自分を「ヤン・シサン」と名付けました。 この本の中のヤン・シサンは矛盾に満ちているが、すべては論理的である。彼は剣の鬼であるが、執着心はない。彼は数え切れないほどの人を殺してきたが、彼自身が言ったように、「一度世に出たら、他に選択肢はない」。このような人物は、中立的だが少し邪悪な態度で見られるかもしれない。謝小峰のポジティブな性格とは異なり、ヤン・シサンの人生における目標はただ一つ、謝小峰を倒すことである。 実は、物語の最後には、二人の男の間に衝撃的な戦いが必ず起こることがここで分かっています。 燕世三は神建山荘に来て謝小峰が死んだと聞いて、神建山荘の船に「十字架」を彫り、二十年間持ち歩いていた魔剣「骨毒」を湖に投げ入れました。 剣士にとって、剣は命そのものである。ヤン・シサンの行動は、彼が何のために生きているかをすでに説明している。謝小鋒と違って、彼はただ勝つことだけを望んでいる。なぜなら、謝小鋒は武術界全体で彼と戦える唯一の存在であり、彼が認めているのは三代目小姐だけであるからだ。 結局、誰も予想していなかったが、皆の予想を超えて、ヤン・シサンとシェ・シャオフェンは頂上決戦を開始し、それは決定的な戦いとなった。古龍は華麗な言葉でこの戦いを表現したが、結末は皆の予想を超えていた。 三番目の小姐はまだ生きているので、主人公のオーラを放っています。 たとえヤン・シサンが彼の前で十三の必殺剣を使ったとしても、謝小峰と比べるとまだ見劣りします。 すべては予測可能な軌道に沿って配置されているようです。 ヤン・シサンが十四番目の剣の変化に気づいたときでさえ、それはまだ予測範囲内でした。 結局のところ、頂点を極める競争は、主人公がただ他人を圧倒するだけでは勝てず、クライマックスも必要です。ヤン・シサンは、この14番目の剣が最高の配置であることに気づきました。この14番目の剣でさえ、謝小峰の魔法剣よりわずかに劣っていたからです。このルーチンによると、「悪役」は不本意に地面に倒れるはずです。14番目の剣は、3番目の若いマスターの力をさらに認識しました。ヤン・シサンは常に脇役であり、驚くべき14番目の剣でさえ、開花しようとしているつぼみに過ぎませんでした。エンディングは完璧でした。 しかし予想外だったのは、ヤン・シサンも死を表す15番目の剣を理解していたことです。三番目の若いマスターでさえこの剣を防ぐことはできませんでした。この剣は必然的に死につながります。この瞬間、咲きそうだった花が突然思いがけず咲きました。 燕世三は突然、三小姐が自分の命を救ってくれたことを思い出した。 間違いなく死に至るこの剣を前に、彼はもう引き返すことができなかった。なぜなら、死を象徴するこの剣は彼の制御下になかったからだ。 むしろ、剣が彼を制御しているようだった。 彼は、死を必然的にもたらすこの剣がこの世に残ることを望まなかったので、剣を向けて喉を切った。 三小姐は、燕世三の体の横にぼんやりと立っていた。 彼は混乱していたし、読者も混乱していた。 この瞬間の燕世三のオーラは、間違いなくキャラクターの限界を超えていた。 なぜなら、彼は、自分と同じくらい孤独で、栄光の重荷に窒息している人物を目覚めさせたからだ。 三番目の若旦那は両手の親指を切り落とし、剣を握ることができないようにした。顔世三は死んだが、三番目の若旦那は敗北した。 |
<<: 金庸の現代武術小説『射雁英雄伝』に登場する霊芝師匠の簡単な紹介
推薦する
『紅楼夢』の宝玉の周りにはどんなメイドさんがいますか?美仁と千雪はどう終わったのですか?
宝玉は、有名な中国の古典『紅楼夢』の男性主人公です。 Interesting History の編集...
石獅子文化はいつ誕生したのでしょうか?中国の石獅子文化の発展史!
今日は、おもしろ歴史編集長が中国の石獅子文化の発展史をお届けします!皆様のお役に立てれば幸いです。石...
五福神はどのようにして生まれたのでしょうか?五福神の起源と伝説
財神は誰もが大好きな神様のはずですが、五大財神がどのようにして生まれたのかご存知ですか? 今日は、I...
魯迅はいつ亡くなったのですか?魯迅は何歳でしたか?
魯迅はいつ亡くなりましたか? 魯迅は何歳でしたか?魯迅は1936年10月19日に55歳で亡くなった。...
なぜ孫悟空は唐僧を女魔族のエロい罠に陥れたのか?
孫悟空はもともと花果山の水幕洞窟の猿の王であり、「孫悟空」として知られていました。その後、何州新...
曹丕の政治政策:官制の改革、皇帝権力の集中、官風の是正、分離主義政権の排除
今日は、Interesting Historyの編集者が曹丕の政治的措置についてご紹介します。興味の...
尚官婉児はどのようにしてその知性と才能を駆使して主要な政治勢力の間で策略を巡らせたのでしょうか?
神龍の政変は、神龍革命、五王の政変とも呼ばれ、神龍の治世の元年(705年)に皇太子の李献、宰相の張建...
馬王妃にはどんな能力がありますか?あなたが生きている限り、朱棣の反乱を阻止できるでしょうか?
馬小慈高皇后は、明代の太祖朱元璋の最初の妻であり、楚陽王郭子興の養女であった。馬皇后は徳が高く、賢明...
包公の事件簿 第47章 愚かな棒
『鮑公案』は『龍土公案』とも呼ばれ、正式名称は『都本鮑龍土百公案全伝』で、『龍土神段公案』とも呼ばれ...
隋唐演義第93章:雷海青は寧壁池で亡くなり、王莫傑は普寺で詩を詠んだ
『隋唐志演義』は清代の長編歴史ロマンス小説で、清代初期の作家朱仁火によって執筆されました。英雄伝説と...
詩人陳玉毅が青墩鎮の僧院に隠棲していた時に書いた作品「臨江仙:夜小亭に登り羅中の昔を思い出す」を鑑賞
陳毓宜(1090年 - 1139年1月1日)は、字を曲飛、号を建寨といい、漢民族である。彼の先祖は荊...
テナガザルはどれくらい強いですか?孫悟空よりも強い猿
西遊記には4匹の猿が登場します。孫悟空の他に、トンギ猿、六耳猿、アカオザルもいます。この4匹の猿は1...
馮巴はどのように発音しますか? 馮巴の簡単な経歴。馮巴はどのように亡くなったのですか?
馮覇(?-430)、号は文斉、号は奇之法、長楽県新都(現在の河北省冀州)の人。十六国時代の北燕の君主...
なぜモンゴルの馬は他の馬よりも戦争に適しているのでしょうか?
1. 物流上の理由: 古代では、戦闘では通常 2 頭の馬が使用され、時には 3 頭の馬が使用されまし...
張騫は長安に戻った後、漢の武帝にどのような詳細な報告をしたのでしょうか?
建元元年(紀元前140年)、漢の武帝劉徹が即位し、張騫は宮廷官吏に任命された。建元3年(紀元前138...