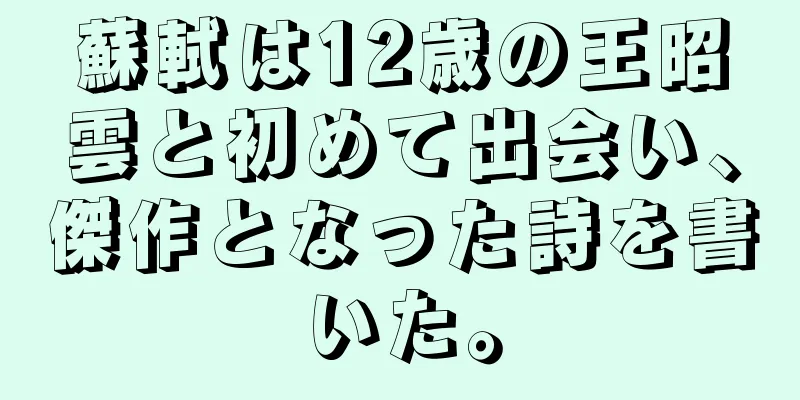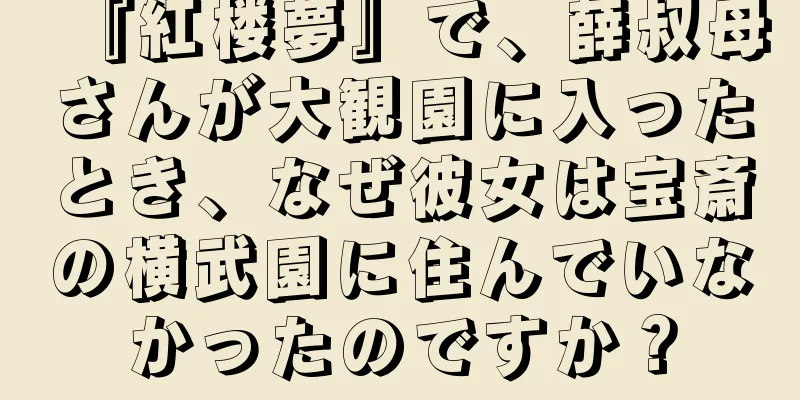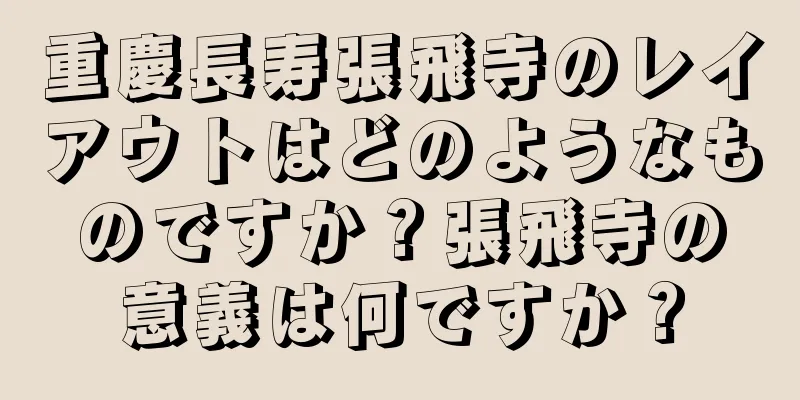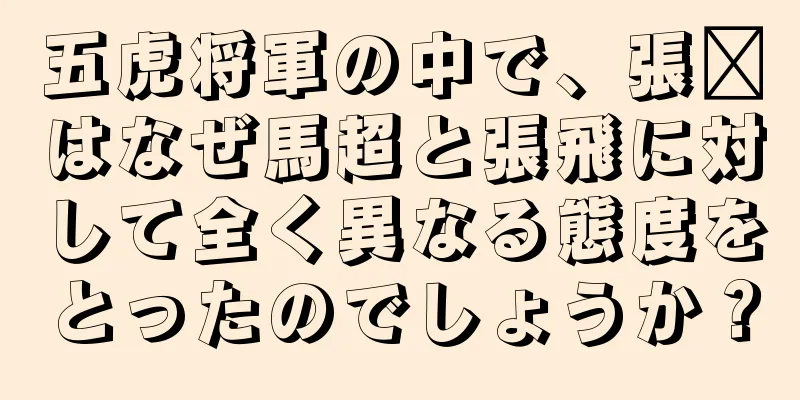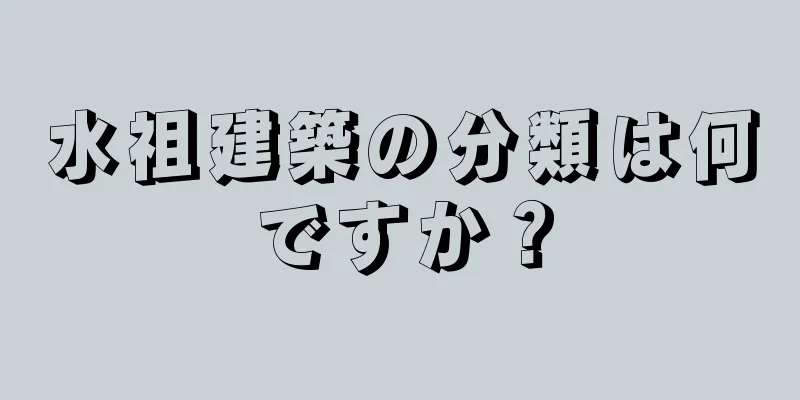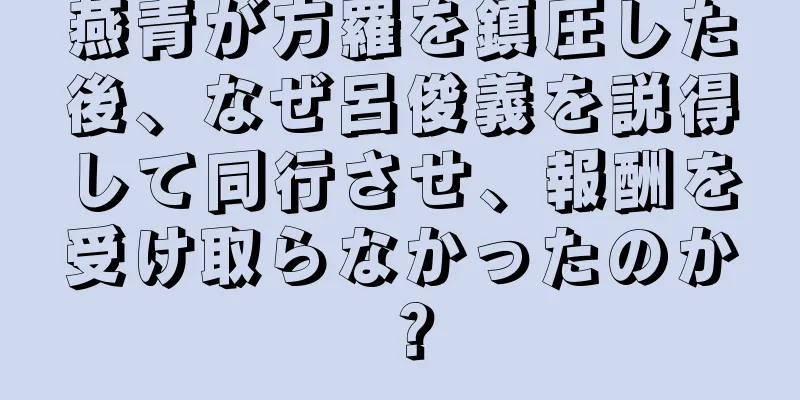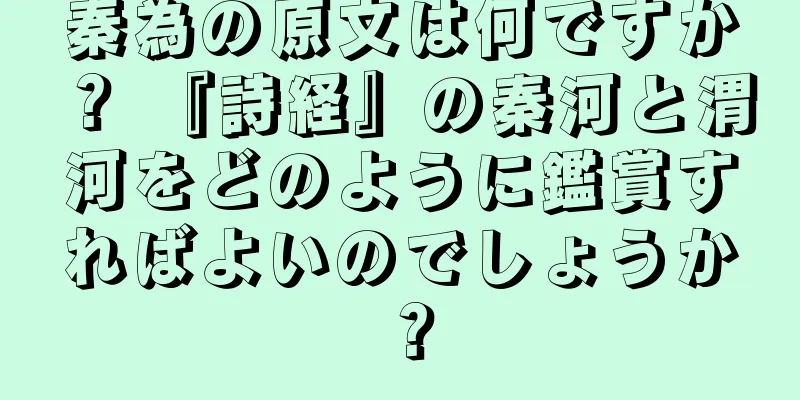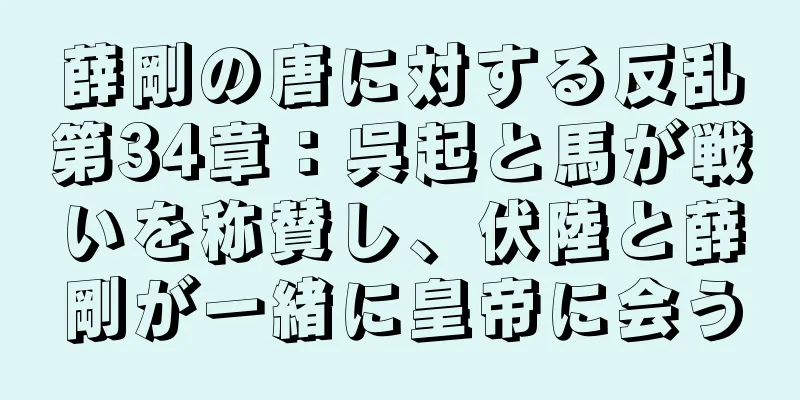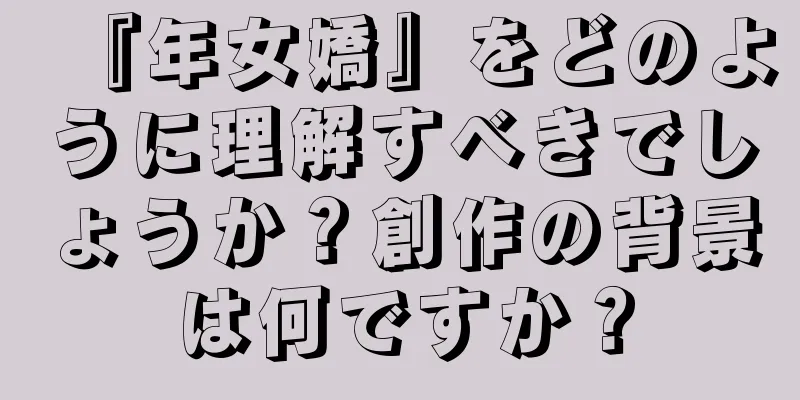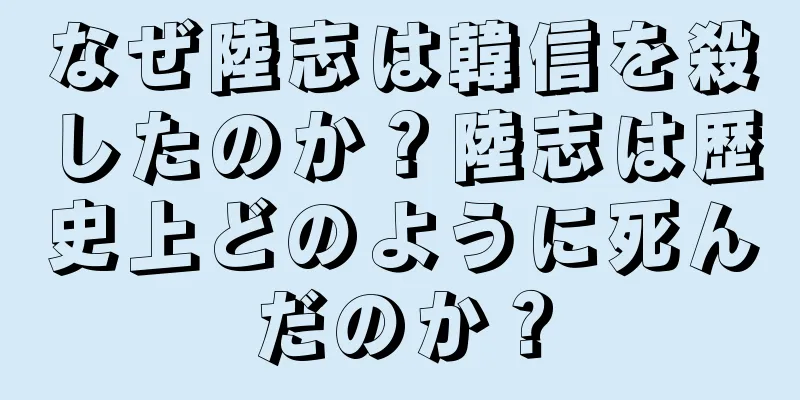「節度」という言葉はどこで最初に登場したのでしょうか? 「中庸の教義」の著者は誰ですか?
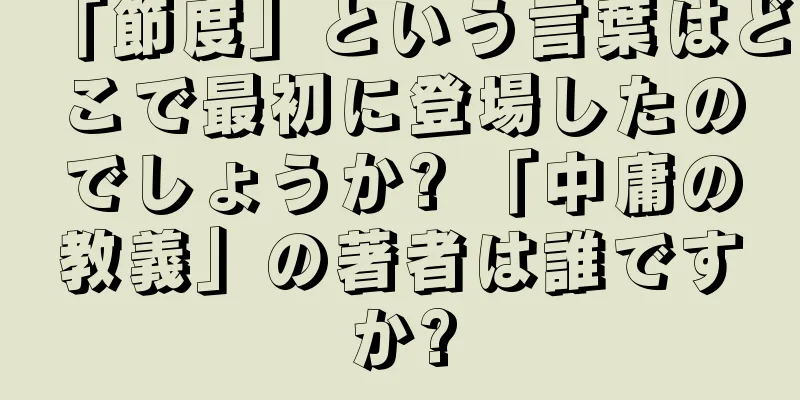
|
「中庸の教義」をご存知ですか?今日はInteresting History編集長が詳しく紹介します。 中庸の教えは、人を公平に、過剰でも不足でもない方法で扱うことを指し、これは儒教の道徳規範と思想方法でもあります。 「中」は調和と公平を意味し、「容」は正常と有用を意味します。 「中庸」という言葉は『論語』という書物に初めて登場しました。しかし、考え方としては、長い歴史的起源を持っています。堯が舜に王位を譲ったとき、社会を統治するには「中庸を保つ」必要があると強調したと言われている(『論語』、と堯は語った)。孔子はかつて舜を称賛してこう言った。「舜は知恵が深い。舜は質問をしたり、周囲の言葉を調べたりするのが好きで、悪を隠し、善を推し進め、両極端を保ち、中間の立場で民を利する。これが舜ではないか」。『商書』などの資料から判断すると、周公も「中庸の徳」を主張した。彼はかつて、事件を裁き、刑罰を科す際には「公平」である必要があると強調した。節度の考え方は易経にも明確に反映されています。孔子は古代の資料に基づいて「中庸」の概念をさらに提唱し、それを最高の道徳基準として体系的に発展させました。孔子は言った。「中庸の徳は最も高い!しかし、長い間、人々の間で稀であった。」(論語、雍業)また、彼は言った。「君子は中庸であり、悪人は中庸の反対である。」孔子の中庸の考えは矛盾の存在を認めており、例えば孔子は言った。「私は知識を持っていますか?私は知識がありません。俗人が私に質問しましたが、私はわかりませんでした。私は彼に両端から質問し、それらを尽くしました。」ここでの「両端」は、2つの反対の極です。対立する当事者に対処する際には、矛盾の激化と変化を防ぐために「中和」のアプローチを採用する必要があります。そのため、『論語』には「君子は和して異なり、悪人は同して不和なり」「異端を攻撃するのは有害なり」とある。 孔子にとって、中庸の教えは行動方法として非常に実践的です。中庸の教義では、すべてが中庸かつ適切でなければならないとされています。孔子は国を治めるにあたり、「正義と公平」を唱え、「礼楽が盛んでないなら、刑罰はふさわしくない」と説いた。また、「寛大は厳しさを助け、厳しさは寛大さを助け、こうして政治は調和する」とも説いた(昭公20年『左伝』)。美学の面では、孔子は優雅さと実質の融合を主張し、「実質が優雅さに勝れば、結果は荒々しくなり、優雅さが優雅さに勝れば、結果は衒学的になる。優雅さと実質が完全に調和して初めて、君子と呼ばれることができる」(『論語』雍業)と信じていました。彼はかつて詩経の関居篇を「喜ばしいが淫らではなく、悲しいが悲しくない」(『論語』八一)と称賛しました。かつて孔子の弟子である子貢が「物と商のどちらが優れているか」と尋ねました。孔子は「物は過剰であり、商は不足である」と答え、また「過剰は不足と同じくらい悪い」とも言いました。 (論語、仙津)彼は、人々の行動はやり過ぎてもやり足りてもいけない、ほどほどにすべきだと信じていました。つまり、孔子の教えには社会生活のあらゆる側面における中庸の教義が含まれているのです。 孔子の中庸の教義は彼の政治思想と相互に関連している。孔子は「礼儀」を非常に重視し、常に「礼儀」の基準に従って個人的な思考と行動を規制しました。彼の中庸の考えについても同様です。孔子が「士は行き過ぎ、商は近づかなかった」と話していたとき、誰かが「中道とはどういう意味ですか?」と尋ねました。孔子は「礼は道である。礼は中庸を規制するために用いられる」と答えました。(『礼記』、閻居中尼) 中庸を規制するために礼を用い、また、礼を測定基準として用いるという、孔子の中庸の考えは時代遅れであるように思われます。しかし、儀式は常に進化し、変化しています。別の観点から見ると、孔子の中庸の教え自体も「節度」と便宜を重視しています。孔子はこう言いました。「君子にとっての中庸の教えは、君子が常に中庸であることだ。」(『中庸の教え』) 孔子が「常に中庸」という言葉で意味したのは、物事を扱う際には状況を判断し、それに応じて行動し、常に中庸であるよう努めるべきだということです。そこで朱熹は次のように説明しました。「君子が中庸であるのは、君子の徳を備え、いつでも中庸でいられるからだ。」 「中庸には決まった形がなく、いつもそこにある。これが常識である。君子はそれが自分の中にあることを知っているので、用心深くても見ず、恐れていても聞かず、いつでも中庸である。」 実際、孔子はこのように物事を扱ったのです。孟子は、伯夷、易寅、劉夏慧と比較した後、孔子を「時を知る賢人」(孟子『万章』下)と称え、「奉仕できるときに奉仕し、立ち止まることができるときに立ち止まり、長く留まることができるときに長く留まり、すぐに立ち去ることができるときにすぐに立ち去ることができる、これが孔子である」(孟子『公孫丈』上)と述べています。孔子自身が「時節に節度を保つ」という行動基準を捉えていたことがわかります。 孔子以降、あらゆる世代の儒学者は中庸の教えを繰り返し解釈し、発展させ、中庸を儒教徒が世界を理解し、社会生活に対処するための基本的な方法としました。宋代以降の新儒学者は中庸を非常に重視した。『中庸論』の序文には程子の次の言葉が引用されている。「中庸は偏らず、中庸は変らない。中庸は世の中の正しい道であり、中庸は世の中の不変の原則である。」朱熹はまた、中庸とは「過不足なく、正しく行う」ことであり、そのためには「すべてを正しく認識し理解することが必要であり、そうして初めてこれが達成される」と信じていた(『朱熹要略』第64巻)。このように、「中庸」は儒教の人々が世界を理解するための基本的な方法、物事に対処するための基本原則となるだけでなく、一般の人々の社会的、心理的な蓄積にもなります。 孔子の中庸の教えが最も古く体系的に解説されたのは、『中庸』という本です。 『中庸論』全体は「中庸」を最高の道徳・自然法として捉え、天の道と人の道の関係を説いている。彼は孔子の中庸を継承した上で、中庸を人性や道徳と結び付けて、「中庸は天下の大元であり、和合は天下の道である。中庸が達成されると、天地は定まり、万物は育まれる」と提唱した。中庸は、「誠意」を最高の道徳境地と天地の根源とみなし、「徳と自然を尊重する」と「道によって知を求める」という二つの修身の形式を論じ、「誠意」の姿勢で人は天の道と一体となり、「最高の智慧と中庸」を達成し、人自然合一の境地に達し、天地の育みを讃えることができると提唱した。 しかし、「中庸の教義」の著者と著作については、常に2つの異なる意見が存在してきました。一つの説は、子思が戦国時代後期に著したとする説であり、もう一つの説は、秦が六国を統一した後に著したとする説である。どちらの見解も、子思が『中庸』を著したという見解に反対している。 伝統的な見解では、『中庸論』は子思によって書かれたとされています。 「子思が中庸を書いた」と明確に述べた最初の人物は、『史記・孔子一族』の司馬遷である。その後、漢代と唐代の儒学者のほとんどがこの見解に従いました。鄭玄は「中庸の教え」と名づけられたのは、節度と調和の用法を記しているからである。用とは用法のことである。孔子の孫の思季が、聖祖の徳を示すためにこれを書いたのである。(『礼記』第52巻)唐代の陸徳明と孔英達もこの見解に同意した。宋代の二成や朱熹も同様で、彼らはみな子思が『中庸』を書いたと信じていました。例えば、朱熹は『中庸篇』を書いたとき、はっきりとこう言っています。「『中庸篇』はなぜ書かれたのか? 子思は道教の研究が失われることを心配して書いたのだ」また、「この篇は孔子が伝えた心法である。子思は時が経つにつれて歪められることを恐れ、本に書いて孟子に伝えた」とも言っています。現代の学者の中には、子思が『中庸篇』の著者だと考える人もいます。例えば、胡適は、この本には後世の資料がいくつか追加されたものの、一般的には孟子以前の著作とみなされるべきだと信じていました。孔子から孟子までの人生哲学の発展には移行段階があるはずだからです。この過程は、極めて倫理的、君主的、かつ極めて実践的な人生哲学から、「個人の尊重」、「公民権の擁護」、「心理学的な人生哲学」への移行です。 『大学教育』と『中庸の教義』はこのプロセスを反映しています。 子思が『中庸』を書いたという事実に異論を唱える意見は、後になってから現れた。彼らが主張する証拠は、『中庸』第28章にある「今日、我々の乗り物は同じ軌道をたどり、我々の本は同じ書き方をし、我々の行いは同じ倫理である」という言葉である。彼らは、これが明らかに秦の始皇帝が中国を統一した後に使われた言葉であると考えている。 『中庸の教義』には、「地位があっても徳がなければ、礼楽を創る勇気はない」とも記されている。これは秦王朝の崩壊後の時代にも当てはまると考えられている。 子思が『中庸の教義』を執筆することに問題はないはずだと私たちは考えています。東漢の班固は『漢書・義文志』の「礼」の項に『中庸』の2章を記録しているが、著者については触れていない。一方、彼は「儒教」の項に『子思』の23章を記録しており、「名は季、孔子の子孫、魯の穆公の師」と注記している。また、『中庸』が含まれているかどうかも明らかではない。 『漢書』の『易文志』の「礼」の項には、『礼書』のどの章にも独立した題名がなく、『中雍説』のみが収録されている。そのため、顔世古は「現在『礼書』には『中雍』の章があるが、これももともと『礼書』のものではなく、同類のものである」と評している。『中雍説』は『詩書』の『陸士説』や『韓士説』のように、「中雍」について「語る」特別な作品なのかもしれない。これは、『中雍』が以前から単独で流布しており、相当な影響力を持っていたことを示している。上で引用した「車は道なり、書は字なり」という言葉について、鄭玄は「孔子は今がその時だと言った」とも言った。実際、李学勤氏は正しい。「孔子は、周王朝が衰退し、政治的、文化的に分裂傾向にあった春秋時代後期に生まれた。『標準的な乗り物、標準的な書物、標準的な倫理』という現実はもはや存在しなかった。……『中庸』のこの一文によれば、『今』という言葉は『もし』と解釈されるべきである。『経文評論』は、古代の書物から多くの例を引用している。……それらはすべて仮説である。孔子の言ったことも仮説であり、当時の事実ではない。この一節によって『中庸』の古さを疑うことはできない。」(『失われた文明』344-345ページ、上海文学芸術出版社、1997年) 子思が『中庸論』を書いたという主張は、最新の資料によって確認された。荀子の『費世子』はかつて子思と孟子の「五行」理論を批判した。馬王堆漢墓絹本から儒教の著作『五行』が発掘され、「荀子の『費世子』で批判された子思と孟子の五行理論が何であるかを証明し、『中庸』と『孟子』にこの教義の痕跡を見つけ、『中庸』が子思の著作であることを確認した」(同書、343ページ)。 1993年冬、湖北省荊門市郭店の楚墓から大量の竹簡が発掘された。『郭店楚墓竹簡』は1998年5月に文化財出版社から出版された。その中には儒教の学術書があり、2つのグループに分けられます。1つのグループには、『黒服』、『五行』、『程知文志』、『敬徳義』、『天性来自』、『六徳』が含まれます。李学芹の研究によると、郭店の竹簡にあるこれらの儒教の書籍は、儒教の子思派に属しています。『黒服』を含む6つの章は、『漢書・易文志』に収録されている『子思』に帰属するはずです。同時に、これらの竹簡の儒教書は『中庸』と多くの類似点を持っています。例えば、『天性天命』では「天性は天命であり、天命は天から授けられたものである」と論じており、これは『中庸』の「天命は天の天命であり、天命に従うのが道である」と一致しています。また、「徳義を尊ぶ」の形式も『中庸』と非常に似ています。沈月はかつて『中庸』は『子思』から取ったものだと言い、また竹簡には『呂慕公問子思』もある。したがって、これらの竹簡の儒教本は『子思』と何らかの関係があるに違いなく、これもまた『中庸』が子思によって書かれたものであることを証明している。 もちろん、子思が『中庸』を書いたという主張には何ら間違いはないが、それは現在の『中庸』がすべて子思自身によって書かれたということを意味するものではない。実際、『中庸の教義』を含む多くの初期の古典は、継続的な流通、編集、執筆のプロセスを経てきました。我々の研究によれば、現在『礼記』に見られる「中庸の教義」は漢代に編纂されたものに由来しており、子思が最初に書いた「中庸の教義」を収録し、関連する内容が補足・増加されたものである。しかし、全体としては、『中庸』の主な内容と思想は主に子思から来ており、子思と最も密接に関連しています。 |
<<: 天鵬元帥は過ちを犯したために現世に降格されたのに、なぜ自分を裏切ったのは孫悟空だと責めたのでしょうか?
>>: 儒教の四大古典の一つ『大学』とはどのような古典ですか?
推薦する
「西安南芍薬図」の制作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
西安南樹牡丹鑑賞劉玉熙(唐代)私たちはこの世界で、増城市の祖母の家で偶然出会いました。こんなにも見事...
唐代の詩人、魏英武の『雨中県庁の学者との宴』の原文、注釈、翻訳、鑑賞
「雨中郡書院士宴」は、唐代の魏応武によって書かれたものです。次の興味深い歴史編集者が、詳細な紹介をお...
中国古典の鑑賞:孟子原典第60巻「朱子余礼」
◎献身的△心を捧げる者の章「自分の心を精一杯使う者は、自分の本性を知る。」この「者」という言葉は、注...
詩人李洵が蓮池を巡る春の少女の情景を描いた「南湘子乗彩舟」鑑賞
李勲(855?-930?)は唐代末期の詩人。彼の愛称はデルンであり、彼の先祖はペルシャ人でした。四川...
范進は科挙に合格したとき何歳でしたか?彼は最終的に宮廷でどのような官位に就いたのですか?
大学入試は、今日の中国社会において人材を選抜する方法の一つであることは誰もが知っています。大学入試の...
石公の事件第465章:リーダーの王は心からアドバイスを提供し、石曹都は部下に提案します
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
水滸伝の関勝と崇はどれくらい優秀ですか?一対一の戦いで勝つ確率が高いのは誰でしょうか?
関勝 - 涼山五虎将のリーダーである関勝は、小説『水滸伝』の登場人物であり、涼山坡の英雄の中で騎兵五...
南宋と南明はどちらも南下した政権でしたが、なぜ両者の間にはこれほど大きな違いがあったのでしょうか。
南宋と南明はともに南下した政権であったが、両者の間には大きな違いがあった。南明朝は文化的業績を残さな...
晋の元帝、司馬叡はそんな人物でした。歴史は司馬叡をどのように評価しているのでしょうか?
司馬睿(276年 - 323年)、晋の元帝、愛称は景文、東晋(在位318年 - 323年)の初代皇帝...
中高年はどうやって健康を維持すればいいのでしょうか?中高年が健康を維持するためにはどのような食品を摂取すべきでしょうか?
中高年は健康を維持するために適切な食品を選ぶ必要があります。健康を維持するために、以下の食品を摂取す...
アチャン民族の歴史 アチャン民族の農業生産技術の発展の歴史
アチャン族の農業生産は主に稲作に基づいています。人類は米の寄生栽培法を開発しました。 「苗を立てる」...
石公の事件第165章:金亭の英雄たちは計画を立て、謝虎はガイドポストハウスで捕らえられました
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
王維の詩「李氏の西川詩に答える」の本来の意味を理解する
古詩「西川の李氏の詩に答える」時代: 唐代著者 王維本当にそこに行くなら、私について来てくれますか?...
『後漢演義』第93話はどんな物語を語っていますか?
街亭を失った後、彼は涙を流しながら馬蘇を処刑し、漢中に戻って王爽を殺す方法を助言した。しかし諸葛亮は...
曹植が七段詩を書いた後、曹丕はなぜ弟の曹植を殺すのを遅らせたのでしょうか?
曹植と曹丕の間で長く語られてきた最も明白な対立は、おそらくよく知られている「七段詩」でしょう。伝説に...